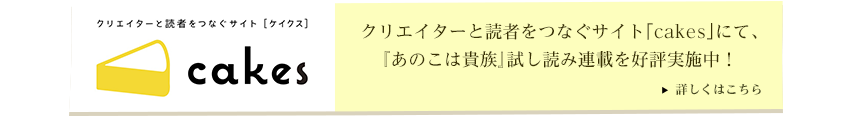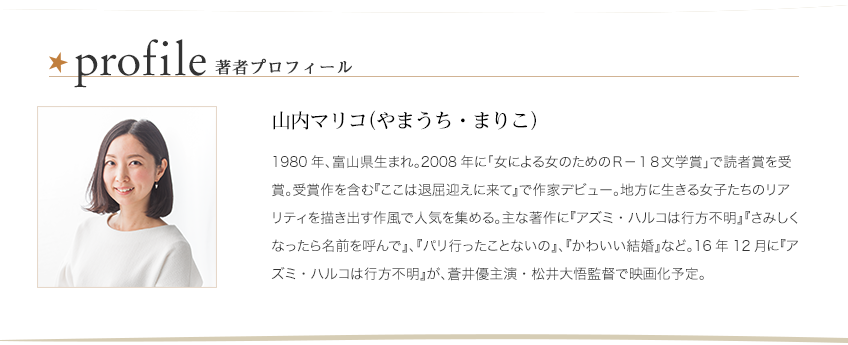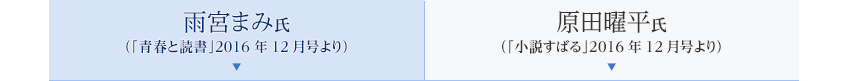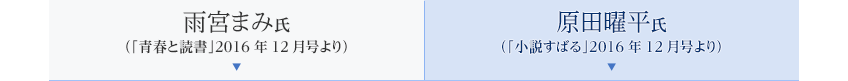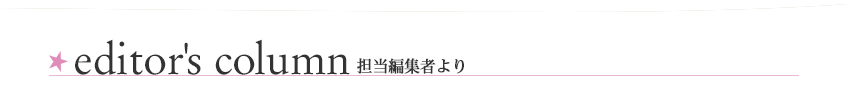東京生まれの箱入り娘VS地方生まれの雑草系女子!? 東京の上流階級を舞台に、アラサー女子の葛藤と解放を描く、山内マリコ『あのこは貴族』。
東京生まれの華子は、20代後半で恋人に振られ、名門女子校の同級生が次々に結婚するなか焦ってお見合いを重ねた末に、ハンサムな弁護士「青木幸一郎」と出会う。
一方、地方生まれの美紀は、美人ながら32歳で恋人ナシ、腐れ縁の「幸一郎」とのダラダラした関係に悩み中。ひとりの男をきっかけに境遇のまったく違うふたりが出会うとき、それぞれ思いもよらない世界が拓けて――。
著者は、デビュー作『ここは退屈むかえに来て』をはじめ、地方都市の郊外に住む女子のリアルを活写して人気を博してきたが、今作の舞台は初めての「東京」。
「苦労してないって、人としてダメですよね」――と華子。
「自分はお話にもならない辺鄙な場所に生まれ、ただわけもわからず上京してきた、まったくの部外者なのだ」――と美紀。
それぞれの葛藤を抱えながら幸せを捜し求める、アラサー女子の恋と人生の行方をぜひお楽しみください。
(担当AT)