
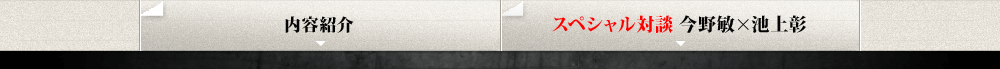
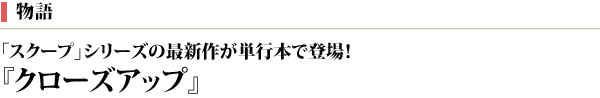
六本木の公園で週刊誌のライターが刺殺された。暴力団関係の記事の多い雑誌の仕事をしていたので、その筋とのトラブルが原因ではないかと警察内部でも取り沙汰される。
捜査一課で未解決事件の継続捜査をする特命捜査係の黒田も、暴力団関係の記事を書いたことが殺人事件の原因かもしれないと考えながらも、数ヶ月前に起きた別の事件と関連があるのではないかと直観を働かせていた。その事件とは、暴力団組長の殺害を試み、失敗したヒットマンが出所直後に殺されたというものだ。
一方、テレビ局・TBNの報道番組「ニュースイレブン」の遊軍記者・布施は、ライター殺人事件の現場近くにたまたま居合わせ、事件直後の生々しい現場映像を携帯の動画で撮影していた。しかし、「殺人事件そのものには興味がありませんよ」と言い放ち、むしろ世間を騒がせている、ある与党大物政治家へのネガティブ・キャンペーンに関心を示す。女性スキャンダル、暴力団組長と一緒に写っている写真、舌禍事件……。
ベテラン刑事と、敏腕報道記者がそれぞれの視点で事件を追い、報道と政治に潜む悪に迫る!
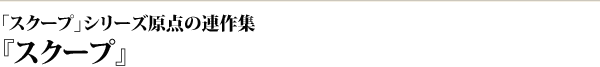
一見、遊んでいるようにしか見えないテレビ局の報道記者・布施。ある時は、遊び友達の芸能人の個人的な麻薬パーティーの場に誘われ、またある時は、日本人が通常立ち入れない中国人専用の歌舞伎町の麻雀の場に参加する。そんな彼はニュース番組の会議に遅刻することも多く、堪忍袋の緒が切れたデスクの鳩村に行動自粛
を命じられもする。しかし、自分が気になった事件の解決のためなら、ルールにとらわれない身体を張った危険な取材を行うこともある。
そうやって数々のスクープをものにしてきた布施に対して、デスクの鳩村は苦々しく思っているが、メインキャスターのロマンスグレ-の鳥飼、女性キャスターの香山恵理子は信頼を寄せている。あげくの果てに恵理子は、布施がしている、クスリと売春の取材に同行したい、とまで言い出す。
「犯罪に巻き込まれている人を、何とかしてやりたくなる」布施が、元アイドル歌手の不審死、電器メーカー役員狙撃事件、ホステス殺しなど数々の事件を調べ、捜査一課の刑事・黒田とのコンビで解決をしていく連作集。
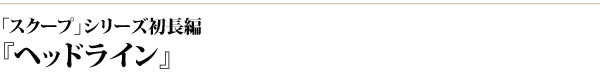
美容学校の生徒が殺されて、死体がバラバラにされた猟奇事件が起きてから一年。世間から忘れられつつある中、二人の男が事件に着目していた。
一人は捜査一課の刑事・黒田。被害者と親しかった女性の挙動が急におかしくなり、新興宗教にも入信したようだという情報が入り、再び事件を洗い直した。もう一人は報道番組の記者・布施。黒田が事件に興味を持った矢先、布施が今になってこの事件を調べているとわかった。滅多に報道関係者に弱みを見せない黒田だが、新しい手がかりが見つからず、布施に協力を求める。
布施によると、全く別の事象を追っていたところ、女子学生のバラバラ殺人に行き当たったという。きっかけになったのは繁華街でドラッグを買った後、行方不明になる若い女性が静かに増えているということだった。
黒田は布施の持つ人脈・情報網を利用し、布施は黒田の警察手帳を利用して取材をする。互いの利害を一致させた異色コンビが、先入観に囚われずに本質をとらえなおし、事件の背景をあぶり出すミステリー。
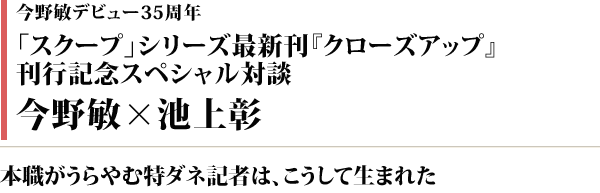
 一九七八年、大学在学中に投稿した「怪物が 街にやってくる」で第四回問題小説新人賞を受賞した今野敏さんは、今年でデビュー三十五年を迎えました。それを記念して、今年の初めから、『同期』の続編『欠落』(講談社、一月刊)、「安積班」シリーズ最新作『晩夏』
(角川春樹事務所、二月刊)、「スクープ」シリーズ最新作『クローズアップ』(集英社、五月刊)、「隠蔽捜査」シリーズ最新作『宰領』(新潮社、六月刊行予定)を刊行。四社合同企画「今野敏デビュー35周年」を展開中です。
一九七八年、大学在学中に投稿した「怪物が 街にやってくる」で第四回問題小説新人賞を受賞した今野敏さんは、今年でデビュー三十五年を迎えました。それを記念して、今年の初めから、『同期』の続編『欠落』(講談社、一月刊)、「安積班」シリーズ最新作『晩夏』
(角川春樹事務所、二月刊)、「スクープ」シリーズ最新作『クローズアップ』(集英社、五月刊)、「隠蔽捜査」シリーズ最新作『宰領』(新潮社、六月刊行予定)を刊行。四社合同企画「今野敏デビュー35周年」を展開中です。
35周年第3弾『クローズアップ』の刊行に合わせて、今野さんのファンであり、「スクープ」シリーズの主人公、布施京一と同じく「遊軍記者」の経験がある池上彰さんとの対談をお届けします。
構成/増子信一 ©小池守
 こんの・びん
こんの・びん
1955年北海道生まれ。78年、上智大学在学中に「怪物が街にやってくる」で問題小説新人賞を受賞。レコード会社勤務を経て執筆活動に専念。2006年『隠蔽捜査』で吉川英治文学新人賞、08年『果断 隠蔽捜査2』で山本周五郎賞と日本推理作家協会賞を受賞。ミステリだけではなく、SF、伝奇アクション、武道小説など幅広い分野で活躍。
 いけがみ・あきら
いけがみ・あきら
1950年長野県生まれ。慶應義塾大学を卒業後、NHKに入局し報道記者に。94年より11年間、「週刊こどもニュース」でお父さん役を務める。2005年からフリージャーナリストとして多方面で活躍中。12年より東京工業大学リベラルアーツセンター教授。著書に『学び続ける力』『聞かないマスコミ 答えない政治家』など。
![]()
池上 『ヘッドライン』の文庫解説にも書かせていただきましたけれど、布施はただ楽しく飲み歩いているようなのに、勝手にスクープネタが転がり込んでくる。
今野 よくいわれます。こんな記者がいたら、うらやましいねって。
池上 ほんと不思議ですね。本当にただ遊んでいるだけなら、事件の真相に迫れるわけはない。実は意図的に、あるいは計算ずくでやっているはずなのに、それを見せない。
今野 ええ。彼の手の内を見せないような書き方をしています。とはいえ、たしかに運が良すぎますよね(笑)。
それから、変な行動ばかりしているから変人だと思われがちですが、布施のいっていることは、意外と真面目なんです。
池上 ええ、そうですね。
今野 彼がまともなことをいうと、周りの人間がわっと驚く。そういう描写を積み重ねていくと、布施という人間がどんどん変人に見えていく。これが実は一種の手品で、小説のテクニックなんです。
池上 なるほど。「隠蔽捜査」シリーズの竜崎伸也も、あまりに真面目すぎて変人に見える。
今野 それも手品です。もし、そういう手法を使わなければ、読者が変人に共感するはずがない。布施の場合も要所要所でそうした手品を使っています。
それでも、本職のジャーナリストの方からすると、こんな記者がいたらうらやましいか、あるいは腹が立つだろう、というのはいつも感じています。
池上 しかし、かつてはそういう記者が実際にいましたよ。私がNHKの社会部にいた頃の大先輩で、とてつもない特ダネ記者がいて、いつも何やっているかわからない。それでいて、ときどきとてつもない特ダネをもってきて、みんながあっと驚く。
今野 まさに布施みたいですね。たしかに、ほかの記者と同じことやっていたら同じネタしか拾えない。特ダネを拾う人というのは、どこか切り口というか、目線が違うんだろうと思います。
池上 黒田刑事も最初の『スクープ』では警視庁の捜査一課とだけ書かれていて、捜査一課にこんな刑事がいるかなと首を傾げていたんですけれど、『ヘッドライン』では「捜査一課特命捜査二係」となっていて、思わず、これならあり得ると思った。
今野 新設された係なんですよね。継続捜査をやるというので、ちょうどいい部署ができたと思って。
池上 私が捜査一課を担当している頃から二係はありました。一係が庶務担当で、二係が継続捜査。当時は特命捜査という名前はありませんでしたが、まさに警視庁の中の遊軍的な担当が二係なんです。ある意味、布施記者と同じようなスタンスで行動している。
捜査一課には、そのほか三係、四係、五係……とあるわけですが、その係の人たちは、何もないときはひたすら事件待ちなんです。捜査一課の大部屋で時間をつぶしていて、警察無線から事件の知らせがあると現場に出ていく。そして捜査本部が立つと、所轄の警察署に通って殺人事件を追う。そうすると、黒田刑事のように自由な捜査はできない。
今野 まずあり得ないですね。
池上 フロアも二係だけ五階で、ほかはすべて六階です。普通は殺人事件があって初めて捜査本部ができるわけですが、二係は死体なき殺人を調べていく。二係には職人的な刑事がいて、その人が自由に捜査をして捕まえるというケースがある。
たとえば、家出人捜索願の書類を読んでいくうちに、「ん?」と引っかかることが出てくる。動物的な勘で、これはおかしい、単なる家出人じゃない、といって調べ始める。そして、行方不明になった人物の周辺を調べていくうちに、怪しい人間が出てきて、事情を聞いて調べていくと殺人が発覚し、「すいません、やりました。あそこに埋めました」ということになる。
今野 まだ発覚してない事件を掘り出す。
池上 まさに、東京近郊の山林とか海辺へ遺体を掘り出しに行くわけです。実際に遺体が出てきたら、とりあえず死体遺棄事件として逮捕し、殺人事件に立件していく。
今野 なるほど。
池上 だから、黒田の二係というのは、うまい手だなと(笑)。
今野 小説家はいかにうそをつくかが勝負所で、同じうそでも本当らしいうそじゃないとだめなんですね。そこが難しいところです。
池上 詐欺師もそうですよね。詐欺が成功するかどうかは、本当のことの中にどれだけうそを入れるかで決まる。
今野 つまり小説家は詐欺師だと(笑)。
池上 読者は、見事にだまされるというのが快感なんです。リアリティーがあってこそ、人をだませるわけですね。
今野 小説家は、読者を信じ込ませるのに、いろいろなテクニックを使います。もっともらしいうそをつくというのも一つだし、さっきの、まともなことをいわせて、周りの反応で変人に仕立てていくという方法もある。
池上 派手なアクションで読者をこっちに引きつけておいて、実はこっちで……というのもある。
今野 陽動作戦ですね。
池上 さりげなく伏線を張っておいて、後になってみて、ああそうか、と。
今野 ミスリードを誘うという手もある。犯人はこっちだと思わせておいて実は……という。うまくだまされてくれたら、しめしめなんですけどね。
![]()
池上 ありきたりな質問ですが、小説で扱う事件はどうやって思いつくんですか。
今野 ぼくが書く事件というのは、それ自体は特殊なものではないんです。むしろ、事件に関わる人間関係が面白いので、あまり特異な事件は必要ない。それこそ、新聞の社会面をばーっと見て、使えそうなものを拾ったりするくらいですね。
池上 スクラップしているんですか。
今野 ええ、毎朝新聞をチェックして、使えそうだと思うものを、アルバイトのスタッフにPDFデータにしてもらって全部ためてあります。スクラップの作業自体は、始めてからもう何十年も経っているので、結構な量になっています。
池上 たとえば、今度の何月号に、これこれのシリーズの新作をお願いしますと依頼が来たとしますね。
今野 そうすると、さて、どんな事件がいいかと、まずは、PDFの画面を順繰りに送っていって、引っかかるものをプリントアウトして手元に置いておく。そうやってもう一回見直していくうちに、この事件とこの事件をくっつけると面白いのではないか、と。
池上 事件単体ではなくて、あっちの事件とこっちの事件が思わぬかたちで化学反応を起こして、新しいものができていくという感じですね。
私もニュース解説の連載をもっていて、テーマをどうしようかと悩んだりします。そのときに、スクラップを見ながら、この話とこの話をくっつけるとまったく新しい展開ができるな、と。同じことやっていますね。
今野 不思議なのですが、普通のテキストのプリントアウトじゃだめなんですよね。見出しの付いた新聞記事のかたちをしていないと、頭に入らない。
池上 本当に不思議ですね。新聞の電子版で記事をプリントアウトしても、何もアイデアが浮かばない。
今野 ぴんとこないんですよね。
池上 アナログの強さですかね。
今野 パターン認識ですね、やはり。見出しのキャッチでインスパイアされるものって、結構あるんですね。
池上 そうやって事件の筋立てが決まったところで、布施記者はどういう行動をとるんですか。
今野 まず周辺のことを調べます。そうすると、ほかの人は気にしないような、被害者の友達とかが気になってくる。で、犯人の知り合いとかも気になってきて、そっちの脇道を調べ始める。脇道を調べてふらふらしているうちに、それが本筋と結びついてきて……ぼくの中ではそんなイメージですね。
要するに、布施が一番関心があるのは人間関係なんです。それは、彼にとってジャーナリズムとは何かということにもなるのですが、ジャーナリズムは商品ではなくて、人のためにあるものだというのが彼の原則なんです。彼のそういう姿勢は、小説の中にちょろっと出してはいますけど、あまり読者に気づかれないように描いておきたい。布施ってこんなに真面目なやつなんだと先に思われちゃうと面白くないですからね。
池上 どうしようもないやつだと思っていたのが、最後の最後に、あれ、そうでもない、骨があるんだっていうことですよね。
その布施のどうしようもなさを描くために、あの鳩村デスクが出てくるんでしょう。
今野 そうです。頭がかたくて真面目で。
池上 『釣りバカ日誌』の課長みたいな(笑)。
今野 報道一筋でやってきた人の中には、ああいう人がいそうですよね。
池上 それに近いような人は実際いました。
今野 組織には、鳩村のような真面目で本筋の報道をきちんと見極める人もいないと困るわけですね。布施も本筋なんですけど、やり方が変化球ですから、ちゃんと上から押さえる人間がいたほうがいい。
池上 ところで、最近どうも、あの女性キャスターの香山恵理子と微妙になりつつあるようですけど(笑)。
今野 ずうっと微妙なままなんじゃないですか。布施の面白さというのは、何を考えているかわからないところですから、誰かと恋仲になって本気になったりすると読者は冷めちゃうところもあって、そこはかとなく匂わせておくくらいのほうがいいだろうと。
池上 でも、微妙な関係を引っ張っていくためには、もう少し際どいシーンといいますか、腕の中に飛び込むぐらいあってもいいのでは?
今野 おっしゃるとおりです。努力します(笑)。
![]()
池上 今野さんは、今年でデビュー三十五周年だそうですね。いまは警察小説のイメージが強いのですが、初期の頃は伝奇的なSFを書いていましたよね。
今野 ええ。デビューしたのは一九七八年で、そのときは自分をSF作家だと思い込んでいました。当時はSFが元気のいい時代で、筒井康隆さんや平井和正さんが活躍されていました。受賞したデビュー作の選考委員に筒井康隆さんがいらっしゃって、それで応募したんです。幸運にも、筒井さんに褒めていただいてデビューでき、SF作家としてやっていこうと思っていたのですが、だんだんSFが売れなくなってきた。
SFの老舗である早川書房は「S‐Fマガジン」と並んで「ミステリマガジン」も出している。大体、早川の本が好きな人はSFとミステリ両方を読んでいる。ぼくもそうでした。
池上 私も、中学生のときに「S‐Fマガジン」を毎月隅から隅まで読んでいました。毎月発売日になると、その日は待ちきれず、書店に朝八時ぐらいに行くわけです。で、届いたばかりで荷ほどきをしているところに、「すいません、『S‐Fマガジン』下さい」と買っていく。昼休みを含めて休み時間にひたすら読んで、その日の夜までに全部読み終わる。もう夢中でしたね。そのうちに、だんだんハヤカワ・ポケット・ミステリにはまっていく。
今野 ぼくも同じような経緯を辿って、海外の刑事小説が好きになりました。日本にも刑事を主人公にした小説はあったのですが、いわゆる捜査を描いた小説というのは、不思議なほどなかったんですね。
池上 エド・マクベインの「87分署」シリーズはほぼ全部読みました。
今野 ぼくは、コリン・ウィルコックスの「ヘイスティングス警部」シリーズが大好きで、それからマイ・シューヴァルとペール・ヴァールーの「マルティン・ベック」シリーズ。
池上 『笑う警官』ですね。私も無我夢中で読みました。
今野 そのほか、マイクル・リューインの『夜勤刑事』とか好きな警察小説があって、いつか自分でも書きたいと思っていたんです。
池上 同じような経路を辿って読んできたのに、ふと気がつくと、書く側と読む側に分かれていた。
今野 いや、ぼくも最初から小説家になろうと思っていたわけではなくて、小さい頃は漫画家になりたかったんです。もともと物語をつくることが大好きだったんですね。
池上 今野さんは、いろいろな作品がテレビドラマ化されていますね。物語の面白さはもちろんですが、もう一つ、絵になりやすいというのもあるような気がする。同じ小説でも絵になりにくい小説もあって、今野さんの場合は、漫画家になりたいと思われたほどですから、絵になりやすい文章になっているのではないでしょうか。
今野 たしかに、文章を書いているときに頭の中に浮かんでいるのは、言葉でもなく音でもなく、映像とか画像であって、それを文章に変換している感じですね。
池上 絵が浮かぶということは、黒田刑事や布施記者のような人物を造形するとき、モデルやヒントになるような人がいるんですか。
今野 いえ、いません。ドラマ化のときに「どんな役者さんがいいですか」と聞かれてもまったくイメージがない。頭の中にあるのは具体的な誰かではなくて、何となくのイメージなんです。だから、目をつぶるとその人の表情は浮かぶけれど、顔の造形は浮かばない。それでぼくの小説には、顔の造形とか、太っているとかやせているといった描写があまりないんです。
池上 いわれてみると、そうですね。
今野 それも、さっきいったテクニックの一つで、描写しすぎないほうが、読者が自分の思うイメージに変換してくれるし、キャラクターが立つ。
![]()
今野 池上さんがジャーナリストになられたきっかけは何ですか。
池上 一冊の本との出合いです。それは小学校六年生のときに読んだ、朝日新聞社から出ていた『地方記者』という本の続編の『続地方記者』という本です。朝日新聞の地方支局の記者の仕事ぶりが書いてあって、それを読んだら、新聞記者、それも地方の支局で働く新聞記者って面白そうだな、と思ったのがそもそものきっかけです。
当時は、テレビではニュースらしいニュースをやっているところはほとんどなかったのですが、大学の四年生になった頃にはNHKがテレビニュースをある程度やるようになっていた。そこで、朝日新聞とNHKの両方に願書を出したのですが、その頃は朝日、毎日、読売、共同、NHKはいずれも試験日が七月一日と一緒で、いずれか一社に絞らなければいけない。ぎりぎりまで悩んだ末、NHKなら必ず地方勤務から始まるので地方記者が経験できる、とNHKを選んだんです。
今野 でも、時代的にはテレビより新聞社のほうがまだメジャーでしたよね。
池上 ことニュースに関しては、NHK以外の民放にはほとんど力がない時代ですね。
今野 それでも放送を選ばれたのは、何でなんですか。
池上 浅間山荘事件です。あのとき、NHKなどのテレビがリアルタイムで一日中生中継していた。そこで、テレビの力を感じたんです。これからはテレビの時代かもしれないという思いが多分あったんでしょうね。それに、NHKと朝日新聞の過去問を見たら、NHKの問題のほうが解けそうだと(笑)。
今野 最初は、どちらの支局だったんですか。
池上 島根県の松江です。松江でサツ回りを経験して、次に自ら志願をして、広島県の【呉/くれ】通信部へ行きました。一匹オオカミの記者に憧れて、取材から何からすべて一人でやる通信部の記者になったわけです。警察でいうところの駐在さんですね。二週間に一回、広島の本局へ泊まり勤務で上がるだけで、あとはずっと呉市あるいはその周辺を自分でカメラをもって取材する。
今野 新聞社の地方記者は、その人が住んでいる家がそのまま支局になっていたりしますよね。NHKの支局はどうだったんですか。
池上 呉通信部には地元の年配の人が住み込んでいて、その家の一階の土間が仕事場なんです。私はそこから歩いて五分ぐらいのアパートから毎日通っていく。最初に各地の警察へ電話する。いわゆる警戒電話というやつですね。呉署、広署、江田島署、音戸署……と次々に電話していくのですが、そうやって毎日かけていると、たとえば江田島署の交換手のおばちゃんと仲良くなる。「NHKの池上ですが、おはようございます。何かありませんか」というと、「何もないけどねえ、何か隣の警察の無線がうるさいわよ」みたいなことをいってくれる。自分のところの話は絶対にしないけれど、そうやって情報を流してくれるんです。江田島署の隣は音戸署ですから、そこに電話するとネタが取れる。実に面白い経験でしたね。
![]()
池上 「スクープ」シリーズには、いろいろな人の視点が入ってきますね。
今野 『ヘッドライン』は鳩村と黒田の視点でしたが、今回は鳩村と新人刑事の谷口の視点です。
池上 そのうちに所轄署が出てきますかね。
今野 多分出てくるんじゃないですか。ただ、ほかのシリーズで所轄を書きすぎているので、連載が三、四本同時に進行しているときなど、同時にいくつも捜査本部ができるんです。そうすると、どこの会議でしゃべった話なのか、わからなくなる(笑)。
池上 TBNはキー局ですよね。そうすると、大阪や名古屋にネット局があるわけですよ。これがライバルにもなる。
今野 はいはいはい。
池上 たとえば、ネット局の大阪府警担当の準キー局の記者が取材で東京に上がってきたり、その逆もあったりする。
 今野 面白いですね。
今野 面白いですね。
池上 鼻っ柱が強くてプライドの高い関西人がTBNにやってきて、引っかき回す――。
今野 よし、次はそれでいきましょう! 貴重なアドバイス、ありがとうございました(笑)。
池上 次回作がますます楽しみですね。
今野 敏×池上 彰
「青春と読書」2013年6月号より転載