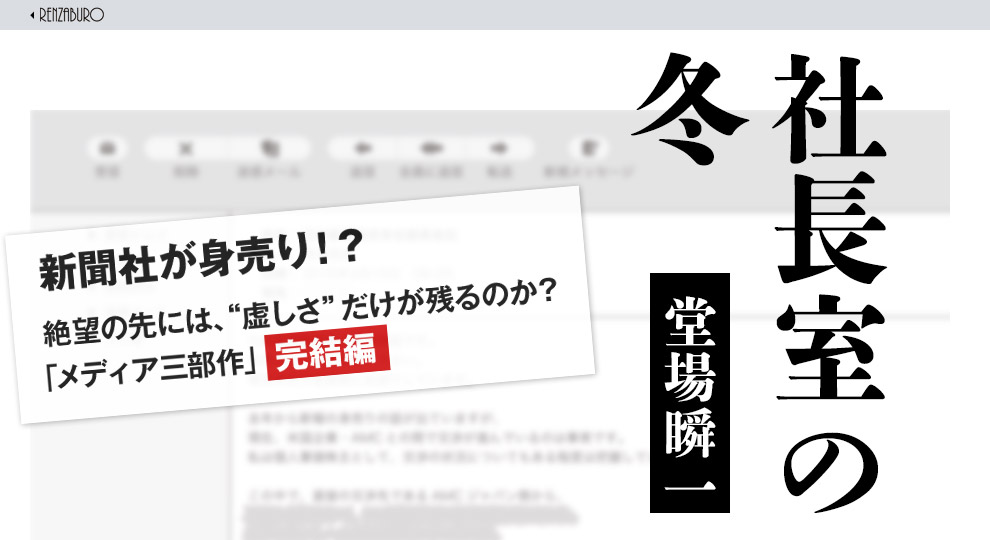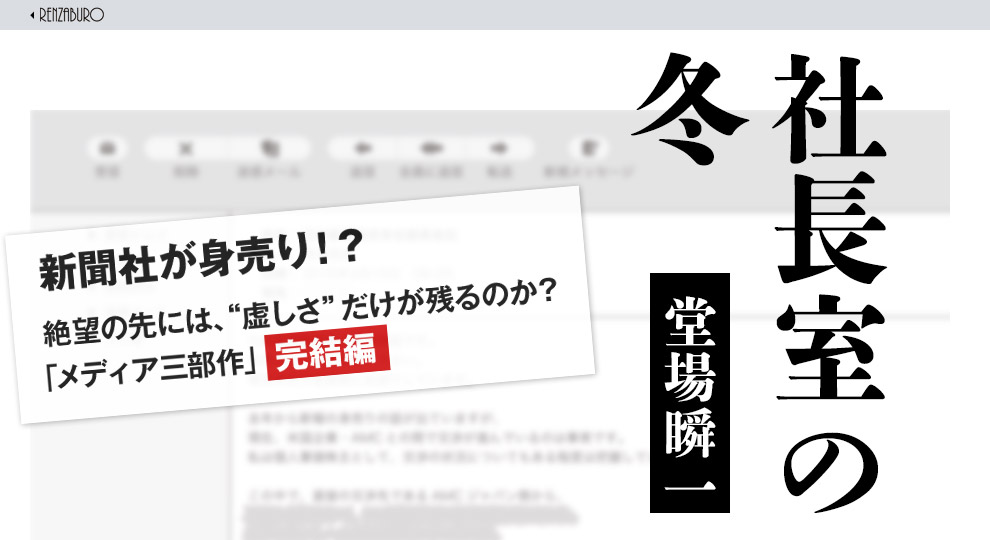新聞はまだ頑張っているなという感じ
まず、新聞社が外資系企業に身売りするという設定に驚きました。前作の『蛮政の秋』でもすでにほのめかされていましたが、この作品では物語の中心になっています。三部作を構想されたときから、決めていたのでしょうか。
全体を通じてのテーマが「劣化」でしたから。マスコミ、それも新聞社を舞台にした時点で、最後は会社自体が劣化していくということは最初から頭にありました。どの新聞社も全力で否定するでしょうけどね。ありえないと。ただ、シミュレーションとしては、あってもおかしくはないと思います。
三部作はそれぞれジャンルが異なるといってもいいくらい幅がありますね。第一部の『警察回りの夏』は、山梨で二児の遺体が発見され、母親が失踪する。主人公の新聞記者、南が事件を追うミステリーとしても読めました。ところが、第二部の『蛮政の秋』では舞台を東京に移し、本社に戻った南が国会議員の収賄疑惑に巻き込まれていく。ポリティカル・サスペンスの趣がありました。そして、『社長室の冬』では新聞社の買収劇です。
最後は企業小説みたいになりましたね。マスコミは普通の企業の感覚とはちょっと違うところがあるので、世間からはあまりそう捉えられていませんが、企業であることに変わりはない。企業として社会のルールから逃れることはできないということです。
三部作を通じて主人公は日本新報の三十代の記者、南康祐です。『社長室の冬』では現場を離れ、社長室で仕事をしている。そこで、身売り話に巻き込まれていきます。
一部で誤報を書いて、二部で挽回しようと焦っていた彼も、バカではなかったということでしょう。何をしでかすかわからない記者を社長室に置いて監視しようという意図もあるんだろうけど、抜擢されてこのポジションにいるわけですから、何か役に立つだろうとは思われている。でも、今回、彼はほぼ何もしていないんです。というか、できないんです。三十そこそこの人間が、これから会社がどうなるかなんていう問題に関してキーストーンになるということはありえないから。だから、今回の彼の役割は観察者ですね。
読者は観察者・南の眼を通して、身売りする側の新聞社の内部をつぶさに見ることになります。たとえば、身売り交渉で、日本新報が外資系企業のA M Cから示された条件の一つに「紙の新聞を止める」とあり、その衝撃の大きさが伝わってきました。AMCはアメリカで地方新聞社を買ってはネットメディア化しているという実績があるからそういう発想が出てきますが、現実には、日本ではまだ起こっていません。
ニュースとネットって相性がいいんですよ。二十四時間更新できるわけですから。事実、ネットが普及し始めた二十年前から、新聞はなくなるぞといわれていた。収入のめどさえ立てば、紙でなくてもニュースは流せるんですから。一般の人もネットでごく自然に記事を読んでいますよね。逆にいうと、インターネットが出てきてから二十年ぐらい経つのに新聞はまだもっている。頑張っているなという感じですよ。
ただ、歴史的にいえば新聞の危機はいままで何回もあった。戦前はラジオが出てきたときに危機だといわれたし、戦後はテレビが登場した。それでもずっと生き延びてきている。ネットが普及したいまも併存しているので、ここで書いたことは現段階ではあくまで極端な話です。
主義主張がまっすぐにぶつからない
AMCの日本法人代表の青井は、かつては日本新報の記者でした。古巣の日本新報に対してどんな思いがあるのか興味深いところです。
彼は新聞記者を辞めて、フリーで週刊誌記者もやって、海外でも仕事をして、とあちこち行っている人です。なおかつ根っこが新聞記者に残っている、微妙な感じの人ですね。だから青井は悪役ではないんです。いわゆる企業小説だったら、買う側と売る側のせめぎ合いを書くと思うんですよ。株主総会へ向け委任状の奪い合いになって、という感じに。でも、この小説はそうではない。お互いに主義主張がまっすぐにぶつからないというか、もうちょっと複雑にアメーバ状に入り組んでいる。とくに青井は古巣に対して、憎しみと愛着が入り交じっているようなところがある。そのへんが普通の企業小説とは違いますね。
しかも青井は、日本新報の新社長になった新里の元部下。新里は青井の辞表を受け取った人物だった。こうした人間関係が交渉をよりいっそう複雑なものにしていきます。
その関係を、小説的にもっとくっきりさせるやり方はあるんです。青井が新里と大ゲンカして日本新報を辞めたという設定にするとかね。ただ、リアルの世界で、なぐり合って会社を辞めたなんてほとんど聞いたことがない。リアルな方向に振っていくと、こういうもやもやとした感じになっていく。そこは意識してやりました。
当事者同士よりも、むしろ周囲が想像をたくましくして気を揉む。いかにも会社の人間関係という感じがしました。お互いこう思っているのかな、と思っても直接言うことはない。
戦後の高度成長期のように、会社は家族だ、みたいな時代もあったわけじゃないですか。そのころだったら、もうちょっと本音をぶつけ合っていたかもしれないですけどね。いまは、周りがいろいろと変に忖そん度たくして、というのは確かにありますよね。僕の感覚ではこういうほうがリアルかなと。
春が来ないのがこの話の “肝”
しかも青井は経営者という立場ですが、ネットメディアの編集長も兼務していて現場感覚を捨ててはいない。ある意味で日本新報の現役記者よりも熱い部分があります。
若いころに十年ぐらい新聞記者をやっていたわけですから、その感覚がぬぐえないんでしょうね。あの業界で十年やると、何だかんだいって染まってしまうので。だから、新聞業界に縁のない人だったら、また別のことを考えていたと思う。結局、青井はニュースとは何ぞや? という問いを投げかける存在なんですよ。
ニュースがなぜ必要なのか? どんな価値があるのか。
お金をとれるニュースって? みたいな話にもなってくるわけで。あまり露骨には書きませんでしたけど、「ニュースとは?」という問いかけをするうえで、青井という人間が必要でしたね。いまは新聞社の外にいる人間だからこそ。
買収する側、される側。そして、それを阻止しようとする人たち。創業者一族からの横やりや、組合からの反発など、さまざまな人たちが口を出す。そのドラマが濃密です。
みんなあがいているんですよ。答えがわからなくてね。自分が所属している組織をどうするかって、そんなに簡単に気持ちを決められないでしょう。昨日まで信じていたものが、今日は信じられなくなったりするわけだから、いわば翻弄された人たちですよね。すべてを目の当たりにする立場の南が一番キツかったかもしれないけど。ただ、今回、彼の傷は浅いかなと思いますね。深手は負っていないような気がします。
社長秘書の同僚とデートしたり、AMC側の女性からアプローチされたりと、南の周囲は華やぎますね。
かわいそうだから、やり直しのチャンスをあげようかな、と(笑)。彼には今後も頑張っていただきたいという気持ちからです。
堂場さんの優しさですね(笑)。三部作を通して見ると、マスコミと社会との関わり、業界で働く人々の人生の一部分に焦点を当て、緻密に描いた作品だと感じました。
ただ、非常に複雑で特殊な業界ですから、なかなか書き切った感じにならないですね。マスコミの場合、現実ではあまりダイナミックな話が出てこないので、想像の域を出ないところもありますし。いつかまた別の形で書くかもしれません。
三部作のタイトルは、順に「夏」、「秋」、「冬」と来て、「春」が来ていません。今後、書かれる可能性はありますか。
ないですね。春が来ないのがこのシリーズの肝だから。この設定で春は考えられない。今後、新聞の身売り話のようなことが現実に出てくるかはわかりませんが、これはようは、おたくら社会に要らないよ、という話なんです。だから実際は、買収しようとする会社すら出てこない可能性があります。お金もうけだけを考えたら、新聞はもう、微妙ですよね。
新聞社が発信するニュースにどれだけの価値があるかが問われるということですね。
昔だったら、新聞の影響力ってすごかったけど、いまはネットがあるから以前ほどではないでしょう。相対的に影響力も収益力も沈没化しているという感じなんでしょうけどね。話が暗いな(笑)。でも、しょうがない、これが僕なりの現状認識であり、僕なりのリアルなんです。
「青春と読書」2016年12月号再掲