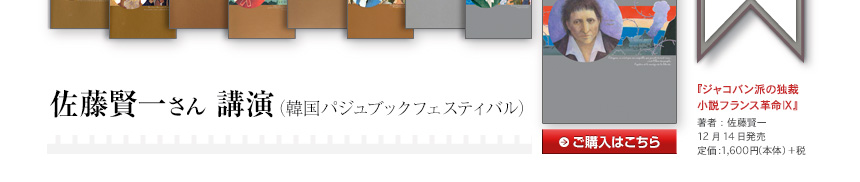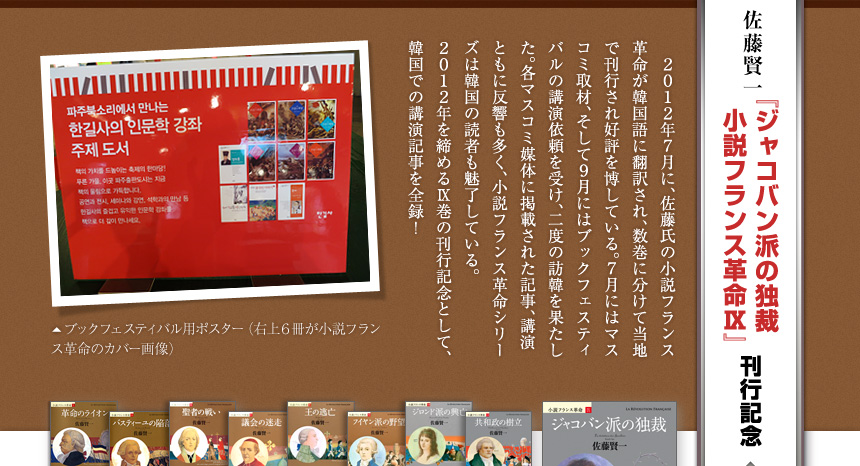
●アジアにとって、ヨーロッパ史とは
今日は、フランス革命が今、私たちに持つ意味という話をしたいと思います。歴史とは先人が残してくれた最大の遺産だと私は考えています。それも、誰と決まった持ち主がいるわけではないとも思います。人類共通の遺産で、どの国の歴史も自由に楽しむことができます。あなたはだめだと言われるようなことはなく、韓国人や日本人のようなアジア人でもフランスやイギリスの歴史を知ることができるんです。
とはいえ、残念ながらそれは一般的な態度ではありません。歴史といえば、まず自分の国の歴史、自国の歴史になるのが普通だと思います。そうでなければ、自分の国の文化や伝統に大きな影響を及ぼした国の歴史になります。アーノルド・トインビーという歴史家がいるんですけれども、トインビーは親文明、子文明という言い方を用いました。これはアジアでいえば、親文明は中国、子文明は韓国や日本ということになるでしょう。実際、韓国人も日本人も中国の歴史なら親しみを覚えます。いろいろと知っているだけではなくて、例えば、三国志のような歴史だとエンターテインメントとして韓国でも日本でも大いに楽しまれているとおりだと思います。反対に遠く離れた国の歴史は、あまり興味を持たれません。ヨーロッパの歴史もやっぱり興味はあまり持たれないと思います。
ところが、ヨーロッパの歴史の場合は、こんなに離れているけれども、全く私たちに無縁というわけでもないのです。それを親子関係と言えるかどうかは微妙ですが、韓国や日本、中国でさえも、少なからずヨーロッパ文明の影響を受けているからです。十六世紀はヨーロッパ史では大航海時代といいますが、ヨーロッパ諸国はこの時代から、勢力を世界に拡張していきます。ヨーロッパから見て一方的にアメリカは発見されたことになり、征服されました。アジアやアフリカもどんどん植民地にされていきました。独立した国々もありますけれども、差はあれ、やはり影響を受けざるを得ませんでした。
しかも、それは単なる征服や植民ではありませんでした。ヨーロッパは近代化の名のもとに、政治、経済、文化と全てをヨーロッパ化していったからです。現に私たちが暮らしている社会は法律でも、あるいは身近なところでは音楽でも、工業製品、あるいはこうやって着ている服に至るまで、ほとんどがヨーロッパの価値観に基づいて、ヨーロッパで考え出されたものがもとになっているわけです。つまりヨーロッパというのは、世界に覇を唱えた文明なわけです。
 こうなると、ヨーロッパは手本になります。日本の場合を紹介しますと、初めて日本人がヨーロッパと出会ったのは十六世紀でした。十六世紀にスペイン人やポルトガル人が多く日本にやってきたからです。当時の日本というのは内乱状態でしたから、熱心に学ばれたのは軍事技術で、とりわけ銃、鉄砲というものが最新兵器として歓迎されました。十七世紀の初めに内乱がおさまると、それから二百年ほどの間は日本語でいう鎖国、つまり外国との交流が厳しく制限された状態が続くのですが、その間も例外としてオランダだけは通商が許されました。オランダを窓口として十七世紀、十八世紀の間もヨーロッパの英知は取り込まれ続けました。
こうなると、ヨーロッパは手本になります。日本の場合を紹介しますと、初めて日本人がヨーロッパと出会ったのは十六世紀でした。十六世紀にスペイン人やポルトガル人が多く日本にやってきたからです。当時の日本というのは内乱状態でしたから、熱心に学ばれたのは軍事技術で、とりわけ銃、鉄砲というものが最新兵器として歓迎されました。十七世紀の初めに内乱がおさまると、それから二百年ほどの間は日本語でいう鎖国、つまり外国との交流が厳しく制限された状態が続くのですが、その間も例外としてオランダだけは通商が許されました。オランダを窓口として十七世紀、十八世紀の間もヨーロッパの英知は取り込まれ続けました。
十九世紀にアメリカに国交を求められ、日本は開国しました。それまでの政体も刷新して近代化を目指すことになったのです。このとき模範と仰いだのもヨーロッパで、使節を出したり、留学生を送ったり、あるいはヨーロッパから先生や教官を招いたりして、それまでに増した勢いでヨーロッパを勉強しました。ヨーロッパの歴史というのも、そうした動きと並行して学ばれていきました。ヨーロッパは手本なわけですから、歴史も一種の理想という感じで学ばれました。そして、ヨーロッパの歴史を理想と拝むような態度は、ごく最近まであったといってもいいと思います。
ところが、既にアジアも先進国の仲間入りを果たしました。経済的にもヨーロッパにおくれをとるものではないと思います。そのような変化が起きると何が起きるかといいますと、ヨーロッパの歴史は姿勢を正して仰がなくてはならない手本ではなくなるわけです。ヨーロッパの歴史も中国の三国志のようにフィクションとして、ノンフィクションとして、あるいはコンピューターゲームとしてまで楽しめるようになったわけです。
アジアのレベルはそこまで来ているというのが私の持論なわけですけれども、さておき、その最大の効用というのは、ただ、手本として学ぶだけでは見えてこなかった、ほんとの歴史が見えてくることだと思います。大切なのは長所短所を含め、ありのままの歴史の姿をとらえることなのです。
●フランス革命の意義
さて、ここからがフランス革命の話になっていきます。フランス革命といえば、例えば、高校の教科書、日本では世界史の教科書ということになるんですが、教科書では今でも封建主義国家を倒し、民主主義を打ち立てた偉大な革命であるとか、近代化に向けた偉大な一歩という形で書かれていることが多いと思います。まさに結構ずくめで非の打ちどころのない偉大な歴史というふうに聞こえますが、ほんとにそうなのでしょうか。
もちろん手本とする部分は多々あります。しかしながら、ありのままの姿をとらえるという態度で見直すと、フランス革命にも実は数々のマイナス面があることがわかってくるのです。時としてそれは成功した革命とさえ思えなくなります。年表を眺めただけでも首をかしげてしまうことがあります。それは、フランス革命は旧弊な王政を廃して共和制を打ち立てたといいながら、その共和制が続いていないからです。
どうなったかといいますと、王政ではありませんがナポレオン帝政という擬似王政といいますか、とにかく君主制に逆戻りしてしまいました。ナポレオン帝政が破綻すると、今度はブルボン王家を呼び戻して、いよいよ王政復古ということになります。その王政復古もだめだとなると、ブルボン王家の分家、オルレアン家を担いで七月王政という立憲君主制を打ち立てます。七月王政が廃されると共和制が復活するのですが、それもしばらくするとナポレオン三世による第二帝政にとってかわられます。最終的に共和制になるのは一八七〇年、第二帝政が倒れてからのことなのです。
フランス革命が成功した革命ならば、こんな紆余曲折があるはずもありません。フランス革命が失敗した、あるいは問題を抱えていて、それを解決できなかったからこそ、これだけ右往左往することになったと見るほうが、むしろ常識的だと思います。
繰り返しになりますが、ヨーロッパを手本として拝み、それを学ぼうとしている限り、そういう常識的な判断もできなくなります。しかし、大切なのは手本になる、ならないではないわけです。そういう事実があったことを通して、フランス人、あるいはヨーロッパ人は、ひいては人間というものは一体どういう生き物なんだろうかとさまざまに思いをはせるというのが、ほんとに歴史を楽しむということだと思います。
フランス革命の場合も無理に成功、あるいは失敗という物差しを当てるべきではないように思われます。人類の歴史にとっての青春時代のようなもの、さらに歴史を紡いでいくための貴重な体験だったと形容したほうがよいかもしれません。あるいは、そのものが後世に対する問題提起をなしていると言うほうが、より正確な形容になるでしょうか。
 ここからは、ちょっと具体的な話になっていきます。フランス革命において行われたのは、まず貴族対平民という戦いでした。生まれながら全ての人間に与えられている人権という考え方を前面に出しながら、貴族も平民もないんだと声を大にし、区別をなくしたことは、素直に賞賛するべき壮挙だと思います。
ここからは、ちょっと具体的な話になっていきます。フランス革命において行われたのは、まず貴族対平民という戦いでした。生まれながら全ての人間に与えられている人権という考え方を前面に出しながら、貴族も平民もないんだと声を大にし、区別をなくしたことは、素直に賞賛するべき壮挙だと思います。
というのは、そこに原理原則の転換があったからです。それまでのフランスでは権利といえば特権のことでした。言いかえれば貴族のような特に権利の与えられた人間だけによりよい人生を約束するものだったわけです。その権利が生まれながら全ての人間に与えられるようになる、それはほんの一握りの人間だけが幸せになればよいという社会から、全員が幸せになるべき社会への移行でした。
まさに革命的な発想の転換と言えるでしょう。貴族を廃止した、それのみならず、フランス革命は王政、王様も廃止しました。つまり王自身をも処刑してしまったわけです。
そして共和制を樹立したわけですけれども、それが正解だったかどうかというのは、なかなか微妙なところだと思います。貴族を廃したのだから、その筆頭である王も廃して当然という考え方ももちろんあります。けれど、王政という政体には立憲君主制という選択もあって、どうでも民主主義と折り合えないわけではありません。現にイギリスや日本には、今も君主がいます。アメリカや韓国などは共和制ですが、そういう場合は大統領権限がほとんど王様と言えるぐらいに強いというのが世界の趨勢のような気がしています。
何よりフランス革命後の歴史というのが示唆的だと思います。先ほど触れましたように、共和制が破綻するや君主制に戻っているからです。また共和制になったと思えば、また君主制に戻り、フランス人は実は君主制が好きなのではないかと思わせるほどです。第三共和制からは、今日まで共和制が続いていますが、それも第四、第五と進むほど、大統領権限が強くなっています。王、あるいは皇帝という感さえある大統領の典型がフランス共和制だと言えるほどです。大衆臣民の働きからすると、どうも君主、あるいは君主的な存在がいたほうが、社会や国家が落ちつきやすいようです。それは、男女平等の社会になり、かえって女性のほうがたくさん稼ぐようになっても、やはり父親がいる家庭のほうが子供たちが落ちつくことと同じ理屈なのかもしれません。いずれにせよ、フランス革命は一方では高邁な理想、新しい原理を掲げながら、他方では人間の理屈では割り切れない不合理な一面をも垣間見せてくれるわけです。
先ほど、ちらっと男女平等の話が出しましたが、フランス革命の取り組みといえば、男対女の戦いもありました。全ての人間が同じというなら、貴族と平民だけではなく、男と女も変わらないだろうとオランプ・ド・グージュというような女性活動家たちが、女性にも人権を求める活動を始めています。当時はまるで報われませんでしたが、これも後世に対する問題提起となりました。二十一世紀に相当程度まで結実することになっているとおりです。
 全ての人間が同じであるというならば貴族と平民だけではない、男と女だけではない、白人と黒人、あるいは有色人種も変わらないだろうと、後の人種差別の撤廃につながるような議論もなされています。フランスといえば白人の国のように聞こえますが、王政時代、つまり十六世紀、十七世紀のころから、実はアメリカ大陸やカリブ海海域にたくさんの植民地を持っていました。そこで奴隷として働かされていたのがアフリカ系の人々だったわけです。みんなに人権が認められる時代になったのだから奴隷なんてとんでもない、白人と変わらない市民なんだと、当の黒人は無論のこと白人からも声が上がりました。
全ての人間が同じであるというならば貴族と平民だけではない、男と女だけではない、白人と黒人、あるいは有色人種も変わらないだろうと、後の人種差別の撤廃につながるような議論もなされています。フランスといえば白人の国のように聞こえますが、王政時代、つまり十六世紀、十七世紀のころから、実はアメリカ大陸やカリブ海海域にたくさんの植民地を持っていました。そこで奴隷として働かされていたのがアフリカ系の人々だったわけです。みんなに人権が認められる時代になったのだから奴隷なんてとんでもない、白人と変わらない市民なんだと、当の黒人は無論のこと白人からも声が上がりました。
ところが、植民地でプランテーション、大農場を経営する資本家などは、奴隷制を廃止されてはとてもやっていけないわけです。ですから、そういった黒人にも人権を与えようという運動に対して反対していきます。奴隷制をめぐっては、十九世紀のアメリカで南北戦争という有名な内乱が起こりますが、ほとんど同じ構図において、既にフランス革命でも議論が紛糾していたわけです。
●フランス革命最大の焦点
ここで資本家というものが出てきましたが、フランス革命の最大の焦点といいますか、フランス革命の中で最も熾烈に争われたのは、実は平民対平民の戦いでした。一口に平民といいますが、その中身は一様ではありませんでした。平民対平民の戦いだったというのは富者と貧者の戦いのことなわけです。一方はブルジョワと呼ばれた資本家、高度な教育を施され、会社の経営者になるような金持ちたちです。他方はサン・キュロットと呼ばれた労働者、ろくろく学校にも行けないために職業に恵まれず、低賃金の境涯に甘んじなければならない貧しい人々です。その両者が鋭く対立していたのです。
貧しい人たちには、最初は選挙権さえ与えられませんでした。革命が起きて初めて定められた一七九一年の憲法では、一定額を納税した人間、つまりはお金持ちしか投票もできなければ、立候補もできないとされていたのです。これはさすがにひどいというわけで、ロベスピエールやダントン、デムーランといったような革命家たちが反対運動を展開しました。フランス革命はそのおかげで一七九二年には普通選挙を実現することができました。制限選挙が廃止されて、政治的には確かに平等が達成されたわけですけれども、まだ全ての問題は解決されたわけではありません。
実際に金持ちと貧乏人を比べると、とてもじゃないが同じ人間だとは思われないわけです。着ている服から、食べるものから、住んでいるところまで生活のレベルが歴然と違うために、同じ人間とは思われないぐらいなわけです。まるで昔の、ちょっと前の貴族と平民ぐらい違います。貴族には貧乏貴族というのもいましたから、もっと違っていたかもしれません。しかし、それは身分ではないということで認められる傾向にありました。
実際のところ、今の我々の感覚からしてもそれは仕方がない、頑張って自分が金持ちになるしかないと言うかもしれません。しかし、それも飢饉などが起きてしまうと、そんなに物わかりよくも言っていられないわけです。貧しい人たちは食べ物が手に入らない、食べなければ死んでしまう、つまりは自分の生存権にかかわる問題になるからです。フランス革命の間には、実際に何度も食糧危機が起こりました。当時は、気候がおかしい、ちょっとした氷河期が起きていたと言われていまして、毎年の農業が振るわなかったからです。そして、暮らしが厳しくなると、だれにでも人権が与えられているのではないか、全員が幸せになる社会ではないのかと貧乏人は怒り出します。
 ロベスピエールやサン・ジュストといった革命家たちも何とかしなければならないと奮闘します。政治的な平等だけでは足りない、社会的な平等までも実現しなければならないという理屈です。そのためには多少の犠牲は仕方がないとも考えました。商業の自由を制限しても仕方がない、財産権を制限しても仕方がない、政府の力で富を再分配しなければならない、そういう政策を並べれば今度は金持ちたちから不満が出ます。その不満の声を無理矢理に押し込めたのが、フランス革命後半に起きました悪名高い恐怖政治だったという言い方もできるかもしれません。
ロベスピエールやサン・ジュストといった革命家たちも何とかしなければならないと奮闘します。政治的な平等だけでは足りない、社会的な平等までも実現しなければならないという理屈です。そのためには多少の犠牲は仕方がないとも考えました。商業の自由を制限しても仕方がない、財産権を制限しても仕方がない、政府の力で富を再分配しなければならない、そういう政策を並べれば今度は金持ちたちから不満が出ます。その不満の声を無理矢理に押し込めたのが、フランス革命後半に起きました悪名高い恐怖政治だったという言い方もできるかもしれません。
恐怖政治というのは、政府に反対する人間を誰彼構わずギロチンに送って首を切ったという、あの恐怖政治のことです。そうした恐怖政治を行ったために、ロベスピエールの一党はクーデターで失脚することになります。直接的には恐怖政治が嫌われたためですが、真因はやはり富者と貧者の対立を解けなかったからだと言っていいと思います。
フランス革命の標語に自由、平等、友愛というものがありますが、そのうち自由と平等を二つながら両立させることができなかったという形容も可能かもしれません。自由、もっと言えば自由競争を容認し、何の保護も与えなければ貧乏な人たちは泣くばかりです。平等を優先し、社会の富を国家の力で再分配しようとすれば、今度は金持ちが怒ります。それらのバランスをどうとるか、この難問を解けなかったがためにフランス革命は破綻を余儀なくされたとも言えるのです。
●革命破綻後の課題
しかしながら、その後の人類はといえば、こうした問題を解決できたのでしょうか。フランス革命が破綻すると、フランスは金持ち中心の社会になりました。おおよそヨーロッパ全体がそうだったと言えるでしょう。これではいけないと平等の理屈を推し進めたのが社会主義です。私有財産を否定するところまでいったのが共産主義なわけです。バブーフという共産主義の祖とされる運動家もフランス革命のさなかにあらわれていますが、そのときはまだ報われる時代ではありませんでした。その理想が結実したのが、ソ連邦の成立以降のことで、ようやく二十世紀のことです。
しかしながら、共産主義国家という壮大な人類の実験も二十一世紀の今日までには失敗という結果が出てしまいました。ソ連は既に崩壊してありませんし、また、中国も変質して、もはや共産主義国家とは言えなくなっています。人間にはやはり平等は合わない、自由が大切なんだと大きく胸を張れるかといえば、そう単純な話にもならないでしょう。他方の自由経済は、弱肉強食の自由競争のことでもありますから、当然勝者と敗者を生み出します。それならば勝てばいいじゃないかと成功した金持ちは言うかもしれません。
けれど、どんなに努力しても勝てないぐらい、もはや貧富の差は大きくなっているのだと貧しい人たちは反論するでしょう。少なくとも人間らしく暮らす権利はあるはずだと言われれば、国家の福祉を手厚くしなければなりません。ところが、福祉予算が膨大な額に上ると、国家財政を破綻寸前にまで追いやってしまうわけです。自由と平等、どうバランスをとりながら社会を運営するべきなのか、フランス革命が悩んだ同じ悩みを現代社会も抱え続けているわけです。
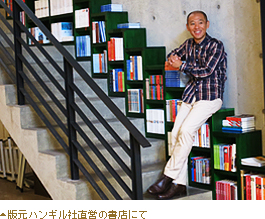 さて、それでは我々はどうすればよいでしょうか。先ほどフランス革命には自由、平等、友愛という標語があったと言いましたけれども、自由と平等、もう一つ友愛というものに、ここで注目してみたいと思います。
さて、それでは我々はどうすればよいでしょうか。先ほどフランス革命には自由、平等、友愛という標語があったと言いましたけれども、自由と平等、もう一つ友愛というものに、ここで注目してみたいと思います。
自由と平等を折り合わせようとすれば、当時は友愛しかありませんでした。ロベスピエールたちが試みたのが、最高存在の信仰というものでした。これはルソー的な善、公共善を神として信仰する、言ってみれば新しい宗教の創造でした。その信仰を絆としてフランス人はみんな家族になろう、助け合おうという理屈なわけですけれども、つまりは友愛という精神をもっと高めようということなわけですけれども、やはりどうにも無理矢理な感が否めません。もとより人権という発想の母体となった啓蒙主義思想は、理性の重視、合理性の重視というキリスト教信仰の否定から始まっているわけです。
そういったキリスト教信仰を否定する動きから出た人権の世界、そこで再び宗教をつくろうとしてもうまくいくはずがありません。
しかし、それがフランスでなく、またヨーロッパでもなかったとしたらどうでしょうか。自由と平等を折り合わせる精神性を持ち続けているのは、それを破壊することなく、途中から接ぎ木のようにしてヨーロッパの近代化の諸理念を取り入れたほかの地域、つまりはアフリカであり、アジアではないでしょうか。そうすると自由と平等を両立させる新たな社会、新たな価値を生み出せるのもアフリカであり、とりわけアジアなのかなと思います。
我々アジア人がフランス革命という歴史を知ることは、フランス革命という歴史を通して、私たちは今、何を見つめ、何を考えるべきなのか、より具体的な示唆を得ることが最大の意味だと思います。それに少しでも役に立てたとするならば、私にとってはとてもうれしいことです。