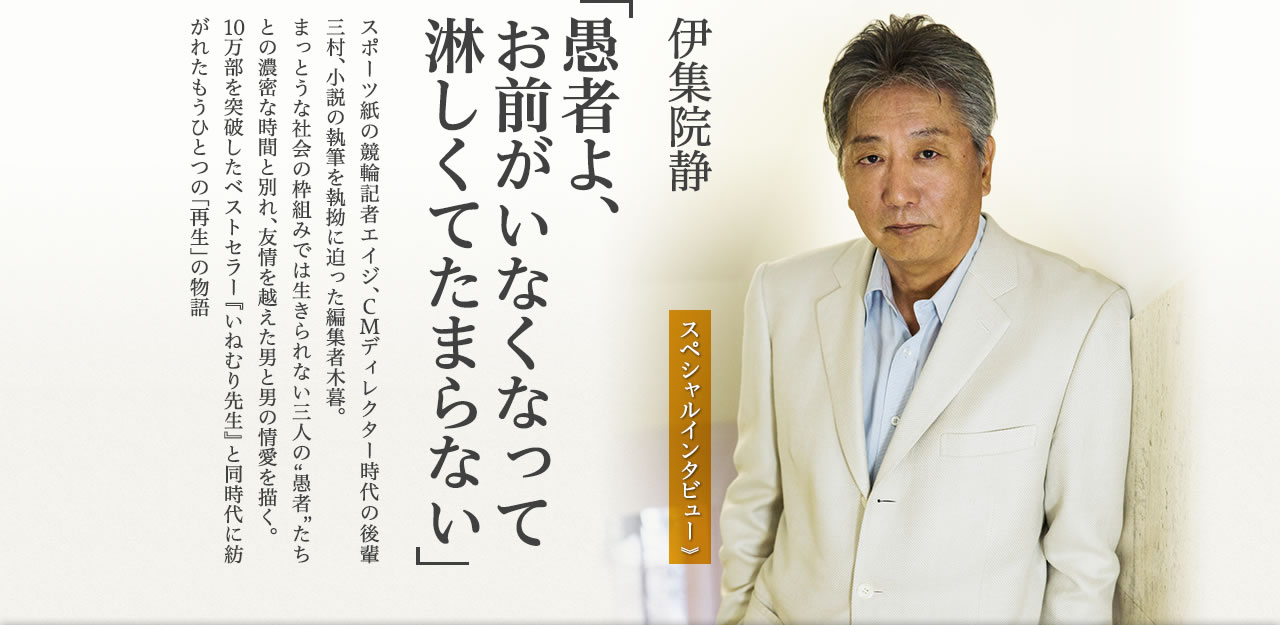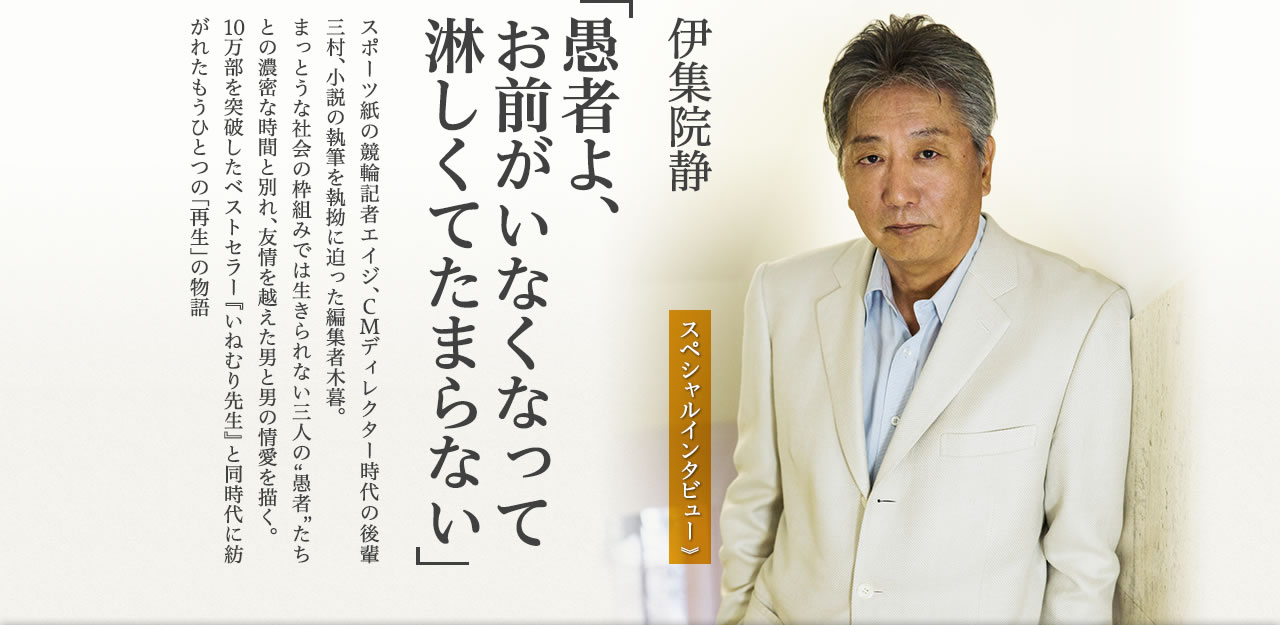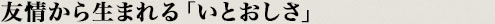
──主人公のユウジが、エイジたち三人の友だちへの想いを語る場面があります。《まっとうに生きようとすればするほど、社会の枠から外される人々がいる。なぜかわからないが、私は幼い頃からそういう人たちにおそれを抱きながらも目を離すことができなかった。その人たちに執着する自分に気付いた時、私は彼等が好きなのだとわかった。いや好きという表現では足らない。いとおしい、とずっとこころの底で思っているのだ。》この「いとおしい」という言葉が印象的です。
一見、愚かに思える人のほうが実は限りなくやさしいところがある。逆にいえば、この主人公は彼ら以外の人たちからやさしさを得ることができなかった。だからこそ、エイジたちのもっている独特の温度みたいなもの、ぬくもりみたいなものを感じていたのだと思う。「原風景」という言葉があるけれど、彼らがもっているやさしさというのは、「原慈愛」みたいなものなのではないか。そこにユウジは感応して、いとおしさを感じたということなのではないかな。もっとわかりやすくいうと、エイジはもう一人の俺なんだ、三村はもう一人の俺なんだ、木暮はもう一人の俺なんだ、と。つまり、彼らのなかにある〝愚かさ〟を自分ももっているからこそ、余計に彼らがいとおしくなる。
社会にうまく適応していくことができなくて、だんだん自分の生き場所を狭くしていってしまう人というのは、いつの時代もいる。彼らは彼らなりに必死に抗っているのだけれど、結局はうまくいかない。しかし、そういう人たちも居場所を得て生きていくことができるのが社会というものなんだから、今さらそういう人たちは要らないと現代社会がいうのだったら、わたしは、「それは違うと思うぜ」と声を大にしていいたい。そうした思いが、この小説を書かせた一つの要因です。
──彼らへの「いとおしさ」を支えている大きな柱が友情ですね。
そう。ここのところのわたしのテーマの一つが友情です。『ノボさん』がそうなんです。漱石と子規の友情です。なんというかな、何十年も生きてきて、一番すばらしいものは友情なんじゃないのかと思うに至った。もちろん、妻への愛情とか子どもへの慈しみにも大いなる喜びがあるのだけれども、友情ほど美しくて切ないものはないのではないか、と。
友情のなにがいいかというと、代償を求めないことです。今はなんにでも代償を求める人が多いけれど、それなしに成立する貴重な関係が友情にはある。そこには男と女とはまたちがった恋愛感情があって、そこからいとおしさも生まれるのだと思う。タイトルの「淋しくてたまらない」というのも、一種の愛情表現ですからね。
──今回の作品には、エイジたち三人の死のほか、海難事故で亡くなった弟、病を得て旅立った妻、そして突然の死に襲われた作家のI先生など、死というものが色濃く出ているように思います。
たしかに。ただ、わたしなりの死のとらえ方というものがあって、たとえば、彼らはほんとうに死んだのだろうかという想いをどうしても拭えないところがある。頭では、彼らが死んだということはわかっている。しかし、どこか納得できないでいる部分がある。小説の後半、夢の場面が出てきます。弟と妻とI先生が一緒の船に乗っていて、主人公も船に乗ろうとすると、妻に「あなたはこの船に乗れないわ」といわれる……。あれは実際に見た夢で、そのとき初めて「ああ、あの三人は、やっぱりほんとうに死んでいたんだ」と実感できた。ということはつまり、それまでは死を受け入れていなかったんです。
死というのは、ただその人に逢えなくなるだけであって、それ以上でもそれ以下でもない。もっといえば、死は完全な別れではないということです。
3・11の大震災でも大切な人を失った人はたくさんいます。逢えなくなったのはとても切ないことだし、なんとも胸が痛むことだけれど、死によって、その人と完全に切り離されたというわけではない。その人との忘れ得ぬ記憶こそが、生き残ったものの生きる証なんだ、そうやってつながっているんだ、と。そうした想いを、この本を読んでくれた人たちが、少しでも共有してくれるとうれしいですね。