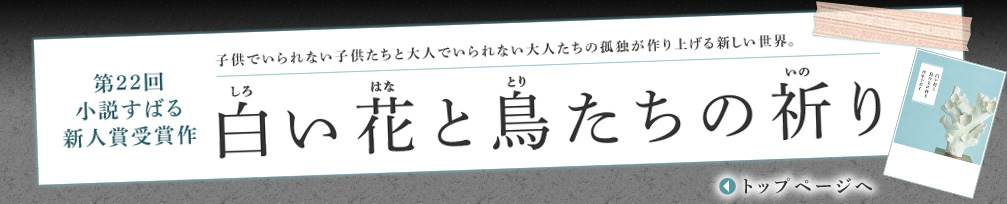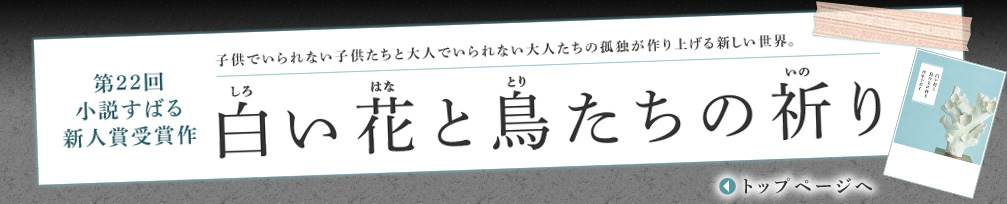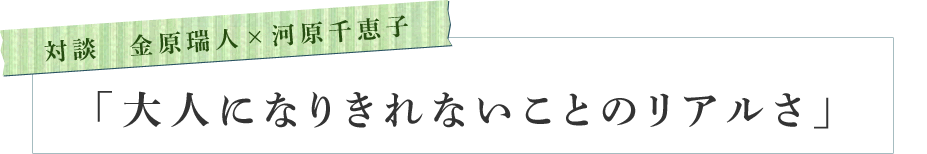| 金原 |
主人公のあさぎのキャラは、ある状況の中でいつのまにか周りからずれてきてしまうんだけれど、現実的によくいそうな女の子ですね。それに対して中村君という郵便局員は、最初からかなりずれてしまっている。その二人の視点から世界を描いていくという発想は、最初のころからあったんですか。 |
 |
| 河原 |
最初はすべてあさぎの一人称でいくつもりだったんですけれども、そうすると、あさぎのわからないこととか、知らないこととかが書けなくて ……。 |
 |
| 金原 |
で、中村君の一人称の部分もちょこちょこ間に挟んでいる。全体の構成としては、それできれいに決まっていますよね。これを読んだとき、森絵都の『つきのふね』という作品を思い出しました。主人公はやはり中学生の女の子。そしてもうひとりスーパーか何かでバイトをやっていて、ひたすら人類を救う宇宙船の設計図ばかり書いているという、ちょっとずれた感じの青年が出てくる。その設定がよく似ているし、もう一つは、手紙がとても効果的に使われているんです。河原さんの作品でも、あさぎのお父さんの手紙が驚くほど効果的に使われていて、並べてみるとすごくおもしろいなと思って。あの手紙は、最初からプロットに入っていたんですか。 |
 |
| 河原 |
お父さんと話すというのは決めていたんですけれど、直接話すとか電話とか、いくつか選択肢があって、どれにしようかと ……。 |
 |
| 金原 |
お父さんの話す、あるいは書く内容は決まっていた? |
 |
| 河原 |
いえ、それだけ最後に残ってしまって、締め切り直前にガッと書きました。 |
 |
| 金原 |
ぼくが一番印象的なのはあそこかもしれない。
中村君もそうだけど、あさぎのお母さんも継父の冬木さんも、ここに出てくる大人たちはみんな大人になりきれてない大人みたいなキャラですよね。そういうキャラは、河原さんの中では自然に生まれてきたんですか。 |
 |
| 河原 |
金原さんの『大人になれないまま成熟するために』を読ませていただいたんですけれども、自分もまさしくそうというか、大人になったという自覚がないんです。周りの同年代の友達とか見ても、どこか大人になりきれてない部分を維持しながら大人をやっているような人がすごく多くて、それが自分にとってはリアルなんです。だから、ここに出てくる大人もそういうふうに書いたんですけれど、ちゃんとした大人が書けてないという批判もきっとあるだろうなと思います。 |
 |
| 金原 |
逆に、いま現代を書こうとすると、こういう小説にならざるを得ないし、現実に大人らしい大人はいない。そういう意味では、まさに現代だなという説得力がありますよ。
そういうリアルさに裏打ちされているからだと思うんですけど、実は、この本の中には、あちこちにぼくの好きなフレーズがあるんです。たとえば、「言葉を重ねれば重ねるほど、遠心力で振り放されるみたいに中心から遠ざかって」とか、そういう、おやっという、芝居の決め台詞みたいな文章が、とくに後半いきなり増えてくる。それは意識的? |
 |
| 河原 |
ちょっといやらしいんですけど、あらかじめ使いたいフレーズがあって、そこに行き着くために書いたみたいなのはあります。 |
 |
| 金原 |
そこが妙に素人離れしていて恰好いいんだよね。「世界は、あなたが考えていたよりはやさしいのかもしれない」「僕にできるのは、一緒に途方に暮れることだけだ」「過去のことは、過去に考えさせておきましょう」とか、付箋を貼ったり、線を引きたくなるようなフレーズがあちこちにあって、後半は読む速度が落ちてしまいました。
ああいうフレーズは自然と頭に浮かんでくるの? |
 |
| 河原 |
ぽかっと浮かんだものを書いておくんですけど、それをうまく使えないときもいっぱいあって、使えたときはすごくうれしいです。 |
 |
| 金原 |
登場人物の心情に台詞がピタッとはまったら、うれしいだろうな。それはわかる。
そういう主人公のあさぎが感じている、周りとずれているという居心地の悪さ、あるいは中村君の置かれている状況の切なさというのは、河原さんの中ではとてもリアルなものとしてあるんですか。 |
 |
| 河原 |
かつていたところという意味では、とてもリアルです。 |
 |
| 金原 |
かつてっていつごろです? |
 |
| 河原 |
ほんの二、三年ぐらい前まで感じていたことですね。 |
 |
| 金原 |
そのリアルな気持ちというのがこの作品を書く原動力にしっかりなっている。 |
 |
| 河原 |
自分でもそう思います。多分その状況のただ中にいたら書けなかった、脱け出たからこそ書けたかなという気はします。 |
 |
| 金原 |
それがとてもいい形で作品になりましたね。そういうものって書きづらいと思うし、なかなかいい形で書けないことが多いんだけど、その意味ではとてもラッキーな作品です。 |
 |
| 河原 |
そうですね。本当に運がよかったと思います。 |