- 青少年のための小説入門
久保寺健彦・著 - 2018年8月24日発売
ISBN978-4-08-775442-1
定価:本体1650円+税
いじめられっ子の中学生・一真は、万引きを強要された店でヤンキーの登と出会う。
一真のピンチを救った登は「小説の朗読をしてくれ」と不思議な提案を持ちかけた。
名作小説を共に読むうち、いつしかふたりは本の面白さに熱狂しはじめる——。

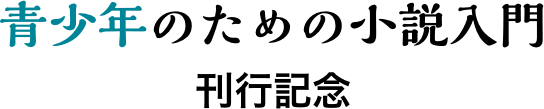
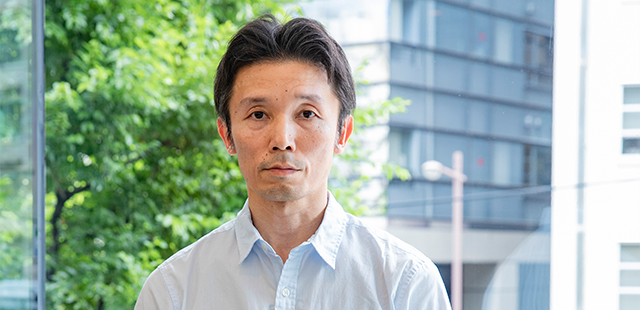
右半身が麻痺したおばあさんのかわりに駄菓子屋の店番をしている不良青年の「登(のぼる)さん」は、僕にとって〈絶対にかかわりたくない存在〉だった。しかし中学二年の春、あるきっかけから毎日彼のために小説を朗読することになり——。
久保寺健彦さんの『青少年のための小説入門』は、中学受験に失敗し公立中学に通う一真(かずま)と、ディスレクシアという学習障害のために、自由に読み書きのできない登さんが、コンビを組んで小説家を目指す物語。
アイデアを思いつくまでに四年、そこから書き上げるまでには三年をかけたという、書き下ろし長編小説に込めた思いをうかがいました。
何千枚と書いてはいたんです
書けなくなっていたんです。まず、前作を出してから『青少年のための小説入門』のアイデアを思いつくまでに4年かかったんですが、それまでがいわゆるイップスの状態で。プロのゴルファーがパターが入らなくなってしまうとか、プロのピッチャーがストライクが入らなくなるといった、ああいう感じに近いです。「これならいける」というアイデアを書き出しても100枚くらいで「あ、これはダメだ」ということを繰り返していました。だから400字詰めの原稿用紙に換算すると何千枚と書いてはいたんです。
手応えはすごくありましたが、やっぱり100枚ほど書いて行き詰まってしまって。これは書き方がダメだと思いました。
それより前に、シド・フィールドというハリウッドの脚本家の『映画を書くためにあなたがしなくてはならないこと』という脚本術の古典を読んだことがあったんです。ずいぶんシステマティックな書き方を推奨していたので「そんな機械的にできるものじゃないだろう」と反感を持っていましたが、今回のアイデアはなんとか形にしたかったので、彼が勧めていることを愚直にやってみることにしました。56枚のカード、つまり場面を作っておく、などといったことです。僕は場面というよりも小説が迷子にならないための56のチェックポイントを作るという意味だと理解して、それを愚直にやっているうちになんとなく書きだすことができたという感じです。そうやってプロットを作り込んで、それも修正して修正して……と、そこからまた時間がかかりました。
ベルンハルト・シュリンクの『朗読者』という、少年が年上の女性に本を読み聞かせる話がありますよね。あれを読んで朗読っていいなと思っていたんです。どの本を朗読したのかも作中にたくさん入れたいと思いました。映画では「ニュー・シネマ・パラダイス」が好きなんですが、あれは映画をめぐる映画の話ですよね。ああいうふうに、小説をめぐる小説の話ができないかという気持ちもありました。
そのためにはどうしたらいいか考えて、読み書きが不自由な人が作家になろうとする、というのはどうだろうかと。自分じゃどうにもならないから誰かを無理やり連れてきてまず読ませて、その後に「俺が頭の中で作った小説を話すから書き留めろ」という設定にしたら、朗読シーンがたくさん盛り込めると思いました。
最初に「読め」と言われた時に「嫌です」と言える人物だと話が成立しないので、登さんはすごく怖い人でないといけませんでした。この話で何が一番ファンタジーかというと、二人のコンビの結成の部分じゃないかと思いますが、ただ、登さんは本当は真面目なんです。
二人が出会う時代を80年代にしたのは、まだディスレクシアという学習障害の存在自体がほとんど知られていなかったから。実際に当時学校に通っていた方の本を読むと、学校でも病院でも「怠けているんだろう」と言われて無理解な目に遭って、不良化した方もいたようです。今はもう補助的な学習ツールができているので、音声ソフトを使って自分で本を読む方法もあるし、登さんは独立独歩の人だから、もし現代なら人を頼っていないはず。このファンタジックなコンビが成立するためには、ディスレクシアが知られていない時代じゃないとまずいと考えました。でも、最初は朗読だけにフォーカスした話だったんですが。
たぶん、尻込みしていたんですよね。後からとことん書いたほうが面白いだろうと思って小説を作る過程も書くことにしましたが、かなり苦労しました。何度も書き直して、キャラクターも展開も、大分変わっているんです。56だったチェックポイントもそれ以上に増えていると思います。
新鮮味がなければ「インチキ」だって感じてしまう
これは楽しい作業で、苦労しなかったです。自分がよかったと思った本をたくさん入れたかったんですけれど、やはりその作品を知らない読者に「え、何それ」と思ってもらえるよう、インパクト重視なところがありました。それで筒井康隆さんの『バブリング創世記』とか、一文がやたら長い柴田翔さんの「ロクタル管の話」とかを入れていきました。いい作品だけれど引用しても驚きのないものは話に組み込めず泣く泣く省きました。それでも、勝手な被害妄想ですけれど、「この人この作品がいいと思っているなんて」と思われるのが悔しいので(笑)、絶対面白い自信があるし、センスがあると思ってもらえる作品を揃えたつもりです。実験的な作品が多くなりましたが、もともと僕自身が筒井康隆さんの薫陶を受けているところがあるので、実験性と笑いのある作品が多いですね。
一真もそうですけれど、読んでいる方も、読み書きできない人が小説家を目指すなんて無理だろうって思うじゃないですか。でも登さんは子どもの頃におばあさんに絵本をいっぱい読んでもらっている。自分で読もうと思っても字は読めないから、絵だけ眺めて何パターンもお話を作ってきた。ストーリーを作る力が潜在的にある人なんですよね。「蒲団」を換骨奪胎したものは面白いかもしれないけれど、新鮮味はないかもしれない。とはいえそのレベルだったらいくらでも量産できる人なんです。
僕自身もあの本が好きなんです。高校生の時に野崎孝さんの訳で読みましたが、村上春樹さん訳の『キャッチャー・イン・ザ・ライ』を読んだらまたすごくよくて、ちょっと特権的な小説じゃないかなと思いますね。
「ノベル」という言葉には、「新奇なもの」という意味もあるんですが、新鮮味がなくても小説って書けると思うんです。けれどそういう作品は、それこそ主人公のホールデン的にいえばインチキなものだと僕は感じてしまう。もちろんそういう小説が流通するのはいいと思うけれど、本当に面白いのかなと思ってしまう。一真と登さんは若いから、それこそストレートに反応して「インチキだ」と言ってしまう。そして、インチキじゃない小説を目指すんです。
彼らが読者の意見が欲しい時、歯に衣着せぬ性格でずばずば言ってくれる子です。本人もコバルト文庫などを読み込んでいてセンスがいい。一真を挟んで登さんの世界とかすみの世界があって、一真にとってはどちらも大事だという、わりと三角関係みたいな話にもなっていると思います。かすみに関しても、後半は何度も書き直していますね。
僕はスポ根世代で、それこそ「巨人の星」みたいに無茶苦茶なギプスをはめて投げて……というトレーニングシーンが好きなんです(笑)。だから一真も登さんに文章をボロクソに言われながらも訓練してうまくなっていく話にしました。小説の指南書もずいぶん読み返したんですけれど、再現クイズに近いものといえば、大塚英志さんが、原作が映像化された作品を受講生に見せて、そこからあるシーンを切り取って文章を書かせることをしていたらしく、それが使えるなと思いました。
僕自身が読んでみたいと思うような小説ということで、彼らが書くものも実験的なものになりました。
アイデアとは既存の情報の組み合わせだとはよく言われますけれど、この作品が『朗読者』や「ニュー・シネマ・パラダイス」からインスパイアされているように、小説というものは何かしら先行作品の影響を受けている。そういうなかで彼らの小説のアイデアを見つけるのは大変でした。換骨奪胎したものではなく、かつ、新鮮で面白そうと思わせないと意味がないですから。「鼻くそ野郎」も、その他に彼らが書く「機械じかけのおれたち」や「パパは透明人間」も、いずれ自分で書きたいと思っています。
二人組の作家、岡嶋二人さんの『おかしな二人』を読んだら、やっぱりアイデア担当と文章担当に分かれていて、セッションしていくうちに横滑りしたりして、結局「それでいいじゃん」となっていく。そのライブ感がとてもよくて、参考にしました。
小説は無力なのか?
僕も経験していることですから、絵空事ではなくちゃんと書こうと思いました。経験を反映しているけれど、そのままでは弱いので多少誇張していって、過激な方向に行ったのが二ノ宮という編集者。反対に久間という人は作家に指図しないタイプで、僕は無能に書きすぎたかと思っていましたが、周囲の編集者からは「久間さんがよかったです」と言われて意外でした(笑)。
僕は言いっ放しでいいので、意見をばんばん言ってくれていいと思うんです。ブレストができればいいので。でも個人的にやめてほしいのは、ブレストでアイデアを口にしているのに「いや、それはダメです」となんでも否定すること。アイデアがしぼんでしまうので。
前の小説『ハロワ!』は連載最終回の締め切りが2011年3月15日だったんです。希望が見える終わり方にしたいなと思いながら最終回を書いていたら、締め切り4日前にああいうことがあって。僕は東京に住んでいるし被災地に親しい人がいるわけでもないから、甘えなんですけれど、小説の最後に希望を持たせることに何か意味があるのか、小説の存在意義みたいなことを考えてしまったんです。
寺脇さんは「小説は無力だ」と言う。でも自分では、この小説は「そうじゃないんだ」という話だと思っています。そう主張する時に一番の敵となるのが寺脇さん的な「なんの存在意義があるんだ」という考え方ですよね。だから寺脇さんは書いていて一番手応えがありました。
いえ、最初は「あ、これで気持ち悪くない」という消極的な感覚でした(笑)。何度も失敗しているので不安だったんですが、読んで気持ち悪くないのでこれで大丈夫という感じ。ただ、最後にどうするかは最初から決めていました。北野武さんの「キッズ・リターン」という映画がすごく好きだったんですよね。まったく違う二人がタッグを組むけれど一人がいなくなって……という。この小説の結末とは違いますが。
そういうことですね。僕も何か、スタート地点にもう一度立てた気がしますね。小説の書き方という面でもそうだし、なぜ自分は小説を書いているのかとか、どういう作品が好きなのかといったことが、改めて分かった気がします。デビューした頃のインタビューでも、自分が読みたい小説、書きたい小説は新奇なものなんだと言っていて。それは新鮮味というような意味に近いと思うんですが、そういうものが書きたいですね。

聞き手・構成=瀧井朝世/撮影=山口真由子
(「青春と読書」6月号より転載)