


| 究極の問い
──カルト宗教について書こうと思ったきっかけを教えてください。 前からずっと書きたいテーマではあったんです。オウム真理教の事件があった一九九五年、僕は高校生でした。多感な時期にいたこともあり、この日本の社会の常識とはまったく別の論理、別の常識を持った人たちが集団として存在していることにものすごく衝撃を受けたんです。当時の僕は社会のなかで疎外感を抱いていたので、もしもオウムが人を殺すような教団ではなかったら、自分も惹かれていたんじゃないかとも思いました。そのことがずっと頭にあったので、いつか小説に書いてみたかったんです。でも書くと絶対に大長編になるので、簡単にできることではなかった。ちょうどデビューして十年が経とうとする頃にそろそろ時期なのかなと思い、二年半前くらいから書き始めました。今の世界情勢を眺めていて宗教は本来人を救うものなのに、宗教にとらわれ過ぎているがゆえに非常に困難な状況が生まれていると感じていたので、オウムの事件で感じていたことと、それが結びついていきました。 もうひとつ、僕は小説を書く時に人間とは何か、世界とは何かということをずっと考えています。それに思い切り取り組もうという気持ちもありました。ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』のような、人間とは何か、世界とは何か、神とは何かという究極の問いに真正面から取り組む必要を感じていたんです。 ドストエフスキーはキリスト教の思想を中心にして自分の文学世界を展開しています。でも僕はキリスト教圏の人間ではないので、また違うアプローチができると思いました。ではドストエフスキーに書けなかったものは何かと考えた時、最新の科学、テクノロジーだと思ったんですね。プラス、仏教も取り入れようと思いました。最新の科学や生物学、宇宙論に仏教を加えて、さらにキリスト教も合体させて、多角的に書いてみたかった。それは過去の作家にはできなかったことだし、二十一世紀の作家がやる意味がある。日本人という特性も活かせる。そうなると日本論みたいなことや、世界の貧困問題やテロの問題も避けて通れなくなる。 それでいろいろ調べ始めました。仏教を書くなら、遡って古代インドの神話まで調べようと思い、『リグ・ヴェーダ』についての中村元さんの本を手に取ったんです。そうしたら、作中にも書きましたが、『リグ・ヴェーダ』に書かれている宇宙論は、最新の宇宙論とかなり似ているんです。これにはびっくりしました。 ──作中にもありますが、宇宙の生成についての部分ですよね。「かれら(=聖賢)の紐は横に張られた」などと、超ひも理論を予見していたような記述があるんですね。 今から三千年くらい前の本がなぜ今の宇宙論とかなり重なっているんだろうと思い、生物学、宇宙科学、物理学にも関心が湧いてくる。こうなったら全部書いてやろう、包括してやろうと思って。膨大な量の本を読みながら、人間とは何か、世界とは何かということに僕なりの答えを出そうと思いました。 |

| 物語の展開はスリリングに
──具体的なストーリーはといいますと、まず楢崎透という青年が自分の前から姿を消した立花涼子という女性を探して、松尾正太郎という男を教祖とする宗教施設を訪れます。そこで聞かされたのは、以前沢渡という男が数十人の参加者を引き抜いて姿を消したことがあり、立花涼子は彼の仲間だった、ということ。その沢渡が教祖の団体が「教団X」です。主要人物が複数いますが、これはどのように想定していったのですか。 楢崎君と立花さんと、沢渡の教団で革命を企んでいる高原君くらいを考えていたんですが、途中から松尾の施設にいる峰野さんがどんどん重要人物になっていきました。この本はその若い男女四人と、松尾と沢渡という二人の教祖の話といえますね。 ──ごく一般人でありながら巻き込まれていく楢崎君と、自ら行動を起こしていく高原君が対照的です。 僕という人格を二人に分裂させていますね。楢崎が僕の中の大人しい部分とすると、高原は僕のちょっと激しい部分が表れている、ということだと思います。考えてみれば立花さんは理性的な女性で、峰野さんは愛情的な女性。意識はしていませんでしたが出来上がったものを見ると、それぞれに個性がありますね。 ──教団を二つ設定したのはどうしてですか。 これは僕の文学的な系譜の問題でもあると思います。『何もかも憂鬱な夜に』に出てきた、主人公の自殺を止める施設長にもつながる、善的な存在が松尾さんで、『何もかも~』でいうところの強姦魔の佐久間や『掏摸』の木崎の系譜の、化け物みたいなものを沢渡として登場させました。沢渡という存在は、これまで書いた中で一番悪い奴を書こうとしたんですが、結果的にとんでもないものができたと思っています。 ──中村さんの小説にはミステリやサスペンス的な醍醐味もありますが、読者の楽しませ方はどう意識しましたか。 読んでハラハラするものが一番いいので、物語をとにかく動かしました。前半のうちに読者にある程度の予備知識を持ってもらわなくてはいけないので松尾さんの話を長くしましたが、後半はテロが起きて、一気に動くようにしました。以前ボストンマラソンでテロが起きた直後、僕はちょうどロサンゼルスのブックフェスティバルに行っていたんですが、そこも警察がずっと監視していたんですよね。どこで何が起こるか分からない状況なんだと思い、それは怖いなと感じて。小説では、最初は原発が関わるテロも頭にちらついたんですが、場所が特定されないテロというのが一番怖いなと考えて、ああいう形にしました。 籠城事件というのも書きたかったことですね。立てこもりって、そこが異空間になるということだから、変な話、若干ワクワクするんです(笑)。包囲された後にどう展開するかは考えていなかったんですが、ある人物が残した携帯電話や財布をうまい具合に利用することができました。 |


|
最先端の知見を盛り込む
──前半は松尾さんの話を長くしたとおっしゃる通り、相当な分量を割いていますね。さきほどの『リグ・ヴェーダ』のことも松尾さんが語る話として出てきます。他にも膨大な知識に基づいた思想的なことが丁寧に語られていく。気になるところに付箋を貼っていたら、付箋だらけになってしまいました。 僕自身が本を読んで線を引きたくなるような内容を書いているので、きっとそうなりますよね(笑)。大事なことしか書いていません。最初にこれらを踏まえておいてもらわないと、後半の沢渡の話や松尾さんの遺言の言葉も、何を言っているのか分からなくなってしまう。だから前半で、物理学や化学、宇宙論に基づいた世界の解釈を書きました。僕の思想告白みたいなことです。例えば、人間が全部素粒子でできていることなんて、普通は意識しないで生きている。でもそう考えていると、また世の中が面白く見えてくるんですよね。人が死んで火葬されても、原子レベルでは解体は行われていなくて消滅はしていない。原子は残りまた何かを構成するということを語っています。シンプルだけれど斬新ですよね。命が生まれるということは無から何かが生まれるというわけではなくて、すでにある材料が組み合わさってできているだけで、そしてまた死を迎えると分解されていくだけだという。そういう世界観は昔の文学では書けないですよ。でも、そこにすでに言及していた仏陀という存在って相当ですよね。 ──私たちの行動は自分の意識が思考して決定しているのではなく、脳が勝手に決定しているという説も面白いですよね。 人の意識は脳に働きかけることができないという説ですよね。それはつまり、起きることが全部、予め決まっているということになる。初めはそういう因果律で全部説明することも考えました。ランダムに見えることにも法則があれば、人間の運命の発見になるから。本当にそうだったら僕自身は嫌ですが、興味を惹かれました。それで大学の教授に話を聞いたら「いや、因果律ではなくランダムだ」と言われました。今の物理学ではまだ確定できないみたいですね。それじゃあこの小説が書けないじゃないかと思ったけれど(笑)、強引に因果律に決めつけることはせずに、ちゃんと書きました。時と場合によって、人はこれは運命だからしょうがないよねと思ったり、運命は変えられると信じたりするという。ただ、量子論と相対性理論を合体させると宇宙の全部が分かるそうですから、生きているうちに誰か天才がちゃんと計算してくれればいいのに。文系の小説家としては、それを使ってまた物語が書けますから。 |

| 作者と主張、そして最高傑作
──松尾さんが影響を受けた鈴木という教祖を存在させたのは。 松尾さんの施設は「みんなで神がいるかどうか考えてみよう」という緩い会で、沢渡のほうは性的な快楽に耽るという集団なので、それだけではまずいと思って、きちんと教義のある鈴木さんの教団というものを出しました。他には、アフリカの武装組織のところで教義的なことを書いています。 ──沢渡の教団は快楽志向が強い。性描写にも果敢に挑んでいますね。 そうですよね。昔は小説の性描写はエロビデオには負けると思っていたんです(笑)。でも最近、勝てるかもしれないと思っていて。どう書くかによって、言葉だけのほうが逆にエロくなるんじゃないか、ということはものすごく意識して書きました。 ──沢渡の教団がなぜそんな形になったのかは、後半に沢渡の過去が明かされると納得いくものがある。彼の過去は壮絶ですね。 沢渡の過去のシーンを書く時に、どれだけホテルにカンヅメしたことか。閉じこもらないと書けなかった。もちろんホテル代は自腹です。だからあの部分は僕の全原稿の中で一番お金がかかっている原稿です(笑)。「沢渡のあの場面はやばいよね」と言われるものにしたかった。そう思って書いたのに最後には仏教へ繋がっていったんです。それは自分でも不思議でした。 高原君の手記を書く時も、何回も手が止まりました。海外の過激派の中に日本人が入っていくという内容ですが、あそこは僕のデビュー作の『銃』や『遮光』に似た文体をもう一度使っています。長編なのでいろんな文体があったほうが面白いと思い、わざとうねるように書いてみました。 ──松尾さんは情報を提供するだけでなく、最終的に自身の意見も主張します。理想論にも聞こえてしまいそうですが、これは慎重に考えられたのではないでしょうか。 松尾さんの平和についての論は、理想ですよね。今の世の中がよくない状況に流れていっているので、その中で理想というものを置いておくことが重要だと思い、僕の考えを松尾さんに言わせました。彼が言っていることは理想論かもしれませんが、理想を持つことは大事であって、そこから現実と理想をどう合わせるか、どう格闘させるのか、ということですよね。でも読者に意見を押し付けるつもりはなかったので、最後に松尾さんの奥さんに、思想に頭を垂れて従うのではなく自分なりのオリジナリティーを加えていきましょう、ということを言わせました。 今回、日本というものを考えたくて、政治の本もたくさん読んだんです。右の本も左の本もいろいろ読んで、その中で抜け落ちていることを書こうと思って。 だから、主張が表れている部分もあります。テロの実行犯の一人とテレビのコメンテーターのやりとりなどで、政治に詳しくない人にも分かるように一から説明しています。こういうことは、本当は触れないほうが作家としてはやりやすいんですよ。政治的なことから距離を置いて、我関せずみたいな態度をとるのが「一番頭のいい」やり方。でもそれじゃ僕が書く意味がないと思ったんで。やっぱりこのあたりが、僕がサルトルの影響を受けているところですね。自分はこう思っているということは言ったほうがいいと、どうしても僕は考えてしまう。「こんなこと書いちゃってるよ」と言う人もいるかもしれないけれど、現代文学としては、こういう作品がなければいけない。むき出しの言葉でなければ伝わらない。 ──作中で、人間が物語を求める生き物だということも、繰り返し主張されていますね。 人は何のために生きるのかということについての、僕なりの結論でしょうか。人間の物語にはおそらく優劣なんかないという、僕の思想というか世界の見方がそこに出ています。 ──ひどく絶望的なことを描きつつも、強い希望を持たせる話になりましたね。 我ながらよくできたと思いました(笑)。三十代でこういうものが書けてよかったです。最高傑作だと思っています。僕、毎回新作が出るたびにそう言っているのであまり説得力がないんですが(笑)、本気でそう思っています。 |
| 聞き手・構成=瀧井朝世/撮影=柳本史歩 |
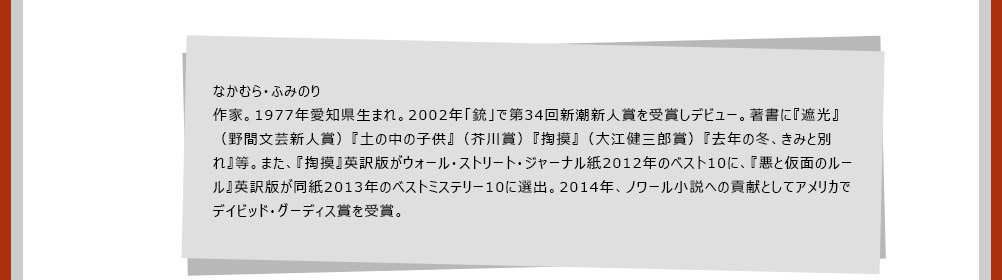

COPYRIGHT (C) SHUEISHA INC. ALL RIGHT RESERVED.