 |
 |
 |
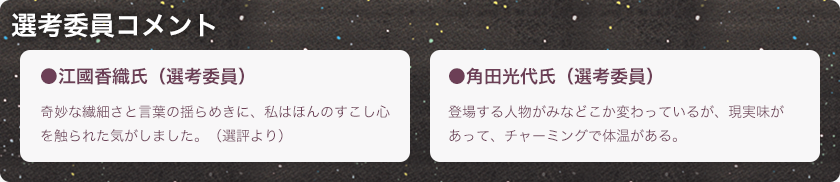 |
 |

|
|
|
|
|
|
|
|
|
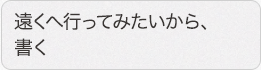
|
|
 |
|
Q 初めて読んだ本のことを覚えていたら教えてください。 A 実際に読んでいた記憶はありませんが、家にあった本の中で一番古そうなのは、バスネツォフという方の絵の『3びきのくま』です。ただ、小学生のころですら怖い絵だなと思っていたこの本を、幼少期の私が本当に楽しんで読んでいたのか、いささか疑問が残るところではあります。 Q 普段はどのような作品を読んでいますか? また、自身が強く影響を受けた本を1冊教えてください。 A 近年の日本が舞台の話が多いような気がします。あとは、遠藤周作さん。影響を受けたというとおこがましいのですが、『沈黙』は読み終えたときの衝撃の形を今でも思い出せます。最後に価値観が裏返るような話が好きなのは、ここに起因しているのかもしれません。 Q 「作家になりたい」と思ったのはいつごろですか? A 淡い憧れは子どものころからずっとありました。確実なものになったのは、小説を書いては応募することを繰り返していた6年半のあいだです。雑誌に一作掲載されればいいのか、本を一冊出せればいいのか、同人誌ではだめなのか、と、自分の欲求を煮詰めていった結果、私は継続的に小説を書いてそれでお金をもらいたいと思いました。 Q 初めて文学賞に応募したのはいつごろですか? A 2007年の9月です。半年ほどかけて初めて書き上げた小説を出しました。当時、ほぼ毎日プールに通っていて、泳ぎながら話の展開を考えては少しずつ書き進めていきました。よく完成させたなと思うほど、まったくの手探り状態でした。このころの記憶は水中の感覚と強く結びついています。 Q すばる文学賞受賞の連絡を受けたときのお気持ちを教えてください。 A あー終わった。書いて、応募して、結果が出るまで半年近く待って、どうして落ちたのかまったく分からなくても次の作品に取り掛かるサイクルからはとりあえず抜けたんだ、と思いました。悲観的な性格なので、今後順調にいくイメージは欠片も浮かばず、でもこれからはきっとだめなときにはだめな理由を教えてもらえる、めげずに書き続けようと決意しました。少し時間が経った今も同じです。 Q 『左目に映る星』は忘れられない少年を抱えた女性が主人公の物語ですが、このテーマで書こうと思ったきっかけはありますか? A 私にも忘れられない同級生の少年がいて、約15年間、かなりの頻度で彼の夢を見る自分に、もはや絶望的な気持ち悪さを感じていました。いつか小説にして昇華できたらと考えていたところで、左右の視力、見え方に差がある不同視という症状を知り、2つ合わせて話にできるかもしれないと思いました。 Q 作品を書く上で、大切にしていること、心がけていることはありますか? A その単語や文章で本当にいいのか、一字一句にまで、現時点でのベストは尽くしたいと思っています。あとは、読む人に無意味な苦痛は与えたくないなぁと。読みづらくするだけの個性に走っていないか、書いている最中からたびたび確認します。けれども、完成後に読み返して叫びたくなることも多いです。 Q 執筆以外の時間は何をして過ごされていますか? A 2歳の子どもがいるので、一緒に公園で滑り台を滑ったりブランコを漕いだり砂をほじったり、家で歌ったり踊ったりぬいぐるみなどあらゆるものにアテレコしたりして過ごしています。気力が尽きたら、子どもを膝に乗せてテレビを見せつつ、後ろで本を読みます。小説を書くのは子どもの就寝後です。 Q 今後、どのような作品を書いていきたいですか? A 部屋を整理しているときなどに目に留まって、そういえばこんな本持っていたな、もう随分読んでいないし手放そうかな、と悩まれても、やっぱりもう一回読むかもと棚に戻してもらえる、そういう小説を書きたいです。ひっそりと、けれどもいつまでもしつこく誰かの本棚に居座ることが私の目標です。 |
© SHUEISHA Inc. All rights reserved.