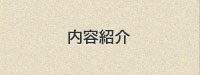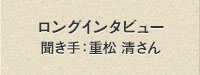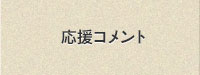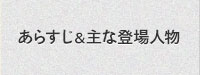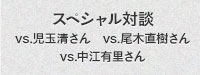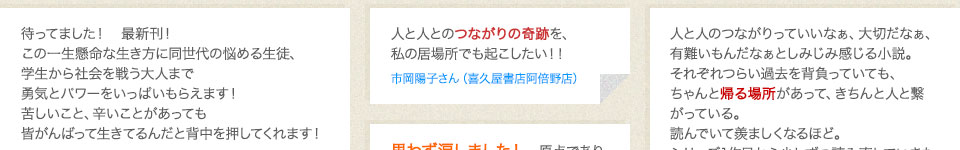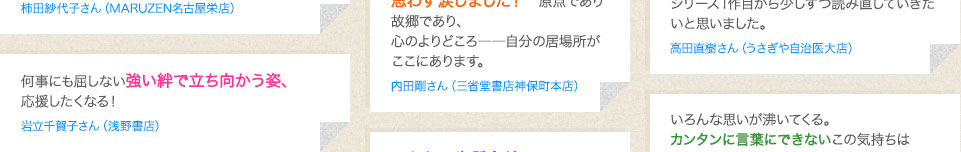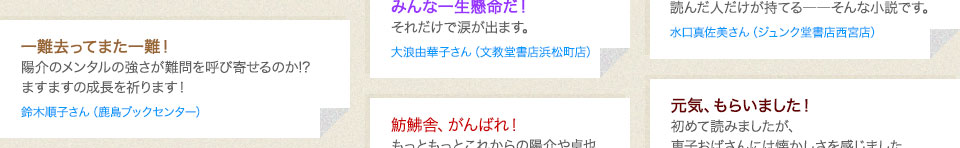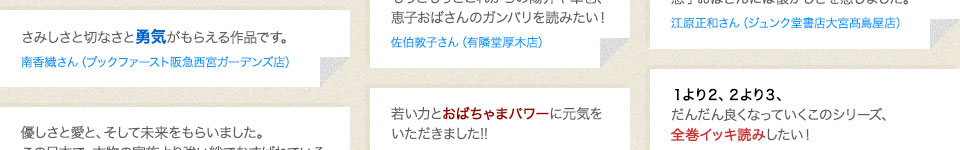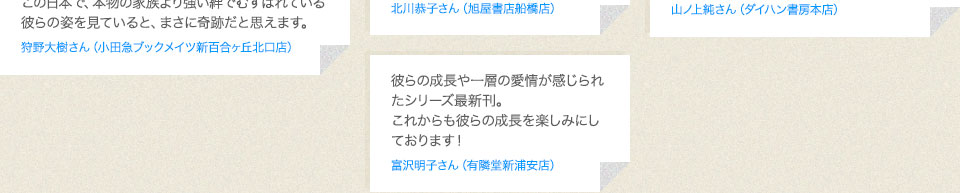『おれのおばさん』
(集英社文庫/本体450円+税)
単身赴任中の父が横領で逮捕。都内有数の進学校に通う中学2年生の陽介は、札幌で児童養護施設を切り盛りする「おばさん」に預けられることに。初めての集団生活に放り込まれた「おれ」は戸惑いながら、自分の生きる道を見出していく。
(解説・中江有里)

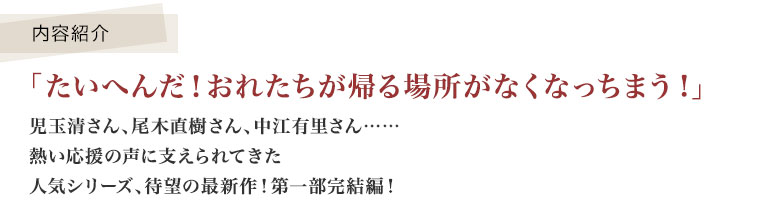
中学生ばかりが暮らす札幌の小さな児童養護施設・魴鮄舎(ほうぼうしゃ)。率いる恵子おばさんはいつだって真っ向勝負、エネルギッシュな変わり者で、彼女の情熱にたくさんの子どもたちが生きる道を見つけてきた。その魴鮄舎が閉鎖の危機にさらされているという。東北地方を襲った未曾有の震災から一年、耐震性が問題視されたのだ。今は魴鮄舎を離れ仙台の高校に進んだ陽介、青森の高校でバレーボール選手として活躍する卓也はすぐにおばさんのもとに駆けつける。が、当の恵子おばさんはなぜか「無理する気はない」と宣言。必死の思いで存続活動を始める陽介だったが、ある日、春高バレー進出を決める大事な試合を前に卓也が寮を飛び出したとの連絡が。卓也はどこへ向かっているのか? そしておばさんの真意は?
児玉清さん、北上次郎さん、中江有里さん、斎藤美奈子さん、尾木直樹さん…たくさんの熱い支持を得てきた青春小説ベストセラー・第26回坪田譲治文学賞受賞『おれのおばさん』シリーズ待望の最新刊、感動の第一部完結編!
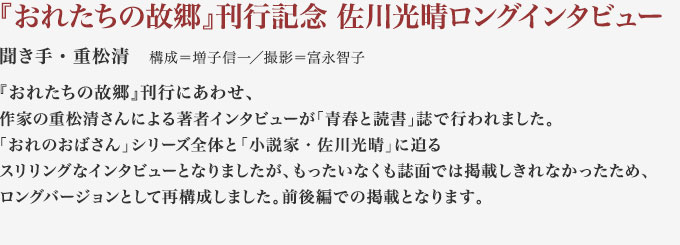
仲間がいる。信じられる大人がいる。
無限に広がっていく出会いと、世界がある。
老いも若きも、男の子も女の子も活躍する物語を書きたかった――
■父として、子どもたちに届けたかった物語
――「おれのおばさん」シリーズは、もちろんフィクションの物語ですが、拝読していると、物語の底には、北大の恵迪寮(けいてきりょう)での経験や『牛を屠(ほふ)る』で書かれていると畜場での経験といった、佐川さんご自身の半生が静かに響いているような気がしてなりません。「ライフワーク」を大江健三郎さん的に「人生の仕事」と言い換えるとすれば、このシリーズは佐川さんのまさしくライフワークとなっているのではないかと思うのです。それも、佐川さんの作家人生の「仕上げ」というのではなく、ともに育っていく主題としてのライフワークです。だからこそ、読者は新作を読むたびに「男子三日会わざれば刮目して見よ」の感覚でドキドキするのではないか、と思っています。
さて、『おれのおばさん』の雑誌連載が始まったのが二〇〇九年で、最新刊の『おれたちの故郷』で四冊目――シリーズの前編ともいえる『家族芝居』(二〇〇五年)も入れれば五冊目――ですが、『おれのおばさん』の連載が始まった時点で、このボリュームになっていくというお考えはあったんですか。
まったくなかったですね。『生活の設計』でデビューした後、芥川賞の候補になるような中編を文芸誌で発表するという形を何年かやって、それなりに力を出せたとは思うのですが、自分が書きたいものは少し違うのではないかという気持ちもあった。『縮んだ愛』や『銀色の翼』で描いた主人公より、おれ自身はもっと元気な人間だよなとか、北大の恵迪寮や出版社を辞めた後に働いていた大宮食肉(荷受株式会社、現・さいたま食肉市場株式会社)には逞しい仲間たちがいたなとか思い出すうちに、老いも若きも、男の子も女の子も活躍する物語を書いてみたいという気持ちが湧いてきたんです。
それから、当時、長男が十四歳で、それまで元気だったはずの息子の同級生たちが、どうも鹿爪らしい顔をしている。学校や親子関係で悩んでいる中学生たちが身近にいっぱいいたわけです。昔であれば、多くの文学や映画でも取り上げられてきた、〈ぼくのおじさん〉的な変わった親戚や先輩がいて、こんな生き方もある、あんな生き方もあるという手本を見せてくれたのだけど、いまはそういう異色の手本がほとんどない。ならば、悩める中学生たちに直接声はかけられないけれど、「君たち、こんな大人もいるぞ、こんな生き方をするのは、相当苦しいけど、できないこともないぞ」ということを、僭越ながら教えてやりたくなった。
――一作目から、この物語を誰に届けるのかというのは非常に明確だったということですね。
ええ。ブー垂れているうちの息子の友達たちに、おまえら読め、と。本なんて読みたくないだろうけど、おれは君たちの同級生のお父さんとして、こういう物語を届けたかったんだということですね。
――最初の『おれのおばさん』一作で書き切ったというよう気持ちだったのか、あるいはまだ続くんだなという手応えがあったのか。擱筆された時点ではどんなふうに思われてましたか?
優等生の高見陽介という少年を埼玉から北海道に飛ばして後藤恵子というおばさんのところに預ける、そこには魴鮄舎という場所がある――最初にそこまで考えてワッと書き出したのですが、おばさんが自分の妹である陽介のお母さんの頬をパーンと張った後に、「卓也、急いで降りておいで」と呼ぶ。ぼくの中でも、あそこで初めて卓也が出てきたんです。
――まさしく、卓也が佐川さんに「降りて」きたわけですね。
はい(笑)。そのときに、もしかするとこの小説は卓也と陽介が二人して一緒に歩いて行くようになるのかもしれないという予感がありました。陽介が一人でおばさんを吸収しながら成長していくのではなく、卓也とともに成長していくのだろうと。第一節の終わりのところで、卓也が「おれの親はさあ……」と言いかけて、口をつぐむ。そこで陽介が「卓也とおれがそうであるように、人と人はお互いの何もかもを知らなくてもつきあっていけるのだし、だからこそ、いつかすべてを知っても、それまでと変わりなくつきあいつづけられるのだ」と思うわけですが、あのことばを書いたとき、たまらなくうれしかったんですよ。陽介と卓也が作品の中で仲間になった。この小説は、とてもよいものになるだろうという手ごたえがありました。
――佐川さんは、プロットやノートを綿密につくってから書き出されるのですか?
つくらないです。
――書きながら動かしていくという感じですか。
そうですね。連載が始まって、真ん中辺りに、魴鮄舎の子どもたちが奄美に行くシーンがありますが、さてどうしようというのは、そこで考えました。陽介は、札幌で恵子おばさんという非常に強烈な人に会ったわけですが、おばさんのところにずうっといると、おばさんにつき過ぎてしまう。どこか離れたところからでもおばさんを感じられる場所にこの子たちが行くのがいいのではないか。さて、それならどこがいいかと思ったときに、奄美大島で牛飼いになっている大学時代の友人がいて、そこに行ったことを思い出した。よし、恵子おばさん抜きで、陽介たちを奄美まで行かせようと。そういうふうな形で進んでいきました。
■おじさんではなく「おばさん」である理由
――このシリーズ全編を通して、魴鮄ならぬHOBO(放浪者)、みんな移動していく。非常に移動距離の長い小説ですが、といってロード・ノベルという感じではない。常に札幌の魴鮄舎というホームタウンが起点としてある。今回の最新作では、その魴鮄舎こそが陽介や卓也の故郷であると規定されるわけですね。それぞれの登場人物はみなダイナミックに移動していくのだけれど、魴鮄舎という磁場はきちんと残っている。
「おれのおばさん」である後藤恵子から発せられる見えない磁力線みたいなものが届くんでしょうね。
――二作目からは卓也君の家出の話があったり、魴鮄舎から少し遠景に引いたり、迫ったり、また遠ざかったりというのを繰り返しますが、おばさんの存在感だけは北極星みたいに変わらずにある。これは、シリーズが始まったときからお伺いしたいと思っていたのですが、これがもし、「おばさん」ではなく、「おじさん」だったら、何が変わり、もしくは何が変わらなかったのか。おばさんである一番の大きな理由は何でしょう?
『おれのおばさん』の前編に当たる『家族芝居』は、伝統的な〈ぼくのおじさん〉に近いわけです。ここに出てくるのが、恵子の元のつれあい後藤善男です。大学受験を控えたアキラが変わり者である善男の生き方に影響されてゆくのですが、男同士であると、どうしてもなぞろうとしたり、過度に批判的になったり、父親の代わりにしたりもする。その点、異性である女性が壮大な頑張りを見せるとなると、父親とのつながりが投影される〈おじさん〉とはまた違う圧倒のされ方が出てくるんじゃないか。これは書いているうちにわかってきたことですが。
――物語の出発点で、陽介のお父さんが会社の金を横領して逮捕されてしまった。そこで父親が不在になるわけですが、その代わりに魅力的なおじさんがその場所に入ったら、実は父親の代わりが欲しかっただけになってしまう。でも、おばさんだから、父親の場所はずっとあいたままで、絶対に埋まらない。
そうですね。おじさんが父親の場所に収まると、結果的にはギリシャ悲劇から中上健次にまで至る、いわゆる〈父殺し〉の系譜につらなる物語になってしまう。おばさんにしたことで、それができなくなった。そのことが、とても効いているのだと思います。もう一つは、陽介の視点だけではなく、卓也の視点が介入することで、おばさんに対する見方にずれが生まれた。それがいい効果を生んでいるんじゃないかと。
――「おばさん」と平仮名で表記なさっていますが、漢字では「叔母」「伯母」とがあって、こういう場合、ありがちなのは母親の妹の叔母さんですね。お母さんより若くて、自由で魅力的な叔母さん。ところが、恵子さんは逆ですね。いきなり妹をひっぱたいたり、そこにはすでに父性がある。そこがこのおばさんの魅力で、こういう人に拮抗するには、陽介もそれまでの「ぼく」ではなくて「おれ」にならざるをえない。そして次には、卓也たちと一緒に「おれたち」になる。
これがここまでの大きな流れだと思って見ているんですけど、陽介がもし女の子だったらどうでしょうね。
ああ、それはぼくにはわからないところですね。
――魴鮄舎にもありさや奈津という女の子がいるけれど、まだ表立っての活躍の場面はないですね。
そうですね。ぼくは五人きょうだいで、ぼくが長男で末っ子が男で、あいだに妹が三人います。ぼくと妹たちとでは、母親を見る視点などは多分違うんだと思うのですが、正直、そこはよくわからない。おばさんの娘で花ちゃんという子がいるんですけど、まだ出てこない。花ちゃんがおばさんをどう見てるのか……。
――母親に対する一番の批評眼を持つのは娘ですからね。
『おれのおばさん』の最後の方に、魴鮄舎第一期生の野月(のづき)という男が出てきますが、彼はブログ上で魴鮄舎を誹謗したり、おばさんに対して皮肉な面を見せるわけですが、たとえば、あの役割を花ちゃんにするという手もある。みんなはおばさんについてこういってるけど、娘から見たらこうだというのを突きつける手はあるとは思ったのだけれど、でも、ちょっと違うかなという感じでした。
ぼく自身、恵迪寮で寮の執行委員長をやったり、大宮食肉に行って牛の仕事をしたり、いまはこうやって物書きになっていますが、ここに至るまで、いろいろな場所で、いろいろな人たちから肯定的・否定的な評価を受けてきました。へこんだり舞い上がったりということはそれぞれの場面であるわけですが、おばさんがこれまでにどういう傷を負ってきたのかは、陽介や卓也も部分的にしか知らない。大人がどのぐらいの傷を負ってるのかは、子どもは自分の親についても知らなかったりする。
無限に広がっていく出会いと、世界がある。
老いも若きも、男の子も女の子も活躍する物語を書きたかった――
■父として、子どもたちに届けたかった物語
――「おれのおばさん」シリーズは、もちろんフィクションの物語ですが、拝読していると、物語の底には、北大の恵迪寮(けいてきりょう)での経験や『牛を屠(ほふ)る』で書かれていると畜場での経験といった、佐川さんご自身の半生が静かに響いているような気がしてなりません。「ライフワーク」を大江健三郎さん的に「人生の仕事」と言い換えるとすれば、このシリーズは佐川さんのまさしくライフワークとなっているのではないかと思うのです。それも、佐川さんの作家人生の「仕上げ」というのではなく、ともに育っていく主題としてのライフワークです。だからこそ、読者は新作を読むたびに「男子三日会わざれば刮目して見よ」の感覚でドキドキするのではないか、と思っています。
さて、『おれのおばさん』の雑誌連載が始まったのが二〇〇九年で、最新刊の『おれたちの故郷』で四冊目――シリーズの前編ともいえる『家族芝居』(二〇〇五年)も入れれば五冊目――ですが、『おれのおばさん』の連載が始まった時点で、このボリュームになっていくというお考えはあったんですか。
まったくなかったですね。『生活の設計』でデビューした後、芥川賞の候補になるような中編を文芸誌で発表するという形を何年かやって、それなりに力を出せたとは思うのですが、自分が書きたいものは少し違うのではないかという気持ちもあった。『縮んだ愛』や『銀色の翼』で描いた主人公より、おれ自身はもっと元気な人間だよなとか、北大の恵迪寮や出版社を辞めた後に働いていた大宮食肉(荷受株式会社、現・さいたま食肉市場株式会社)には逞しい仲間たちがいたなとか思い出すうちに、老いも若きも、男の子も女の子も活躍する物語を書いてみたいという気持ちが湧いてきたんです。
それから、当時、長男が十四歳で、それまで元気だったはずの息子の同級生たちが、どうも鹿爪らしい顔をしている。学校や親子関係で悩んでいる中学生たちが身近にいっぱいいたわけです。昔であれば、多くの文学や映画でも取り上げられてきた、〈ぼくのおじさん〉的な変わった親戚や先輩がいて、こんな生き方もある、あんな生き方もあるという手本を見せてくれたのだけど、いまはそういう異色の手本がほとんどない。ならば、悩める中学生たちに直接声はかけられないけれど、「君たち、こんな大人もいるぞ、こんな生き方をするのは、相当苦しいけど、できないこともないぞ」ということを、僭越ながら教えてやりたくなった。
――一作目から、この物語を誰に届けるのかというのは非常に明確だったということですね。
ええ。ブー垂れているうちの息子の友達たちに、おまえら読め、と。本なんて読みたくないだろうけど、おれは君たちの同級生のお父さんとして、こういう物語を届けたかったんだということですね。
――最初の『おれのおばさん』一作で書き切ったというよう気持ちだったのか、あるいはまだ続くんだなという手応えがあったのか。擱筆された時点ではどんなふうに思われてましたか?
優等生の高見陽介という少年を埼玉から北海道に飛ばして後藤恵子というおばさんのところに預ける、そこには魴鮄舎という場所がある――最初にそこまで考えてワッと書き出したのですが、おばさんが自分の妹である陽介のお母さんの頬をパーンと張った後に、「卓也、急いで降りておいで」と呼ぶ。ぼくの中でも、あそこで初めて卓也が出てきたんです。
――まさしく、卓也が佐川さんに「降りて」きたわけですね。
はい(笑)。そのときに、もしかするとこの小説は卓也と陽介が二人して一緒に歩いて行くようになるのかもしれないという予感がありました。陽介が一人でおばさんを吸収しながら成長していくのではなく、卓也とともに成長していくのだろうと。第一節の終わりのところで、卓也が「おれの親はさあ……」と言いかけて、口をつぐむ。そこで陽介が「卓也とおれがそうであるように、人と人はお互いの何もかもを知らなくてもつきあっていけるのだし、だからこそ、いつかすべてを知っても、それまでと変わりなくつきあいつづけられるのだ」と思うわけですが、あのことばを書いたとき、たまらなくうれしかったんですよ。陽介と卓也が作品の中で仲間になった。この小説は、とてもよいものになるだろうという手ごたえがありました。
――佐川さんは、プロットやノートを綿密につくってから書き出されるのですか?
つくらないです。
――書きながら動かしていくという感じですか。
そうですね。連載が始まって、真ん中辺りに、魴鮄舎の子どもたちが奄美に行くシーンがありますが、さてどうしようというのは、そこで考えました。陽介は、札幌で恵子おばさんという非常に強烈な人に会ったわけですが、おばさんのところにずうっといると、おばさんにつき過ぎてしまう。どこか離れたところからでもおばさんを感じられる場所にこの子たちが行くのがいいのではないか。さて、それならどこがいいかと思ったときに、奄美大島で牛飼いになっている大学時代の友人がいて、そこに行ったことを思い出した。よし、恵子おばさん抜きで、陽介たちを奄美まで行かせようと。そういうふうな形で進んでいきました。
■おじさんではなく「おばさん」である理由
――このシリーズ全編を通して、魴鮄ならぬHOBO(放浪者)、みんな移動していく。非常に移動距離の長い小説ですが、といってロード・ノベルという感じではない。常に札幌の魴鮄舎というホームタウンが起点としてある。今回の最新作では、その魴鮄舎こそが陽介や卓也の故郷であると規定されるわけですね。それぞれの登場人物はみなダイナミックに移動していくのだけれど、魴鮄舎という磁場はきちんと残っている。
「おれのおばさん」である後藤恵子から発せられる見えない磁力線みたいなものが届くんでしょうね。
――二作目からは卓也君の家出の話があったり、魴鮄舎から少し遠景に引いたり、迫ったり、また遠ざかったりというのを繰り返しますが、おばさんの存在感だけは北極星みたいに変わらずにある。これは、シリーズが始まったときからお伺いしたいと思っていたのですが、これがもし、「おばさん」ではなく、「おじさん」だったら、何が変わり、もしくは何が変わらなかったのか。おばさんである一番の大きな理由は何でしょう?
『おれのおばさん』の前編に当たる『家族芝居』は、伝統的な〈ぼくのおじさん〉に近いわけです。ここに出てくるのが、恵子の元のつれあい後藤善男です。大学受験を控えたアキラが変わり者である善男の生き方に影響されてゆくのですが、男同士であると、どうしてもなぞろうとしたり、過度に批判的になったり、父親の代わりにしたりもする。その点、異性である女性が壮大な頑張りを見せるとなると、父親とのつながりが投影される〈おじさん〉とはまた違う圧倒のされ方が出てくるんじゃないか。これは書いているうちにわかってきたことですが。
――物語の出発点で、陽介のお父さんが会社の金を横領して逮捕されてしまった。そこで父親が不在になるわけですが、その代わりに魅力的なおじさんがその場所に入ったら、実は父親の代わりが欲しかっただけになってしまう。でも、おばさんだから、父親の場所はずっとあいたままで、絶対に埋まらない。
そうですね。おじさんが父親の場所に収まると、結果的にはギリシャ悲劇から中上健次にまで至る、いわゆる〈父殺し〉の系譜につらなる物語になってしまう。おばさんにしたことで、それができなくなった。そのことが、とても効いているのだと思います。もう一つは、陽介の視点だけではなく、卓也の視点が介入することで、おばさんに対する見方にずれが生まれた。それがいい効果を生んでいるんじゃないかと。
――「おばさん」と平仮名で表記なさっていますが、漢字では「叔母」「伯母」とがあって、こういう場合、ありがちなのは母親の妹の叔母さんですね。お母さんより若くて、自由で魅力的な叔母さん。ところが、恵子さんは逆ですね。いきなり妹をひっぱたいたり、そこにはすでに父性がある。そこがこのおばさんの魅力で、こういう人に拮抗するには、陽介もそれまでの「ぼく」ではなくて「おれ」にならざるをえない。そして次には、卓也たちと一緒に「おれたち」になる。
これがここまでの大きな流れだと思って見ているんですけど、陽介がもし女の子だったらどうでしょうね。
ああ、それはぼくにはわからないところですね。
――魴鮄舎にもありさや奈津という女の子がいるけれど、まだ表立っての活躍の場面はないですね。
そうですね。ぼくは五人きょうだいで、ぼくが長男で末っ子が男で、あいだに妹が三人います。ぼくと妹たちとでは、母親を見る視点などは多分違うんだと思うのですが、正直、そこはよくわからない。おばさんの娘で花ちゃんという子がいるんですけど、まだ出てこない。花ちゃんがおばさんをどう見てるのか……。
――母親に対する一番の批評眼を持つのは娘ですからね。
『おれのおばさん』の最後の方に、魴鮄舎第一期生の野月(のづき)という男が出てきますが、彼はブログ上で魴鮄舎を誹謗したり、おばさんに対して皮肉な面を見せるわけですが、たとえば、あの役割を花ちゃんにするという手もある。みんなはおばさんについてこういってるけど、娘から見たらこうだというのを突きつける手はあるとは思ったのだけれど、でも、ちょっと違うかなという感じでした。
ぼく自身、恵迪寮で寮の執行委員長をやったり、大宮食肉に行って牛の仕事をしたり、いまはこうやって物書きになっていますが、ここに至るまで、いろいろな場所で、いろいろな人たちから肯定的・否定的な評価を受けてきました。へこんだり舞い上がったりということはそれぞれの場面であるわけですが、おばさんがこれまでにどういう傷を負ってきたのかは、陽介や卓也も部分的にしか知らない。大人がどのぐらいの傷を負ってるのかは、子どもは自分の親についても知らなかったりする。


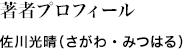
1965年2月8日生まれ。東京都出身、茅ヶ崎育ち。北海道大学法学部卒業。出版社勤務を経て、大宮の食肉処理場で働く。2000年「生活の設計」で第32回新潮新人賞を受賞。2002年『縮んだ愛』で第24回野間文芸新人賞受賞。『ジャムの空壜』『家族芝居』『虹を追いかける男』『静かな夜』『鉄童の旅』など著書多数。ノンフィクションに『牛を屠る』。2011年『おれのおばさん』で第26回坪田譲治文学賞受賞。
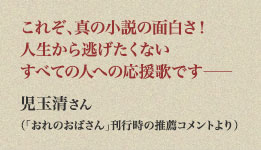
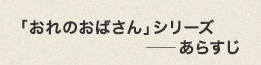




『おれたちの青空』
(集英社文庫/本体500円+税)
魴鮄舎(ほうぼうしゃ)に暮らす中学生たちも受験の季節。陽介とともに施設で暮らす同級生・卓也も受験を前に自らの出自に苦しんでいた。ある大雪の日、とうとう家出を敢行する…(「小石のように」)、「あたしのいい人」、表題作の全3篇を収録。
(解説・木皿泉)
(集英社文庫/本体500円+税)
魴鮄舎(ほうぼうしゃ)に暮らす中学生たちも受験の季節。陽介とともに施設で暮らす同級生・卓也も受験を前に自らの出自に苦しんでいた。ある大雪の日、とうとう家出を敢行する…(「小石のように」)、「あたしのいい人」、表題作の全3篇を収録。
(解説・木皿泉)



『おれたちの約束』
(単行本/本体1200円+税)
札幌を離れて仙台の高校の寮へ入った陽介。中国からの留学生、政治家の息子、芸大志望の変り種、など新しい仲間もできた。しかし、秋の学園祭の日に大地震が起きる。学校の再開まで仙台に留まり復興を担う決意をした陽介は、出所した父と再会を果たすが…。
(単行本/本体1200円+税)
札幌を離れて仙台の高校の寮へ入った陽介。中国からの留学生、政治家の息子、芸大志望の変り種、など新しい仲間もできた。しかし、秋の学園祭の日に大地震が起きる。学校の再開まで仙台に留まり復興を担う決意をした陽介は、出所した父と再会を果たすが…。

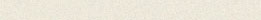

高見陽介
17歳。仙台の新興進学校・東北平成学園の特待生として寮暮し。中学2年のとき、銀行員だった父親が横領して逮捕。母の姉である恵子おばさんが切り盛りする札幌の児童養護施設・魴鮄舎に預けられた。
おばさん(後藤恵子)
魴鮄舎代表。親の反対を押切り福井から北海道大学医学部に入学するも、中退。ともに劇団を立ち上げた後藤善男との結婚・離婚を経て、児童養護施設の運営を始める。ひとり娘の花は東京で看護師として働く。陽介の母の姉。
柴田卓也
陽介の親友であり魴鮄舎での同級生。複雑な生い立ちを背負い小学6年生にあがる前に魴鮄舎に入り、陽介と出会う。現在は、青森大和高校バレー部で才能を開花させ、U-19の選抜選手としても活躍する。
17歳。仙台の新興進学校・東北平成学園の特待生として寮暮し。中学2年のとき、銀行員だった父親が横領して逮捕。母の姉である恵子おばさんが切り盛りする札幌の児童養護施設・魴鮄舎に預けられた。
おばさん(後藤恵子)
魴鮄舎代表。親の反対を押切り福井から北海道大学医学部に入学するも、中退。ともに劇団を立ち上げた後藤善男との結婚・離婚を経て、児童養護施設の運営を始める。ひとり娘の花は東京で看護師として働く。陽介の母の姉。
柴田卓也
陽介の親友であり魴鮄舎での同級生。複雑な生い立ちを背負い小学6年生にあがる前に魴鮄舎に入り、陽介と出会う。現在は、青森大和高校バレー部で才能を開花させ、U-19の選抜選手としても活躍する。
後藤善男
恵子おばさんの元夫。東京でグループホームを運営している。東京へ行った陽介が世話になったことがある。
陽介のお父さん
副支店長として単身赴任中、愛人のため横領、逮捕。離婚せず、ともに借金を負った妻に支えられ、出所後の現在は群馬の老人ホームで働く。
陽介のお母さん
夫の逮捕後、陽介を姉に預け借金返済のためがむしゃらに働く。魴鮄舎では「ほうおばさん(優しいほうのおばさん)」と親しまれている。
大竹徹
陽介、卓也の中学校時代の同級生。父親の失業で、仙台に引っ越した。卓也とは中2の冬、お互いが学校をさぼった日に偶然会い、ちょっとした旅をした。
波子さん
陽介が中二の夏休みに奄美大島で出会い、父への複雑な思いを打ち明けた相手。陽介とは、以来文通やメールで交流を続けている。東京在住の高校二年生。
中本/菅野/周
東北平成学園の陽介の同級生。中本は政治家志望、菅野は芸大志望の変わり種。周は、中国からの留学生。
ありさ/奈津
魴鮄舎での同級生。乗り鉄として恒例の夏休み合宿のときに大活躍。
野月
魴鮄舎の第一期生。
恵子おばさんの元夫。東京でグループホームを運営している。東京へ行った陽介が世話になったことがある。
陽介のお父さん
副支店長として単身赴任中、愛人のため横領、逮捕。離婚せず、ともに借金を負った妻に支えられ、出所後の現在は群馬の老人ホームで働く。
陽介のお母さん
夫の逮捕後、陽介を姉に預け借金返済のためがむしゃらに働く。魴鮄舎では「ほうおばさん(優しいほうのおばさん)」と親しまれている。
大竹徹
陽介、卓也の中学校時代の同級生。父親の失業で、仙台に引っ越した。卓也とは中2の冬、お互いが学校をさぼった日に偶然会い、ちょっとした旅をした。
波子さん
陽介が中二の夏休みに奄美大島で出会い、父への複雑な思いを打ち明けた相手。陽介とは、以来文通やメールで交流を続けている。東京在住の高校二年生。
中本/菅野/周
東北平成学園の陽介の同級生。中本は政治家志望、菅野は芸大志望の変わり種。周は、中国からの留学生。
ありさ/奈津
魴鮄舎での同級生。乗り鉄として恒例の夏休み合宿のときに大活躍。
野月
魴鮄舎の第一期生。