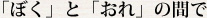
中江 文庫の解説で、それまで「ぼく」といっていた陽介君が、札幌に来てから「おれ」に一人称を変えるというのが、自分自身の「わたし」という呼称にも重なるところがある、と書きました。そして『おれたちの青空』になると、「おれ」がずいぶん様になってきたなと思っていたのですけど、今度の『約束』の冒頭にいきなり、「おれは、まだ『おれ』なのか? それとも、いつの間にか『ぼく』にもどってしまったのだろうか?」と出てきますね。あれ? 陽介君はまだ迷いがあるんだと、ちょっとびっくりしたんですけど、同時に、迷うのも当然だなとも思いました。
佐川 順風満帆の「ぼく」の時代から、突然疾風怒濤のような魴ぼう舎での暮らしに投げ込まれる。そこにもどうにかこうにか適応して、中学校を卒業することになったときに、このまま札幌でおばさんの傍にいるか、それともどこか別の土地に移るのか、陽介は相当悩んだはずです。彼がどうするのか、実はぼくも楽しみにしていたんです。
中江 佐川さんご自身も、わからなかったんですか。
佐川 書くまではわからなかった(笑)。ぼく自身、北海道大学の恵迪(けいてき)寮という寮で集団生活をして、そこで人との関わり合い方を大分もまれたわけですけれど、寮を出てからどうするかというときに、やはり陽介と同じように迷い、結局、北海道を出ました。ぼくと陽介は別人格ですが、書いているうちに、この子も出るだろうなということがおおよそわかってきた。敢えておばさんの許を離れ、もう一度新しい人間関係の中に入っていくと決めたのだけど、やっぱりおっかなびっくりですよね。
中江 初めての場所で、しかも、この東北平成学園にいる人たちは、誰もお父さんの事件のことは知らない。陽介君がお父さんのことを知られたくないと思うのは当然ですよね。
たとえば中学や高校へ進学して学校が変わるときに、今までの暗い自分じゃなくて明るくなろうといってキャラを変える人が結構いますよね。陽介君も、仙台へ行くと決めたとき、「おれ」からもう一度「ぼく」に戻ろうという、揺れがあったのかもしれない。
佐川 ぼく自身、何度も揺れました。大学を一年間休学して南米へ行ったり、牛の仕事(食肉処理場での作業)をしたりしたのですが、牛の仕事をしている最中でも、いつまでこの仕事を続けていけるのか、今ならまだ、新聞社に入り直したりすることもできるんじゃないか ……と。
陽介にも、そういう揺れをつくってやりたかったんです。たとえそこで彼がまた優等生を目指したとしても、元の優等生には戻れない。おばさんや卓也たちに鍛えられた陽介は、勉強のできる優等生として世間にすり寄っていこうとする自分と、そうではない自分とがせめぎ合っていかざるを得ないんです。
中江 そして、その陽介君を文字通り大きく揺るがすのが大地震ですね。ここに書かれている大地震は、東日本大震災そのものではないけれども、当然重ね合わせられているわけですよね。
佐川 陽介が仙台に行くことになったところで、物語の中で地震を扱おうということは頭にありました。ただそのときに、地震に立ち向かうために陽介の人格をつくるような形にはしたくなかったんです。陽介だけでなく、同級生の中本も菅野も、みんないろいろなものを抱えながら高校生活を送っていて、そうした日常の中で地震に遭う。まず地震ありき、ということから逆算してこの子たちの人格をつくっていったわけではありません。
 中江 地震は物語の中核ではなく、中心にあるのはあくまでも彼らの生活であると?
中江 地震は物語の中核ではなく、中心にあるのはあくまでも彼らの生活であると?
佐川 たしかに、陽介や中本たちにとって、大地震は大きな出来事であり、そこで強いストレスを受けるわけですが、それによって決定的に彼らの人生が変えられてしまうというのとは違うということです。地震の前と後とで運命が決定的に分かれるような話にしてはいけないぞ、というのがあった。むしろ、地震という出来事を通して、彼らの人間関係がいろんなふうに新しい局面を見せていく、そこを書きたかったんです。
中江 地震が起きたことで、陽介君は少し気まずかった波子さんとの関係が修復できたし、音信不通だったお父さんと連絡がとれたとか、それまで滞っていた関係が一気に動いていくじゃないですか。それまでのややこしいことをすっ飛ばして、自分のことをほんとうに大事に思ってくれている人がいる。わたし自身、あの大震災のときにそれを再確認しました。
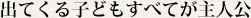
佐川 地震だけじゃなくて、何か大きなものに当たったときに、その人の生地みたいなものが試されるときがありますよね。陽介は平成学園に入ってから、また「ぼく」に戻ることもやぶさかではないみたいな感じだったのが、生徒会選挙のときにもう一回「おれ」に引き戻される。友人の中本が生徒会選挙で会長に立候補するのだけれど、そこで元国会議員の父親のことで悪いうわさが生徒たちの間に広まり、中本は苦境に立たされてしまう。そのとき陽介は、自分の父親が横領罪で逮捕されて、今も服役中であることを告白して、その場の雰囲気を一変させる。
中江 わたし、あの場面にほんとに感動しました。読んでいたのがたまたま病院の待合室だったんですけど、読んでいるうちに泣けてきて、周りの人に、重病を宣告されたか何かで泣いていると思われているのだろうと感じつつも、涙が止まりませんでした(笑)。
佐川 これまでの陽介は、実はあまり自分から積極的な行動はしていないんです。
中江 たしかに、そうですね。
佐川 つらい境遇に耐えてはいるのですが、自ら逆境に抗して頑張るのは卓也のほうで、陽介が自分からアクションを起こして働きかけていくというのはほとんどなかった。その陽介が、ようやく自分から、「おれはこういう人間なんだ」ということを、外に対してはっきりいう。ここに来るまでずいぶん長くかかりましたが、よくぞいった、偉いぞ、と。
 中江 わたしも、親戚の男の子に久々に会った感じで、大きくなったね、と(笑)。
中江 わたしも、親戚の男の子に久々に会った感じで、大きくなったね、と(笑)。
たくましくもあり、でも、まだ頼りない部分もあって、そういう部分も含めて、成長の途上にあるんだなと妙に感じ入っています。フィクションだとわかっていても、ついつい感情移入してしまいますよね。
佐川 大人になってもそうですが、年齢相応にしっかりしているように見えて、小学校のときと変わらないような精神状態でごじょごじょしているときがあるじゃないですか。
中江 あります。胸が痛いというか、耳が痛いというか(笑)。
佐川 そういうときにはやはり、ある支えが必要なんですよね。陽介も中本も、そのときどきでどちらかが柱となってお互い助けるようにしながら、伸びていく。中本のような世の中に対して背筋を伸ばしている人間が傍にいることが陽介の糧になることもあれば、生徒会選挙では逆に陽介が中本の支えになることもある。ただ一人の人間がヒーローになるのではなく、その場その場である人間が頑張り、そのことによって周りの人間も負けずに頑張っていく。今度の『おれたちの約束』では、いい意味での影響の与え合いを、納得がいく形で書けたように思います。
中江 タイトルが物語っているように、『おれのおばさん』のときは「おれ」が主人公でしたけど、二作目以降「おれたち」になってからは、陽介君だけじゃなく、出てくる子どもたちすべてが主人公のような気がしますね。
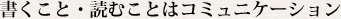
中江 わたしは十歳のときに親が離婚して、母と妹と三人で暮らし始めたんです。それこそ離婚という言葉があるのをそのとき初めて知りました。結婚したらそれでおしまいで、その先はもうないと思っていたのに、離婚というものがあることを知った。それが自分の親の身に起こっていることもわからなかったので、大きな衝撃でした。ですから、最初、『おれのおばさん』を読んだときも、自分のことを思い出しながら、陽介君のしっかりした姿に泣けてしようがなかったんです。
佐川 寂しいのに、一所懸命無理してね。
中江 自分の置かれた状況に負けるわけにいかない。それに負けちゃったら、誰のせいだといえるかもしれないけれど、結局、自分に全部はね返ってくるのは悔しい、そういう部分があるんです。ですから、わたしとは状況は違うけれど、陽介君にかかっている負荷は、昔、わたし自身にもかかっていたものだなと思いました。そういうときって、普通、その年頃では考えないようなことを深く考えさせられるんですよね。
佐川 『おれのおばさん』を読んだ方から、中学生でこんな難しいことは考えないといわれることがありますが、ぼく自身、十歳のときに父親がうつ病になって家庭がややこしくなりましたから、そのときにずいぶん考えました。
中江 考えますよね。これから、うちの生活はどうなるのか、このまま学校に行けるのかとか、子ども心に考えざるを得ない。それに、親が働きに出ているので、家庭のことはある程度自分でやらなきゃいけないわけですね。掃除したり、お米研いだり、朝起きたら妹を起こしてご飯食べさせて、髪を結んで、ランドセル背負わせて、学校に行かせたり。何でわたしばかりこんなことしなきゃいけないんだと思っていました。
佐川 そのとき、中江さんの支えになったものは何だったんですか。
中江 その頃の救いは、書くことでしたね。物語を書くことで、現実から想像の世界に逃げていたのと同時に、書くことで自分の考えをまとめていたのだと思います。当時は、架空の物語を書いては、それを自分で読むのを楽しみにしていたんです。だから、すごく暗い子だと思われていました(笑)。
十五歳で東京に出て芸能界で仕事をするようになってからは読書が支えになりました。芸能界という世界は、どこか外界と遮断されてしまうところがあって、学校も休みがちになるし、仕事先に行けば大人の人ばかりで、自分というものがどこにあるんだろうとほんとうに悩み、そういうときは、本を読んでずいぶん救われました。読書に救われたというよりも、それで世間からの風を防いでいたというか、そうしないと自分が吹き飛ばされそうな気がしたんです。今、自分がこうあるのは、物語の中に置かれた環境なんだ、どこかでそういうふうに思いながら生きていた感じがありましたね。
佐川 本を読むことでその世界にひとりで没頭できたわけですね。陽介も、魴ぼう舎に来る前は、ひとりで勉強に没頭する環境があったのですが、おばさんも卓也も、中本も菅野も、決して陽介をひとりにさせない。ひとりの世界には逃がさんぞといって、やたらにちょっかいを出してくる。もちろん、おばさんにも卓也たちにもそれぞれ固有の世界はあるのだけれど、それは物理的に確保されたひとりのスペースではなくて、ちょっかいの出し合いの中でつくられてきた個性なんですね。
それはまさに、ぼく自身が育ってきた恵迪寮や『牛を屠(ほふ)る』で描いた世界と同じです。個室ではなく、いつでも人のいるところにいさせられる。最初はストレスなんですが、だんだんとそこでのふるまい方を覚えていく。
中江 わたしも自分の中にこもってしまうときが今でもありますけれども、大体、読んでいるか書いているかのどちらかです。それは、人間同士ではないけれども、やはり一つのコミュニケーションだと思っています。書くことで自分が思っていることがはっきりとわかってくるし、読むことで、物語の登場人物やストーリーによって自分の「今」が映し出される。わたしが今、この本を読んでいるのは偶然なのだけれど、まるで自分のために書かれた話だと思えてしまう。おそろしいぐらい、そう思えることがよくある。この〈おれのおばさん〉シリーズにも、そういう運命的な出会いを感じました。
わたしはそうやって、本を通じて自分の居場所を見つけてきたのだと思います。
佐川 おかげさまで、このシリーズはとても多くの人に読んでいただいているようなのですが、どちらかというと、自己確立とか自己発見とか、閉じこもった「個」の世界が強調される時代にあって、多くの人間たちが一つ所にいて、お互いが強い影響を与え合う、こうした物語が読まれていることは嬉しいですね。
中江 これから陽介君や卓也君がどんな影響を与え合って成長していくのか、楽しみです。
さがわ・みつはる
作家。1965年東京都生まれ。
2000年、「生活の設計」で新潮新人賞を受賞して作家デビュー。
著書に『縮んだ愛』(野間文芸新人賞)『家族芝居』『銀色の翼』『牛を屠る』『おれのおばさん』(坪田譲治文学賞)『山あり愛あり』等。
なかえ・ゆり
女優・作家。1973年大阪府生まれ。
89年、芸能界デビュー。2004年から12年までNHK‐BSプレミアム「週刊ブックレビュー」の司会を務める。
「納豆ウドン」でBKラジオドラマ脚本懸賞最高賞受賞。著書に『結婚写真』『ティンホイッスル』。




