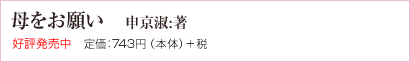![]()
 ──申さんが初めて日本に来られたのは、一九九五年一一月、島根県松江市で開催された日韓シンポジウムのときですね。その年の一月には阪神・淡路大震災が起こり、今年はまた東日本大震災が起こっています。
──申さんが初めて日本に来られたのは、一九九五年一一月、島根県松江市で開催された日韓シンポジウムのときですね。その年の一月には阪神・淡路大震災が起こり、今年はまた東日本大震災が起こっています。
韓国ではほとんど地震がありません。私自身、これまでに一、二回しか経験していなくて、多分、震度2とか3とかだと思いますが、それでもみんな大騒ぎしましたから、震度7などという大地震は、正直想像がつきません。 私はあのときはニューヨークにいて、テレビのニュースを見ていました。見ているだけでつらいのですが、自分には何もできないというもどかしさを感じました。ああいう自然の大きな力の前では人間は実に無力であると、謙虚にならざるを得ません。
──『母をお願い』は、四章+エピローグという構成ですが、各章で長女、長男、夫、次女と視点が推移し、地の文の主語も、それぞれ「あなた」「彼」「あんた」と変化し、そして四章の途中からはオンマ=母のひとり語りが挿入されるという、非常に複雑な構成になっています。今回、こうした構成をとられた意図というのは?
こういう人称の形式で小説を書いたのは初めてです。なぜこういうふうな構成にしたのかというと、この作品のテーマである〈母=オンマ〉という存在を理解するためには、娘の視点だけではとらえることができないし、夫や長男の視点だけでもとらえられない。オンマと関わる家族の人たちが、それぞれ自分とオンマとの思い出を語っていくことで、全体的なオンマの像、イメージが出来上がってくるのではないかと思ったからです。
それから、四章でオンマが自分について語るところがありますね。これは、ほかのだれでもなく、オンマだけに「あたし」という一人称を使おうという気持ちが強くあってのことです。ひとりの女性が生まれてから成長していくわけですが、母親になると〈私〉として自分のことについて語るチャンスがなかなかないんですね。なぜなら、母親というのは、自分と関わっている周りの人たちみんなに〈私〉を分け与えてしまうからです。そうだからこそ、オンマには「あたし」として自分のことを語らせてあげたかったのです。
 もうひとつ、この小説は、「母さん(オンマ)の行方がわからなくなって一週間目だ」という文章から始まります。つまり、オンマが失踪しているという前提なのですが、その失踪してしまったオンマが急に「あたしは……」と語り出すと、読んでいる人は、一体だれがいなくなっているのかと、戸惑ってしまう。そうした混乱状況をあえて作り出すことによって、自分たちがなくしているものは何なのか、もしかすると、大事なものを失っていることすら忘れてしまっているのではないのか……そうした意味合いを喚起させたいということもありました。
もうひとつ、この小説は、「母さん(オンマ)の行方がわからなくなって一週間目だ」という文章から始まります。つまり、オンマが失踪しているという前提なのですが、その失踪してしまったオンマが急に「あたしは……」と語り出すと、読んでいる人は、一体だれがいなくなっているのかと、戸惑ってしまう。そうした混乱状況をあえて作り出すことによって、自分たちがなくしているものは何なのか、もしかすると、大事なものを失っていることすら忘れてしまっているのではないのか……そうした意味合いを喚起させたいということもありました。
![]()
──最後のエピローグは、単行本のときに書き足されたそうですね。
連載のときは、四章で終わっていました。この作品で一番書きたかったのは、第四章の最後のシーン──死に行くオンマが自分の母親の膝の上で抱きかかえられながら、自分にも母親が必要だったということを、この母は知っているのだろうかと問いかける、あのシーンでした。それを連載の最後に書いて、これが書けたのだから終わりにしようと、終わらせました。ところが単行本にするとき、このまま話が終わってしまうと、あまりに希望がないのではないかと思ったんですね。そこで、オンマを甦らせるべく、「 母さん(オンマ)の行方がわからなくなって九ヵ月目だ」で始まるエピローグを付け加えて、この物語は終わりではなく、まだ進行中だということにしました。残された人たちが今後どうするかは、それぞれの課題であり、もしかするとオンマを探し出せるかも知れないという希望の余地を残しておきたかったのです。
 ──四章のあの場面は、聖母マリアが十字架から降ろされた我が子イエスを抱く、ミケランジェロのピエタ像を彷彿とさせます。そしてエピローグで、そのピエタ像が登場する。あのイメージは最初からあったのでしょうか。
──四章のあの場面は、聖母マリアが十字架から降ろされた我が子イエスを抱く、ミケランジェロのピエタ像を彷彿とさせます。そしてエピローグで、そのピエタ像が登場する。あのイメージは最初からあったのでしょうか。
実は連載が終わるまではピエタ像のイメージはまったくありませんでした。ただ、連載が終わって単行本の作業にかかる前に、たまたま一ヵ月ほどイタリアに行く機会があって、そのとき初めて、バチカンで実際のピエタ像を見たんです。聖堂に入ると、自分を呼び寄せる不思議な引力みたいなものを感じて、導かれるままに進んでいくと、そこにピエタ像がありました。それを見た瞬間、凍りつくような激しい感情が湧き上がりました。これは一体何だろう? と。小さいときから教科書などでよく目にしていた写真と実物とでは全然違っていました。
書いているときにはピエタ像のことは頭になかったのですが、考えてみると、四章の最後だけではなく、長女が納屋で倒れていたオンマを膝に抱きかかえる姿とか、たしか三回くらいそういう場面が出てきていたことに、後になって気がつきました。そこで、旅行から戻ってきてエピローグを書くときにピエタ像の話を入れることにしたんです。イタリアへ行ったのはまったくの偶然でしたが、結果的には、まるでこの作品を完成させるために行ったような形になりました。
こうした経験をすると、私の作品だけではなく、音楽なり美術なり、いろいろな芸術作品が世界中に散らばっていて、ある瞬間、異なったジャンルの作品同士がお互いを引き寄せる、そういう引力みたいなものが、この世界にはあるのではないかという気がします。
──エピローグで、長女が「オンマがいないのに春がやって来るなんて」という一節が出てきます。日本では大震災後、ポーランドのノーベル賞詩人、ヴィスワヴァ・シンボルスカの詩集『終わりと始まり』がずいぶんと話題になっています。その中の「眺めとの別れ」という、長年連れ添って夫が亡くなったときに書かれたであろう詩に、「またやって来たからといって/春を恨んだりはしない/例年のように自分の義務を/果しているからといって/春を責めたりはしない」という一節があります。大震災、そして原発事故で深い喪失感にとらわれた日本人の心に深く響く言葉ですが、お話をうかがいながら、このエピローグの言葉も、シンボルスカの詩と引き合っているのではないかと思いました。
大切なものを失ったにもかかわらず、いつも通り季節はめぐってきて、花が咲き誇っている。そんな春を恨む気持ちも、よくわかる気がします。それでも、変わらずに春が訪れて、決まっていることがきちんと循環していることにホッとするところもある。人間の営みというのは、そうした大きな自然の流れにあるのだということを改めて感じますね。
![]()
──『母をお願い』は、韓国本国だけではなく多くの国で反響を呼び、特にアメリカでは非常に好調な売れ行きだとうかがいました。
この作品は母の話ではありますが、私がここで書こうとしたのは、親しみがあって、温かくて、必要なときに手を差しのべてくれる存在、あるいは命を生み出し、それを見守って育て、次の世界に送り出す存在、そういうものの象徴としての母のイメージです。こうしたイメージは、文化や民族を超え、共通して人びと心の底に潜んでいるものであり、それに対する共感があったのではないかと思います。
──そういう意味では、普遍的な作品といえますが、それと同時に、実際の申さんのお母さまのイメージも色濃く映し出されていますね。申さんの自伝的な作品『離れ部屋』(集英社刊)の中に、「(オンマの黒い瞳は)牛のそれに似ている」という表現が出てきますが、今度の作品にも「牛の目」がキーワードのように頻出します。このオンマには実際のお母さまと重なり合うところがあるのではないですか。
 自分が田舎育ちだったからでしょうか、子供の頃に見た牛の目がとても印象に残っているんです。牛の目をじっと見ていると、真っ直ぐで、正直で、それでいて底知れない何かを含んでいるように思えてくる。自分の中のそういうイメージは、他の人にはなかなかうまく伝わらないかも知れません。でも、私にとって「牛のような目」と譬えられるのは、母の目だけなのです。
自分が田舎育ちだったからでしょうか、子供の頃に見た牛の目がとても印象に残っているんです。牛の目をじっと見ていると、真っ直ぐで、正直で、それでいて底知れない何かを含んでいるように思えてくる。自分の中のそういうイメージは、他の人にはなかなかうまく伝わらないかも知れません。でも、私にとって「牛のような目」と譬えられるのは、母の目だけなのです。
子供の頃には、鳥の目とかもよく見ましたが、鳥の目はなんとなく冷たかったり鋭かったりするし、可愛いワンちゃんの目は、いたずらっぽく親しみやすいけれど、牛のような哀しみも含めた深さが感じられない。子供の頃からそうやって目ばかり見ていたせいか、私は人と会うと、つい目を見てしまうんです。この人の目は何の目に似ているのか、って(笑)。
──韓国の雑誌が、『母をお願い』のモデルである申さんのお母さまに会うべく取材を敢行して、その記事がネットに出ていますね。
「私もそのネットの記事をアメリカで見たのですけど、本当にびっくりしました。ネットには、両親がふだん生活している部屋の写真まで載っていました。私の実家は田舎の貧しい家で、両親は六人の子供に教育を受けさせるために一生を捧げたような人です。韓国では、大学を卒業するときに、アメリカと同じように四角い帽子を被るのですが、その部屋には、六人のきょうだいそれぞれが四角い帽子を被っている昔の写真が壁に掛けられていて、それもネットに載っている。そんなプライベートな場所までが公になってしまったことには、戸惑いを超えてかなり不愉快な思いをしました。
 ──アポ無し取材だったようですね。
──アポ無し取材だったようですね。
連絡したら断られるますから(笑)。韓国では、特に田舎ではそうなのですが、よそから来た人は親切にもてなすんですね。突然のお客さんでも、それがちょうど食事時であれば、家の中に招いて一緒に食事をしたりする。ですから、いきなり訪ねてきても、遠いところからわざわ来たとわかれば、母としては家に入れないわけにはいかなかったのでしょうね。その後に電話して、そういう人たちをむやみに家に入れないように注意したのでが、プライバシーなんて考えのない母は、「何で?」っていってました(笑)。
──ここに出てくるオンマたちの世代というのは、自分たちが貧しく苦労しながら子供たちを育てわけですが、子供たちの世代になると割合に豊かな時代になって、それまでの貧しかった生活や両親のことを疎んずるようになる。こうした構図は韓国のみならず、多くの国でも共通しているように思います。
この作品は、さまざまな読み方が可能だと思います。伝統と現代のギャップを埋める作品として読まれたり、あるいは世代間の関係を回復するための小説として読まれることもありますが、共通しているのは、現在、母親たちの時代よりも物質的には豊かになったけれど、その一方で大事なものを失ってしまったのではないか、その失ったものとは一体何なのか、という問いです。
小説の中の家族は、オンマを失うまで、オンマの存在を忘れていたところがある。実際にオンマがいなくなってはじめて深い喪失感を味わうわけです。そしてオンマを求めて彷徨っている家族たちの姿を通して、本当に私たちが取り戻すべきものは何か、本当に大切にしていくものは何かということの重要さに気づいてくれるのではないかと思っています。
エピローグに、次女がお姉さんに宛てた手紙が出てきます。あれはお姉さん宛になってはいますが、実はオンマ宛に書きたかった手紙なんですね。この作品が、若い世代が自分の母親の世代に送る手紙のように読んでもらえたら、うれしいですね。(了)
撮影/chihiro.