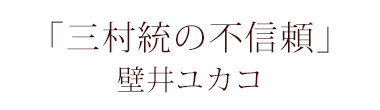『空への助走 福蜂工業高校運動部』書き下ろしショートストーリー
「三村統の不信頼」壁井ユカコ
「統、遅ぇー」
「でけぇ奴がショーケースん前でうんこ座りしてがっつり悩むなや。他の客迷惑してたぞ」
五月某日、福井駅近のドーナツショップにて。三村が最後に会計を終えてテーブルに合流すると、先に座って談笑していたバレー部の仲間たちが三村が置いたトレーに目をとめるなり「多っ!?」と揃って二度見した。
「一、二、三……六個って、よう食えんな」
「最初五個に決めたんやって。ほやけどしょっぱいのも一個欲しなってー、ほやけどしょっぱいのは百円セールの対象外やろー? ほやでかわりに甘いの一個足した」
「そこで甘いの足す理論がわからん。五個でも多いわ」
「甘いのもこれでも厳選に厳選したんやぞ。だって今だけ百円なんやぞ? 定番は押さえるとして、定番になに足すかがセンスの問われるとこやでここで個性を……」
「春夏のファッションみたいに言ってるけど、ドーナツやぞ」
椅子を引き、テーブルを囲む輪に加わる。部活あがりの汗がまだ引ききらない中、クーラーの風が一番あたるテーブルに陣取るのはいつものことだ。メラミン化粧板のテーブルの上に六人分のトレーが所狭しと並べられ、テーブルの下にも部活用のエナメルバッグと、バレー部員にとっては小ぶりな椅子からもてあまされた脚が押し込まれている。
越智一人がドーナツのかわりにブラックコーヒーをすすりつつ、眉間に皺を寄せてえらく長そうなメールを打っていた。
三村が視線を送っていると、疲労感が漂う溜め息を一つついて越智が携帯電話から目をあげた。
「なんか問題?」
と一応三村は訊く。話すようなことじゃなければそれでいいし、話してなにか糸口になるならなんでも言えよ、という温度で。
「いや……」と越智が口を濁し、三村の前にあるトレーにやっと気づいて「多いな、おい」と頰を引きつらせた。
今日は帰り道で自然と学年ごとにばらけたので三年だけで店に入った(より正確には普段は大人数すぎて入るのを諦めるドーナツ屋にこの人数だから寄れた)。主将の三村やマネージャーの越智を初めとして同期は六人。一年のときからどっぷりつきあっているので全員気心が知れた間柄だ。
この顔ぶれなら話しても問題ないと思ったのか、越智が切りだした。
「岡から相談されててな……部活やめたい、って言いだしてて」
にわかに全員が深刻ぶって身を乗りだしたりは――しない。夕飯前の空きっ腹に各々ドーナツを収めながら何気ない態度のまま越智の話に耳を傾ける。
「まあ一年の五月って、しんどなる奴いる時期やしな。去年の今頃は工兵ですら弱音吐いてたし。インハイ行って帰ってくる頃には一年もだいぶ肝据わるもんやけど」
越智も深刻になりすぎない口調で言い、テーブルの上に携帯を伏せた。
「統。ひとまずおれが預かっていいけ。必要あったらおまえにフォロー頼むで」
「ああ……。そのへんはもちろん、任すわ」
別に入れなくてもいい断りを律儀に入れてくるので三村は頷いたが、釈然としない顔が表にでたのか、
「ヘコんでんやろ、統」
と朝松がからかう調子で言ってきた。中学が一緒の朝松とはこの中でも一番つきあいが長い。
「だって、なあー」誰かしらのフォローを求めて三村は仲間の顔を見まわした。「今年の主将、もしかして人望ないんか? つまりおれですけどー」
福蜂のバレー部では一月頭の春高が終わるまで三年が現役だ。春高の終了――つまり敗退と同時に三年から二年へと部の中心が引き継がれたので、三村が主将のバトンを受け取って四ヶ月になる。四ヶ月たってもまだ主将として後輩の信頼を得られていなかったのかと、自分でも思いのほかじわじわヘコんできた。
「いや、だってやぞ、やめるやめないとかいうことまで考えてるんやったらおれに直接相談すりゃいいのに……越智のほうが信頼されてるってこと?」
「っちゅうか越智のほうが言いやすいんやろ」
「まあな、ここで言わんような相談もあっちこっちからけっこうされてるしな」
と当の越智が頷き、それにまた三村は若干ショックを受ける。そんな話初めて聞く。
「一、二年にとっては越智はいい上司やろ。弱音吐いても同じ目線で共感して、親身になって話聞いてくれそうやもんな」
「おーいちょっと待て。まるでおれが親身にならんみたいな……」
「ほういうわけやないけど、なんちゅうか、なあ」
朝松たちが言葉を探しあぐねて顔を見あわせる中、
「統に弱音は言いづらい」
ばっさり切って捨てたのは高杉だった。「えーっ……。なんで? おれ別に怒ったりせんぞ?」不満げに三村は高杉を見やる。
「おまえと一緒にいる場所では、みんなかっこつけたいんや。一番かっけぇ自分として三村統のチームに属したい。おまえが自分でほーいう空気作ってもてるでな」
鋭い評に、つい三村はリアクションを失って絶句した。
「それが悪いとは言ってえん。弱音吐ける場所もいるけど、それ以上におれらには、いいかっこする場所かって必要やろ」
「ほやほや、それな。わかる」
芯を食ったという顔で朝松たちが賛同を示した。満場一致で結論づけられて今度は越智が「なんかほれやとおれが微妙な気んなるな。おれはかっこようなくていいほうけや」と不満げに口を尖らせる。言った高杉は話題から一抜けしてテーブルから身を離し、突然熱い台詞を吐いて恥ずかしくなったのか、わざとクールぶって脚なんか組んでアイスティーに口をつけた。
*
小腹を満たすつもりで立ち寄ったのだが、入店したのがすでに夜八時だったので店をでたのは客足も引いた九時近くだった。「遅なってもたな」自転車の籠に各自バッグを押し込み、スタンドを次々に蹴りあげる音が暗い駐輪場を騒がせる。これから帰って夕飯を食べて風呂に入って、身体の回復と成長を促すためだけに夢も見ないで睡眠を貪って、起きたら朝練でまた同じ顔が揃う。気分的にはほぼ二十四時間部活の仲間と一緒にいるようなものだ。
駐輪場から自転車をだすと、越智が自分の自転車を押して横に並んできた。
「統。岡のことやけど……」
思い煩っていることがあるようで、握ったハンドルに目を落としてやや歯切れ悪く言いだした。三村は軽く眉をあげただけで続きを促す。
「さっきはみんなああ言ってくれたけど……なんかおれ、岡の弱音聞いてやってるっていうより、岡がやめる理由固めしてやってる気んなってきてな……。今しんどい思いしてる奴に無責任に頑張れとも言えんくて、頷いてやってるだけんなってもて」
越智らしいと、少々呆れ気味に三村は思う。相手の痛みや苦しみに真面目に寄り添おうとする奴。共感しやすくて、一緒に悩んで、よくも悪くも一緒に落ちていってしまう奴。
いい相談相手ではあるんだろう。ただ、とおりいっぺんの励ましをかけるしかないときだってある。結局は本人が周囲の言葉を推進力に変えられるかどうかだ。
「おれが一年の夏にしんどかったとき、おれの前にいたんがおまえやったで、おれはやめんかったんやと思う。もしおれみたいな奴が同じ目線で話聞いてくれて、共感とか同情とかしてくれたら、おれはそんで気ぃ済んで、逆にやめてたかもしれん……って、今考えると思う」
「おまえんとこでなんとかしようとせんでも、おれんとこ持ってきていいんやぞ」
助け船をだすつもりで三村は言った。小学校時代のバレーチームから数えればこんなことは腐るほど経験してきた。たぶん自分のほうがこういうことに関しては割り切っている。
越智が目をあげた。一度逡巡するように唇が真一文字に結ばれた。
「……なあ統。もし今やったら、おまえ、一年んときと同じこと言えるか?」
一年の夏のインターハイ前、越智は膝の怪我を機に、監督にプレーヤーからマネージャーへの転向を持ちかけられ、退部を考えるまで思い詰めていた。三村くんにはわからんなどと僻みをぶつけられて目の前で泣かれたのには正直言って辟易したが、その越智に、マネージャーになってみろと言ったのは他ならぬ三村だ。
――おまえの三年間、おれに預けろ。おれがおまえを春高のセンターコートのマネージャーにしてやる――
自分がチームみんなを背負えると、二年前は今より本気で思っていた。あれから福蜂で二度のインターハイと二度の春高、県で一つの選抜チームが組まれる国体も入れれば、二年間で六度の全国大会を経験した。”望みの場所”への道のりの遠さをそのたびに思い知らされるばかりだった。
もしも今、二年前の越智と会ったら同じことを言えるだろうか?――二年前ほどには自分で自分の言葉を信じられなくなっているとしても。二年前よりも自分が背負えるものの限界をうすうす感じてはいても。……あとに引けなくなっているだけだとしても。
「言えるさ。今でも」
気障っぽく言ってみせた。
ハンドルに肘を預け、前屈みに自転車を押しながら、隣の越智の顔を覗き込む。
「おまえの残り一年、おれに預けろ」
別にまだ心を折られたわけではない。今年が三年間の集大成だ。
苦虫を嚙み潰したような顔で越智がぷいと横を向いた。
「一番のいいかっこしいがおまえなんやで、世話ねぇわ」
匙を投げたような溜め息をつかれた。「岡とはおれがもうちょい話すわ。あいつかって統を煩わせるんが嫌やでおれに言ってきたんやしな」一応は吹っ切れたらしい。さっぱりした口調でそう言うと、あらためて声色を妙に厳めしくして、
「ほんでもな、おまえにかって弱音吐ける場所あるってことは、忘れんなや」
ここに、というように、自分の胸を右手の親指で指し示した。
二年前、まだ使い込まれていない福蜂のエナメルバッグを大事そうに抱きかかえて、本当はやめたくないんだって、ぐずぐず泣きながら吐露した一年坊も、いつの間にか恰好つけた台詞を言うようになっていた。
三村は相好を崩し、「覚えとく」と答えた。