試し読み
- プロローグ二人の死
-
雨の音がする。行く手を阻む砂嵐のような激しい雨の音だ。
目を覚ましたとき、僕は窓の外のその雨音をぼんやりと聞くともなく聞いていた。鼻を刺す消毒液の臭い。ピコン、ピコン、と無機質で不快な機械音が耳に響く。横たわったまま見上げたそこには白く輝く無影灯がある。
置かれた状況が少しずつ分かってきた。
そうか……。あの公園からの帰り道、僕は事故を起こしたんだ。六月の梅雨空から降りだした雨にバイクのタイヤを滑らせたんだっけ。それできっと病院に。恐らくここは救急外来だろう。
でもあのとき、僕の後ろには彼女が乗っていたはずだ。
じゃあ、まさか——。
起き上がろうとしたけど力がまったく入らない。金縛りにあったときのようだ。かろうじて眼球だけを横に動かすと、隣のベッドで仰向けになる彼女の姿が霞んで見えた。傷だらけの頬には鮮血が滲んでいて、口に挿管チューブを突っ込まれ、救命医から懸命な心臓マッサージを施されている。
彼女の命の灯は、今にも消えてしまいそうだった。
-
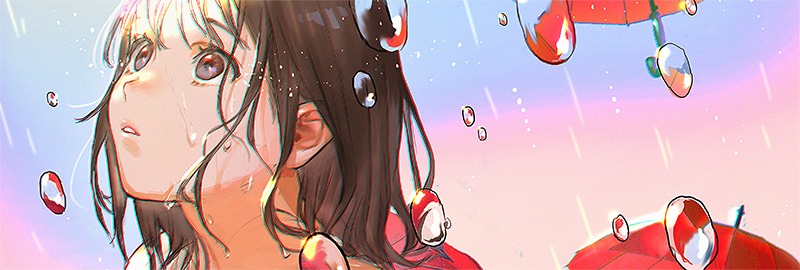
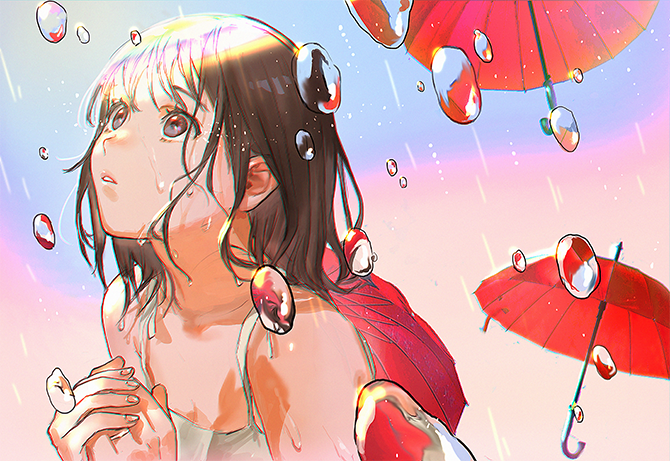
-
どうしてこんなことに……。目の奥が熱くなって視界が滲んでゆく。
僕は心の中で叫んだ。
死にたくない! まだ死にたくないんだ!
誰でもいいから僕らを助けてくれ!
そのときだ。
「雨宮誠君だね」どこからともなく男の声が聞こえた。医師や看護師ではない。脳に直接語りかけてくるような重い響きを持った不思議な声だ。
誰だ? やっとの思いで声の方へと首を倒す——と、驚きのあまり目を見開いた。
ベッドの脇、僕の腰の位置あたりに喪服姿の男が立っているのだ。
男は皺ひとつない真っ黒な背広に身を包み、ウィンザーノットで結んだ黒ネクタイの結び目がずれていないかを指で触って確かめている。緩くウェーブのかかった髪、ブラウンの瞳、すっと通った鼻の下には厚ぼったい唇がある。三十代前半くらいだろうか。優しそうな笑顔が印象的な男だ。
薄く微笑む姿を見て、その正体がすぐに分かった。
ああ、これが〝天使のお迎え〟ってやつか。でもまさかそんな非科学的なことが本当にあるなんてな。しかも天使は喪服姿かよ。羽は生えていないんだな……って、こんなときになにを冷静に考えているんだ僕は。死ぬんだぞ? 人生が終わってしまうんだぞ?
悔しい。悔しくてたまらない。僕にはまだやらなきゃいけないことがあるんだ。いつか一緒にあのタイムカプセルを掘り起こそうって約束したばかりなのに。それなのに……。
奥歯を噛む僕のことを男は上から覗き込む。そして、明瞭な声でこう言った。
「大丈夫。君たちは死なないよ」どういうことだ? 僕らは助かるって、そう言いたいのか?
「ああ、そうだ」と彼は小さく頷いた。どうやら僕が思っていることはテレパシーのように伝わっているみたいだ。
「僕は君たちに、奇跡を届けに来たんだ」奇跡? なんだよ、奇跡って……。
しかしその問いには答えてくれなかった。その代わり、男はふっくらとした唇を動かして「さぁ、行こうか」と僕の身体にそっと手をかざした。すると、今まであんなに重たかった身体は春のタンポポの綿毛のように軽くなる。そして次の瞬間、目が眩むほどの光が辺りを包み、僕の意識はその輝きの中に溶けるように消えていった。
- 第一章二人の夢
-
彼女の笑顔を想うと、時々、涙がこぼれそうになる。
玄関の戸を開けて中に入ると、いつも決まって出迎えてくれる愛らしいあの笑顔。「おかえりなさい」と言うときの少し鼻にかかるその声。抱きしめたときのぬくもり。身体の細さ。からかうとすぐに拗ねてしまうところ。ちょっと味の濃い料理。
そのなにもかもがかけがえのない幸せなんだと、僕は時々、心からそう思う。
この幸せがずっと続いてほしい。消えないでほしい。その願いが僕を弱虫にさせる。彼女を想うと、どうしようもなく涙がこみ上げてしまうんだ。
僕は今、涙がこぼれてしまうような恋をしている。
-
バイト先での打ち合わせから帰宅した僕は、いつものように建て付けの悪い玄関のガラス戸を引いた。かなり力を入れなきゃ開かない。築五十年も経っているから所々ガタがきているのだ。
「おかえり!」と奥から溌剌とした声が聞こえる。ドタドタドタと大きな足音を立てて出迎えてくれたエプロン姿の女の子。相澤日菜。僕の恋人だ。
肩まで伸びた茶色がかった髪を雨粒の形をしたヘアピンで留めた日菜は、輪郭の良い顔をまん丸にして笑っている。くりくりとした大きな目が印象的な少女のような顔立ち。もうすぐ二十三歳になるだなんて、この外見からは想像できない。見ようによっては高校生? いや、中学生——は、さすがに無理かな? とにかくすごく若く見える。
あ、ちなみに、これは僕の名誉のために言っておきたいのだけれど、僕には幼女趣味など一切ない。好きになった女の子がたまたま、たまたま童顔だっただけだ。
「お仕事お疲れさまでした。丸二日徹夜でしょ? 大変だったね」上がり框に座ってブーツを脱ぐ僕の頭を、日菜が後ろからぽんぽんと撫でる。
「まぁね。でも所長が特別ボーナスをくれたんだ。雨宮君は仕事が速いから助かるって」
「へぇ~、やるじゃーん。さっすがぁー」
「だから、はいこれ。『鎌倉ル・モンド』のチーズケーキ」隠し持っていたケーキの箱を差し出すと、日菜は八重歯を見せてパッと笑った。
「わざわざ買ってきてくれたの!?」
「わざわざってほどの距離じゃないよ。バイクだったしね。それに日菜、ここのチーズケーキが食べたいって前から言ってたでしょ?」
「やっさしい~! キョロちゃん、ありがとう!」立ち上がったと同時に日菜がぎゅって抱きついてきた。ケーキが潰れてしまいそうだったので「危ない危ない」と彼女を受け止めつつ箱を上へと逃がした。
日菜は僕を『キョロちゃん』と呼ぶ。みんなは「変なあだ名」って笑うけど、僕はすごく気に入っている。この世界で僕を『キョロちゃん』と呼ぶのは日菜だけだ。彼女に『キョロちゃん』と呼ばれるたび、たった一人の特別な存在でいられる気がして、そのことが誇らしくて嬉しいんだ。
「今日ね、シチュー作ったの! キョロちゃんが好きな鶏肉のトマトクリームシチュー」
「ガレージまで良い匂いがしてたよ。あー、おなか減った。早く食べたいな」
「じゃあ手を洗ってきてくださーい」日菜はケーキの箱を胸の前で掲げて、ふふふと微笑む。相変わらず可愛らしい笑顔だ。
彼女の頭をぽんぽんして洗面所へ向かう。と、日菜がシャツの裾を引っ張った。
あ、しまった。忘れてた。振り返ると案の定、日菜はむすっと頬を膨らませていた。
「忘れてません?」
「ごめんごめん」
「もー、約束でしょ? お帰りのチュー」僕らの間には〝恋人ルール〟がある。キスは一日四回はすること。おはよう、行ってきます、ただいま、おやすみのときだ。もし忘れたら日菜はご機嫌斜めになってしまう。一度へそを曲げたらなかなか機嫌を直さない。だからこれは同棲生活を円滑に送るための大事な大事なスキンシップだ。
僕らはくちづけを交わす。彼女の唇は柔らかい。まるでマシュマロみたいな感触でそのまま食べてしまいたくなる……って、自分で言っていてちょっと気持ち悪いことは重々分かっている。でも日菜とのキスは僕にとって幸福のしるしだ。
付き合ってもうすぐ一年、人が見たら恥ずかしくなるような愛情表現を日菜は今でも求めてくれる。初めはちょっと照れ臭かったけど、小型犬のようにすり寄ってくる小さな日菜が今は愛おしくてたまらない。お金はないけど、愛情だけで言えば僕らは億万長者だ。
いや、でもなぁ、本音を言えば金銭面はなかなか苦しい。
僕は独立して間もない建築家で、仕事の依頼なんてまるでない。だから知人の設計事務所で図面を引いたり、模型を作るアルバイトをしたりして、なんとか生計を立てている。日菜は七里ヶ浜にある『レインドロップス』という喫茶店で働いているけど、給料はそんなに高いわけじゃない。家賃も生活費もすべて折半。二人で力を合わせてなんとかギリギリ生活できている状況だ。年上としてはちょっと、いや、かなり情けない。せめて光熱費くらいは僕が負担するべきなんだけどな。
それでも以前のアパート暮らしに比べれば、ここでの生活は経済的に非常に楽だ。この古民家は日菜の知人の磐田さんという方の持ち物で、月にたったの一万円で住まわせてもらっている。ちょっとおんぼろではあるものの、住み心地は良いし、駅も近い。ちなみに最寄り駅は江ノ電の稲村ヶ崎駅だ。でもだからと言ってこの状況に満足してはいけない。日菜にはもっと良い暮らしをさせてあげたい。彼女は仕事がどれだけ忙しくても僕のことを大切に考えてくれる。ネガティブで傷つきやすい僕は日菜の底なしの前向きさに何度となく助けられてきた。だからこそ、日菜のためにも建築家として大成したい。すべては僕ら二人の〝夢〟を叶えるために。
-
「難しいのは大人と子供の交流でさ。図書館って読書をするための場所だから求められるのは静けさなんだ。でも施主は設計方針として『賑わいのある笑顔の溢れる施設であること』って掲げててさ。図書館としての側面と人々が交流する憩いの場としての側面、その両面を持っていないと応募条件を満たせないんだ」
食卓を囲みながら、僕は今取り組んでいる建築コンペのことを日菜に熱心に話して聞かせた。
鎌倉市内に新設される市立図書館の分館のコンペだ。延べ床面積は五〇〇平方メートル。雑誌・新聞コーナー、絵本を中心とした児童書コーナー、一般図書開架コーナー、交流用のカフェの併設が必須。設計方針としては、①誰に対しても開かれた優しい施設であること。②環境に寄与する施設であること。③賑わいのある笑顔の溢れる施設であること。以上の三点だ。
このコンペの魅力のひとつ、それは参加条件にある。『三十五歳以下の若手建築家に限る』という条件は、僕にとっては夢のようなものだ。普通こういったコンペの場合、過去の実績を問われて僕のような新米はスタートラインにすら立てないことが多い。でも今回は施主の強い希望で「これからの建築界をけん引する若い才能と、鎌倉という古都が融合することで新しいまちづくりを目指したい」と実績は不問だ。締め切りは来月。六月十五日の消印有効。A2用紙一枚にコンペ案をまとめて郵送する。審査結果は二次審査に進めた者だけがホームページに掲載される。審査は鎌倉市長と教育委員会、そして三年前にこの図書館の本館を設計した建築家・真壁哲平が当たる。
真壁哲平——。僕がこのコンペに情熱を燃やす一番の理由は彼だ。
真壁哲平は今業界で最も注目されている建築家の一人だ。三十代前半から数多くの戸建てを手掛けてきた彼は、派手さこそないが、そこに住む人の人生や生活を最大限に考慮した家を造る職人気質な建築家だ。大きなビルや商業施設などには目もくれず〝人が住まう建物〟を造ることをポリシーとしている。考え抜かれた利便性。自然との共存。住む人の気持ちを第一に考えた優しい建物造りには感動すら覚える。以前は戸建てを中心に設計を行っていたが、四十代後半からは——彼は現在五十三歳だ——保育園や図書館のような〝人が集う建物〟へと作品の幅を広げている。
僕は真壁哲平の造る建物が好きだ。いや、好きなんてもんじゃない。お手本のように思っている。素朴だけど細部にまで魂を宿したような考え抜かれた建築は、見ているだけでため息が漏れる。いつか僕も彼のような建物を造れたら……。ずっとずっとそう思ってきた。
ちなみに、僕は真壁哲平のことをフルネームで呼び捨てにしている。僕にとって彼はヒーローのような存在だ。仮面ライダーやウルトラマンを〝さん〟付けにしないのと同じようなことだ。
「ねぇ、これ見てよ。真壁哲平が作った『藤沢の住宅』」彼の作品が載った古い建築雑誌を日菜にも見せてあげた。
「これさぁ、彼が三十五歳のときに造ったんだ。敷地面積が狭いのにこの開放感を生み出すなんて魔法みたいだって思わない? ほら、こことか見てよ。すごいでしょ」
「キョロちゃん、とりあえずシチュー食べません?」
「あ、それからこれも!」と、もう一冊の雑誌をテーブルの上に広げた。「今やってる図書館の本館。ここもすごいんだよ。光の差し込み方が絶妙でさ」
「ねぇ、シチュー冷めちゃうよ?」
「やっぱ分館も光をどう扱うかがポイントだと思うんだよね。あ、そうだ! 最上階のトップライトから吹き抜けを通して光を導く。そうすれば交流室の子供たちが太陽光の下で遊べるなぁ」テーブルの端に置いてあった小さなスケッチブックにすらすらと絵を描いてみる。太陽の光が差し込む天窓の下で子供たちが遊ぶラフスケッチだ。
「でもなぁ~。そうなると下の階の防音性がなぁ——」
「もぉ! キョロちゃん!」
「え?」こめかみにペンを押し当てたまま顔を上げると、日菜は目を吊り上げて怒っていた。
「シ・チュ・ウ! 冷めちゃうよ!」またやってしまった! 僕は慌ててシチューを一口頬張った。
「もー、建築に夢中になるのはいいけど、わたしのことも忘れないでよね。キョロちゃん最近忙しそうだから寂しかったんだよ? だから今日は色々話したいなぁって思ったのにさ……」彼女はタコみたいに唇をにゅっと突き出して不貞腐れてしまった。
「ごめんごめん。じゃあご飯食べたらいっぱい話そうよ。食後のコーヒーは僕が淹れるからさ」
「キョロちゃんがぁ? ほんとに美味しく淹れられるのぉ?」目を細めて怪しむ日菜に、「任せなさい」と自信満々に胸を叩いてみせた。
食事のあと、僕らはあまり美味しく淹れられなかった残念なコーヒーと、買ってきた美味しいチーズケーキを食べながらたわいのない話に花を咲かせた。日菜はこの二日間の出来事をあれこれ楽しそうに話してくれる。色々話したくて焦っているのか、時々息継ぎを忘れて苦しそうだった。コンペのことは気になる。まだアイディアが固まっていないから気ばかりが急いてしまう。でも日菜があまりに嬉しそうだからもう少しだけ付き合うことにした。
結局おしゃべりは夜中の十二時近くまで続いて、彼女はしゃべり疲れてソファで眠ってしまった。「風邪引くよ?」と揺すっても起きる気配はない。一度寝たら朝まで起きないのが日菜の特徴だ。
しょうがないなぁ。寝冷えしないようにタオルケットを掛けてあげた。よだれを垂らしていたのでハンドタオルで口元を拭って、それからよしよしと頭を撫でる。日菜の髪はサラサラで手触りが良い。だからつい飽かず撫で続けてしまう。
しばらくすると雨の音が聞こえた。開け放たれた窓の向こうの小さな庭に目をやると、日菜が植えたトマトやきゅうりの葉の上で雨粒が踊るように弾けているのが見えた。
僕は雨が嫌いだった。でも今は違う。今はこうして雨を眺めるのが好きだ。こんな気持ちになれたのは日菜に出逢ったおかげだ。あの日、日菜と出逢って僕の中で雨の意味は大きく変わったんだ。
-
彼女と出逢ったのはレインドロップスだ。第一印象は可愛らしい店員さん。でも恋愛感情とかそういうことではなく、一般的な意味合いで可愛いと思っただけだった。
それが恋に変わったのは、桜流しの雨が降る、とある午後のことだ。
レインドロップスの店の奥。ガラス窓の向こうにはクチナシや檸檬や枇杷といった常緑樹に囲まれた大きな庭が広がっている。丁寧に刈り込まれた芝生が敷き詰められていて、その中をなだらかな曲線を描いた瓦の小径が縫うように延びている。庭の隅には小さな花壇もある。赤、白、黄色のチューリップが雨に打たれて首を垂らしていた。
僕は窓際の席に座って庭に降るその雨をぼんやりと眺めていた。そして「雨って嫌ですね」と隣のテーブルを片付けていた日菜に世間話のつもりでなんとなく話しかけてみた。そうしたら、
「雨、お嫌いなんですか?」
「そりゃあ誰だって嫌いだと思いますよ。濡れるし、ジメジメするし、気分だって憂鬱になるし」彼女は「うーん」と人差し指で顎の先を押し上げるしぐさをした。
「でもわたし、雨って好きなんですよね」雨が好き? どういうことだろう?
「だって雨の日は傘を差せるじゃないですか。この間、新しい傘を買ったんです。青い水玉模様の折り畳み傘。すっごく可愛くて、雨が降るのを楽しみに待ってたんです」彼女の目はキラキラ輝いている。まるで光に照らされた雨粒みたいに。
お気に入りの傘が差せるからか。なるほどな。いつもビニール傘の僕にはない発想だ。
「それに雨って、誰かが大切な人を想って降らす〝恋の涙〟なんですよ」
「恋の涙?」
「はい。和泉式部の和歌でこんなのがあるんです」彼女は小さく咳ばらいをすると、その歌を僕に教えてくれた。
-
おほかたに さみだるるとや 思ふらむ
君恋ひわたる 今日のながめを -
「どういう意味なんですか?」
「あなたはこの雨を普通の雨と変わらない五月雨と思っているのでしょうか。あなたを想う、私の〝恋の涙〟であるこの雨を」思わず笑みがこぼれた。「素敵な歌ですね」
「ですよね」と彼女も釣られるようにして笑った。
「わたし、この歌を知ってから雨がとっても好きになったんです」雨を愛する人か……。素敵だなって、心から思った。
窓外の雨を見つめるその横顔に、僕はいつの間にか恋をしていた。
-
だから今も雨が降ると思い出す。日菜に恋したあの日のことを。雨は僕を初心に戻してくれる。彼女を大切にしなきゃって思わせてくれるんだ。僕らの夢を叶えなきゃって。
いつか日菜に家を建ててあげたい。それが僕の、僕らの夢だ。そのためにも次のコンペは絶対に勝ち取ってみせる。このコンペをきっかけに建築家としての名を上げるんだ。
午前一時。うーんと大きな伸びをして、リビングと続き間になっている作業部屋でアイディアの続きを練った。眠気になんて負けている暇はない。頑張らなくては。
優しい雨音を聞きながら、僕はいつまでもスケッチブックに鉛筆を走らせ続けた。
-
*
-
朝の新鮮な太陽の光を浴びて海がキラキラと輝いている。
レインドロップスへの出勤途中、自転車を止めて湘南の海を眺めるのがわたしの日課だ。
今日も一日頑張ろう! って思えるこの瞬間は大事な宝物のひとつだ。
江ノ電の七里ヶ浜駅を越えると、線路わきに階段が見えてくる。青い外観のアパートに自転車を停めさせてもらって、ゆるやかな階段を上ってゆく。草木が生い茂った細い道は、まるで異世界へ続くトンネルのようだ。
階段が終わると今度は坂だ。遠くの波音を聞きながらのんびり進むと、レインドロップスが見えてきた。お店は二十年ほど前からこの場所にあるらしい。でも外観に古めかしさは感じない。ログハウス風の建物とカナリーヤシが特徴の洒落た佇まいをしている。
肩ほどの高さの木の門を押し開けて、店へと続くレンガの道をゆく。カウベルを鳴らして中に入ると、ヒノキの優しい香りが鼻をくすぐった。
店内はゆったりしている。テーブル席が五つに大きな一枚板のカウンター。天井にはライトと一体になったシーリングファンがくっついている——掃除が大変だからわたしはこれが嫌いだ——。店の裏手には庭があって、バルコニーにテラス席が四席もある。ちなみに、テーブルと椅子はすべて『ヘパイストス』っていうブランドのものを使っていて、キョロちゃんは「趣味が良いね」って褒めてくれる。お客さんからも座り心地が良いって好評だ。
でも、ちょっと疑問に思うことがある。店主のエンさんはズボラな性格だ。あ、エンさんっていうのはあだ名で、本名は大石縁っていう。みんな、彼女を『エンさん』って呼ぶ。字だけを見たら『ゆかり』と読めずに、だいたいの人が『えん』って誤読してしまうからだ。
エンさんは物への執着がまるでない。なのになんでこんなに趣味の良い——しかも高価な——テーブルや椅子を揃えたんだろう? もしかして元カレの趣味だったりして。この店をはじめた頃に付き合っていた彼氏の影響かな? よし、今日こそは訊いてみよう。
店の奥の倉庫兼従業員部屋でささっと着替えを済ませる。半袖の黒いTシャツにサロンエプロンというシンプルなユニフォームだ。
古いオーディオのスイッチを入れて音楽を流す。BGMは昔の洋楽やジャズが多い。倉庫で埃を被っていたCDをわたしが引っ張り出したのだ。これも誰のCDなんだろう。エンさんの趣味じゃないと思う。エンさんは洋楽なんて聴かないし、サザンオールスターズにしか興味がないから。
八十年代のダンスミュージックに合わせて床掃除をして、それからランチの下ごしらえをはじめる。メニューは三種類。日替わりメニューの『豚肉と彩り野菜のレモンビネガーソース定食』と『鰆の西京焼き定食』、そして定番の『レインドロップス特製豆乳グラタン』だ。メニューを決めるのはわたしの仕事。エンさんは面倒くさがってランチについてはノータッチ。考えるのはひと苦労だ。でもレインドロップスの一番の売りはなんといってもこのランチ。ボリュームがあって健康的で、女性客はもちろん、お年寄りや会社員、身体を使う職人さんにまで幅広く好まれている。
鎌倉野菜の直売所で買ってきた肉厚の赤パプリカをカットしていると、カランカランとカウベルが鳴って「おはよう~」と気怠そうな声が聞こえた。ようやくエンさんの出勤だ。寝不足らしき顔はむくんでいるけど、整った顔立ちをした黒髪の美人さん。でもここ最近、毎晩飲み歩いているせいでお肌の張りが失われつつあるって愚痴っている。それって自業自得だと思うけどな。
「も~、昨日も遅くまで飲んだんですか?」
「昨日じゃなくて今朝までよ~」エンさんはカウンターに倒れ込むようにして突っ伏した。
「いい加減にしないと身体壊しちゃいますよ?」
「じゃあ壊れないようにいつもの作って~」わたしはやれやれと包丁を置いて庭に面したサンテラスへ向かった。いくつものハーブの鉢が所狭しと段々に並んでいて、朝日を浴びて緑の葉が輝いている。みんな今日も元気だ。「あとでお水あげるからね」って話しかけながらミントを摘んで、ハチミツと混ぜてミントティーを淹れた。
エンさんは淹れたてのミントティーを熱そうに飲むと「はぁ、肝臓が喜んでる~」ってかすれた声で唸った。少し舌足らずなしゃべり方は少女みたいで可愛らしい。
「やっぱ日菜ちゃんが淹れるミントティーは最高ね~」
「褒めてくれるのは嬉しいけど……」
「けどなぁに? あ、またお説教? 店長としての自覚を持てって言うつもりでしょ~」
「正解です」腰に手を当てて口をへの字にしてみせた。
「わたし自覚とかそういうの全然ないからさ~。そもそもこのお店にも愛情ないしね~」
「じゃあどうして喫茶店はじめたんですか?」
「うーん、どうしてだろう? 忘れちゃったな~。そんな昔のこと」あ、チャンスだ。わたしはシンクに手をついて身を乗り出した。
「もしかして元カレが『エン、俺と一緒に喫茶店やろうぜ』って言ったとか!?」
「なによそれ」エンさんはカップを両手で包んで、ふふふって笑った。
「だってほら、このお店って内装もテーブルも椅子も全部趣味が良いじゃないですか。ずっと不思議だったんですよね。ズボラで無頓着なエンさんらしくないって。だから元カレの趣味なのかなぁって。意外と名推理だったりして!」
「ズボラで無頓着は余計よ。それから、四十四のおばさんの過去をほじくり返そうとしてもロクなことないわよ。男なんて長いこといないしさ」
「えー、でもエンさんモテると思うんだけどなぁ。彼氏いないのが不思議なくらいですよ」
「あのねぇ、最後にキスしたのいつか教えてあげようか? 二十世紀の出来事よ?」とエンさんは切れ長の目でわたしのことをじろりと睨んだ。つい調子に乗ってしまった。エンさんはプライベートなことを詮索されるのが嫌いだ。高校を卒業して働きはじめて四年くらい経つけど、恋愛事情とか私生活はあんまり詳しく教えてくれない。常連さんの話では、このお店がオープンしてしばらくは情緒不安定だったらしい。ヒステリックなエンさんなんて想像できない。やっぱり一人でお店を経営するのは大変なんだろうな。
反省しているわたしを見て、エンさんはくすっと笑う。
「この店をはじめたことに男なんて絡んでないわよ。なんとなく喫茶店でもはじめようかなぁって思ったんじゃない? 過去のわたし。結婚することもなさそうだしさ~」
「え、結婚したいって思ったことないんですか?」
「そりゃ一度や二度くらいはあるわよ~。現に酔った勢いでウェディングドレス買っちゃったしね」
「酔った勢いで!?」
「そうそう。ある日気付いたらクローゼットの中にウェディングドレスがあったの。そりゃもう、びっくりしたわよ。多分酔っぱらった勢いで買っちゃったんじゃないかなぁ~?」酔った勢いでウェディングドレスを買うって……。
やっぱりエンさんはちょっと、ううん、かなり変わっている。
-
昼時のレインドロップスは戦場のようだ。ランチを求めて大勢のお客さんが来店する。
カウンターの向こうのキッチンにはわたし一人だけ。料理もドリンクも、すべてのオーダーに対応しなければならない。フライパンを振りすぎて腕はもうパンパンだ。
「日菜ちゃ~ん、四番テーブルさんに魚定食とグラタンね~。飲み物はレモンティーとアイスコーヒー。あと六番さんには日替わりとドリップコーヒーよろしく~。深煎りね~」オーダーを取るのはエンさんの仕事だ。でも忙しいから少しはこっちも手伝ってほしい。
「あのぉ! 手が離せないんで代わりにドリンク作ってくれませんか!?」
「ごめ~ん。わたしドリンク作らない主義だから~」ドリンク作らない主義ってなに!? もぉ、絶対面倒くさいだけじゃん!
「日菜ちゃん! こっちのメシも早く作ってくれよ!」
「サービスでおかず多めにしてくれよな!」
「すみません! ちょっと待っててくださーい!」泣きそうになりながら叫ぶと、常連さんたちは声を上げて笑った。みんな必死なわたしを見て楽しんでいるんだ。くそぉ、負けてはいられないぞ。
忙しさの波が引いたのは午後二時を過ぎた頃だ。土日の忙しさに比べればまだマシだけど、この日はかなり忙しかった。シンクに山積みになった洗い物を片付け終わるまではお昼ご飯にはあり付けない。早くしなきゃテーブルのグラタンが冷めちゃうよ。
「さっすが日菜ちゃ~ん。今日のグラタンも美味しいわね~」カウンターでは一足先にエンさんが舌鼓を打っている。
「褒めてくれるのは嬉しいけど……」
「けどなぁに? あ、またお説教?」
「違います。洗い物、手伝ってくれません?」
「うーん。それはパスかなぁ~」ちょっとは手伝ってよ! ムカつく気持ちをフライパンにぶつけたら手を滑らせて落としてしまった。ガシャーンという音が店内に響く。うわ、やっちゃった……って片目を瞑っていると、
「んだよ、相変わらずドジだなぁ!」この声は——。ドアの方に目をやった。
「ドジって言わないで」わたしは唇を尖らせた。
「うるせーよ。どこからどう見てもドジじゃねぇか」ニカッと歯を見せて笑うニッカボッカの茶髪の青年。ガタイが良くて筋肉質。まくったシャツからは逞しい腕が見える。畑中研。小学生時代からの幼馴染みだ。
「もうランチタイム終わりましたけどぉ」って嫌味っぽく言ってやった。
「あるじゃねぇかよ、そこに美味そうなグラタンが」研ちゃんはそう言って、わたしのグラタンへ一目散に向かった。
ヤバい! 食べられちゃう! 慌ててカウンターを飛び出したけど遅かった。研ちゃんはスプーン片手にすごい勢いでグラタンを頬張りはじめた。
グラタンの悲鳴が聞こえる。こんな汗臭い男に食われたくねぇよぉ! って。
「それわたしのグラタン! 返してよぉ!」取り戻そうとしたけど、大きな手で顔を押さえられて動けなくなってしまった。
「かえひなはいよ! なくなっひゃうでしょ!」
「うるせぇなぁ! もうちょっとだけ食わせろって!」
「いーやーだ! 返してぇぇぇ——!!」悔しさのあまり手のひらの端をがぶっと噛んでやった。
「痛っ! なにすんだよ! よだれがついただろうが!」研ちゃんが慌てて手を離したので、その隙にグラタンの奪還に成功した。
よかったぁ~。まだ半分くらい残ってる。ごめんね、グラタン君。
「ねぇねぇ、研ちゃん? その手についた日菜ちゃんのよだれ、舐めるつもりでしょ~」エンさんの衝撃発言に口に入れたグラタンを噴き出してしまった。
「な、舐めるの!? キモい! やだ! やめてよ!」
「はぁぁぁ————!? 舐めるわけねぇだろうが!」
「でもでもぉ~、研ちゃんは日菜ちゃんのことが好きなんでしょ~?」
「はぁぁぁぁ—————————! んなわけないじゃないっすよ!」
「ほらほら~、動揺してなに言ってるか分からなくなってる~。明太子みたいに耳が真っ赤よ~」
「あり得ないっすよ! こんなちんちくりんのバカ女、誰が好きなもんか!」
「ちょっとぉ! バカってなによ! バカって!」研ちゃんは意地悪だ。いつもこんな風に悪口を言っていじめてくる。子供の頃からずっとそう。今でこそ実家の『畑中工務店』で働きだして丸くなったけど、昔は超が付くほどの不良だった。高校生の頃なんて先生の車をチェーンソーで真っ二つにして退学になりかけた筋金入りの不良少年だ。
まぁでも、そうは言っても憎めない奴なんだけどさ……。
研ちゃんが「おい日菜、代わりになんか作ってくれよ」ってせがむから、残り物で肉野菜炒めを作ってあげた。こんもり山盛りにしたご飯と味噌汁をあっという間にぺろっと平らげる姿はまるで吸引力抜群の掃除機だ。食いっぷりは見ていて清々しい。
ご飯を食べ終えると、研ちゃんは「ごちそうさん」とそそくさと席を立った。
「なによ? 素っ気ないなぁ。もしかして怒ってる?」
「別に」
「やっぱ怒ってる。あ、エンさんが言ったこと? もー、分かってるって。研ちゃんがわたしのこと好きなわけないもんね。研ちゃん巨乳好きだし。大丈夫大丈夫。真に受けたりしてないからさ」
「人をエロガキみてぇに言うんじゃねぇよバカ! 俺はただ——」
「ただ?」研ちゃんは舌打ちして恥ずかしそうに紙袋を差し出した。
「なにこれ?」
「はぁ? 今日、おめぇの誕生日だろうが。二十三の。忘れてたのかよ」
「もしかしてプレゼント?」
「ち、ちげーよバカ! たまたま今の現場の目の前が雑貨屋で、たまたまおめぇの誕生日を思い出したから、たまたま買ってきただけだって! 調子乗んなバカ!」
「へぇ~~。いいとこあるじゃーん」ニヤニヤしながら顔を覗くと、研ちゃんは恥ずかしそうにまた耳を真っ赤にした。
「そっかそっか。これを渡すのが照れ臭かったんだね? 可愛いところもあるもんだ」
「うぜーんだよ、お前は! ここに置いておくぞ!」研ちゃんは紙袋とランチ代の千円をカウンターに置いてさっさと出て行ってしまった。
研ちゃんからのプレゼントはマグカップだった。おにぎりみたいな猫のイラストが描いてある可愛いやつだ。これを買っている研ちゃんを想像するとちょっと笑える。「おい! 早く包んでくれよ!」って店員さんに恥ずかしそうに頼んだんだろうな。こういうところが憎めないんだ。
わたしは研ちゃんに『ありがと。大切に使わせていただきます☺』ってメールを送った。
閉店は六時半だ。店じまいの準備をして、いつもだいたい七時頃には帰ることができる。ちなみに、暇なときはエンさんの気分次第でもっと早く閉めてしまうことだってある。
帰り際、エンさんが「はい、これ」とプレゼントをくれた。ずっと欲しかった、切れ味抜群の包丁だ。通販番組で見つけて以来、買おうかどうしようか迷っていた。
「彼氏と喧嘩してもこの包丁で刺したらダメよ~?」
「やだなぁ、刺しませんよ。これでキョロちゃんに美味しいご飯を作ってあげます」
「そういえば、なんで〝キョロちゃん〟っていうの? 変なあだ名だなって思ってたんだよね~」
「あれ? 話したことありませんでしたっけ? 彼が初めてここに来たとき、店内をキョロキョロ眺めてたんですよ。その姿が挙動不審でおかしくて。だから心の中で勝手にキョロちゃんって呼んでたんです。で、付き合ってからもそのままで」
「ふーん。誠君はきっと日菜ちゃんのことを見てたのね~」
「え~、恥ずかしいじゃないですかぁ~。でもまぁ、確かにそうかもしれませんね~。そっかそっかぁ、キョロちゃんはわたしのことを見てたのか~。ふふふ」
「枯れたおばさんの前で惚気ないでくれる? ムカつくから」エンさんは嫌味なくらいにっこり笑った。
「ごめんなさい……」とわたしは肩をすぼめた。誕生日ということで会う人みんながプレゼントをくれた。帰り道に立ち寄った八百屋さんでは段ボールひと箱分の野菜。魚屋さんでは旬のアジ。お肉屋さんではコロッケ。お花屋さんでは花束を。家に着く頃には自転車のカゴは荷物でいっぱいだった。こんな風に祝ってもらえて嬉しいな。レインドロップスで出来たこの繋がりはわたしの大事な大事な宝物だ。
山のようなプレゼントをよいしょと抱えて、指先で玄関のガラス戸を頑張って引く。でも建て付けが悪いからなかなか開かない。鍵をかけてないからキョロちゃんは中にいるみたいだ。だから「キョロちゃーん。荷物持つの手伝ってー」って呼んでみた。けど、いくら待っても来てくれない。
あれれ? どうしたんだろう? コンビニでも行ったのかなぁ?
キョロちゃんは作業部屋で難しい顔をしていた。煮詰まっているみたいだ。「ただいま」って言ったけど、「うん」と短く答えるだけ。集中しているときはだいたいいつもこんな感じだ。
まったく、しょうがないなぁ。じゃあ夕ご飯の支度でもしますかね——ん? 待てよ。これってもしかして誕生日忘れてるパターンじゃ……。いやいや、まさかね。そんなことないよね。だって彼女の誕生日だよ? さすがに覚えてるはずだよね?
それから一時間経ってもキョロちゃんはちっともかまってくれなかった。リビングのソファから作業部屋の彼をじーっと観察する。相変わらず頭を抱えている。これはいよいよ忘れている可能性が高いぞ。ちょっとだけイライラしてしまった。
「ゴホン!」わざとらしく咳ばらいをしたけど、キョロちゃんは全然こっちを見てくれない。ほほう。そっちがそういうつもりなら、そろそろ怒りますけど覚悟はいいですね?
怒ってやろうと大きく息を吸い込んで——いや、やめておこう。せっかく集中しているのに邪魔したら悪いよね。キョロちゃんにとって今は大事な時期だ。憧れの建築家さんに認められるかもしれない大チャンスを前にしているのに「誕生日お祝いして~」なんてちょっと自分勝手すぎる。
けどなぁ~~~、寂しいしなぁ~~~。気付いてほしいなぁ~~~。
よし、こうなったら念を送ろう! 気付け……気付け……気付けぇぇぇ!
ちっとも気付いてくれなかった。わたしは撃沈してソファに顔を埋めた。
はぁ……。今日はわたしの誕生日ってだけじゃないんだよ?
キョロちゃんを好きになった〝恋愛記念日〟でもあるのにな。
-
一年前の六月六日——。わたしは彼に恋をした。
さっきまで晴れていた空が嘘みたいに真っ黒になって一気に雨が降ってきた午後。彼はレインドロップスの窓辺の席に座って、雨の降り具合を観測するように真剣な顔つきで外を眺めていた。
うん、やっぱり今日もイケメンだ。わたしはコーヒー豆を補充しながら彼を盗み見て思った。
鼻筋はすっと伸びて、顔は繊細なガラス細工みたい。透き通るような白い肌のせいか、どこか女性的な印象を受ける。でも黒縁の眼鏡をくいっと押し上げた指の下の手の甲は筋張っていて、そこになんとも言えない男っぽさを感じる。
わたしは最近よく来る彼のことが気になっていた。芸術家っぽい雰囲気や繊細そうな外見は結構、ううん、かなりタイプだ。着ている濃紺のジャケットとカーキ色のチノパンツもすごく良く似合っている。ふんわり漂う柔軟剤の香りも良い感じだ。
お客さんもエンさんもいない店内には、わたしと彼の二人だけ。辺りの音をすべてかき消しちゃうくらいの雨音の中に二人きりでいると、この世界にわたしたちしかいないような気がして妙にドキドキしてしまう。
「あの……」とキョロちゃんがこっちを見た。すごく緊張した顔だ。その表情にドキッとして「な、なんでしょう?」って声がうわずってしまった。彼は窓の外に目を向けると、震える声でわたしに言った。
「この雨、僕が降らしたって言ったら笑いますか? あなたを想って降らした〝恋の涙〟だって言ったら……」眼鏡の奥の潤んだ瞳に吸い込まれそうになる。なにか言おうとしたけど言葉が全然出てこない。
「——って、引きますよね? 忘れてください。ははは……」彼は恥ずかしそうに後ろ髪を撫でた。自分の発言を後悔しているみたいだ。
わぁわぁわぁ! どうしよう! 引いているわけじゃないの! びっくりしただけなの! そのことを伝えなくちゃ! えっと、えっと……あれ? でも今のって——、
「もしかして今のって、告白……ですか?」彼の顔が真っ赤になる。それから下を向いて雨音に消されるくらい小さな声で「そうなりますね」と呟いた。わたしはなんて答えたらいいか分からなくて「そっか。そうですよね。変なこと訊いてごめんなさい。そっかそっか」と何度も頷く。全身がものすごく熱くて、吹き出す汗を手のひらで拭った。でも汗は止まらない。濡れた雑巾にでもなった気分だ。
告白かぁ……。その言葉を噛みしめるとニヤニヤが止まらない。
「迷惑ですよね?」キョロちゃんが上目遣いでこっちを見た。
「そ、そんなこと! 嬉しいですよ! 少し!」
「……少し」
「あ、いや、少しって言うか、結構? かなり? なんて言ったらいいんだろ」頬っぺたをぽりぽり掻いた。それから身体中の勇気を集めて、
「たくさん嬉しいです……」チラッと見たら、彼は顔をくしゃくしゃにして笑っていた。その笑顔を見た途端、心が二つに割れた音がした。そこから流れ出す甘酸っぱい気持ちが全身に広がる。そして思った。
ああ、わたし今、恋に落ちたんだ……って。
煙草を買いに行っていたエンさんが帰って来ると、彼は恥ずかしそうにコーヒーカップを手にそっぽを向いてしまった。知らんぷりしているけどカップを持つ手がちょっとだけ震えている。その姿がなんだかとっても可愛らしく思えた。
雨が降って、よかった……。突然降り出した夕立に、心の中で「ありがとう」って伝えた。
それからひと月くらいして、わたしたちは正式にお付き合いをはじめた。
-
「——日菜、起きて」
肩を揺すられて目を覚ましたとき、時計の針は十一時を指していた。キョロちゃんはようやくわたしの存在に気付いてくれた。「やっと起きた」って笑っている。さっきからたくさん揺すってくれていたらしい。だけど誕生日のことは気付いてないんだろうな。あと一時間で誕生日が終わっちゃうよ。「今日、誕生日だよ」って言ってみようかな。でもプレゼントなんて用意してないだろうし、キョロちゃんはきっと自分のことを責めちゃうと思う。それが創作の妨げになったら……。
わたしは誤魔化すように「先にお風呂入るね」と——、
「あ、待って!」振り返ると、キョロちゃんは緊張して口をもごもごさせている。
「あのさ、今からちょっと散歩に出かけない?」
「え? でも外、雨降ってるよ?」と庭に降る小雨を指さした。
「うん。雨が降ってるから出かけたいんだ」意味が分からず首を傾げると、キョロちゃんは後ろ手に隠していた赤い傘を出した。
「……もしかして、それって」
「うん、誕生日プレゼント。買っても良かったんだけど、どうせなら手作りでって思ってさ。でもちょっと苦戦しちゃったんだ。日菜が帰って来たときにはまだ半分くらいしかできてなくて。寝たのを見計らって大慌てで続きを作ったんだけど……。ごめん! 急いで作ったからちょっと不格好になっちゃったよ」傘をこっちに向けながら、彼は情けなく目尻を下げて笑った。
嬉しさとびっくりした気持ちがごちゃまぜになって涙がこぼれてしまった。
「えぇ!? なんで泣くのさ!?」
「だってぇ! 誕生日忘れてると思ったんだもん! もー、覚えてるなら言ってよぉ!」
「言ったらサプライズにならないじゃん」と彼はくつくつ笑った。
「それはそうだけどぉ。でも不安だったんだよ」キョロちゃんは「ごめんね」と頭を撫で撫でしてくれた。
「じゃあ日菜、誕生日が終わる前に散歩に出かけましょうか」その笑顔に、わたしは「うん!」って大きく頷いた。
自宅を出て海を目指す。家の周辺は細い道ばかりで迷路みたいに入り組んでいる。なだらかな坂を石垣に沿って下って行くと、やがて江ノ電の線路とぶつかる。赤く光る踏切のランプ。カンカンカンという警告音が小気味良い。のんびり走る最終電車を見送ると、わたしたちは再び歩いて国道一三四号線に出た。
赤い傘の下、肩を寄せ合い、波の音を聞きながら海沿いの国道を進んでゆく。今日の雨は優しい。細い糸のような雨が空からまっすぐに落ちて世界を濡らしている。こういう雨のことを〝糸雨〟って言うらしい。雨の名前は詳しくないけど、キョロちゃんが時々教えてくれるんだ。
彼の手作りの傘が嬉しくてさっきから上ばかり見ちゃう。さすがは建築家さんだな。模型とか作ってるから手先が器用だ。傘を作れるなんて男子としてはかなりポイント高いですよ。それに、わたしが無類の傘好きってこともちゃんと分かってくれている。それが嬉しさを倍増させる。うんうん、ツボを心得ていらっしゃる。
「重くない? 僕が持とうか?」
「ううん、わたしが持ちたいの」
「そっか。じゃあ悪いけど、傘を右手に持ち替えてくれるかな」
「どうして?」
「手をさ」とキョロちゃんが恥ずかしそうに右手をこっちに向けた。
「ふふ。つなぎたいんだね。仕方ないなぁ。あ、でもキョロちゃんが濡れちゃうよ」
「いいさ。それでもつなぎたいんだ」傘を右手に持ち替えると、それを合図に彼の手がわたしの手を優しく包んだ。すべすべで温かい手。大好きな彼の大きな手だ。指と指を絡めて恋人つなぎをする。このつなぎ方は別の言い方で〝貝殻つなぎ〟って言うらしい。きっとみんな探しているんだ。この世界のどこかにいる、もう片方の貝殻を。ぴたっと重なる相手のことを。
「昔ね、お母さんに教えてもらったことがあるの。人にはそれぞれ手が付いている理由があるって。手ってね、物に触ったり持ったりする以外にも、その人のやるべきことが込められてるんだって。それでお母さんに言われたの。日菜の手はなんのために付いてるんだろうねって。その理由が見つかるといいねって」お母さんのことを想うと今も胸が痛くなる。普段は思い出さないようにしているけど、こんな風に誕生日にはちょっとだけ思い出してしまう。
小学五年生のとき、お母さんは男の人と出て行った。その手をわたしやお父さんじゃない他の人のために使ったんだ。そう思うと苦しい。だからいつもはお母さんの記憶は心の底に深く沈めている。悲しい気持ちに飲み込まれないように。
「日菜は今でもお母さんに会いたいって思う?」
「どうだろう。昔は会いたかったよ。でも今はそこまで思わないかな」
「でもさ、日菜にとってお母さんは唯一の肉親なわけだし……」
「いいのいいの。だってわたしには——」ぎゅっと手を握った。
「キョロちゃんがいるから」彼は手を握り返してくれた。わたしの心を包み込むように。大切そうに、すごく優しく。
胸がじんわりと熱くなる。悲しい気持ちが雪のように溶けてゆく。
幸せだな……。ずっとずっと一緒にいたいな。
彼の手はそう思わせてくれる魔法の手だ。
「——あ!」キョロちゃんが短く悲鳴を上げた。「雨漏りだ……」傘の生地に雨が染みている。ぽとりぽとりと雨粒が落ちてきた。
「えー、嘘だろぉ。完璧だと思ったのに」キョロちゃんはがくりと肩を落とした。その姿がおかしくて、ついつい笑ってしまう。
「笑いごとじゃないって。早く帰らなきゃ濡れちゃうよ。ほら、行こう日菜」手を握ったままキョロちゃんが走り出す。
わたしはその手をもう一度握った。強く強く、握った。
これからもずっとずっと、死ぬまでずっと、離れないように。
-
*
-
続きは本編でお楽しみください!