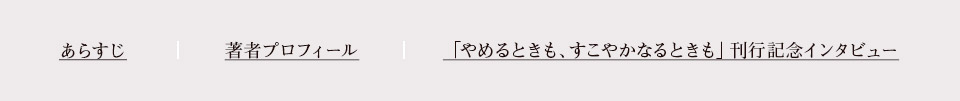──本作は三十二歳のふたり、家具職人の壱晴(いちはる)とパンフレット制作会社勤務の桜子(さくらこ)の目線で語られていく物語です。壱晴は、大切な人の死を忘れられず、毎年十二月になると声が出なくなる「記念日反応」という症状を抱えていますが、この設定はどのようなところから生まれたのでしょうか。
最初に編集の方から「何かひとつ感覚的なものが欠落している人の話を書いてみませんか」という投げかけがあったんです。ただ、最初から感覚を失っている人の話だと読者の方との間に距離感が出てしまうので、時期が来ると何かが失われる話のほうがいいのではと思いました。そこで調べたり、心療内科の先生にお話をうかがったりするうちに、「記念日反応」というものがあることを知って。登場人物がそれを抱えていて、原因となった出来事が明らかになっていく話にしようというところから始まりました。
──一方の桜子は家族の暮らしを経済的に支えながらも、そこから抜け出すために結婚を願っている、恋愛が苦手な女性です。冒頭はそんなふたりが、あるきっかけでベッドを共にした翌朝から始まります。家具職人で、椅子をつくっている壱晴は、眠っている彼女の脚の長さを指で測ります。エロティックで職人らしいシーンでした。
ふたりとも酔っていたので、記憶がないのだけれど、壱晴が桜子を知る最初の手掛かりはそこだったんですね。以前から職人的な仕事をしている人を書きたいという気持ちがあったので、壱晴を家具職人にしましたが、彼がつくる椅子には結構大きな意味があったなと、書いたあとに思いました。誰かを休ませて、また立ち上がって歩いて行かせるための生活の道具が椅子。壱晴が師匠から離れて独り立ちして、桜子のための椅子をつくることが小説のひとつの筋になっていますが、椅子がふたりの関係を表しているような気がしました。家具工房などにも取材にうかがったのです。「木は傷を抱えながらも大きくなっていく」という言葉など、資料からもいろいろなヒントをいただきましたね。
──桜子は壱晴の身辺から木の香りを感じ、壱晴も桜子の気配からジャスミンのような香りを感じる。嗅覚がふたりの内面をざわつかせ、恋愛の萌芽になった気がしました。
壱晴は記念日が近づくと声が出なくなるという欠損を持っているので、その他の感覚が余計に研ぎ澄まされるのではと想像しました。もともと私は、人の匂いや香りが結構好きなんです。暑い時期に電車に乗ると空気が汗くさかったりしますが、嫌なニオイだなと思いつつも、人が生きていることを実感して。男性の体臭とか、赤ちゃんのほこりっぽい匂いとか、生命と感覚的に結びつきやすい気がします。私にとって三十二歳はまだ若々しいというイメージなので、壱晴と桜子には木やジャスミンといったみずみずしい香りが浮かんだような気がします。
──壱晴は子どもの頃からよその家を見るのが好きで、間取りなどから家庭の事情を想像しますが、家も不思議と独特の匂いを持っているものですね。
そうですね。実家を出てしばらくして帰ったとき、初めて家の匂いに気づいたり。壱晴にとって香りやよその家は、他者や他の世界を認識する手掛かりだったのだと思います。それらを使って、彼は世の中を知るための扉を不器用に開けていった気がします。
──よその家を見ることで、壱晴はその家の経済状態と自分の家のそれを比較し、現実の厳しさを認識するようになります。高校時代の同級生、真織(まおり)との関係もそうして始まりました。窪さんにとって「経済」は、問いかけてくるものが大きいのでしょうか。
小説は人を描くものですが、経済状態はそのために絶対に切り離せないものだと思っています。その考えはデビュー作から変わらなくて、真織にしても桜子にしても、どんな暮らしを送っているのか、家計は誰が担っているかはどうしても欠かせない要素。書かざるを得ないぐらいの気持ちです。
──壱晴と桜子が近づいていく過程が丁寧に描かれる一方で、父と娘の難しい関係がもうひとつのテーマになっていますね。
家族の問題のキーワードとして、お金はすごく大きいと思っています。経済状態さえ良ければ、男の人ってのびのびするじゃないですか(笑)。女の人も「生活費さえ入れてくれれば」と思っちゃうところがある。でもそこがうまくいかなくなると、夫婦は精神を縛られたようになっていきます。残酷なことに子どもは親の経済状態に大きく左右されるし、そこから抜け出すことが難しいんです。それは私自身が体験したことでもあり、ぜひとも書き留めておかなければならない現実だと思っています。
──桜子の妹や母は、善人とも悪人とも言い切れないキャラクターのように感じましたが、どのようなイメージで書かれたのでしょうか。
妹の桃子(ももこ)は、ちゃっかりしているように見えて、桜子ほど家族のことを考えていないかというと実はそうでもない。そして母は、会社が倒産して落ち込む夫を支えたという側面があったかもしれないけれど、桜子を苦しませた悪人と見る人もいるかもしれない。私としては登場人物の誰も責めたくないし、決着を付けることが小説だとも思っていないんです。むしろ読者の方の目線や視力によって、いく通りにも読めるように書きたいと思っています。
──物語の中盤で壱晴は真織との過去を桜子に語り、大切な人の死という心の傷を克服するために、学生時代を過ごした島根県松江への旅に誘います。松江を思い出の地にされたのは、どんなお気持ちからだったのでしょうか。
二年ほど前に米子(よなご)市の書店さんからイベントに呼んでいただいたときに足を延ばし、初めて訪れたときの記憶が残っていました。書き始めてからひとりでもう一度行きましたが、松江っておだやかなんですよね。海みたいに大きい宍道湖(しんじこ)が街の真ん中にどーんとあって、昔から変わっていない日本みたいな雰囲気があって。小さないtい街だと思いました。小説の中に、縁結び祈願のために出雲(いずも)大社に向かう女性たちが出てきますが、今回は結婚がテーマなので、そういう意味でも松江を舞台にしたのは良かったなと思っています。
──ずっと結婚したいと思っていた桜子ですが、壱晴と出会って現実的になると結婚の見方が変わっていきます。縁結び祈願の女性たちを旅の途中で目にして、自分は先んじていると優越感を持つ一方で「純粋な喜びにばかり浸ってはいられない」と、もやもや考える姿が印象的でした。
これまで桜子は結婚にふわっとしたイメージを持っていたけれど、壱晴と出会って、彼がとんでもないものを背負っているかもしれないと気づいて、少し怯(ひる)むんですね。そんなふうに、結婚へ一歩踏み込んだときの女性を書いてみたかったんです。特に相手がいないうちは、結婚がピンク色に見えるかもしれないけれど、現実には相手の人生を背負うという意味合いもある。もちろん全部を背負う必要はないけれど、一緒に暮らすということは、相手の過去の恋人や家族の事情を引き受けるということだと思います。
──タイトルにあるように「やめるときも、すこやかなるときも」生活は続くわけですね。
結婚生活に「すこやかなるとき」だけをイメージする人が多いけれど、実際のところそこは半々。「やめる」ほどではないにしろ、人間は大なり小なり負の部分を抱えているものだよ、ということは言いたかったですね。
──壱晴は桜子に心理面でも仕事面でも風穴をあけてくれることを期待していて、一方の桜子は壱晴に、今の自分や生活を変えてくれることを期待していた。純粋な好意だけではなく、〝不純〟なものが入っているのも恋愛とわかっているところが、リアルな三十二歳という印象です。
そういった正直な気持ち、綺麗ごとだけではないゴツゴツした部分がぶつかりあうのが恋愛であり結婚だと思います。そもそも人間同士は、生身でぶつかっていかないと化学変化みたいなものは起きないんじゃないでしょうか。そうじゃない関係もあるのかもしれませんが、私はわりとガチでぶつかりたいタイプなので、相手にもガチで全部見せて下さいよと思ってしまうんです(笑)。
──特に最初の頃の桜子は悲観的で、妄想ばかり膨らませています。彼女は窪さんが気になる女性像のひとつなのでしょうか。
桜子はひとりで稽古ばかりしていて、土俵にあがらないタイプの女性です。私の周りを見ても、頭の中だけで考えてわかった気になって、あきらめてしまう人が多い気がします。今はネットで相手のことを調べられるので、不安の種を見つけては心配したり。恋愛が大変な時代になって、しんどそうだなとは思うけれど、さっきも言ったように、生身でぶつからないと化学変化は起きないはず。ネットでいろいろ調べてばかりいるのは、無駄なエネルギーかもしれないですね。
──壱晴とは「貝のむき身みたいな自分をさらして向き合ってきた」桜子ですが、ひとたび「社会で働いている人」という仮面をつければ生々しい部分を容易に隠すこともでき、そんな自分にかすかに失望します。働く人なら共感できる心情だと思いました。
恋愛のまっただなかにいる女性が、前の晩にすごくつらいことがあっても、翌日はしゃきっと仕事に行く。そんな仮面のつけ方が、不思議に感じるときがあるんです。私は今、会社に行かない生活をしているので、よけいにそう感じるのかもしれません。ただ仮面をつけても、隙を見せまいとしても、どうしようもなく取り乱すときやボロボロこぼれ落ちる感情はある。でもそれは社会人としてダメなこととは言い切れなくて、その人らしさが垣間見える瞬間ではないでしょうか。人が感情を揺さぶられたり、魅力を感じたりするのは、むしろそういうときだと思います。
──先ほどおっしゃった「生身でぶつかって生まれる化学変化」にもつながる気がします。
そうですね。だから、未完成なままぶつかっていいんです。仮に完璧な自分が出来上がったとして、そこで恋愛のバッターボックスに立っても、相手はそういう人にひかれるかな?と思うんです。桜子は今まで「付き合う人には隠しておきたい」と思っていた家族の素顔を、壱晴には最初にさらけ出したいと考えましたが、現実の恋愛でも隠さないほうがいいんじゃないかな。「あなたの負の部分をちょっと背負うから、私の負の部分もちょっと背負ってね」という気持ちが、ひいては結婚につながると思います。
──まずはお互いに「生身を見せたい、話したい」という気持ちになることが大事ということでしょうか。
「この人に話してみたい」というちょっとした興味が人と人の距離を近くすることは多々あるし、自分の中では悲しみだった出来事が、誰かに話したらおかしみに変わることもあります。心の重しがとれて軽くなったり。私が思うに、人間にとって一番つらいのは「これを失ったり、ここからはずれたりしたら生きていけない」と切羽詰まること。でも世の中にはいろいろな人がいるし、いろいろな生き方があります。考え方をたくさんストックして多様性を認められれば、つらいことがあっても、また前を向けるのではないでしょうか。
──「これしかない」と思い詰めると自分を苦しめてしまいますね。
そうですね。だからいろいろな生き方、考え方を知る必要があって、そのためにも「生身を見せていこうよ」と言いたいですね。具体的に言えば、気軽に人を家に招くとか。特に結婚するなら、自分や住んでいる部屋の見せたいところだけ見せるのは難しい(笑)。最近はインスタグラムにインテリア雑誌に出てくるような素晴らしい部屋の写真をあげる人が目立つので、ハードルが上がったように感じるかもしれないけれど、そもそも「家」と「人」はすごく近いもの。あまり身構えないほうがいいと思います。
──壱晴と桜子の歩みはこれからもふたりらしいものになっていきそうな予感がしましたが、書き終えて気づいたことはありましたか。
やさしさ成分が多い作品になったかなと思っています。デビュー作から、激しく人の心を揺さぶるものを多く書いてきましたが、今回は、ちょっと違うものになったな、と。読者の方に「行間を読んで下さい」と突き放すことをせずに、登場人物のやりとりや心の動きを丁寧に拾って書いたからかもしれません。扱っているテーマは決して軽くはありませんが、読み口がやさしいので、効き目がある薬をシュガーコーティングした糖衣錠(とういじょう)のような小説になった気がしています。