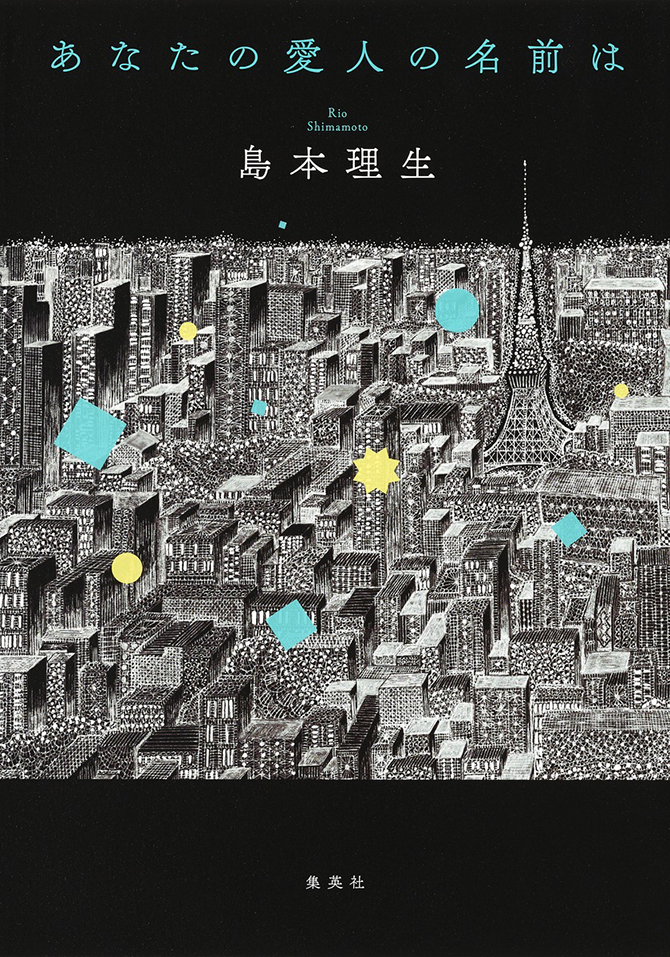- 『あなたの愛人の名前は』島本理生 著
- 発売中・単行本
本体1,500円+税

人間の奥行を美しく描く
島本理生×米澤穂信 対談
2018年12月にそれぞれの新刊『あなたの愛人の名前は』(島本)、『本と鍵の季節』(米澤)が発売された大人気作家二人の対談が実現。
同じ年にデビューしたお二人は、活躍する場が違うけれど、清潔な世界観や登場人物への優しいまなざしで読者を魅了し続けている。
今回の語らいで、ジャンルが違うからこその創作の秘密が垣間見え……。
聞き手・構成=タカザワケンジ/撮影=露木聡子
「時間をかけてできた作品」
──お二人は今日が初対面だそうですね。今回、新刊が同日発売されるということですが、お互いの作品の感想からお話を伺いたいと思います。
- 島本
-
どんどん引き込まれて、あっという間に読んでしまったんですけど、意外とボリュームがあるんですね。長い間連載されてたんですか。
- 米澤
-
最初の短篇を書いたのはもう七年ぐらい前になります。アンソロジー企画に寄せたものが最初で、シリーズ化しようという意図はなかったんですが、当時の編集部の方々が登場人物たちを気に入ってくださいまして、「彼らの話をもっと読みたい」と言われました。続くとは考えてなかったものですから、少し面食らいました。島本さんは今回の作品はどのように書かれたんですか?
- 島本
-
私も始まりはけっこう前で、最初の短篇を書いたのは八年ぐらい前です。産休に入っていてちょっと時間があったんですよね。それで、純文学の文芸誌に載せるつもりでストックしてあったんです。二、三本目ぐらいまではどこに発表するとも決めないで書いて持っていました。
- 米澤
-
そういうことをときどきされるとエッセイかインタビューで拝読していたんですけれど、これがまさにそうだったんですね。
- 島本
-
そうですね。依頼されてからだと熟成してから出すことができないので、短いものはいくつかストックがあります。
- 米澤
-
三、四十枚の作品のストックがぽろっとできたりすることは、自分もあるんですが、それが二篇、三篇とあるのはすごいですね。書きたくて仕方がない時期があるってことですか。
- 島本
-
そうですね。特に長篇を書いていると、短篇がすごく書きたくなります。そういうことってありますか。
- 米澤
-
ありますね。あまり名誉な話ではないですけれども、手がけていた長篇が行き詰まるというか、迷走ぎみになってしまってなかなか仕上がらない。どうしようかって思ったときに、他愛ない話を──他愛ないといっても手を抜いているわけではないんですけれども──ぽろっと書いて、載せていただいたりします。
- 島本
-
プロットは最初からしっかり立てられるんですか。
- 米澤
-
ミステリなので、個々のお話に関してはきっちりつくり込んで、穴がないように検討しながら進めます。一冊の本としてのプロットに関しては、書きながらつくっていった部分も大きいですね。島本さんも八年、長い期間にわたって書かれてますが、並びは時系列ですか。
- 島本
-
そうですね、ほぼ時系列です。
- 米澤
-
単行本にするにあたってシャッフルしようとか、組みかえようとは思われませんでしたか。
- 島本
-
並びかえてみたんですけど、登場人物を出すタイミングが時系列と関係していたりして、変えないほうがいいっていう結論になりました。
- 米澤
-
やっぱり並び順をお考えになるんですね。私はよく、短冊状に切った紙にタイトルを書いて、どういう順番で並べるのが一番いいか、最適な並びを模索するんです。でも、結局時系列が一番すっきりすることが多いですね。
- 島本
-
そうなんですよね。やっぱり登場人物の心情やストーリーの変化が一番自然かな、と。
- 米澤
-
今回の『あなたの愛人の名前は』に収録されている短篇はどれも苛烈さがあると思うんですが、最初のほうの作品と最後のほうの作品ではタイプの違う苛烈さがあると思いました。うまく言葉にできないけれども。それは書いてる時期の反映だと思われますか。
- 島本
-
書いてる時期の反映だと思います。それに最初のほうの短篇は、純文学として発表しようと思っていたことも関係があると思います。私はもともと『群像』の出身なんですが、純文学って、ある種はっきりと書き過ぎてはいけないようなところがあって、必ずしも明確なオチをつけるものではないんですよね。それが後半になるにつれて、もう少し具体的に書こうというふうに変わっていきました。あとは一冊の本として構成する段階に来て、わかりづらいからもう少しここをクリアにできないかという編集者からの指摘が入ってきたりしたり。ジャンルを跨いだことで文体も微妙に変化していると思います。
- 米澤
-
なるほど、おもしろいですね。私も今回は長い間にわたって書いたものですが、読みやすさの差みたいなものを感じられましたか。
- 島本
-
いえ、さっきそれを伺ってびっくりしたんです。というのも全体の作品のトーンが丁寧に統一されていて、後半に行くにしたがって謎解きへと期待が高まっていくと同時に、語り手が親友の内面に言及してくる。物語の盛り上がりと、友達との関係が深まっていくプロセスがシンクロする構成がとても綺麗で見事だと感じたんです。てっきり考えてから書き始められたと思っていたので、最初は連作にするつもりがなかったんだと驚きました。全体を通して大きい謎と、各章の細かい謎がありますが、それぞれ個別に考えるんですか。それとも同時進行で脳の中にあるんでしょうか。
- 米澤
-
初出は雑誌なので、個々の短篇が独立して読めるというのがマストです。それにミステリなので一話で一つの謎を解いて完結したい。かつ少しずつ彼らのテンションが変わっていくという変化を出していければなとは思っていました。
- 島本
-
そのテンションは、書きながら自然に変わっていくものなんですか。
- 米澤
-
毎回書くときに、これまで書いてきた蓄積を読み返して、ああそうか、彼らはこういう人だったという気づきを自分の中に呼び込んでくるような感じはありました。
- 島本
-
私、「ロックオンロッカー」で次郎くんと詩門くんの二人で美容院に行く場面がとても好きでした。高校生の男の子たちの初々しさがすごく出ていて、自分が高校時代に初めて一人で美容室に行ったときのことを思い出したんですけど、そういう感覚って大人になってしまうと忘れてしまう。米澤さんが青春ミステリを書き続けられるのは、その頃の感覚をずっと覚えてらっしゃるのか、それとも意識して思い出されているんですか。
- 米澤
-
残念なことではありますが、学生時代に持っていたひりつきとか焦りはやっぱり消えていくものだと思っています。だから、二十代から三十代にかけて、今のうちに書けるものをと思って青春ミステリを書いた覚えがあります。今回、久しぶりにシリーズ以外の青春ミステリを書いたんですけれども、登場人物の一人に関しては、思春期そのものを生きるというよりは、少し冷めた視線で、一足先にちょっと大人になっているように描ければいいかな、と思っていました。

- 島本理生(しまもと・りお) '83年生まれ。'01年『シルエット』で群像新人文学賞優秀作を、'03年『リトル・バイ・リトル』で野間文芸新人賞を、'15年『RED』で島清恋愛文学賞を、'18年『ファーストラヴ』で直木賞を受賞。『アンダスタンド・メイビー』(上・下)『よだかの片思い』『夏の断裁』『イノセント』『わたしたちは銀のフォークと薬を手にして』など著書多数。
「旅で小説のアンテナを張る」
- 島本
-
取材はよくされるんですか。
- 米澤
-
するものとしないものとに分かれますね。今回はしていません。島本さんはどうですか?
- 島本
-
今回はあまりしてないです。長篇のときには職業取材をメインにかなりやりますけど、今回はどちらかというと、自分が想像して自由に書こうという思いがあったので。短篇って、厳密に整合性がとれていなくてもいいというか、むしろちょっと想像力で遊ぶっていうのも楽しいかなって。
- 米澤
-
わかります。表題作の舞台になっているマカオには行かれたのかなと思ったんですが。
- 島本
-
あ、マカオに行きました。
- 米澤
-
行きましたか。体調崩しませんでしたか。小説では主人公が調子を悪くしていましたね。
- 島本
-
ほぼあのままです(笑)。
- 米澤
-
そうでしたか(笑)。もしかしたら島本さんの体験かなと思ったんです。だって、お茶だけがまずくて、ワンタン麺がすごく美味しいってなかなか想像だけで書けないんじゃないかと。
- 島本
-
私の小説は若い女性の読者が多いので、リアルな初めての女子海外一人旅の物語として読んでもらうのもいいかなと思いまして。お茶がまずくてワンタン麺の美味しいお店は本当にありました。小説のとおりに一人で行って、具合が悪くなって、現地の鼻炎薬を吸引しながら、何とか旅しました。
- 米澤
-
それはお疲れさまでした。『ファーストラヴ』に登場する富山も行かれたのかなとか思っていたので、マカオもそうかなと。
- 島本
-
富山も実際に行って、雪山を歩き回り、ふらふらになったりしましたね。基本的に、その土地を書くときにはいつも一人で取材に行くんです。ふだんの旅行でも、新しい小説のネタがないかなって探してますね。
- 米澤
-
わかります。私もどこかに行くときは何かないかなってアンテナを張っています。
- 島本
-
ですよね。家族旅行のときぐらいですかね、張っていないのは。逆にそういうときは読書しようと決めていて、この前の家族旅行には米澤さんの『王とサーカス』を持っていきました。夫と子どもが温泉に入ってる間に読んで幸せを感じました。
- 米澤
-
ありがとうございます。
- 島本
-
米澤さんの本を初めて読んだのは『満願』でした。その頃、エンターテインメントに専念しようと思っていたこともあって、ミステリ短篇ってこう書くのか、と勉強させていただきました。
- 米澤
-
おそれ多いことでございます。恐縮です。
- 島本
-
『満願』の中では、個人的には「万灯」がすごく好きです。冒頭の伏線が、最後に予想を裏切りながら完璧に回収される。どうやって思いついたんだろう、と思いました。はじめに犯人がわかっているのに、予想を裏切る仕掛けって高度で書き手としても憧れます。
- 米澤
-
今回のご著書の最初の一篇「足跡」を拝読して、これは今おっしゃった、最初に犯人が登場するミステリのつくりかな、と思ったんですが。ミステリの人間って悪い癖があって、何もかもミステリの構成に合わせて考えてしまう。自分のものさしを何にでも当てるんじゃありませんって言われそうで、いいことじゃないですけれど。
「足跡」は最初の強烈な一言から始まって、幸せな家庭が描かれて、そこからふっと、一歩踏み出してしまう。そこの部分、家庭の不信から行為に行くところに、何か落差というか、差があるように思える。でもその差をあえて説明していないんですよね。だから、外から見れば幸せな家庭で暮らしていて、ふっとそういう行為に走ったように見えるけれど、先に進むうちに少しずつその理由がほのめかされていく。ミステリでいう最初の殺人があって、一体この殺人はどういうことだったのかという謎を、あとから追っていくタイプだなと思ったんです。的外れだったらすみません。
- 島本
-
いえいえ。おもしろいです。自分にはまったくない視点でした。昔からミステリ小説が好きでよく読んではいたんです。憧れはあったんですが、自分に物理トリックは考えられないと諦めていました。でも、女性の心理ってある意味でミステリなんじゃないかと思ったときがあって、女性心理の複雑さを題材にすることで謎めいた小説を書けるんじゃないかな、と。
- 米澤
-
主人公の女性が自分の気持ちを踏み止める場面が印象的でしたね……。あっ、これは小説の美味しいところだから。やめておきましょう。
- 島本
-
雪がキーワードになって。
- 米澤
-
あそこが素敵だったと言おうと思ったんですけど、でもこれは読んでもらったほうがいいと思うので黙っておきます(笑)。

- 米澤穂信(よねざわ・ほのぶ) '78年生まれ。書店員として勤務していた'01年、『氷菓』で角川学園小説大賞ヤングミステリー&ホラー部門奨励賞を受賞しデビュー。'11年『折れた竜骨』で日本推理作家協会賞を、'14年『満願』で山本周五郎賞を受賞。『リカーシブル』『いまさら翼といわれても』『真実の10メートル手前』『王とサーカス』など著書多数。
「人間の複雑さや奥行き」
- 島本
-
北村薫さんが好きだったと何かの記事で拝見したんですが、やっぱりミステリを一番よく読まれていたんですか。
- 米澤
-
そうですね。ほかのジャンルも読んでいたんですが、北村薫先生の作品を読んで、ミステリを書こうと思いました。
- 島本
-
私も学生のときに本好きの女友達から勧められて、北村薫さんの作品を読んでいました。ああいうやわらかい感じの文章をお書きになるミステリ作家の方はあまりいなかったので印象的でした。米澤さんの作品を拝読していると、本への愛があふれているってすごく感じます。最初の作品がのちに〈古典部〉シリーズとなっていき、今回も高校の図書室が舞台。この質問はたぶんみなさんから聞かれていると思うんですが、高校生の頃、図書室に通ってらっしゃったんですか。
- 米澤
-
いや、じつは高校時代は部活をやってまして、それほど図書室には通っていなかったんです。本好きということでは、たぶん島本さんのほうがはるかに本好きではないかと。
- 島本
-
そうなんですか。図書室の本のラベリングとか、ディテールをたくさん書かれているので、てっきり本へのこだわりが学生時代からすごくお強かったのかなと。
- 米澤
-
もちろん小説は好きで読んでいましたが、図書委員ではなく弓道部の部員でした。
- 島本
-
弓道ですか。そういえばデビュー作の『氷菓』でも最後に弓道部が出てきますね。
- 米澤
-
最後にほんとにちょこっとだけ。あれは自分がやっていたからですね。お恥ずかしい。
- 島本
-
『本と鍵の季節』は終わり方も好きでした。作者がコントロールしすぎないというか、余韻と先の展開を残していくような終わり方で。ラストだけは決めていたとか?
- 米澤
-
おぼろげには。二人がものすごく気が合っていて、何もかもわかり合っているかのような関係から始まって、だんだんと自分が思うほどわかり合っているかな? と疑問が湧いてくる。わかり合っていると思っていたのは、あくまで学校という小空間の中だけで、じつはほんの部分集合でしかなかったっていうのが見えてくるようにはしたいなと思っていましたが。
- 島本
-
近付いていくほどかえって分からない部分が増えていく感じがものすごくリアルでした。それって男女でも言えることですし、女同士でも言えることかもしれない。
- 米澤
-
私が思う友情をラストでは少し描けたんじゃないかと思います。
- 島本
-
その結論はぜひ小説を読んでいただきたいですね。米澤さんの作品って、いろいろな仕掛けに引き込まれながらも、謎やトリックだけに重点を置くのではなく、人間の複雑さや奥行きが子細に描かれている印象を受けます。にもかかわらず、すごくやわらかいというか、距離感が心地よい。ガンと強く来過ぎない感じがすごく絶妙で。
- 米澤
-
そこは意識しているかもしれませんね。島本さんの小説にこそいつもギクリとするような、鋭いところがあります。そう考えると、意識するしないよりも作家の質なんでしょうね。たぶん、私がグサリと鋭いものをやろうと思っても、何かを真似したようなものになってしまうのかもしれません。
島本さんは、今回は全体の構成をいつ決められたんですか。連作短篇ですよね。
- 島本
-
書いてる途中から連作になりました。
- 米澤
-
登場人物が少しずつ重なっているんですよね。だからこれ、同じ街にいるんだろうなと思って。ホテルが二、三軒しかない、あまり大きくない街なのかな、と。
- 島本
-
はい。都会の真ん中というよりは、郊外か、郊外の中の大きい街の近くっていうイメージでしたね。中央線の中でも、武蔵境とか、立川あたりから、都心に近い中野ぐらいまでのイメージが混ざっています。じつは実際にあるお店や場所がかなり登場しているんですけど。「氷の夜に」の小さな和食のお店とか。
「文化圏が重なっていない」
- 米澤
-
「氷の夜に」で男の人が女の人に「おい、絵未ちゃんだろ」って軽々しく声かける場面がありますよね。女性が青ざめているのを見て、主人が雨の中に男性客を追い出す。あのときの追い出す手際があざやかで、このご主人、あたりはやわらかいけれども、じつはいろんなお客さんにつき合ってきたなっていうのがわかって印象的でした。
- 島本
-
ありがとうございます。今、ちょうど長篇の連載をしているんですけど、じつはそのために飲食店の取材を続けているんです。お店の方にお話を伺うと、一人でお店やってらっしゃる方ってかなり下積みしてるんですよね。厳しい修業してたりとか。あと、大きいお店で働いてると、それこそたちの悪いお客さんがいっぱい来るそうで、みなさん意外と厳しい世界でもまれているなって。
- 米澤
-
よく取材されているんですね。
- 島本
-
なるべくリアリティが出るようにと思って、取材をしたりすることが多いですね。
- 米澤
-
本当にありそうなやり取りでした。「あなたは知らない」でも……どうしよう。あまり小説の内容は、話し過ぎてもいけないと思って。
- 島本
-
ありがとうございます。ネタバレを気にしてくださって。
- 米澤
-
ミステリでは何より重要なことなので(笑)。ネタバレにならないようにしますが、「あなたは知らない」は、主人公の女性に、この婚約者とはたぶん合わないからやめたほうがいいよ、と言ってあげたい気持ちで読んでいました。彼とは文化圏が重なっていない。仮にこのあと一緒になったとしても大変だなと思っていたんですよ。
- 島本
-
今おっしゃった、文化圏が重なっていないっていうの、すごく的確な表現だなと思いました(笑)。先日、テレビ番組で作家の羽田圭介くんと中村文則さんとお話をしていたときに、女の前でだけ現れる男のひどさがどうやらあるっていう話になったんです。女性作家の小説を読むと、いくら何でもこんなひどいことを言う男性はいないって思うらしいんですけど、女性に「こんな男いないよね」って言うと「いっぱいいるよ」と言い返されるって言うんですよ。きっと男性同士のときには登場しない、女性の前にだけ現れる男性の顔っていうのがあるんじゃないか、と。
- 米澤
-
そうかもしれませんね。そういう多面性をとらえているところが島本さんの小説のおもしろさですよね。この婚約者の、耕史くんですか。少しだけ気の毒だったのが、サッカーが文化圏の断絶の象徴のように描かれていること。サッカーしてもいいじゃないですか、っていう(笑)。主人公の瞳さんは美術部で高校時代は対象的なポジションにいたってことなんですけど。いわゆるスクールカーストですよね。
- 島本
-
言葉には出さないけれど、女性も社会に出た後も昔のポジションを引きずっていることがあるんですよね。特にその短篇は、学生時代の、ちょっとうしろに下がっていた自分っていうものがまだ残っている女性というイメージだったので。そういう女性たちの中で、敵視すべき部活はサッカー部だという印象があって。
- 米澤
-
野球よりもサッカーなんですか。
- 島本
-
野球部よりもサッカー部です(笑)。とにかくサッカー部の子たちは、自分とは口を利かない人種だっていうイメージがありました。
- 米澤
-
それは気づかなかったですね。語り手の瞳さんは体育会系文化圏で育った男性の行動そのものになじめてないとはすごく感じましたが。そこで大丈夫かな、この二人って思ったんですけど、そこまでサッカーそのものを敵視してるとは思わなかったです(笑)。
- 島本
-
サッカー部の人とは絶対つき合えない、みたいな刷り込みが文系の女性の中には少なからずあると思います。なのでサッカーボールを意図的に登場させました。
- 米澤
-
なるほど(笑)。今にもサッカーを始めそうなやつら、みたいな書き方をされていますね。たしかに、彼らが学生時代を引きずってる感がよくわかりますよね。
- 島本
-
リアルにより過ぎず、でも、たぶんどこかにはこういう人がいるんだろうなみたいなものを、織りまぜて書けたらなと思いました。
- 米澤
-
二人が重なり切ってない。重なり切らないところのもどかしさとか、重なり切ってないから安心できない感じとか、あるいは、最初はあたりがやわらかいとしても、もっと重なってしまったら、暴力的なところも出てくるんじゃないかっていうことを感じました。「足跡」の二人の距離感も、心を分かち合うみたいな関係ではないですから。そこのところが距離感を生んでるのかな、と思いながら拝読いたしました。
- 島本
-
『本と鍵の季節』では、次郎くんと詩門くんの距離感がいいなってすごく思いました。女性には究極、男の子同士の友情ってなかなかわからないところもあるので、小説で覗き見るのは楽しいですね。米澤さんは、男の子同士の距離感とか友情ってどうお考えですか。
- 米澤
-
今回に関しては、学校の外で会うかどうかが微妙な距離感、みたいな感じでは考えていました。もともと自分も、「俺たち仲間だよな」的なべたべたした価値観があまり得意なほうではなくて。いや、そういう人がいるのは全然かまわないし、それが嫌だというわけでもないんですけど、それは自分が書かなくてもいいかなとは思っています。
- 島本
-
次郎くんが、詩門くんの事情がわかったときに交わした、シャツに関する会話がすごく印象的でした。世の中でこう思われがちだなってことにさっと異議を申し立てる。小説を書いているとき、多様な目で人を見ようと心がけている自分でさえ、一瞬、次郎くんのように思ってしまうことがあるなと思って。ここのセリフ、刺さりました。
- 米澤
-
ありがとうございます。
- 島本
-
こういう視点を、大人はもちろんですけど、十代の子たちが小説に出合うことで持ってくれたら、人間関係ってもっといいものになると思うんです。
「心の動きとチェックポイント」
──お二人の作品に共通してるのは、人が持つ弱さへのやわらかな視線だと思います。本を通して、傷ついてる子たちを救いたいという気持ちがあるのではないかと。いかがですか。
- 米澤
-
小説で何かを救いたいって思ったことはあまりないんです。小説は小説、スタンドアローンなものだと思っています。結果として、読んだ人が自分の中にある何かを再発見するということはあるかもしれません。ですが、それを目指して書いてはいないですね。手元の自分の小説を完成させるので精いっぱいで、受け取り手がそれをどう受け取るかまでは考えられない。「あとは任せた」という感じです。
- 島本
-
私は米澤さんとは逆に、小説は人を救うためのものであってほしいというのが十代のときから思っていることですね。すべての小説でそうあるべきだと思っているわけではなくて、自分が書くものはそうであってほしい。その思いがすごく強かったので、シリアスなテーマを扱いがちだったんです。でも、最近、「あ、おもしろがらせるってこと忘れてた」ということに気づきました。人を救う前にまずおもしろく読めないと、ということに気づき、最近はバランスを考えるようにしています。一つのテーマを追ってると視野が狭くなっちゃうんですよね。
- 米澤
-
書いてる最中に読者のこと考えますか。
- 島本
-
書いてる最中に……考えるかもしれないです。
- 米澤
-
そうですか。この小説をこういう人が読むんだっていう。
- 島本
-
ありますね。強くあります。
- 米澤
-
おもしろいですね。私は書いてる最中は、この小説よ、自分が思うような形で完成してくれ、と願うだけで、読者はいったん忘れる感じです。書く前にはこういう読者に読んでもらえればいいなって思うし、書いたあとはこういう読者に届きますようにと思うのですが。
- 島本
-
書いてる最中は楽しいですか。
- 米澤
-
あまり楽しくないです。
- 島本
-
そうなんですね。私は人が読んだらお腹痛くなりそうな話を書きつつも、意外と楽しんでます(笑)。ノッて書いているときは意外と内容のシリアスさは関係ないというか。
- 米澤
-
(笑)。私があまり楽しくないというのは、ミステリだから──と言ってしまうとちょっと卑怯かもしれませんけれども、ミステリってチェックポイントが多いんですよね。ここを通過させないと、ミステリが成り立たないという点がある。でも、書いてるうちに、登場人物の心が揺れ動くじゃないですか。この揺れ動き方だと、このチェックポイントを通過しないみたいなことが起こる。
- 島本
-
ああ、ありますね。
- 米澤
-
今、この子たちはこんなことをする気分じゃないよね、というときでもその流れに任せられないときがある。かといって、彼らの心を無視して、まるっきりこちらでコントロールしてしまうと、作者が頭だけでつくったようなものになってしまい、おもしろくない。小説であるためには、自分ではなくて、彼らがどう考えるのか、彼らがどうものを見るのかを書いていかなきゃいけないなと思いながら、でも、君たち自由にしてもらっては困るんだよ。このチェックポイントは通ってもらわないと、っていうジレンマ。ここで君はこの引き出しを開けるんだよっていう。
- 島本
-
そこはどうやって折り合いをつけるんですか。
- 米澤
-
大変です。楽しくは書けないですね。『ファーストラヴ』はすごくチェックポイントが多いですよね。
- 島本
-
多かったですね。そういうときは、私の場合、謎のほうを変えてしまいます。裁判の場面で、ああ、一から調べ直しだ、みたいなことがありました。
- 米澤
-
それはすごい! 『ファーストラヴ』で弁護士の迦葉が、獄中から被告人の環菜が出した手紙を、環菜の元カレから引き上げますよね。どうやって手紙を渡してもらおうかと悩まれませんでしたか? というのは、獄中からの手紙を弁護士に渡すって、あの男性にとってはハードルが高いことなので。それを自然にそうなるように書かれていたので、すばらしい動機づけだなと思ったんです。
- 島本
-
あれはたしか、手紙が迦葉の手に渡るという案が先にあったわけではなく、そろそろこの女の子、昔の彼氏に手紙を出すんだろうな、というのが先でしたね。そしたらたぶん、また一時的に復縁して、迦葉への不満もたまってる時期だろうから、火の粉が飛んでいく。その展開で考えていった結果ああなったんです。
- 米澤
-
面白いです。登場人物の心理の流れが先にあるんですね。
- 島本
-
あの小説は結局、環菜の心理が一番の肝だったので、そのつじつまを合わせるためには裁判の流れも変える、ほかの登場人物たちの流れも変えるということをやってました。
米澤さんはチェックポイントを設ける一方で、登場人物の心の動きにも意識的に気を配ってらっしゃるんですね。だから米澤さんの小説の登場人物って、内面や心が感じられるんだなって思いました。
- 米澤
-
自分の話をするのはまことに恐縮なんですけど、犯人の側も考えてやってるんだっていうところはあって。犯人の心の動きがおかしいと、トリックだけが浮くんですよね。この犯人、こんなトリック仕掛けないだろうって話になってしまって。だから、犯人の心の動きが自然じゃないと、小説部分と謎の部分が分離しちゃうのかなって思います。
- 島本
-
それを伺って、もう一つすごく心に残った会話があったのを思い出しました。その中で「(ルールは)いつか守れなくなる。だったらせめて守れるうちは守りたい」という言葉が出てきて、これが作品の一番の本質なんじゃないかと個人的には思ったんです。『王とサーカス』にもどこか共通するような、矛盾だったり、両面性をはらんだ世の中で、自分はなにを選択し信じるかという問いかけを与えられたようでした。
- 米澤
-
いつか破綻が見えてくるとしても、それは今信じない理由にはならないっていうのは、あるかもしれません。読み込んでくださって嬉しいです。
- 島本
-
それが小説の美しさだったりするのかなと思いました。
『本と鍵の季節』を読んで、構成力ももちろんのこと、読んでる方が純粋に「楽しい」と思えるような物語づくりをもっと学ばなければ、と思いました。楽しませる読書が読書の本質なんじゃないか。自分がまだ学生で、純粋に本を読んでいたときのことを思い出しました。一冊の本に出合ってわくわくしたときの感覚を。そういう小説を自分も頑張って書きたいなと思います。
- 米澤
-
今日、島本さんとお話をさせていただいて、自分の小説でも登場人物の距離感をもうちょっといじってもいいかもしれないなと思いました。作家それぞれに登場人物の距離感、間合いのようなものがあると思うんですが、もう少し意識的に遠ざけてみるとか、もう少し意識的に近づけてみるとか、ずっと考え続ける。そのあたりに、小説をおもしろくしていく方法が隠されているのかもしれないと思いました。