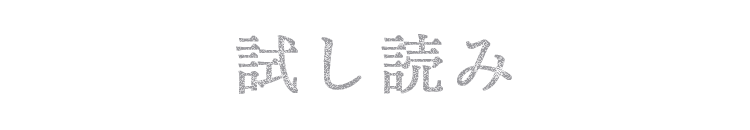
913
- 1
-
図書室は寂しくなった。
三年生の図書委員は互いに顔見知りで仲がよく、放課後になると図書室は図書委員会の遊び場になっていた。他愛ない雑談やちょっとしたゲームでいつも盛り上がり、閉室まで笑い声が途絶えることはなく、それだけに六月に入って受験準備のため先輩たちが委員会を退くと図書室は火が消えたようになってしまった。
なまじそれまで賑わっていたので、残された一、二年生は気が抜けたのか、当番でもなければ図書室に寄りつかない委員が増えた。その当番ですら、誰かに肩代わりさせることがはやっている。つまらなくなったと嘆く声も聞いたけれど、僕はそう思わない。いまのように静かな図書室も居心地がいい、というか、いくら利用者がいないからって図書委員が図書室でわいわい騒いでいたのは、やっぱりどこかおかしかったのだ。
-

-
その日、図書当番は僕と松倉詩門の二人組で、図書室にほかの生徒の姿はなかった。利用者皆無なのに二人も詰めるのは無駄だろうけれど、松倉が相手なら時間はつぶせる。静まりかえっている図書室を貸出カウンターの内側から眺めながら、僕は言った。
「図書委員会が好き放題したから誰も来なくなったのか、誰も来ないから図書委員会が好き放題したのか。どっちだと思う」
松倉はあくびをしていた。遠慮のない大あくびを途中で止めようともせず、最後まで遂げてから涙の浮かんだ目を僕に向ける。
「どっちでもいい。俺たちは別に、利用者数に責任を負ってない」
それもそうだと思ったので、僕はなにも言わなかった。
松倉とは今年の四月に、委員会の第一回会議で知り合った。もちろん、それまでも見かけたことはあった。背が高く顔もいい松倉は目立つ存在で、廊下ですれ違ってもなんとなく印象に残る。見るからに運動が得意で本には縁がなさそうなので、委員会で会ったときには内心驚いた。
話してみるといいやつだった。快活でよく笑う一方、ほどよく皮肉屋だ。運動部には入っていないが、子供の頃はスイミングスクールに通っていて、そこそこ成績もよかったらしい。これが同じ高校二年生かと思うほど分別くさいことを言うかと思うと、意外に間が抜けたところもある。図書室が遊び場だった頃、お付き合い程度に愛想笑いはしても自分から騒ぐことはしないという彼の立ち位置に共感して、よく話すようになった。
松倉が図書返却箱に手を伸ばす。返却された本はいちおう下校時刻までに書架に戻しておくことになっているが、まだ時間があるせいか、その手の動きは緩慢だ。返却箱は空のことも多いけれど、今日は三冊ほど入っていた。一番上の一冊を手に取って、松倉は不意に苦笑いする。横から覗くと、ダン・シモンズの『ハイペリオン』だった。僕は読んでないし、松倉は翻訳物が苦手だったはずだから、やっぱり読んでいないだろう。それでも僕には苦笑いの理由がよくわかる。案の定、松倉は言った。
「やっぱりシモンはないな」
僕も、いつものように答える。
「そうかな。なくもないと思うけど」
松倉詩門は自分の名前が嫌いだ。「詩門」は恥ずかしいと思っている。けれど僕はもっとすごい名前のやつを知っていたので、そのぐらいならたいしておかしいとも思っていない。もっとも松倉はこの問題に関しては、僕に同意を求めているのではない。
「シモンはどう見てもキリスト教だろ。俺はクリスチャンじゃないし、失礼だ」
「そうか?」
「大人になったら改名する」
「前にも聞いたよ」
「何度でも言うぞ」
松倉の決意は固い。でも別の言い方をすれば、松倉は大人になるまでは改名しないと決めていることになる。その理由も前に聞いた。親の付けた名前に付き合うのも、浮き世の義理だと思っているのだ。
会話の端々から、松倉の父親はもう亡くなっているのではと思うことがある。彼が詩門という名前を我慢するのは、親への義理立てじゃないのか。本人に確かめたことはないし、これからも訊くことはないだろう。
松倉ほどではないけれど、僕も自分の名前はあまり気に入っていない。堀川次郎。次男だから次郎。変に捻られるよりはありがたいけれど、もう一工夫欲しいところだった。
『ハイペリオン』をカウンターに置いて、松倉が返却箱から出した二冊目は『新明解国語辞典』だった。辞書は禁帯出だ。図書室内で自習に使い、戻す棚がわからなくなったか、自分で戻すのが面倒になったのだろう。
そして、残った三冊目がひどかった。
ブックコートフィルムも貼られていない、古い文庫本だ。岩波文庫から出ている志賀直哉で、『小僧の神様 他十篇』。手に取った松倉がたちまち顔をしかめる。
「ひどいな」
表紙は真ん中あたりで折れ曲がり、全体的に乾いた泥で汚れている。
「どうしたらこうなるんだ」
松倉がそう言うので、適当に思いついたことを言ってみる。
「読みながら泥沼に突っ込んだんじゃないか」
「ダイナミックな読書だな。いい趣味だ」
「いい趣味か? 図書室の本を汚して返してくるなんて」
「そうだな。けしからん」
僕たちは言葉ほどには怒っていなかった。どちらも多少は本を読むけれど、ものとしての本を神格化するには愛が足りていないのだ。持ち歩いていれば汚れることもあるし、破れることもあるだろう。入手が難しい本ではなかったのは不幸中の幸いだ。
松倉がぱらぱらとページをめくって、中の状態を確認する。
「どうだ?」
と訊く。
「まだ読めるな」
「拭いてみた方がいいか」
「それもそうだが、もうひとつ」
松倉が見せてきた本の背表紙は、著者名の下が無惨な擦り傷になっていて、背ラベルまで剝がれてしまっていた。
「結構重傷だな。もう除籍した方がいいんじゃないか」
そう言うと、松倉は面倒そうに眉を寄せた。
「俺たちが決めることじゃない。あとで、どうして勝手に捨てたのかなんて言われるのは嫌だぞ」
「それもそうだな」
「とりあえず直そうぜ」
松倉はスポーツも勉強も出来るが、手先はちょっと驚くほど不器用だ。「俺がやると破りそうだ」と尻込みするので、補修は僕がやることにする。
泥汚れは水拭きしたいところだけれど、ものが紙だけにごしごし擦るわけにもいかない。ウェットティッシュが欲しかったけれど、図書室の貸出カウンターにそんなものは用意していないので、トイレでティッシュを濡らして固く絞り、汚れが落ちるか撫でてみた。
一通り撫でて、乾いたティッシュで乾拭きし、出来映えを眺める。
「あんまり変わらないな」
僕の率直な感想に、松倉も頷いた。
「駄目か」
「でもこれ以上は紙が傷む」
「そういえば、本の汚れ落としには消しゴムがいいって聞いたことがある」
あまりにぬけぬけと言うので、さすがに少し腹が立つ。
「先に言えよ」
松倉はさほど悪いとも思っていなさそうに、「すまん」と言った。水気が完全に抜けるのを待って言われた通り消しゴムを使うと、たしかに少しはきれいになった。
「あとは擦れたところか。放っておくと、ここから破れていきそうだ」
「フィルムで補強すればいいんじゃないか」
「そんなやり方も聞いたことがあるのか」
松倉は笑った。
「いま思いついた」
一度ブックコートフィルムを貼ってしまえば、剝がしてやり直すことは難しい。少しためらったけれど、ほかにいい方法があるわけじゃないと思い切る。貸出カウンターの引き出しからフィルムのロールを出して小さく切り取り、斜めにならないよう慎重に、擦り傷の部分に貼りつける。
もう一度、出来映えを見る。
「……おお。いいんじゃないか?」
思わず出た自画自賛に、松倉も「やってみるもんだな」と同意してくれた。
思いつきの割には意外と目立たないよう直せた。これなら、背ラベルを貼れば損傷はほとんどわからないだろう。背ラベルなら在庫がある。これはさすがに手先の器用さは関係ないだろうし、字は松倉の方が上手い。
「ラベルは任せた」
そう言うと、松倉は頷いて引き出しから在庫のラベルを探し出し、ボールペンを構えた。まずは日本十進分類法に基づいて、日本の小説であることを示す分類記号の「913」を書き入れ、著者は志賀直哉なので、「シ」と書き添える。傷んだ背ラベルの上から新しいラベルを貼り、僕がフィルムで固定した。
あとは三冊とも書架に戻すだけで、三分とかからず用事は済んでしまった。となるとほかにやることもない。トランプぐらいならどこかに隠してあるはずだけれど、僕も松倉もいまさら図書室を遊び場にしようとは思っていなかった。あれやこれやで一時間はこうしているけれど、たった一人の利用者すら入ってこない。いくらうちの図書室が不人気だからといって、これほど静かな日も珍しい。
先に退屈に音を上げたのは、松倉の方だった。
「堀川。なにかやることはないか」
もちろん、いろいろとある。
「図書室だよりの原稿は、早ければ早いほどいいだろうな。未返却本の督促状を書いてもいい」
「なあ。そういうこと言いたいんじゃないってわかってるだろ」
「ああ。宿題のことか?」
松倉は付き合いきれないというようにそっぽを向いたけれど、「そうだな。じゃあ、督促状からやるか」と呟いた。
それで、あとは黙々とした作業のうちに放課後は過ぎていくはずだった。
けれどこの日はそれで終わらなかった。松倉が督促状の用紙を取り出したところで、ずっと閉じたままだった図書室のドアが開かれた。入ってきた生徒を一目見て、本を借りに来たのではないとわかる。よく知っている人だ。
僕は、
「あ、ども」
と小さく頭を下げ、松倉も申し訳程度に僕に倣う。
入ってきたのは、このあいだ図書委員会を引退した三年生のひとり、浦上麻里先輩だった。手に小さなペットボトルを二本持っている。先輩は僕たちを見て、いまにも片目をつむってみせるのではないかと思うほど、悪戯っぽく笑った。
「や。暇そうね」
-
引退後、なにくれとなく理由をつけて図書室を覗きに来る先輩は何人かいたけれど、浦上先輩を見たのは今日が初めてだ。
浦上先輩は、最後に見たときよりも少し日焼けをしているように見えた。肩までの髪は軽く内側にカールして、いつものように少し眠そうな目をしている。なにか塗っているのか、ぼってりとしたくちびるに光沢があるのについ目がいった。
「見ての通り、暇です」
僕がそう言うと、松倉がすぐに補足する。
「督促状を書こうと思ってたところです」
「そ。じゃあ、暇ね」
貸出カウンターにもたれかかり、浦上先輩は手にしていたペットボトルを僕たちの前に置く。爽健美茶だった。
「はい、差し入れ」
嬉しいけれど、
「どうしたんですか、いきなり」
そう訊いても、先輩は笑顔を向けるだけ。松倉がポケットからハンカチを出して、少し結露しているペットボトルの下に敷いて、口の端を持ち上げた。
「差し入れじゃないですよね。買収か……手付け金?」
浦上先輩はあっさりと、「ばれたか」と両手を上げた。
「詩門くん、やっぱりなかなか鋭いね」
「おごってもらう理由がないですから」
「おお、かわいくないかわいくない。後輩と上手くやれてる?」
その返事は待たず、先輩は秘密めかして声を落とす。
「実はそうなんだ。ちょっといい話があるんだけど」
「僕たちに?」
「うん」
ということは、先輩は僕たちが今日の図書当番だと知っていて来たようだ。
「いきなりなんだけど、アルバイトしない? 堀川くんたちに向いてる話だと思うんだ」
僕たちに向いていると言いながら、先輩はなぜか、僕の方ばかりを見て話す。松倉が口を挟んだ。
「なんか怪しいですね」
「まあね。でも、話だけでも聞いてよ。それともぜんぜん興味ない? 忙しいかな」
「そういうわけじゃないですが」
「じゃ、いいよね」
そう受け流し、まだ聞くとも言っていないのに「うちのことなんだけどさ」と話を切り出した。
「おじいちゃんが死んだんだよね」
「そうだったんですか」
「あ、結構前のことだから、そんな気の毒そうな顔しないで。でね、いいおじいちゃんだったんだけど変なところで凝り性で、いまちょっと困ってるの。恥ずかしい話なんだけど……」
恥ずかしいと言いながら、先輩は少し嬉しそうだ。
「金庫に鍵かけたまま死んだのよ」
「金庫?」
「そう。こんなやつ」
手を大きく広げて、先輩は金庫の大きさをアピールする。もし本当にその大きさなら、人間だって入れそうだ。先輩は続けて、ツマミを捻るような仕草をした。
「こうやってダイアルまわして番号合わせる金庫なんだけど……。もう、なにを頼みたいかわかったよね?」
まさかとは思うけれど。
「僕たちにその金庫の番号を探り当ててくれ、なんてことじゃ」
「正解!」
先輩はにこりと笑って、親指を立てる。
僕が言いたいことは、松倉が言ってくれた。
「冗談でしょう」
「なにが?」
「『おじいさんの遺した開かずの金庫』ってのが、まずひとつ。その解錠を俺たちに頼むのがもうひとつ」
すると先輩は少しのあいだ黙り込み、やがて、作ったような笑顔になった。
「どんなことでも起こるのよ。おじいちゃんだって、開かずの金庫にするつもりなんかなかったと思う。ただ、自分が思ってるより早く死んじゃっただけ。誰にも教えられずに」
先輩の笑顔は、ひどく寂しそうに見えた。
けれどそれは一瞬のことで、すぐに目を輝かせて身を乗り出してくる。
「堀川くんたちに頼むのは、ほら、いつだったか暗号を解いたじゃない。あれすごいなって思ってて、鍵が開かないってわかったとき、あの子たちなら! って思っちゃったのよね」
「ああ……」
溜め息をつくように、松倉が頷いた。
浦上先輩が言う通り、僕と松倉は前に暗号を解いたことがある。図書委員会では普段、誰も本のことなんて話題にしなかったけれど、ある日、どういう流れだったか、先輩の一人が江戸川乱歩の短篇「黒手組」を持ち出してきた。「これ暗号なんだけど、誰か解ける?」と言われて、僕と松倉がその気になった。さすがにその場ですぐに解くことはできなかったけれど、下校時刻直前になって松倉が突破口を見つけ出し、夕暮れ時の図書室で僕たちは大いに面目を施したのだ。
「あれは、まあ、たまたま」
「たまたまでもいいよ。駄目で元々、当たれば大きい」
僕は割と興味を惹かれていた。けれど松倉は、苦い顔で、どうも気が進まない様子だ。
「でも、ダイアル式の金庫ですよね。要するに俺たち、正解の数字を探してひたすらダイアルまわすだけじゃないですか。総当たりしたって面白くもなんともないし、いつまでかかるか」
「察しが悪いなあ。総当たりしてなんて言ってないでしょ。手がかりがあるに決まってるじゃない」
たしかに、暗号小説を解いたという理由で僕たちに目をつけたのなら、なにか手がかりはあるのだろう。暗号っぽいものが。
「とにかく、挑戦するなら夕飯ご馳走してあげる。で、もし金庫が開いたら中身次第でバイト代を出すわ」
そこまで言って、浦上先輩はちょっと人が悪そうな笑みを作った。
「言っておくけどね。あたしのおじいちゃん、けっこう、お金持ちなのよ」
-
続きは本編でお楽しみください!