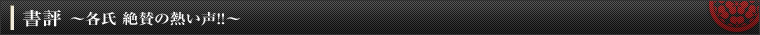 |
 |
|
 |
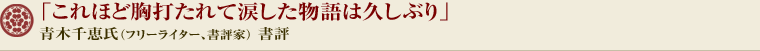 |
 |
鬼と姫の双貌を持つ男は、豊かな国を思い描いて夢の翼を拡げた。その行く手にあった光景は、どんなものだったのか――。
第20回小説すばる新人賞受賞作『桃山ビート・トライブ』、続く『青嵐の譜』で、過酷な社会状況下での青春群像を描いた著者の最新作は、一介の豪族から躍進して土佐を平定、四国統一の目前で豊臣秀吉に屈した戦国大名、長宗我部(ちょうそかべ)氏の盛衰を描いた正統派時代小説だ。これほど胸打たれて涙した物語は久しぶりだったと、まず言っておきたい。
軸となる人物は、永禄3年(1560年)に家督を相続し、15年かけて土佐一国を統一、一族の最盛期を築いた長宗我部元親(もとちか)である。武勲重視の荒武者ばかり、“いごっそう”を尊ぶ土佐の気風の中で、細面の美男子で、武芸よりも読書を愛好する少年だった元親は、“土佐の姫若子”と陰口を叩かれていたが、22歳の遅い初陣で目覚ましい戦功を挙げ、“土佐の鬼若子”と呼ばれて、戦略でも内政でも非凡な才を発揮するようになる。
領民の暮らしを豊かにするには、周辺の豪族を制圧して戦をなくせばいい。そう考えた元親は、「土佐平定」を自らの夢にする。だが、猛将・安芸国虎(あきくにとら)を攻めあぐね、卑劣な手段で勝利した後ろめたい「秘密」を胸にしまい込んだとき、元親の人生に微かな綻びが生じる。秘密に気付いた弟を殺害し、殺害の罪を阿波の豪族になすりつけて、阿波に出兵せざるを得なくなる。次第に元親は、謀略の糸を張り巡らせ、筋書き通りに他者を操ることに暗い喜びを感じるようになる。手を汚すたび、領土と権威は伸張するが、何か大切なものが心の中から欠けていった――。
物語は、元親の死から15年後の慶長19年(1614年)、家督を継いだ長宗我部盛親(もりちか)の京都の蟄居先に、元親の側近だった久武親直(ひさたけちかなお)が訪れる序章で始まる。まず冒頭で、長宗我部家がすでに滅んだに等しい状態であることが分かる。先の元親の代で四国を制覇する勢いだった一族は、なぜ急速に衰微したのか。元親を若き日から知る、親直が語る構成だ。
長宗我部氏の躍進は、若き日の元親が抱いた夢、「土佐平定」が原動力だった。だが、たび重なる戦いと老いていく過程で、初心を維持するのは難しい。また、力をつけるほど、各方面から反発勢力が襲いかかってくるのも人の世の常である。敗れれば命そのものがなく、肉親同士で殺し合って当たり前だった戦国の世では、一族を束ねる主に「ささやかな幸福」など許されなかった。元親は「土佐平定」を夢見ただけだったが、命がけのその羽ばたきは、織田信長に「鳥無き島の蝙蝠(こうもり)」と嘲笑され、信長、秀吉、家康という地の利と信長の築いたネットワークに則った「中央の支配者」に、翼を畳むことを強いられる。〈所詮、自分は鳥無き島の蝙蝠に過ぎなかったのか。本物の鷹や鷲が現れれば、羽根を畳んで頭を垂れるしかないのか〉――。屈辱に苛まれ、疑心暗鬼に陥る元親の前から、愛妻が病で先立ち、福留隼人(はやと)ら剛毅な“いごっそう”たちが、戦いの中で落命して去っていく。一族の命運を担っていた人物が、謀略で命を落とす場面は、人の世の非情さが悲しすぎて、読みながら涙が止まらなかった。かつて「姫」と揶揄された元親の繊細な心は、ゆっくりと、そして静かに、壊れていく……。
ただ、もしも長宗我部家が歴史的「勝者たち」であったら、この物語は生まれていなかっただろう。それに、元親の挫折と長宗我部家の衰退は、本山氏、一条氏ら、敵対する豪族の夢を打ち砕いた後に起きたものだ。〈夢であれ野心であれ、どちらにしろ分に過ぎていたのだ。いつからか、元親はそのことに気付いていた。だが、止まることはできなかった。自分の夢の犠牲になった者が、あまりに多すぎた。それこそ、数えきれないほどの命を奪ってきたのだ〉と、元親は深い絶望と悔恨を抱えている。かつて心に誓った「子が誇れる親になること」「領民が豊かになること」という夢が変質し、そのための手段に過ぎなかった「土佐平定」「四国制覇」が前面に躍り出ていた。とすると、本来的な夢とはなんだろう? その「翼」は、相手との力の拮抗次第で畳まざるを得ないものなのか?
土佐は、はるか南へ広がる太平洋に開けた土地である。土佐の一角を根城に、若き日の元親が見つめたのは、空や、南方に開けた土佐の海という「森羅万象」だった。元親の翼は、信長、秀吉、家康に手折られたようにみえても、森羅万象を視点の礎とすれば、人は命ある限りそれぞれ夢を持ち続けていいし、その夢は他人に挫かれるようなものではないのだろう。元親も、一族の暗黒面を見つめて暗い人生を生きざるを得なかった久武親直も、元親の子の信親(のぶちか)、盛親も、側近たちも、生ききっていたと私には読める。主従が敗戦地を落ち延びる、ふたつの場面の描き方の対比が見事だと思う。自ら翼を折るな。熱い生命賛歌の物語だ。 |
 |
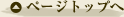 |
 |
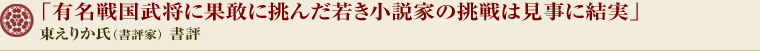 |
 |
幕末の志士に土佐出身者が多いのはよく知られている。今年の一番人気、坂本龍馬(さかもとりょうま)を筆頭に、武市半平太(たけちはんぺいた)、岡田以蔵(おかだいぞう)など郷士出身者が多い。この遠因が、戦国時代、四国の雄として知られた長宗我部元親(ちょうそかべもとちか)の行った「一領具足」であったのではないか、と言われている。平時は農民として田畑を耕し、一朝事が起こったときには、領主から配された武具を身に着け兵士として戦う、というこのシステムで元親は多くの戦いに勝利をおさめた。長宗我部が廃された後も、この半農半兵は土佐に残り、後の領主の下、身分差別に泣いた。それが後の倒幕に結びついたと言われている。歴史は連綿と続いているのだ。
血湧き肉躍る傑作『青嵐の譜』から一年。天野純希、待望の新作『南海の翼』は、時代小説として真っ向から取り組んだ意欲作となった。四国の雄、長宗我部元親の生涯をドラマティックに描いた大長編である。
時は室町末期。世に言う戦国時代である。桶狭間の戦いに勝利した織田信長の台頭が著しく、まさに群雄割拠の時代に土佐の長宗我部元親は22歳で初陣を迎える。長浜の戦いで勝利した若武者は、美丈夫としての誉れが高かったと言われている。
秦の始皇帝を先祖に持つ長宗我部一族は、聖徳太子の片腕であった秦河勝(はたのかわかつ)の子孫でもある。保元の乱で敗れ土佐に逃れたのち、長宗我部を名乗り始める。罪人の配流場所でもあった土佐は、遠く京から離れた土地であり、大きな戦いから隔絶されていた。元親の父、国親(くにちか)は岡豊(おこう)城周囲を制圧し、徐々に勢力を広げていく。
元親の初陣となった戦も、宿敵、本山氏を攻略するためのものであった。本作品では、戦場に佇む姫君のような美男子の元親が、お付きの武将に槍の使い方をその場で習い、五十騎ほどを率いて敵陣に乗り込み、見事勝利に導いたと記している。信長、後には秀吉の足元を脅かす武将の誕生を予感させる、勇ましい登場である。
さて、本作品は、冒頭、盛親(もりちか)という元親の息子が、関ヶ原の戦いに臨むところから描かれている。西軍に属し敗走した14年後、大岩祐夢(たいがんゆうむ)と名を改め寺子屋の師匠として京で暮らしている。ここに父・元親の腹心であった久武親直(ひさたけちかなお)が訪れる。長宗我部亡き後、肥後の加藤家に身を寄せていた親直が、盛親を訪ねたのは、お家復興の夢を果たすためであった。
盛親は、父親を好いてはいなかった。むしろ憎んでいたと言ってもいい。末息子の盛親が、なぜ家督を継がなくてはならなかったのか、血で血を洗うようなお家騒動がなぜ起こったのかを、老武士、久武親直は静かに語り始めた。
地方の一領主として、隣国との争いだけに汲々としていればいい時代ではなかった。まさに国盗りのために、日本国内を大軍が駆け抜ける日々。太平洋に臨み、安穏に暮らしていた土佐も中央の煽りを受け始める。土佐一国を平らげたのち、元親は四国の背骨ともいうべき雲辺寺(うんぺんじ)山頂から周囲を一望し、四国統一を誓った。強固な一族・家臣団を作るために、民の暮らしを守るために、親族を殺め、毒を盛り、家来たちを欺く。影の部分を担う久武親直は元親の近くに付き従っていたのだった。15歳から近習として仕え、元親を一番身近に見てきた親直は、次第に力を付けていく。
四国一帯を懸けた織田信長との戦いは、明智光秀の本能寺の変により雲散霧消した。しかし、その光秀を討った秀吉により、元親はまた土佐に押し込められてしまう。大望を胸に描きながら潰えていく男の悲しみと怒りは指先が届きそうだったがゆえ、懊悩となって元親を苦しめる。唯一の望みは嫡男信親(のぶちか)の成長であった。
親直が語る元親の実像は、盛親の胸に一条の光を点す。長宗我部一族の誇りを取り戻し、父親・兄弟たちの無念を晴らすこと。後半の部分は戦国時代の終わりを飾った一人の武将の姿を浮き彫りにし、圧巻である。敵の陣地へ勇猛果敢に切り込んでいけばよかった武者たちとは違い、いかに生き延び家を残すべきかを考える。徳川家康が天下を取るのは、もう目の前であった。
前作『青嵐の譜』では蒙古襲来を題材に取りながら、戦乱に巻き込まれた民衆の、力強く雑草のように生きる様を描いた天野純希が、真正面から戦国時代の名将の物語に挑戦するとは夢にも思わなかった。最近の歴史ブームでも、長宗我部元親は歴女たちの人気が高く、大河ドラマの主人公になって欲しいという要望も高いと聞く。司馬遼太郎『夏草の賦』という大作もある。そんな有名戦国武将に果敢に挑んだ若き小説家の挑戦は見事に結実した。優男が持て囃される現代では見ることすら難しいような豪傑たちの物語は、胸の中を熱く滾らせ、ページを捲る手にも力が篭る。読み終わると豪快に酒を飲みたくなる、そんな一冊だ。 |
 |
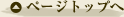 |
 |
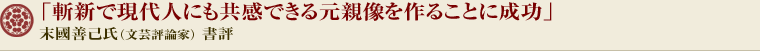 |
 |
一代で土佐一国を統一したことから「土佐の出来人」と評される一方、織田信長からは強敵のいない四国で暴れただけとの意味で「鳥無き島の蝙蝠」と揶揄された長宗我部元親は、辺境で活躍したマイナーな戦国武将に過ぎなかった。この状況を一変させたのが、若い女性を中心に戦国武将ブームを巻き起こした人気ゲーム『戦国BASARA』シリーズで、海賊の親分風にデフォルメされた元親は、今や最も人気のある武将の一人である。
天野純希は、厳格な身分制度による社会の統制を進める石田三成に反発する若者が、現代でいえばロックバンドを結成する『桃山ビート・トライブ』で小説すばる新人賞を受賞、元寇によって人生を翻弄された若者たちを活写した『青嵐の譜』で話題を集めた。待望の第三作となる『南海の翼』は、これまでの青春小説路線とは一線を画し、元親を主人公に、長宗我部家の興亡をダイナミックに描く重厚な歴史小説となっている。
多くのファンがいることに加え、元親を題材にした歴史小説は長く司馬遼太郎『夏草の賦』が独占してきただけに、プレッシャーも大きかっただろう。だが結論からいえば、著者は読みやすい文章とスピーディーな展開はそのままに、国の命運を背負った元親の苦悩や息子との葛藤を通して、斬新で現代人にも共感できる元親像を作ることに成功していた。
元親は、槍一本で敵に突撃した初陣以来、土佐の統一から四国の制覇、さらに家中の混乱を収束させるために、戦争と謀略に明け暮れる。それだけに、元親自身が乱戦に巻き込まれる野戦から大軍を指揮しての攻城戦まで、迫力の合戦シーンが連続する。中でも、宿敵ともいえる猛将で、優れた用兵家でもある十河存保との死闘、剽悍で知られる薩摩島津家の大軍に、寡兵で挑むことを命じられるクライマックスは圧巻である。ところが著者は、合戦を“戦国の華”と見なすことも、元親を好戦的な人物とすることもしていないのだ。
武芸が苦手なこともあって少年時代は「姫若子」と呼ばれていた元親は、もともと領土的な野心など持っていなかったが、戦乱で疲れた家臣と貧困にあえぐ領民を憂い、平和で豊かな国を作るため土佐を統一する戦いに打って出る。しかし土佐を統一しても、すべての家臣、すべての領民を満足させることはできなかった。そのため元親は、四国の覇者など自分の“器量”を超えると思いながらも、領土拡張戦争を続けることになるのである。
長宗我部家は、普段は農業に従事しているが、動員命令が出ると自前の具足を持って参陣する「一領具足」という制度を作っていた。司馬遼太郎は、半農半士の「一領具足」が元親が躍進する原動力になったと絶賛するが、著者は最前線で戦う「一領具足」が元親にさらなる戦争を要求し、それが戦線の拡大に拍車をかけたとの歴史解釈を示す。
親兄弟が血を流したのだから、それに見合う勝利と報酬を得るまでは戦いを続けて欲しいと願う「一領具足」たちの論理は、多くの戦死者を出した日露戦争で獲得した利権を守るため、昭和に入って日中戦争に突き進んだ日本軍や、9・11テロの報復に中東へ兵を進めたものの、泥沼の戦闘に巻き込まれているアメリカ軍と変わることはない。
貧困を解決するための手段だった戦争が、いつしか目的へと変わり、領主でありながら世論には逆らえず、戦争の継続を決めては苦悩する元親の姿は、戦争が発生する普遍的なメカニズムはもちろん、一度始まった戦争が簡単に止められない理由も明らかにしているのである。
物語は、長宗我部家配下の忍びを率いることを命じられた久武親直が、実兄の津野親忠を殺したため徳川家康の怒りに触れ土佐を奪われた長宗我部盛親に、知られざる元親のエピソードを語るという形で進んでいく。そのため、元親が戦争に勝つために行った謀略の数々も、余すことなく描かれている。嫡男の信親が戦死する後半になると、四男の盛親を後継者に指名した元親と、それに反発する家臣の間で内紛が勃発。反盛親派も忍びの者を雇い、久武親直の忍びに対抗するようになるので、忍者ものとしても楽しめるのではないだろうか。
味方の兵を損じることなく、謀略で敵を倒したり、内応をうながしたりする武将は、知将、謀将などと呼ばれ、武闘派よりもレベルが高いとされる。その意味で元親と久武親直は知将といえるが、謀略を誇るどころか、使うたびに後悔と罪悪感に押し潰されていく。
四国を制覇すれば、天下を狙う織田信長、豊臣秀吉と有利な和平交渉ができると考え、謀略の限りを尽くす元親は、厳しい競争原理にさらされ、利益を上げるためなら、多少の倫理違反ならば目をつぶるようになった現代人を彷彿とさせる。血みどろで切り取った阿波、讃岐、伊予を秀吉に没収され、信親も失った元親が、自分の本当の夢に気付くラストは、人間の幸福は金銭や地位にあるのか、ささやかな日常の中にあるのかを問い掛けているように思えてならない。 |
 |
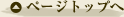 |
 |
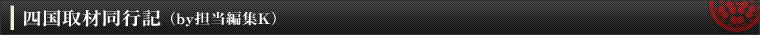 |
 |
雨続きの合間、久しぶりに晴れ渡った6月某日。
今回の取材旅行は、『南海の翼 長宗我部元親正伝』の原稿執筆も8割がた終了し、「確認」の意味をこめて現地の空気に触れ、登場人物たちの墓参もしましょう、ということで予定されたもの。
天野純希さんにとっては、初めての取材旅行です。
四国松山空港の到着口で、名古屋空港発の飛行機に乗った天野さんを待っていると・・・・。
コロコロと小型トランクを転がしながらご登場、二泊三日、夏の旅、男子なのにその荷物の大きさは何!? という疑問を飲みこみ、JR松山駅に移動し取材先の香川県に向かうべく、特急「しおかぜ」に乗車しました(この疑問の答えは最終日にわかります)。
長宗我部元親の足跡を辿る目的で、香川県と高知県を中心にまわるので、本来ならば、高知龍馬空港、もしくは高松空港から現地入りすべきなのですが、大河ドラマ『龍馬伝』の影響か空席はなく、松山から入ることに。
瀬戸内海を眺めながら、まずは観音寺駅で降り、タクシーで香川と徳島の県境にある雲辺寺へ向かいます。
かつて、このお寺の住職は四国統一の夢を語った元親に対し、「あなたはその器じゃない、土佐くらいにしておきなさい」と手厳しいことを返したという逸話を思い出しながら、ロープウェイ乗り場へ。
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| ロープウェイに乗る前の天野氏。 |
ロープウェイ窓から、麓を見る。 |
麓は晴れているのですが、乗車口の係員の方が「この天気の感じだと、ロープウェイは途中で止めることもあるかもしれませんねぇ。強風が出て危険な場合はそのまま数時間待っていただくこともありますが、それでもいいですかっ!!??」
と、即答しかねる難問をふりかけてきます。
「もちろん行きますよね? 天野さん」
予定通り旅程をこなすことを第一に考える担当編集としては、貸し切り状態のロープウェイ車内に無理矢理?天野さんを閉じ込めました。
途中から霧が急に濃くなり、車内にいても気温がぐんぐん下がっていくのがわかります。そして、山頂は、なんと豪雨、雷鳴、濃霧。
「祟り? それとも歓迎?」
ドン引き気味の天野さんを横目に、取材ズレした編集は、持参の雨具を自分だけ着込み、「とりあえず、境内に行きましょう」と傘のみで、強風にあおられ雨に打たれまくっている天野さんを促しました。
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 雨のせいか、境内に人影はなし。 |
瀬戸内海、讃岐平野を見やる。 |
清潔に保たれた広い境内をうろうろしているうち、雨も止み、薄日がさすほどに。
標高900メートルから見下ろすと、讃岐平野の向こうに瀬戸内海も見渡せます。晴れていれば、対岸の本土まで見えるとか。当時、敵味方の動き、あるいはこのように動くであろうという予想図を思い浮かべるにはうってつけの場所です。
「やはり元親の戦略眼は相当なものですね・・・」
長らく眼下の風景を見つめ続けていた天野さんが呟きます。
元親がここに登ったのは、戦略を練るためだったのだという思いをあらためて実感し、次なる目的地、阿波白地(はくち)城跡へ。土佐統一後の元親が、四国制覇の本営とし、秀吉の四国攻撃の際には防衛拠点となったお城です。
谷あい、山あいの国道を抜けて辿り着いた城跡は、小山一つぶんほどの敷地はあったのだろうと想像はできても、拍子抜けする狭さ。大群が押し寄せた場所とはとても思えません。「ここまで山あいとは……。馬で来るのも大変だったでしょうね」と天野さん。遺構はなく、記念碑が立つのみで、思わず「兵どもが夢のあと」という言葉が浮かびます。
二日目は、今回のメインとも言える高知県入りです。
交通の便が悪いため、タクシーを貸し切ろうと、行き先リストを運転手さんにお見せすると・・・。
「え? お客さんたち、何者ですか? 長宗我部関係の場所ばっかりですね。うわー。龍馬じゃなくて、長宗我部ですかぁ、嬉しいなあ」と、やおらノートを取り出します。
それは、小さな文字でびっしりと書かれた<長宗我部メモ>でした。
なんでも、運転手さんは、数年前に見た夢の中で、血だらけの侍に怒られたとのこと。何を怒っているのかわからなかったそうですが、横には年老いた武将がおり、それが元親だったように思えた、と。血だらけの侍は、お前は龍馬ばかりで長宗我部家の勉強が足らん! と怒っていたように感じ、その夢の後から長宗我部関連について勉強されたとか。
よくぞ、このような運転手さんに当たったものよ! ご縁を感じつつ、まずは、南国市の岡豊城へ。ここは、13~14世紀に築かれたとされる長宗我部家の本拠です。
本丸、石垣、井戸、曲輪、土塁などが残り、白地城と比べれば、当時を想起させるには十分の遺構が残っています。
「思ったよりずっと狭いですねえ。ちょっと原稿の描写を変えなくてはなりません」
この狭さでは、たくさんの人が同時に在住することは難しかっただろう・・・など、天野さんの想像力を刺激しているのが見て取れました。
城跡に立つ高知県立歴史民俗資料館には、元親の肖像画や自筆の書状などが展示されています。
若いときには姫若子と呼ばれ、長身でイケメンだったと言われる元親の肖像を見ては「なんだか神経質そうっすよね」、直筆の文字も伸びやかな書体とは言い難く、「細かい性格だったかもねーやっぱ」なんて、失礼?かもしれないことを言い合いながら見学。
館内売店には、長宗我部関連の図録や、手ぬぐい、扇子などのグッズが充実していました。
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 長宗我部一族のものと伝わる墓所。 |
元親の墓前で手を合わせる。 |
雪蹊寺内の長宗我部信親の墓所。 |
岡豊城そばにひっそりと残る、一族の墓所で手を合わせた後、元親が晩年をすごした桂浜の浦戸城、白浜にある元親と長男・信親のお墓参りをし、本日の行程は終了。
市内の古書店で資料を探し、店主に伺ったおすすめの郷土料理の居酒屋で夕食です。
定番・カツオのたたき(元親考案説もあり)などを堪能、もちろん、地酒とともに・・・・。
さきほどまで体感していた城跡の空気、直接目にした元親の肖像、書状などが、ぐるぐると頭の中をめぐり、天野さんの酔いに加速をつけたことは間違いありません(たぶん)。
「完全に書き上げる前に現地に来て本当によかった、とは思いますが、書き始める前に来ていたら、イメージが限定されすぎて、書けなくなっていたかもしれません・・・・」
とは、ほろ酔い加減の天野さんから出た言葉でした。
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 高知城(大高坂城)にて。 |
長宗我部軍が毒を入れたとされる安芸城の古井戸。 |
矢流古戦場の碑文を読む。 |
最終日の三日目は、元親の頃は大高坂城と呼ばれていた高知城を見学。もともとは元親の築城ですが、山内一豊の方が前面に出ているのが、なにやら盛者必衰を思わせ哀しい印象です。
そして、最後の目的地は、小説の前半に描写される安芸国虎の本拠地、安芸市。今なら、岩崎弥太郎の生家があることの方で有名かもしれません。
単なる低山と化した安芸城跡、国虎の墓所などをまわり、矢流古戦場へ。
「国虎くん、いい戦略を立てましたねぇ・・・彼のことはかっこよく書いたつもりです」
なぜならば、とこちらに説明してくださいました。
太平洋と陸地に広がる山を見渡し、当時の戦闘シーンを反芻していると思われる天野さん。
戦国時代の甲冑を身に着けた武将、一領具足の兵たちが闘うさまが、頭の中で3Dで甦っているのだろう思うのは、その生々しい様子が小説中で躍動感を持って見事に描かれているからです。
というわけで、予定通りに無事取材終了。というか、予定以上に濃い取材となりました。
さて、冒頭で触れた例の小型トランクの意味。集めた資料のためではなく、酔鯨、司牡丹など地酒を持ち帰るためのものだったのでした。お酒好きの天野さん、ご友人にも「買ってきてね!」と頼まれたとか。市内の酒屋で物色し、数本を詰め込んで名古屋へ戻られました。
後日。
「名古屋にも四国のお酒、いっぱいありました(笑)」
天野さんから戴いたメールに爆笑、初陣取材は、心理的にも物理的にも、そして何より今回の作品にとっても、お土産たっぷりに終了したのでした。
小説完成の残り2割はもちろんのこと、この取材を経て、各シーンがより深みと密度を増したのは言うまでもありません。 |
 |
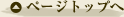 |
|

