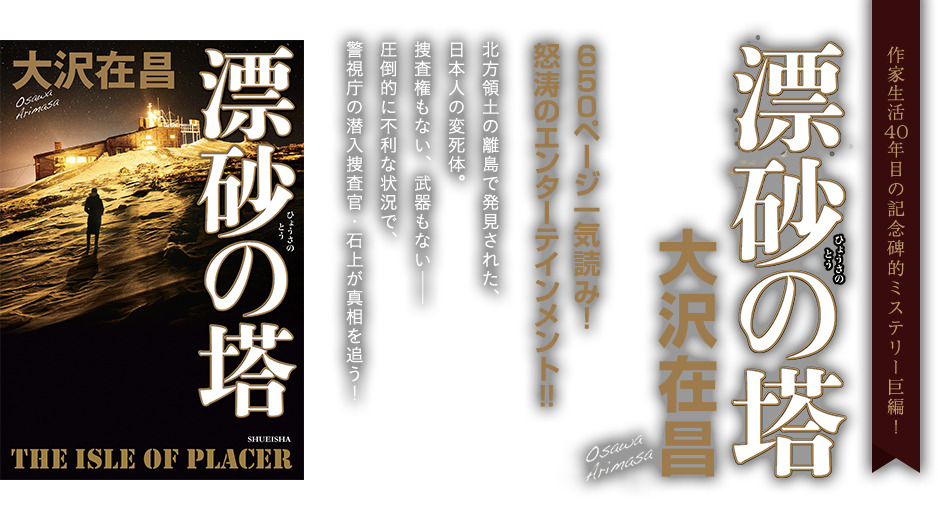人種に関係なく、誰もが汗をかいていた。もし汗をかいていない者がいるとしたら、私の隣のボリスくらいのものだろう。あとはボリスの向かいにすわる杜(ドウ)か。日本での東北グループの凋落に乗じるかたちで勢力を伸ばした四川省出身の男だ。事前の調査によれば四川出身というのは自称で、実際は南の雲南省出身らしい。二十代の初めに省都昆 明(こんめい)で警官を殺し、ミャンマーに逃亡した。その後タイを経由して中国に舞い戻り、レアメタル採掘でひと山あてる。が、共同で所有していた鉱山が環境汚染の原因となったことを追及され、拠点を重慶に移した。
重慶ではホテルやレストラン、ナイトクラブを経営し、日本にもホテルとレストランをもっている。
「こいつらにいえ。カザフやキルギスの女は駄目だ。モルドバかルーマニア、本物の金髪を用意しろ、と」
杜が通訳の侯(ホウ)に中国語でささやいた。侯は向かいにすわる私に日本語でいった。
「白人、金髪、絶対です」
私はボリスを見た。
「中央アジアの女は駄目だといってる。本物の金髪に限るらしい」
ロシア語でいった。
「歳については何といってる」
ボリスが訊ねた。母親はウラジオストクで水兵を相手にする商売女だったが、父親はロシア海軍の提督だというのが自慢だ。ウラジオストクの小さな組織がユージノサハリンスクに進出したときが、ボリス・コズロフの人生最初の勝負だった。それまでユージノサハリンスクの商売を牛耳っていた朝鮮族系の老ボスのもとを訪れ、拳銃を口につっこんで引退を約束させた。
ユージノサハリンスクからウラジオストクに戻り、さらにハバロフスクまで勢力を広げたのは、日本向けの海産物と女の輸出が当たったからだ。
「何もいってない」
私が答えると、ボリスはにやりと笑った。黒髪でずんぐりとした体型は、ロシア人というよりチェチェン人に見える。頰にある深い傷跡は、拳銃をつきつけて引退させた老ボスの甥に市場で襲われたときのものだ。ボリスは顔を切られながらもナイフを奪い、相手の右手の指をすべて落とした。
「かわいい奴らだぜ。ひとり二万USドルだ」
「ひとり二万USドルです」
私は日本語で侯にいった。侯の通訳を聞いて、
「元(げん)だ、元!」
と、杜が叫んだ。
「元以外じゃ支払いはない」
「こいつらは元以外で払う気はないようだ」
侯の言葉を通訳するフリをして、私はボリスに告げた。ボリスは目を大きく開き、愛敬たっぷりの笑みを浮かべた。
「馬鹿にしやがって。手前らのきたねえ元を、俺の懐ろで洗う気だな。パブロ」
ボリスのうしろにすわるパブロが唸声をたてた。
「殺しますか。呼べばすぐくるのが、上に四人います」
ボリスの笑みにつられたように杜も笑いを浮かべた。
「奥にいるか」
背後にすわる烈(リエ)に小声で訊いた。
「厨房に二人います。すぐに殺れます」
烈が答える。
背中にどっと汗がふきだした。
「一万をUS、一万を人民元でどうです?」
私はロシア語でボリスに訊ねた。ボリスは首を縦にふり、私の肩をもんだ。
「ユーリ、お前は天才だ」
私は同じことを日本語でいった。侯の通訳を聞いた杜は思案顔になった。
「日本人の女を四人つけてやる。金髪が十人、日本人四人だ。日本人は一万USだけでいい」
ボリスがいい、通訳を聞いた杜は大きく破顔した。
「話を整理しましょう。白人女十人と日本人女四人。十四万USドルと十万USドル相当の人民元」
私の言葉を侯が通訳し、杜は頷いた。立ちあがり、ボリスに右手をさしだす。
「取引成立です」
ボリスが握り返す。
「ボス」
耳にイヤフォンをとめていたパブロが声をかけた。手にした携帯の画面をボリスに見せる。
不意に吐きけがこみあげた。悪い兆候だ。が、ボリスは私にいった。
「ユーリ、お前のおかげでいい取引ができた。本当にお前は天才だ」
立ちあがった私を抱きしめる。ジャケットの革の匂いが鼻をついた。
「いかなけりゃならない」
私の耳元でボリスはいった。
「どこへ?」
「イケブクロだ。うちの女がひとり、クスリでぶっとんで客を刺した。日本人のヤクザだ」
「本当か?」
体を離し、訊ねた私にボリスは深刻な表情を見せた。
「ヤクザは怒ってる。たいした怪我じゃないが、ボスの俺が"ワビ"をしなけりゃ店を潰すそうだ」
「殺すのか、そのヤクザを」
「場合によっては。パブロも連れていくから、あとはお前に任せる。どうせ金は、女たちとひきかえだ」
「期限は?」
「二ヵ月。女は三回に分けて連れていく。俺が信用できる上海の旅行会社を使う」
早口でボリスは答えた。
「伝えておく」
ボリスは人さし指で私をさした。
「ユーリ、お前は最高だ。お前みたいな天才は見たことがない」
「よせよ、ボリス。言葉が話せる以外、俺にはとりえなんてない」
「謙遜するな」
ボリスは片目をつぶり、私の右手を握った。不自然なほど力のこもった握手だった。
「じゃあな。友だちによろしく」
友だち? と訊き返す間もなく、ボリスは店をでていった。
あっけにとられている杜やその手下に、私は大急ぎで告げた。
「ボスは急用ができました。あとの話は、私が進めます」
侯が訳すのを聞いて、杜は首を傾げた。
「こいつはただの通訳じゃないか。奴は俺をなめてるのか」
背筋が冷たくなった。杜の言葉がわからないフリをしていった。
「女は二ヵ月以内に手配しますが、人数が多いので、三回に分けて中国に連れていきます」
「渡航の方法は?」
「ボスが取引している旅行会社が上海にあるので、そこを使います」
「旅行会社の名を教えてくれ」
「それは——」
私は黙った。そこまでは聞いていない。知るわけがない。通訳としてボリスに私が雇われてから、まだ四ヵ月しかたっていない。ロシア語と中国語がわかる人間をボリスが捜しているという情報を得たのは半年前のことだ。
「なんだ。教えられないのか。こっちだってビジネスパートナーのことは調べておきたい。以前とちがって公安も、なかなか鼻薬がききにくくなってるんだ」
杜がいった。侯が日本語に訳すまで私は杜を見つめていた。
不意に店の扉が開いた。ボリスがでていったあと、鍵をかけていなかった。泡をくったように烈が腰を浮かした。
地味なスーツにネクタイをしめた、サラリーマン風の男二人がいた。
「すみません! 貸し切りです」
侯が叫んだ。
「貸し切りだって」
「貸し切りなの?」
いいあいながらも店の中に入りこんでくる。
「何時まで貸し切り?」
先頭にいた眼鏡の男が訊ねた。もうひとりは扉を手でおさえている。
「今日はずっと。お客さん、入れません」
どどどっという足音が階段から聞こえた。
「そのまま動かないで!」
眼鏡の男がバッジを掲げた。
「警察です。入管難民法違反の疑いでこの店を捜索します」
「警察!」
侯が杜をふりかえった。
「厨房に二人! 武器をもったのがいる」
私は叫んだ。
「突入!」
抗弾ベストにヘルメットをつけ、MP5をかまえた集団が店内になだれこんだ。銃器対策部隊選抜のERTだ。グラスが割れ、テーブルが倒れた。パン! という銃声が一発だけ聞こえて、
「制圧!」
「制圧」
という言葉が口々にくり返された。杜と侯、烈は一瞬で床におさえこまれた。
「どういうことだよ!」
私は大声をだした。今日、急襲があるとは聞いていなかった。そもそもターゲットは、杜ではなくボリスなのだ。そのボリスがいないのにガサをかけても意味がない。第一、女や金なしでは、組織犯罪処罰法の「共謀罪」くらいしか問えない。杜もボリスも、あっという間にシャバにでてくるだろう。
警視庁組織犯罪対策第二課の課長、稲葉は六階の会議室で私を待っていた。甘めのコーヒーを飲めば、腹のもたれが消えるかと思ったが、まちがいだった。むかつきはよけいひどくなり、食いものが原因ではないと気づいた。
「吐くのなら、さきに吐いてこい」
私の顔を見るなり、稲葉はいった。
「そういう顔ですか」
そっけなく稲葉は頷いた。歳は私のひと回り上の四十九、準キャリアの警視正だ。結婚しているが子供はいない。ゲイだという噂があるが、たぶんちがう。
私はトイレに立ち、指を口につっこんで吐いた。四川料理の辛みが再び喉を焼く。だが胃の中が空になると、少しすっきりした。
顔を洗い、涙目をぬぐった。今度はブラックコーヒーを買って会議室に戻った。
「だいぶよくなりました」
「前のときも吐いたな」
稲葉は手にした書類に目を落としながらいった。
「そうでしたっけ」
「グルジア人グループをやったときだ。何とかシビリだったか、ナイフをふり回した奴だ。検挙のあとクラブのトイレで吐いていた」
「向いてないんですよ。いつ正体がバレるかと思うと、生きた心地がしない」
「生きた心地がしない、か」
稲葉はふん、と笑った。
「笑うことはないでしょう」
「生きた心地がしないなんていい回しを、映画やドラマ以外で初めて聞いた」
私は稲葉をにらみつけた。
「じゃやってみてください」
「君みたいに何ヵ国語も喋れたら、喜んでやってる。中国語はがんばってみたが、五年やって君の足もとにも及ばない。ロシア語にいたってはいわずもがなだ」
「おばあちゃんに感謝したのは、この顔で女の子にもてた十代まででした」
両親が離婚したあと、私は青森の祖母のもとで六年暮らした。
イリーナ・シェフチェンコ・イシガミが祖母の名だ。家ではロシア語しか話さない祖母のおかげでロシア語を覚え、大学で中国語を学んだ。
「国際犯罪捜査官といやあカッコいいですがね。いつ殺されるかわからない」
ただ語学が得意だというだけでは、通訳にしかなれない。捜査共助課にいた私を潜入捜査に使おうと思いついたのが稲葉だった。
おもしろそうだと思ったのが、まちがいの始まりだ。
「しばらく東京を離れられる仕事がある。マフィアとはかかわらない」
「ロシアも中国も?」
稲葉は頷いた。
「信用できません。そんな仕事が組対にありますか」
「組対じゃない。お前さんだけに、だ」
「意味がわかりません」
「北方領土」
稲葉は短くいった。私は首をふった。
「公安(ハム)にいなかったのは知ってるでしょう」
「ひっぱられたが断わった。今でもたまに欲しいといわれる」
「この顔は向きません」
確かに若い頃は女の子にもてたが、四分の一のスラブ人の血が濃くですぎている。ハーフどころか白人にまちがえられることすらある。公安で働くには目立つ顔だ。
目立つのを逆手にとれ、といったのが稲葉だ。「外人顔のお巡りはいない、とマフィアは思っている」
今は思っていない。少なくとも杜志英とボリス・コズロフは思っていない。
「歯舞(はぼまい)群島の中に、春勇留(はるゆり)島という島がある。納沙布(のさっぷ)岬から東北東に四十キロの海上だ。ロシア名はオロボ島」
「人が住んでいるんですか」
「四年前までは無人島だ。大正末期から昭和の初めにかけてはコンブ漁が盛んで、多いときには百人近い人口があったらしい。が、じょじょに減少し、ソ連軍が占領した昭和二十年はほぼ無人だった」
「今も?」
「約三百四十人が住んでいる。ロシア人が百人、中国人が百三十人、日本人が百十人。『オロテック』という合弁会社の関係者ばかりだ」
「何の会社なんです?」
「レアアースだ。資料によると、オロボ島の南海底に、錫(すず)やチタン、モナザイトといった金属や鉱物の漂砂鉱床がある」
「ヒョウサコウショウ?」
「比較的浅い海底にある、特定の鉱物が集まった地域だ。比重の大きい鉱物が、潮や海流などで分離されて濃縮されたものらしい」
「昔、水の入った椀に砂を入れて砂鉄をとったのを思いだしました」
「おそらくそれの大規模なものを何万年もかけて自然が作ったのだろう」
「何ていいましたっけ? 錫とチタン——」
「モナザイトだ。このモナザイトが非常に有用で、ネオジムというレアアースを含んでいる。ネオジムは、小型磁石の材料として、ハイブリッドカーやコンピュータのハードディスクに欠かせない物質らしい」
「レアアースってのは中国でほとんど生産されているのだと思っていました」
「生産されたレアアースの九十パーセント以上が中国産だ。鉱山じたいは、アメリカやオーストラリア、ベトナムなどにもあるらしいが、価格競争で中国産が市場を独占した。それを政治的に利用しようとして、国際的に反発をくらったのが二〇一二年だ」
十年前だ。
「今は?」
「落ちついている。だがまたいつ輸出禁止などの外交カードに使われるかわからない。そこで日本も独自にレアアースを生産する方向を模索してきた。ただ地質上の特性で、日本にはレアアース鉱床はあまりないといわれていた」
「それが北方領土の海底で見つかった」
「現在はロシアが実効支配している島のすぐそばの海底だ。ロシア一国で生産しようとしたらしいが、製錬技術ではロシアは遅れている。最も進んだ技術をもっているのが中国だ。世界のレアアース生産量の大半を占める中国が、ノウハウを蓄積している」
「ロシアは実効支配の強みを主張し、中国には技術がある。日本人は何の権利で加わっているんです?」
「ここから先は、俺の付焼き刃じゃおっつかん。関係者を呼ぶから話を聞いてくれ」
稲葉は内線電話に手をのばした。
「待ってください。そこにいけって話なんですか」
稲葉は私をふりむき、わずかに間をおいて、
「そうだ」
と答えた。
私は何といってよいかわからず黙った。警視庁の管轄区域ではなく、そもそも日本ですらない。政府は、日本固有の領土と主張しているが、仮りにそうだとしても北海道警察の縄張りだ。
「お連れしてくれ」
受話器をおろし、稲葉は私を見た。
「その島にいる間、君は警視庁警察官としての職務権限を失う」
「はあ?」
会議室のドアがノックされた。
「どうぞ」
眼鏡をかけた、四十四、五の男がドアを開いた。首から入館証をさげている。
「お待たせしました。どうぞおかけください」
ノータイでスーツを着け、運動をやっているような体つきだ。男は私を見つめた。
「こちらが石上です。ロシア語と中国語が堪能です」
「あ、日本の方なんですね。一瞬、どこの国の方だろうと。失礼しました。私、ヨウワ化学工業の安田と申します」名刺を手渡された。
「申しわけありません。さっき現場から戻ったばかりで、名刺をもっておりません」
うけとった私は頭を下げた。
「ヨウワ化学工業株式会社 電源開発部 開発四課チーフ 安田広喜」
と名刺にはあった。会社は芝公園だ。
「安田さんは半月前まで、オロテックに出向しておられた。北方領土の合弁会社に、どうして日本企業が加わったのか、石上君に話してやってください」
私は安田を見返した。
「ロシアは地の利、中国は技術、日本は何でくいこんだのです?」
「それでしたら、まずレアアースについてお話をさせてください。もし石上さんが詳しいのなら、しませんが……」
安田は迷ったようにいった。私は首をふった。
「まるで詳しくありません。たった今、課長から、車やコンピュータに必要なネオジムというのがある、というのを聞いただけで」
「そうですか。ではなるべく簡単に説明をいたします。レアアースというのは、十七種類の元素の総称です。元素周期表、『水兵リーベ、僕の船』と覚えた表、あれの二一番スカンジウム、三九番イットリウム、そして五七番から七一番までの十五元素をあわせたものです。レアメタル四十七元素のうちの、電子配列が似たものをレアアースと呼び、超伝導性や強磁性、半導体、触媒特性などが産業的に利用されています。このうち、特に現在有用とされているのが、ネオジムやサマリウムなどの永久磁石の材料となるレアアースです。レアアースは、レアアース鉱物に含まれており、その代表的なものが、モナザイト、バストネサイト、イオン吸着鉱などです。もともとは地下深くのマグマに含まれていたレアアースが地表近くに上昇し、他の元素と化合してできたのです。このレアアース鉱物には、トリウムという放射性元素が含まれている確率が高く、モナザイトなどは六から十パーセントも含んでいます」
「つまりレアアースをとると放射性元素もくっついてくる?」
「すべてのレアアース鉱物ではありませんが、モナザイトやゼノタイムなどは含有量が高い。鉱石内で、レアアースとトリウムが共存しているのです。チタンなどとも共存するケースの多い元素です。選鉱の段階で、これらの元素は分離されますが、放射性元素であるトリウムは、ただ保管しておくというわけにはいきません。野積みなどすれば、環境汚染をひき起こしますから」
杜の資料を思いだした。杜と仲間が所有する鉱山からたれ流しになった放射性物質で、近隣の住民に癌患者が多発した。その責任を逃れるため、杜は重慶に逃げたのだ。
「このトリウムを有効に利用する方法があります。原子力発電です。トリウムを使った原子力発電は、施設を小規模にできるという利点があります。なぜなら、ウランを核分裂させて発熱させるシステムと異なり、プルトニウムがほとんど発生せず、比較的低発熱で運転することが可能だからです。ところがプルトニウムが発生しないため、核兵器への転用が不可能だという理由でこれまで多くは建設されませんでした」
「つまり原子力発電は、核兵器開発のためでもあったということですか」
「日本以外の国では」
安田は頷いた。
「さらにトリウム発電所は、溶融塩炉という構造上、発電量に比べどうしても施設が高層化する傾向があり、インドやドイツ、アメリカにあるものの原子力発電の主流とはなっていませんでした。建物はかさばるのに、発電量が少なく、プルトニウムも作れないでは魅力に欠ける。しかし五年前、ヨウワ化学工業は、高層化しない溶融塩炉で発電するシステムを開発しました。発電量は二十メガワットですが、副産物のトリウムを燃料にしてレアアースの選鉱、分離、精製に必要な電力をまかなうことができます」
「それがオロテックに加わった理由ですか」
安田は再び頷いた。
「ヨウワ化学工業が参加したことで、トリウムの保管と電力供給のふたつの課題をオロテックはクリアしました。ヨウワの発電所がなければ、離島であるオロボ島では、採掘から選鉱、分離、精製にいたる工程のエネルギーを確保できず、海底から掘りだした鉱物を選鉱しないまま、ロシア本土なり北海道に運ぶ他なかったわけです。そうなれば運搬費用が高くつきますし、環境汚染の問題もでてくる」
「加えざるをえなかったわけですね」
「ただ政治的な問題がありました。日本政府の主張は、あくまでもオロボ島、春勇留島は、日本の領土です。実効支配されているとはいえ、ロシア領だとは認められない。合弁に日本企業が加わることに関して、政治的な意味を一切もたせないという条件が経産省からつけられました。つまりオロテックへの参加とレアアースの生産は認めるが、それがロシア領産だとは認めない。あくまでも民間の経済行為にとどめ、対中外交でレアアースをカードに使われない保険のひとつとする」
「でも中国も合弁に参加しているのですよね」
「広東省に本社のある電白希土(でんぱくきど)集団という企業が入っています。六大グループと呼ばれる中国のレアアース集団のひとつです。ただ技術提供という条件ですから、生産されたレアアースに関しては、日本、ロシアと同等の権利しかもちません」
黙っていると、稲葉がいった。
「少し理解できたか」
「一種の三すくみですかね。領土を主張するロシア、生産技術の中国、エネルギー供給の日本」
「おっしゃる通りです。島内の住民はほぼオロテックの社員で、このうちロシア人は島南部の海底にある漂砂鉱床からの採掘と運搬、居住施設の運営などの作業にあたり、中国人が選鉱、分離、精製、日本人が発電というすみ分けができています。人数も、百、百三十、百十と、ほぼ同じくらいです」
「公務員はいますか」
「ロシア国境警備隊の人間が数名常駐していて、私がいた当時は、グラチョフという少尉が指揮をとっていました。三十そこそこの若い将校です。オロボ島がロシア領だと、我々日本人や中国人に思いださせるだけのためにいるようなもので、仕事など何もありませんでした」
「社員はずっと島に缶詰ですか」
「我が社は六ヵ月交代でローテーションを組んでいますが、ロシア人や中国人には一年、あるいはそれ以上の任期できている者もいます。三日以上の休暇がとれれば、だいたいユージノサハリンスクや根室に向かいます。船だとユージノサハリンスクまで二十四時間、根室まで二時間です。緊急の場合や要人の移動にはヘリを使い、ユージノサハリンスクまで二時間、根室には十五分ほどで到着します。島にはロシア人ドクターのいる診療所がありますが手術などの設備はないので、根室に患者を空輸していました。食料品は北海道とサハリンの両方から運ばれます」
「気候はどうなんです?」
「六月から九月までは、過しやすいといえます。残りの八ヵ月は冬です。特に十一月から四月は雪と氷の世界です。海に囲まれているので最低気温がマイナス何十度にもなるのはまれですが、一月二月は、平均気温でマイナス四度五度といった気候です。夏は霧がよくでます。あとは風が強い。ひどくなるとヘリも飛べません。夏場は釣りなどをする人間もいますが、冬は外にほとんどでなくなる。娯楽というと、ビリヤードや麻雀、ダーツ。あとは映画を部屋で観るか、酒を飲むくらいです」
「酒場はあるのですか」
「港の近くにロシア人の経営する酒場が何軒かあります」
稲葉がテーブルに書類を広げた。地図だった。
「ご覧の通り、オロボ島は英語のHを歪(いび)つにしたような形をしています。東西、南北はそれぞれ約五キロで、Hの上側のくぼみが天然の良港になっていて、小型の船舶は接岸できます。大型船の場合は沖に停泊して艀(はしけ)でいききすることになる。このくぼみの部分を囲むように西側が中国人区、中央にロシア人区、東側に日本人区という具合で集合住宅が設置されており、酒場や食堂などはロシア人区に集中しています。分離や精製をおこなうプラントはHの左のたて棒に、発電所は右のたて棒の下半分に建設されています。また下のくぼみ部分に選鉱場とつながったパイプラインが海に向かってつきでており、南部の海上プラットホームから運んでくる鉱物を流しこんでいます。これらの輸送作業はほぼロシア人社員の仕事で、ヘリや船を動かしているのもロシア人です」
地図を指さして安田は説明した。
「プラントは二十四時間稼動しており、従業員は三交代で勤務しています。海上プラットホームは全部で三基あり、お盆が浮いたような形で、その中心からストローのような管を海底におろし、鉱石を吸いあげています。鉱石といっても実際は泥状で、それを選鉱し、分離、精製するのがプラントの作業になります」
「先ほど大型船は接岸できないといわれましたが、パイプラインにはどうやって船をつけるのです?」
興味を惹かれ、私は訊ねた。
「島の南部のほうが水深があるので運搬船を近づけることが可能なのです。ただ地形的には切りたった崖で、パイプラインを垂直におろして、運搬船のタンクにつっこむことはできても、人や物が上陸するのは北部の港からでないと不可能なんです」
「ひとつうかがってよろしいですか」
稲葉がいった。
「どうぞ」
「その北部の港ですが、大型船の接岸ができないのなら、生産されたレアアースはどう運びだすのですか」
「精製されたレアアースは砂状で、ことにネオジムなどは年間の生産量で千トンくらいです。艀でピストン輸送しても充分間に合う量です」
「それで採算がとれるのですか」
「ネオジムのトンあたりの輸入価格は、過去十年で安値のときで五万USドル前後、最も高かった二〇一二年は十六万USドルです。千トンなら五千万ドルから一億六千万ドルということになります。さらに精製されるレアアース鉱石にはネオジムより価格の高いジスプロシウムなども含まれますし、他にもランタンやセリウムといったレアアースも採取されますから、原子力発電所の建設費用を含めても、採算がとれないということはないと思います」
「なるほど。納得しました」
「こっそりもちだすような輩はいないのですか?」
訊いた私を、稲葉は咎めるような目で見た。
「すみません。ふだんつきあっているのが密輸とか密売を商売にしている連中なんで、つい下品なことを考えてしまうんです」
「世界中で生産されているレアアースをすべてあわせても十万トン強です。価値はあっても市場は決して大きくありません。盗んでも売る場所がない。盗品だとすぐバレてしまうでしょう」
「金やダイヤとはそこがちがいますね。誰にでも価値があるわけではないし、麻薬のように非合法な市場が最初からあるのでもない」
稲葉がいった。
「ええ。もしかすると、中国国内などには、盗んだレアアースを買いとるような商社があるかもしれませんが」
私は頷いた。稲葉を見る。稲葉は一瞬私を見返し、安田に目を向けた。
「まだ石上君には話していません」
安田は大きく息を吸いこんだ。上着から携帯をとりだす。
「実は、二日前に私の後任で発電部門の責任者である中本君から連絡がきて、当社から出向している人間が変死した、と。国境警備隊が処理にあたっているが、社員に動揺と不安が広がっている。何かいい方法はないかと相談をされました」
「変死、ですか」
安田は携帯をいじった。画面に写真が浮かんだ。
水色のジャンパーを着た男の上半身が写っている。両目がなく、かわりに赤い穴があいていた。背景は、岩山のような屋外だ。
「西口という社員でした。死因の調査も含め、遺体を根室に搬送するようにいったのですが、国境警備隊が許可をださないようなのです。オロボ島に警察署はありませんし、対処する機関となると確かに国境警備隊なのですが、警備隊といっても実際は軍隊です。死因を調べることなんてできません。ご覧の通り、西口が事故や自殺でこうなったとは、とても思えません。正直、誰かに殺されたとしか考えられない」
私は稲葉を見た。無茶だ。捜査一課にいたことはないし、鑑識の経験もない。
「日本から警官をさし向けることはできない。ロシアが実効支配している土地に、日本人の警官が乗りこんで捜査をすれば国際問題になる。そのことは安田さんに申しあげた」
稲葉はいった。
「承知しております。といって、このまま放置してもおけません。万一また誰かが殺されるようなことになったら、オロテックからの引きあげを考えざるをえなくなる。ですから何らかの形で抑止というか、社員を安心させるためにも、調査にあたる人間をさし向けていただきたいと考えているのです」
私は息を吸いこんだ。
「それはかたち上、ヨウワ化学の社員としてこの島にいく、ということですか」
「はい。ですがうちの人間には刑事さんだということを話します。それだけでかなり安心すると思うのです」
「実際に犯人がつかまらなくても?」
私は安田に訊ねた。
「いや……。それは、できれば犯人をつかまえていただければ助かります。しかし三百四十人いる社員全員に訊きこみとかは大変でしょうし……」
「国境警備隊はそうした調査をしていないのですか」
「遺体を監視下におく以外は今のところ何もするようすはないそうです」
「最寄りの警察はどこです?」
私は稲葉を見た。
「距離的には根室警察署だが、政治的にはサハリン州のユージノサハリンスク警察だ。ただ被害者は日本人だし、国境警備隊が管理している島に、二十四時間かけて警官を送るかどうか」
「オロテックの微妙な立場もあります。ロシアが実効支配する地域でプラント0を稼動させていますが、日本の主張もわかっているわけで、さらにそこに多くの中国人もいます。警官を送ることには慎重にならざるをえないと思うのです。国境警備隊が調査らしい調査をおこなわないのも、あるいはそれが理由かもしれません」
安田はいった。
「といって放置していて、第二第三の犠牲者がでないとも限らない。石上君は知っていると思うが、殺人事件はほとんどの場合、加害者と被害者のあいだに密接な関係がある。友人や家族、恋人といった人間関係の中で発生するのが大半だ。つまりヨウワ化学工業の社員の中に犯人がいる確率が高い。石上君がいって捜査にあたれば、あるいは簡単に犯人をつきとめられるかもしれないし、そうでなくても次の犯行を犯人がためらう理由にはなる、ということだ」
「その中本さんという方には、犯人の見当はついていないのですか。殺して両目を抉るというのは、かなり恨みのある人間がやることだと思いますが」
私はいった。
安田は首をふった。
「それが西口は、オロテックに出向してまだひと月足らずで、そんなに親しい人間もいなかったようです」
「死体はどこで見つかったのですか。画像によると屋外のようですが」
私は訊ねた。
「日本人区から少し離れた、島の東側の海岸で、三月十日に発見されました。砂浜もあることから、散歩する人間がいます。死体を見つけたのも、散歩をしていた中国人だということです」
「発電所も当然、二十四時間、操業しているのですよね」
稲葉の言葉に安田は頷いた。
「三交代制で、常時三十人が施設内におります」
「犯人をつかまえるといっても、その島で私に逮捕権はありませんよ。国境警備隊にひき渡すのですか」
私は稲葉を見た。
「それに関しては、犯人が判明した段階で、検察や法務省と相談、ということになるだろう。重要なのは、オロテックに出向しているヨウワ化学の社員に安心感を与えられるかどうかだ。君がいるあいだ第二の事件が起きないだけでも効果がある」
稲葉は私を見返した。
「いるあいだって、どれくらいの話です?」
「とりあえず三ヵ月でどうだ」
私は目をむいた。
「失礼」
私の顔を見た稲葉は安田に告げて、会議室の外へと私を誘った。
「無理です。鑑識にいた経験もなければ、殺人事件の捜査だってしたことがない。何の役にも立ちませんよ」
廊下にでると小声で私はいった。稲葉は私のことは見ず、ブラインドのおりた窓に目を向けている。
「捜一の経験者を送って、通訳をつけたほうが絶対に結果がでます」
「通訳を介して、ロシア人や中国人に訊きこみをおこなうのか。自分が警官だと宣伝するようなものだ。そんなことになれば、ロシア側も警官を送ってくるだろう」
「それでいいじゃないですか。政治的にはユージノサハリンスク警察の管轄なのでしょう?」
「だがもともとは日本固有の領土だ」
私は天を仰いだ。
「それなら自衛隊といっしょに上陸しますか。第二次日露戦争の勃発ですね」
「真面目な話をしているんだ。この事案については、外務省や内閣官房も重大な関心を寄せている」
「じゃあそっちに任せましょう」
「現役警察官がいくことが重要なんだ。オロテックに出向している日本人に安心感をもたらすことが第一。刑事がいると伝われば、空気がかわる」
「いじめかもしれないというのに?」
私はいった。
「いじめ?」
「三ヵ国の技術者が小さな島に押しこめられているんです。精神的に不安定になる奴がいて不思議はない。だいたいそういうところでは新人がいじめの対象になります」
「目をくり抜くのがいじめか?」
「自殺したんです。それを動物がつついたか、いじめを隠そうと考えた誰かがやった」
「よく考えているじゃないか。それくらいの勘が発揮できれば、犯人をつかまえられる」
「つかまえてどうするんです? 日本に連れ帰って裁判にかけるのですか」
「日本人なら可能だ。釧路地裁の根室支部がある」
「私の権限は? 何もありません」
「根室警察署にフォローさせる。かたち上、自首でもかまわないし、民間人の君が逮捕したことにしてもいい」
「私人逮捕は現行犯、準現行犯に限られます」
私がいうと、稲葉は私の顔を見直した。
「いくのが嫌らしいな」
「一年の三分の二が雪と氷の世界の島に、警視庁警察官の身分なく三ヵ月間おかれ、やったこともない殺人事件の捜査にひとりであたるんですよ。わくわくして、また吐きそうです」
「そういう減らず口を叩けるところを買っているんだがな」
「今日のところは見逃してください」
「内閣官房に、適任者がいると部長が太鼓判を押したらしい。ロシア語と中国語に堪能で、潜入捜査のベテランだ、と。組対の部長が官房長官にお目通り願えることなんてめったにない、外務省の鼻も明せるってんで、張りきったみたいだ。君が断われば、部長のメンツはまる潰れだ。それはそれで喜ぶ人間はいるだろうが、君の骨を拾ってまではくれんぞ」
「脅迫ですか」
「もうひとつ香ばしい情報がある。ボリス・コズロフが飛んだ。港栄会の知り合いに、『スーカを殺せ』といいおいて」
スーカとはメス犬、つまりビッチのことだが、警察の犬という意味もある。
「港栄会に刑事をつけ狙う度胸があるとは思えないが、コズロフの手下には無茶をする奴がいるかもしれん」
「この場で吐きます」
「三ヵ月の転地療法だ。気分もよくなる」
私は大きく息を吐いた。
「内閣官房の機密費から特別手当もでる。うまくすれば国家安全保障局にひっぱってもらえるかもしれん。悪くても、内調の目はある」
「よくそう簡単に、嘘をつけますね」
私は稲葉を見た。
「今日あるを見越して、君をひっぱったのさ」
すました顔で稲葉は答えた。
「考えさせてください」
「三日やる。水曜には現地に飛んでもらいたい」
「三ヵ月いなくなるのに、三日しか準備をさせてもらえないのですか」
「準備なんてものは、限られた時間の中でおこなうもんだ。そうだろう」
稲葉は、私を会議室の扉へと押しやった。