|
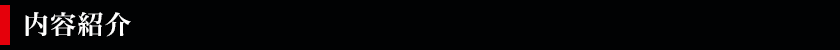
| 人類学者の河鍋未來夫は講義の最中に突如全裸となり、停職処分に。彼の研究テーマは裸体主義であり、自身もヌーディストだった。その未來夫のマンションに、未來夫に賛同する仲間が訪れる。マンションの外では未來夫のスキャンダルを追う、週刊誌記者の田原が張っていた。ある深夜、田原はついに堂々と全裸でマンションから出てきた未來夫らをキャッチするが、何故か彼らは田原の取材車に勝手に乗り込んで……その道程でも続々と新たなシンパが裸体行脚の仲間に加わり、彼らはともにある「島」を目指すことになる。島には未來夫の妻・研究者のマリアがボノボの「アムニ」を連れて先に移住していた。そこでは人類史に新たなる1ページを刻むべく、ある壮大な計画が行われていた――。 |
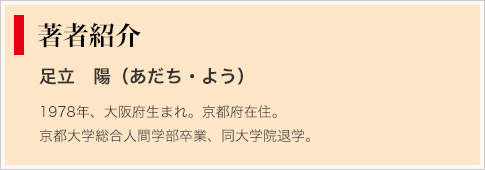
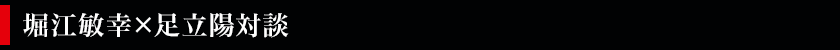

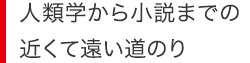
大学の講義中に全裸になり停職処分を受けた人類学者・河鍋未來夫教授。彼はヌーディストだった。未來夫を案じて彼のマンションを訪れた、美術系ヌードモデルのミチと、ヌーディストキャンプで知り合った男二人、ソーとナリ。全裸の四人はある深夜、教授のさらなるスキャンダルを狙い張っていた週刊誌記者・田原を巻き込み、彼の車で〝ある「島」〟を目指すことに。そこでは、ボノボの「アムニ」とともに先に移住していた未來夫の妻・マリアが、「人類」に関するある壮大な構想を企てていた──。
第38回すばる文学賞受賞作『島と人類』は、人類学者が主人公。強硬なヌーディストでこそないものの、著者の足立陽さんもかつて大学院で人類学を研究されたという経歴の持ち主です。受賞作刊行にあたり、同賞選考委員・堀江敏幸さんをお迎えし、人類学をはじめ、ヌーディズム、海外文学など、幅広くお話しいただきました。
| 構成=宮内千和子/撮影=chihiro. |
堀江 御受賞おめでとうございます。
足立 ありがとうございます。
堀江 受賞作『島と人類』を最初に読んだとき、人類学の話が出てきますし、海外文学をよく読まれている印象もありましたので、著者はどんな方だろうと思っていました。選考会では高評価が得られた一方で、何か引っかかるとの意見もありました。僕は、その引っかかりに魅力を感じて手を挙げたわけです。
引っかかりとは、言い換えれば書き手の側の積み重ねということでもあります。この作品には、小説を書きたいという思いに加えて、小説で何ができるかという思索とそれをどう書くかという試行錯誤の痕が見え隠れしています。おそらく、いろいろ試してうまくいかなかった過去の作品を統合したような、これまでの足立さんの集成というか、個人的な総合小説の趣がある。小説を書かれたのは、初めてではないですよね?
足立 はい、今回が六作目になります。
堀江 足立さんは大学院で人類学の研究をされていた。小説中にも、アカデミズムの中にいなければわからないくすぐりが出てきます。学問の内側から小説という表現形態へと、どのように辿りついたのか、今日はまずその話をお聞きしたいですね。
足立 人類学を始めたのは大学院に入ってからです。研究していたのは、主に北インドの農村部や巡礼地の宗教実践なんですが、さあやるぞとなったときすでに「人類学は終わった」と囁かれ出して早十余年、というような段階でして(笑)。ミシェル・レリスという作家兼民族学者がいます。彼はフランス人類学創成期のアフリカ調査を斜めから見て、著名な人類学者がろくに現地人と交流もせず、テントに引きこもってそれらしいデータを書き上げていく様子を日記の形で暴露しました。
八〇年代以降、レリスの読み直しとともに、人類学の自己批判が進みます。現地人と人類学者の非対称な関係は、近代アカデミズムの権威に正当性を付与されているにすぎない、というわけです。
堀江 アカデミズムの権威というのは、建前なんですね。
足立 その側面は否定できないと思います。そこには、ともすると卑怯な嘘や欺瞞が構造的に含まれてしまう。それに対して、実験的民族誌というジャンルがありまして、僕自身、他者化してゆく自己を描き込めないかと、あれこれ多声的なテクスト実験を試みたりしました。でも結局、僕の手には負えなくて。悩んだ末に研究をやめて、二年くらいインドで暮らしていたんですが、あるときふと思ったんです。はじめからフィクションとしてなら、良心の呵責に苦しまずに自分がリアルに感じていることが書けるんじゃないかと。
堀江 思考転換をした。
足立 はい。たとえば、カルロス・カスタネダという人類学者の著作などは、もはや民族誌のテクストなのか小説なのか分類不能ですよね。ああ、こういう方法もありなんだと思考転換できた。ところがそこから小説を書くところまで、頭で考えるとあと一歩のはずなのに、人生そうそう都合よくは転びませんで、四年ほど試行錯誤の連続でした。

堀江 そうでしたか。僕がいい意味で足立さんの作品に引っかかったと言ったのは、そういう蓄積や悩みが一旦整理されないと出てこないような書き方だと感じたからです。最初はフィールドワークのノートの形でフィクションを重ねていく方法を取っていた。その蓄積の中で、何作目ぐらいから物語のほうにぐっと飛躍したと思いますか。
足立 とりあえず今までの五作は、どうしようもないがらくたですね。今回は、ある種の膂力をためて飛ぶぞみたいな感じで、このテーマに飛びつきました。
堀江 「裸」一貫から。
足立 はい。自分の頭の中の自意識も、一回全部捨て去って何かを始めないと、このままじゃだめだと思ったんですね。
堀江 たしかに『島と人類』には、一回捨てようという感じの人物ばかり出てきます(笑)。
足立 そうそう(笑)、出てきます。
堀江 今回のテーマの一つ、ヌーディズムに結びつくきっかけのようなものは、何かあったんでしょうか?
足立 きっかけは、ある古本屋で偶然手に入れた本です。ぱっと開いたら献辞が書いてあって、そこに裸のおじさんの写真が貼ってあった(笑)。どうも熟年ヌーディストの写真らしくて、八〇年代後半の日付がついていて、僕は初めてこういう人たちの存在を知ったわけです。興味を持って調べてみると、ヌーディズムというのは必ずしも性的放埒なものじゃない。むしろ性的禁欲のほうなんですよ。
堀江 なるほど。
足立 ヌーディスト自体は、ダイアン・アーバスやラリー・クラーク、ライアン・マッギンレーといった写真家がよくモチーフにしています。アーバスなんかは、自分も全裸になって首からカメラひとつ下げて、ヌーディストのキャンプに潜入して写真を撮っている。彼女の文章によると、そこには厳しい掟が二つあります。一つは、男性は絶対に勃起してはいけない。もう一つは、男女を問わず相手の身体をじっと凝視してはいけない。これって、簡単なようですごく難しい、ある種オルタナティブな道徳観念みたいなものだと思いました。一見馬鹿馬鹿しいようでいて、実は高度な自律性と共同性が求められる。
堀江さんが選評で挙げて下さったミシェル・ウエルベックは、ヌーディストの実践をのぞき見て欲情してしまうみじめな中年男の姿を描いていますが、性的放埒と性的禁欲が一つの裸体の上に重なっていく眼差しが、おもしろいなと思ったんです。
堀江 今名前が出てきましたが、足立さんの作品を読んだとき想い浮かべていたのは、ウエルベックの『ランサローテ島』や『素粒子』の世界でした。とくに後半、「島」へ向かうあたりで、絶対ウエルベックがお好きだろうと確信しました。彼の小説では、欲情と生殖とを分けて、遺伝子操作によるクローンが次世代をつくっていくわけですが、この作品は、人間の女性とボノボが新人類をつくるんですね。この設定にもウエルベックへのオマージュをすごく感じました。
足立 『素粒子』や『ある島の可能性』など、すごく好きですね。ずっと、僕みたいな人間には、オーソドックスな恋愛や官能小説のようなものは絶対に書けないと思っていたんです。だけどウエルベックを読んで、裏側からこんなふうに性愛を描く人がいるのかと、すごく衝撃を受けまして。僕の感じるリアリティに近いなと思ったんですね。
堀江 それは小説の形式というより、発想や精神的なあり方に対する親近感ですよね。
足立 ええ。生き方のスタンスに共感したりして。
堀江 でも、ウエルベックの小説は、ショーペンハウアー的な哲学的命題を持ち出して、どんどん暗くなっていきますが、足立さんの作品は陽性です。じめじめとした感じがなくて、すこーんと抜けた「青い空」のような。島に行きつく前に、「あおいそら」(蒼井そら)を連呼する場面がありますが、ここには本気で裸になろうとする人たちのあいだでしか成り立たない、美しい絆がある。その明るさが、この小説の一番の魅力ですね。
足立 ありがとうございます。ウエルベックは大好きなんですけど、随分上の世代の、あくまでヨーロッパの白人男性の特殊なセクシュアリティだなという点で、違和感も感じるんです。もちろん彼はすごく意識的にそうしているわけですが。この間初めて秋葉原へ行ったんですね。すると、二次元のエロ漫画ばっかりが所狭しと並ぶ部屋に迷い込みまして。これは性愛と生殖の分離の最終形態ではないかと思ったわけです(笑)。たぶん描き手は男ばかりだし、実体としての女性はもはや必要ですらない。だからこそ満たされるようなタイプの欲望なのだとしたら、それで自足してそこそこ楽しく生きていけるんじゃないか。少子化問題は絶望的ですけど(笑)。

堀江 この作品には面白いところがいっぱいあります。あまり難しい話ばかりしていてもしょうがないので、話を替えましょう(笑)。例えば、作中にベジカレーを食べる場面がありますね。
足立 はい(笑)。
堀江 とてもおいしそうなんですが、御自身もお好きなんですか?
足立 ええ、好きですね。
堀江 たいていお米で代用してしまうところで、ナンもちゃんと焼いている。ふだんは、自分でも焼いておられるんですか?
足立 チャパティをそのまま焼いて。僕、この十年ほどずっとベジタリアンのインド流食生活をしてたんですが、日本で生活していくためにある会社に就職したときの歓迎会が、あろうことか焼肉屋さんでして。「実は僕ピュアベジで」とはさすがに言えなくて、そこから決壊が始まりました(笑)。
堀江 崩壊したんだ。それはきつかったですね。でも食べる場面にはリアリティがあります。それから、田原という雑誌記者の悲しい過去のエピソードに、結構笑わされたんですけれど、あれはどういうところから発想されたんですか。
足立 あれも単なる思いつきなんです。
堀江 思いつきですか。子どもの頃に蟯虫検査のPRキャラクターとしてテレビCMに出ていたその人の、蟯虫の検査が陽性だったって(笑)。蟯虫検査なるものを体験してきた世代なので、懐かしさと、恥ずかしさと、空しさが同時に迫り来るようなおかしさを感じましたね。田原はそういうトラウマを脱ぎ捨てなければいけない。
『島と人類』という小説には、田原をはじめ、脱ぎ捨てなければいけない人が何人も集まってきている。このヌーディストたちが求めているのは、じつは服を脱ぐことではない。それが最後までぶれていないと思います。
足立 ありがとうございます。
堀江 ボノボを相手に次世代の人類をつくろうという、教授の奥さんのマリアさんは、日本人ではないですよね?
足立 一応アメリカ国籍ということで。
堀江 つまり、すでに混血であると。そこに何か意図があるんですか。
足立 後づけなんですが、周囲を赤旗の船団が跋扈するあの島に、日本人だけが行くのはまずい気がして(笑)。
堀江 違う血が入ったほうがいいと?
足立 なるべく国際的にしておこうと。
堀江 領有権の問題はあっても、どこにも属さないような島が偶然にせよ日本の近海にはあって、そこを舞台にした。設定がよかったですね。
足立 ある意味ラッキーでした。
堀江 いくら新しい島でも、あれが今噴火している西之島では危険すぎる。他に無国籍な土地といったら、南極や北極、あるいは宇宙しかないわけでしょう。一方で、島への憧れ、あるいは島をめぐる想像力は、未来よりも過去へ向かうことが多い。太古の生き物が棲息しているイメージですね。ゴジラとか恐竜とか。でも、そこで人間が新しい種をつくろうとする発想は、すごいなと思います。
足立 何とかこじつけようとしていたら、たまたま辿りついてしまったという感じですが。
堀江 ただ、課題もある。例えばこの小説にあるような新人類が本当に出現して、さらに世代が重ねられたとき、彼らがどのような喜びと苦しみを感じるのか。それを、すぐにではなくても、いつか書かなければならない(笑)。しかもその物語は、現在の日本語ではない、新しい言語にしないといけないわけです。
足立 はあ、難題ですね……。
堀江 アメリカの言葉が入っているマリアさんとボノボのあいだの、クレオール的な言語で。その意味でいえば、足立さんの発想は新しい言語小説の可能性を秘めている。ぜひ実現してください。
足立 頑張ります。この物語のその後を考えてみたんです。ボノボの血を引いている新種の人類は、きっとあり得ないほどの性欲の持ち主なんですね。すると、この国の少子化問題は意外な形で解決するのかもしれない。でもその新種が見えない形で増えていくとなると、社会が動揺して、とんでもない差別や優生思想を生む可能性もある。歴史は繰り返す。ただし二度目は茶番として、みたいな。
堀江 ウエルベックも突き詰めれば優生思想をテーマにやってきていますよね。よりよい人類をつくるという考え自体が優生思想なわけですから。どう生き延びることができるのか、その可能性のなかにある一つの矛盾です。同じ土壌の中にボノボ化している人もいれば、先細っている人もいる。そこでどんな共通言語を見つけ出せるのかが鍵になる。
足立 異なるものをつなぐ言葉ですね。
堀江 先ほどの「青い空」こと、AV女優の蒼井そらさんの存在もひとつの共通言語かもしれない。国境を超えて、作中の男ならみんな知っている気象なわけですから(笑)。あの海上でのように、突然降って湧いたような共通言語に出会えるかどうか。
足立 はい。僕の小説の問題点は、最初に全体のプランとか全然なくて、浮かんだアイデアの四角いユニットを積んでいくような書き方なので、いつも言葉が後づけになるんです。堀江さんの小説を読ませていただいてすごいなと思うのは、小説全体の流れがあって、その中に言葉が言葉を生む運動がある。川の中で転がっていく石が、だんだん角がとれて丸くなっていくような。そういう文章の書き方にすごく憧れがあります。
堀江 非常にありがたいお言葉ですが、うまく流れる川に行けるとは限らないわけで、場合によってはずっと底に沈んでいなければならない。小説には、どこに進むかわからない霧の中を手探りで行くような姿勢も大切ではないでしょうか。
足立 その霧の中で何ができるか、模索してみたいと思います。
| 「青春と読書」2015年2月号掲載から |
COPYRIGHT (C) SHUEISHA INC. ALL RIGHT RESERVED.