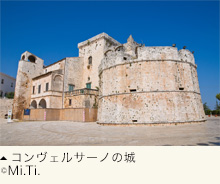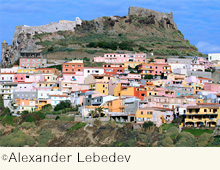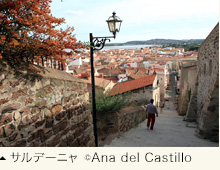『カテリーナの旅支度 イタリア二十の追想』著者:内田洋子
定価:1,600円(本体)+税 10月4日発売

☆経済ではなく文化ありき

☆町に惹かれて、人に惹かれて
(了)
人物撮影/chihiro.
編集協力/中嶋美保
 内田洋子(うちだ・ようこ)
内田洋子(うちだ・ようこ)
●1959年兵庫県神戸市生まれ。
東京外国語大学イタリア語学科卒業。
UNO Associates Inc.代表。2011年『ジーノの家 イタリア10景』で日本エッセイスト・クラブ賞、講談社エッセイ賞をダブル受賞。
著書に『ジャーナリズムとしてのパパラッチ イタリア人の正義感』『ミラノの太陽、シチリアの月』『イタリアの引き出し』、翻訳書に『パパの電話を待ちながら』などがある。
 陣内秀信(じんない・ひでのぶ)
陣内秀信(じんない・ひでのぶ)
●1947年福岡県北九州市生まれ。
東京大学工学部建築学科卒業。
73年~75年にかけて、イタリア政府給費留学生としてヴェネツィア建築大学に留学、翌年にはユネスコのローマ・センターに留学した。83年東京大学工学博士。
90年法政大学デザイン工学部建築学科教授、07年法政大学デザイン工学部教授。イタリアを中心にイスラム圏を含む地中海世界の都市研究・調査を行う。
著書に『都市のルネサンス―イタリア建築の現在』『ヴェネツィア―水上の迷宮都市』『南イタリアへ!―地中海都市と文化の旅』『イタリア 小さなまちの底力』などがある。
*陣内秀信さんの講演情報
担当編集テマエミソ
その本に出会ったのは、旅行ガイドブックコーナーでした。
講談社エッセイ賞と日本エッセイスト・クラブ賞をのちに受賞することになる、内田さんのエッセイ『ジーノの家』のことです(今現在は、ほとんどの書店で、通常のエッセイ
本コーナーにも置いてあるようです)。
微妙なブルーのシックなカバーは、色の氾濫する各国各地のガイドブックの中で、独特の存在感を放っていました。静謐感に包まれてひっそりと、でも力強く。
イタリアに暮らす人々の日常と息遣いが、繊細かつ鮮明に描かれたその内容に、読んですぐ引きずり込まれました。
ステェファニア、ブルーノ、パトリツィア、ルチア。
ミラノ、シチリア、リグリア。
知らない街に生きる、知らないイタリア人たちが、まるで旧友か隣人でもあるかのように、くっきりと残像を残していく――。
もっと知りたいと強く思いました。イタリア在住30余年の内田さんが知るイタリアを、イタリア人たちを。
そして出来上がったのが、こちらの『カテリーナの旅支度 イタリア 二十の追想』です。
裏キーワードは「モノ」。鞄、本、椅子、ヨット、哺乳瓶など、取り上げられている「モノ」は多岐にわたります。モノを通して見える人々の思いや人生が、さりげなく、でも、思いもかけない方向から照射されているのです。
読み手はやがて気づくでしょう。大切にしているかどうかにかかわらず、自分の身の回りの「モノ」には、それぞれに物語がつきまとっていることを。
遠い異国に暮らす外国人のエピソードでありながら、自分に置き換えて、我が身の半生、過去、思い出を見つめなおすきっかけとなる20篇。どこかに、あるいは登場人物複数に自分を重ね合わせることが、きっとあるはずです。
縁あって、ミラノからヴェネツィアへ短期間の予定で引っ越した内田さんに、かの地でお会いする機会がありました(この引っ越しにまつわるエピソードは、本文「ヴェネツィアで失くした帽子」をお読みください)。
サン・マルコ広場そばの待ち合わせ場所のホテルの前で、内田さんは佇んでいらっしゃいました。静かに、でも力強く。
瞬間、『ジーノの家』との出会いを思い出しました。一見、クールでシック、でも中味はあたたかく、深く、熱い。
お書きになるものの目線そのもの、内田さんのお人柄に助けられて、ヴェネツィアでご一緒した時間が忘れがたいものになったことは、言うまでもありません。
ヴェネツィアでも楽しい道案内をしてくれた、常に内田さんを見つめる美男子犬・レオン君は、新連載エッセイ初回を飾ります。
必読の内田さんの連載、こちらもお楽しみに。
(編集K)