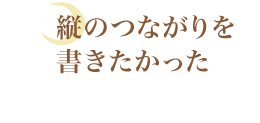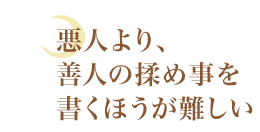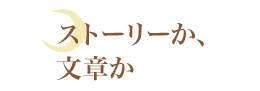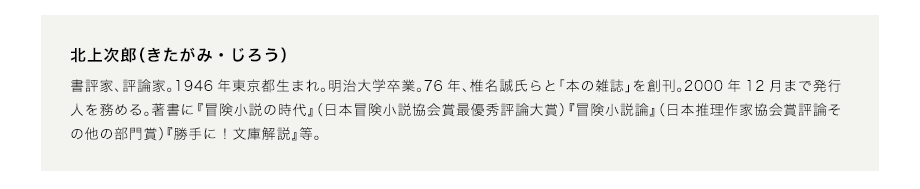森さんご自身は塾に通われていたんですか?
中学三年生のときに近所の塾に通ったくらいです。勉強熱心でもありませんでしたから、塾に対して良いイメージも悪いイメージもなかったんですね。一生懸命通った方ほど、塾には悪いイメージを持っているようですが、私は真っ白でした。北上さんはいかがですか。
全く通っていません。ただ、僕の時代は塾なんてなかったと思い込んでいたんだけど、この本を読んで、えっ、あったんだ! と。隠れて通っている子はいたのかもしれないと思いましたね。
世代や環境によって"塾観"ってかなり違って面白いですよね。本は小さいときから読まれていたんですか?
中学三年生まで全く読んでいませんでした。
そうなんですか!
今でもよく覚えています。中学三年生のときに、野球仲間が面白いと言っていた『点と線』(松本清張著)を貸本屋で借りて読んだんですね。これが面白かった。それから高校三年間で、その貸本屋の本を全部借りて読みました。
この経験でわかったんですよ、エンターテインメントの面白さというのは絵が動くことなんだと。だから、エンタメにはストーリーが大事とよく言われますが、僕は必ずしもそうではないと思っています。絵を動かすには文章やキャラクター、プロットの巧みさも重要ですから。
歳をとり、最近はとりわけ文章派になりました。文章が良ければストーリーはなくてもいいくらい。森さんはストーリーと文章をどのような比重で考えていますか。
どうでしょう……あまり分けて考えてはいませんね。自然と連動してくるというか、ストーリーによって文章の質感が変わってきますから、いつも最初に文体を捕まえるまでにちょっと手間取ります。今回の本で言うと、時代に合った言葉を選ぶようには心がけました。吾郎の時代にはできるだけ片仮名を使わないとか、一郎の時代になると今っぽい言葉が出てきてもいいなとか。その辺の微調整はしました。
書く前に、ストーリーのプロットはつくられたんですか?
初めての長編連載だったので、ある程度はつくりました。ただやはり、書いていくうちにどんどん変わっていきましたね。
タイトルも素晴らしいですね。読み終わってはじめてすべての意味がわかるというタイトル。
なるべく広く受け止められるタイトルにしたいということと、字面が綺麗だと自分もテンションが上がるなと、そのくらいで、深くは考えていなかったんです。連載初回の千明の言葉、〈学校教育が太陽だとしたら、塾は月のような存在〉〈今はまだ儚げな三日月にすぎないけれど〉という箇所から取ったんですが、そのタイトルを頭の隅に置くようになってから、色んな要素が「みかづき」にリンクしてきた気がします。
今後の展望はありますか?
やったことがないことをやりたいという気持ちは常にあります。
個人的な希望を言っていいですか。
はい。
僕、タイムトラベルものが大好きなんです。過去に行くか未来に行くかはどちらでもいいんですが、森さんがお書きになったらと想像しただけで……。
女性より男性のほうがタイムトラベルものが好きな印象があるのですが、どうでしょう。乗り物が好きだから?
確かに、近年のタイムトラベルものは『流星ワゴン』(重松清著)、『地下鉄(メトロ)に乗って』(浅田次郎著)など、男性作家ばかりですね。たぶん男にはもう一度人生をやり直したい、あるいは新たな人生を送りたいという願望があるんじゃないかな。
未来を書きたいな、という気はしているんです。未来が舞台の世界を考えていたのですが、タイムトラベルも仕掛けとして面白いかもしれません。あまり期待せずに待っていてください。
はい。でも僕、古希なので、書いていただけるならあまり待たせないでください(笑)。
(「青春と読書」2016年9月号より)