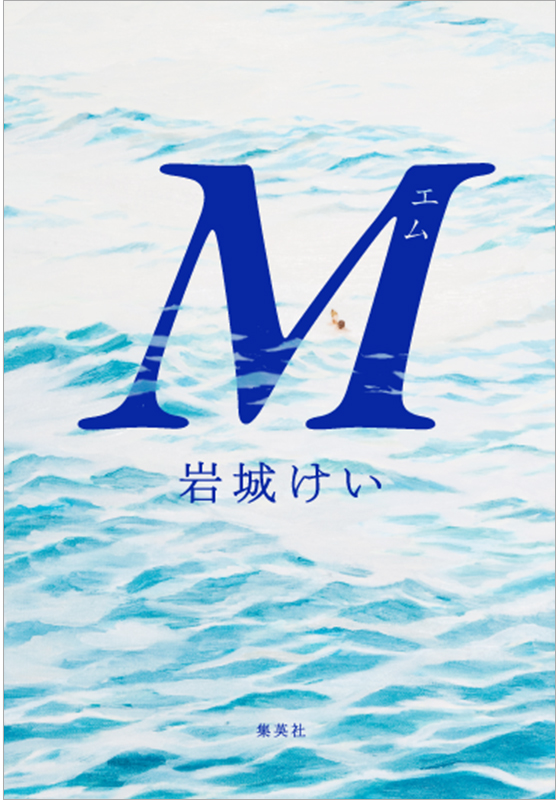『M』刊行記念対談 岩城けい×小島慶子「今の自分の居場所を求めて」

『Masato』『Matt』に続く三部作の完結編『M』が、この六月刊行されました。小学生の時にオーストラリアに移住した真人が、今作ではメルボルンの大学生として登場します。前二作で言語やアイデンティティの壁に阻まれ、家族・友人との関係に苦しんできた彼が、『M』ではアルメニア人の女の子・アビーという新しい個性と出会い……。
刊行を記念して、デビュー作『さようなら、オレンジ』から岩城さんの著作を読んでいらした小島慶子さんにご登場願い、お互いの作品や文化・教育における日豪の差異について語っていただきました。
構成/三宅香帆 撮影/神ノ川智早(岩城) 撮影/鈴木愛子(小島)
海外へ渡った家族の、その後
小島 『Masato』『Matt』『M』と、「アンドウマサト三部作」シリーズ、ほんとうにおもしろく拝読しました。我が家も、息子たちがオーストラリアに住んで、自分は日本で働くという生活をはじめてもう十年目です。だからこそ共感したところもあり、うちはこうじゃなかったなと感じたところもあり、いろいろなことを考えながら読みました。
岩城 ありがとうございます、光栄です。
小島 真人たちの一家の葛藤は本当にリアルでした。「子どものため」と思ってやったことが、結果として夫婦の間にひびを入れたり、家族それぞれが見る方向を違わせてしまう。
岩城 そうですね。「英語ができてほしい」とか「大学に入ってほしい」とか、親の願望って、全部悲しいくらいに子どものためなんですけどね。もちろんどの言語でも、どの土地でも、最終的には子どもが健康で幸せであればいいけれど、親はなかなかそんな俯瞰の視点は持てません。その時々は必死ですから。オーストラリアで様々なケースを見たり聞いたりする中で、子どものヘルスやウェルビーイングを考えたいなと思ってきました。
小島 海外移住が合うかどうかって、人によりますよね。帰国子女や英語圏で長く暮らした人がみな海外生活に適応できていたかというと、そんなことはない。子どもの頃に海外でいじめを経験したゆえに、大人になっても白人社会に対して非常にセンシティブになっているという例もたまに聞きます。前二作の『Masato』や『Matt』では真人も同級生にいじめられていました。
岩城 お母さんは「子どものため」と現地校に無理やり行かせ、英語を習得させようとしたけれど、子どもにとってそれはハッピーな経験ではなかった、という話も聞きますよね。
小島 私は父の転勤先だったオーストラリアのパースで生まれたのですが、70年代に現地で出産した母は、私を一人抱いて海辺まで車を飛ばし「もう日本に帰りたい」って泣いたそうなんです。だから「真人シリーズ」を読みながら、母のこともずいぶん考えました。駐在妻として三百六十度他人に気を遣いながら、本当に胃が痛くなるような思いをして暮らしていた母の姿を、私は子どもとして見ていた。でもきっと、今でも同じような苦しみを抱いている駐在員の方々もたくさんいますよね。
岩城 私もたまに駐在員さんと交流することがありますが、お話を聞く限り、日本よりも日本らしいお付き合いが待っていますよね。それで苦しむ方は非常に多い。昔、「日本に帰りたい」と言う奥さんと知り合いになったのですが、夫が妻のパスポートを毎日持ち歩いていたんですよ。奥さんに一人で帰られてしまうのではないかと怖がって。
小島 中には、駐在員として海外に住んでいるけれど、帰国後にわが子を東大に入れることしか考えていない人もいるという話を聞いたことがあります。海外にいるからこそ、日本社会に後れを取らないようにと焦ってしまうという。
岩城 そうかと思えば、駐在員生活をエンジョイしている方もいらっしゃったりしますけどね。それは人それぞれです。
小島 そうですね。ちなみに当時「日本に帰りたい」と泣いていたという私の母は、オーストラリア生活を振り返るたびに、「本当にすばらしいところだった」と言うんですよ! オーストラリアの自然が彼女に与えた安らぎとか、異国での暮らしが彼女に与えた自由も、たしかにあったんです。でも同時に、日本社会の縮図である駐在員コミュニティでの超濃密な生きづらさもあった。そのふたつが同居していたんでしょうね。
岩城 小島さんの書かれた『ホライズン』は、様々な事情でオーストラリアという地に辿り着いた女性たちの物語ですが、日本人の海外コミュニティについての描写がかなり生々しかったです。駐在さんと在住の違いがはっきりしていました。それから、自然描写や小道具の使い方もリアルだなあと。こういうふうに私は書けないので、驚きましたし、感心もしました。
小島 ありがとうございます。
岩城 この物語には三十代の女性がたくさん出てきますが、このくらいの年齢は一番悩ましい時期なのかもしれませんね。出産やキャリアについて人と比べたくもなる。そこに渦巻いているものを読める小説です。海外へ転勤になった男性に女性がついていく風習は今もありますし、そこで生活の変化に戸惑う描写もリアルでした。
小島 妻が夫の海外赴任に帯同するうえでの苦労を考えるとき、母の時代は駐在員コミュニティの生きづらさが主たるものでした。でも今の時代は、そこにキャリアが絡んでくる。私の周りでも、正社員として働いている女性が夫の転勤に帯同する際に、仕事をどうするかかなり悩ましいようです。「制度を組み合わせたら三年までは休めるんだけど、三年超えちゃうともう休めない。じゃあ、自分だけ日本に帰る? それとも会社辞めちゃう?」と。かつての女性たちとは、また違ったところに悩みどころがあるんです。今はそうしたケースに対応する企業も少しずつ出てきたようですが。
表現が救済になる
小島 岩城さんの作品はいつも、「母語ではない言語を使って、母国ではない社会で、どのように居場所を得ていくか」を描いていますよね。やっと英語を習得した真人は、今回の『M』で「じゃあこの英語というツールを使って、母国ではないこの社会でどう生きていくのか」を考えるフェーズに入っている。
岩城 そうですね。『M』で大学生になった真人にとって、もう英語の習得は目的ではなく、英語で何を表現するかが重要になってきています。英語を使って自分はどういう人間か表明する、どうやって社会に貢献するか、社会に溶け込んでいくかを考えている。そういう意味でも、語学は一つの重要なツールですよね。こちらに来た人が英語を話せるようになるのに、二年かかると言われるんですよ。でも書き言葉になると平均八年。だから小学生の時に移住してきた真人は、ようやく英語を習得し終わったくらいかな、と。
――演劇に興味を抱き続けてきた真人ですが、卒業後の就職活動にあたって「表現」を自分の仕事にするかどうかで悩む場面もありました。
岩城 彼は銀行員になろうとしているのですが、何かが違うと思っている。でも、やっぱりお金は必要なんですよね。オーストラリアでは年金制度がしっかりしているから、会社に勤めることには大きなメリットがあります。でも、彼は本当にそれでいいのか最後まで悩み続けている。彼にとっては「自分が誰なのか」を追求するためには、表現することが大事だったのだと思います。
小島 真人にとっては、演じること、すなわち表現がある種の救済になっていますよね。「母語ではない言語」を自分のものにするときは、その過程でどうしても苦しみが存在する。言語の壁は高く険しいですが、表現はその苦しみを救済してくれるというか……。そしてそれ以上に、言語の習得過程で、家族との関係に変化が生じてしまった苦しみに対する救済でもある。
岩城 嬉しい。すごくじんときました。
小島 岩城さんのデビュー作『さようなら、オレンジ』では、その救済が非常に美しい形で結実していました。今回の『M』でもまた「表現することは救済である」というテーマが描かれ、『さようなら、オレンジ』と通底するものがあるな、と拝読していました。
きっとこのテーマは、移民の方々に限った話ではないんですよ。日本で生まれて日本で生きている人にも通用するはずです。母語が同じ者同士でも、話が通じないことはたくさんあります。その結果「自分はこのコミュニティに居場所がない」と疎外感を覚えて、孤独を深めていく人はいくらでもいる。そういう意味で、『M』は決して海外生活を経験した人にしか分からない小説ではなくて……社会に居場所がなくて、他者と通じ合えている実感が持てない人にとって、「表現するとはどういうことか」を示す小説になっているんです。
岩城 ああ、それはまさにその通りかもしれません。昔、メルボルンでアウシュビッツ収容所にまつわる展覧会を観たことがあるんです。ユダヤ人の生存者が作ったアート作品がたくさん飾られているんですね。それらを観ていると、絵を描いたり表現したりすること自体によって心は慰められるのだ、ということがよく分かりました。ああ、やはり表現は心の救いになり得るんだな、と。
移民二世のアイデンティティと多様性の実現
小島 『M』のなかで、真人が自らアイデンティティの読み替えに成功したシーンとして、自分に振りあてられた「ステレオタイプな日本人の役」に対して、異議を申し立てる場面がありました。「人の言葉を馬鹿にするのは、その人自身を馬鹿にすることだ」と、真人がディレクターに向かって発言するところ。
岩城 ステレオタイプについては、私も書くかどうしようかと思ったのですが……なんだか最近、変なステレオタイプが広まってしまっている気がしていたんです。政府や企業が、ダイバーシティという観点から様々な人種を配置したコマーシャルをやっているでしょう。インスタントに「ダイバーシティを重んじていますよ」と表現するには、やっぱりステレオタイプが一番効果的なんですよね。みんなが「いろんな人種がいるな」ってすぐわかるから。でもそれによって広まるのって、けっこう典型的なステレオタイプなんです。それで真人もイライラしているのかな、とは思いました。
小島 でも、真人は自らそこに異議の申し立てをしますよね。彼の成長を感じたシーンでした。というのも、たとえステレオタイプな役であったとしても、自分に居場所が与えられることで安心してしまうことがあるじゃないですか。それは海外生活だけの話ではなく、たとえば飲み会でサラダを取り分けるような「女らしい」役を与えられることによって、居場所を得られて安心できる、というような話も同様です。これまで彼は「日本人」の役を与えられていた。当初はそれで安心を得られていたかもしれないけれど、『M』の真人はそこを自力で超えられた。他者から与えられたアイデンティティに甘んじるのではなくて、自らアイデンティティを読み直し、組み直していく。そうやって彼は与えられた役について「これはステレオタイプじゃないですか」と言い返すことができたわけです。私はこのシーンを読みながら「真人、成長したなあ」って、親心みたいなものが湧いてきてしまいました(笑)。
岩城 優しい(笑)。うちの娘を見ていても、自らのアイデンティティとは自分で作り上げていくものなんだな、と感じます。他者の目によって作られたアイデンティティを自分の中で作り替え、自分なりのアイデンティティを作り上げてゆく。そういう過程が成熟なんだなと感じます。
小島 しかも真人がやったことって、すごく勇気が必要な行為です。言い方によっては、相手に「おまえはレイシスト(人種差別主義者)だぞ」と言ったことになるわけだから。多文化共生社会でレイシストと相手に言う、あるいはレイシストと言われるって、非常に深刻なことです。
岩城 そうですね。
小島 でも、その危険性も恐らく理解した上で、彼はステレオタイプに申し立てをした。しかも結果的に、レイシスト呼ばわりしたと受け取られずに自分の意図を相手に伝えることができた……彼が成長した証ですよね。他者からアイデンティティを与えられてきた少年が、それを自分で読み替え、しかも最後は相手の価値観を更新するという能動的なアクションを成功させた。とても象徴的なシーンです。
岩城 ありがとうございます。そこは一番書き換えた場面かもしれません。
小島 そうでしたか。やっぱり、難しいところですよね。
岩城 アイデンティティの問題は、真人のような移民二世、あるいは一・五世、つまり小さい頃に移民としてやって来た人にとって、とても重要な問題です。彼らに共通するのは帰属意識がないことなんですよ。「自分はここで生まれて育ったけど、ここの人間ではない」という感覚が、彼ら彼女らの呪縛になってしまう。これは恐ろしいことです。「日本人でもない、オーストラリア人でもない、どこの人でもない」という感覚がつきまとうんですよね。たとえ日本に帰っても、「帰国子女」とか変な日本語になってしまうし、どこへ行っても「どこから来たんだ?」と言われる。だからこそ彼ら彼女らは、たとえその国で生まれていても、「自分はこの国の人間だ」と言わないんです。自分自身について説明する必要に迫られると、「父と母が○○から来ました」という説明の仕方をする。そういう方々を見ていて、彼ら彼女らが抱える独特の孤独があるのだ、そしてその孤独はその人たちの表現する世界でもあるのだ、と感じるようになりました。
小島 最近は、ダイバーシティを重視するグローバル企業などでは「ダイバーシティ&インクルージョン&ビロンギング」が重要だと言われているそうです。「ダイバーシティ&インクルージョン」は「多様性と包摂性」のこと。つまり、多数派の人がいろんな少数派の人を包摂してあげましょう、という意味です。でももうひとつ重要なのは、「ビロンギング」つまり「帰属性」。少数派の人々が、自分の居場所はここだ、ここが一番心地よく伸び伸びできる場所なんだと感じられるかどうかです。「帰属性」があってはじめてその人は力を発揮できる。これは企業だけでなく、おそらく社会運営でも、家族でも同じですよね。
岩城 本当におっしゃる通りだと思います。
小島 「少数派を包摂したよ、制度つくったよ、オーケー」じゃないんですよね。少数派に対して「包摂されて、実際はどうですか、居心地がいいと感じますか」と耳を傾ける必要がある。二世や一・五世の人々が、自分のアイデンティティを考えるうえで、「自分はもともと違うところから来たけれど、今の自分の居場所はここだ」と思えるまでやるべきことがありますね。
岩城 そうですね……でも難しいなと感じるのが、ダイバーシティにはかなり制約も伴うこと。最近、「これはしてはいけない」「この表現はこういう人に対してアグレッシブになる」とか、表現の制約もかなり増えました。うちの夫は小学校の先生なのですが、「注意点の講習だらけで息苦しい」と言っています。一表現者としては、ダイバーシティによる制約が多くなりすぎていないかなと、ちょっと懸念するところもありますね。これはだめ、あれもだめとなると、そもそも表現したいことがある表現者にとって、非常にしんどいことになる。最近はみんなびびりながら、これは大丈夫なのか? と言っている印象があります……。ダイバーシティの最終目標は「どんな人でも住みやすいところにする」ことなので、その目標から外れないといいな、と感じます。
真人とアビーの葛藤の対比
小島 『M』において、真人と同じくらい重要な人物として登場するのが、アルメニアにルーツを持つアビーという女の子です。真人は彼女との衝突とコミュニケーションを通じて自分のアイデンティティを見つめなおしていく。私、なぜアビーをアルメニア人という設定にしたのか、岩城さんに伺いたかったんです。実はかつてロケで一度アルメニアに行ったことがあって。アルメニアは複雑な成り立ちを持つ国ですよね。
岩城 息子の友達にアルメニア人の子がいたんですよ。お話を直接伺ったわけじゃないのですが、彼女が話しているのを聞いて、かなりしんどそうだなと感じていたんです。その後調べていったら、やはり同族結婚が当たり前のカルチャーで……。オーストラリアに来たらいろいろ複雑な思いをするだろうな、と。息子の友人には後日談があって、その後彼女は好きな子ができたのですが、そのお相手の親御さんのどちらかがトルコの方だったそうなんです。
小島 ああ……。たしかオスマントルコ帝国の時代に大虐殺事件が起きて、アルメニアの人たちがたくさん殺されたんですよね(編集部注:19世紀末~20世紀初頭、オスマン帝国における少数民族であったアルメニア人の多くが、オスマン帝国政府による強制移住や虐殺の犠牲になった)。
岩城 そう。だから彼女はそれを聞いた瞬間に相手と別れた、という話を聞きました。
小島 なんと……。
岩城 彼女の場合はそうだったんです。
――日本から来た真人はステレオタイプについて悩んでいますが、アビーにはステレオタイプすらありませんよね。
岩城 真人の苦しみとアビーの苦しみはまた違うものですよね。アルメニア人のアビーにはステレオタイプさえなくて、安心できる役割も存在しない。みんなアルメニアのことを知らないんです。さっき小島さんがおっしゃった「ビロンギング」について、彼女はかなり苦しんだのだろうと思うんです。アルメニア人って、見た目は俗にいう「オージー」と変わらない白人ですから。
小島 見た目が白人だと、内面的・文化的な孤独が可視化されづらいですよね。
岩城 そう、可視化の問題です。見えないものも貴重なのに、見えることばかりが広がってしまう。みんな、見えるものしか見ようとしない。もっとそのあたりは、うまく書けたらよかったなと思うのですが。
小島 私は真人とアビーがよい対比になっているなと思いました。アビーは白人の見た目だからこそ、内面の葛藤が可視化されづらいという悩みがある。真人はアジア人の見た目だから、ステレオタイプ化され、自分の葛藤がステレオタイプに吸収されてしまって可視化されないという悩みがある。両方とも実は「可視化されない」ことについての悩みなんだけれども、その成り立ちが見事な対比になっていますよね。
岩城 ありがとうございます。
小島 しかも、宗教も歴史も、アルメニアと日本の文化はかなり異なるところがあるでしょう。二人のバックグラウンドにある母文化の対比にもなっているところがすごいなあと思いました。
岩城 うわあ、すごく読み込んでくださっている……!
日本とオーストラリアの教育の違い
――作中で交わされる真人とアビーの議論は、日本の大学生に比べるとかなりしっかりしていて、大人びているなと感じました。環境問題しかり表現の問題しかり、二人とも自分の意見をしっかりと持っています。
小島 それはやはり、日本とオーストラリアの教育の違いじゃないでしょうか。息子たちは小学校五年生と二年生までは日本の公立小学校に通っていたのですが、オーストラリアの小学校に通い始めてから、長男が「先生に『君はどう思うの?』と聞かれたとき、なんて言えばいい?」と困っていたんですね。つまり日本の公立小学校では、「自由に意見を言いましょう」と先生が言ったとき、本当は自由に意見を言うことは求められていなくて、先生が想定している自由の範囲内で意見を言うことが求められるでしょう(笑)。
岩城 (笑)。本当にそうですね。
小島 私と夫は、長男に「差別や暴言はダメだけど、それ以外であれば君が考えていることを本当に自由に言っていいんだよ」と伝えました。「信じられないかもしれないけれど、本当に君の思ったことを言っていいんだ」って(笑)。長男はすごく驚いていました。やがてそのやり方に慣れて、本当にのびのびと自分を開いていくのがわかりました。たまたまですが、息子たちにはオーストラリア式の教育がすごく合っていたみたいです。
岩城 うちの娘も、四歳の時に二ヶ月ほど日本の幼稚園にお世話になったことがあるんです。その後、日本の幼稚園からオーストラリアのキンダーガーテン(幼稚園)に移った時は、ちょっとした試練でした……。帰り際に先生から、「彼女はずっと私の顔を見て、指示を待っている」「何をしたいかちゃんと自分で決めて遊ぶように言っているんだけど」と言われるんです。一度日本の幼稚園に慣れてしまうと、みんなで先生の言うことを聞くのが心地よく思えてしまう。だから彼女は最初オーストラリア式が辛かったみたいで。キンダーガーテンって、帰るときに先生が一人一人に「今日は何をしましたか。何が楽しかったですか。どんな気持ちでしたか」と聞くんですよ。彼女はそれに答えられなかった。
小島 もちろん子どもとの相性もありますし、日本の教育が全部だめで、オーストラリアは理想郷、と単純化するべきではないですが。でも本当に、日本とオーストラリアの教育の違いを感じますよね。
岩城 小学生になるともっと顕著ですよね。「show and tell」といって、「自分が週末に何をしたか教えてください」「プレゼンしてください」「授業で手を挙げて、意見を言ってください」という場面があります。意見や考えは人それぞれだから、内容にはマルもバツもない。でも、それを皆の前で言えるかどうかが問題になってくる。
小島 オーストラリアでは、小学校の段階からパワーポイントを使っての発表が基礎的な学習に入っていますよね。パワーポイントを作る能力とプレゼン能力は基礎学力とされている。
岩城 そうそう。ハイスクールになると、何を考えているのか意見をはっきり表明しなければいけないんです。たとえば数学でも、どうしてその考えに至ったのかをちゃんと記述しないとバツになってしまう。なぜあなたがそう考えたのかを表明しなさいという教育の在り方が、日本とオーストラリアの大きな差かもしれません。
小島 私がオーストラリアですごくいいなと思うのは、テストの結果に納得がいかないと先生と点数の交渉ができることですね。先生と交渉して先生が納得すれば、何点か上がるんですよ。そういうことが中学生のときから可能なのです。「自分より立場が上の人間に対してノーを言う」「自分の意見を言って交渉する」、それが習慣化されるってすごく重要なことですよね。これも日本でこれをやるとしたら、必要なのは先生側の覚悟……大人がその対話をできるかどうか、だと思いますが。
岩城 あと、オーストラリアでは大学で、自分と違う意見を踏まえたエッセイライティングを学びます。様々な立場の意見を全部総合した上での、自分の意見を表明する技術を習得する。反対意見ともディベートし対話したうえで、自分の意見をつくることが求められる。そういう教育を経ているから、日本の大学生よりも、真人やアビーは少し大人びて見えるのではないでしょうか。
――真人のルームメイトのゼイドなどは、デモを行い政治的な意見をはっきり表明しています。
岩城 政治に関しては、オーストラリアで市民権を持つ人間は選挙は義務で、絶対に選挙へ行かなきゃいけないんです。だからみんな選挙や政治にも関心が高い。若い世代は、誰に入れるか誰に入れないかをSNSで意見表明しているようです。
小島 政治に関して私が驚いたのは、子どもが学校を休んでデモに参加することもOKだということです。たとえば、前政権が地球温暖化対策に消極的だったことに対して子どもたちが怒り、デモをしていたのですが、その時に息子の学校から「授業を休んでデモへ行くときには、親の許可をとって、先生にも連絡をください」と言われて。え、デモ参加のために授業休んでもいいんだ? って。日本では高校生が政治的な活動をすることを否定的に捉える学校もあるのに、随分違うなと驚きました。そのときには、公共放送系の番組のインタビューで、デモに参加した子どもたちが首相に対する批判を述べていました。子どもがなにか言ったときにメディアがどのように報じるか、そこが重要だなと。日本とオーストラリアでは、大人が子どもの意見をどのように扱うかが、全然違います。
岩城 これも大人側の問題ですね。
小島 本当に。子どもに意見の表明を求める教育って、教師や親の側にも覚悟が必要ですよね。受け入れ難いものでも受けとめ、あなたはそう考えるのだね、それはなぜ? と対話を重ねて、意見を尊重する態度を見せる。「自由を許す側の責任」を大人が自覚するところから始めないと、日本で子どもの意見を尊重する教育、あるいは個の意見をのびのびと言えるような社会は作り得ないと思います。
家族がマイノリティになること
小島 真人を見ていると、今後自分の息子たちがオーストラリアに渡ったことをどう評価するか、分からないなあと思います。でも私としては、息子たちがオーストラリアに住んでいて良かったと思うことがあって。それは、「移民の親は弱くなる」ということです。まさに真人が、お父さんやお母さんとの間で繰り返し経験することなんですが。
岩城 そうそう。分かります。
小島 日本では私はテレビに出る仕事をしていて、夫も大きなテレビ番組に関わるディレクターの仕事をしていました。さらに日本においては、息子たちはジェンダーや人種など多くの面で社会のマジョリティとして育ってきた。加えて「お前のお母さん、ゆうべテレビに出ていたよ」などと言われて、彼らは素朴に親を「すごい人」として捉えてしまうところもあったんですよね。それは幼い子どもらしい、自然な気持ちでもあるのですが。ところが、オーストラリアに行ったら、私も夫もバイリンガルではないので英語がなかなか通じない。
岩城 親が言語的弱者になるんですね。
小島 そうなんです。ちなみに私は、不完全な英語でも最終的に念で通じさせるので、マイ・イングリッシュ・イズ・ネングリッシュです(笑)。
岩城 念!(笑)。
小島 はい、念です(笑)。息子たちは親がいいかげんな英語をしゃべっていることに、次第に気づいていくわけです。そして小学生のときから親の通訳をやらされる。真人がお父さんに「俺が代わりに交渉してやったじゃん」と言うシーンがありますが、まさにそういう場面がよくあった。でも、だからこそ「親は無力なんだ」と気づけるんですよね。親が社会の中で弱者である体験をすることは、子どもにとってはいい教育でした。もちろん、そんな吞気なことを言えるのは、日本で恵まれていたからこそではあるのですが。いずれにしろ、一・五世や二世の子たちは、自分のほうが親よりもできるという経験をせざるを得ない。早期の親殺しです。しんどいことではあるのですが……でも親殺しって、早晩どこかでしなくてはいけないことですから。
岩城 うちもそうでした。移民の親を持つ子どもって、普通と異なるアクセントを持った人に対してすごく優しいんですよね。言葉が違う人に「お手伝いしましょうか」と言うことができる。
小島 親を通じて多文化社会での弱者が可視化されるんですよね。岩城さんがおっしゃった言語弱者への優しさや共感、こういう苦労があるだろうなという想像力が働く。多文化共生社会で生きていく上ではとても大切な能力です。
岩城 大事なことですよね。みんな簡単に「思いやりが大切です」と言うけれど、やっぱり弱者が目の前にいないと、あるいは自分がつらい目に遭わないと、なかなか共感もできないものです。ましてやそれを表現することもできない。そういう意味ではうちも親殺しが早くてよかった。
小島 本当にそうですね(笑)。
岩城 うちなんてもう、子どもからはリスペクトも何もありません(笑)。電話のとき「うちのオカンは英語がだめだから」と友達に大きな声で言っていて……。
小島 でも、そうやって親のことを友達に言えるって、とても尊いことですよ。親のことを恥じていたら言えないですものね。英語がだめなことと彼女の偉大さ素晴らしさは関係ない、そう思っていないと「うちのお母さん英語だめだから」なんて言えませんよ。
岩城 相手の英語が聞きとりづらいとわかっているからこそ、相手を助ける。多文化社会って、それが当然の国のことなんですよね。
小島 本当にそうです。私、もともと岩城さんのデビュー作『さようなら、オレンジ』をちょうどオーストラリアに移住するタイミングで拝読していたんです。今もやっぱり、主人公のサリマの心境が人ごととは思えなくて……。私がもしオーストラリアで働くとしたら、日本でのキャリアは何にも役に立たないので、「サリマは私だ」という気持ちなんです。岩城さんとはいつかお話ししたいと思っていたので、今日は本当にお話しできてよかった。そして、サリマのその後が読みたいです!
岩城 みんなそれ言うんですよねえ、小島さん、続きを書いてくださいよ(笑)。
小島 ええーっ!(笑)。まずはメッセンジャーでお友達になりましょう! よろしくお願いいたします。
(2023・6・19 Zoomにて収録)
「すばる」2023年9月号転載
プロフィール
-
岩城 けい (いわき・けい)
作家。1971年大阪府生まれ。大学卒業後、単身渡豪。以来在豪約30年になる。2013年に『さようなら、オレンジ』で太宰治賞を受賞しデビュー。2014年に同作品で大江健三郎賞、2017年に『Masato』で坪田譲治文学賞を受賞。他の著書に『ジャパン・トリップ』『Matt』『サンクチュアリ』『サウンド・ポスト』『M』がある。
-
小島 慶子 (こじま・けいこ)
エッセイスト、タレント。1972年オーストラリア生れ。幼少期は日本のほか、シンガポールや香港で育つ。95年にTBSに入社。アナウンサーとしてテレビ、ラジオに出演する。2010年に独立後は各種メディア出演のほか、執筆・講演活動を精力的に行う。著書に『解縛』『わたしの神様』『ホライズン』『おっさん社会が生きづらい』など。
新着コンテンツ
-
新刊案内2025年06月26日
 新刊案内2025年06月26日
新刊案内2025年06月26日筏までの距離
水原涼
デビュー作で芥川賞候補に挙がった著者が贈る、わたしとあなたの8つの物語。
-
インタビュー・対談2025年06月20日
 インタビュー・対談2025年06月20日
インタビュー・対談2025年06月20日宇山佳佑×檜山沙耶(フリーアナウンサー)「風が吹くたび、物語が生まれる」
ウェザーニューズで気象キャスターとして活躍し、その後も活動の幅を広げる檜山沙耶さんと作品、風、お天気について語っていただきました。
-
お知らせ2025年06月17日
 お知らせ2025年06月17日
お知らせ2025年06月17日小説すばる7月号、好評発売中です!
新連載はいずれも小説すばる新人賞出身の佐藤雫さん、神尾水無子さんの2本立て!
-
お知らせ2025年06月17日
 お知らせ2025年06月17日
お知らせ2025年06月17日本日開店、「スキマブックス」!!
文芸ステーションに新しい読みもののコーナー「スキマブックス」がオープンしました!
-
スキマブックス2025年06月17日
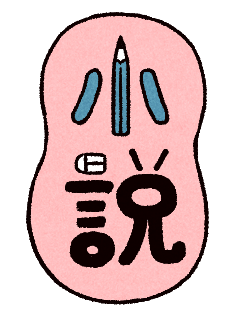 スキマブックス2025年06月17日
スキマブックス2025年06月17日今度こそ許すまじ春野菜といんげん豆の冷製スープ事件
結城真一郎
彼氏が浮気をしているのではないかと疑った大学生は、「あるレストラン」に浮気調査を依頼するが――。
-
インタビュー・対談2025年06月17日
 インタビュー・対談2025年06月17日
インタビュー・対談2025年06月17日堂場瞬一「日本政治の未来をフィクションで問う」
堂場瞬一さんの通算195冊目の作品にして、実験的政治小説第二弾『ポピュリズム』の世界観を語ってもらった。