『スターゲイザー』刊行記念対談 佐原ひかり×真下みこと「持続可能な光の中に」

佐原ひかりさんの小説すばる連載作『スターゲイザー』が、この度刊行されることになりました。
デビュー前のアイドルたちを描いた今作は、デビューまでの期限の中で、懸命に“アイドル”と向き合う6人の男性が登場します。
今回、『スターゲイザー』刊行を記念し、8月に『かごいっぱいに詰め込んで』を刊行されました真下みことさんとの対談が実現。
お互いの新作について、熱く語り合っていただきました。
構成/タカザワケンジ 撮影/露木聡子
アイドル版の『蟹工船』⁉
――お二人はふだんから交流があるそうですね。まずは真下さんに『スターゲイザー』の感想をうかがってよろしいですか。
真下 佐原さんにはLINEで直接お伝えしたんですが、青春小説でありながらお仕事としてアイドルを捉えている小説だなと思いました。
アイドル小説って、どういうアイドルを描くか、アイドルとどんなジャンルの小説を掛け合わせるか、それにテーマをどうするかという三つのポイントがあると思うんです。佐原さんの『スターゲイザー』は、まだデビューしていないアイドル候補生たちの青春小説でありつつ、最終的にはアイドルという仕事の持続可能性について書いていると思います。そこが佐原さんらしいし、アイドル小説として新しいと思いました。
これまでのアイドル小説は、朝井リョウさんの『武道館』とか、安部若菜さんの『アイドル失格』とか、デビュー済みのアイドルを描いた青春小説で、アイドルと恋愛の是非を問う話が多かったと思うんです。『スターゲイザー』は恋愛ではなく、アイドルの労働について考えている小説なんですよね。
佐原 『蟹工船』みたいな。
真下 アイドル版の『蟹工船』。
佐原 プロレタリア文学ですね。
真下 体はもう限界なのに、お客さんがいてステージがあったら出ていかなきゃいけないという限界労働感が新しいと思いました。
私自身、デビュー作(『#柚莉愛とかくれんぼ』)がアイドルを描いた小説だったんですが、その時は、がけっぷちアイドル×ミステリー×SNS炎上というたてつけで書きました。同じアイドル小説でも『スターゲイザー』とは全然違いますよね。
佐原 アイドルものを書くとなった時に、最初に考えたのが、真下さんが言っていたように、アイドルと何を掛け合わせるかでした。私自身、男性アイドルが好きで、彼らが睡眠時間三時間で活動しているとか、心身に限界が来て休養します、引退しますというニュースを聞くと心が痛かったんです。そこそこのペースでいいから長くアイドルを続けてほしい。そういう気持ちがあったから、真下さんがこの小説からアイドルの持続可能性を読み取ってくれたのはめちゃくちゃ嬉しいです。
真下 『スターゲイザー』は六章立てでそれぞれ語り手が違いますが、全員男性ですよね。これまでの佐原さんの作品は女性視点が多かったと思うんですけど、男性視点で通したのは初めてですか?
佐原 初めてですね。もともとは編集者さんとの打ち合せの時に、何かハマっていることはないか、みたいな雑談をしていて、私が異様に男性アイドルに詳しいことがばれて(笑)。
真下 ばれちゃったんですね(笑)。
佐原 そんなに詳しいなら書いたほうがいいですよ、と言っていただけたことがきっかけなんです。だから自然と男性アイドルたちの視点になりました。
真下 ファン視点で男性アイドルを見てきたから細部に神が宿っているんですね。しかもデビューをめざす六人全員がそれぞれ違うタイプ。六人にモデルはいるんですか。
佐原 モデルは特にはいないんですが、何となく各グループに一人はこういう人がいるよね、という人にしたかったので、アイドルの要素をピックアップして考えました。アイドルファンの人が読んでもリアリティーがあるようにしたかったので、誰かをイメージしてというよりは、アイドルの混沌から拾い上げるみたいな感じでつくりましたね。
真下 私は六人の中では若さまが好きなんですけど、若さま視点で長編が書けるくらい分厚い設定だなと思いました。でも、あえて語り手を六人にしたのは、やっぱりいろんなタイプのアイドルを書きたかったからですか。
佐原 そうですね。いろんなタイプのアイドルをいろんな視点から書きたかったんです。アイドル自身はこう思っているんだけど、ほかのアイドルからはこう見えているよ、という。タイトルの「スターゲイザー」とも関わってくるんですけど、自分では才能がないと思っている部分が、他者から見たらそんなことはないということを表現するには、群像劇が一番いいなとは思ったんです。

初めて小説を書きながら泣いた
真下 『スターゲイザー』は、アイドルファンの人が読んでも傷つかないつくりになっているところもいいなと思いました。男性だけで集まると、どうしてもホモソーシャルなノリが出てきてしまいますよね。同性愛をばかにしたり、女性を下に見たりとか。『スターゲイザー』にもそういう感じの子たちが脇に出てきますけど、それが間違っているということがちゃんと書かれているのがよかったです。作者がそれを悪いことだと認識してないような書かれ方の小説を読むともやっとするので。
佐原 ありがとうございます。実際の男性アイドルのメイキングビデオを見ていても、下ネタっぽい話題になった時に、入っていけない人が一人、二人いるんですよ。「俺は関わりたくないから」みたいなテンションの人。そういう人たちが実際にいるのでちゃんと取り込まないと嘘だなと。
真下 視点人物に一人もホモソーシャル的な価値観を内面化している人がいないのは、佐原さんがそうじゃないアイドルを実際に見ていたからなんですね。
お客さんとして見ているだけではアイドルの内面までは分からないと思うんですが、佐原さんは彼らの心のうちまで踏み込んで書いていますよね。
佐原 今回『スターゲイザー』を書く時に意識した目標の一つが、推される側の言語化でした。最近、アイドルを推す側の言語化は進んできていますが、推される立場の人たちは言語化されていないなと思います。アイドルは表では言えないことがたくさんある。何かあった時に出てくる言葉は運営が考えた言葉だったり、事務所が用意したものだったりして、言わされている感があるんですよ。インタビュー記事でも本当はもっと尖った言葉だったのが丸められたんだなと感じることもあって、本当はどうなんだろうと思っていました。
そんなことが気になっているうちに、私も作家になって、推す立場から推される立場になった。今なら推される側をうまく言語化できるかもしれないと思ったんです。
真下 私も『スターゲイザー』を読んでいて、自分と重ねてしまうところがありました。速いサイクルで進化を要求されて、それについていけない人はどんどん振り落とされていく。そういうところは作家も同じ。人ごとじゃないと思いました。作家も結局、求められるものを書いて、それが売れるか売れないかで判断される。「これ、私の話や!」って(笑)。
佐原 今回の対談のために真下さんのデビュー作の『#柚莉愛とかくれんぼ』を読み返したんですけど、そこでもアイドルが売るための仕掛けをしなくちゃならなくなりますよね。これがうまくいかなかったらあなたたちはこのままじゃいられないよ、と宣告されて。それって我々作家も同じですよね。「この作品を外したら次はない」みたいな気持ちはつねにあります。
『スターゲイザー』で、コンサートに来てくれたファンが涙を流しながら「ありがとう」と言うシーンを書いたんですけど、ファンを見たアイドルが「すごいことだよ、これって。/俺、こんな仕事してたんだな」って気づくんです。それって私にも覚えがあって、私もファンレターをもらった時やサイン会で読者の方から感謝の言葉をいただくと「私ってすごい仕事しているんだな」って思ったりするんです。このくだりは自分とめちゃくちゃリンクして、書きながら泣きました。小説を書きながら泣いたのは初めてでしたね。
普通の人たちの悩みを抱きしめて
真下 三章の「愛は不可逆」で、遥歌が自分の美貌について、「顔が綺麗って言われるけど、それってほめ言葉じゃないと思う。この顔はもともとのものだから、おれがどうとかって話じゃない」と言ってるのが衝撃でした。顔が綺麗と言われる人ってそうなの? って。
佐原 小説の中で語られがちなのって、容姿に恵まれていないがゆえの苦しみですよね。でも、容姿に恵まれている人にも、恵まれているがゆえの悩みがあると思うんですよ。それってたぶん人には言えない悩みなんですよね。「顔を褒められても別に嬉しくない」なんて言ったら「はあ?」みたいな空気になるじゃないですか。でも、本人にとっては切実な悩みかもしれない。
実際、アイドル誌で男性アイドルのインタビューを読むと、「顔がいいって褒めてもらえるんだけどね(笑)」って、ちょっと自虐的に言っている子がいるんですよ。顔がピカイチにいい子が。たしかにその子は踊りとか歌とかが顔に追いついてないって感じだったので、コンプレックスを感じているだろうし、周りからやっかまれることもあるのかも。そこは言語化しておくべきところだなと思いました。
――大丈夫そうに見えても悩んでいる部分がきっとあるみたいなのは、真下さんの新刊『かごいっぱいに詰め込んで』のテーマにも通じるところがありますね。
佐原 『かごいっぱいに詰め込んで』を読んで、「真下さん、マジですごいことやっている」と思ったんですよ。何がすごいかというと、ここに出てくる人たちって、本当に普通の人たちなんです。私の場合は特殊な人たちが、その特異性に対して悩んでいる話を書きがちなんですけど、真下さんは『かごいっぱいに詰め込んで』でごく普通の市井の人たちの悩みを描いている。誰でも身に覚えがある、ふだん見落としてしまっている悩み。それってかなり難しいことだと思います。
例えば第一話の「おしゃべりなレジ係」。主人公の美奈子が専業主婦を二十年やってから就職活動を始めるんですが、なかなかうまくいかない。そういえば、うちの母親も定年退職を迎えて、もうちょっと働きたいからってハローワークに行ったんですけど、なかなか採用されなくて悩んでいたことを思い出しました。
第四話の「なわとびの入り方」は妊活の話。私の友人にも、主人公の咲希のように、周りに追いつかなきゃみたいな感じで悩んでいる人がいて、どんな言葉をかけたらいいか分からなかったことを思い出しました。そういう自分の身近にいる人たちの悩みをちゃんとすくい上げて、抱きしめていると思いましたね。

読後感のいい小説への挑戦
真下 『かごいっぱいに詰め込んで』では、もともとはいろんな年代の、いろんな人の話を書きたいと思ったんです。振り返ると、これまで自分と年代の近い女性視点でばかり書いてきたことに気づいて、そうじゃない小説を書きたくて。デビュー作(『#柚莉愛とかくれんぼ』)でSNSを使った話を書いたので、二作目(『あさひは失敗しない』)はSNSを使わなくても書けるぞというところを見せたかった。三作目の『茜さす日に嘘を隠して』は長編ではなく連作短編で、歌詞を書けることもアピールしたいなと思ったんですね。いつも同じ感じだと飽きられちゃうと思うので、新しいことに挑戦したいんです。
佐原 「おしゃべりレジ」は後から?
真下 そうですね。今セルフレジがどんどん増えていますよね。私自身はセルフレジ派で、セルフレジがあったらセルフレジを使うんですけど、セルフレジしかないお店で困っていたおばあさんがいたんですよ。結局、店員さんがやってくれたんですけど、その店員さんが素っ気ない対応だったんです。セルフレジが使えないというだけでそんなに冷たくしなくたっていいじゃないかと思って、そういう人がゆっくりお会計できるようなレジがあればいいのになって思いました。
調べてみたら、オランダで世間話ができるレジがスーパーに導入されているというニュース記事が見つかって、まだ日本にはないから書いてみようと思いました。おしゃべりレジを軸にすればいろんな世代の人たちの話を書いて連作にできるんじゃないかと。
実はもう一つやりたかったことがあって、それは読後感のいい小説を書くということ。私の小説って、読後感が悪いと言われていて、自分自身、読者として読後感が悪い小説が好きだったので自然とそうなったんです。でも、自分が就職して本を読もうとなった時に、現実がこんなつらいのに本の中でもつらい気持ちになりたくないと思ってしまって。それで今回は読後感のいい小説、ハッピーエンドをめざそうと。佐原さんには「これハッピーエンドですか?」みたいに言われたんですけど(笑)。
佐原 連作のうち、いくつかはただのハッピーエンドじゃないってことですよ(笑)。この後、ホラー待ってるぞみたいな予感が漂っていたりして。
真下 そういう話もあるんですけど、全体として前向きエンドみたいな感じにはしたいなと。働いている人の話でもあるので、お勤めの方が手に取った時に、読まなきゃよかった、すっごい嫌な気持ちになった、みたいにならないようなものにしたかったんです。これは就職しないと分からなかったので、就職した経験が生かされているのかなと思います。
佐原 五つの短編の主人公、それぞれの解像度がめっちゃ高かったです。自分と全く属性が異なる人を書く時に、どうやって解像度を上げたのかを聞きたいです。
真下 登場人物に似た属性の知り合いに、取材というほどかしこまった感じじゃなくて、何時に会社に行って何時に帰ってくるとか、ルーティンはありますかとか、質問させてもらいました。後は就活の時に見ていた『業界地図』とか『会社四季報』で、どんな業界のどんな規模の会社に勤めていることにしようかなと考えたりしましたね。
仕事の描写に関しては自信がなかったんですけど、自分が会社員だった時の経験をベースに、主人公の属性に近い人に聞いた話と、自分がやっていた仕事との差異をあぶり出していき、想像して書くみたいな感じでした。

真下みこと
講談社 定価1815円(税込) 発売中
持続可能な光が届いた先に
佐原 『かごいっぱいに詰め込んで』を読み返して気づいたんですが、真下さん、第二話以外、光の描写を最後に書いているんですね。
真下 何かの時に佐原さんに言われたことが生きているんですよ。
佐原 何か言ったっけ? 怖い(笑)。
真下 「真下さんは最後にもうちょっと光量を上げたほうがいい。ハッピーエンドだったら花火をぶち上げるような光を書いたほうがいい」って。
佐原 え!? そんなこと言いましたっけ。
真下 「真下さんのハッピーエンドは、真下さんが思っているほどハッピーに見えないから、もしハッピーに見せたいなら、もっと分かりやすく、光とか、花火とか、そういうものを出したほうがいいですよ」って言われたんです。
佐原 ごめん。めっちゃ偉そうなこと言ってるな、私(笑)。
真下 言われてみると、たしかに佐原さんの作品って自然に光が当たっているんですよね。それで、私も今回、がんばって光らせてみたんです。
――佐原さんは今回、『スターゲイザー』の三章で「光が嫌いだ。/逃げも隠れもできないステージで、おれを突き刺す光」という書き出しで、光のネガティブな側面も描いていますね。
佐原 そうですね。『スターゲイザー』は全編通じて星とか光が出てきますが、必ずしも肯定的な光の話だけではないというのは自分でも意識していました。
真下 佐原さんが光を否定するような感じで書かれていたから、光を書き尽くすとそうなるのか、と思ったんですよ。佐原さんはお名前がひかり。光の権化というか。
佐原 光の権化でやっております(笑)。
真下 『スターゲイザー』で、ステージの光が目を刺すようにまぶしいという描写が印象的で、たしかにあれだけ光っていたらまぶしいよなって。
佐原 そうですよね。私、いつもアイドルのコンサートにサングラスに耳栓で行っているんですよ。あまりにも照明がまぶしすぎて、音が大きすぎるから。私たち観客はそうやって対策できるんですけど、歌って踊っている側はできないじゃないですか。そういう肉体的な負荷は絶対あるなと思っていて、それも書きたかったんです。
私、今回、書店員さん向けの見本にメッセージを書かせてもらったんですけど、そこにはこう書きました。
「私自身が推す側であり推される側である。だからこそ、私の好きな人たちが、そして私自身がどうすれば持続可能な光でいられるのかみたいなのを考えながら書きました」。
真下 「持続可能な光」っていいですね。
佐原 めちゃくちゃ輝いていたら一瞬で燃え尽きてしまいそう。燃え尽きないようにアイドルを続けてほしい。真下さんも「お体大切に」とか読者の方に言われることないですか。
真下 言いますね。最近、私、大河ドラマの『光る君へ』にハマっていて、ドラマに出てきた「お健やかに」っていうセリフを挨拶代わりに言ってます。たしかに大切な人には「お健やかに」いてほしいなと。
佐原 祈りですよね。ブログとかメールの末筆に、「お健やかに」とか「体調にお気をつけください」とか毎回書いているのは、とりあえずみんな健康でいてほしいという気持ちからなんですよね。ファンもアイドルに対して思っていると思うんですよ。「お健やかに」。親みたいですけど(笑)。
「小説すばる」2024年10月号転載
プロフィール
-

佐原 ひかり (さはら・ひかり)
1992年兵庫県生まれ。大阪大学文学部卒業。2017年「ままならないきみに」で第190回コバルト短編小説新人賞受賞。2019年「きみのゆくえに愛を手を」で第2回氷室冴子青春文学賞大賞を受賞し、2021年に同作を改題・加筆した『ブラザーズ・ブラジャー』で本格デビュー。他の著書に『ペーパー・リリイ』『人間みたいに生きている』『鳥と港』『スターゲイザー』がある。
-
真下 みこと (ました・みこと)
1997年埼玉県生まれ。'19年『#柚莉愛とかくれんぼ』で第61回メフィスト賞を受賞し、'20年にデビュー。ほかの著書に『あさひは失敗しない』『茜さす日に嘘を隠して』『わたしの結び目』などがある。
新着コンテンツ
-
新刊案内2025年06月26日
 新刊案内2025年06月26日
新刊案内2025年06月26日筏までの距離
水原涼
デビュー作で芥川賞候補に挙がった著者が贈る、わたしとあなたの8つの物語。
-
インタビュー・対談2025年06月20日
 インタビュー・対談2025年06月20日
インタビュー・対談2025年06月20日宇山佳佑×檜山沙耶(フリーアナウンサー)「風が吹くたび、物語が生まれる」
ウェザーニューズで気象キャスターとして活躍し、その後も活動の幅を広げる檜山沙耶さんと作品、風、お天気について語っていただきました。
-
お知らせ2025年06月17日
 お知らせ2025年06月17日
お知らせ2025年06月17日小説すばる7月号、好評発売中です!
新連載はいずれも小説すばる新人賞出身の佐藤雫さん、神尾水無子さんの2本立て!
-
お知らせ2025年06月17日
 お知らせ2025年06月17日
お知らせ2025年06月17日本日開店、「スキマブックス」!!
文芸ステーションに新しい読みもののコーナー「スキマブックス」がオープンしました!
-
スキマブックス2025年06月17日
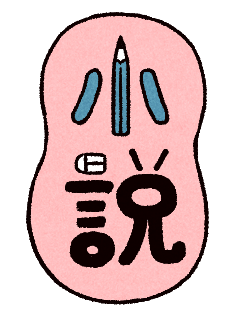 スキマブックス2025年06月17日
スキマブックス2025年06月17日今度こそ許すまじ春野菜といんげん豆の冷製スープ事件
結城真一郎
彼氏が浮気をしているのではないかと疑った大学生は、「あるレストラン」に浮気調査を依頼するが――。
-
インタビュー・対談2025年06月17日
 インタビュー・対談2025年06月17日
インタビュー・対談2025年06月17日堂場瞬一「日本政治の未来をフィクションで問う」
堂場瞬一さんの通算195冊目の作品にして、実験的政治小説第二弾『ポピュリズム』の世界観を語ってもらった。



