
内容紹介
「勧進帳は不敬である!」
昭和十年、東京。満州国皇帝溥儀が来日し、亀鶴興行は奉迎式典で歌舞伎の名作「勧進帳」を上演。
無事成功するが、台詞が不敬にあたると国粋主義者が糾弾。
脅迫状が殺到した直後、亀鶴興行関係者が舞台装置に首を吊った姿で発見――。
江戸歌舞伎狂言作者の末裔、桜木治郎が大いなる謎に挑む、驚嘆の“劇場×時代ミステリー”!
あの戦争へ、日本が最後の舵を切った時代を彫刻する渾身作。
『壺中の回廊』、渡辺淳一文学賞受賞『芙蓉の干城』に続く、昭和三部作がここに完結!
プロフィール
-
松井 今朝子 (まつい・けさこ)
1953年、京都市生まれ。早稲田大学大学院文学研究科演劇学修士課程修了。歌舞伎の企画制作に携わった後、故・武智鉄二氏に師事し歌舞伎の脚色・演出を手がける。
1997年『東洲しゃらくさし』で小説デビュー。同年『仲蔵狂乱』で第8回時代小説大賞、2007年『吉原手引草』で第137回直木賞、2019年『芙蓉の干城』で第4回渡辺淳一文学賞を受賞。昭和初期の日本を活写する劇場×時代ミステリー三部作『壺中の回廊』『芙蓉の干城』『愚者の階梯』の他に、『師父の遺言』『料理通異聞』などがある。
インタビュー
書評
「愚者」という言葉にこめられた著者の哀惜
加藤陽子
松井今朝子が、ここ一〇年ほど、端正な文体で綴ってきた歌舞伎バックステージミステリーも、『壺中の回廊』、『芙蓉の干城』に続いて、『愚者の階梯』で三作目となった。一作目の時代背景は、一九三〇(昭和五)年[以下、西暦は下二桁で表記]の大不況下の社会であり、二作目は、内に国家改造運動、外に国際連盟脱退という、国内外の緊張が高まった三三年の社会を背景として描かれていた。
そして本書『愚者の階梯』の最初の山場は、三五年四月一〇日、既に同月六日に来日していた満州国皇帝溥儀が、東京市主催「奉迎式余興演劇」鑑賞のため歌舞伎の殿堂・木挽座を訪問した時の玄関ロビーに設定される。政官財の貴顕が集う晴れの日に、ふだん出会わないはずの人と人との偶然の邂逅が生まれ、悲劇の幕が切って落とされる。名作映画の一場面を髣髴とさせる導入部が見事だ。
評者は三〇年代の日本の軍事と外交を専門としてきたが、正直に告白しよう、この場面のモデルとなった溥儀の歌舞伎座臨御については、本作で初めて教えられた。昭和天皇の事績を宮内庁が編纂した『昭和天皇実録』には、天皇が溥儀を東京駅まで出迎え、宮中での歓迎晩餐会の後、一時間ほど舞楽を鑑賞した、との記述があるのみだ(『昭和天皇実録』第六巻、東京書籍、二〇一六年、七〇五頁)。天皇と溥儀が観たものは伝統的な舞楽であり、歌舞伎座に天皇は同道しなかったとの事実は、天皇と溥儀との立場の対比、舞楽と歌舞伎との対比を、これ以上なく端的に表象するエピソードとなっており、ここに照明を当てた著者の慧眼に恐れ入った。
歌舞伎の舞台裏と時代を交差させて精緻に描く本シリーズの強固なファンならご理解いただけると思うが、本作で著者は前二作を超える格別な境地に達したと評者には思われた。著者は、昭和戦前期の人々の暮らしを、職業や階層を異にする人々、思想や教養を異にする人々の交わす言葉を幾重にも交差させる手法で描いた。読んでいると、登場人物の息づかい、衣擦れの音まで聞こえてくる心地がするから不思議だ。
例えば、初代が演じた演目を孫の宇源次に試演会で舞わせるべく、六代目荻野沢之丞が主人公・桜木治郎(早稲田大学の文科で教鞭を執る、江戸の歌舞伎狂言作者・桜木治助の末裔)に監督を依頼する。その稽古の日、雷鳴轟く夏の中の稽古場。木挽座の舞台で首を吊って死んでいた川端繁之専務の一件を、治郎と沢之丞が対座する場面。
また、何度目かの稽古の場。沢之丞の顔を眺めていた治郎はつくづくと感じ入る。歴史をくぐってきた人の顔は立派なものだ、と。そして、女形の沢之丞の顔と、大道具の職人を仕切る長谷部棟梁の顔が、「幕末から明治、大正、昭和の今日にまで疾風怒濤の時代を乗り越えてきた年寄りの立派な顔」だという点で似ていると気づく。人間として立派な顔というテーマは、本作の最大の伏線にもつながる。
本書を貫く隠れたテーマとして、学問・芸能をめぐる「不敬」とは何かという著者の重い問いがある。溥儀の歌舞伎座訪問前日の四月九日は、不敬罪で告発されていた美濃部達吉の『逐条憲法精義』など三著作が発禁処分となった日にあたる。天皇機関説事件への治郎の思いは次の言葉に表れていよう。「不敬罪に問われた美濃部博士が、検事局でなんと十六時間もの取調を受けたと新聞で知って治郎は恐怖した。法曹界の権威だった人物が、瞬く間に犯罪者扱いされてしまうこの国の現状がとても信じられなかった」。
まさに瞬く間に「不敬」は芸能世界まで追ってくる。溥儀の観た『勧進帳』の読みあげに、右翼の箕輪志辰(蓑田胸喜がモデル)が修正を求める事態となった。聖武天皇の大仏建立の理由を、愛する妃を追慕する故とするのは、「女々し」く天皇を描くことになるという理由が一つにあった。治郎は「このセリフは能の『安宅』からそっくり採った詞」であり、「四百年来これにケチをつけるような真似はだれもしなかったからこそ今日に伝わっ」たと心の中では啖呵を切るものの、口には出せない。ここにいう愚者が「偏狭な日本バカ」の謂いなのは明らかだが、意気地がなく反論もできない治郎の弱さをも、著者の目は見逃していない。
愚者の最たるものは、本作のミステリーの核心を担う人物に他ならないが、著者はその性格を評して「優秀な兵卒タイプ」だと断ずる。優秀な兵卒は、上官の「どんなに理不尽で常軌を逸した命令でも粛々と遂行」してしまうからだ、と。著者の理性の目は、「そうした愚かしさ、心の弱さ」を、実は「この国の多くの人」が持っていると見抜いている。伝統の歌舞伎と新興のキネマが一瞬斬り結んだ場で生じた悲劇の決定版を著者は描いた。私たちは著者が描き出した、街に息づく人々の会話によって、一九三〇年代の日本を体感できた。感覚は時に思想よりも強靱だということを憶えておきたい。
かとう・ようこ ◆ ’60年、埼玉県生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科教授。専門は日本近現代史。’10年『それでも、日本人は「戦争」を選んだ』で小林秀雄賞を受賞。
「小説すばる」2022年9月号転載
新着コンテンツ
-
新刊案内2025年06月26日
 新刊案内2025年06月26日
新刊案内2025年06月26日筏までの距離
水原涼
デビュー作で芥川賞候補に挙がった著者が贈る、わたしとあなたの8つの物語。
-
インタビュー・対談2025年06月20日
 インタビュー・対談2025年06月20日
インタビュー・対談2025年06月20日宇山佳佑×檜山沙耶(フリーアナウンサー)「風が吹くたび、物語が生まれる」
ウェザーニューズで気象キャスターとして活躍し、その後も活動の幅を広げる檜山沙耶さんと作品、風、お天気について語っていただきました。
-
お知らせ2025年06月17日
 お知らせ2025年06月17日
お知らせ2025年06月17日小説すばる7月号、好評発売中です!
新連載はいずれも小説すばる新人賞出身の佐藤雫さん、神尾水無子さんの2本立て!
-
お知らせ2025年06月17日
 お知らせ2025年06月17日
お知らせ2025年06月17日本日開店、「スキマブックス」!!
文芸ステーションに新しい読みもののコーナー「スキマブックス」がオープンしました!
-
スキマブックス2025年06月17日
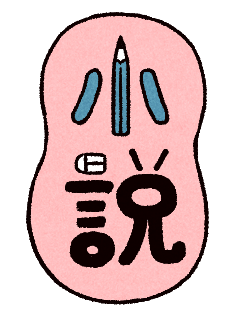 スキマブックス2025年06月17日
スキマブックス2025年06月17日今度こそ許すまじ春野菜といんげん豆の冷製スープ事件
結城真一郎
彼氏が浮気をしているのではないかと疑った大学生は、「あるレストラン」に浮気調査を依頼するが――。
-
インタビュー・対談2025年06月17日
 インタビュー・対談2025年06月17日
インタビュー・対談2025年06月17日堂場瞬一「日本政治の未来をフィクションで問う」
堂場瞬一さんの通算195冊目の作品にして、実験的政治小説第二弾『ポピュリズム』の世界観を語ってもらった。





