
内容紹介
同じ電車の同じ車両に、たまたま乗り合わせた見しらぬ男女たちがつなぐ、幸せのふしぎスイッチ。
小さいけれど確かに人生を豊かにする(かもしれない)7つのミラクルを描く、連作短編小説!
第一話「青戸条哉(あおと・じょうや)の奇跡 竜を放つ」——満員の朝の快速電車。ぼくは過去最凶の腹痛に耐えていた。もうダメだと思い、その場にしゃがもうとした瞬間、隣に立つ同い年くらいの女性が、ぼくよりもわずかに早く、しゃがみこんだ。
第二話「大野柑奈(おおの・かんな)の奇跡 情を放つ」——大学時代、わたしは小劇団にのめり込んだが、結局就活をして、食品会社へ。通勤途中、具合が悪くて社内で声をかけた女性の様子が気になり、駅を一つ戻ってホームに降りると、そこには意外な先客が——。
第三話「東原達人(ひがしはら・たつひと)の奇跡 銃を放つ」——満員電車での尾行中。住宅街の駅で降りた捜査対象者に気づかれぬよう後を追っていると、赤ん坊を抱いた裸足の女性が、すごいスピードで無表情のまま目の前を通り過ぎていった。
第四話「赤沢道香(あかざわ・みちか)の奇跡 今日を放つ」——五年ぶりのデート。満員電車で、男の人の手が、女性のお尻のあたりで円を描くように動いているのを見てしまった。女性は、まったく別の男性に「触りましたよね?」と詰め寄った。どうする、わたし?
第五話「小見太平(おみ・たいへい)の奇跡 ニューを放つ」——カップ麺会社の宣伝部で、おれは失敗した。起用した女性大食いユーチューバーが炎上した。代替案を上司に提案しなければならないが、電車が止まってしまう。「イッキュウちゃんの動画。見た?」という会話が聞こえたのはその時だ。
第六話「西村琴子(にしむら・ことこ)の奇跡 業を放つ」——満員電車で、彼の浮気相手をひそかに凝視する。彼はわたしの8歳年下で、その女はわたしの16歳下。有休をとり、女の乗った通勤電車にわたしも乗った。だが、わたしは決してストーカーではない。
第七話「黒瀬悦生(くろせ・えつお)の奇跡 空を放つ」——ななめ掛けしたボディバッグに拳銃を入れた俺は、とっくに尾行されていることに気がついていた。目的地の一つ前の駅で降りて住宅街を歩いていると、声をかけてきたのは、尾行していた刑事ではなかった。
小さいけれど確かに人生を左右する(かもしれない)7つのミラクルを描く、連作短編小説!
プロフィール
-
小野寺 史宜 (おのでら・ふみのり)
1968年、千葉県生まれ。法政大学文学部卒業。2006年に短篇「裏へ走り蹴り込め」で第86回オール讀物新人賞を受賞。08年『ROCKER』で第3回ポプラ社小説大賞優秀賞を受賞し、初の単行本を刊行。『ひと』で19年本屋大賞2位。主な著書に「みつばの郵便屋さん」シリーズ、『ひりつく夜の音』『夜の側に立つ』『ライフ』『縁』『まち』『今日も町の隅で』『食っちゃ寝て書いて』『タクジョ!』『今夜』『天使と悪魔のシネマ』『片見里荒川コネクション』『とにもかくにもごはん』『ミニシアターの六人』『いえ』など。
刊行記念エッセイ
奇跡の定義
小野寺史宜
前からずっと、『○○集』というタイトルの小説を出したいと思っていた。
理想は、『○○短編集』だ。『マーク・トウェイン短編集』や『スタインベック短編集』のような。でもそれは超大物作家さんだから許される話。僕の如き超小物ではとても無理。『小野寺史宜短編集』。って、誰だよそれ、になってしまう。下手をすれば、そんな名前の架空の作家が出した短編集という体なのね、と思われてしまう。
小説すばるさんから連載のご提案を頂いたとき、小さな奇跡の話、を思いついた。それが、集、と結びついた。その小さな奇跡の話を集めれば『奇跡集』になるじゃないの。
ただ、独立した話を集めるのでは連載の意味がない。奇跡くくりはあるにしても、それだけでは足りない。物語の幹がほしい。
考えに考えた。
僕は毎日一時間歩くのだが、歩くあいだずっと考えた。たまには各社の編集者さんとの打ち合わせ場所に赴くために電車に乗りもするのだが、電車のなかでもずっと考えた。
僕は立っていて、前の席には女性が座っていた。その女性は、書店さんの紙カバーが付けられた文庫本を読んでいた。『奇跡集』の第一話と似た状況だ。
僕は思った。女性が読んでいるのが僕の本ならうれしいだろうなぁ。でも超小物でそれはないだろうなぁ。自分の本を読む人と同じ電車に乗り合わせてそれを目撃するなんて凄まじい確率だもんなぁ。そんなのまさに奇跡だもんなぁ。
で、閃いた。
電車に乗り合わせた人。これは、いいんじゃん?
たまたま同じ電車に乗り合わせただけ。それぞれには何のつながりもない人々。でも小さな奇跡によってつながっていく。結果、ある程度大きなことも起こる。自分たちはそれを知らない。全容を知るのは読者だけ。いい。
その時点で構想ができていたのは第一話のみ。大変だぞ、と思ったが、これは書きたいぞ、とも思ってしまった。
初め、小説すばるさんへの連載は三回の予定だった。一号に二話×三回で計六話。すべて書いたあとで、もう一話増やして七話にしませんか? と担当編集者さんに言われた。連載も全四回にしましょう。
マママママジですか。喜び半分、不安半分。いや、うそはダメ。喜び一割、不安九割。でも僕は笑顔で言った。じゃ、そうしましょう。
また考えに考えた。
歩きながら考えた。他社の編集者さんとの打ち合わせを終えて乗った電車のなかでも考えた。
僕は立っていて、前の席には男性が座っていた。その男性は、書店さんの紙カバーが付けられていない文庫本を読んでいた。超大物作家さんの本だった。
そうか。超大物作家さんの本なら紙カバーを付けなくても恥ずかしくないのか。だとすれば、先の女性が読んでいたのは超小物作家すなわち僕の本だった可能性もある。いや、まさかね。
なんてことを思い、僕は電車の窓ガラスにうっすらと映る自分の顔を見た。『奇跡集』の登場人物たちもそうしたような感じで。
その場では思いつかなかったが、電車を降りてからあれこれ思いついた。そうなったらもう止まらない。止まれない。自宅の前を素通りし、右へ左へ歩きながらさらにいろいろ考えた。歩くのは、ものを考えるのにちょうどいいのだ。だから僕は一日一時間歩く。
朝四時台に起きて数時間書き、一時間歩いて昼ご飯。そのあとバッテリーが切れるので、がっつり昼寝。起きてまた数時間書く。一つの小説を書きはじめたら、書き終えるまで一日も空けずにその生活を続ける。手書きで下書き、パソコンで本書き。二回書く。そして推敲推敲また推敲。そんないつもの流れで、『奇跡集』は仕上がった。
かつて僕は長い投稿暗黒時代を過ごしていた。暗黒は今も微妙に続いているが、より暗黒。小説すばる新人賞にも何度か応募したことがある。
だから、そこで連載させてもらえたのはとてもうれしかった。『奇跡集』というタイトルで本を出してもらえるのはなおうれしい。
決して明るい話ではないが、この小説は書いていて楽しかった。
書き終えて、気づいた。奇跡と呼ばれるのは人に気づかれたものだけなのだと。
言えるのはそのくらい。あとは、読んでいただくしかない。
「青春と読書」2022年6月号転載
書評
本当に難しい「普通」のこと
藤田香織
あぁ、いい話だな、と思った。思ってしまった。
これほど雑な言い方もないが、小野寺史宜の小説は、基本「いい話」だ。
二〇〇八年にポプラ社小説大賞優秀賞を受賞し単行本デビュー作となった『ROCKER』や、作家として頭角を現した「みつばの郵便屋さん」シリーズからしてそうだったし、二〇十九年の本屋大賞二位となった『ひと』から続く『まち』、『いえ』の三作は言うまでもなく、怒濤の刊行ラッシュとなっている近年の作品(二〇二〇年から現在までで新刊単行本は本書で十冊目!)も、もちろん其々に味は異なり違う特長はあったが、総じていい話だった。
でも、だけど。その一方で、本書『奇跡集』を読み終えた今、これを「いい話」だと括ってはいけないのではないか、という気持ちも胸のなかにある。やばい、とちょっと心拍数が上がってしまうのは、もしかして、自分は大きな勘違いをしていたのかもしれない、と気付いたからだ。
舞台となるのは、通勤時間帯に走る満員の快速電車。物語は、何駅も通過する約十五分の「快速」区間で、突然しゃがみ込んでしまった若い女性の、周囲に居合わせた七人を連作形式で描いていく。
二十時間も前に飲んだキンキンに冷えた缶コーラが原因で、腹の暴れ竜が限界寸前まで動き出し、絶体絶命な十九歳の大学一年生・青戸条哉。父親が肺がんで余命半年の宣告を受け、三ヵ月が過ぎた状況にある二十四歳の大野柑奈。ある事件の捜査対象者を尾行している二十九歳の刑事・東原達人。ガス会社に勤める三十四歳の赤沢道香は、有休をとって実に五年振りのデートに向かう途中で、食品会社の広報宣伝部勤務の小見太平三十九歳は、仕事でどうにか成果をあげたいと気を焦らせていた。四十四歳の市役所職員、西村琴子は、八歳下の恋人の浮気相手を追跡中。そして最終話の主人公となる黒瀬悦生は無職の三十一歳、刑事の東原に追われている捜査対象者である。
車内でしゃがんでしまった女性は新倉凪。エアコンによる寒暖差に弱く体調を崩した彼女は、快速区間が終わった次の駅でどうにか降り、ホームのベンチに座り体調を整えようとする。同駅で下車し、駆け込んだトイレでお腹の暴れ竜を解放した青戸条哉は、そんな凪を心配し声をかける。彼女の目の前に座っていた大野柑奈も、わざわざひと駅先から様子を見に戻ってくる。
電車に残った他の五人のうち、赤沢道香は痴漢騒動を目撃し、犯人と間違えられた男性が連行されていくのを追いかけ、初デートに遅れることに躊躇いながらも、降りるはずではなかった駅で下車してしまう。
〈耳がキーンとする。ここ大事、とわたしは思う〉
この場面がとても印象的だった。〈こんな瞬間はこれまでに何度もあった。決断を迫られる瞬間だ。わたしはそれをすべて見逃してきた。時にはそうとわかっているのに見過ごしてきた〉。見過ごしたところで、どうということはない。男は赤の他人だ。余計な傷を負うこともない。〈何日か経てば、わたしはもうそのことを忘れていたはずだ。何も考えずに過ごしていたはずだ〉。
あぁ。と目を瞑りたくなる。自分がどれだけのものを見過ごしてきたのか、私も知っている、と息が詰まりそうになる。
作中、登場人物たちは、あんなことをしなければ、こんな酷いことにはならなかった、と何度も思う。けれど、ああしたから、こうなったのだ、助かったのだ、とも思う。どうしようもないこともある。防ぎようのないことも起きる。時間が経ったからこそ分気付くことも分かることもある。いくつもの「もしも」が重なって、いくつもの小さな奇跡が生まれるのだが、その様子が、ことさら大袈裟に強調されるわけでもなく、感情的にも感傷的にも過ぎることなく、描かれていくのがいい。
鋼鉄の胃袋を持つ北川くん、実在していたホワイトシチューうどん愛好者。直接交わることなくすれ違っていく登場人物たちの意外な関係性が見えるのも楽しく、さらには小野寺作品ではお馴染みの作家、横尾成吾や、劇団「東京フルボッコ」なども登場する。二重三重に人の輪が出来ていくような心強さが伝わってくる。
と、同時に苦しくもなるのだ。このひと言を自分はかけられるか。手を差し伸べられるか。この決断が出来るのか。小野寺史宜が本書で描いているのは、いやこれまで描き続けてきたのは「いい話」ではなく、本来「普通の話」と呼ばれるべきものだったのではないか――。
いつの日か、本書で描かれる「奇跡」を、多くの人が「よくある話だよね」と感じる日が来るといいな、と心から思う。
ふじた・かをり ◆ ’68年三重県生まれ。書評家。
著書に『ホンのお楽しみ』、書評家の杉江松恋氏との共著『東海道でしょう!』など。
「小説すばる」2022年6月号掲載
『奇跡集』試し読み
新着コンテンツ
-
新刊案内2025年06月26日
 新刊案内2025年06月26日
新刊案内2025年06月26日筏までの距離
水原涼
デビュー作で芥川賞候補に挙がった著者が贈る、わたしとあなたの8つの物語。
-
インタビュー・対談2025年06月20日
 インタビュー・対談2025年06月20日
インタビュー・対談2025年06月20日宇山佳佑×檜山沙耶(フリーアナウンサー)「風が吹くたび、物語が生まれる」
ウェザーニューズで気象キャスターとして活躍し、その後も活動の幅を広げる檜山沙耶さんと作品、風、お天気について語っていただきました。
-
お知らせ2025年06月17日
 お知らせ2025年06月17日
お知らせ2025年06月17日小説すばる7月号、好評発売中です!
新連載はいずれも小説すばる新人賞出身の佐藤雫さん、神尾水無子さんの2本立て!
-
お知らせ2025年06月17日
 お知らせ2025年06月17日
お知らせ2025年06月17日本日開店、「スキマブックス」!!
文芸ステーションに新しい読みもののコーナー「スキマブックス」がオープンしました!
-
スキマブックス2025年06月17日
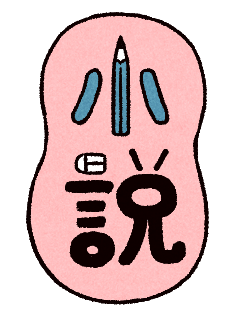 スキマブックス2025年06月17日
スキマブックス2025年06月17日今度こそ許すまじ春野菜といんげん豆の冷製スープ事件
結城真一郎
彼氏が浮気をしているのではないかと疑った大学生は、「あるレストラン」に浮気調査を依頼するが――。
-
インタビュー・対談2025年06月17日
 インタビュー・対談2025年06月17日
インタビュー・対談2025年06月17日堂場瞬一「日本政治の未来をフィクションで問う」
堂場瞬一さんの通算195冊目の作品にして、実験的政治小説第二弾『ポピュリズム』の世界観を語ってもらった。



