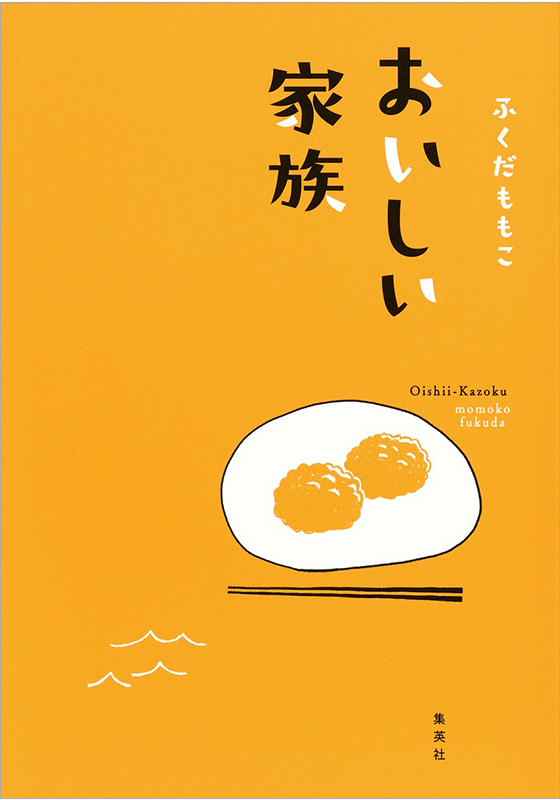プロフィール
-
ふくだ ももこ (ふくだ・ももこ)
作家、映画監督、脚本家。
1991年大阪府生まれ。日本映画学校で映画を学ぶ。卒業制作『グッバイ・マーザー』がゆうばり国際映画祭2014、第6回下北沢映画祭、湖畔の映画祭で入選。16年「えん」で第40回すばる文学賞佳作を受賞し小説家デビュー。映画『おいしい家族』では脚本・監督を務めた。
『おいしい家族』刊行記念インタビュー
ハッピーエンドを信じ、小説と映画で伝えたい
銀座でビューティーアドバイザーとして働く橙花(とうか)が、母の三回忌のため実家のある離島へ帰ると、父・青治(せいじ)が母の服を着て生活していた。驚きを隠せない橙花に、青治は「この人と家族になる」と、和生(かずお)という男を紹介する──。
「えん」で第40回すばる文学賞佳作を受賞したふくだももこさんの新刊は、映画監督でもあるふくださん初の長編映画『おいしい家族』撮影終了後に執筆され、映画版公開と同時期に発売されるという話題作です。
島で農業を営む弟の翠(みどり)と翠の妻でスリランカ人のサムザナは、素直に青治と和生、和生の娘で島では珍しい白い肌の少女・ダリアという“あたらしい家族”を祝福しますが、橙花は納得できません。個性豊かな人物たちが自分らしさを求める姿をみずみずしく描いた今作について、家族というテーマにこだわるふくださんご自身の生い立ちや小説と映画の違いなども含めながらお話しいただきました。
聞き手・構成=山本圭子/撮影=冨永智子

母の不在を考えるふたつの理由
── 仕事も夫との関係もうまくいかない橙花が、母の三回忌で離島の実家に帰ると、母の服を着た父が「おかえり」と言った──この驚きの場面から一気に物語は動いていきますが、ふくださんは前作「ブルーハーツを聴いた夜、君とキスしてさようなら」(「すばる」2017年12月号)でも、主人公の母がいなくなったあと母親を演じる父を描いていらっしゃいます。ふくださんにとってこれは、深めたいテーマなのでしょうか。
そればっかり書いてしまっていますね(笑)。私が小3か小4のとき、オカンが家を出ていったことがあったんです。しばらくして帰ってきましたけど。連絡もとれず、どうなるんだろうと思っていたら、その日からオトンが何も言わずに料理や家事を始めた。「なんだ、これは!?」という、当時のインパクトが強く残っているんです。「ブルーハーツを聴いた夜、君とキスしてさようなら」は、主人公の母が置いていった口紅が物語のキーですが、そのときの経験がもとになっていて。オカンがいなくなったあと、三面鏡の引き出しを開けてみたら、コロコロと口紅が転がってきた。「あ、オカンは母親という人種やなかったんや。女の人やったんや」と気づいた瞬間でした。母を演じる父を書くのにはもうひとつ理由があって、私の生い立ちも影響していると思います。
── それはどういうことでしょうか。
私は養子で、自分を産んだ人を知らないんです。「母親が不在」という感覚がずっとあるので、オカンが出ていったときのインパクトと重なって「考えなきゃいけないこと」として自分の中にあるんだと思います。
── 「父親を知らない。不在である」ということは、あまり意識しないのですか。
父親を想像したことは一度もないですね。なんでやろうな。絶対いるはずなのに。想像ですけど、私を産んだ人はその時、一人やったんちゃうかなと思います。事情があって施設に託してるわけやし。言われてはじめて、子どもにとっての父親の存在の希薄さを感じてしまいました。私も心の中で、母親の存在の方が圧倒的に大きくなってしまっていますね。いつか自分が母親になるかもしれないということが、関係しているような気もします。
── ご両親の実子ではなく養子だということは、いつ頃お聞きになったのですか。
小1くらいのときです。私は0歳で子どもがいなかった今の両親に引き取られたんです。それを聞いたときのことはあまり覚えていなくて。あとからオカンに聞いた話では、次の日に学校で「私、養子やねんて。めっちゃおもろない?」と言いふらしたらしい。そのあと同じクラスの子に「じゃあももちゃんは捨て子ってこと?」と言われて、「捨て子ちゃうし、もらい子やから!」と言い返したみたいで。オカンは「“こいつ、強っ!”と思った」と言っていました(笑)。もしかしたら「養子だ」と聞いて、アイデンティティーを得た感覚になったのかも。血のつながりに重きを置く家族の話を映画で観たりすると、「おお、そうなんだ! でも、そこだけにこだわる必要ないのにな」と思いますね。
── この物語では、島の高校の校長をしている橙花の父・青治が「実はな、父さんたち(父と福島から移住してきた和生とダリア親子)、家族になる」「父さんな、あたらしい家族の母さんになろうと思う」と言い出します。それを聞いた橙花は弟の翠のように“あたらしい家族”をあっさり祝福できないし、何より父の言葉に納得できない。橙花の気持ちは理解できるだけに、物語に引き込まれていきました。
橙花が一番ひっかかっているのは「母親になりたい」という父の考えであり、価値観なんです。母が亡くなったあと、そう思うようになった父を認めたら、母の存在が消えてしまうんじゃないか。そして父の人格もなくなってしまうんじゃないか。とにかく橙花は母が大好きすぎたから、そこが反発の核になっていると思います。
生きるのに欠かせないのはユーモアと食
── 家族の問題にはそれぞれの深い思いが絡んでいるだけに、解決が難しいのは当然だと思います。ただこの物語にはクスッと笑える雰囲気が漂っているので、重くなりすぎない。そこがふくださんの個性かなと感じました。
ユーモアはめっちゃ大事にしていますね。自分では意識していなかったけど、映画を観た方に「ユーモアがありますよね」と言われて、自分が大事にしていることに気づいたんです。どんなに悲惨な状況でも、ユーモアがあれば生きていける気がするから、本当に大事にしていきたい。
── そこには大阪のご出身ということも関係しているのでしょうか。
やっぱり大きいと思います。まわりにはいろんな子がいたけど、不幸な話もだいたい笑いにしてたし。さっき養子の話をしましたが、映画の学校で初めて課題の撮影に取りかかるとき、先生にそのことを話したんです。そしたら「きみ、それめちゃめちゃ面白いよ。それを脚本にしなよ!」と言われて。「私、そんなふうに言ってほしかったんだ」と初めて気づきました。同じ齢くらいの子に養子のことを話すと、引かれることが多かったので。それが「私は映画で生きていけるかもしれない」と思った瞬間でしたね。
── 和生とダリアの親子、ダリアの同級生・瀧(たき)、橙花の弟の翠など多彩な人物が登場しますが、みんな個性豊かで魅力的です。そこも物語の雰囲気にマッチしていますね。
ありがとうございます。映画『おいしい家族』を撮り終わったあと、この小説を書きましたが、映画のもとになっているのが『父の結婚』という以前製作した短編映画。短編をふくらませて長編にするためにまず思いついたのが、ダリアと瀧なんです。最初は小学生を考えていましたが、高校生にすれば以前から撮りたかったモトーラ世理奈ちゃんと三河悠冴くんを役者に使えると思った。それに「将来に夢と不安を抱いているふたりを家族とは違う軸にして橙花とかかわらせたら、彼女は自分が抱えている整理がつかない問題を引いた目で見ることができる」と考えたんです。そして、橙花がもともとの自分に立ち返ることができるんじゃないかな、と。
── ダリアはアイドルに憧れている女子高生で、ちょっとひねくれた瀧のことが好き。ただ彼は、ある秘密を抱えています。橙花がダリアと瀧に見せるさりげないやさしさは、決してわからずやではない、本来の彼女の性格を表していると思いました。
「橙花を悪い人にしたくない」という思いはずっとありましたね。彼女が父親を許せないのは家族だから。根はいいヤツなんです(笑)。
── タイトルに「おいしい」という言葉が使われていますが、家族で食卓を囲む場面がたびたび出てきます。ふくださんにとって食べることはどんな意味を持っているのでしょうか。
食べることはこの物語のキーになっています。人間の営みはまず食べないと始まらないし、家族の事件は食卓で起きることがほとんど。そして事件が解決するのも食卓じゃないのかな、と思っていますね。
── 大勢でとる食事のにぎやかさやパワーがお好きなんですか。
私の青春時代の実家の食卓は居心地が悪くて、あまり好きじゃなかったんです。あるとき大家族の友だちの家でご飯を食べたら、でっかい皿にハンバーグがバコバコのっていて、「好きなだけ食べて!」みたいな感じだった。それを「なんだかいいな」と思ったんです。みんなでワイワイしゃべったり、ああだこうだ言いながら食べる雰囲気も。ウチはひとり分のハンバーグがそれぞれの皿にのっていて、だいたいみんなテレビを見ながら無言で食べていた。だから「食卓ってこういうことか。家族ってこういうことか!」と感動したし、あこがれたんだと思います。台所もそうですよね。どんな鍋、どんな調味料が、どんなふうに置かれているか。そこに家族が表れていると思います。
小説では橙花のことをさらに深く考えた
── 物語の舞台が「島」ということにも、大きな意味があると思いました。たとえば、和生はあてもなく移住してきて“なんでも屋”を始めた男ですが、最初は苦労したものの青治の口利きをきっかけに人手が足りない農家などの手助けをして、収入を得るようになった。島を舞台にしたから、こういうキャラクターもできた気がします。
両親が島の出身なんです。オカンが愛媛の島で、オトンが淡路島。私が住んでいたのは大阪郊外の盆地みたいなところですが、小さい頃はよく島に行っていました。軽トラに乗って海に行ったりした思い出が、私の原風景になっているのかも。島にずっといる人にとっては人間関係などしんどいこともあると思うけど、子どもにとってはみんなおおらかでいい場所でした。だから短編から長編映画にするとき、プロデューサーから「家の話だけでは広がらないから町の話にしよう」と言われて思いついたのが島。やっぱり海があるというのはメチャクチャ大きいと思います。住んでいる人には「海は自分を包んでくれるけど、海に阻まれて島から抜け出せない」みたいな感覚があると思うので。
── 映画の撮影場所になった式根島と新島は、ふくださんご自身で見つけたそうですね。
予算の関係で都内の島を探していたんです。写真やグーグルマップで。実際に行ってみたら、式根島の入り江は本当にきれいだったし、新島はめっちゃ人との距離が近い島でした。エキストラの島の小学生と撮影の翌日にばったり会って「きのうはありがとう!」と言ったら「いいよー!」と返してくれたり。舞台を島にしたからユートピアという感じが出せたし、今は「こういう島が本当にあるんじゃないかな。あるといいな」と思っていますね。
── 脚本・監督を手がけた『おいしい家族』を小説にしてみて、それぞれの面白さや違いをどう感じていらっしゃいますか。
私の中では映画と小説はまったくの別物です。脚本は映画の設計図みたいなもので、それをもとにいろんなプロフェッショナルたちがかかわってひとつの作品にしていく。小説はそれだけで作品だから、書き方が全然違ってきます。今回は脚本を書いて映画を撮って、仕上げまでに何回も見て完成させたものをもう一度小説として書くという作業だったから、ほんまにきつかった(笑)。
── 書きやすいわけではなかったんですね。
最初は映像を文字に起こす感覚で書いてしまって。「これではダメだ!」と思いました。主人公なのに橙花の影が薄くなったんです。いろいろ模索して、章によって視点を変える、橙花のことをもっとちゃんと考えるという作業を始めました。そこから気持ちを切り替えられて、いい感じになっていきましたね。この映画の取材を受けることも多いのですが、小説を書いてからのほうが自分の思っていたことをはっきり話せるようになりました。多分、頭の整理ができたのだと思います。
── 橙花の父への反発心、ダリアと瀧の未来像の変化がクライマックスにつながっていきますが、そこに大きくかかわるのがメイクや服です。特にメイクについては、橙花の仕事がビューティーアドバイザーという設定で、彼女の口紅へのこだわりも描かれていますね。
私自身はそんなにごてごてメイクはしませんが(笑)、口紅って見た目を一番変えるし、気分もすごく変えるもの。オカンの口紅の思い出もあるから、小説でよく使うのかもしれません。橙花は仕事も人間関係も、そしてメイクもうまくいかなくて落ち込みますが、映画では出せなかったそういう面──メイクと気分の関係を小説ではちゃんと書けた。そこはすごくよかったと思っています。
── 自分を大切にするとは。人にやさしくするとは。読みながらそんなことを考えて、心がふわっとあたたかくなる小説でした。
私にはハッピーエンドを信じたいという気持ちがすごくあるんだと思います。みんなちょっとでもよくなってほしい。よく生きてほしい。これからも小説と映画で、それが伝わるものを作っていきたいと思っています。
「青春と読書」10月号より転載
<映画情報>
ふくだももこ長編初監督作品
全国ロードショー公開中
出演
松本穂香 板尾創路 浜野謙太 笠松将 モトーラ世理奈 三河悠冴 鉼俊太郎
監督・脚本
ふくだももこ
©2019「おいしい家族」製作委員会
STORY
都会で働く橙花(松本穂香)が母の三回忌に実家のある離島に戻ると、父・青治(板尾創路)が亡き妻の服を着て、ごはんを作って待っていた。驚く娘に青治は「この人と家族になる」と居候の男性・和生(浜野謙太)を紹介する。
新着コンテンツ
-
インタビュー・対談2025年07月08日
 インタビュー・対談2025年07月08日
インタビュー・対談2025年07月08日桜木柴乃「波風立てずに生きる器用さを、ちょっと残念だなと感じる大人に読んでほしい」
著者五十代の最後を飾る、集大成的な短編集である本作。仕事に対する現在の思いや、短編を書く面白さをうかがいました。
-
お知らせ2025年07月04日
 お知らせ2025年07月04日
お知らせ2025年07月04日すばる8月号、好評発売中です!
演劇界注目の劇作家・演出家ピンク地底人3号さんによる初の小説を掲載! 遠野遥さんの短期集中連載も最終回を迎えます。
-
インタビュー・対談2025年07月04日
 インタビュー・対談2025年07月04日
インタビュー・対談2025年07月04日石井遊佳×藤野可織「魂を自由にする虚構の力」
ホラー愛好家を自認する藤野さんは石井さんの新作に詰まった四つの物語をどう味わい、そこに何を見つけたのか。
-
新刊案内2025年07月04日
 新刊案内2025年07月04日
新刊案内2025年07月04日給水塔から見た虹は
窪美澄
2人の“こども”が少しずつ“おとな”になるひと夏を描いた、ほろ苦くも大きな感動を呼ぶ、ある青春の逃避行。
-
新刊案内2025年07月04日
 新刊案内2025年07月04日
新刊案内2025年07月04日青の純度
篠田節子
煌びやかな「バブル絵画」の裏に潜んだ底知れぬ闇に迫る、渾身のアート×ミステリー大長編!
-
新刊案内2025年07月04日
 新刊案内2025年07月04日
新刊案内2025年07月04日情熱
桜木柴乃
直木賞受賞作『ホテルローヤル』、中央公論文芸賞受賞作『家族じまい』に連なる、生き惑う大人たちの物語。