
内容紹介
第一稿 昭和三十四年六月二十一日。
主人公太郎の悪漢ぶりが痛快なピカレスク物語。
時は156…年。舞台は羽前の国、小松郷。病気の老母を連れて、馬一頭と村にやってきた太郎。村の有力者、横暴な松左エ門は、この馬が黄金のくそをすると聞き、太郎から無理矢理買い上げるが、黄金のくそなどするはずもなく、馬は殺された。その後、太郎は巧みな嘘を重ね、松左エ門ら村人から大金をまきあげ……。
プロフィール
-
井上 ひさし (いのうえ・ひさし)
1934年山形県東置賜郡小松町(現・川西町)生まれ。上智大学外国語学部フランス語学科卒業。浅草のストリップ劇場フランス座文芸部員兼進行係を経て、放送作家として「ひょっこりひょうたん島」などを手掛ける。その後、戯曲、小説、随筆の執筆へと活動範囲を拡げる。’72年『道元の冒険』で岸田戯曲賞、『手鎖心中』で直木賞受賞、ほか著作、受賞歴多数。’84年こまつ座を旗揚げ。旗揚げ公演の『頭痛肩こり樋口一葉』から以降、’09年の『組曲虐殺』まで、こまつ座のために共催を含めて25作品を執筆。「九条の会」呼びかけ人、日本ペンクラブ会長、仙台文学館館長、また多くの文学賞の選考委員を務めた。’10年4月9日、75歳で死去。
トークイベント
※2023年1月29日に実施された配信のアーカイブです
書評
井上芝居の万華鏡
今村麻子
井上ひさしさんほど亡くなってからも存在感のある作家はいない。井上作品が上演されない年はなく、繰り返し上演されてもいつも新しく、何度観ても新発見がある。東北の震災後に観た、江戸から釜石へ若旦那とたいこもちが流れ着き果てない「道の苦」が始まる『たいこどんどん』(蜷川幸雄演出)や、死者の思いを「思い残し切符」に託した『イーハトーボの劇列車』(長塚圭史演出)は、震災で犠牲になった方々への鎮魂として響いた。東京オリンピック開催で揺れる時期に観た『藪原検校』(杉原邦生演出)には大国の支配構造を肌で感じた。コロナ禍の中で初日を迎えた『キネマの天地』(小川絵梨子演出)は、上演を目指す俳優・スタッフへの讃歌として励まされる。『貧乏物語』(栗山民也演出)観劇後、ウクライナの劇場再開が報じられた。文化活動継続が武力への抵抗だ。思想弾圧や拷問に屈せず信念を貫く劇の登場人物に重なった。
井上さんは未来を見通していたかのように次世代にバトンを渡し、いつどんなときも、どう生きるべきかを忘れないよう指針を示してくれる。新型コロナウイルスの変異株の種類がどこまで増えたか追いつけなくなり、キーウの街が爆撃される映像に陰陰滅滅としているところへ突如飛び込んできた「井上ひさし未発表戯曲が見つかる!」というニュース。暗い世を見かねた井上さんが「見つかりましたね」と笑顔でひょっこり現れたよう。
発見の経緯は本書の付録で井上ユリさんが教えてくれる。生前井上ひさしさんは「東京小劇場」という劇団の演出家に戯曲を渡した。その演出家から戯曲を託された俳優は故人。押し入れの奥から見つけた家族がテレビ東京『開運!なんでも鑑定団』に出品し三百万円の値がついた。すぐさま二〇二二年七月号の『すばる』に掲載された後、単行本になったのがこの一冊だ。
時は一五六…年、所は羽前の国、小松郷。主人公の太郎が村にやってきて「金のくそ」をする馬を権力者(馬地主)の松左エ門に売る。だが、馬はただのくそしかしない。松左エ門は腹を立て、太郎を叩く。太郎は怒り、殺された馬の皮が予言めいたことを話すと騙り、言葉巧みに五助、和尚をだまして金を得る。その後も噓に噓を重ねるのだが、噓をつく相手が金と権力で思い通りにしようとする馬地主とそれに言いなりになっている村人たちなのだから痛快。こうして太郎は無法な論理をふりかざす馬地主の権威をひっくり返す。
井上さんが元気だったとき取材でこんな話をしてくれた。「わたしたちは究極の詐欺の軍団です。芝居ができあがっていないのに切符を買ってもらうから。ただ、できあがったものがいい芝居だと、詐欺が詐欺でなくなる。お金をもらっていながら、つまらない芝居を観せるほうが詐欺に近くなって、わたしたちの方がまともになる」と。太郎が言葉を武器に真実を作り出す逆転劇の構造が見える。
これまで観てきた井上芝居が万華鏡のように乱反射しながら蘇る。あるときの太郎には蜷川幸雄演出『天保十二年のシェイクスピア』で観たきじるしの王次(藤原竜也)の無邪気、『道元の冒険』の道元(阿部寛)の狂気、『たいこどんどん』の若旦那(中村橋之助、現・芝翫)ののほほんとした明るさもある。また平然と人を殺めて金をかすめとる場面では栗山民也演出で観た『藪原検校』の杉の市(野村萬斎)の極悪さや、『雨』の徳(市川亀治郎、現・猿之助)の眼光も彷彿とさせる。どれも矛盾し相反する役ばかりだが、太郎に彼らの魅力が見え隠れする。井上芝居の原点として、その多彩さと多面性がぎっしりと詰まっている。
「ひょっとしたら、私は日本のシェイクスピアかモリエールになれるかも知れぬ」とは井上さん三十五歳のときの言葉。モリエール『守銭奴』の主人公アルパゴンは、息子の若い恋人を後妻としてその晩のうちに迎えたい。この構造は『うま』にも当てはまる。松左エ門はアルパゴン同様に同意なしに養女ちかとその日のうちに祝言をあげると言い困らせる。金を持つ自分との結婚は「女の望める最高の地位」と考えているところも重なる。井上さんはこの発展形として文楽『金壺親父恋達引』を一九七二年に書いた。金を土に埋めて隠す太郎もまた、金の入った小箱を庭に埋めて隠すアルパゴンそのもので、松左エ門とアンチヒーロー太郎は分身の関係とも言える。同一人物の二つの顔を二人の人物が演じ分ける『表裏源内蛙合戦』や『道元の冒険』の道元が現代の狂者に入れ替わる趣向に通じる。二人は一人であり一人は二人、もっと言えば『父と暮せば』の父娘も。
馬の皮がしゃべるという発想もおもしろい。風間杜夫が馬の前足、吉田鋼太郎が馬の後足を演じた『しみじみ日本・乃木大将』(蜷川幸雄演出)がある。井上さんに訊いたとき「馬の目線で乃木希典を語ります」「え? 馬が人間の言葉で?」「そうです。ふふふふ」と。「馬格分裂」を起こし足並みが揃わなくなっていく。馬の身体が代弁する趣向はここにもあった。
登場人物の名前のちかと権ずは『うかうか三十、ちょろちょろ四十』に登場し本書の今村忠純の解説では「木下(順二)民話劇を擬装したこの戯曲には地主と小作人の力関係と宗教が隠れている」と指摘する。名前のことだけで言えば、太郎という名は『日の浦姫物語』の魚名の別名だ。『うま』の太郎はせつやちか、お京を口説いては一夜を共にする。日の浦が初夜で「やめて、やめて、続けて、やめて」という卑猥さにも自分が何者かを探す太郎にも『うま』の要素がある。
『うま』を読んでいると、これまでの井上芝居が走馬灯のように駆け巡る。井上さんほど今現在を生きる作家を他に知らない。
「すばる」2023年3月号転載
新着コンテンツ
-
新刊案内2025年06月26日
 新刊案内2025年06月26日
新刊案内2025年06月26日筏までの距離
水原涼
デビュー作で芥川賞候補に挙がった著者が贈る、わたしとあなたの8つの物語。
-
インタビュー・対談2025年06月20日
 インタビュー・対談2025年06月20日
インタビュー・対談2025年06月20日宇山佳佑×檜山沙耶(フリーアナウンサー)「風が吹くたび、物語が生まれる」
ウェザーニューズで気象キャスターとして活躍し、その後も活動の幅を広げる檜山沙耶さんと作品、風、お天気について語っていただきました。
-
お知らせ2025年06月17日
 お知らせ2025年06月17日
お知らせ2025年06月17日小説すばる7月号、好評発売中です!
新連載はいずれも小説すばる新人賞出身の佐藤雫さん、神尾水無子さんの2本立て!
-
お知らせ2025年06月17日
 お知らせ2025年06月17日
お知らせ2025年06月17日本日開店、「スキマブックス」!!
文芸ステーションに新しい読みもののコーナー「スキマブックス」がオープンしました!
-
スキマブックス2025年06月17日
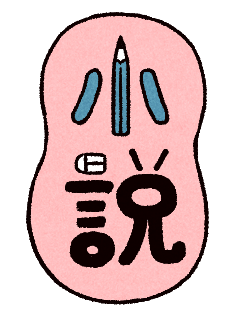 スキマブックス2025年06月17日
スキマブックス2025年06月17日今度こそ許すまじ春野菜といんげん豆の冷製スープ事件
結城真一郎
彼氏が浮気をしているのではないかと疑った大学生は、「あるレストラン」に浮気調査を依頼するが――。
-
インタビュー・対談2025年06月17日
 インタビュー・対談2025年06月17日
インタビュー・対談2025年06月17日堂場瞬一「日本政治の未来をフィクションで問う」
堂場瞬一さんの通算195冊目の作品にして、実験的政治小説第二弾『ポピュリズム』の世界観を語ってもらった。


