
時間がないけど読書がしたい!
そんなあなたのための、スキマ時間で楽しめるネット上の小さな本屋さん。
スキマブックス、開店します。
「昨日は蛍」 其ノ参
森晶麿
【30分で読める】【小説】
俳人・虚池空白と編集者の古戸馬が紛れ込んだ、ある怪しい村の秘密――『虚池空白の自由律な事件簿』初のスピンオフ!
2025年10月15日
7
劇はその後も続いた。ただしそれは『聖書』におけるモーゼが十戒を告げるよりも冗長で退屈な芝居だった。まるで止まらない貨物列車みたいだ。二十分ほど経っただろうか。〈光の神〉は戒律のお告げに一区切りをつけると、ようやく客席全体にこう宣言した。
「村はまた新たなる光を手に入れるであろう。いざ行かん、今日よりも輝ける明日へ」
「いざ行かん、今日よりも輝ける明日へ!」
どうやらこれが、この劇のお決まりの締めの文句であるらしかった。村人たちの輪唱が終わると、空の上に無数の光が点灯した。蛍だった。
これが、伊藤の言っていた〈素敵な光景〉なのか……。その煌きに圧倒されながら、〈光の神〉が再びマンタのごとく去るのを見送った。
そのあとは風間が「業務連絡」を始めた。ほとんどは農作業に関することで、僕らにはまったく興味の持てない内容だった。客席の意識が風間の業務連絡に集中している隙に、虚池が璃々に尋ねた。
「確かめたいことが。まずあなたも木村さん同様、碑の落書きの作者はご友人のマサシさんだとお考えですか?」
「……はい、もちろんです」
「根拠は、筆跡ですか?」
「それもありますが、もう一つは内容です」
「内容?」
「私にはよくわからないんですが、木村が言うにはあれはマサシから我々へのメッセージだ、と」
「〈捨てた蛍光性の過去〉という言葉が、お二人へのメッセージだと──木村さんはそうお考えだったわけですね?」
「我々二人かはわかりません。もっと広い意味かも……でも、とにかく急に連絡を途絶えさせるような友達じゃないんです」
木村の話を聞いていた段階では、僕はまだ半信半疑だった。でも今は状況が変わってきている。いくら村が大切にする虫を踏んだとはいえ、さっきの対応は異様だ。
「お辛いところ、お答えいただきありがとうございます」
その虚池の言葉に僕は驚いた。そんな人間らしい気遣いが、虚池にできるとは思わなかったのだ。
虚池は何事か考え込むようだったが、不意に遠くを見つめた。それから、木村がさっきまでいた方面へとおもむろに歩き出し、しゃがみこんで何かを摘まみ上げた。
細長い黒い虫の死骸だ。
村長が愛すべき存在と呼んだものの正体──蛍だった。
「いろいろと、腑に落ちないな」と虚池が呟いた。
「何がだい?」
「いろいろさ。何から何まで」
「あの……」とそこで璃々が僕に話しかけた。「……できれば場所を変えて話せませんか」
虚池は気を遣ったのか「俺は先にホテルに戻る」と囁いた。
虚池が僕らに背を向けて歩きだすと、璃々が僕の手を握ってきた。
その手は冷たく、かすかに震えていたのだった。
8
璃々が予想だにせぬ打ち明け話を始めたのは、〈ひかりの広場〉から遠ざかって〈ほたるホテル〉に向けて川沿いを歩き始めた時だ。
「私たちミス研メンバーには専門分野があります。私は国内ミステリ、それも新本格以降のものが中心で、充はコリン・デクスターとか、P・D・ジェイムズのような海外のパズラーが好きでした」
息継ぎもせずに話すことで、どうにか精神の均衡を保とうとしているかに見えた。
「同期のマサシは、ポオや涙香、乱歩、最近だと竹本健治が好きでした。暗号マニア、廃墟マニア、孤島マニア、ある意味いちばん風変わりな子でした」
そこまで言ってから、璃々はエコバッグの中から水筒を取り出して飲んだ。彼女にも例のエコバッグは用意されていたようだった。
「なるほど。〈ほたるとぴあ〉跡地へ行く計画を立てたのもマサシさんなんですね? だからお二人より一日早くこの村へたどり着かれた。ところが姿が見えない。どこに隠れているんでしょうね?」
「それは私たちにもわかりません。ただ、マサシは私なんかよりずっと頭のいい子です。彼がもしメッセージを発したのだとしたら、それはよほどの危機に面していたんじゃないでしょうか。そうでなければ、自分一人で切り抜けられるタイプですから」
彼女は僕の目をじっと見た。だが、次の瞬間、何かを言おうとしてひっこめ、代わりに僕に抱きついてきたのだった。
「え、あの……璃々さん……?」
「怖いんです……何か予想を超えた恐ろしいことが起こりそうで」
予想を超えた恐ろしいこと──。それは何だろうか?
だが、僕は同時に考えていた。もしかしたら、そんな最悪の未来さえ、人間は脳の片隅で予想している時がありはしないか、と。
その時だった。ある一点を凝視して、璃々の表情が固まった。
「うそ……そんな……見てください、あの言葉……」
突然、彼女が震え出した。彼女の視線は、川辺にある例の碑に向けられていた。
彼女の視線を追う。そして──それを見つけた。
「あれ……? うそだ、そんな馬鹿な……」
そこには消されたはずの例の落書きが、記されていたのだ。
〈捨てた蛍光性の過去〉
野良句がよみがえった? または、新たに記されたのか? 誰が、何のためにそんなことをするのだろう?
「充が言うには……」
そう言いかけて彼女がハッと言葉を飲み込んだ。川沿いに村人たちが数名こちらへ向かって歩いてきていたからだ。先頭にいるのは、風間。それ以外は女性ばかり。風間は璃々に向かって頭を下げた。
「先ほどは木村さんに大変失礼を致しました。しかし、木村さんも心に溜めておられた罪を吐き出してすっきりされました」
「充は……充はいまどこに……!」
璃々がすがるようにして尋ねた。すると、風間は彼女の興奮を鎮めようとでもいうのか、深く頷いてみせた。
「大丈夫、いまは我々のおもてなしを受けて寛いでおられます」
ゆっくり話すことで、風間の言葉には独特の魔力めいたものが備わるようだ。よく考えれば妙だ。なぜおもてなしを? そんなことより、早く璃々のもとに木村を戻してあげるのが礼儀なのでは?
しかし、となりで聞いている僕でさえ、咄嗟にそれらの疑問が出てこなかった。ある意味では、風間に封じられていたのだ。
そのまま風間は、さらに璃々との距離を縮め、自分のペースで言葉を続けた。
「蛍を踏んだのは、過ちに気づくきっかけです」
「過ち……? 充がどんな過ちをしたというんですか?」
震える声で尋ねる璃々を安心させるように、風間はその肩に手を置いた。
「彼が後ろめたく思っていたのは、マサシさんの恋心を知りながらあなたを自分のものにしたことでした」
「……何を言っているの? そんなの、でたらめだわ……」
風間は璃々の目を見据え、ゆっくりと首を横に振った。
「彼は語ってくれました。マサシさんへの対抗心があっただけで、あなたのことを好きだったわけでは少しもない、と」
「うそよ……そんな……充がそんなことを言うはずは……」
言葉とは裏腹に、璃々の目には涙が溢れていた。彼女は内臓が口から飛び出すのを防ごうとするかのように、両手で口元を押さえた。風間の言葉がもともとある璃々の内面の恐れを炙り出したのに違いなかった。
風間は、今度は恵比寿も仰天するくらいの笑みを浮かべると、目を細めながらこう告げたのだった。
「本当ですよ。その証拠に、いまはうちの村の女性と楽しい夜を過ごしています。ご覧になりますか? あまりお勧めはしませんが」
風間は相変わらずゆっくりとした口調で魔力を維持していた。宣告内容の残酷さと釣り合わぬ笑顔が余計にこの男を不気味にみせた。だが、その背後に付き従って無表情でいる村人たちのほうが、実際には何倍も僕には恐ろしく思えた。
なんだ……何なのだ、この村の連中は一体……。
けれど、璃々のほうは死刑を告げられでもしたかのごとく茫然自失の状態に陥っていた。とてもではないが、「何なんでしょうねこの人たち」なんて同意を求めても相槌の一つも期待できそうにない。
璃々は僕から体を離し、川のほうへ後ずさった。内なる恐れから遠ざかろうとするあまり、足が勝手に後退してしまったのだろう。
「心中お察しします。でも本人は、罪の意識から解放され、幸せそうです。祝ってあげてください」
風間の言葉を頭に入れまいと、璃々は己の頭を両手で押さえた。
「ああああああああああころすころすころす!」
目や鼻や耳から血でも吹きださんばかりの剣幕だ。その肩を、風間がさすり、村の女たちに静かな口調で命じる。
「璃々さんの気持ちを鎮めて差し上げなさい」
すると、どうだろう。それまで人形のごとく表情を殺して風景と化していた彼女たちが、途端に有能な手足となって動き始めた。
女たちは璃々を取り囲んだ。
「ちょ……ちょっと待ってください……」
そう言った僕の声はひどく掠れていたし、何なら夜風に舞ってちぎれて消えてしまったかもしれなかった。
村の女たちは、花びらで包み込むように璃々を抱きしめた。うち何人かは璃々と呼吸を揃えて涙を浮かべてもいた。それが少しもわざとらしくなく、本当に感情を同期化しているようであるのが、かえって気色悪かった。
不意に、風間が僕の肩に手をあてた。
今度は僕が何かのまじないに掛けられる番なのか。戦慄が身体を駆け巡った。風間は、やはりあのうさん臭い笑みを浮かべた。
「女性のことは女性にお任せしましょう。今日はもうお休みください」
嚙んで含めるとはこのことかというくらい、まったりとした口調だった。
女たちが璃々を連れ去り、風間も去ると、川沿いには僕だけが残された。何もできなかった。何も。僕はまったく木偶の坊だった。
例の碑を見た。そこには、いまだにあの言葉がある。よく見れば闇夜でも浮き立つように白く光ってみえる。
まるで──その言葉こそが蛍であるかのように。
僕は、せめてもの務めを果たそうと、それをそっと写メに収めた。
9
ホテルに着くと、何とはなしに体がだるかった。あれこれと慣れぬ騒動を目の当たりにしたせいだろう。ロビーのソファに腰を下ろし、エコバッグの水筒からまたぐびぐびと飲んだ。不思議と、飲んでいる間は水のように体に入って、疲れがほぐれる感覚がある。
すると、すぐ隣に人影があるのに気付いた。
「よう、色男」
隣のソファに腰を下ろしていたのは、ほかの誰でもない。虚池空白その人であった。
「璃々は君に何を打ち明けた?」
「あまり大した追加情報はないんだけどね……」
僕は璃々が話したことをひとまず虚池に伝えた。虚池は興味深そうに何度か頷いた。
「ふむ。やはり野良句の作者はマサシという学生なのか」
「一応、謎を整理してみよう。
●野良句の作者は誰か?
●野良句は何を意味しているのか?
●マサシはいまどこにいるのか?
んん、思いつくのはこんなところかな。で、そのうち一つ目にはほぼ答えが与えられた。残るは二つか」
「もう一つ忘れてる。
●野良句はなぜ消えたのか。
ただ、いずれの謎も集約すれば、あの野良句に託されているともいえるけどね」
「消えたといえば、重要なことが一つ。あの碑の落書き、また現れたよ」
「また現れた?」
「一度消されたのだろうが、誰かがまた書いたのさ」
僕はスマホの画像を見せた。すると、虚池はすぐに、フォルダを遡って、保存してある〈ぽえむ様〉の撮った画像と見比べた。
「ああ、君も見たのか。これは〈また現れた〉んじゃないよ。ずっとそこにあったのさ。見てごらん」
二つの筆跡を見比べる。信じがたいことだが、その筆跡は、SNSに投稿されたそれと、寸分たがわず同じなのだった。
「ほんとだ……そんな馬鹿な……」
「蛍と同じだよ」
この男はいつだって僕にはよくわからない比喩を使うのだ。
「何だかよくわからないな」
「あの野良句は、この村で何が起こっているのか、これから何が起こるのかを知っているんだ。まあ俺から言えるのは一つ。もうこの村に長居は無用ってことだ」
「どういうことだ?」
虚池はニヤリと笑うと、ポケットから何かを取り出した。例の死んだ蛍だった。
「こいつに聞いてみるか?」
「な、何を言っているのだ……君は……」
「おい貴様」とついに虚池は虫に話しかけ始めた。「この村の秘密を話せよ。ふむふむ、そうか。ああ、やっぱりな、思ったとおりだ」
それから、虚池は体をがばりと起こした。
「光らぬ蛍と光らぬ俺の会話が滑稽か? なに、この村の実態ほどじゃないさ。俺について来るがいい。真夜中の冒険と行こうじゃないか」
「どこへ行く気なんだ? もう暗いのに……」
「行先は、こいつがすべて知っているさ」
虚池はまた蛍をポケットにしまい込み、玄関へと向かった。〈ほたるホテル〉は静まり返っている。伊藤はまだ戻っていない。璃々は女性たちに連れて行かれ、木村に至っては強制連行されている。
つまり、ここには僕らしかいないのだ。
仕方なく、僕は虚池の後を追いかけた。ホテルを出ると、彼は小川に沿って、さらに西向きに歩き始めた。村の門や畑、家畜小屋、集合住居のある地区からは離れ、徐々に草木の丈も高くなる。手入れが行き届いていない。その中にある、集会場へ向かうのとは別の、みすぼらしい橋を渡った。
「どこへ向かう気なんだ? まるでこの土地についてある程度の知見を得ているようじゃないか」
「そのとおり。俺はこの土地について知見を得ている。正確にいえば、〈ほたるとぴあ〉についてのね。ここはもともと〈ほたるとぴあ〉だった。ホームページはもうないが、ファンサイトでスクショが残っていて、当時の見取り図もあった。それによれば、この先には、〈ほたる美術館〉があるようだ」
「美術館だって?」
「そこに〈照神〉という名のアーティストの作品が展示されている」
「てるがみ……それってまさか……」
「村人が口にしていたね。あの怪物のフィギュアも〈照神〉が作ったものだろう。〈ほたるとぴあ〉について調べてみると、どうも蛍の存在は作品を展示するためのダシだった節がある」
「その美術館に、なぜいま向かわなくちゃならないんだい?」
「明日の夜では遅いからさ。ん……いや、もう今だって遅すぎるかもしれないな……見ろよ」
虚池の示したのは草むらの斜め前方だった。そこに、何かが横たわっていた。僕はスマホのライトを照らして近づき、腰を抜かした。
「ひぃ……」
悲鳴とも呼吸ともつかぬものが洩れた。前方に、若い男が倒れている。うつ伏せなのに、顔はこちらを向いたまま。息をしていないのは、明らかだった。
「けけけ……警察に……」
「無駄だな。急ごう。時間がない。ほら、そこだ。もう見えた」
「ここは……」
現れたのは、オフィス然とした近代的な建物だった。村全体の雰囲気とまったく異なるモダンな造り。
回転扉を通った先を、燭台の光が薄ぼんやりと照らしていた。
僕らの影ばかりが巨大に映し出された通路を、一列で進む。先頭の虚池の足取りに迷いはない。
不意に──視界が開け、陰影が深くなった。
そこは醜悪な先住者が息を潜める塒だった。異形のオブジェが所狭しと展示されている。あの黒甲虫の怪物の仲間のような有象無象が、其処彼処に点在している。タイトルがそれぞれついているが、タイトルを見ても何を意味しているのかよくわからない。作品の出来にもばらつきがあり、中には幼児の工作クラスのものもある。共通しているのは、どれもが昆虫を擬人化して解剖したようなグロテスクな構図だという点か。しかし、そこからテーマ性を摘出することはついぞ叶わなかった。
「駄作集まる地獄を歩く」
虚池は俳句か感想かわからぬことを言って先へ進む。
「地獄、とは少し失礼ではないかね? 楽園と言いなさい」
黒甲虫をバラバラにして再構成したような作品の背後から、声が聞こえた。
作品がくるりと回転する。どうやら、その不気味なオブジェは椅子になっていたらしい。そこに──村長が腰かけていた。
「君たちにはホテルが用意されているはずだが?」
村長は煙草をくゆらせていた。
「この村の代表さんにお見せしたいものがありましてね」
虚池はポケットから、例の蛍の死骸を取り出して投げた。
「これがどうかしたかね?」
「さっき木村に殺された蛍です。あなた方はこれを現場に放置した。生き物との共生を謳っているのに」
「大地に還すためだ」
「いいえ。ちがうんですよ」
虚池はニヤリと笑った。その笑みは悪魔よりも悪魔的であった。
「この蛍には何のありがたみもない。むしろ恨みならおありでしょう。蛍は蛍でも、オバボタル。光らない蛍ですから」
ほの暗い明りのなかで、村長の顔色がわずかに変わった気がした。
9
「辰野はもともとゲンジボタルが多く棲息する土地でした。しかし、観光化するには少なく、他県からゲンジボタルを移入させた。同じことを、恐らく〈ほたるとぴあ〉のオーナーもした。ところが、業者に騙されて、ゲンジボタルではなくオバボタルを大量繁殖させ、先住民たるゲンジボタルが駆逐されてオバボタルの土地となった。それが〈ほたるとぴあ〉倒産の理由でしょうね。その跡地に作られたこの村にとっても、光らないホタルの命など本当はどうでもいい。だが──罰を与える口実には使える」
「君はおかしなことばかり言うね。そんなことをして、私に何の得があると言うのだね?」
虚池はそれには答えずに、言葉をつづけた。
「〈ほたるとぴあ〉のホームページは、ドメインの有効期限が切れていました。でもテーマパークマニアの人のホームページでは、当時の状況、倒産理由、その経営者の情報が出てくる。〈ほたるとぴあ〉社長、星川光の顔写真も」
虚池はスマホを取り出して見せた。そこには、星川光の名とともに、村長の顔写真があった。
「村長が……前オーナー……?」
「そのホームページによれば、テーマパーク倒産後、廃墟化した敷地を一目見ようとする物好きは跡を絶たなかった、とある。中には石を投げこんだり、敷地に入り込んで悪戯をする者もいたとか。廃墟は死して同時に生きてもいる不思議な存在です。その崩壊の躍動に自らも加わりたいという好奇心は、わからなくはない」
「私にはわからないね」と村長──星川は吐き捨てるように言った。
「そう、あなたにはわからない。それが──村を作った動機ですね? つまり、野次馬への報復」
星川は、黙っている。図星だということなのか。
「つまらない日常を送る奴らが、廃墟化したテーマパークで悪行を働く。なら、いっそ哀れな闖入者を労働力に替えればいい。それが〈霧蛍村〉の出発点だよ。幸い、従業員の九割を大量解雇したからいくらか預金はあった。自治村の基盤を立ち上げるくらいのね」
「どうやって闖入者を労働力にしたのです?」
「まず奴らのうち一人を生贄にする。輝けない奴に自分の惨めさを自覚させ、その光景を仲間に見せる。そうすることで改心させ、村を一つにまとめる新たな光になってもらう」
星川は表情のない目で笑った。
「テレビの罰ゲーム程度の粛清さ。〈光の神〉の衣装を纏った私が、彼らの尻にオイルを塗る。そして火をつけては消しを繰り返す。かわいい拷問だ」
「なるほど。ちなみに〈捨てた蛍光性の過去〉、この言葉をご存じですか?」
「……何の遊びかよくわからないな」
「やはり。ありがとうございます」
いまの反応ではっきりした。星川はあの野良句の作者ではない。伊藤が可能性として口にした村長の宣託なんかではないのだ。
「この言葉は、川辺にある碑に落書きされていました」
「そんな勝手な真似をする者はこの村にはいない」
「でも実際に落書きはあったんですよ。恐らく蛍光性の特殊なペンで書かれているので、昼は見えない。そして、夜には牧場側から川辺を見る者が、この村にはいなくなる。住居は川を渡った北側に集中しており、南側にはゲスト用のホテルしかないからです」
蛍光性のペン──。その言葉で、謎が氷解する。到着してすぐに碑を見たとき、野良句が見えなかったのは昼間だったからなのだ。集会の帰りは夜だから、その字が浮かび上がっていた。
木村が昨夜はあった、と言ったのもそのため。
そう、野良句を消した者など初めからいないのだ。
虚池はスマホの画面で〈ぽえむ様〉の投稿写真を見せた。
「この句を書いた人間に、心当たりはありますか?」
「村人はそんな愚かなことはしない。よそ者の仕業だろう。そういえば、二日前にここを訪れた学生がいたね。すぐに追い返したが」
璃々たちの言っていたとおり、マサシはたしかにこの村に来ていたようだ。
「なぜ追い返したのですか?」
「〈照神〉を解放しろ、とかわけのわからないことを騒いでいたからだ。人間は愚かな生き物だよ。不自由に囚われて生きているのは自分たちだと気づきもしないのだからね」
虚池が冷笑する。
「自由律俳句の世界も、何もかもから自由なわけじゃないです。たとえば、五・七・五よりもっと根源的な日本語特有の音律から自由になることはない。まあ、俳句の話はさておき──それでも、やはり俺にはここが地上の楽園には少しも見えませんがね」
「愚か者には見えないのさ。私は生贄の光によって、村人の心を一つにしてきた。その光が、村人のエネルギーとなり、彼らを蛍にする。この村にいる実際の蛍は君が指摘したとおりオバボタルだから光らない。だが、村人は私がその虫どもの尻に蛍光ペンを塗ったのを、蛍の光だと喜んでいる。照神さまのもたらす光だ、とね」
集会場で、最後の退場の際に空に舞う蛍。あれは蛍光ペンで尻を光らされた蛍か。考えてみれば、蛍の光ならば点滅せねばならない。だが、あのときのそれは、点滅ではなく点灯だった。
あるいは──その蛍光ペンは、碑の落書きに使われたのと同じかもしれない。
口の中がからからに乾いて、また水筒をひと口啜った。
だんだん頭痛がしてきた。脳天の奥から蛍の大群がやってきて、無数の光が部屋中に散る。やめろ集中できない。その光をよけながら二足歩行の甲虫がうねり歩く。
これは幻覚か。そうに違いない。だが、幻覚だとしたら、なぜそんなものを自分が見なくてはならないのか。
待て。やめてくれ。蛍の怪物が、僕に向かって手を伸ばそうとする。まるで、僕を飲み込んで存在を大きくしようと企むみたいに。
いまの状況に集中しなくては。すべて幻想だ。こんなものが現実であるわけがないのだから。目を覚ませ。これはただのオブジェであって……。
「学生を追い返した、と言いましたね。殺した、の言い間違えでは?」
「莫迦な……そんな手間の増えることはしない」
「先ほど、ここへ来る途中の草むらに若い男性の遺体があった。恐らくはマサシという学生のものです」
「……何の冗談かね? これ以上私を困らせる気なら……」
「いいえ、死体はあったのですよ」
「君はよほど私の楽園に泥を塗りたいらしい。だが、そんな場合かな? 君の相方を見たまえ」
虚池が振り返って何を目撃したかは、誰よりも僕が理解している。そう、それはすでにぐでんと横たわり朦朧とした意識下にある編集者、古戸馬に他ならないのだから。
(つづく)
プロフィール
-

森晶麿 (もり・あきまろ)
1979年生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。日本大学大学院芸術学研究科博士前期課程修了。2011年、『黒猫の遊歩あるいは美学講義』で第1回アガサ・クリスティ―賞受賞。〈黒猫シリーズ〉の他『探偵は絵にならない』『切断島の殺戮理論』『名探偵の顔が良い 天草茅夢のジャンクな事件簿』『あの日、タワマンで君と』等著書多数。
関連書籍
新着コンテンツ
-
連載2026年03月13日
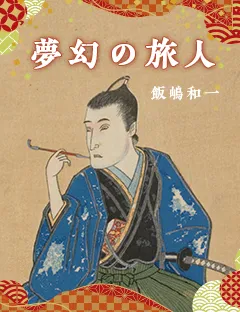 連載2026年03月13日
連載2026年03月13日夢幻の旅人
飯嶋和一
平賀源内の生涯を描く歴史大長篇。
-
インタビュー・対談2026年03月12日
 インタビュー・対談2026年03月12日
インタビュー・対談2026年03月12日トークイベント 永井玲衣×後藤正文「いまことばとは」
永井玲衣さんと後藤正文さんが言葉を通して今を考えるトークイベント「いまことばとは」の様子を再構成してお届けします。
-
お知らせ2026年03月06日
 お知らせ2026年03月06日
お知らせ2026年03月06日すばる4月号、好評発売中です!
特集のテーマは「道をゆく」。椎名誠さん×高田晃太郎さんの対談、駒田隼也さんの紀行ほか、小説、エッセイなど一挙16本立てです。
-
インタビュー・対談2026年03月06日
 インタビュー・対談2026年03月06日
インタビュー・対談2026年03月06日椎名 誠×高田晃太郎「自由に人は生きられる」
最新刊は逃避行がテーマの椎名誠さん。ロバを相棒に旅をしている高田晃太郎さんをお相手に、おふたりのこれまでの旅を振り返っていただきました。
-
新刊案内2026年03月05日
 新刊案内2026年03月05日
新刊案内2026年03月05日たったひとつの雪のかけら
ウン・ヒギョン 訳/オ・ヨンア
韓国を代表する作家のひとりウン・ヒギョンが、生きる孤独と哀しみ、そして人と人の一瞬の邂逅を描く、6篇の珠玉の短編集。
-
新刊案内2026年03月05日
 新刊案内2026年03月05日
新刊案内2026年03月05日劇場という名の星座
小川洋子
劇場を愛し、劇場を作り上げてきた人々の密やかな祈りがきらめく豊饒な短編集。




