
時間がないけど読書がしたい!
そんなあなたのための、スキマ時間で楽しめるネット上の小さな本屋さん。
スキマブックス、開店します。
「昨日は蛍」 其ノ肆
森晶麿
【30分で読める】【小説】
俳人・虚池空白と編集者の古戸馬が紛れ込んだ、ある怪しい村の秘密――『虚池空白の自由律な事件簿』初のスピンオフ!
2025年10月22日
10
夢を見ていた。何ともとりとめのない夢だ。僕は甲虫の怪物に怯えながら、闇深い森へと逃げ込む。ところが、その森には異形の神々がいて僕を通せんぼする。まるでクトゥルー神話だ。森が燃え始める。熱い。早くここを抜けなければ。そう思うのに、西へ向かうも東へ向かうも、異形の神々が邪魔をする。そして漂いだす化学繊維の匂い。
ん? そこで初めて妙に思った。森に化学繊維のあろうはずがない。そして──どうやら閉じているらしい我が目を無理やり開けた。
最初に目が捉えたのは、先ほど目にしたグロテスクなオブジェだった。だが、景観よりも刺激臭が気になって、その匂いの元を振り返った。
「ああああ!」
燃えているのは僕の尻だった。ズボンに火がついているのだ。どうやら夢を見ていると錯覚している間も、身体は動いていたようだ。
「消せ! 消してくれぇええ!」
「無理だ。ここに水はない。風力に頼れ。走れ!」と虚池。
無茶を言う。こいつは僕を殺す気なのか。だが、言い争っている間に焼け死んでしまうのでは困る。僕は無我夢中で駆け回った。
「落ち着くのだ! 火が作品に移る! やめたまえ!」
星川光が叫ぶ。だが、そんな無理を聞いている場合ではない。こちらは焼け死ぬかどうかの瀬戸際だ。ちょっとでも走る速度を緩めれば、火は身体を蝕む。
熱い。熱いが、走らなければ。僕は壁に尻を押し付けた。
ああ、これでいい。これで尻はどうにか……。
いや待て。よく見れば尻の火は落ち着いたものの壁が燃えている。いま押し付けた箇所には、〈照神〉の描いた絵画があったようだ。
「作品がぁあああ……!」
星川が頭を抱えて壁に近寄り、なんとか火を消さんとしている。そのすきに僕の腕を虚池が引っ張って立ち上がらせた。
「行くぞ。一刻の猶予もならん」
もつれる足で走り出す。けれど、途中で気が付いた。
「璃々さんを助けないと」
「放っておけ。逃げたければ自分で逃げるさ」
「そうはいかない。だって彼女は……」
「彼女は、何だ?」
腕にはまだ彼女に抱きつかれた時の感触が残っていた。僕は惚れっぽいのだ。だが、水筒に幻覚剤が仕込まれていたのは璃々だって同じなはず。ならば、あの抱擁さえ、幻覚の仕業か。げんにその後、木村の浮気を知らされた彼女の狂乱ぶりは明らかに常軌を逸していた。おのれ幻覚め。
川沿いに走っていくと、次々と村人たちが蠟人形を思わせる瞳孔の開いた目で迫りくる。星川から連絡がいったのだろう。すでに我々はお尋ね者になったようだ。あたかも低予算恐怖映画の死霊のごとく襲い掛かってくる彼らを、虚池は片っ端から蹴り飛ばす。そういえばこの男、高校時代は何かの武術を習っていたのだったか。
斧をもった男の急所を蹴り、斧を奪ってぶんぶと振り回す。村人は誰も近づけない。僕だって近づけない。下手をすれば、身体が真っ二つにされかねない。尻が痛い。とにかく尻が焼けるように痛い。いや実際焼けたのである。
どうにか死霊の群れから抜けて這う這うの体で〈ほたるホテル〉の前まで戻った時、その入口で我が目を疑った。我々を連れてきたタクシーの運転手の武田さんがいるではないか。タクシー運転手の帽子を被っており、業務の合間にここを訪れたものと思われた。
「武田さん! タクシー出してください、お願いします」
だが、助けを求める相手を間違えた。彼の手に鎌が握られていたのだ。
武田さんが、襲い掛かってくる。
彼がこの村に好意的なことばかり並べたてたのも道理。彼もまたこの村に魂を奪われた者の一人だったのだから。
武田さんの役割は、差し詰めこの村に新たな生贄を齎す導き役か。彼のもった鎌を、虚池が斧でぶんと一振り破壊した。しかし、武田さんはめげずに虚池の腰に絡みつく。虚池は容赦なく膝蹴りを食らわせ、老体を仕留めた。
それから、例の獣道を、今度は虚池が僕を半ば担ぎ上げるような感じで移動した。それができるなら、行きもそうしてほしかった。
人類を嘲笑うかのごとく鬱蒼と生い茂った獣道の暗闇のなか、門に寄りかかってへたり込む女性の姿を認めた。
璃々だった。僕は慌てて虚池の背中から下り、彼女に駆け寄った。
「璃々さん、一緒にいこう。この村を出るんだ」
僕の声が聞こえているのか、その目はうつろなままだった。
そして──その服は何によるものか、月明りの下に咲くアマリリスのごとく深紅に染まっていた。
「終わりました……何もかも、きれいさっぱり」
璃々が手にしている斧を見れば、何が起こったのかは明らかだ。彼女はたぶん、過去を清算したのだ。自らの意志か、村の女たちに唆されてかはわからないが。
けれど、いまの一点の曇りもない晴れやかな顔つきを見ているうちに、自分の意志かそうでないかなんて些細こなことのように思えてきた。
何であれ、璃々はようやく過去から自由になれたのだろう。
「どうぞ逃げてください。ここは私が彼らを食い止めます」
「え……? 璃々さん? 僕たちと一緒に……」
思いがけぬ言葉に、僕は大いに戸惑った。なぜこの状況で、璃々は自分を人身御供なにしようなどと考えるのか。
「いいから早く。もう私は浮世には戻れませんから」
その言葉に、なおも食い下がろうとする僕を押しのけて、虚池が言った。
「恩に着ますよ、あなたのことは忘れるまで覚えています」
虚池は僕の腕を引いて走り出した。あまりにその力が強かったので、走るつもりもなく、走らされてしまった。
引きずられながら、璃々の発する〈浮世〉は特別美しい響きだな、などと考え、そんな自分を薄情だと反省した。
璃々が斧をもって果敢に村人たちに向かっていく叫び声を後ろ耳で聞きながら、僕らは門の外に出た。
そうして、塀沿いに停められているタクシーに乗りこんだ。
キーはささったままだった。
運転免許のない虚池に替わって、僕が車を発進させた。
追ってくる村人たちを振り切って、霧深い夜道を進む。
その時──目の前にあの黒甲虫の怪物が立っていた。キーホルダーやドアノッカーのような小さいものではなく、人間と同じ大きさだった。怪物はじっと仁王立ちしたまま、タクシーを拾いでもするかのように手を挙げた。
幻想に吞まれたか。近づいて運転席の窓を五センチだけ開けた。
「もう、行ってしまうのですね。フィナーレを見届けもせずに」
その声を聞いて、一気に強張った肩から力が抜ける。伊藤の声だ。
「フィナーレ……?」
助手席から、虚池が顔を出して、伊藤に尋ねた。
「あなたが──〈照神〉ですね?」
僕は、また眩暈を覚えた。
「え……て、てるがみ……? 何を君は……」
伊藤が、〈照神〉だというのか?
「またの名を星川ほたるさん。村長、星川光の実子だ」
伊藤が、不気味なコスチュームの中で、不敵に笑った。
「その名はもう捨てましたよ。いまは〈照神〉。この世界の神です」
そう宣言する口調には、静かな狂気の気配が感じられた。
「よく僕の正体に気づきましたねぇ」
「オバボタルをよける足取りがあまりに慣れていた。とてもゲストには思えませんでしたよ」
それは失敗したなぁ、と言いながら伊藤──もとい〈照神〉は爽やかに頭を搔いた。
「あなたたちをこの村に案内なんかしなきゃよかったですよ」
「でもあなたはそれを選んだ。恐らく、我々がすでにこの土地に向かっていたがために。そうですね?」
観念するように〈照神〉は首をすくめた。
「どういうことかわからないな……」
僕はまだ混乱していて状況がよく吞み込めなかった。
「僕は〈ぽえむ様〉というアカウントに連絡をとった。あのアカウントがすでに仕組まれたものだったってこと?」
「ちがう。あれはマサシさんのアカウントなんだよ。〈ぽえむ〉は詩のこと。〈詩さま〉を反対から読めば、〈マサシ〉となる」
「あ……!」
あまりに意表を突かれて僕は言葉に詰まってしまった。〈ぽえむ様〉のアカウントがマサシのものだった?
「しかし古戸馬くんがコンタクトをとった時、すでにそのアカウントはマサシさんの手を離れ、〈照神〉が操作していた」
「そうか……最初から乗っ取られていたのか……でもなぜ、彼は〈ぽえむ様〉の〈中の人〉を演じなければならなかったの?」
虚池が、静かにそれに答えた。
「そうしなければ〈中の人〉の異変に早々に気づかれるからさ。だから、我々二人に対してだけは〈ゲスト〉を演じねばならなかった」
「我々二人にだけ?」
「僕と古戸馬くんにとって、彼は同じゲストだ。だが、木村さんや璃々さんからは村人に見えていた。彼は我々に黒の甚平を着る理由を〈滞在三日目になると認められる〉と、あたかもゲストの特別待遇を装った。そうすることで我々からはゲスト側に、木村さんたちからは村人側に見える」
「なぜ、木村さんたちには村人に見えている必要があったんだ?」
「木村さんたちは、彼が〈ぽえむ様〉でないことを知っているからね。何しろ、彼らは〈中の人〉のご友人だったわけだから」
「そうか……そういえば木村さんたちと僕らがいる場には、うまい具合に伊藤さんは姿を消していた」
「まいったなぁ。よくお気づきになられましたね」
のんきな様子で〈照神〉は頭を搔いた。
虚池は〈照神〉に尋ねた。
「それではお聞きしましょう。なぜ、マサシさんを殺したのです?」
11
「人聞きが悪いですよぉ……」
そう笑って〈照神〉はかぶりを振った。
「村から追い出された後、彼は車に轢かれて死んだんです。だからせめて肥料になれば、と敷地内に放置しただけですよぉ」
交通事故──タクシー運転手たちの血相が変わったのを思い出す。あの辺りは事故が……と言葉を濁していた。
「彼……マサシくんは、ただの廃墟マニアではないんですよぉ。だから、村の住人に取り込むわけにはいかず追い払うことにしました。だけど最後までジタバタして、挙句死んでしまいましたねぇ。がっかりです」
「事故死で済ませられるとは思いませんね。あの野良句が、事件性を物語っています。木村さんたちがあれをマサシさんのものと考えたのは、筆跡以外に、もう一つ理由があった。それはあの言葉自体が発するSOSです」
「SOS……? あの落書きがなぜそうなるのです? さすがに邪推が過ぎるんじゃないですか?」
〈照神〉は乾いた笑い声を発した。
だが、その笑いを動揺に変えるほど、虚池の目は冷徹だった。
「邪推じゃないですよ。むしろ、聖推と言ってほしいところです。あれはモールス信号になっていた。〈捨てた〉は音にすれば単発です。つまり、〈・・・〉、対して間にある〈蛍光性〉はすべて伸ばす音ですから〈―――〉となります。そして、ふたたび〈の過去〉は〈・・・〉。〈・・・―――・・・〉、これは、モールス信号の世界では助けを求めるSOSの信号です」
〈照神〉が押し黙った。言葉を忘れ本当に虫になったみたいに。
「たとえモールス信号だとわからなかったとしても、メッセージの意味を確定することは可能です。状況的にマサシさんが自分の意志で行方を晦ましたとは考えにくい。であれば、野良句は自分に迫る危機を第三者に伝える目的があった、と考えられます。場所を特定できるヒントになるような背景でそれを写真に撮り、SNSに上げれば、仲間以外の目にも入る。また、自由律俳句を装っている点や、特殊な蛍光ペンを用いたことで、身近な者、つまり村人たちに気付かれては困るメッセージなのだということもわかる。ここまでわかれば、もう暗号など解かなくても、その内容はSOSしかあり得ないですよ」
「あの学生も小賢しい真似をしたものですねぇ」
そう吐き捨てる〈照神〉は、どこかの邪神そのものに見えた。
さっきの草むらで月を見上げていた青年の顔が浮かぶ。あの男が、僕が連絡をとろうとしていた〈ぽえむ様〉だったのか。
「あなたは、村のシンボルともいうべきフィギュアの作者として神に近い存在だ。村長はダミーで、実権はあなたが掌握している。だが、それでも解せないのです。これまでは粛清を使って野次馬を労働力に替えていただけのあなたが、なぜ殺人に及んだのか」
くつくつくつ
くつくつくつ
〈照神〉に、異変が生じた。
思わずハンドルを握る手に力が入った。すぐにでもアクセルを踏み込みたかった。だが、まだ虚池がそれを手で制している。
やがて、〈照神〉はいびつな笑い声をやめた。
「マサシくんはね、僕を哀れんだのです。彼はその昔、〈ほたるとぴあ〉時代にここを訪れたことがあった。その時に管理者の息子であった僕と遊んだことを鮮明に記憶していました。そして、莫迦げたことに、この村が僕を束縛しているのだ、と主張したんです。何もわかっていない! 何も何も何も何も何も何も何も何も! 僕が、長年かけてようやく手にした地上の楽園だっていうのに!」
マサシは大学の仲間との廃墟探訪にかこつけて、かつて旅行で訪れた〈ほたるとぴあ〉を訪れた。そして、そこから出ようとしない星川ほたるを救い出そうとしていたのか──。
虚池は、〈照神〉の狂気に抗うように、冷静な口調で言った。
「〈捨てた蛍光性の過去〉──この句はSOSの意味のほかに、もう一つあなたへのメッセージもあったと思いますよ。すなわち、自分と一緒に遊んだ楽しかった時間を思い出してほしい、と。恐らく、それを書くのに使った特殊な蛍光ペンは〈ほたるとぴあ〉の土産ものコーナーで買ったものだったはずです」
それは蛍の点滅のように、ある意味では神々しく、ある意味では儚い幻の光。友情の灯を、マサシは残したということなのか。
「どうでもいいですねぇ。それで、僕の罪を立証できますか? モールス信号なんて、裁判官の前で言いだしても戸惑われるだけですよ。木村さんと璃々さんも、こうなっちゃ証言台には立てないでしょうしねぇ。もともと始末もやむをえないなと思っていましたが──璃々さんが勝手に手間を省いてくれたようですから」
また〈照神〉はくつくつと笑った。
野良句が秘めた友情の光でさえ、この邪神には効果がないのだ。
「あなた方を殺そうと思っていましたが、もう必要なくなりました」
「つまり、そういうフィナーレということですか?」
虚池はじっと〈照神〉を見つめた。〈そういう〉が、どういうものか、まだ分からなかった。ただぼんやり最悪の事態が予感された。
「どうぞ、行ってください。警察に通報しても構いませんよ」
くつくつくつ
くつくつくつ
黒甲虫の怪物は、いびつな笑い声を残して走り去っていった。
怪物の後ろ姿が闇に吞まれると、虚池がため息をついた。
「言ったろ、野ざらしの言葉は狂暴なのさ。企画を続けるなら覚悟することだね」
「……いまそんなこと言わなくても」
「いま言わないと、効果がないだろうが」
だとしても、途中で放りだすわけにはいかない。この企画は会議を通過してしまった。僕は編集者で、企画のとおった作品は世に出す使命があるのだから。
「見ろ……後ろ。霧蛍村の南側が赤く光っている。蛍の尻みたいだ」
見れば、たしかにめらめらと闇夜に紅一点の輝きが放たれている。
その光が、〈照神〉の決意の表れであることは、すぐにわかった。邪神は、自らの創造した地上の楽園に、終止符を打ったのだ。
ゆっくりブレーキペダルから足を離すと、車が動き出した。心の中で、さよならを唱えた。何よりまず、野ざらしの言葉に。
「拾い物の今日尻で一服」
「……俳句?」
「どうかな。尻からまだ煙が出ているぞ」
見れば、たしかに煙が尻から漂っていた。それが、あの騒動が夢幻でないことを示していた。
「拾い物の今日……たしかに、ここにいるのが夢みたいだ。まったく恐ろしい蛍だったよ」
すると虚池は苦笑した。
「蛍なもんか。ありゃ蝮だ。闇夜では蝮の目を蛍の光と間違えやすいから、命取りになるんだよ」
(了)
プロフィール
-

森晶麿 (もり・あきまろ)
1979年生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。日本大学大学院芸術学研究科博士前期課程修了。2011年、『黒猫の遊歩あるいは美学講義』で第1回アガサ・クリスティ―賞受賞。〈黒猫シリーズ〉の他『探偵は絵にならない』『切断島の殺戮理論』『名探偵の顔が良い 天草茅夢のジャンクな事件簿』『あの日、タワマンで君と』等著書多数。
関連書籍
新着コンテンツ
-
連載2026年03月13日
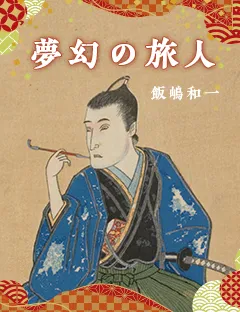 連載2026年03月13日
連載2026年03月13日夢幻の旅人
飯嶋和一
平賀源内の生涯を描く歴史大長篇。
-
インタビュー・対談2026年03月12日
 インタビュー・対談2026年03月12日
インタビュー・対談2026年03月12日トークイベント 永井玲衣×後藤正文「いまことばとは」
永井玲衣さんと後藤正文さんが言葉を通して今を考えるトークイベント「いまことばとは」の様子を再構成してお届けします。
-
お知らせ2026年03月06日
 お知らせ2026年03月06日
お知らせ2026年03月06日すばる4月号、好評発売中です!
特集のテーマは「道をゆく」。椎名誠さん×高田晃太郎さんの対談、駒田隼也さんの紀行ほか、小説、エッセイなど一挙16本立てです。
-
インタビュー・対談2026年03月06日
 インタビュー・対談2026年03月06日
インタビュー・対談2026年03月06日椎名 誠×高田晃太郎「自由に人は生きられる」
最新刊は逃避行がテーマの椎名誠さん。ロバを相棒に旅をしている高田晃太郎さんをお相手に、おふたりのこれまでの旅を振り返っていただきました。
-
新刊案内2026年03月05日
 新刊案内2026年03月05日
新刊案内2026年03月05日たったひとつの雪のかけら
ウン・ヒギョン 訳/オ・ヨンア
韓国を代表する作家のひとりウン・ヒギョンが、生きる孤独と哀しみ、そして人と人の一瞬の邂逅を描く、6篇の珠玉の短編集。
-
新刊案内2026年03月05日
 新刊案内2026年03月05日
新刊案内2026年03月05日劇場という名の星座
小川洋子
劇場を愛し、劇場を作り上げてきた人々の密やかな祈りがきらめく豊饒な短編集。




