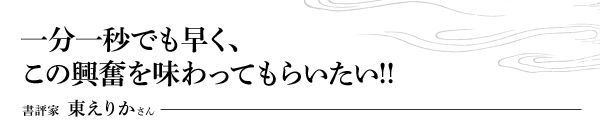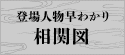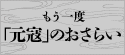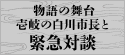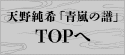何だこれは! 何だこれは! 何だこれは!
読み終わって叫んでいた。
天野純希『青嵐の譜』を手に取ったのは、わずか5時間前に過ぎない。
この間、呼吸をするのも忘れて読みふけってしまうとは思いもしなかった……。
ファンタジー風の装丁でタイトルがアルファベット。裏には可愛い女の子の絵。普段、ノンフィクションの書評を主としている私ならスルーしてしまう本だ。しかし帯の小さな文字が目に飛び込んできた。
「蒙古軍」?「元寇」?
確か著者はちょっと変わった時代小説『桃山ビート・トライブ』で小説すばる新人賞を取った人ではなかったか。ファンタジー小説にしても文永・弘安の役を題材にするとは豪胆な新人だと興味が湧いて読み始めた。ところが違った。まさに正統派、硬骨の時代小説だったのだ。
中世、特に鎌倉中期から南北朝にかけての時代は日本という国にとって初めて「侵略」を受けた時代でもある。小学校の社会科でも蒙古襲来・元寇は習うし、神風によって日本は守られた、と幼心に刻み付けられている。実際のところ、ユーラシア大陸を席巻したモンゴル帝国がこの島国まで傘下に入れようと攻め入ったところが、思わぬ反撃と台風によって阻まれた、というのは後に知ったことである。
舞台は壱岐。主なる登場人物は高麗の高官の娘で笛の名手「麗花」、博多唐人街の遊女の息子で壱岐の武士の養子「宋三郎」、博多の大商人・謝国明の番頭喜平次の息子で絵の才がある「二郎」。兄弟のように育った3人は、天災と文永の役による壱岐の壊滅で引き裂かれ、思いもよらぬ過酷な運命を辿ることになる。
私は北方謙三氏の秘書をしていたとき、中世の九州について調べたことがある。だから多少は詳しいと思うのだが、博多の様子から地方武士の生活、物流、地理や自然が緻密に描かれていることに驚嘆した。主人公3人のほかはほぼ全て実際にいた人物で、歴史的事実は違えていない。にもかかわらず物語はダイナミックにうねり、読者は先を急がずにはいられない。今でも絶大な人気を誇る歴史家・網野善彦の唱えた民衆の姿が生き生きと描き出されていく。無辜(むこ)の民を犠牲にする、無策ともいえる幕府と朝廷の愚かしさに腹を立て、命を落とす者に涙する。まさにこの本を読んでいた5時間は、道々の輩とともに旅をし、戦に投げ出され、生死の境をさまよった。
わずか30歳、新人賞受賞後初の作品が800枚にも及ぶ書き下ろしで、スペクタクル溢れる作品をモノにするとはなんとすごいことだろう。一分一秒でも早く、多くの人たちにこの興奮を味わってもらいたいと強く願う。