有吉玉青×阿川佐和子 『ルコネサンス』刊行記念対談 「小説家を親に持つ二人――「書く」ことで見えてきたものとは?」

『小説すばる』で連載されていた作品『ルコネサンス』を4月に上梓した有吉玉青さん。
母・有吉佐和子の離婚によって絶縁状態となっていた父と、
25年ぶりに再会した自身の経験をもとに書き上げた父と娘の切ない物語だ。
一方、エッセイ『強父論』などで、たびたび父・阿川弘之について語ってきた阿川佐和子さん。
ユーモラスな筆致で綴られる父の暴君ぶりには、永遠にすれ違う父と娘の苛立ちと愛情がにじむ。
ともにスター作家を両親に持つ二人が語る父と娘とは─。
撮影/天日恵美子 有吉さんヘア/千葉智子(ロッセット) 聞き手・構成/佐藤裕美
有吉 阿川さん、本当にご無沙汰しています。以前、お会いしたのは、もう20年前になりますね。
阿川 玉青ちゃん、本当にお久し振りですね。そうそう、雑誌の対談でお会いしたんですよね。親同士は交流があったけれど、二人でゆっくり話したのはあのときが初めてで。それで今日は玉青ちゃんに会うというので、これを持ってきたの。先日、実家の荷物を整理していたら出てきて懐かしくて。(袋からガラスケースに入った手まりを出す)
有吉 これはもしかして母が?
阿川 そうです。お母さまは、私の「佐和子」という名前は、ご自身の有吉佐和子からとったと思っていらしたんですね。それで私が小学生の頃、「深いつながりだから」とおっしゃって、この美しい刺繍が施された手まりを直々にくださったんです。
有吉 ずっと大事に持っていてくださったんですね。ありがとうございます。母も喜んでいると思います。母は和歌山県の出身なので、地元の伝統工芸品の「紀州てまり」を差し上げたんですね。でも、佐和子というお名前は、じつは母からとったものではないと、その後、うかがって。
阿川 そうなんですよ。よそ様の家の墓石からとってつけた名前でして(笑)。
有吉 よそ様の家の……。
阿川 はい。そもそも兄が生まれたとき、父が女の子の名前しか考えてなくて、それでたまたま通りかかった青山の墓地でみかけた墓石から勝手に名前をいただいて、長男に名付けたんですね(笑)。それで私が生まれたときも、同じおうちの墓石から名前をいただいて「佐和子」とつけたという。ひどいでしょう?
有吉 うかがっていると、お父さまらしいような気もします。
阿川 玉青ちゃんは、ハワイ時代にうちの父とは会っているんですよね。
有吉 はい。私が小学校1年の頃、母がハワイ大学に客員教授として招かれて、私も7か月ほど向こうで過ごしました。そのときにハワイに旅行でいらした阿川先生とご一緒したことがありました。先生が運転する車にも母と何度か乗せていただいて。
阿川 そのときのことは、父から聞いております。あるとき、二人を車に乗せて、父が運転していたら、お母さまが急に「お兄ちゃん! そこ曲がって!」って指示なさったらしい。
有吉 母は阿川先生のこと、「お兄ちゃん」って呼んでいたんですよね。
阿川 それで父がお母さまに「むちゃ言うんじゃないよ」とか言ったら、玉青ちゃんが何か言ったそうで、父が「ガキは黙ってろ!」って叱りつけたとか(笑)。ほんと、すみませんね。
有吉 いえいえ、私も生意気な子どもでしたから、何か失礼なことを言ったんだと思います。あれから40年以上もたって、阿川先生も母も亡くなってしまいましたが、今でも楽しい思い出として心に残っています。
いつか書いてみたかった自分と父との物語
阿川 今回の対談は、玉青ちゃんの新刊小説『ルコネサンス』について、お話しするつもりで参りました。
有吉 阿川さんには素晴らしい帯文を書いていただいて、本当にありがとうございました。
阿川 「自伝的フィクション」とあるように玉青ちゃんがお父さまのことを題材に書いた小説です。ご両親が離婚されていたのは知っていたけれど、お父さまと玉青ちゃんの関係については、全然知らなかったので、拝読して驚きの連続でした。そもそもどうして今これを書こうと思ったの?
有吉 父のことはずっと書きたいと思っていました。それで『小説すばる』で連載のお話をいただいたときに、この機にと思い立ちまして。私が生まれてすぐに両親が離婚して、父とはそれきり25年くらい会っていなかったんです。でも、母亡きあと、私の結婚を機に再会して、それから父が亡くなるまでの約8年間は、父娘として過ごす時間がありました。この小説は、その経験を題材にしています。
阿川 父娘の関係が、我が家とは比べものにならないほどミステリアスで、「お父さまとの間にこんなことがあったんだ!」「こんなにいろいろなことを抱えていたんだ!」って、主人公の珠絵ちゃんと玉青ちゃんを思い切り重ねながら読んでしまいました。25年ぶりに再会した珠絵ちゃんと、父親の「ジンさん」が紆余曲折を経て、本当の父娘になっていく姿は感動的でした。
有吉 ありがとうございます。でも、あくまでフィクションなので、この小説と実際に起きたことは、かなり異なっているんです。珠絵のキャラクターも私とは全然違っていて、似ているのは、いつも食べることばかり考えているところくらいで。
阿川 でも、珠絵ちゃんが小説家を目指していたり、名前も玉青と似ているから、事実みたいに読めてしまうのよね。お父さんも小説では「陣内さん」で、実際のお父さまは、「神さん」。神さんは、有名なプロモーターだったんですよね。
有吉 当時、国交のなかった旧ソ連からドン・コザック合唱団やボリショイ・サーカスを招聘した、今で言うところの国際プロモーターです。再会したときは、居酒屋チェーン店(北の家族)を経営していました。父と初めて会ったとき、何て呼んでいいのかわからなくて、「神さん」って呼んでたんです。それを小説では「陣内さん」の愛称で「ジンさん」としました。
阿川 小説では父と娘の再会のシーンは、とてもドラマチックに描かれていましたね。ジンさんがまた素敵なのよ。スーツが似合って、いい匂いがするようなセクシーな男で、うちの父とは大違い(笑)。「ドラマにするなら誰が演じるのがいいかしら!?」なんて考えながら読んじゃいました。
数十年ぶりに父と再会。心中は複雑だった……
阿川 玉青ちゃんは、生まれてすぐお父さまとは離れ離れになってしまったわけだけど、その後、一度も会おうとは思わなかったんですか。
有吉 会おうと思ったことはまったくなかったし、チャンスもありませんでした。
阿川 父親不在という喪失感みたいなものはなかったんですか。
有吉 母と祖母と3人暮らしでしたけれど、父親がいなくて寂しいと感じたことは全然なかったんですよね。母や祖母が父の話をすることはありませんでしたし、子どもながら、どこかで「会ってはいけない」という気持ちがありました。だから本当に父のことはノータッチでいた。でも、不思議なことに、情報がいろいろなところから集まってくるんですよね。たとえば私が幼稚園の頃は、まだ親権が父にあって、ハンカチに書いてある名前が「じんたまお」だったんです。
阿川 お父さまの姓だったんですね。
有吉 はい。小学校では、友達が「玉青ちゃんのお父さん、サーカス団員だったんでしょう?」なんて言ってきたりして(笑)。子どもだから情報は正確ではないんですけれど、そうやって知ったことが積もり積もっていって。だから自分では調べたことはないんですが、なんとなく父については知っていました。
阿川 お父さまに関する情報のピースが、少しずつ集まってくる感じね。でも、会うことになったのはどうして?
有吉 結婚が決まった頃に、伯父に「一度、会ってみないか」と言われて会うことになったんです。母は生前、私を父に会わせなかったので、父に会ったら母は怒るだろうかと考えたりもしたんですが、一回会って、『この人だ』とわかれば、もう会わなくてもいいくらいの感じで、会ってみることにしました。
それでホテルのレストランの個室で、伯父夫婦と一緒に会ったのですが、そこに現れた父は、小説のようにダンディな雰囲気ではなくて、老人の風貌だったんです。母よりだいぶ年が上ですし、病気だったこともあって、「えーっ、この人がお父さん!?」って、ちょっとショックでした。
阿川 あら~。でも、その後も交流は続いたわけですね。
有吉 はい。最初はどんなふうに接していいか、わからなくて、ぎくしゃくしていたんですけれど、何度か会って話をするうちに、「おもしろい人だな」と思うようになりました。
阿川 大きな事業をされていた方だし、勝ち気なお母さまが大恋愛をされるくらいだからねえ。
有吉 「この人、何をやらかすんだろう」というような男性としての魅力がありましたし、ものの考え方とか切り口が独特で、自然と会話が弾んで、「あ、母もこの人だったら、好きだっただろう」と思ったんですね。その瞬間、すべてがもうどうでもよくなったというか。母は私が父に会うことを喜んでないかもしれない、と少し悩んでいたのですが、もういいやって。
阿川 それはお父さまが、とてもいい印象として体の中に入ってきたってことよね。
有吉 はい。父も母のことが大好きで、二人は惚れあって一緒になったんだなって確信したとたんに、全て受け入れられました。別れた理由も最初は知りたいと思っていたんですけれど、それももう聞きませんでした。私もそのとき、20代後半で、男と女、いろいろあるでしょうってこともわかっていたし。
阿川 結婚が決まって、自分が安心できる居場所をみつけていたから、父親を受け入れられたっていうこともあるんじゃないかなあ。これがまだ自分の核となる場所を見つけられず、不安定なままだったら、父親との再会もまた違っていたものになっていたような気がする。
有吉 ああ、そうですね。父と、私はいいときに会ったんですね。
阿川 それと小説では「父親に恋する」という感情が珠絵ちゃんの中に芽生えていきますけれど、実際もそういう感情が生まれたんですか。
有吉 残念ながら、そこはまったくのフィクションです。「父と娘は永遠の恋人」ってよく言いますよね。私は父と離れて暮らしていたから、そのあたりが理解できなくて、それってどういうことなのか知りたくて、この小説を書いたところがあります。阿川さんのところは……。
阿川 いやいや、父が恋人なんて、冗談じゃないって感じですよ(笑)。これを読みながら、羨ましくて仕方なかった。世の父親と娘は、互いに、こういう関係に憧れるところがあるだろうなという気がしましたね。父は娘が恋人のように慕ってくるのはうれしいだろうし、娘は娘で、銀座で一緒にお寿司を食べられるような素敵なお父さんは夢だろうし。私自身は、父親にやさしくされた経験がほとんどないから、欠落したものがあって、うちの父とは正反対の穏やかでやさしいお父さんを求めていましたね。
有吉 いえいえ阿川さん、絶対お父さまに愛されていましたよ。『強父論』の表紙の写真を見ればわかります。阿川さんを手のひらにのせて、可愛くて仕方がない感じ。
阿川 娘の前であんなにニコニコしている写真は、あの一枚ぐらいしかなかったから、表紙にしたんです!(笑)

事実とフィクションを織り交ぜた巧みな構成
阿川 『ルコネサンス』という本のタイトルはどういう意味なんですか。
有吉 フランス語で「再認識する」というような意味で、あるとき、本を読んでいて、この言葉に出会いました。知らないで普通に会っていた人が、「じつはあなたがそうだったんですか」というようなくだりで使われていて、いい言葉だなと思って。
阿川 なんの本ですか?
有吉 『オイディプス王』について書かれた本だったと思います。
阿川 読んでるものが違う(笑)。
有吉 それで辞書で引いてみたら、他にも感謝という意味があったりして、おもしろい言葉だなと。父が生きている頃から、このタイトルだけは決まっていたんです。
阿川 ええっ、ってことは構想20年!?
有吉 そうですね。当時から、父との関係はおもしろいなと思っていて、「小説になるかもしれない」って考えていました。
阿川 その関係をおもしろがれたっていうのは、やっぱり小説家の視点よね。そして、そこがこの小説の構成のおもしろいところだと思うんですよね。明治のメリーミルクのパッケージみたいだなって思って。
有吉 どんなパッケージでしたっけ?
阿川 イラストの女の子がメリーミルクを持っていて、その中にまたメリーミルクを持った女の子がいて……とずーっと続いているんです。
有吉 ああ、わかります。絵の中にまたその小さな絵があって、という感じですね。
阿川 そうそう。そうやって果てしなく繰り返すことを「ドロステ効果」というそうで、永遠の中に引き込む効果があるらしいです。『ルコネサンス』も有吉玉青さんが書いているんだけれど、小説の主人公もこの事実を小説に書こうと思っているという入れ子構造が、まさにメリーミルクと同じだと思って。そこがすごく巧みだから、フィクションとわかりつつ、実話に読めてしまうのよね。
有吉 そんなふうに読み解いていただいてありがとうございます。自分でも書いているとどこまでがフィクションで、どこまでが事実か、わからなくなってくるんですよね。でも、困ったなぁ。ほとんどフィクションなのに、事実と思われたらどうしよう。
阿川 いやいや、そこがおもしろいところだし、もう全部本当ってことでいいんじゃない? だますことが小説家の醍醐味なんだから。
有吉 そう思えるといいんですけれど、やっぱり気になってしまう。
阿川 あと、読んでいて笑ったのが、珠絵が父親の足を見て、自分の足と似ていると気づく場面があるでしょう。私もその昔、トイレに座って、ふと足を見たとき、父に足がそっくりで愕然としたことがあって。私は父に似てると言われるのが、嫌で嫌でたまらなかったのに同じだわって。
有吉 阿川さんのお顔、お父さまに似てらっしゃいますよ。
阿川 はい、薄々自覚はしています(笑)。顔とか性格とか、嫌なところ、いっぱい受け継いだなって。高校の頃、学校でみんなで話していたとき、あんまり父が厳しいので、「私、もしかして、本当の子どもじゃないのかも」って、私が言ったら、地理の先生がガハーッと笑って、「そんなことはないわよ。あなた、お父さんそっくりだから」って。ガーンですよ(笑)。玉青ちゃんのお父さんの顔はどうでした? 似ていらした?
有吉 初対面では思わなかったんですけれど、似ていると思います。父が亡くなったとき、新聞や雑誌に出た写真を見た友達も「似てるね」って。
阿川 内面的に、お父さまから何か受け継いだなと思うことはありましたか?
有吉 「なぜドン・コザック合唱団を日本によんだの?」と尋ねたとき、「ああ、きれいだな。みんなに聴かせてあげたいなと思ったんだよ」と言ったんですね。私も何かに感動したら人に伝えたい。だから書く仕事をしているんだと、そのとき初めてわかり、これは父から受け継いだものかなと思います。
阿川 最初は「神さん」と呼んでいて、最後は「お父さん」と呼べたんですか?
有吉 父が雑誌のインタビューで、娘が自分のことを「お父さん」ではなく、「神さん」と呼ぶと、残念がっているのを読んだことがありました。でも、私、最後まで「お父さん」と呼ばなかったんです。その代わり、途中から「親父」って呼んでました。それは「お父さん」と呼びたくないからではなくて、「親父」のほうがあっていたからなんです。父もそれで満足していたようでした。一緒に過ごせたのは短い時間でしたが、父と会い、父という人間を知ることができたのは、私にとって、本当に幸せなことだったと思っています。

小説家を親に持つと子どもは苦労する?
阿川 玉青ちゃんは、お母さまのことは『身がわり』というエッセイで書いていますよね。
有吉 はい。私が20歳のとき、ちょうどイギリス留学中に母が53歳で亡くなって、突然のことだったので、何だかよくわからないまま、日が過ぎていったという感じでした。それから4~5年たって、やっと母のことを書くことができたんですね。
阿川 24~25歳で、あれだけのことを書いたのか。すごいわ。お母さまは、家ではどんな感じだったんですか。
有吉 母は料理をしたり、掃除をしたりっていうことは一切なくて、本当に書くことだけでした。家のことはお手伝いさんがやって、祖母が秘書的な役割をしていましたね。私の面倒も普段は祖母が見ていて、時間があるときだけ、ワーッと過剰に愛を注いでくるので、子どもとしては迷惑で。いつも仕事をしていましたけれど、「書けない」と悩んでいるのは、見たことがなかったです。
阿川 それは父も言ってました。吉行淳之介さんと二人で、「もう何も書くことがない」「絞っても水一滴でない」と話していたら、お母さまが「お兄ちゃんたち、何言ってんの? 私なんか絞れば絞るほど、ジュージュー、ジュージュー出てくるわ」っておっしゃったらしくて、「有吉はすごいな。絞っても絞ってもまだ書くことが出てくるらしい」って父が感心していたのを覚えています。
有吉 母がそんなことを……。亡くなって30年以上たちますけれど、あらためて思うのは、作家の家は何でもありってことですね。生前は、母への不満もありましたが、あれぐらいでないと小説は書けなかったのだ、と今は思います。だから、阿川さんの『強父論』を読んでも全然驚かなかった(笑)。
阿川 そうでしょ。作家の子どもが集まると、決まって、「うちはひどかった」「いや。うちはもっとひどかった」という話になるものね。私の場合、父のためを思って何かやっても、いつもそれを裏返されるんですね。まだ父が元気だった頃、父と母を京都に連れていったことがあったんです。以前、私が取材で、とてもおいしい料理を食べたので、両親に食べさせたいと思って、「私がおごるから」って3人で行ったんです。
有吉 親孝行ですね。
阿川 そうしたら、帰りの新幹線で、「高山寺に行けたのは良かったよ。高山寺に行けたのは良かった」って何度も繰り返すの。ひどくない??(笑)「阿川さん、報われませんね」って秘書にも言われたわ(笑)。
有吉 でもそれは、お父さまが照れてらしたんじゃないですか。照れがあるから、いつも「佐和子ー!」って叱りつけていたとか?
阿川 照れもあるけれど、やっぱり父は自分の理想の娘像っていうのをもっていたと思うの。たとえば「おいっ、日本酒つけてくれ」って父に言われたとき、「はい」って口では言いながら、内心『試験で忙しいのに』とか思うでしょ。そうすると父はそれを敏感に察知して、「なんだ、今のため息は!?」って怒り出すのよ。「あ、お父さま、お酌いたしましょう」みたいな娘を望んでいたのに、私が全然違うから、癪にさわったんだと思うのよね。
父が亡くなったあと、いろいろな方に言われました。「私も父とうまくいってなくて、死んだ直後は涙も出なかったけれど、しばらくときがたつと、突然ダーッと滂沱のような涙があふれてきた」って。悲しみはじわじわくるんだと。でも、7年たつけど、全然来ないのよ(笑)。夢の中でも相変わらず父は不機嫌で、私は怯えていて、いまだに父を恐れてる。本当に不幸な娘です(笑)。
有吉 そういえば、阿川さんは、最初の頃は、お父さまに文章指導をしていただいていたんですよね。羨ましいなと思いつつ、私だったら見せなかったかもしれないと。親に読まれるのは嫌じゃないですか。
阿川 嫌ですよ。本当に嫌でしたよ。でも、阿川弘之の娘がこんな日本語を使っていると思われたら体裁が悪いということなんでしょうね。
私が最初にエッセイを書いたとき、原稿を編集部に届けようと支度をしていたら、父が「すぐに編集部の人に30分遅れると電話しなさい」「書斎から鉛筆とメガネを持ってきなさい」って。キター!!って感じですよ(笑)。それで私の原稿を読み始めて、「まず名前の位置が悪い」って。
有吉 そこからですか(笑)。
阿川 それからダメ出しの嵐です。「だった、だった、だった、と同じ語尾が3回続く。安機関銃じゃあるまいし」とか、「こういう形容詞を身内に使うべきでない」とか、徹底的に直されて。ただ、内容については、何も言われなかったんですね。「父にこんなひどい目にあった」っていう悪口をもっぱら書いていましたけれど、それに関しては、怒られなかった。そこはさすがに物書きだなと思いました。
有吉 いろいろ口を出しつつ、娘が同じ仕事をするようになって喜んでいらしたんじゃないでしょうか。
阿川 確かに、私が物書きになったことは、喜んでました。「どれほど、俺が苦労して、おまえたちを育てたか、やっとわかったか」「書くことはこんなに大変なんだ、ざまあみろ」って感じではあったけど(笑)、書くようになって、父との会話が増えたっていうのはありますね
有吉 それは羨ましいですね。
阿川 玉青ちゃんが書くようになったと知ったら、お母さまはそれはもうお喜びになったと思いますよ。
有吉 どうかなあ。母は、作家の方が亡くなって、お子さんが何か書いたのを見ると、「私が死んでも恥ずかしいから書かないでね」って言ってたんですよ。
阿川 ウチもそうですよ。でも、出版社というところは、作家がいてそこに娘がいると原稿を依頼するものなんですよ(笑)。やっぱり父親と娘の関係って、どこかミステリアスなところがあるように思われているから、書けるか書けないかわからないけれど、とりあえず依頼する(笑)。娘は、それで鍛錬されて、書き続けることになるんだと思うの。玉青ちゃんは作家になって良かったと思いますか。
有吉 自分が書くようになって、初めて母のことがわかったような気がしますから、良かったと思います。母は多忙で、根を詰めて仕事をしていたので、それで早く死んだと思っていましたけれど、今はその逆のことを思うんですね。母は、体が弱くて、とても20歳まで生きられないと言われていたらしいのですが、実際は、倍以上生きました。それは書いていたからだと。書きたいから、書くのが楽しかったから生きられたんじゃないかって。母には到底及びませんが、自分がやってみて、そんなふうに思うようになりました。
阿川 優秀な子だねぇ。最後にまた小説のことで、ひとつ確認。ジンさんが、お寿司を吸い込むように食べるシーンがすごく印象的で。あれは事実?
有吉 あれもフィクョンです(笑)。お寿司をとてもおいしそうに食べる友人がいて。
阿川 そうなのねぇ。あの描写はよかった(笑)。小説に出てくるジンさんは、今まで玉青ちゃんが出会ったいい男たちの集合体ってことですね(笑)。
「小説すばる」2022年6月号転載
プロフィール
-
有吉 玉青 (ありよし・たまお)
1963年東京都生まれ。早稲田大学第一文学部哲学科、東京大学文学部美学藝術学科卒業。ニューヨーク大学大学院演劇学科修了。大阪芸術大学教授。89年、母・佐和子との日々を綴ったエッセイ『身がわり』を上梓、90年、同作で第5回坪田譲治文学賞を受賞。2014年、母を支えた祖母を描いたエッセイ『ソボちゃん』を発表。小説に『ねむい幸福』『月とシャンパン』『美しき一日の終わり』、エッセイに『雛を包む』『恋するフェルメール 37作品への旅』など著書多数。
-
阿川佐和子 (あがわ・さわこ)
1953年東京都生まれ。エッセイスト、小説家。’99年『ああ言えばこう食う』(檀ふみとの共著)で講談社エッセイ賞、’00年『ウメ子』で坪田譲治文学賞、’08年『婚約のあとで』で島清恋愛文学賞、’14年に菊池寛賞を受賞。その他『聞く力 心をひらく35のヒント』『ばあさんは15歳』『負けるもんか 正義のセ』『強父論』『ないものねだるな』など著書多数。
新着コンテンツ
-
新刊案内2025年06月26日
 新刊案内2025年06月26日
新刊案内2025年06月26日筏までの距離
水原涼
デビュー作で芥川賞候補に挙がった著者が贈る、わたしとあなたの8つの物語。
-
インタビュー・対談2025年06月20日
 インタビュー・対談2025年06月20日
インタビュー・対談2025年06月20日宇山佳佑×檜山沙耶(フリーアナウンサー)「風が吹くたび、物語が生まれる」
ウェザーニューズで気象キャスターとして活躍し、その後も活動の幅を広げる檜山沙耶さんと作品、風、お天気について語っていただきました。
-
お知らせ2025年06月17日
 お知らせ2025年06月17日
お知らせ2025年06月17日小説すばる7月号、好評発売中です!
新連載はいずれも小説すばる新人賞出身の佐藤雫さん、神尾水無子さんの2本立て!
-
お知らせ2025年06月17日
 お知らせ2025年06月17日
お知らせ2025年06月17日本日開店、「スキマブックス」!!
文芸ステーションに新しい読みもののコーナー「スキマブックス」がオープンしました!
-
スキマブックス2025年06月17日
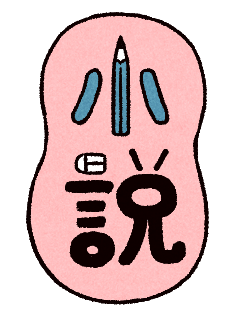 スキマブックス2025年06月17日
スキマブックス2025年06月17日今度こそ許すまじ春野菜といんげん豆の冷製スープ事件
結城真一郎
彼氏が浮気をしているのではないかと疑った大学生は、「あるレストラン」に浮気調査を依頼するが――。
-
インタビュー・対談2025年06月17日
 インタビュー・対談2025年06月17日
インタビュー・対談2025年06月17日堂場瞬一「日本政治の未来をフィクションで問う」
堂場瞬一さんの通算195冊目の作品にして、実験的政治小説第二弾『ポピュリズム』の世界観を語ってもらった。


