岸本佐知子×石田夏穂 『我が友、スミス』刊行記念対談 「ディテールに宿る 小説の魅力」
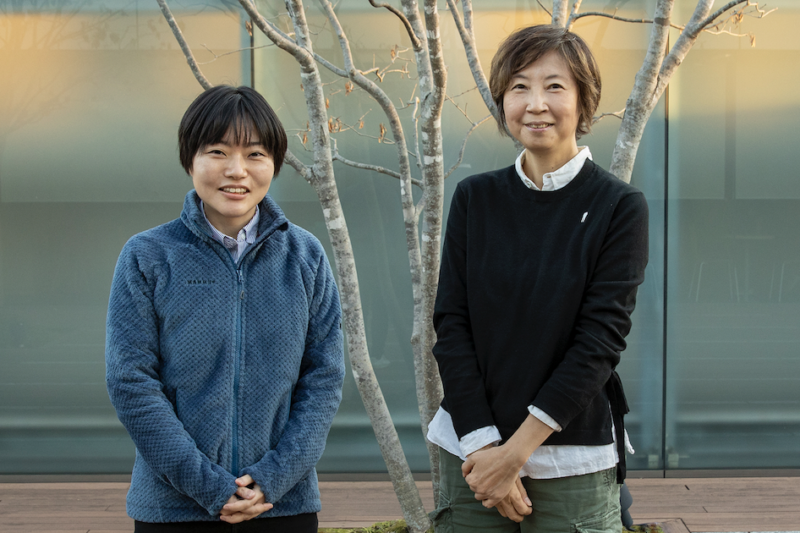
第四十五回すばる文学賞の佳作に選ばれ、第一六六回芥川賞候補となった小説『我が友、スミス』。鍛錬による強い筋肉のみならず女性美までもを求められる、女性のボディ・ビルの世界の虚実を描き、描写の細かさや織り込まれたユーモアなどが選考委員から高く評価された。この対談では、作品を強く推した選考委員の一人、翻訳家の岸本佐知子さんと作者の石田夏穂さんが、本作品の執筆の経緯や背景、創作について語り合う。
構成/綿貫あかね 撮影/中野義樹
ディテールの喚起力
岸本 このたびはおめでとうございます。今回のすばる文学賞は受賞作と佳作の二作受賞になり、この『我が友、スミス』も「すばる」に掲載されて芥川賞候補になりました。
石田 編集部の方から佳作になったとの知らせが届き、とても驚きました。その後、芥川賞候補に入ったと聞いてしばらく経ちましたが、まだあまり実感が湧いてきません。
岸本 選評でも書きましたが、私は最終選考に残った五作のうちで『我が友、スミス』を一番面白く読みました。とにかくオープニングでいきなり引き込まれてしまって。私もそうですが、ボディ・ビルは世の中の大半の人にとっては未知の世界。それなのに細かく書き込まれたディテールで、その知らない世界の情報がしっかりと伝わってきて、なおかつイメージが喚起されてなめらかに読まされてしまう。その吸引力といったらなかったです。
石田 ありがとうございます。
岸本 私、翻訳の師匠に「小説の魅力はオープニングに詰まっている。だから一行目でどんな話なのかを読者に想像させるように訳しなさい。作家は一行目から自分の描きたい世界に引きずり込もうとしているのだから、そのインパクトをちゃんと感じなさい」といつも言われていて、この作品はまさにその見本のようです。私は文学賞の選考委員になってからまだ日が浅いのですが、これがもし英語で書かれていた場合、自分で訳したいと思うかどうかを選考基準の一つにしています。その意味で石田さんのこの作品は本当に訳したいと思いました。トレーニング・マシンの名前や筋肉の名称を調べるのは大変そうですが。
石田 本当に嬉しいです。
岸本 でもこんなに詳しく書き込んでいるのに、石田さんご自身はボディ・ビル競技をやってらっしゃらないんですよね。それなのに、どうやって大会までの準備や、本番の迫真のディテールを書かれたのでしょうか。
石田 私はジムには通っていますが、平均的な筋トレをしている程度で、むしろ通うのもときどきだるい、と思うくらいです。でも、そのジムの会員の中には私のようなトレーニーがいる一方で、大会を目指していると思しき方も多く通われています。大会が近づくと競技日程の掲示が張り出されるなど、関係のない自分にもさまざまな情報が入りますし、すごい高重量でトレーニングされている方も見かけます。あと、合同トレーニングやパーソナル・トレーニングも身近に目にします。明らかにその道で何年もやってきたとわかる人が、トレーニーとペアになってトレーニングしている。その光景にとても臨場感があって、小説のイメージが湧いてきました。
岸本 そもそもどうしてジムに通おうと思ったのですか?
石田 単純に運動不足を解消したかったんです。もともと怠惰な人間で、ガチなジムに通えば自分もそれなりにやるかな、という期待がありました。
岸本 まさかこんなものを書くとは思いもよらずに入ったんですね。
石田 そうでした。大会に出るためにトレーニングしている選手の方々を傍から見ていると、筋肉を作る以外にもたくさん頑張っていることがあるんだろうなと気づいて、それを書いてみたいと思いました。
岸本 でも、あのディテールの書き込みはちょっとただ事ではない感じを受けました。末尾に挙げてある参考文献も一冊しかないし。どういうことなんだろうと。
石田 日々のことをSNSで発信するトレーニーの方が結構多いんです。「今日は大会十五日前で、こんなトレーニングをします、こんなものを食べます」のように。
岸本 ではあの書き込みは、大会を目指すトレーニーに直接聞いたわけではなくて、文字情報からなんですね。驚きです。大会当日の舞台裏の準備の場面は本当にリアルでした。そういう情報も集めたのでしょうか。
石田 巷に流れている情報と、自分のイメージとを組み合わせて書きました。YouTubeでトレーニング方法をアップしている人も大勢います。
岸本 必要な情報をストーリー内に入れ込むのがすごくうまいですよね。読む側は知らない単語ばかり出てくるんですが、それが全然気にならなくてぐいぐい読ませる。今回❝パンプ・アップ❞という言葉を覚えました。この小説には、絶対ガチでトレーニングをやっていないと出てこない表現が使われています。重量の負荷がマシンで逃げて筋肉に届かないとか、筋肉が水っぽいとか。
石田 あれは自分の話も少し入っていて、それと想像を組み合わせて書きました。水っぽいというのはボディ・ビル業界では割と共通の認識、という理解です。
岸本 以前、トム・ジョーンズというアメリカの作家の短編集『拳闘士の休息』を訳しました。この本には、ベトナム戦争のものすごく血みどろの臨場感あふれる短編が何編か収録されているのですが、後で知ったところ、なんと彼はベトナム戦争に行っていなかったんです。そのときの驚きに匹敵するくらい、今びっくりしています。でも、そうやって文字情報と想像の組み合わせでこれだけすごいものが書けるなら、この先どんなものでも書けますね。
石田 そう言っていただけると励みになります。
岸本 これもよく翻訳の師匠に言われましたが、登場人物は全員魅力的であるべきということ。この小説の主人公であるU野、それからE藤やO島も、S子というちょっとチャラめの人でさえ魅力的。顔がはっきり見えていて寄り添いたくなります。登場人物でモデルにした人はいるのでしょうか。
石田 これという特定の人はいませんが、強いていうならジムで見かけた方々ですね。
岸本 では、ジムに来ている女性で、大会を目指しているすごく格好いい人がいるんですね。
石田 はい。そうした方々からはただ者じゃないオーラを感じます。
岸本 ではこの中に出てくる、たとえば筋肉増量期とか大会前の減量期というのは、ほぼ事実に近いのでしょうか。
石田 大会に向けた準備は個人によりけりですが、概ねそうだと思います。
真顔の文体に挟まれるユーモラスなたとえ
岸本 文章がとても面白いですよね。文体がポーカーフェイスというか真顔な感じなのですが、これは狙ってやっているのか、それとも素なのかがわからなくて。「スヌーピーの言う通り、我々は配られたカードでゲームするしかないのだ」とか、笑ってしまいました。なぜここでスヌーピーなんだ? と。
石田 主人公の気持ちになったときに出てきました(笑)。
岸本 「調整が阪神タイガースのマジック点灯のようにせっかち」とか「血管は令嬢のように細い」とか、たとえが面白くてたくさん書き写してしまいました。この文体は地声なんでしょうか。
石田 地声だと思います。読者としては真面目な堅い文章が好きなんですが。
岸本 どんな作品を読まれるのでしょうか。
石田 髙村薫さんの小説が好きです。ごく一般に髙村さんはユーモアの隙がないような文章を書かれますが、読む方はそうした作品が好きです。
岸本 髙村薫作品の感じを狙ったのにこうなったんですか?
石田 結果的に、こうなりました(笑)。
岸本 それは本当に得難い。選考委員の金原ひとみさんも選評で「久しぶりに小説でこんなに笑った」と書いておられました。だから、今のままの何ともいえない味わいをぜひ保っていってほしいと思います。
石田 書き終えて送ったときは、あまりにふざけすぎていて、これは純文学ではなくエンタテインメント小説なのかもしれないと思いましたが、そう言っていただけて嬉しいです。
岸本 これを書いているときはどういう気持ちでした? 楽しかったですか?
石田 楽しかったです。
岸本 そうですよね。楽しそうに書いているのがこちらにも伝わってきました。やっぱり筋トレがお好きなんでしょうか。
石田 好きですね。ジム通いは二年くらい何とか続いています。やっぱり、やればやるだけ身体が引き締まって、しっかり運動しているという肯定感が出てきます。仕事でパッとしなかった日や大失態した日も、せめて筋トレくらいはちゃんとやろうと思い、やったら、今日も頑張ったなあと思えます(笑)。

女性ならば浴びるように言われる言葉
岸本 U野はそんなに内面を語る人ではありませんよね。ひたすら筋肉のことやトレーニングについて語っていて、ある種彼女が空洞みたいになって途中まで進んでいきます。空洞というのは悪い意味ではなくて、筋肉の話に薄っすらと彼女の内面が透けて見えるというか、その感じがとても面白い。でも途中で、弟の結婚相手との顔合わせで実家に帰るシーンがあります。そこでテレビに映る女性ビルダーを見ていた母親に「あんなムキムキにならないでよ?」と言われて、彼女が怒りますよね。そして帰りの電車内で「怒るという形で自分の考えを表明したことが、何やら愉快だった」と振り返り、そこから楽しいとか幸せだとか、自由だという言葉が彼女からだんだん出てくるようになります。その流れが感動的でした。
石田 今そう言われて初めてそのことに気づきました。確かにそうですね。自分は心理描写をそれほど書かないタイプかと思っていましたが、少しずつ出てきたものがあり、書いていくうちに慣れてきて、書く方法もわかってきたのかもしれません。
編集部 読み終わってみるとこの小説はジェンダーがテーマの一つだと気づきます。書き始める前に、こういう展開で書いていこう、という設計図は作られたのでしょうか。
石田 女性のボディ・ビル大会のポージングで、優雅なポーズをするある種の矛盾のようなものを書こう、とは思っていました。
岸本 作家と話をしていて「これは書き始めのときから設計図はあったんですか」と質問すると、ほぼ全員ないと答えるのですが、それは噓ではないかと疑っていて。ないと言ったほうが格好いいからではないかと思っているんですよ(笑)。
石田 自分も今、若干迷いました(笑)。
岸本 このあたりでこういうことを書こう、と覚書のようなノートは作っているんですか?
石田 あります。主人公U野、脱毛の後は日焼けして、その次はポージングのレッスンを受ける、という程度ですが。
岸本 でもその中で、これは絶対に書くと決めていたことはありますよね。
石田 ポージングのレッスンで、ハイヒールでずっこける場面は一番書きたいと思っていました。
岸本 U野というキャラクターは、顔も含めて最初から見えていましたか? 自分と重なるところが結構あったのでしょうか。
石田 率直に言うと、やはり多少は自分が出ているのかなと思います。あえて言うなら、地味な会社員がアイデンティティです。
岸本 小説の主人公としては相当に地味ですよね。そこがとてもいい。だから最初は話の中心が筋肉やトレーニングのことで、彼女自身はあまり前に出てこない感じなのが、なぜ彼女が筋トレをやっているのかが明らかになってくるあたりから、だんだんゾクゾクするようなスリルが出てくる。途中で、自分の気持ちとあまり向き合おうとしてこなかった、というようなことを彼女が言っていますが、それが少しずつ変化してきたのかなと読めました。彼女が本腰を入れて筋トレに励むようになり、ほぼ定時に退社しようとすると、職場の同僚男性が放つひと言がありますよね。
石田 「女性は大変ですね」ですね。
岸本 彼女は最初にO島から勧誘を受けたとき「別の生き物になりたい」と思います。そして最後の大会本番の舞台裏で同僚の発言を思い出し、再び「別の生き物になりたい」と切実に願う。実は最初読んだときに、こんなひと言で「別の生き物になりたい」とまで思うだろうか、ちょっと弱いのではないかと感じたんです。でもあらためて読んでみると、いやいや、これだと。日本で女性として生きていると、「女性は大変ですね」というような言葉は浴びるように言われますよね。
石田 言われます。
岸本 「非情この上ない」と書いておられましたが、あれは一見気遣っているようでいて、実は彼女を女性という雑なくくりに入れて、個として見ていない発言です。この国で女性として生きていると、日々そういう形のないもわっとした嫌な感じの抑圧、息苦しさを感じる。それがあのひと言に凝縮されていて、むしろこれでいいのだと思いました。たとえばもっときついセクハラとか、トラウマになるような酷いことがあって、それで強くなりたくて筋トレをする、という流れだと図式的過ぎて、読者にはかえって響きにくいのかもしれません。「女性は大変ですね」というフレーズは書き始めから浮かんでいたのでしょうか。
石田 これは最初から頭にありました。同情しているようで、ちょっと下に見ているでしょう、みたいな発言。その発言が出てくるときに、もっと具体的なエピソードがあったほうがいいだろうかとも考えましたが、あまりくどくど書くのは、こちらも読む側もつまらない気がしました。ここは賛否両論と思いますが、今そう言っていただけて嬉しいです。
岸本 何かこのもわっとした嫌な感じが「女性は大変ですね」というひと言に表れていて、うまいなと思いました。「そうか、女は大変か。きっと、それは正しいよ。だが、お前の言う「大変」と、いま私を突き動かしている「大変」は、恐らく別物だ」という部分は、めちゃくちゃ格好良くて拍手しました。他にも決めゼリフみたいなしびれるフレーズがたくさん出てきます。「身体は、一番正直な他人だ」とか。
石田 書く側が楽しんでいるフレーズですね(笑)。
岸本 「筋肉は年功序列だ」とかね。これは実際のトレーニーが言うような言葉なんですか?
石田 これもボディ・ビル業界では共通の認識で、続けた者が偉い、という意味だと思います。
編集部 トレーニーは言葉を愛する人が多いんでしょうか。
石田 これは私の主観ですが、ボディ・ビルダーには確固とした信念というか、名言が多い気がしました。外から見ると完璧なのに決してナルシストではなく、むしろ謙虚な方が多い印象です。
岸本 内向的なのかもしれませんね。黙々とトレーニングするような。自分の筋肉は唯一、自分で完璧にコントロールできるものですものね。
石田 努力次第なところはあると思います。個々の体質はあるでしょうが、一般にやればやるだけ成果が出ます。
岸本 先ほどU野が地味という話が出ましたが、彼女はとても質素ですよね。大会で着るビキニをメルカリで買おうとするし、YouTubeを気絶するほど見るのに絶対に課金しない。そういう質実剛健なところもとてもかわいくて好きでした。
石田 凡人らしさが出ていたら良かったです。
岸本 そうですね。でも怒りみたいなものからだんだんと彼女自身の内面が出てきて、最終的に決勝ではハイヒールを脱ぎ捨て、ピアスを取り、自分の思うままにポーズを決めます。そこで私もいっしょに拳を握りしめて、ちょっと泣けました。そのラストへの盛り上げ方も素晴らしかった。石田さんは大会を実際にご覧になったことはあるんですか?
石田 実は大変恥ずかしながら、YouTubeでしか見たことがないんです。
岸本 それでこれだけ書けるなんてすごい。大会へ向けての準備段階で、顔のピーリングや身体のタンニングをするところ、衣装合わせをする場面も面白かったし、大会本番の舞台裏も細かく書き込んでいて緊迫感に溢れていました。なのに、彼女がいざ舞台に出てきて演技するシーンはすっぽりと抜けている。これはわざとですよね?
石田 そうです。彼女はたぶん、舞台に上がったら無我夢中になって何も記憶がないだろうなと想像しました。
岸本 なるほど……! そのシーンをみっちり書いてしまうと、それまでの舞台裏の緊迫感が生きないかもしれない。だから場面がぽんと飛んで競技後に移っているのが、うまいと思いました。
知られざる業界内のディテールを書き込む
岸本 石田さんは幼い頃はどんな子どもだったんですか?
石田 実は小さい頃のことをあまり覚えていないんです(笑)。本当に特筆すべきことは何もなくて。なので岸本さんのエッセイを拝読すると、中学時代や高校時代のことが手に取るように書いてあり、記憶力がすごい、自分とは違うと思いました。
岸本 どんな性格の子だったんでしょう。
石田 内向的だったと思います。幼稚園に行くのは億劫だったし、お遊戯とかも、なぜこんなことをしなくてはいけないんだろう、とか冷めていました(笑)。かわいくない子どもでした。
岸本 大学は理系の学校を出られているんですよね。いつから文章を書くようになったんでしょうか。
石田 もともと日記を書くのが好きでした。書きたいときだけ書く日記ですが、高校生ぐらいから書いていました。初めて小説を書いたのは大学生のときです。
岸本 やはり書くことがもともと好きだったんですね。最初に書いた小説はどんな内容だったのでしょうか。
石田 無駄に長いテロリストの話でした(笑)。髙村薫さんの作品を読んで自分も書いてみようと、五百枚くらい書きました。完成して一応文学賞に応募しましたが、全然駄目でした。
岸本 いきなり五百枚はすごい。話の筋を伺いたいです。
石田 ある工事現場で完成した配管の耐圧テストが行われます。管の内側から圧力をかけて漏れがないかをチェックするもので、その際少しでも漏れがあると場合によっては爆発に匹敵する威力の事故に繫がる危険な作業です。一人の作業員が親会社を倒産させようと、それをわざと画策して成功するのですが、最後は相棒と分かれて逃亡する、みたいな話です(笑)。
岸本 面白そう。ちょっと今までにないタイプのテロリストですね、それは。そのテストに危険が伴うのは事実なんですよね。それはどこから題材を?
石田 大学で耐圧試験のことを知り、そこから着想した記憶があります。
岸本 一般的には知られていない業界内のディテールを小説のモチーフに使うのは、もうその頃から始まっていたんですね。
石田 髙村薫さんの小説を読んでいると描写がとても細かくて、そこに傾倒したから自分の書くものにも影響したのかもしれません。
岸本 その次はどんな小説を書いたんですか?
石田 溶接工の話でした。溶接にはさまざまな種類があり、たとえば片手でするものと両手でするものがあります。両手でする溶接のプロが、あるとき喧嘩で片手を失ってしまい、やさぐれたんですが、片手でする溶接を頑張るようになった、みたいな内容です(笑)。
岸本 想像するに、その作品でもディテール描写が炸裂していたんでしょう。溶接はやったことがあったんですか?
石田 研究室で少しだけあるのですが、自分はめちゃくちゃ下手でした。
岸本 その小説は溶接工の一人称だったんですか?
石田 そのときは三人称でした。「彼は」みたいな書き方です。
岸本 『我が友、スミス』は何作目くらいなんでしょうか。他の作品についても聞きたいです。
石田 十作目くらいだったと思います。あとは脚が太いことで悩んでいる女性が脂肪吸引する話を書きました。その作品は大阪女性文芸賞をいただきました(「その周囲、五十八センチ」)。そのときに初めて文学賞というものを受賞して、びっくりしました。
岸本 読んでみたいです。それは一人称でした?
石田 一人称です。「私」という視点が入りました。
岸本 どういうきっかけで脂肪吸引の話を書こうと思ったんでしょうか。
石田 単純ですが自分の脚が太く、これを脂肪吸引でぐいぐい吸って細くできたらいいのに、と思ったのが最初です。
編集部 たとえばルッキズムであるとか、見た目のことで悩んでいて自信が持てない女性とか、そういう現代の社会や人間が抱える問題からの発想なのか、脚を細くしたいという気持ちが先なのか、どちらでしょうか。
石田 後者で、社会がどうという大きなことではなく、身近な出来事を書きたいと思っています。
岸本 でも身近なことを書いていても、今の世の中は酷い問題が身の回りに山積みになっているから。たとえばU野が大会に出るため見た目に気を使うようになったら、職場で扱いが良くなった、という場面がありましたが、これはよくあることだろうなと思いました。それから、化粧が恥ずかしいという描写も個人的に共感しました。この人はこういう手順を踏んで化粧をした、と思われるのが恥ずかしい気持ちはとてもよくわかる。スーパーマーケットで肉と玉ねぎとじゃがいもを買ったら、カレーでしょうと言われて恥ずかしい、というのと似ています……いやちょっと違うか(笑)。
編集部 先ほどのテロリストや脂肪吸引の小説にも、石田さんのユーモアはちりばめられていたのでしょうか。
石田 一人称が「私」のときは照れが出てしまうのか、結構入れてしまいます。溶接工の話はものすごく真面目に書きました。
岸本 照れで入れているの?(笑)溶接工の話は髙村さんの小説みたいな感じだったんですか?
石田 パクリと言われても仕方がないくらいに寄せました(笑)。
岸本 髙村さん以外にも影響を受けた作家はいますか?
石田 ミステリが好きです。パトリシア・ハイスミスやサラ・ウォーターズをよく読みます。
編集部 『我が友、スミス』ではジェンダーバイアスが一つのテーマとして浮かび上がって来ました。ジェンダーについては石田さんがこの先も書いていきたいと、インタビューで答えておられました。ジェンダー問題やルッキズムについて書かれた海外文学も、今たくさんありますよね。
岸本 古くはマーガレット・アトウッドの『侍女の物語』などがありますし、ここにきて本当にたくさん出てきています。最近読んで面白かったのは、ナオミ・オルダーマンの『パワー』という近未来の長編小説です。ある日突然、世界中の女性が電撃のパワーを身に付けてしまうんです。肩のところに謎の器官ができて、『うる星やつら』のラムちゃんみたいに相手に電撃を与えることができるようになるんです。すると男女の肉体的な優位が逆転することによって、あっという間に社会的地位も逆転、女性がすべての権力を握り、男性を弾圧しはじめる。これは男女の立場を逆転させて違和感を描くことで、今ある男女間の不均衡をあぶり出す、ミラーリングという描き方なんですが、それだけにとどまらない。女性は今まで男性に対しての何百年分の恨みつらみがある。だから力を手に入れたことで、男性が女性に対するよりももっと酷い暴力を加えるようになるんです。だから男女逆転で最初のうちは胸がすくんですが、そんな単純な話では済まされない。
石田 日本語に訳されているのでしょうか。
岸本 河出書房新社から出版されています。私も日本語で読みました。

エッセイもフィクションで構わない
石田 私からも岸本さんに質問していいでしょうか。岸本さんが訳された海外小説や、ご自身のエッセイを拝読して本当に面白かったです。自分が海外小説で最初に惹きつけられるのはタイトルで、何となく原題と引き比べてしまいます。たとえば、映画化もされましたがパトリシア・ハイスミスの小説『太陽がいっぱい』は、原題(The Talented Mr. Ripley)をそのまま訳すと「才能あるミスター・リプリー」のようになり、そのギャップが新鮮です。トーマス・マンの『ヴェニスに死す』も、昭和初期に出版された和田顕太郎訳では『ベネチア客死』というタイトルで、受ける印象が全然違います。これは翻訳者か出版社か、どちらがどうやって決めているのでしょうか。
岸本 翻訳書のタイトルは映画の邦題のつけ方とは違います。それから日本で初めて訳されたときと新訳でタイトルが変わる場合もあります。J・D・サリンジャーの『The Catcher in the Rye』も、繁尾久さん訳では『ライ麦畑の捕手』、野崎孝さん訳では『ライ麦畑でつかまえて』、村上春樹さん訳では『キャッチャー・イン・ザ・ライ』となっています。サン=テグジュペリの『星の王子さま』も原題からそのまま訳すと「小さな王子」です。原題には星なんて単語は全く出てこないけれど、そこは最初に訳された内藤濯さんのみごとな裁量というかセンスですね。やっぱりタイトルのセンスが英語圏の人と日本人とは全然違うと思います。
石田 そこを伺いたいです。
岸本 大体の人はタイトルとカバーデザインでその本が面白いか、買うか買わないかを判断しています。日本で出版されるまで、最もその本について知っているのは翻訳者。何度も繰り返し読んでいるから、もしかすると作者よりも知っているかもしれません。だから売れてほしいし、たくさんの人に読んでほしいから、それに見合ったタイトルをつけるのはかなり大事な仕事だと思います。そういう意味で翻訳者はプロデューサーのようなところがあります。
石田 担当編集者といくつも案を出し合うのでしょうか。
岸本 そういうときもあります。訳者が考えて駄目出しされることもありますし、とても訳しにくくて困ったことも。『我が友、スミス』はすぐに思い浮かんだのですか?
石田 筋トレで使うスミス・マシンが人の名前みたいで面白かったのと、呼びかけるようなタイトルがいいなと思いました。
岸本 迷いなく決まったんですね。
石田 はい。あと、翻訳のときに登場人物の会話の語尾をどうするのかも、訳者の裁量で決まるのでしょうか。
岸本 そうですね。でも、語尾の問題は奥が深い。女性のセリフの語尾としてよく使われてきた「〜よ」、「〜だわ」、「〜ね」は、「よわね問題」といって同業者の間で最近よく話題になります。女性の役割語のように使われていますが、現実の会話ではもうあまり言いませんよね。でも女性同士がリアルに喋っているのをそのまま書き写すと、たぶん男性言葉とほぼ同じになるし、文字上ではかなりぶっきらぼうな感じになってしまうので、ある程度仕方がないところもあります。とはいえ十年前に自分が訳したものでも、今読むと女性のセリフがちょっと、もう違うなと思うことがあるし、重版がかかったり文庫になったりするときに直す場合もあります。悩ましい問題です。
石田 英語圏の小説と日本の小説で表現されやすいことの違い等はあるのでしょうか。たとえば日本の小説だとこういう描写が多いとか、アメリカの小説だとこういう描写が多いとか。そういうことは国や言語の違いではなく、それぞれの作家次第なのでしょうか。書きっぷりの違いといいますか。
岸本 作家個人によるでしょうね。翻訳家は楽天的でないとできない職業だといわれています。全然違う文化を持ち、違う日常を暮らしていて、肌の色も話す言葉も異なる作家の書くものを、自分たちとは全く違うと思いながらだと一語も訳せない。人間なんだから基本的な喜怒哀楽はそんなに変わらないだろう、という気持ちで訳すしかない。
石田 そうですね。
岸本 でも、文化の違いで「えっ?」と驚くことはありますね。たとえばアメリカ人と日本人では、トイレの個室の感覚が違っていてびっくりします。アメリカの小説で女の子が二人で個室に入り、おしっこを代わる代わるしながらおしゃべりする場面があったり(笑)。アメリカ映画でも、個室の扉の上下が結構空いていて、上は顔が丸わかりだし下はふくらはぎが見えるとか。喜怒哀楽や人間としての根幹は同じでも枝葉末節のところでかなり差異を感じることがあって、その違いは面白いです。
石田 岸本さんは留学されたことはあるんでしょうか。
岸本 ないんです。
石田 翻訳家の方は帰国子女とか英語圏の大学を卒業したとか、勝手にそうしたイメージを持っていましたが、そうではないんですね。プロの方なので当然と言えば当然ですが、その文化圏に直に触れたことがないのにリアルに訳せるのはすごいと思います。
岸本 翻訳家で外国に住んだことがない人は意外とたくさんいる気がします。みんながみんな外国語がペラペラっていうわけでもないです。話すのと辞書を引きながら訳すのは異なる作業ですからね。もちろん両方できればそのほうがいいでしょうが、話せるからといって翻訳ができるわけではないし、逆もそうです。
編集部 石田さんはある媒体からエッセイの依頼を受けられたと伺いました。
岸本 何について書いてほしいという依頼なんでしょうか。
石田 お題はなく、二千字くらいでとご依頼がありました。
岸本 エッセイだと身構えると、みんなエッセイ脳になってしまって、ちょっと素敵なことを書かなきゃいけないと思いがちですよね。
石田 はい。自分の中では今正にそんなふうになっています。酒井順子さんや群ようこさんのような。
岸本 ぜひ石田さんの素全開で書いてほしいなあ。私はぜひそういうのを読みたいです。
石田 岸本さんのエッセイ集を拝読しました。電車の中で聞いた会話で子宮の真似をする、という話がツボに入り、半日くらい思い出し笑いが止まりませんでした。
岸本 あれは本当にそのままの話だったんです。言った本人に届いていればいいなと思います。
石田 またタイトルの話を訊いてしまうのですが、岸本さんはエッセイ集をまとめる際に、収録されているエッセイのタイトルの一つを、そのまま本のタイトルにされていますよね。『なんらかの事情』とか『ひみつのしつもん』とか。あれは直感やセンスで、これだ、と選ばれているのでしょうか。
岸本 そう訊かれると恥ずかしいです。最初に出したエッセイ集『気になる部分』では、何となく中のエッセイのタイトルから取りました。その次の『ねにもつタイプ』は、『気になる部分』とイントネーションを揃えたかっただけなんです。その次はもうどうしていいかわからなくて、装丁をしてくれたクラフト・エヴィング商會の二人に相談し、『なんらかの事情』がいいんじゃない、と言われて「なるほど!」とそれに決めました。だから意外といい加減。
石田 そう聞いてちょっと安心しました。
岸本 エッセイもフィクションで構わないんですよ。私もときどき「お前の書いていることは噓ばっかりだ」と批判されることがありますが、本当のことだと言い張ります。だって頭の中で起こっていることの実況中継だから。そういう意味ではどんなことを書いたって本当だと思っています。だから素敵なことよりも、溶接とか配管の話でいったほうがいいです。
石田 あまりに攻めたことを書いたらどうなるのでしょうか。
岸本 気にせず攻めていってください。怒られたら直せばいい、ぐらいの感じで(笑)。小説のほうは、次に書きたい作品や今書いているものはもうあるのでしょうか。
石田 今は会社員の話を一人称「私」で書いています。おじいさんが職場から迫害されて、それを助けようとする人の話です(笑)。自分の中にある引き出しが少ないので、これから増やしていきたいと思います。
岸本 それは長編ですか?
石田 百五十枚くらいだと思います。もっと少ないかもしれません。
岸本 書いた後、結構直しますか?
石田 直します。何でこんなに長いのかと、削ることが多いです
岸本 でも削れるってすごい才能ですよ。それも早く読みたいです。今からとても楽しみです。
(2021.12.27 神保町にて)
「すばる」2022年3月号転載
プロフィール
-
岸本 佐知子 (きしもと・さちこ)
神奈川生まれ。訳書にミランダ・ジュライ『最初の悪い男』、ルシア・ベルリン『掃除婦のための手引き書』、ショーン・タン『内なる町から来た話』など。著書に『なんらかの事情』『ひみつのしつもん』など。2007年『ねにもつタイプ』で第23回講談社エッセイ賞を受賞。
-
石田 夏穂 (いしだ・かほ)
1991年埼玉県生まれ。東京工業大学工学部卒。2021年「我が友、スミス」が第45回すばる文学賞佳作となり、デビュー。同作は第166回芥川龍之介賞候補にもなる。他の著書に『ケチる貴方』がある。
新着コンテンツ
-
連載2025年07月15日
 連載2025年07月15日
連載2025年07月15日【ネガティブ読書案内】
第44回 ホリコシさん
「10分遅刻して卒論を出せなかった時」
-
インタビュー・対談2025年07月08日
 インタビュー・対談2025年07月08日
インタビュー・対談2025年07月08日桜木柴乃「波風立てずに生きる器用さを、ちょっと残念だなと感じる大人に読んでほしい」
著者五十代の最後を飾る、集大成的な短編集である本作。仕事に対する現在の思いや、短編を書く面白さをうかがいました。
-
お知らせ2025年07月04日
 お知らせ2025年07月04日
お知らせ2025年07月04日すばる8月号、好評発売中です!
演劇界注目の劇作家・演出家ピンク地底人3号さんによる初の小説を掲載! 遠野遥さんの短期集中連載も最終回を迎えます。
-
インタビュー・対談2025年07月04日
 インタビュー・対談2025年07月04日
インタビュー・対談2025年07月04日石井遊佳×藤野可織「魂を自由にする虚構の力」
ホラー愛好家を自認する藤野さんは石井さんの新作に詰まった四つの物語をどう味わい、そこに何を見つけたのか。
-
新刊案内2025年07月04日
 新刊案内2025年07月04日
新刊案内2025年07月04日給水塔から見た虹は
窪美澄
2人の“こども”が少しずつ“おとな”になるひと夏を描いた、ほろ苦くも大きな感動を呼ぶ、ある青春の逃避行。
-
新刊案内2025年07月04日
 新刊案内2025年07月04日
新刊案内2025年07月04日青の純度
篠田節子
煌びやかな「バブル絵画」の裏に潜んだ底知れぬ闇に迫る、渾身のアート×ミステリー大長編!


