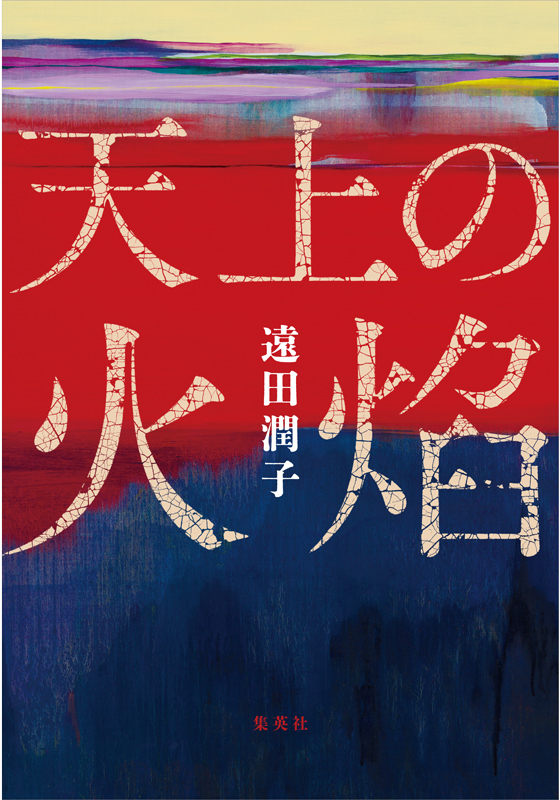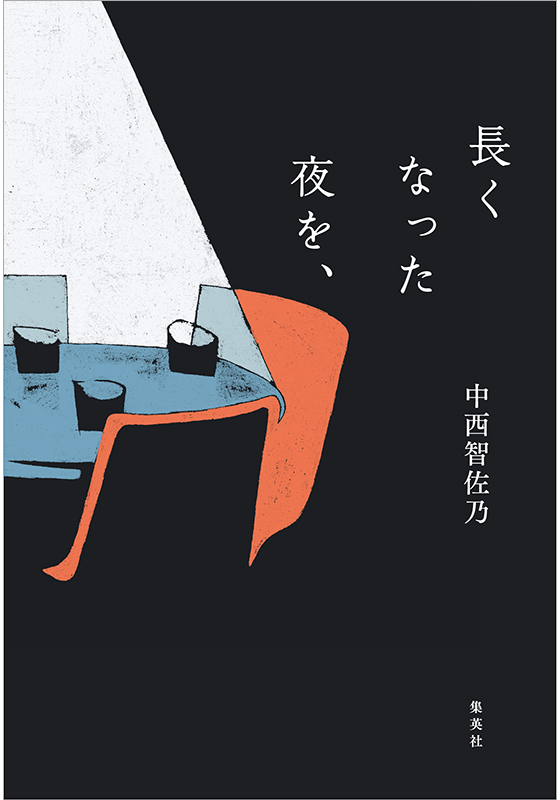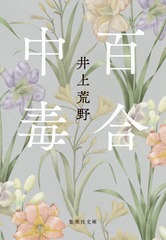『天上の火焰』刊行記念インタビュー 遠田潤子「家族の“業”に対峙する」

炎と土の芸術といわれる備前焼の里・伊部で、人間国宝である祖父の優しいぬくもりと、硬くて冷たい水のような父に挟まれて育った城。
作陶家として、家族として、三世代にわたり紡がれてきた“業”のありかを描き出す、最新刊『天上の火焰』。
作品を通じて、 遠田潤子さんが見つめたかったものとは?
構成/立花もも 撮影/露木聡子
踏みとどまる人を書きたかった
――遠田さんはこれまでも血縁のしがらみや家族のありかたをテーマに物語を描いてこられましたが、『天上の火焰』は、とくに二〇二二年に刊行された『人でなしの櫻』と対になる作品なのでは、と感じました。どちらも父と息子の関係性と、芸術家としての業の深さを重ねて描かれています。
遠田 まさに、今作を書くうえでは『人でなしの櫻』で描いたことが念頭にありました。あの作品では、物語冒頭ですでに父親が亡くなっていて、和解の手立てを見つけられないまま、息子である主人公も越えてはならぬ一線を越えていってしまうのですが、『天上の火焰』では業の深さゆえに生まれた心の歪みを加速させるのではなく、現実に向き合うことで、どうにか踏みとどまる人の姿を描いてみたいと思ったんです。
でも、書きはじめてすぐ、それがどんなに難しいことかを思い知りました。恨みのアクセルを踏んで、とことんまでいってしまうほうが、ずっとラクだったんだと。
――主人公の城は、生まれてすぐに母を亡くし、父からはその思い出を語り合うどころか、ろくに話しかけてももらえず、愛されていないことを実感する日々。父と不仲の祖父にかわいがられ、ますます父との距離が開いていくことに葛藤し続けています。城のキャラクターは、どのように生まれたのでしょうか。
遠田 いわゆる“いい子”にはしたくないと思っていました。備前焼の人間国宝である路傍を祖父にもち、地元の伊部ではいちばん大きな窯元に生まれた城は、いってしまえばヒエラルキーのトップにいる存在。実際、人間国宝を輩出した窯元へ取材でお邪魔したら、ご自宅は立派だし、敷地に一歩足を踏み入れるだけで圧を感じるほど威厳があって。冒頭で、路傍のドキュメンタリーを撮るため、ロケ隊が出入りする場面を書きましたけど、子どもの頃から、芸能人が家を訪ねてくるのもあたりまえの家庭で、いちばん権威のある路傍に溺愛されて育てば、多少甘えたところがあって当然かなと。ところが書きはじめてみたら、想像していた以上にダメダメのぐにゃぐにゃの子になってしまって、どうしたものかと戸惑いました。
――轆轤もぐにゃぐにゃ、お点前もぐにゃぐにゃ。でも、なんでも吸収していく柔らかい手をもっている。それが城の魅力でもあり弱点でもあると、路傍と茶道のお師匠さんが笑う場面がありました。
遠田 はたから見ていて情けないと思われるようなところがあったり、悩んでいるときにまわりを気遣う余裕をなくして、大事な人を傷つけてしまったり。そういう、人のダメな部分をきちんと描きたいと思ったのですが、あまりの迷走ぶりに、書きながら「もうちょっとしゃっきりしようよ」と言いたくなりました(笑)。
――思いがけず祖父を亡くし、祖母と父との三人暮らしになってからの城は、どんどん鬱屈していきます。お師匠さんに芯のない“ふにゃふにゃ”になってしまったと言われるほど。
遠田 五重塔が地震で揺れても倒れないのは、中心に心柱があって、むしろ揺れることで衝撃を分散させているから。支えるものがなくなれば、かたちを保っていられず、崩れ落ちるだけ。その違いを“ぐにゃぐにゃ”と“ふにゃふにゃ”で表現したのはただの思いつきですが、芯を失うほど己を見失いかけた状態から立ち直っていく城の姿こそが、私が最初に描きたいと思った、現実に踏みとどまるということなのかなと書きながら感じていました。
備前焼に魅せられて
――その舞台に備前焼の窯元を選んだのはなぜだったのでしょう。『人でなしの櫻』にも備前焼に関する記述があるので、思い入れが深いのかなと思ったのですが……。
遠田 旅行で訪れた伊部で、はじめて備前焼に触れたとき、衝撃を受けたんですよ。私の母は能登の生まれなので、自宅にある食器は輪島塗や九谷焼が多かったんです。それ以外も、有田や伊万里、ヨーロッパの磁器といった、つるつるとした絢爛豪華な器ばかり。土を焼いた器になじみがなかったので、備前焼の放つ得も言われぬ迫力に圧倒されてしまったんです。すべてを振り捨てて堂々と土臭さだけで勝負するような覚悟が感じられた。きれいというよりは、強い。それこそが王者のプライドであるような気がして、物語にしたいと思ったんです。
それに、窯元はたいてい代々受け継がれるものなので、いつか家族の年代記を書きたいと思っていた私には、うってつけのモチーフでもありました。というわけで、今作は満を持してということになるのですが、実をいうと、書きはじめてすぐ、後悔しました。まずは陶芸を知るところから始めようと近所の教室に通ってみたら、想像以上に難しくて。
――轆轤、まわされたんですか。
遠田 まわしました。なんとか十数回のコースを満了しましたが、後日送られてきた、最終制作として焼いた作品があまりに不細工で、見た瞬間にこんなものはいらないと捨ててしまったくらい。
――はじめて焼いた器を「なんの価値もない」と全部割ったという、城の父・天河に通じるところがありますね(笑)。
遠田 もともと手先の細かい作業は得意じゃないけど、こんなにも不器用で、果たして備前焼の小説なんて書けるだろうかと不安になりました。でも、私が書きたいのは芸術のなんたるかではなく、芸術とともに生きている人たちの営みなんですよね。窯焚き(作品を窯に入れて高温で焼きあげること)の炎はただ備前焼を完成させるために燃えているのではなく、その隣であたりまえのように焼き芋をつくる姿があるように、生活に根差した存在なんだということを描きたかったんです。
――窯の横に芋を置いておくと勝手にできあがる焼き芋は、炎のあたたかさとともに、城にとっては路傍との大切な思い出であると描かれます。本当に、みなさん焼いているんですね。
遠田 そうなんです。とても印象的だったので、エピソードとして使わせていただきました。人間国宝である路傍も、一見特殊な存在だけど、城にとっては優しい祖父でしかなく、天河にとっては過去のわだかまりを溶かすことができない父親。どんなに立派な芸術も、しょせんは人の手で生み出されたものにすぎず、家族との関係は、他の人と同じようにままならないことだらけなんだということを、描けたらいいなと思いました。
――城にとって、路傍は安心基地のような存在でしたが、路傍の妻の良子や、息子の天河にとってはそうではなかった。家族のままならなさは、路傍の死後、徐々に明らかになっていきます。
遠田 才能にも意欲にも恵まれた、路傍のように天真爛漫な人の近くにいるのは、本当に大変なことなんじゃないでしょうか。陰ひなたなく支え続けた良子はもちろん、物心ついたころから跡を継ぐ以外に将来の選択肢はないとされてきた天河は、どれほどつらかっただろうかと思います。
路傍との対比を強めるためにも、天河は窯の人とは対照的な冷たさを持つ存在として描くことにしました。炎に対するのは、やはり水。伊部は山間の小さな町なので、流れる不老川以外に水の気配なんてどこにもないのですが、地図を見れば、山を越えたすぐそこに海があることがわかる。ああ、これはいいな、と思いました。この海を天河のイメージにしよう、と。
――それで、天河のことを冒頭から〈見えない海を孤独な舟で進んでいく〉人だと表現していたんですね。ためらいなく周囲を巻き込んで、ときに振り回しながら我が道を進み続けた路傍との違いをあらわす表現でもあるなと思いました。
遠田 人としてだけでなく、作陶家としての質も、路傍と天河は異なるどころか、決定的に相容れない。才能とは、あってもなくても苦しいものだなあ、と思います。私は作家として、ずっと才能がほしくてたまらなかった。今も、もっと自分に才能があればと願い続けています。でも、轆轤の名人として他に類を見ないと称される天河は、心の底から路傍に認められることはなく、めざす境地にたどりつけず、焼いた器を割り続けている。そこにもまた果てのない苦しみがあるのだろう、と思います。きっと才能というのは一種類でなく、人それぞれに開花するものと決して手に入れられないものがあり、才能の数だけ苦しみの数もあるのだろう、とも。
――路傍ですら、納得のいく骨壺をつくるため、毎年、作品を壊し続けていた。どんなに頂点を極めたように見える人にも、たどりつけない場所がある。理想を追い求めて手を伸ばし続けるのだと、さまざまな登場人物を通じて描かれる姿に、胸が詰まりました。
遠田 作中には物原という小高い山が登場します。大量の焼き損じを捨てるうちに山となった、器の墓場。初めて訪れた伊部を歩き回るうち、物原にたどりついてその情景を目の当たりにしたときは、本当に嬉しかったですね。物語の核となるものを見つけられたような気がして……。才能があろうとなかろうと、誰にだって成し遂げたい何かがあって、何者かになりたいという欲がある。承認欲求とひとくくりにして軽んじるのは簡単だけど、どうしても捨て去ることができないその欲にもがきながら、人は死ぬまで生きていくしかない。それは芸術家であろうとなかろうと変わらないのではないかという想いを、城と路傍が物原に立つ場面にはこめています。
――その欲を、作中では〈餓鬼〉とも表現していますね。もっと好かれたい、もっと褒められたい。キリのない「もっと」に飢えている餓鬼を、私たちは腹の中に飼っている。飼いならせなくなったとき、餓鬼は私たち自身を食い始めるのだと、路傍が語る場面もありました。
遠田 心の中に鬼がいる、という表現をよく聞きますが、ちょっとカッコよすぎますよね。それよりも、どれだけ与えられても満ち足りない餓鬼のほうが合っている。そしてそれは、親子の関係に重なる部分がある気もします。親が憎くて恨み続けるのも、毒親だと断じるのも簡単だけど、それもまたやっぱりキリがない。キリがないことを重ねたまま、行きつくところまで行ってしまったのが『人でなしの櫻』だったので、今作では、どうすればその連鎖を断ち切れるだろうかと考え続けていました。城が一人、気持ちに区切りをつけて立ち直るだけでなく、家族全体が再生に向かって歩んでいける物語になればいいな、と。

なぜ父と息子なのか
――そもそも、遠田さんはなぜ「家族の物語」にこだわるのでしょう。
遠田 私自身、両親との関係がよくなくて、最期まで和解することなく……というか、和解するつもりもないまま、二人を見送りました。そして今、もうすぐ六十歳になろうというのに引きずっているわだかまりを解消するため、小説を利用しているところがあります。一種のリハビリみたいなものだから、作品ごとに異なる角度から描くことに挑まなくては、意味がないんですよ。いわゆる毒親と呼ばれる人たちに対する許せなさを発散し続けるだけでは、どこにも出口を見つけられない。積極的に書きたいと思わないからこそ、親子の和解というテーマに向き合ってみることが作家としては必要で、物語のなかではきちんとそれを成し遂げられるようになりたいと思って、今作を書きはじめました。
――父と息子という男性同士の関係を描くことが多いのは、どうしてですか。
遠田 私の父は子どもっぽいところがある人で、母に比べると親になりきれていなかったように思えるんですよ。私には娘が二人いますが、よほどの事情がない限り、女性は妊娠したら産むことになる。どんどん大きくなっていくお腹とともに日々を送るのに対し、男性は生まれるまで実感がないまま。もしかしたら生まれてなお、実感は薄いままかもしれない。そのしわ寄せを食う子どもはたまったもんじゃないし、城が天河から受けた仕打ちはとうてい許すことができないものだと思うのですが、天河の過去を描いたことで、少しずつ城のなかに、許すか許さないかはさておき、もっとお父さんのことを知ろう、知りたいという気持ちが芽生えてきた。
これは、私にとって一つの成長といえますね。これまでは、親の過去なんて知りたくもないと頭から拒絶していたし、知ったうえで理解することを押しつけられるのもごめんだった。だけどもし、少しでも知りたいと自分から思えるのであれば、それもありかもしれない。私なりに両親のことを受け入れてもいいのかもしれないと、今作を書いたことで思えるようになったんです。私自身が、城よりも天河のほうの心情に寄り添いやすい年齢になった、ということも大きいかもしれません。
――城と天河の関係には、天河と路傍の関係が影響していて、路傍にもまたその父との確執があったと、物語を追ううちにわかっていきます。いったいどこまでさかのぼれば、どの段階で歪みが解消されていれば、問題は起きなかったのだろうと考えると、家族というものの業の深さに、途方に暮れてしまいますね。
遠田 私は祖父母との縁も薄く、顔も知らない祖父は聞く限りではずいぶんとひどい人だったようなので、両親もいろいろ大変だったんだろうなとは思うんですけどね。でも、さかのぼれば延々と続くわだかまりの連鎖を、私が食い止められているかというと、そうとは断言できない。娘にとっては毒と感じられる部分があるかもしれないし、今はまだわかりやすく発露していなくても、私から受けた何かしらの影響で、娘が次の世代に引き継いでしまうことがないとも言い切れない。この途方に暮れてしまいそうになるほど深い業の流れに興味があるので、きっとまだまだ、そういう小説を書き続けていくと思います。

ありふれた悲劇を描き続ける
――食い止めるのは、もしかしたら家族じゃないのかもしれないな、とも思います。本作でいうと、ドキュメンタリー取材のために路傍に密着していた兵 藤さん。彼は折に触れて、城に厳しくもあたたかい助言をくれますよね。彼の存在がなかったら、家族だけに向き合っていたら、城は変わらなかったかもしれない。
遠田 兵藤さんは、お気に入りの人物です。勝手に、津田健次郎さんみたいな声だと設定しているんですけど(笑)、いい人ですよね。城にとっては父親代わりで、他人だけど甘えられる存在で。あまりにいいことを言いすぎる、クサいキャラになっちゃったかもしれないなというのが唯一の心残りです。
――むしろ、大事なことは全部兵藤さんの言葉である、というのはリアルだと思いました。家族には面と向かって「いいこと」って言えないじゃないですか。説教だと思われたり、お前に言われたくないと素直に聞いてもらえなかったり。他人だからこそ、まっすぐすぎる言葉も届く、ということがあるよなあ、と彼と城との対話を読みながら感じました。
遠田 確かに。そう思うと、つくづく家族というのは不思議なものですね。なぜ、たまたま血がつながっているというだけで、あんなにも密接に暮らし、わかりあえると思っているのだろう。城が香月に出会ったように、恋人のほうがよほど、心の深い部分で通じ合い、愛し合うことができるのに。
――でも、恋人は距離が近づきすぎると、また違う関係のいびつさが生まれたりしますよね。幼なじみの香月に対する城の態度も、なかなかのものでした。
遠田 ふにゃふにゃでしたから(笑)。どうすれば、主人公として嫌われない程度に迷走できるかというのも、今作では悩みどころの一つでしたが……彼は決して言ってはいけないことを言ってしまった。人は自分に対して誠実でいられなくなると、他人のことも傷つけてしまうんだろうなあ、と思いました。祖父の死、そして父との確執という苦しみを抱えながらも、城はまっすぐ前を向いているつもりだった。だけど、自分の苦しみの根源はなにか、客観的にとらえることもできず、ただ痛みをごまかしてがむしゃらに突き進む先は、決して「前」とは言えない。その結果、いちばん大事にしなくちゃいけない人を傷つけてしまった。香月は香月で、そんな城を支えることで自分の居場所を得ようとしていたから、お互い様のところはありますけどね。そう思うとやっぱり、兵藤さんがいちばんの善人ですね。彼には、すこやかに幸せになってほしい(笑)。
――でもきっと、彼には彼の迷いと苦しみがあるんだろうなあ、と想像させられるのも今作の魅力です。〈ありふれた悲劇〉という言葉も出てきましたが、誰もが唯一無二の地獄を生き抜きながら、それをたいしたことではないと自分に言い聞かせているのだろうと思わされる。
遠田 ありふれた悲劇。我ながら、きつい言葉を書いたなと思います。その言葉を発した人の経験した地獄は、とうてい「ありふれた」なんて言えるものではないけれど、その人だけが特別だったわけではないというのも事実。当人以外は簡単に忘れてしまうということも、また。
だからこそ私は、物語を書き続けなくてはいけないのだとも思うんです。ありふれているからといって、悲劇をなかったことにしないために。特別じゃないからといって、痛みや苦しみがたいしたことないなんて言わせないために。そこに生きている人たちの営みを丁寧に重ねながら小説を書いていきたいと思います。
――そうした気づきを経て、新たに書いてみたいテーマはありますか。
遠田 北杜夫さんの『楡家の人びと』のような、もっと長大な家族の年代記にはいずれ挑戦したいと思っています。あとは、家庭内の殺人。それこそ、割合でいうと一番ありふれているはずなのに、特別視されがちなそのテーマにも挑みながら、私なりに家族とは何か、その業の深さを見つめ続けていくつもりです。
プロフィール
-
遠田 潤子 (とおだ・じゅんこ)
1966年大阪府生まれ。関西大学文学部独逸文学科卒業。2009年「月桃夜」で第21回日本ファンタジーノベル大賞を受賞しデビュー。2012年『アンチェルの蝶』が第15回大藪春彦賞候補に。2019年『ドライブインまほろば』が第22回大藪春彦賞候補、2020年『銀花の蔵』が第163回直木賞候補となった。他の著書に『雪の鉄樹』『オブリヴィオン』『冬雷』『蓮の数式』『廃墟の白墨』『雨の中の涙のように』などがある。
新着コンテンツ
-
新刊案内2026年01月07日
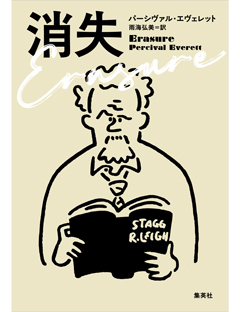 新刊案内2026年01月07日
新刊案内2026年01月07日消失
パーシヴァル・エヴェレット 訳/雨海弘美
文学を志向する作家が、別名で低俗に振り切った中編小説を書くのだが……。アカデミー賞脚色賞受賞映画〈アメリカン・フィクション〉原作。
-
インタビュー・対談2026年01月07日
 インタビュー・対談2026年01月07日
インタビュー・対談2026年01月07日ピンク地底人3号「「わしのこと以外、書くことなんてないやろ」圧倒的な暴力と不条理の果てに見える世界」
小説デビュー作が野間文芸新人賞を受賞した、今注目の作家であるピンク地底人3号さんの不思議な魅力に迫る。
-
新刊案内2026年01月07日
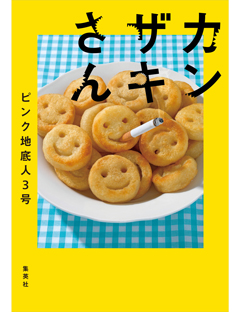 新刊案内2026年01月07日
新刊案内2026年01月07日カンザキさん
ピンク地底人3号
圧倒的な暴力と不条理の果てに、見えてくる戦慄の光景。注目の劇作家による初小説!第47回野間文芸新人賞受賞作。
-
お知らせ2026年01月06日
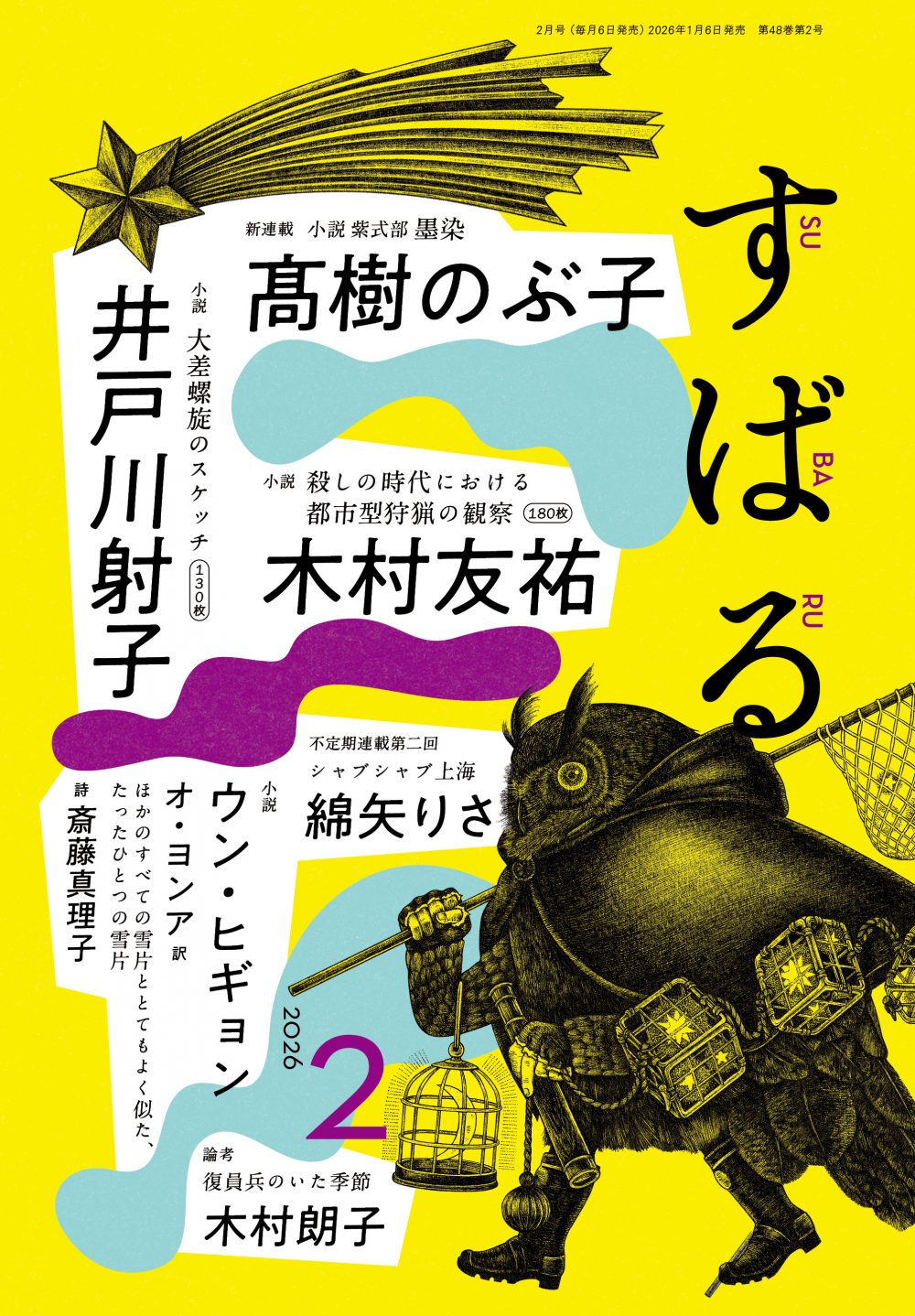 お知らせ2026年01月06日
お知らせ2026年01月06日すばる2月号、好評発売中です!
髙樹のぶ子さん待望の新連載は紫式部がテーマ。韓国文学界で活躍を続けるウン・ヒギョンさんの短編も必読です。
-
お知らせ2025年12月26日
 お知らせ2025年12月26日
お知らせ2025年12月26日2025年度 集英社出版四賞 贈賞式 選考委員講評と受賞者の言葉
本年も集英社出版四賞の贈賞式が執り行われました。喜びと激賞の言葉の一部を抜粋してお届けします。
-
お知らせ2025年12月24日
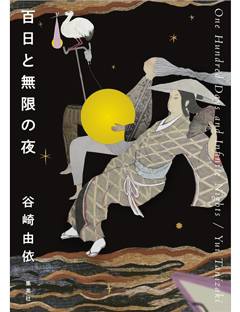 お知らせ2025年12月24日
お知らせ2025年12月24日谷崎由依さん『百日と無限の夜』が織田作之助を受賞!
谷崎由依さんの『百日と無限の夜』が第42回織田作之助賞に決定しました!