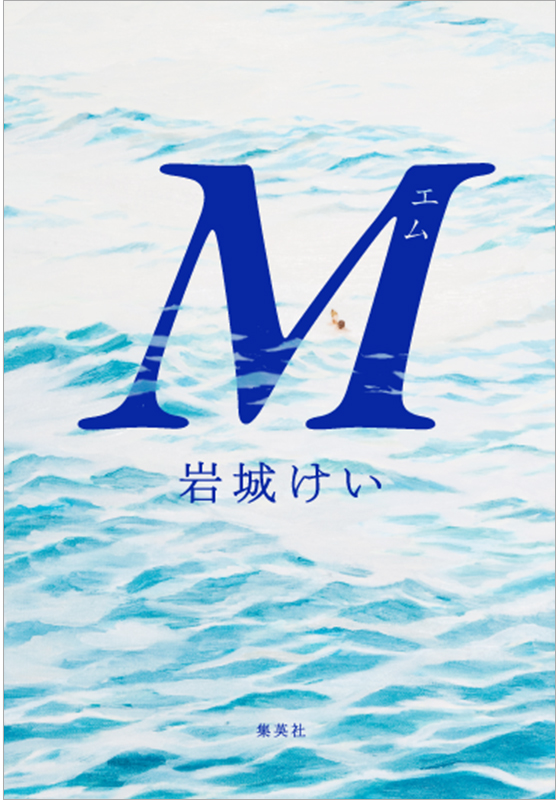『続きと始まり』刊行記念対談 柴崎友香×斎藤真理子「終わらない“続き”を生きていく」

斎藤 柴崎さんとお会いするのは初めてですが、ずっと作品は読んでいました。パク・ソルメさんの短篇集『もう死んでいる十二人の女たちと』が出た時は、書評を書いてくださいましたよね。すごくありがたかったです。
柴崎 私も斎藤さんが翻訳された小説は読んでいました。パクさんの短篇集はすごく好きで、新刊『未来散歩練習』も読みましたが、過去と現在と未来を今この場所から重ね合わせて見るところが、自分と近い感覚の人なんじゃないかなと感じます。
斎藤 『未来散歩練習』はコロナ禍の時に書かれていたものなので、柴崎さんの『続きと始まり』と地続きな感じがしますね。
『続きと始まり』は二〇二〇年の三月から二〇二二年の二月の間の、三人の人物の日常が交替で二か月おきに書かれていく。一か月おきだとそんなに変化がないから、二か月おきというのがいいですよね。あの時期にいろいろな人が思っただろう気持ちが瑞々しく描かれているなと思いました。
柴崎 ありがとうございます。この小説を書こうと思ったのは二〇二一年の前半で、コロナ禍の状況を書こうと思いました。その時はまだまだ渦中で、この先どうなるか分からない状態だったんですけれど。
コロナ禍の最初の頃って、小説やドラマにその設定をどのくらい入れるかどうか、みなさん悩んだと思うんです。私も当時、他の作家さんとそういう話をしたことがありました。ただ、私は身近な生活から書いていくことが多いので、避けては通れない部分がありました。一年以上経っても世界中が困難な状況に直面したままで、それをない設定で書くのは自分の小説では難しい、だったらもう、正面から、この時間自体を書こうと思ったんです。
でも最初は、連載が終わる頃にはもっと落ち着いているだろうと思っていたんですよね。そもそもコロナ禍元年の二〇二〇年の最初くらいには、この夏が終わればある程度終息しているだろう、みたいな感覚もありましたよね。
斎藤 そうなんですよ。その後も、年末にはみんなワクチンを打って飲みに行けるとか言っていましたよね。ワクチンを受けられるのがあんなに遅くなるなんて思っていなくて。
私は三年日記を書いているんですが、『続きと始まり』を読みながら、作中と同じ時期の日記を見返したんですよ。やっぱり自分も登場人物と同じようなことを書いていました。二〇二〇年の五月の小坂圭太郎さんの章で、緊急事態宣言が前倒しで解除されますよね。私もその頃、友達とメールで、「いつの間にか終わっているって感覚が不思議だね」と話し合っていたりしていたんです。そういうことと重ね合わせながら読むと、本当に不思議な時期があったんだなと、しみじみと感じるというか。
柴崎 斎藤さんとくぼたのぞみさんの往復書簡集『曇る眼鏡を拭きながら』の中で、斎藤さんは日記からメモまでいろいろな記録をつけていると書いてましたよね。私は全然日記をつけていないんですが、あれを読んで、私もちゃんと書いておけばよかったなと思いました。
今回の小説を書く時も、手帳とか、スマホで撮った写真とか、友達とのメールとか、新聞やニュースのアーカイブを見て思い出していきましたが、自分の実感としての記憶がすごく曖昧になっていて。
斎藤 分かります。二〇二〇年はやっぱりコロナ元年だから憶えているんです。二〇二二年は去年だから、なんとなく憶えている。でも二〇二一年になると、結構大変だったはずなんですけれど記憶が圧縮されて干物みたいになっていて。
柴崎 干物(笑)。
斎藤 『続きと始まり』を読んで、干物に水がかけられて元に戻った感覚になりました(笑)。一人暮らしで一年間、ほとんど出かけず、人に会わずにいると記憶って混乱するものなんだなと思いましたね。
柴崎 やっぱり人に会って話したりすると記憶ってある程度整理されますね。自分たちの生活は、節目っていうほど意識していない節目があるから、時間的に整理されていたんだなと思いました。
書き始める前に、出版された日記や特集企画なども読んでいつなにがあったか確認していたんですが、コロナ禍の最初の何か月かの日記は結構あるんですけれど、その後がほとんどなくて。それこそ干物みたいになっている二〇二一年くらいのことが知りたいんだけどな、と思っていました。
斎藤 自分の三年日記も、二〇二〇年は出来事と心情の両方がいろいろ書いてあるんです。二〇二一年になると、心情があまり書いていなくて、時々気を取り直してコロナについての気持ちを書いておこうとしているのがありありと分かるんですよ(笑)。コロナとちょっと距離ができている感じが読み取れて。
柴崎 制限がある状態に慣れてそれがデフォルト的になると、そこの部分をわざわざ記録しておかなくなる気がします。それよりも自分の生活だったり、仕事だったりが前に出てくるのかな、って。
斎藤 そうですね。
柴崎 今もまだ、コロナに関することが終わったわけではまったくないんですけれど。
斎藤 でも、かなり気分は変わりましたよね。
柴崎 いろんなところに移動したり人に会ったりはできるようになりましたよね。そうしたら急激に二〇二三年の始めくらいまでのことが忘れられていくというか。二〇二〇年から二二年の三年間は、それこそ一年分くらいに記憶が圧縮されていますよね。
斎藤 圧迫骨折ってあるじゃないですか。転倒も転落もしてないのに、骨がいつの間にかすかすかになって折れるっていう。あの三年間は、圧迫骨折したような、不思議な時期だったと思います。私たち、これから死ぬまで、あの時期は変だったねって言い続けるんでしょうね。作家のお仕事というのは、そういう形で流れていってしまうものに一本杭を打ってくれる。すごく貴重なことです。
柴崎 連載は二〇二二年の始めから二〇二三年の始めまでだったんですよね。小説内の現在進行形からはちょっとずれていますけれど、まだまだ先が分からなくて、本が出る時の世の中の状態によって読まれ方も違ってくるだろうから、どうなるのかなと思っていました。でも、今の時期に単行本になってよかった気がします。その時期の感覚を自分自身も急激に忘れていっているので、書いたことに意味があったかなと。
斎藤 意味、ありますよ。
柴崎 小説ってすぐには書けないし、時間がかかるものだと思うんです。今はインターネットがあるから、強い言葉がぱっと広がって、でも、その分すぐ忘れられてしまう時もある。即時的な言葉に助けられることももちろんあるんですけれど……。でも、すごく時間がかかることによって書けることがあるし、伝えられることもあるんじゃないかとは思います。
斎藤 そう思います。読んでいる間、自分が今までに行った場所や経験した時間がせりあがってくる思いが何度かありました。三人それぞれの心情が語られていきますが、ものすごく自分と近しい感じがしました。
柴崎 これまでも三人や複数の視点というのは何回か書いてきたんですが、ここ何年か、今の世界の複雑さを書くには、一人のストレートな視点だけで書くのは難しい、かといって客観的な視点があるわけではなくて、一人から見た不完全な世界を重ねていくしかないんじゃないかと考えていて、それでこれも三人の視点にしました。
斎藤 一人一人の置かれている状況とか、経歴とか、家族関係とか、すごく丁寧に作りこまれていますよね。みんな、本当にいそうな人たちでした。
柴崎 今まで人から聞いた話などが熟成して形になっていく感じですね。
斎藤 私は前から、柴崎さんの小説の、ちょっと内省的な人がいろいろ考えている描写がむちゃくちゃ好きなんですけれども、その感じが、今回のこの三人にも強くありました。
柴崎 登場人物たちって、書いているうちにどんどん“存在していく”というか。どういう人生を生きてきて、今こういう生活をしている、というのは書く前にかなり詳細に考えるんですけれど、それでもやっぱり、その人がどういうふうに感じて考えるかは、書いていく中で分かってくるところがあります。
斎藤 私、ファン・ジョンウンという作家が好きなんですけれど、ファンさんが以前言っていたのが、自分はその人物たちのことを知っているから書くんじゃなくて、彼らのことが気になるので書く、って。
柴崎 すごく分かります。私も、自分でこういう人だと決めて書いているわけではなくて、書いているうちにだんだんその人のことが分かってくるんです。分かってきた時に「おおっ」となります。自分の最初の想定を超えてくれるような瞬間があると「あ、この小説はちゃんと成り立っているな」と思えます。今回、だいたい二年間くらいの間の話なので、登場人物たちそれぞれの仕事や家族の状況にこんな変化がある、くらいは考えていたんですけれど、その時々で彼らがどう思うかは、書き始めた時には分かっていませんでした。
斎藤 視点人物は、滋賀県で夫と二人の子供と暮らしている優子さん、妻と一緒に幼い子供を育てていて、コロナの影響で休業中の圭太郎さん、フリーの写真家のれいさん。状況も仕事も年齢も違う三人ですね。
柴崎 コロナ禍のなかで個人個人の仕事や働き方、生活が大きく影響を受けたのでそこを書こうと思いました。もちろん、登場人物たちとはまったく違う状況だった人も多いだろうし、書いているのは全体ではなくて、一部分だけなんだとは常に意識しなければなりませんが。コロナ禍ではリモートワークできる人と、出勤しないといけない人でも全然違いましたよね。家族構成とか、家に個室があるのかなどでも大きな差があって。
斎藤 状況の違う人のことがなかなかお互い理解できないような時期でしたよね。格差と言っていいと思うんです。こういうときに本当に格差が表に出るんだな、と。戦争の時もそうなるんだろうなと思いました。
柴崎 やっぱり何かあった時に、どこか違うところに避難できる人と、そこを動けない人もいるし。
斎藤 コロナによって、改めて自分がどうしてここにいて、この仕事をして、この人と一緒に暮らすようになったかというのを、確認した人も多かったと思いますね。
柴崎 そうだと思います。
斎藤 私、圭太郎さん一家は、読んでいてすごく楽な感じがしたんですね。彼らは子供を育てるためのユニットみたいな感じで一緒に暮らし始めたわけですよね。二人の間に圧があまりないところがいいなと思いました。
柴崎 今の社会って、恋愛と結婚と子育てがあまりにもセットになりすぎていますよね。愛し合って、結婚して、家族みんな仲良くというイメージが前提になりすぎているので、そこに当てはまらない家族や関係性も現実には多く存在するのに、と。それで、予想外に“家族”となった彼らを書こうと。
斎藤 いいですよね。そんな彼らの会話もとてもよかったんですよ。圭太郎さんは中学生の頃、父親が韓国人だという同級生、中村さんについて無神経なことをしてしまった。今でも彼はそれを気にしていて、それを妻の貴美子さんに話しますよね。その時に貴美子さんが「言ってしまったことは、消せないよね」って言う。あそこがすごくよくて。圭太郎さんは慰めるようなこと言ってくれるのを期待していたけれど、貴美子さんは言わなかった。それで彼は、やっぱりあれは駄目な行為だったって思うわけじゃないですか。ああいう過程がひとつひとつ、すごく、「今」だなと思いました。いろんな出来事、いろんな葛藤を通過してきた「今」だから、こういう会話が活字で読めるようになったなと思ったんです。圭太郎さんがやったこと、あれはアウティングってことですよね。
柴崎 そうですね。
斎藤 アウティングという言葉が使われるようになって、そういうことはいけないと認識されるようになったのは最近ですが、そういう言葉がなくても、そもそもやっちゃいけないことですよね。
柴崎 言葉が使われるようになって私も明確に意識できるようになりました。その内容がどんなふうに思われているかなどに関係なく、自分ではない人のことを、その人の了承を得ずに勝手に他の人に言ったりするのはやってはいけない。
斎藤 小説の中では、中村さんが本当はどう思っていたのかは書いていない。そのことにも、すごく安心しました。
柴崎 分かるようにはしたくなかったんですよ。もし貴美子に「それはしょうがなかったよ」とか「私は気持ちが分かるよ」みたいに言われて圭太郎が慰められたとしても、中村さん本人がどう思っていたのかは結局分からないし、それはどうすることもできないですよね。本人を探し出して謝ったらいいかというと、相手は今さらそんなことをしてほしくないかもしれないし、謝られた側はなにか反応を返さないといけなくなるなど負担をかけることもあるということも含めて、特に時間が経ってしまったことって、自分が何をしたのかということ自体をまず受け止めるしかないんじゃないかと思っていて。その行為の主体は自分だという責任というか。
斎藤 柴崎さんの小説の強さって、そういうところにありますよね。物語って、何かしらが分かって決着がつく形になりがちだけれど、柴崎さんは分からないままにする。駄目だったということを、空き地のままで置いておくというのは、すごく強いと思います。そういうところが好きです。
柴崎 分かったつもりにならないようにしよう、というのは自分の中にすごくあります。結局のところ、そんなに都合よく何か分かったり見つかったりなんてしないですよね。しないからこそ、自分自身で受け止めるしかない。
特に相手があることに対して、勝手なストーリーにまとめたくないというのがあります。「それも意味があった」みたいに納得できるものを用意すると、そこでまとまって終わってしまう気がします。でもそこはやっぱり、終わらせられないというか。自分自身の中にも、終わらない、わからないからこそ考え続けるみたいなところがあります。
斎藤 後半になって、圭太郎さんをはじめ私の好きな内省的な人たちが、それぞれにとってのポイントを見つけるところまで行きますね。優子さんはちゃんと社長に自分が思っていることを伝えるし、圭太郎さんは妻の貴美子さんとの出会いについて自分がどう思っているのかに気づいたりして。そういう三人の様子にすごく安心しました。
柴崎 そこも、書いているうちにそういうふうになってきました。
斎藤 私、連載の最終回を読んだ時に、思わずXに感想を書いたんですよね。れいさんの、〈なんとなく世の中は少しずつよくなっていくのだと思っていた。〉という言葉を引用して。あの言葉は、本当に私もそう思っていたんですよね。
コロナになる前、在日韓国人の知人とお酒を飲んでいて、ベルリンの壁崩壊のころの話になった時に「もうちょっと世界はよくなると思っていたよね」と言ったら、相手に「本当にそうだよね」って言われたことを思い出しました。私たちの世代から見ると、七〇年代は在日韓国人への差別は本当にひどかった。八〇年代に本名宣言というのが始まって、韓国人の子供たちが本名で学校に通うことを始めているんですけれど。
柴崎 私が高校一年生の時に、三年生の人が本名で通うと宣言をして、テレビのドキュメンタリー番組に取材されていました。八九年でした。高校に入学したばかりの私にとって印象深い出来事で、その時は、これからは差別はなくなっていく、状況は変わっていくんだと感じていました。
斎藤 私もそう思ったんです。でも、そうではなかったですね。
柴崎 あの時のXの斎藤さんのコメントを読んでから、自分でももう少し考えてみたんです。それこそ八九年にはベルリンの壁が崩壊して冷戦が終結に向かい、九三年にはオスロ合意でPLOのアラファト議長とイスラエルの首相が握手する姿が大々的に報道されて……。
斎藤 九〇年には南アでもネルソン・マンデラが釈放されましたしね。そうやって、世界のいろいろな争いが、一応静かになると思いましたよね。
柴崎 そうですよね。九〇年代はこれから差別や争いみたいなことは終わって世の中はよくなっていく、みたいな雰囲気がありましたよね。今になってみれば、私にはわかっていなかった、見えていなかったこともたくさんあるわけですが。そしてその「よくなっていく」「よくなってきた」という状態までに、どれだけ苦しい思いをしてきた人たちがいたか、戦ってきた人たちがいたかをよく分かっていなかったと実感するようになりました。ブラック・ライヴズ・マター運動が起きた時に関連する本を読んだり映画を見たりしたなかで、公民権運動の行進に参加していた人たちがセルマで警官隊にひどい暴力を受けた血の日曜日事件を描いた『グローリー 明日への行進』という映画も見たんです。行進、マーチという言葉から全然想像がつかないくらい激しい暴力とそれに対する抵抗が描かれていて。
もちろんアメリカで黒人が差別されてきた歴史は知っていましたが、運動していた人の家族が殺されたり行進しているだけでこれほどの暴力を受けたことははっきり認識していなかった。中学校の英語の教科書に載っていたキング牧師の「I have a dream」という演説の、あのドリームという言葉に対する現実を自分は明確には理解していなかったと愕然としました。九〇年代、なんとなく世の中はよくなっていくんだと思っていたし、「昔よりよくなってきた」と言ってしまったりするけど、勝手によくなってきたのではなく、よくしてきた人がいるんだということを、やっと、はっきりと実感として分かってきました。そこは単行本にする時に書き足しました。

斎藤 今回、小説内でポーランドの詩人、シンボルスカの詩をいくつか引用されていますよね。前からお好きなんですか。
柴崎 シンボルスカは、デビュー作の『きょうのできごと』が映画になる時に、監督の行定勲さんからいただいたメールに書かれてあったので知りました。こういう映画にしたい、と書かれた文面の中に、今回作中で圭太郎が読むシンボルスカの「一目惚れ」という詩があったんです。行定さんが『きょうのできごと』を読んだ時にその詩を思い出して、こういうことを考えた、といったことが書かれていました。それでシンボルスカの詩集『終わりと始まり』を買って読んでみたら、自分にもとても響いてきました。なので、その頃からシンボルスカの詩集は繰り返し読んできました。
斎藤 『続きと始まり』には、自分が今まで読んできたいろんな言葉の思い出を喚起するところがあって、なぜかというと、余白があるからだと思うんです。その人物の気持ちがべったり隅から隅まで描写されていなくて余白があるので、それで自分が今まで聞いた言葉や読んだ言葉をいろいろ思い出すんですよね。それはシンボルスカが呼び水になっているところもあると思うんです。
柴崎 ああ、それは絶対あると思います。シンボルスカの詩はシンプルな言葉で書かれていて、だからこそ何度も何度も思い出すんですよね。作中にも出した「終わりと始まり」という詩は、第二次大戦が終わった後の光景を綴っていると思うんですけれども、別の戦争や、何かがあるごとに、すごくあの詩を思い出すんです。
斎藤 あの詩は〈戦争が終わるたびに〉という一行で始まりますよね。でも、この小説を連載している間にウクライナの戦争が始まってしまうし、それでまた、ガザでの戦争が始まってしまって。
柴崎 そうなんです。書き始めた時はまったく想像もしていなかったことで、しかも連載が終わるまでに戦争が終わらないのはどういう状況かということもやっぱり想像がついていなかった。
斎藤 冷戦後から現在までって、一直線に繋がっている気がします。
柴崎 冷戦が終わって平和へのムードがと言いましたが、同時期の九一年には湾岸戦争があって、それも自分にとっては大きなできごとでした。中継されてテレビゲームみたいだと言われていましたが、テレビゲームと表現する感覚が私には分からなかった。その後、ユーゴスラビア紛争があって、「冷戦が終わってよかった」では終わらないんだと思ったんですよね。
斎藤 あれは私もショックでした。他にも世界中のあちこちで戦争はずっとあったのに、ヨーロッパの戦争って、ヨーロッパの人間じゃないのに揺るがされるところがありますね。ウクライナの時も、他のいろんなところで戦争があるのにみんな動揺したし、自分も動揺しました。自分はそういう世界観に染まっているんだなと改めて思いましたね。
柴崎 ユーゴスラビアのことが自分にとって深く影響するできごとだったのは、この間まで隣に住んでいた人と敵対する状態になったことでした。それまでは戦争って国の外を相手にするものだとどこかで思っていたのかもしれませんし、ドキュメンタリー番組で狙撃される危険の中で食糧を買いに行く「日常生活」を目の当たりにして、戦争とはこういう状況なのかと。朝鮮戦争もそれに近い状態でしたが、斎藤さんの『韓国文学の中心にあるもの』を読んで今まで具体的なイメージが薄かったということにも気づきました。
斎藤 私も、韓国に住んでいたのにそんな感じでしたよ。
詩の話に戻りますが、私は『続きと始まり』を読みながら、今が未来でもあり過去でもあるという時間の捉え方を感じて、思い出した詩があるんです。私、二年くらい前に亡くなった高良留美子さんという詩人の方の詩が好きなんです。高良さんの「指紋」という詩に、〈眩暈はどこまでつづくのか/今日はそのなかのどんな日なのか/区切りは少しも感じられないのに/ひとはあとになって区切りをつける〉という箇所があります。高良さんは〈深い裂け目の底〉って表現しているんですね。〈(でもそのときは二人とも/深い裂け目の底にいたんだ/未来はまぶしい光の先で/そこに達することなんて/考えることさえできなかった〉〈いまでも裂け目はつづいている/ひとはときどき振り返ってみる/不思議な気持ちで/余裕をもって/それでも裂け目はつづいているんだ)〉。二十歳くらいで読んだ時は、この意味がよく分からなかったんですよ。その頃はいいか悪いかの二分法で考えていたので、この〈裂け目〉というものが、暗い、悪いものとして捉えられているのかどうかが分からなかったんです。
今読むと、光も闇も等しいものとしてあって、どっちがいい、悪いと思ってないなと感じるし、〈それでも裂け目はつづいているんだ〉という言葉が腑に落ちるんですけれど。
柴崎 〈区切りは少しも感じられないのに/ひとはあとになって区切りをつける〉というのは、まさにコロナ禍の時期に対する感覚に重なりますね。
詩って何度も何度も、憶えるくらい読むものじゃないですか。だからこそ、後になっていろんな時に響いてきますよね。ああ、あの詩はこういうことだったのかな、とふと思ったりします。
斎藤 自分が書かれたものでもそう感じることはありますか。
柴崎 そうですね。久々に読んで、あの頃こんなこと書いていたのか、と思うことはあります。ある程度の時間書いていないと、この感覚はないんだなという気もします。
斎藤 柴崎さんは、二十年書き続けていらっしゃる。
柴崎 いつの間にか二十五年近いですね。それくらい書いてきたからこそ、ああ、あの時の自分はすごく分かったつもりだったけれど全然分かっていなかったなとか、今はそういうふうには思わないな、とよく考えます。それができるのが、小説や詩の言葉の持っている力なのかなと思ったりもします。私は本は、付箋を貼りながら読むんですけれど、久々に読み返すと、なんでここに貼ったんだろうという箇所もよくある。読む時期によって感じ方が違うんですよね。
斎藤 それはありますね。
柴崎 今読んでも私はここに貼るな、という部分もあれば、過去の自分が分からない時があります。あるいは、貼ったままにしておけば、未来の自分が読んだ時に分かるかもしれないと思って貼ったこともあったと思います。
斎藤 とってもよく分かります。だから自分が付箋を貼った本って捨てられないんですよね。私、『続きと始まり』はゲラをいただいて読みましたが、たくさん付箋を貼ったので、これはもう捨てられないです。
それにしても、『続きと始まり』というタイトルがすごくいいですよね。「終わりと始まり」じゃなくて、「続き」という意識なんですよね。
物語が後半に行くに従い、このタイトルに含まれていることがだんだん見えてきますよね。たとえば、優子さんが「終わることってあるんですかね」と言って、「なにも終わらないのに、次々始まって、忘れていくばっかり」って。これ、かなりはっきり言っていると思うんです。そもそも、続きと始まりというものは、柴崎さんが作品でずっと書かれていることですよね。
柴崎 はい。何かが何かに繋がっているとか、あの時のあの出来事はこういうふうに繋がっている、ということは書きたいです。
斎藤 続いているから始まっちゃうんだよということもありますしね。
柴崎 そうですよね。二〇一一年の震災の時に、こういう大きいことが起きてはじめて問題が起きるんじゃなくて、もともとある問題が大きくなるだけだと誰かが言っていて、本当にそうだなと思いましたし、今回のコロナ禍でも、それを思いました。日本は災害も多いし、他にもいろいろな事件や事故があって、その上に積み重なっているのに、いつの間にか忘れていくというか、忘れたみたいになっていくというか。その上に積み重なっているのに、うまく捉えていないような感じがずっとあったので、今回はそれを書きたいなと思いました。
斎藤 優子さんの章に出てくる河田さんという同僚が、会社がこれまで抱えていた問題についてかなりはっきり指摘しますよね。ああいうのもいいなと思って。
柴崎 日本って、なんでも個人の問題にされがちですよね。自己責任という言葉がどんどん使われるようになって、就職できなかったり、結婚して出産すると働くのが難しくなることも、「やる気がないからだ」などと、個人の問題にされてしまう。
斎藤 システムがそうなっている、ということは言われない。
柴崎 そうなんです。「だって、女性が管理職になりたがらないから」みたいな感じで。自分自身も「自分が頑張れなかったからこうなんだ」と思いこんできたこともあるんですよね。でも、少し前からそれは個人だけのことではないんだということが話されるようになってきて、特にコロナ禍の間、政治や社会で決まったことによって自分の生活がこんなにも左右されるんだということがすごく見えたと思うんですよね。
斎藤 コロナ禍ではっきりしたのは、日本型のシステムといえますね。初期の頃は日本人は素直に言うことをきいてくれると言われていましたし、それは確かにずっとそうだった。ですけれど、コロナを通じて日本のシステムへの不信というか、政治不信は深まりましたよね。
柴崎 自分もある程度の年数を生きてきて、「あの時ああだったのが今こうなっているのか」というのが分かるようになったことも大きいかなと思います。本当は何も終わっていないのだけれど、次々にいろいろなことが起きるので、そこを捉えずにきたんだな、というか。
私は九五年に大阪にいて、阪神淡路大震災は今までにない激しい揺れに衝撃を受けましたし停電もしましたが、家が壊れたりはしませんでした。直接被害を受けているわけではない私が何を書けるんだろうというのがずっとあったんですけれど、なにかしらの形で書いたほうがいいというのはずっと思っていて。それはチョン・イヒョンさんの「三豊百貨店」(『優しい暴力の時代』所収)を読んだ時にすごく感じました。
斎藤 「三豊百貨店」って、韓国の経済がどんどん上向きになっていった頃に、手抜き工事をした大きな百貨店がどーんと崩落した事故があって、その話なんですよね。
柴崎 実際のニュースは記憶にありました。
斎藤 イヒョンさんが前に日本にいらした時にインタビューか座談会ではっきり言っていましたね。あの事故は、個人と社会の問題なので書きたいと思いました、って。
柴崎 韓国の小説は個人と社会について、正面からはっきり書くことが多いですね。問題があるというだけでなく、そこでの人の関わり方への問いも明確にあったりする。日本でもたくさん読まれるようになってきている理由の一つかな、と感じます。
斎藤 それはあるかもしれません。三豊百貨店の事故は私もすごくショックだったんです。百貨店の販売員の人って、韓国だと階級が下に見られるんです。日本とは違って、接客をする仕事は大学を出た人がやるものじゃないという感じがあるので、韓国人が読んだらはっきり階級差を感じると思う。そういう人たちが犠牲になった事故について書かれた、上っ面をなでただけの新聞のコラムに主人公は腹を立てるんですよね。そのコラムを書いた人は、あそこにいた人たちは誰だったのか知っているのかと言って怒るという内容です。
柴崎 百貨店の事故が九五年なので、阪神淡路大震災と同じ年なんですよね。それもあって、チョン・イヒョンさんのお話は自分と繋がるところがありました。自分というか日本の人みんなが、テレビなどを通じて惨状を見た時、それをどう考えて捉えていけばいいのかというのは、ずっと考えていることです。直接大きな被害を受けていなくても、その時期の社会の状況に自分もなにかしら関係してきたわけですし。今回の小説でも、そこに触れるようにはしたんですけれど、まだすごく書けたという感じではなくて、この先もなにをどう書いていけるか、一作ごとにやっていきたいです。
斎藤 柴崎さんの『わたしがいなかった街で』では主人公の現在が描かれるなかで、主人公が読んでいる、過去に書かれた海野十三の日記が出てきますよね。あのスタイルもすごく好きです。同じ場所の違う時間を、他の人が書き残したものを通じて見ていく。それでも、全部が分かるわけじゃないところも好きです。
柴崎 あれはパクさんの『未来散歩練習』に近い書き方ですよね。過去の出来事を書くにしても、当時を書くというよりは、今ここにいる私がそのこととどう関係しているのかを書きたいんですよね。パクさんの「じゃあ、何を歌うんだ」(『もう死んでいる十二人の女たちと』所収)では、光州出身の自分はよく光州事件について訊かれるけれど、自分が生まれる前の出来事で、今ここにいる自分とは距離がある、その距離から今の世界を描こうとしていて、その感覚はすごく分かるというか。私もその距離からなにをどう書けるだろうかと考えています。
私は、なぜ過去の話を書いたり考えたりするのかとよく訊かれるんです。大学で地理の勉強をしていた時に、大阪の地下鉄御堂筋線の話を知ったことが大きいです。御堂筋線は一九三三年にできたんですけれど、その時は一両しか電車がなかったんですよ。でも、この後もずっと使えるように十両分のホームを造ったんだそうです。だから今でもそのまま使えているという。
斎藤 え、すごい。
柴崎 今は一両だけれど将来はもっと電車が長くなるから、その時も使えるようにって、すごく立派な十両分のホームを造っている。それを聞いた時にすごく感動しました。その地下鉄を使って大学に通っていたので、私は、過去のその人たちが想像した未来を生きているんだと思いました。ということは、自分は百年先の人から見たら過去の人なんだ、みたいなことも思うようになりました。今自分が経験していることは過去から繋がっているし、今自分がやることは先に繋がっている、みたいなこともよく考えます。それを書きたいなというのが、すごくあります。
斎藤 『続きと始まり』の最後にも、今はいつかの未来であり、いつかの過去であると感じさせる場面が書かれていますね。三人の登場人物が交錯するんですけれど、そこもものすごくいいなと思って。
柴崎 私、自分が書いたものと近いことが後から起きる、みたいな出来事が時々あるんですけれど、あの場面と似たことがありました。この間、早稲田大学で開催された「世界とつながる日本文学~after murakami~」というシンポジウムに出たんです。村上春樹の文学に影響を受けた外国の作家たちが参加していました。
斎藤 ああ、チョン・イヒョンさんがいらっしゃったやつですね。私、残念ながら行けなかったんです。
柴崎 すごく良かったんですよ。チョン・イヒョンさんが「三豊百貨店」の話もされていて。村上春樹が震災や地下鉄サリン事件のことなどを書いているのを読んで、自分も書かなければと思った話をされて、それを受けて私は、「三豊百貨店」を読んで震災の話を書かないといけないなとコロナ禍で考えていた、と話しました。文学の翻訳もテーマだったので、私がはじめて外国のシンポジウムに参加した、二〇一〇年のソウルでの日韓中の文芸誌のイベントのことを話したんです。そのイベントでは、私の話したことを中国語にする時は日本語から韓国語、韓国語から中国語と二段階ふんでいたんです。韓国語まではお客さんの反応でなんとなく今この部分を言っているなと分かるけれど、そこから中国語に翻訳されるともう全然分からない、それが面白くて。それまで翻訳というのは自分がわからない言葉が自分に近くなることだと思っていたんですけれど、自分の言葉が自分から離れて遠くに行くことでもあるんだなと思ったんです。小説を書くというのは時間がかかるけれど、時間をかけて書いたものが、また時間をかけて遠くに届く。それが面白いなと思った、ということを話したら、イベントが終わった後に、チョン・イヒョンさんが「あのシンポジウムに私もいました」って。

斎藤 へええ。あれって東日本大震災より前でしたよね。
柴崎 はい。二〇一〇年の十二月でした。しかも二〇二三年夏のロベルト・ボラーニョのイベントにパク・ソルメさんがいらしてて、「書評を書きました!」とご挨拶したら、パクさんもそのソウルでのシンポジウムに行っていて、客席にいた、とうかがって。
斎藤 二〇一〇年というと、パクさんは学生だったんじゃないかな。
柴崎 なんか本当に、『続きと始まり』みたいなことが起きていたんだなと思って。言葉って、その場からどこへ行ったか分からないけれど、そうやって流れ着くところがあるんだなとも思いました。思わぬところに流れついていて、それが時間が経ってから分かることがあるんだなって。
斎藤 面白いですね。みんな十三年前に同じ場所にいたんですね。
柴崎 そうなんです。そういえば当時、今度シンポジウムに登壇する人たちの小説を読もうと思って探しに行ったけれど、韓国文学の邦訳がすごく少なかったんですよ。新宿の紀伊國屋書店でも棚一段くらいしかなかった。
斎藤 二〇一〇年はクオンが韓国小説の出版を始める前ですよね。二〇一一年に『菜食主義者』(ハン・ガン著、きむ ふな訳)を出してスタートして、あれで日本の韓国文学の状況が変わっていったんです。
柴崎 二〇一〇年の頃はほとんどなかったのに今はどんどん邦訳が出ている。すごく変化したなと思います。そういう変化のなかで、影響を受けているんですよね。今の日本で韓国文学を読んで、社会と個人の描き方について考えた人も多いんじゃないでしょうか。これまでの日本だと、社会の問題と個人を描いてきた小説はもちろんたくさんありますが、どちらかというと個人に焦点が当てられるほうが多かったんじゃないかと思います。私が小説やフィクションに触れるようになった八〇年代以降にはその傾向が強かったかもしれないです。韓国の小説を読んでいて問題の所在を問うような部分には強い印象を受けます。日本の小説だとそのつながり方はもう少しひねって描かれるというか。どちらがいいということではなくて、それぞれの社会の問題のあり方、見え方が反映しているんだと思います。
斎藤 明らかに違うと思うんですけれど、私はその違いを上手く言葉にできなくて困るんです。
日本の人は、そんなに社会のことを考えなくてもよかった歴史が長いんだと思う。戦後しばらくはいわゆる戦後文学があって、今と全然違うアプローチがあったと思うけれど、それ以降は個人の物語を書けばよかったし、それが求められていた。でも今急速に、自分の人生は自分一人の性格や運命だけのせいで決まるわけじゃない、ということが可視化されて、システムごと書かなきゃいけない時代に入ったと思うんです。やっぱり韓国とは歴史が違うので、それぞれの違いは出ますよね。
柴崎 日本は今、いろいろな面で過渡期ですね。
斎藤 私、韓国の小説とは違うという意味で「日本の小説らしさ」について考えるとき、いつも柴崎さんの小説と黒川創さんの小説が思い浮かぶんですよ。
柴崎 そうなんですか。
斎藤 なぜか分からないんですけれど、おふたりの小説にあるものが、韓国の小説にはないと感じるんです。ぼんやりした言い方になってしまうけれど、おふたりの小説はなんというのか、すごく練り上げられている、個人と社会がとても自然に、ちゃんと混ざっている気がする。
柴崎 最近、自分について考えていたのは、私は小児喘息があって、小学校に行く前から公害健康被害認定を受けていたんですね。尼崎・国道四十三号訴訟というのがあって、私は尼崎ではないですがその四十三号線の大阪のほうに住んでいて認定を受けられたんです。それで、自分の身体の苦しさと社会と制度が繋がっているという感覚がずっとあったんです。それが自分にとっては当たり前だったから、そんなに表立って書くということも思いつかなかったんですけれど。
斎藤 認定されると、どういうことがあったのでしょう。
柴崎 医療費の支援が受けられますし、大阪市では子供は夏に転地療養というのがあって、喘息の子ばかりで山のほうの病院とかに宿泊しに行ったんですよ。私はそれがすごく楽しくて、毎年旅行に行けると思って毎回ウキウキしていたんです(笑)。でも、学年が上がるにつれて参加者が減っていって、小学五年生の時に皆勤が私だけなのに気づいて「あれ? みんなあんまり病院に泊まる行事には参加したくないのかな」と思って。
斎藤 病院に泊まって、みんなでなにか遊んだりするんですか。
柴崎 腹式呼吸の練習や水泳ですね。多少遊ぶ企画もあるんですけれど。先生なのか市の職員なのか分かりませんがずっと同じ担当の人がいて、参加する人が減っていくのは治ったということだからいいことなんですよみたいなお話を聞いたときに、もしかして私がずっと来ていると治らないことで心配かけてしまうのかなと思って六年生の時は行かなかったんですよね。行きたかったけれど。
斎藤 優しい子だな。でもそうか、日本は本当に公害大国だったんだなあ。
柴崎 そうですね、七〇、八〇年代はまだ公害は現実的に大きな問題として身近に考えられていました。その経験というか、そういうふうに個人と社会の繋がりを捉えていたのは大きかったのかもしれません。
パクさんの『未来散歩練習』も、子供の時の体験について書かれていて、ああ、お友達がいると感じながら読みました。ファン・ジョンウンさんの『ディディの傘』でも、大きな災禍を間接的に経験することについて書かれていますよね。
斎藤 そうですね。『ディディの傘』は二〇一九年に書かれたものですが、私、ガザのことが始まった時、あの小説の一部分をすごく思い出したんです。
主人公の男性とその友人が、なんとなくデモ隊と一緒になって、歩きながら会話する場面があるんですよね。一人はイタリア留学をして帰ってきた人で、もう一人はソウルでずっと派遣で働いている人で。イタリアから帰ってきた方の人が、「兆候はいつだってある」という話をするんですよ。日常の中にすべての兆候がある、「有事の際」という言葉は、非常なことが起きるときという意味だけど、非常なことはいつも日常の中に兆しを見せているんだ、と。ちょっと長くなりますが読んでみますね。「戦争を見てみろ。脈絡なしに起きる戦争はないんだ……放射能も同じだ、原発という兆候があって放射能漏れがあるわけじゃないか。今もそうだ。俺にはいつだって、今がそうだ……今はまさに戦争と戦争の間みたいだ。第二次大戦と第一次大戦、二つの巨大な戦争の間には兆しがすごく充満してただろ。そんな兆候を感じるよ。もうすぐ世界が、もういっぺん、滅びるんだろうって予感がして、それはものすごく確かなんだ」。こんなことを言いながら歩いていく。
小説って、今であって、過去でもあって、未来でもあることが書かれているけれど、まわりまわって予言みたいになってしまうこともあるんですよね。
柴崎 そうですね。コロナ禍が始まった時に『ペスト』などこれまでに書かれた小説が読まれましたが、それらも過去のことなんだけれど予言でもあるようになっていましたよね。
私は二〇一八年に韓国に行った時、『ディディの傘』のその二人が歩いている大きな道を通りました。あの通り沿いは、座り込みをしている人たちが常にいますよね。
斎藤 あそこはそういう広場なんですよね。セウォル号の遺族もずっとあそこにいました。
柴崎 座りこみをしている人たちを見た時、まだ終わっていないことを伝えるためには、常にこうして人に見える場所に、人が通る場所にいることが重要なんだと思いました。
斎藤 可視化することが大事という。見えないと終わったことになっちゃう。
柴崎 災害から時間が経って、時々ニュースの街頭インタビューで「報道がなくなったからもう復興したのかと思っていました」みたいな声が象徴的に使われたりしますよね。見えなくなるとそういう部分もあるなと思って。セウォル号の時は、現地の港に何組もの遺族の人がずっといましたよね。
斎藤 やっぱり韓国は、とんでもない事件があった後に報道管制がしかれて、何が起きたかが伏せられてきたことが何回もあったので、見える場所にいるということは、かなり強力だと捉えられているんじゃないかと思います。
柴崎 日本は報道管制みたいな明示的な規制はなくても、見かけ上なんとなくなかったことにする方向ですよね。「忖度」や「自粛要請」はそれをよく表している言葉だなと。
斎藤 やり方が違うだけなんですよね。
柴崎 いつの間にか曖昧になる。差別も「もうないよね」みたいに言われて、ないことにされ、見えなくされることがあります。
私が書くものは「何気ない日常を書いている」と言われることが多いんですけれど、私は日常って怖いものでもあると思います。何か起きても、「何気ない日常」に戻す圧力を感じます。大変なことが起きているのに、何も起きていないみたいに振る舞おうとするというか。そこで「いや、こんな大変な状況なんですよ」などと異議を言う人も隠されていく。
小説の中でも何度か書きましたけれど、コロナ禍で仕事がなくなった人や、家族が大変な状況になっている人はいるのに、町の光景自体はすごく平穏に見えて、何事もないように感じさせるという、そういう“日常圧”の強さみたいなものがあるな、と。
斎藤 “日常圧”がかかって、本当は思ってもないことを言ってしまう、みたいなことも結構ありますよね。『続きと始まり』の中で優子さんが、自分は本当はそうは思っていないのに、親から聞かされてきた前時代的な言葉をつい言ってしまう場面がありますよね。その場を終わらせるために、何も波風が起きないことを言おうとして、でも何も考えていなかったから言葉のチョイスがなくて。
柴崎 それで、本心ではないのにどこかで聞いた言葉を言ってしまうという。
斎藤 やっぱり、何気ない日常が一番“現場”ですよね。
柴崎 だからこそ自分は、何か大きなことがある瞬間よりも、普段の生活にあることから書いているのかもしれないです。
斎藤 でも、ここに出てくる人たちは、“日常圧”のなかで、できるだけ踏ん張ろうとしていると読めました。
柴崎 そうですね。それは私自身の抵抗でもあると思います。
斎藤 この先、どうなるんでしょうね。どうにもならないんでしょうけれど。
柴崎 どうにもならないなかでも、小説や詩の言葉はささやかでも支えになってくれるのかなと。それにやっぱり、書かないと残らないですし。私の小説は、読んだ人から「いろいろ思い出した」と言われることが多いんですが、そういうことでもいいのかなと思っていて。
斎藤 柴崎さんの小説は、微動で揺すってくるんですよね。お盆の上にぱーっと広げた小豆とかを揺する感じ。
柴崎 大きく揺すってわーっと喚起されるものもありますが、そこに収まらないもの、こぼれ落ちるものが絶対にあるので、自分はそれを書けたらと思っています。
斎藤 『続きと始まり』で微動で揺すられたことで、私のなかのなきものとされた二〇二一年を反芻できて、本当に助かりました(笑)。やっぱり小説って大事だなと思いました。
折に触れて読み返すと、自分の中で何かが起きる本ってありますよね。この先読み返したら違うだろうなという予感がある本。これは本当に、そういう本だと思います。
柴崎 ありがとうございます。そういう本になれていたのなら嬉しいです。
(2023.11.27 神保町にて)
構成/瀧井朝世 撮影/露木聡子
「すばる」2024年2月号転載
プロフィール
-
柴崎 友香 (しばさき・ともか)
1973年、大阪府生まれ、東京都在住。大阪府立大学卒業。1999年「レッド、イエロー、オレンジ、オレンジ、ブルー」が文藝別冊に掲載されデビュー。2007年『その街の今は』で芸術選奨文部科学大臣新人賞、織田作之助賞、咲くやこの花賞を受賞。2010年『寝ても覚めても』で野間文芸新人賞、2014年『春の庭』で芥川賞、2024年『続きと始まり』で芸術選奨文部科学大臣賞及び谷崎潤一郎賞を受賞。その他に『パノララ』『千の扉』『百年と一日』ほか、エッセイに『よう知らんけど日記』など、著書多数。
-
斎藤 真理子 (さいとう・まりこ)
1960年新潟県生まれ。翻訳家。主な訳書に、チョ・セヒ『こびとが打ち上げた小さなボール』、ハン・ガン『すべての、白いものたちの』、チョン・セラン『フィフティ・ピープル』、チョ・ナムジュ『82年生まれ、キム・ジヨン』、ファン・ジョンウン『ディディの傘』、パク・ソルメ『もう死んでいる十二人の女たちと』、ペ・スア『遠きにありて、ウルは遅れるだろう』など。著書に『韓国文学の中心にあるもの』『本の栞にぶら下がる』。2015年、パク・ミンギュ『カステラ』(ヒョン・ジェフンとの共訳)で第1回日本翻訳大賞受賞。
新着コンテンツ
-
インタビュー・対談2025年07月08日
 インタビュー・対談2025年07月08日
インタビュー・対談2025年07月08日桜木柴乃「波風立てずに生きる器用さを、ちょっと残念だなと感じる大人に読んでほしい」
著者五十代の最後を飾る、集大成的な短編集である本作。仕事に対する現在の思いや、短編を書く面白さをうかがいました。
-
お知らせ2025年07月04日
 お知らせ2025年07月04日
お知らせ2025年07月04日すばる8月号、好評発売中です!
演劇界注目の劇作家・演出家ピンク地底人3号さんによる初の小説を掲載! 遠野遥さんの短期集中連載も最終回を迎えます。
-
インタビュー・対談2025年07月04日
 インタビュー・対談2025年07月04日
インタビュー・対談2025年07月04日石井遊佳×藤野可織「魂を自由にする虚構の力」
ホラー愛好家を自認する藤野さんは石井さんの新作に詰まった四つの物語をどう味わい、そこに何を見つけたのか。
-
新刊案内2025年07月04日
 新刊案内2025年07月04日
新刊案内2025年07月04日給水塔から見た虹は
窪美澄
2人の“こども”が少しずつ“おとな”になるひと夏を描いた、ほろ苦くも大きな感動を呼ぶ、ある青春の逃避行。
-
新刊案内2025年07月04日
 新刊案内2025年07月04日
新刊案内2025年07月04日青の純度
篠田節子
煌びやかな「バブル絵画」の裏に潜んだ底知れぬ闇に迫る、渾身のアート×ミステリー大長編!
-
新刊案内2025年07月04日
 新刊案内2025年07月04日
新刊案内2025年07月04日情熱
桜木柴乃
直木賞受賞作『ホテルローヤル』、中央公論文芸賞受賞作『家族じまい』に連なる、生き惑う大人たちの物語。