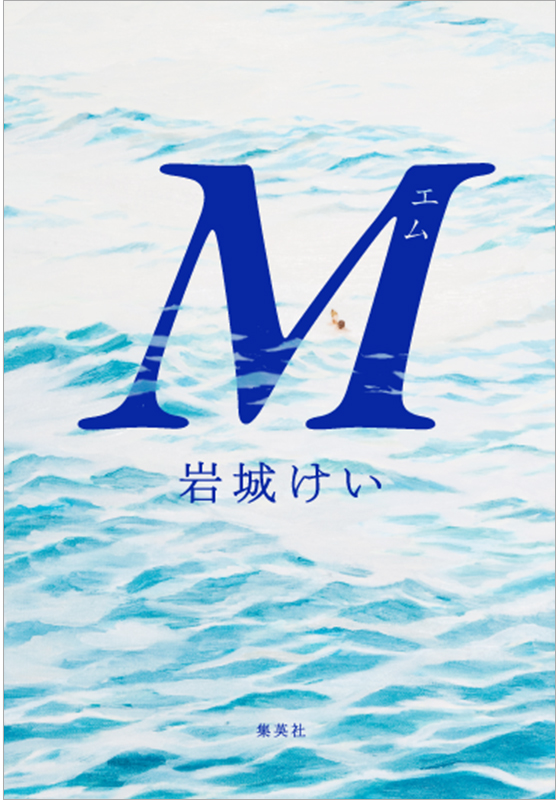内容紹介
あなたを知ることは、あなたという人を選んだわたしを知ること。
多民族国家の生きた声を掬う在豪作家が贈る、力強くみずみずしい《越境青春小説》。
父の転勤にともない12歳でオーストラリアに移住し、現地の大学生となった安藤真人。憧れていたはずの演劇の道ではなく就職を選ぼうとしていたところ、デザイン科でマリオネットを制作しているアビーと出会い、人形劇の世界に誘われる。日本人としてのアイデンティティの問題に苦しんできた真人のように、「同じアルメニア人と結婚を」と刷り込まれてきたアビーもまた、出自について葛藤を抱えていた。互いを知りたい、相手に触れたい。しかし、境遇が似通うからこそ、抱える背景の微妙な差が、猛烈な「分かりあえなさ」を生み……。
話題の既刊『Masato』『Matt』につらなる、「アンドウマサト三部作」最終章!
プロフィール
-
岩城 けい (いわき・けい)
作家。1971年大阪府生まれ。大学卒業後、単身渡豪。以来在豪約30年になる。2013年に『さようなら、オレンジ』で太宰治賞を受賞しデビュー。2014年に同作品で大江健三郎賞、2017年に『Masato』で坪田譲治文学賞を受賞。他の著書に『ジャパン・トリップ』『Matt』『サンクチュアリ』『サウンド・ポスト』『M』がある。
対談
書評
揺らぐアイデンティティと自由
鴻巣友季子
あの「アンドウマサト」が二十二歳になり、就職活動をしている。そう思うとたいへん感慨深い。『Masato』『Matt』から続いたシリーズの第三部である。
父の仕事で十二歳のときに日本からオーストラリアに移住したマサトが、現地校に通って差別にあい、苦しみながら自らの居場所を探す物語が『Masato』だった。彼は『Matt』で演劇に出会う。
そして『M』。呼び名が短くなる一方、彼の可能性と重層性は増している。大学の数学科で最高学年を迎えた今も、外見はイエローでも中身はホワイトなのかと自問自答する日々。映画のエキストラのバイトを続けつつ、製薬会社か銀行への就職を考えている。大学に残り、副専攻の文学の勉強を続けることを教授に勧められても、決意は揺るがない。
とはいえ、デザイン科の人形作家アビーから人形劇団への誘いを受けると、演劇魂がうずき、手伝うことに。この出会いはマサトに新たな軋轢とアイデンティティの動揺を連れてきた。
彼には「白人」にしか見えないと言うアビー・グリゴリアンはアルメニア系二世だ。幼い頃から同郷男性との結婚を親族に強いられ、アルメニア語の補習校に通わされた。両親の英語の拙さを恥じた時期もあるが、両親の一番「強い」言葉であるロシア語をアビーは話せない。国家、民族、言語にまつわる亀裂と迫害と偏見の歴史が何重にも透けて見える。
マサトはマサトで、地元のパブで中年男に、かつて豪兵を斬殺した日本兵の末裔として暴言を受け、出演する映画での奇妙な日本人役にステレオタイプを感じているが、アビーの言葉は彼の固定観念を打ち砕く。アニメやスシで知られる日本人は、いわば「目立ちたがり屋と人気者の寄せ集め! ダイバーシティーなんて、わたしから見たら、新種のマジョリティーのパレードみたいなもんよ!」と。
作中では、返事の来ない「あしながおじさん」式の書簡が大きな働きをする。
操り人形が自由になる方法は、自分を何かに繫ぐ糸を切ることだけではないだろう。MがMを探す旅はまだまだ続くはずだ。
こうのす・ゆきこ●翻訳家、エッセイスト
「青春と読書」2023年7月号転載
「違い」から知る、自分のアイデンティティ
竹田ダニエル
この本で描かれているのは、私の話であり、あなたの話でもある。
今作『M』は、『Masato』『Matt』の前二作に続く、三部作の完結編。シリーズを通して、子どもの頃に父親の仕事の都合でオーストラリアへと渡った主人公・真人の成長が描かれてきたが、『M』ではメルボルンで大学生として過ごす真人が語り手となる。「日本人留学生」でもなく、「オーストラリア人」でもない彼が、自身のアイデンティティと向き合い、他者や「社会」からの括られ方に葛藤する過程が鮮明に描かれる。
私自身、アメリカ生まれ・アメリカ育ち、母親が日本人で家では「日本人」としてのアイデンティティを強く刷り込まれて教育をされた、いわゆる「本当のホーム」がどこだかわからない「third culture kid」だ。本書にもまた、アビーというアルメニア系オーストラリア人の女の子が登場する。彼女はオージーであり、アルメニア人であり、同時にどちらでもない、「third culture kid」の典型的な悩みを語る。大きな括りで言うと、真人も同じ属性にあたるだろう。しかし大きく異なるのが、私やアビーは現地生まれであるのに対して、真人は移住者であること。その相違点を鮮明に突きつけられ、自身の考えを浮き彫りにされた。私は「アメリカ生まれのアメリカ人」として認められるために、マイノリティとしての人権の主張や、デモをはじめとするアクティビズムにも「連帯感を持って関心を寄せるべきだ」と、当事者として強く感じている。対して真人はそのような「自己主張」との向き合い方に悩んでいた。 「おれは自分の考えは簡単に言いたくないだけだ。おれだけのオリジナルなんだからな。何回も言ってるけど、デモは苦手なんだ」。一方でアビーは「アルメニア人としての自分」に高いプライドを持つが、アジア系のように「見た目による差別」を受けないからこそ、文化的な違いや複雑な出自の面で、また異なる葛藤を抱えている。
「Z世代」という言葉も本書を読み解くうえで外せない。私はアメリカに住むZ世代として、アメリカの若者たちにまつわる様々なトピックを日本語で書く活動をしているが、同時に日本の「Z世代」とアメリカ(ないしは欧米)の「Z世代」は全く同じものではない、ということを繰り返し主張してきた。
真人はまさにオーストラリアに住むZ世代だ。いわゆる「SDGs」などの言葉が、彼らオーストラリアの大学生たちの会話の中では記号的な形ではなく、重要なトピックとして登場する。真人のルームメイトであるゼイドとの会話は、人種差別や格差問題を中心に回っている。自己アイデンティティ、環境問題、政治やデモなど、あまりにそのような話題に敏感すぎやしないか、と日本人の読者は思うかもしれない。しかし、すぐ隣にいる人が全く違う見た目や属性であったり、出自を理由に「自分」を見てもらえない場合があると(真人は「日本人/アジア人」としてしか見てもらえなかった)、自分にとっての「世界」は「アイデンティティ」にまつわる物事を中心に回るものとなり、会話のネタもそれに限られてくる。というか、それが最も大事である以上、永遠についてまわるのだ。
アメリカにおいては、Z世代は最も多様な世代だ。差別や格差問題、そしてその根源である人種やジェンダー・セクシュアリティなどの問題は、見て見ぬ振りをしているだけではなくならないことを、彼らは理解している。だから議論をし、ぶつかり合い、問題の所在を明確にする。
アメリカに留学に来る日本人男子学生が、留学中にコンプレックスをこじらせたり、逆に自らの「マイノリティ性」を持ちネタギャグ的に使ったりと、有害な男性性や特権を捨てきれていない様子を多く見かける、という話を先日Twitterに投稿した。アメリカ(欧米)に留学して初めて、日本人男性は「マイノリティ」としての生活を実感する、という話題に応答してのことだった。
真人はというと、他の日本人留学生と一緒にされたくない、自分は「日本人やめたくなる」と心情を吐露する。「正直、イヤなんだ。日本っていう国にいつまでも付き纏われるのが。こっちで生まれ育っても、中には『自分は日本人』だと胸を張るやつもいるけど、おれはこの国をないがしろにしているみたいでそれはイヤだ」。「日本人らしさ」を捨ててオーストラリア社会に同化しようとするある種の「名誉白人」的な自分の行動の醜さや、「日本人であることを誇りに思えない」悔しさなど、中途半端な自己アイデンティティに振り回される様子が描かれる。他者から不正確にカテゴライズされる真人の怒りの言葉を読むたびに、自分の奥底に隠していた感情を見透かされたように感じた。
日本国内で「日本スゴイ」と持ち上げる時、対外的で表層的な文化であったり、物質的で本当のカルチャーを反映していない「クールジャパン」であったり、「白人」コミュニティに「認められる」ことをベースにした指標で物事を測っている。国内でそのような薄いアイデンティティしか育まれないと、いよいよ外に出た時に何をもって「日本人」と思えばいいのか、少しでも日本という環境を離れて自分と向き合ったことがある人は疑問に思い始めるだろう。そのようなリアルな心境の変化、自らの日本という「鎖」に対して生まれる抵抗が、アビーとの衝突や話し合いの場面を通じて繊細に描かれる。新たなアイデンティティと出会い、真人が日本という「鎖」とどう向き合うのか、ぜひ本書を読んで確かめてほしい。
日本にしか住んだことがなくて「海外のことなんて関係ない」と思う人、海外に住んでいて辛い思いをした人、そしてそれ以外の人も。この本で描かれているのは、私の話であり、あなたの話でもある。
「すばる」2023年8月号転載
新着コンテンツ
-
新刊案内2024年07月26日
 新刊案内2024年07月26日
新刊案内2024年07月26日地面師たち ファイナル・ベッツ
新庄耕
不動産詐欺の組織犯罪の闇に迫る、新時代のクライムノベル『地面師たち』の待望の続編!!
-
インタビュー・対談2024年07月26日
 インタビュー・対談2024年07月26日
インタビュー・対談2024年07月26日新庄耕「釧路がシンガポールになる、というあり得なさで「いける!」と」
今夏Netflixでドラマシリーズ化された前作と、その待望の続編である本作への思いを著者に伺いました。
-
インタビュー・対談2024年07月19日
 インタビュー・対談2024年07月19日
インタビュー・対談2024年07月19日青波杏「「語れない」をテーマに描く、女性同士の繫がりと植民地の歴史」
現代の台湾に生きる女性二人が、古い日記に隠された真実を探る物語。謎と日常、過去の歴史と現在が交わる中で見えてくるものとは。
-
インタビュー・対談2024年07月19日
 インタビュー・対談2024年07月19日
インタビュー・対談2024年07月19日ファン・ボルム「休めない社会だからこそ、休む人たちの物語を描きたいと思った」
本屋大賞翻訳小説部門第1位に輝き、ロングセラーを続けている本作への思いを、著者のファン・ボルムさんに伺いました。
-
お知らせ2024年07月17日
 お知らせ2024年07月17日
お知らせ2024年07月17日小説すばる8月号、好評発売中です!
奥田英朗さん「家」シリーズの待望の新作読切を始めとした大特集のテーマは”家族”。新川帆立さん、遠田潤子さんの対談も必読です!
-
連載2024年07月12日
 連載2024年07月12日
連載2024年07月12日【ネガティブ読書案内】
第32回 浅倉秋成さん
「ポジティブ思考が羨ましくて仕方がない時」