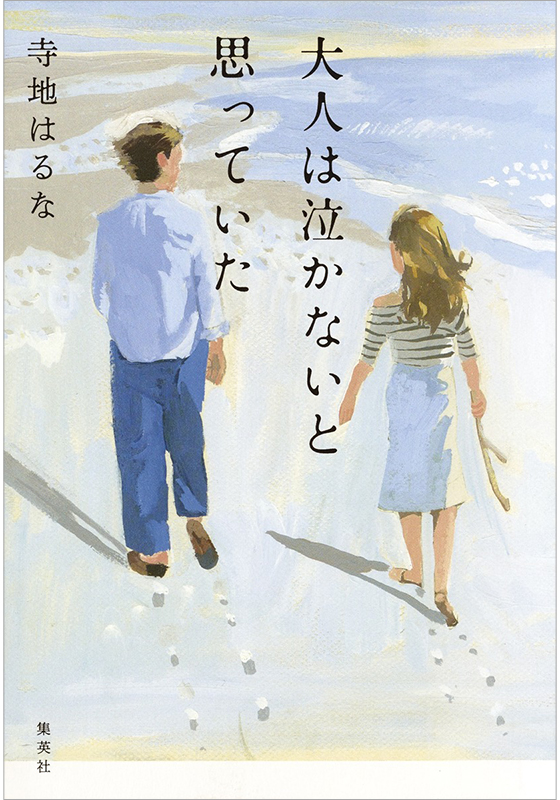作家・寺地はるなさんによるエッセイ連載。食べて眠って働いて……日々をやりくりしている全ての人に贈る、毎日がちょっと愉しく、ちょっと愛おしくなる生活エッセイです。
第11回:ちょっとしたパーティー
2025年02月21日
洋服を買いに行った時に「これならちょっとしたパーティーなんかにも着ていけますね」というすすめかたをされることがある。長年「ちょっとしたパーティーってなんだよ、そんなの行く機会ないよ」と思っていたのだが、小説を書くようになってはや十年、私はついに気づいてしまったのだ。今の自分って「ちょっとしたパーティー」に行く機会がけっこうあるかも、ということに。たとえば文学賞の贈賞式だとか。
招待状はいろいろなところからいただくが、これまで出席したことはない。たいてい平日の夕方に開催されるし、会場は東京である。私は大阪に住んでいるので行けない。いやがんばったら行けるのだが、そこはがんばるところじゃないだろという思いがある。しかし、たとえば、自分がその賞の受賞者になったとしたら話は違ってくる。
ここ数年、毎年のようになんらかの賞の候補に選出していただく機会に恵まれてきた。いきなり受賞の連絡が来るタイプの賞もあれば、「あなたの本を候補にしまっせ」という連絡が来たのちに選考会がおこなわれるタイプの賞もある。この後者のタイプに、私は縁が薄い。候補にはなるが賞はもらえない。2020年から2024年のあいだにこれが四回もあった。最初は「候補になれただけでじゅうぶんです」などと殊勝なことを言っていたが、だんだん疲れてきた。賞の候補になるのはほんとうに嬉しいし名誉なことだと思う。でもあの選考会を待つ期間というのがとにかく辛い。
べつに賞に執着とかないし、という人は平気なのかもしれないが私は喉から手が出るほど賞が欲しかったので、候補の発表から選考会までの期間はいつも気分が落ちつかなくて夜七時間しか眠れないし、ごはんも一膳ぐらいしか食べられないしで、とにかく辛かった。
今年の四月に、友人とふたりで買いものをしていた。また賞の候補になったんだよーなどと話していた時、一着のワンピースが目に留まった。黒い、ごくシンプルな形状で、胸から裾にかけて青い花が描かれていた。「これ、買うたら」と彼女は言った。授賞式で着たらええやんと、まるで賞をもらうことが決まっているかのように、じつに軽やかに。
そして、私はそのワンピースを買った。ちょっとした願掛けみたいな気持ちもあったのだと思う。でも普通にだめだった。だめだったことにショックを受けたというより、またかよ、もう疲れたわ、と思って泣いた。父親の葬式でもあんなに泣いてないと思う。
泣いて泣いて泣いたその三日後に、そのワンピースを着て外に出た。いつものショッピングモールの、いつもの書店で本を買い、いつものコメダ珈琲で食事をした。家に帰ってきてから、どんな服着て、どこに行ったっていいんだな、と思った。ちょっとしたパーティーじゃなくったって、着たい時に着ればいいんだと。いつもよりすこしきれいなかっこうでいつもの場所を歩くのは、なんとなく気分のいい行為だったのだ。
好きな服を着て好きな場所に行くように、好きな小説を書いてみよう。そう思った。喉から手が出るほどの執着心をいったん手放して、自分はどんな小説を書いていきたいのか、ということをあらためて考えてみよう、と。
おかげで、と言ってしまっていいのかどうかはわからないが、今は小説を書くことがものすごく楽しい。今がいちばん楽しいかもしれない。
悩みがなくなったわけではないけれども、いろいろなものを手放したことで身軽になった。これからまた新たに抱えこんでしまうかもしれないけれども、その時はまた好きな服を着て、好きな場所に出かけようと思う。
プロフィール
-
寺地 はるな (てらち・はるな)
1977年佐賀県生まれ、大阪府在住。2014年『ビオレタ』でポプラ社小説新人賞を受賞しデビュー。2021年『水を縫う』で河合隼雄物語賞受賞、2023年『川のほとりに立つ者は』で本屋大賞9位入賞、2024年『ほたるいしマジカルランド』で大阪ほんま本大賞受賞。『大人は泣かないと思っていた』『こまどりたちが歌うなら』『いつか月夜』『雫』など著書多数。
関連書籍
新着コンテンツ
-
新刊案内2025年07月30日
 新刊案内2025年07月30日
新刊案内2025年07月30日マスカレード・ライフ
東野圭吾
警視庁を辞め、コルテシア東京の保安課長となった新田浩介が、お客様の安全確保を第一に、新たな活躍をみせる最新作。
-
インタビュー・対談2025年07月25日
 インタビュー・対談2025年07月25日
インタビュー・対談2025年07月25日宇佐美まこと×松浦秀人(日本被団協代表理事)「被爆80年、物語に託した軌跡と奇跡」
宇佐美まことさんの最新刊は戦争の愚かさがテーマ。被爆者の松浦秀人さんをゲストに招き、おふたりが暮らす愛媛県松山市でお話を伺いました。
-
新刊案内2025年07月25日
 新刊案内2025年07月25日
新刊案内2025年07月25日ライアーハウスの殺人
織守きょうや
孤島に聳え立つ来鴉館で嘘つきたちの饗宴が始まる――。二度読み必至の超本格ミステリ!!
-
インタビュー・対談2025年07月22日
 インタビュー・対談2025年07月22日
インタビュー・対談2025年07月22日窪美澄「「私はあなたを見ている」、その視線を感じるだけで救われる人がいる」
外国人が多数暮らす団地を舞台に、著者はどのような物語を書き上げたのか。その物語から、どんな希望を紡ぎ出したのか。
-
インタビュー・対談2025年07月18日
 インタビュー・対談2025年07月18日
インタビュー・対談2025年07月18日窪 美澄×藤野千夜「団地を書くふたり」
団地を書き続けてきたおふたりに、団地に対する思いや互いの作品の印象、執筆の背景などを語っていただきました。
-
お知らせ2025年07月17日
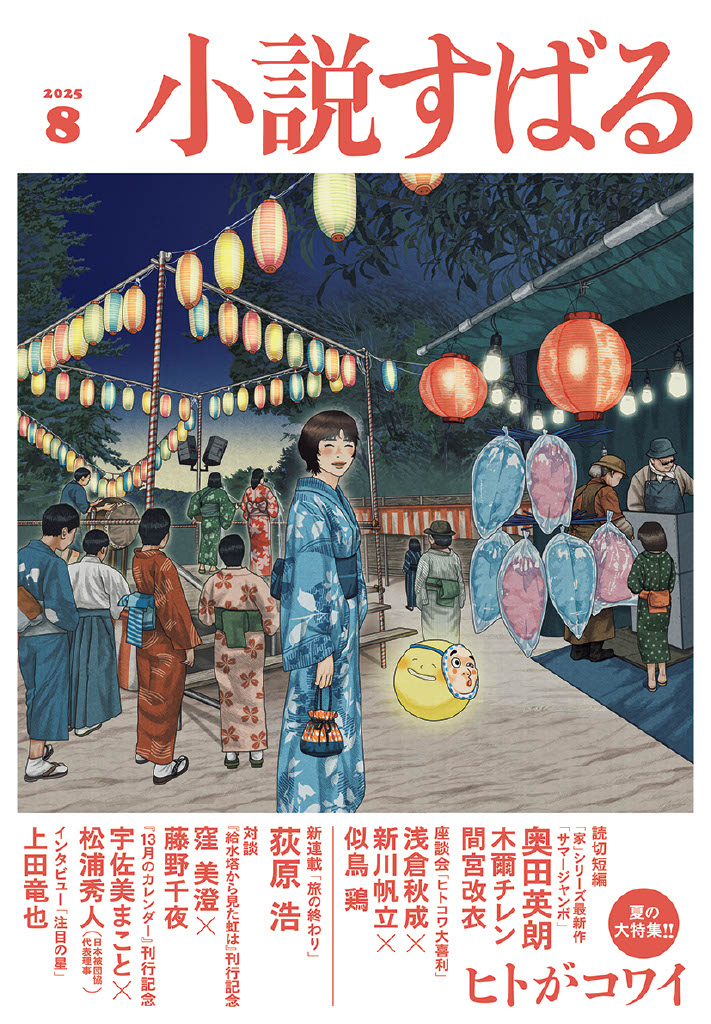 お知らせ2025年07月17日
お知らせ2025年07月17日小説すばる8月号、好評発売中です!
巻頭は荻原浩さんの新連載。特集〈ヒトがコワい〉では奥田英朗さん「家」シリーズ最新作の読切短編も!