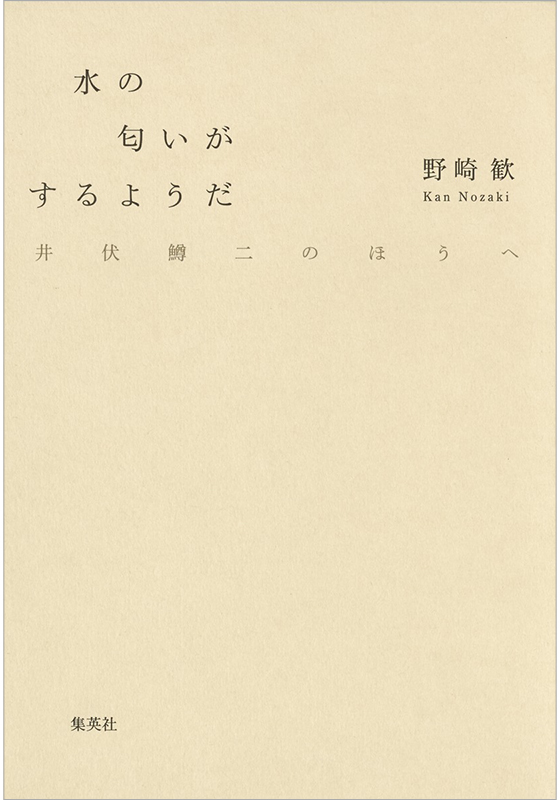プロフィール
-
若松 英輔 (わかまつ・えいすけ)
批評家、随筆家。1968年新潟県生まれ。慶應義塾大学文学部仏文科卒業。2007年「越知保夫とその時代 ──求道の文学」で第14回三田文学新人賞を受賞。16年『叡知の詩学 小林秀雄と井筒俊彦』で第2回西脇順三郎学術賞を受賞。18年『詩集 見えない涙』で第33回詩歌文学館賞を受賞。同年『小林秀雄 美しい花』で第16回角川財団学芸賞を受賞、19年に第16回蓮如賞を受賞。他の著書に『井筒俊彦──叡知の哲学』『霊性の哲学』『イエス伝』『詩集 愛について』などがある。
『霧の彼方 須賀敦子』刊行記念エッセイ
弱き勇者たちの軌跡──須賀敦子とその仲間たち
若松英輔
奇妙なことをいうと思われるかもしれないが、「評伝」という形式は、書き手の努力だけでは書き進められない部分がある。もちろん、紙を文字で埋められはするが、それだけだとどうしても「作りもの」になってしまう。登場人物の息吹を感じることができない。
それは「生まれてきたもの」でなくてはならない。言葉は、何とも呼びようのないところから湧き上がってくる。そのとき書き手は、助産師になる。「生まれて」きた作品は、じっさいの子どもがそうであるように、遠からず、一個の独立した存在として書き手である親のもとから離れていく。それどころか書き手が、いつまでも親であると主張することを暗黙のうちに拒むようなところさえある。
須賀敦子の作品にも、そうした巣立っていった言葉の香りがする。だからこそ読者は、彼女が描き出す、未知なる人の姿にふれながら、私の奥にいて、見過ごしてきた「わたし」を見出す。そして、それは強い「わたし」ではなく、むしろ、弱い「わたし」ではあるまいか。
代表作の一つ、『コルシア書店の仲間たち』では、しばしば弱い人たちの姿に出会う。当然ながら、人の弱さに気が付けるのは、おのれの弱さを知っている人だけだ。
一見すると弱さは至らなさと判別がつきにくい。しかし、それは似て非なるものである。至らなさが、その人の悪癖とつながっていて、他者を遠ざけることが珍しくない一方、弱さは、それに接する他者の胸の眠れる愛に火をつける。
コルシア書店──正確にはコルシア書店だった場所──には、幾度か行ったことがある。須賀がミラノを後にしてからは様子が変わってしまったこともあったようだが、現在はかえって彼女がいた頃に近くなっている。何があったのかは知らない。並んでいる本が、「どんぐりのたわごと」で須賀が紹介していた文章と強く呼応しているのである。この「書店」は、本を売るだけでなく、出版する機能もあった。むしろ、それがいわばコルシア精神の支柱だった。書店全体を切り盛りしていたのが須賀の夫ペッピーノである。彼は一九六七年に、何かに連れ去られるように亡くなった。今、目にしているこれらの本は、もしペッピーノが生きていたら、この書店から世に送り出されていたものだったのかもしれない、そう思いながら書架を眺めていた。
その典型的な著者が、ディートリヒ・ボンヘッファーだ。数年前、この書店を訪れたとき、真っ先に目に入ってきたのが彼の本だった。ボンヘッファーは、一九〇六年ドイツに生まれ、一九四五年、ナチスによって処刑されたプロテスタントの牧師である。若くして、二十世紀でもっとも影響力をもった神学者カール・バルトにその才能を認められ、イギリス、アメリカに渡ってキリスト教諸派との対話を重ねた。分裂した教会に、新しい一致をもたらそうとするエキュメニカル運動を象徴するような人物でもあった。非暴力主義者でもあった。インドで、ガンディーに学ぼうと試みたこともあった。処刑されたのは、ヒトラーの暗殺計画にかかわったからだった。これは単なる嫌疑ではない。非暴力を説き、徴兵すら拒んだ経験がある彼が、主体的に下した決断だった。
ファシズムとたたかう。それはコルシア書店の原点でもあった。「書店」の創設者で、神父でもあるダヴィデもカミッロも、ファシズムと戦ったレジスタンス、イタリアでいう「パルチザン」だった。その言葉を「羅針盤」にしたというサン=テグジュペリ、スペインの独裁を批判したジョルジュ・ベルナノス、そしてシモーヌ・ヴェイユもまた、ファシズムという現代の悪とたたかった人たちだった。『コルシア書店の仲間たち』の「銀の夜」にはこんな一節があった。
「神を信じるものも、信じないものも、
みないっしょに戦った」
ダヴィデは、ミラノ大聖堂で共産主義者の唱歌である「インターナショナル」を歌ったことがあるというほど開かれた人だった。その言動を見た目通りに受け止めるだけでは、彼が司祭でいる理由も理解できないかもしれない。しかし、彼だけでなく、その仲間たちも信仰を手放すことはなかった。たとえ教会が、ミラノからの「追放」を命じてもダヴィデは一介の司牧者であることを止めなかった。それは須賀も同じである。彼女が、時代の教会に対してときに厳しい見解をもっていたことはイタリアに行く以前に書かれた文章からも窺(うかが)える。しかし、信仰者であることは止めない。
おそらく彼、彼女たちは、真の意味で悪とたたかい得るのは、世にいう善ではなく、聖なるものであることをどこかで感じていたのではないだろうか。そして、聖なるものとのつながりは、人が、おのれと他者の弱さを受け入れたところに始まることも、深く体得されていたように思われる。
今、私たちは、須賀敦子とその仲間たちと同質の試練に対峙しなくてはならない境遇にいるのかもしれない。そのとき彼女とその同志の軌跡は、私たちにとって、かけがえのない道標になるだろう。そこに私たちは、おのれの「弱さ」と向き合うという暗夜の経験の彼方に、単なる力強さを超えた、容易に折れることのない「勁(つよ)さ」を発見するのである。
(「青春と読書」7月号より転載)
新着コンテンツ
-
インタビュー・対談2025年07月08日
 インタビュー・対談2025年07月08日
インタビュー・対談2025年07月08日桜木柴乃「波風立てずに生きる器用さを、ちょっと残念だなと感じる大人に読んでほしい」
著者五十代の最後を飾る、集大成的な短編集である本作。仕事に対する現在の思いや、短編を書く面白さをうかがいました。
-
お知らせ2025年07月04日
 お知らせ2025年07月04日
お知らせ2025年07月04日すばる8月号、好評発売中です!
演劇界注目の劇作家・演出家ピンク地底人3号さんによる初の小説を掲載! 遠野遥さんの短期集中連載も最終回を迎えます。
-
インタビュー・対談2025年07月04日
 インタビュー・対談2025年07月04日
インタビュー・対談2025年07月04日石井遊佳×藤野可織「魂を自由にする虚構の力」
ホラー愛好家を自認する藤野さんは石井さんの新作に詰まった四つの物語をどう味わい、そこに何を見つけたのか。
-
新刊案内2025年07月04日
 新刊案内2025年07月04日
新刊案内2025年07月04日給水塔から見た虹は
窪美澄
2人の“こども”が少しずつ“おとな”になるひと夏を描いた、ほろ苦くも大きな感動を呼ぶ、ある青春の逃避行。
-
新刊案内2025年07月04日
 新刊案内2025年07月04日
新刊案内2025年07月04日青の純度
篠田節子
煌びやかな「バブル絵画」の裏に潜んだ底知れぬ闇に迫る、渾身のアート×ミステリー大長編!
-
新刊案内2025年07月04日
 新刊案内2025年07月04日
新刊案内2025年07月04日情熱
桜木柴乃
直木賞受賞作『ホテルローヤル』、中央公論文芸賞受賞作『家族じまい』に連なる、生き惑う大人たちの物語。