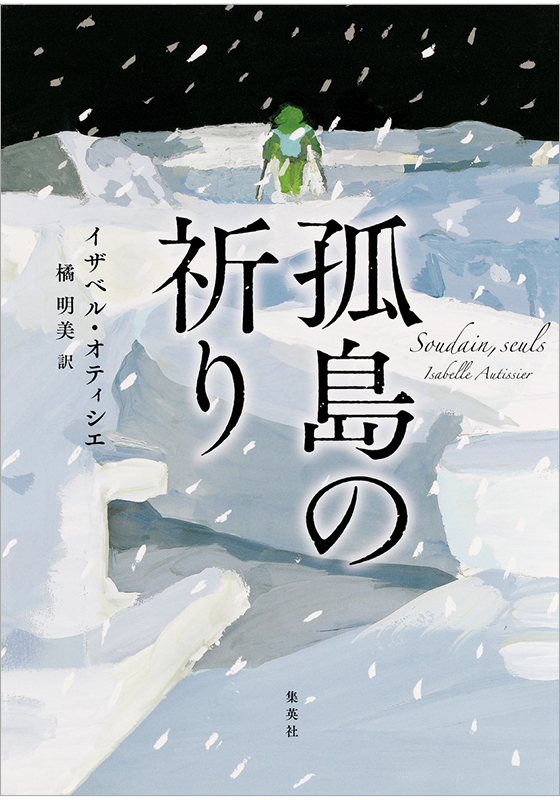プロフィール
-
リアノン・ネイヴィン (Rhiannon Navin)
ドイツのブレーメンで育つ。広告エージェント業界で働く中でニューヨークに渡り、結婚したのちに退職。現在はニューヨーク郊外で、3人の子供と夫、猫2匹犬1匹と共に暮らしている。デビュー作である本書は、17ヵ国で版権が取得された。
-
越前 敏弥 (えちぜん・としや)
1961年生まれ。文芸翻訳者。東京大学文学部国文科卒業。著書に『文芸翻訳教室』(研究社)、『翻訳百景』(角川新書)など。訳書にダン・ブラウン『オリジン』(KADOKAWA)、同『ダ・ヴィンチ・コード』(角川文庫)、E・O・キロヴィッツ『鏡の迷宮』(集英社文庫)、『世界文学大図鑑』(三省堂)、キャロル・ボストン・ウェザーフォード作/ジェイミー・クリストフ画『ゴードン・パークス』(光村教育図書)など多数。
【書評】評者:宮下奈都(作家)
また、歌が聞こえる日まで
ある日、小学校に銃撃犯が侵入し、無差別に銃を撃つ。19人が犠牲になる。主人公は、その小学校に通う6歳の少年ザックだ。ザックには、父親と母親、そして10歳の兄アンディがいる。襲撃の最中のなまなましい描写が続き、ようやく解放されて母に抱きしめられる場面から、物語は転がっていく。「アンディは?」──兄のアンディは、銃弾に倒れていた。
平仮名の多い文は、ザックが6歳だからだ。6歳の頭と心で、理解できることも、できないことも、手に負えないところも、そのまま語られていく。たとえば、悲嘆に暮れた母親が少しずつおかしくなっていくことに、ザックはどう対処していいかわからない。ただつらくて、寂しくて、涙をこらえる。父親もまた、大きな助けにはならない。肝心なところでザックの心に寄り添うことができない。ザックは、ひとりで、あるいは、死んでしまったアンディと対話しながら、なんとか生きのびる方法を手探りしていく。
登場人物ひとりひとりの造形が素晴らしい。頭がいいってどういうことか、やさしいってどういうことか、何度も考えさせられる。希望はある。でも、絶望もある。手を差し伸べてくれる人がいる。でも、出した手を引く人もいる。そうしてついにザックが胸に抱く決意がけなげでいじらしい。まわりの大人たちには見えなかったものが、6歳の少年だからこそ見える。無垢だから、というだけでなく、この子だけが兄の魂に寄り添おうとしたからではないか。
家族はやさしさを取り戻すけれど、問題はすべて解決したわけではない。母には母の、父には父の、そして加害者側の家族にも、他の犠牲者の家族にも、学校にも、報道陣にも、課題は残されたままだ。そこが、とてもリアルだと思った。私たちにできることはなんだろう、と考える。ザックを救うために、それ以前に、アンディを救うために、できること。でも、今はともかく、ザックと家族のこれからを祈ろうと思う。
宮下奈都(みやした・なつ)●作家
(「青春と読書」2月号より転載)
担当編集より
小学校に、「じゅうげき犯」がきた。ぼくのお兄ちゃんが死んだ——アメリカの小学校で起きた銃乱射事件。兄を失った6歳の少年の視点から家族の絆を描いた小説『おやすみの歌が消えて』2019年1月4日発売
ニューヨーク近郊の町。6歳の少年ザックは、小学校での授業中に「パン パン パン」という奇妙な音と叫び声を聞く。はじめは「ゲームの音にそっくり」だと思ったザックも、前に経験した「ひなんくんれん」とは全く違う早口で焦った声の校内放送、担任教師が通報する電話の内容に、「じゅうげき犯」がこの学校に来たのだと知る。
担任の指示で教室のクロゼットに隠れ、無事助かったザックだが、10歳の兄アンディは犠牲者のひとりとなってしまった。死者19名。そして警察に射殺された犯人は、ザックやその母が長年慕っていた用務員チャーリーの、19歳の息子だった──。
*
本書は瞬く間に17か国に版権が売れた、衝撃のデビュー作です。3児の母である著者リアノン・ネイヴィンはインタビューで、2012年サンディフック小学校で起きた銃乱射事件によって、我が子と同じ年の子供たちが犠牲になってしまったこと、また我が子が学校で『悪い人』から隠れる避難訓練をしていると知ってショックを受けたことが、本書を執筆するきっかけとなったと語っています。子供たちは『悪い人』から隠れて、実際の銃撃から生き延びるなくてはならない社会に生きていると痛感した、とも。
アンディを失い、失意と混沌にのまれてしまう一家。憔悴しきった母親はもう「おやすみの歌」をザックに歌ってはくれず、父は何か秘密を抱えてもいます。ザックは悪夢に悩まされ、おねしょをするようになります。そんな中ザックが家の中で見つけた「ひみつ基地」、それは死んだ兄の部屋のクロゼットでした。一方、母親はチャーリー夫妻に対して監督保護責任を追及しようと画策し、マスコミに煽られはじめ……。
物語は全編とおして、6歳の少年の無垢な目線で語られていきます。原文は非常に容易な英語で綴られているのですが、翻訳者・越前敏弥さんのアイディアで、「小学3年生までの漢字を使用(例外あり)」となりました。ひらがなが多い文体から、子供のいたいけさ、痛ましさが突き刺さる、素晴らしい訳文です。ぜひご一読いただければ幸いです。(K.S.)
新着コンテンツ
-
インタビュー・対談2025年07月08日
 インタビュー・対談2025年07月08日
インタビュー・対談2025年07月08日桜木柴乃「波風立てずに生きる器用さを、ちょっと残念だなと感じる大人に読んでほしい」
著者五十代の最後を飾る、集大成的な短編集である本作。仕事に対する現在の思いや、短編を書く面白さをうかがいました。
-
お知らせ2025年07月04日
 お知らせ2025年07月04日
お知らせ2025年07月04日すばる8月号、好評発売中です!
演劇界注目の劇作家・演出家ピンク地底人3号さんによる初の小説を掲載! 遠野遥さんの短期集中連載も最終回を迎えます。
-
インタビュー・対談2025年07月04日
 インタビュー・対談2025年07月04日
インタビュー・対談2025年07月04日石井遊佳×藤野可織「魂を自由にする虚構の力」
ホラー愛好家を自認する藤野さんは石井さんの新作に詰まった四つの物語をどう味わい、そこに何を見つけたのか。
-
新刊案内2025年07月04日
 新刊案内2025年07月04日
新刊案内2025年07月04日給水塔から見た虹は
窪美澄
2人の“こども”が少しずつ“おとな”になるひと夏を描いた、ほろ苦くも大きな感動を呼ぶ、ある青春の逃避行。
-
新刊案内2025年07月04日
 新刊案内2025年07月04日
新刊案内2025年07月04日青の純度
篠田節子
煌びやかな「バブル絵画」の裏に潜んだ底知れぬ闇に迫る、渾身のアート×ミステリー大長編!
-
新刊案内2025年07月04日
 新刊案内2025年07月04日
新刊案内2025年07月04日情熱
桜木柴乃
直木賞受賞作『ホテルローヤル』、中央公論文芸賞受賞作『家族じまい』に連なる、生き惑う大人たちの物語。