
内容紹介
息ひとつ吸いてこの世に生まれ来る ものみな息を吐きて逝くなり
二十五歳の若い頃、『ベルサイユのばら』の中で、オスカルが死を目前にして亡きアンドレに問うシーンを描いた。
「苦しくはなかったか? 死はやすらかにやってきたか?」
あの当時でも、私にとっては真剣な問いかけだった。六十代では何故か、老いや死に対して居直れたつもりでいたが、七十歳を越えた今になって、まさに一層切実な問いとなりつつある。
(本文「老いと向き合って」より)
愛すること、生きることに真摯に向き合い、数々の傑作漫画を生み出してきた著者が、短歌に託して想いを綴る。
プロフィール
-

池田 理代子 (いけだ・りよこ)
漫画家、声楽家。1947年大阪府生まれ。東京教育大学(現・筑波大学)在学中の67年に「バラ屋敷の少女」でデビュー。72年に連載を開始した『ベルサイユのばら』が空前の人気を博す。80年『オルフェウスの窓』で日本漫画家協会賞優秀賞を受賞。95年、47歳で東京音楽大学声楽科に入学。卒業後はソプラノ歌手として舞台に立つ。オペラの演出も手掛けており、2021年にはフィンランドにおいて、書下ろしオペラ『眠る男』を上演予定。2009年、フランス政府からレジオン・ドヌール勲章を授与される。「塔」短歌会会員。2017年より熱海在住。
父と戦争
八月十五日が近づくたびに、テレビでは、あの戦争のドキュメンタリー番組を放送する。今年はコロナ禍で異例の形にはなったが、いつもならちょうど甲子園では、高校球児たちの熱闘が繰り広げられている時期だ。
どちらも観なくてはならないと意気込む私は、この時期、慣れないビデオ収録のボタンを押すための操作で、時々パニックに陥ることさえある。土と汗にまみれ懸命に白球を追う高校球児たちの戦いが愛しいのは、彼らの姿があの戦争とどうしても重なってしまうからだ。
かつてこんな年齢の、まだ幼ささえ残る少年たちが、あの戦争に駆り出されてその命を落とした。
私は、八月十五日を甲子園球場で戦う高校球児たちの姿に、八月十五日を生きて迎えることのできなかった人々の姿をどうしても重ねてしまう自分の感傷を、哀しくも恥ずかしくも疚しくも感じつつ、テレビの画面にこの時期見入る。
そしてまた、あの戦争のドキュメンタリーフィルムの、粗い画像のモノクロ画面の中に、もしや若かりし父の姿でも見つけることができはしないかと、誇大妄想にも等しいような一縷の望みを抱いて。
こんな私だが、若い頃はずっと、中国や南方に出向き現地の人々に辛い思いをさせたであろう日本軍兵士に対して、憤りと憎しみを抑えることが出来なかった。その思いが、あの戦争について父と語る時間を、私から遠ざけた。
父は、徴兵されて中国にも行き、そして南方にも行った。多くの日本軍兵士たちが、全滅に近い戦いを強いられた南方の島で、父は生きて捕虜となり、日本に帰ってきてくれた。そして母と結婚し、私が生まれた。
自分をこの世に生み出してもらえたというその奇跡を、年を経るごとに私は感謝するようになっている。あれほどの戦いを生き抜いて帰ってきてくれた父にも、ただただ感謝の思いしかない。
そして、何にせよ生きて祖国に帰ってきてくれた兵士たちに、ただ感謝と労りの思いしかない。
南方の戦を生きて父は還る 命を我につながんがため
行く先も知らぬ船底に命なきものと俘虜らは覚悟を決めしか
船底より甲板に出されし俘虜らみな眼前の富士に向かいてありぬ
戦友の声の限りに泣きしとう この富士の山わが祖国よと
南方のいずれの島とも聞かざりき 若くとがりし娘にてありけり
戦争に行かざりしことを恥じ 戦友に遅れしことを恥ずる兵もあり
手榴弾一個ばかりの命にて 語れぬ日々を兵士は生きたり
【書評】 喪失が芸術へ変わる時
評者・中江有里(女優、作家)
二十代で漫画が大ヒット、四十代で声楽を学び、ソプラノ歌手として活動する著者が、これまでの人生を表わすのに選んだのは短歌。歌人・池田理代子の第一歌集である。
短歌とエッセイで11のテーマを綴った本書は、徴兵された父のエピソードから始まり、母へと続く。
「母を語ることは、まさに自分を語ることだ」とあるように、著者は母と二人三脚で歩んできた。母が娘の人生に過剰に侵食したとしても、最終的に赦していく。愛憎半ばするのが、親子の宿命なのかもしれない。
特にわたしが気になったのは、女性としての喪失感をしたためた歌だ。
〈作品は男ものこす 我はただ 女に生まれた理由を知りたし〉
自らを〈子を容れる器〉と表わした歌もあり、子を生さずに老いていった自分を見つめている。表現者にとって作品は我が子同然。そして我が子を得られなかった気持ちも作品となる。
エッセイと交互に紹介される短歌はおそらく現実世界では決して明かせなかった声なのだろう。
迫りくる「老い」「死」についてこんな歌がある。
〈美しき老いなどないと知っていて あほらしく語るインタビュアーに〉
若いこと、美しいことに重きをおくような風潮に対し、表向きはうなずきつつも否定する。ただ「老い」に従ってあきらめるのではなく、自らの人生に正直に対峙する。「初恋」と「最後の恋」の章はそんな著者のまっすぐな思いがあふれる。
好きな人から愛されるわけがない、その一点は初恋も最後の恋も同じ。特に恋愛に関してはどんなに齢を重ねても人は達観などしない。気付けば恋に落ち、劣等感に苛まれ、不安に駆られ、自分が自分でなくなってしまう。
〈悠然と二十五年を遅れ来て 我を愛すとなど君のいう〉
幸せな結末のようにみえるが、「老い」が迫る事実は変わらない。それもまた歌になる。喪失は、紙の上で昇華する。
新着コンテンツ
-
新刊案内2025年06月26日
 新刊案内2025年06月26日
新刊案内2025年06月26日筏までの距離
水原涼
デビュー作で芥川賞候補に挙がった著者が贈る、わたしとあなたの8つの物語。
-
インタビュー・対談2025年06月20日
 インタビュー・対談2025年06月20日
インタビュー・対談2025年06月20日宇山佳佑×檜山沙耶(フリーアナウンサー)「風が吹くたび、物語が生まれる」
ウェザーニューズで気象キャスターとして活躍し、その後も活動の幅を広げる檜山沙耶さんと作品、風、お天気について語っていただきました。
-
お知らせ2025年06月17日
 お知らせ2025年06月17日
お知らせ2025年06月17日小説すばる7月号、好評発売中です!
新連載はいずれも小説すばる新人賞出身の佐藤雫さん、神尾水無子さんの2本立て!
-
お知らせ2025年06月17日
 お知らせ2025年06月17日
お知らせ2025年06月17日本日開店、「スキマブックス」!!
文芸ステーションに新しい読みもののコーナー「スキマブックス」がオープンしました!
-
スキマブックス2025年06月17日
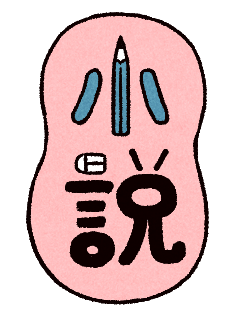 スキマブックス2025年06月17日
スキマブックス2025年06月17日今度こそ許すまじ春野菜といんげん豆の冷製スープ事件
結城真一郎
彼氏が浮気をしているのではないかと疑った大学生は、「あるレストラン」に浮気調査を依頼するが――。
-
インタビュー・対談2025年06月17日
 インタビュー・対談2025年06月17日
インタビュー・対談2025年06月17日堂場瞬一「日本政治の未来をフィクションで問う」
堂場瞬一さんの通算195冊目の作品にして、実験的政治小説第二弾『ポピュリズム』の世界観を語ってもらった。


