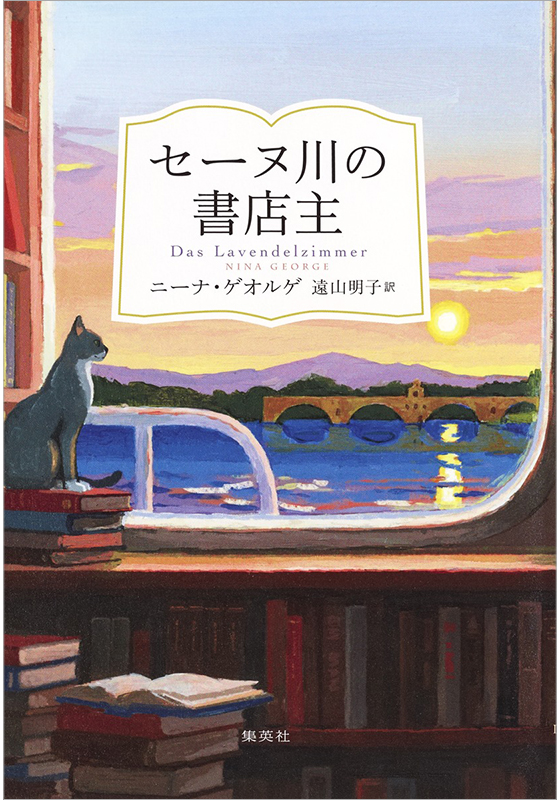プロフィール
-
ユーディト・W・タシュラー (Judith W. Taschler)
1970年、オーストリアのリンツに生まれ、同ミュールフィアテルで育つ。外国での滞在やいくつかの職を経て大学に進学、ドイツ語圏文学と歴史を専攻する。国語教師として働き、2011年『Sommer wie Winter(夏も冬も)』で小説家デビュー。現在は専業作家として家族とインスブルックに在住している。2013年に発表された『国語教師』が2014年度のフリードリヒ・グラウザー賞長編賞を受賞。その後も精力的に執筆を続けており、最新作『誕生日パーティー』は邦訳2作目にあたる。
-
浅井 晶子 (あさい・しょうこ)
1973年生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程単位認定退学。2003年マックス・ダウテンダイ翻訳賞受賞。2021年ジェニー・エルペンベック『行く、行った、行ってしまった』(白水社)で日本翻訳家協会賞翻訳特別賞を受賞。そのほか訳書にパスカル・メルシエ『リスボンへの夜行列車』、イリヤ・トロヤノフ『世界収集家』(以上早川書房)、トーマス・マン『トニオ・クレーガー』(光文社古典新訳文庫)、エマヌエル・ベルクマン『トリック』、ローベルト・ゼーターラー『ある一生』(以上新潮クレスト・ブックス)、ユーディト・W・タシュラー『国語教師』『誕生日パーティー』(以上集英社)など多数。
訳者あとがきより(抜粋)
物語は、オーストリアの小学生ヨナスが、父の50歳の誕生日を祝うパーティーに、サプライズゲストとして両親の幼馴染テヴィを招待するところから始まる。
ただの幼馴染ではない。ヨナスの父キムはカンボジア出身で、少年のころポル・ポト政権の大虐殺を生き延びた経験の持ち主だ。政権最末期、ジャングルを抜けてタイを目指したキムは、瀕死の少女を背負っていた。それがテヴィだ。ふたりはその後、難民として一緒にオーストリアへ来て、田舎の家庭に引き取られた。やがてテヴィは家を離れ、フランスの伯母のもとで暮らすようになる。オーストリアに残ったキムは、後に受け入れ家庭の娘イネスと結婚し、ヨナスを含めて3人の子供が生まれた。
キムは家族に対して、カンボジアでの子供時代をなにも語ってこなかった。テヴィについても、子供たちはほとんど知らない。だが末っ子のヨナスは、いまは音信不通になっているものの、テヴィは両親にとって家族同然のはずだと考え、再会をお膳立てしてやろうと思いついたのだった。
キムの誕生日の当日、子供たちに伴われて、テヴィがキムとイネス夫妻の前に現れる。現在はアメリカに暮らすテヴィは、富裕な都会人であることが一目でわかる洗練された女性だった。ところが、子供たちの期待どおりの驚きと喜びはなく、両親とも戸惑いをあらわにする。しかもテヴィは唐突に、今日はキムの本当の誕生日ではないと言い出す─―
本書『誕生日パーティー』は、2019年に刊行されたユーディト・W・タシュラーの最新作だ。2019年に日本に紹介され、大きな反響を得た『国語教師』同様、時代も舞台もばらばらの場面が、次々に入れ替わる。キムの50歳の誕生日パーティーが催される週末。キムの妻イネスの子供時代。イネスの母モニカの日記。そして圧巻なのが、70年代のカンボジアを舞台にした場面だ。向学心に溢れた貧しい漁師の息子が、貧富の差のない理想の社会を夢見てクメール・ルージュの一員となり、やがて残虐な行為に手を染めざるを得なくなっていく過程が、息詰まる筆致で描かれる。
全編を通して、ミステリらしい事件が起きるわけでもないのに、なにかがおかしい、なにかこちらの知らないことがある、という感覚を抱かせて、読者をぐいぐい引っ張っていくタシュラー得意のストーリーテリングは、本書でも健在だ。キムとテヴィは互いの過去をどこまで知っているのか。テヴィはキムに対してどんな感情を抱いているのか。命がけでともにジャングルを抜け、兄妹だと偽って一緒にオーストリアへ来るほどの固い絆がありながら、なぜ大人になったふたりは何年も音信不通だったのか─小さな違和感から大きな疑問まで、パズルのピースが足りない、というもどかしさが募り、読者は次から次へとページをめくることになる。パズルの全景が一気に目の前に現れる瞬間には、上質なミステリの謎解きを読むようなカタルシスがある。
とはいえ、吸引力のある構成にばかり目が行きがちだが、作家タシュラーの真骨頂は、丁寧に描かれる人間ドラマにこそある。カンボジアからの難民であるキムとテヴィを里子として受け入れたのは、オーストリアの田舎に暮らす、祖母、母、娘の三世代母子家庭だった。家族それぞれの人生と、彼らを互いに縛りつけ、傷つけ合うことになった軋轢(あつれき)や誤解、それでも切れない家族の絆。本書はなによりもまず家族の物語だ。
【中略】
本書のクメール・ルージュ時代の描写は、そのあまりの凄惨さに、ときに読むのがつらくなるほどだが、決して歴史的事実の説明や残酷な出来事の羅列では終わっていない。どんな時代を背景にしようと、タシュラーが描き出すのは人間の葛藤であり、人と人との軋轢、愛情と信頼だ。正義感に溢れた純粋な人間が、その正義感ゆえに悪へと引きずり込まれていく過程。自分が生き延びるため、なにより家族を守るために、他者を犠牲にせざるを得ないことの葛藤。時代と運命に翻弄(ほんろう)される人間の苦悩と悲劇に、読者は圧倒されることだろう。
【以下略】
浅井晶子
新着コンテンツ
-
インタビュー・対談2025年07月08日
 インタビュー・対談2025年07月08日
インタビュー・対談2025年07月08日桜木柴乃「波風立てずに生きる器用さを、ちょっと残念だなと感じる大人に読んでほしい」
著者五十代の最後を飾る、集大成的な短編集である本作。仕事に対する現在の思いや、短編を書く面白さをうかがいました。
-
お知らせ2025年07月04日
 お知らせ2025年07月04日
お知らせ2025年07月04日すばる8月号、好評発売中です!
演劇界注目の劇作家・演出家ピンク地底人3号さんによる初の小説を掲載! 遠野遥さんの短期集中連載も最終回を迎えます。
-
インタビュー・対談2025年07月04日
 インタビュー・対談2025年07月04日
インタビュー・対談2025年07月04日石井遊佳×藤野可織「魂を自由にする虚構の力」
ホラー愛好家を自認する藤野さんは石井さんの新作に詰まった四つの物語をどう味わい、そこに何を見つけたのか。
-
新刊案内2025年07月04日
 新刊案内2025年07月04日
新刊案内2025年07月04日給水塔から見た虹は
窪美澄
2人の“こども”が少しずつ“おとな”になるひと夏を描いた、ほろ苦くも大きな感動を呼ぶ、ある青春の逃避行。
-
新刊案内2025年07月04日
 新刊案内2025年07月04日
新刊案内2025年07月04日青の純度
篠田節子
煌びやかな「バブル絵画」の裏に潜んだ底知れぬ闇に迫る、渾身のアート×ミステリー大長編!
-
新刊案内2025年07月04日
 新刊案内2025年07月04日
新刊案内2025年07月04日情熱
桜木柴乃
直木賞受賞作『ホテルローヤル』、中央公論文芸賞受賞作『家族じまい』に連なる、生き惑う大人たちの物語。