
時間がないけど読書がしたい!
そんなあなたのための、スキマ時間で楽しめるネット上の小さな本屋さん。
スキマブックス、開店します。
「昨日は蛍」 其ノ弐
森晶麿
【30分で読める】【小説】
俳人・虚池空白と編集者の古戸馬が紛れ込んだ、ある怪しい村の秘密――『虚池空白の自由律な事件簿』初のスピンオフ!
2025年10月08日
4
紫がかった霧に目を凝らした。その向こう側に、地上の楽園があった。伊藤の言葉は嘘ではなかった。円陣を組む赤い麻の浴衣姿の美しい女たち。その表情は幸福そのものだった。彼女らは歌う。
〈葡萄酒は豊か、私のめぐみ、大地の血潮、めぐりゆくめぐみ〉
歌謡曲に近い親しみのある曲調。祭りでも開かれているのか? ひときわ目をひくのが、円陣の中央のドラム缶に入っている女性だ。一人だけ唇が溶けたようなロックなイラストのTシャツを着ている。そのうえ、服装以上に派手な顔立ちの美人ときている。
「真ん中にいる方は、昨日到着されたゲストの女性です。彼女の入っているドラム缶には収穫したての葡萄が入っています。ああして歌に合わせて葡萄を踏み、葡萄酒に変えます。それが、ここの人たちの貨幣代わりとなるのです」
「葡萄酒が?」
「ここの葡萄酒は、無農薬で他県でもかなり評判がいいのです」
ドラム缶の中の彼女を凝視する。その肉感的な唇、知性と魔性を天秤にかけるような瞳。すべてが好ましく特別に感じられた。
「村でとれない農作物やその他生活に必要なものは葡萄酒を売った金で賄います。もちろん村の貯金もあります。ここは電気もガスも水道も通っていますから。公共料金支払いのための最低限の現金がいるんですよ」
「すべて自分たちで行なっているんですね。すごいなぁ……」
言葉とは裏腹に、僕は会話に集中していなかった。ドラム缶の女性に見とれていたのだ。
「ようこそ、霧蛍村へ」
振り返ると、いつの間にか、三人の男たちがそこに立っていた。いずれも黒い甚平を羽織っている。左右の男たちの没個性的な顔立ちに比べ、真ん中の男の達磨みたいな風貌が強烈だった。小柄だが恰幅がよく、大きなぎょろ目が場の空気を支配した。
達磨は「風間です」と深々頭を下げた。男の首から掛けられたネックレスに、例の二足で立つ黒甲虫が揺れていた。
また──こっちを見ている。
伊藤の紹介によれば、風間は霧蛍村の中間管理職的な立場らしい。
「今月はゲストに恵まれていますな。ほら、あそこの女性も昨日からいらしているゲストです」と風間はドラム缶の中の女を示した。
「あの方は恋人とご旅行でいらっしゃっていましてね。はっはっは、我々としても、残念です。あと二十若ければ立候補するところ」
読まれたな、と虚池が耳元で囁いた。うるさいよ、とこれも小声で答えた。虚池は、学生時代からの僕の好みを知り抜いている。
僕は話題を変えるついでにあの碑のことを尋ねてみることにした。
「我々はあそこの碑に書かれていた落書きを取材しに参りました」
「落書き?」
風間の眉間にしわが寄る。
「ええ。〈捨てた蛍光性の過去〉。ご存じありませんか?」
「捨てた蛍光性の過去……? 申し訳ないが、そんな落書きは見たことがないですね。そもそも、村にあるものはすべて共同財産。村の人間が単体で落書きをすることはあり得ません」
「ですが……」
僕は伊藤のSNSの画像のことを話そうとしたが、風間はそれ以上話を聞くまいとするように顔を背けた。
「では、このお二人を宿へご案内してもらえますか?」
風間が伊藤に言うので、僕は慌てた。
「あの、できれば今日村長にお会いしてお話を伺えたら、と」
それができれば、宿泊なぞせずに済む。だが風間は顔をしかめた。
「村長は集会の公務以外、予定が埋まっています。明日がよいかと」
「……そうですか、それじゃあ仕方ないですね」
「都会の方はお忙しいのでしょうな。でも一泊なされば気持ちも変わります。俗世の垢を落とす最高のおもてなしをしましょう」
「はあ……それはどうも……ところで、そのネックレスはすごいですね。風変わりといいますか……」
すると、風間は、嬉しそうに笑った。
「面白いデザインでしょ? 以前のテーマパークで売られていたグッズです。我々の村も、人をもてなす心、蛍や自然環境を大事にする思いは〈ほたるとぴあ〉に相通じると思っています」
それまでの堂々としすぎた雰囲気からすれば、やや早口だった。まるで、こちらを言いくるめようとしているような、そんな感じだ。
この風間という男は何を隠したがっているのか?
僕からの追及を逃れようとしたのか、あるいは──。
「とにかく、楽しんでお帰りください」
風間はそう言うと、左右の二名とともにその場を去った。
僕はすかさず伊藤に尋ねた。
「なぜ彼は碑の落書きを知らなかったのでしょう?」
「僕はゲストだから目に入るものすべて珍しくて写真に収めましたが、彼らには日常の一部ですからね。落書きに気づかなかった可能性はあります」
ところが、そこへ虚池が割って入った。
「あるいは──落書きをなかったことにしたいか」
虚池のその指摘に、伊藤は目を大きく見開いた。
「虚池さんは面白いことを考える方ですね。考察は尽きないのでしょうが、まあまずはホテルに参りましょう」
伊藤に促されて、不意に遅れて疑問がわいてきた。
「そういえば、なぜ彼らではなく、ゲストのあなたが案内を?」
「驚くのも無理はないですね。じつは、ここではゲストは偉くないんです。滞在を許されただけですから。新たなゲストが現れたら、その案内役は一つ前のゲスト。持続可能な村づくりの一環です」
その回答から、伊藤が案内役の任を嫌がっていないことはわかる。
「セルフうどんみたいなものでしょうかね。なんだか、ぞんざいな扱いを受けているだけのような気もしますが……」
「ふふふ。でも僕は今日、長期滞在者と認められて、この甚平までもらえた。いわば、村の一員と見做されたわけです。大丈夫、お二人もそのうちもらえます」
そのうち──そこまで長居する気はなかったが、黙っていた。
やがて、伊藤は川沿いを西に向けて歩きだした。僕の興味は、ひたすら消された野良句に集中していた。誰が、いつ、何のために消したのか。それは野良句の作者なのか。またべつの者なのか。
だが、虚池は僕の思考を先回りするように言うのだった。
「君が何を考えているかはおよそ想像がつくね。そしてそいつは無駄だ。前提一つでまったくの無駄な思考とわかる」
「ん? どういう意味? さっぱり意味が……」
「だろうね。いいんだよ、今はそれで」
こういう時、虚池はいつだって不親切なのだ。そのせいで悶々としながら十分ほど川沿いを進んだ。さらに五分ほど歩いただろうか、黒のタイルで覆われた平たく細長い建物の前で伊藤は足を止めた。
「ここが本日お泊まりいただく〈ほたるホテル〉です」
建物の最上部だけが赤いのは、蛍を意識したデザインだからか。結果的にわりと禍々しい印象の外観に仕上がっている。
伊藤に付き従い、恐る恐る中へと足を踏み入れた。
しかし、館内はその悪印象を払拭するかのように、明るく近代的だった。サザンオールスターズの昔のヒット曲がオルゴールでかかっているのも、親近感がわく理由の一つだった。
「この後、夜七時から歓待の劇があります」
「劇……ですか」
「それほど大げさなものではなくて、この村の目指す新世界のイメージを、ゲストに体感してもらう神聖な時間、といった感じでしょうかね。僕も先日初めて観ましたが、一見の価値はありますよ。それまで、ゆっくりお過ごしください」
伊藤はそう言いながら、廊下の突き当たりにある部屋のドアを開く。白い壁に囲まれた空間に、ベッドがナイトテーブルを挟んで二つ配置されていた。他にはものは見当たらない。恐ろしく簡素だ。
「お二人の部屋です。僕は手前の通路東側の部屋ですので、何かあれば呼んでください。ほかのゲストの方は手前の通路西側の部屋に」
「先ほどの、葡萄を踏んでいた女性のことですか?」
「はい、それと、その恋人です。では」
伊藤が自室に消える。最後の「その恋人です」のくだりが、改めて僕に注意を促すように聞こえたのは、疚しい気持ちがあるせいか。
5
「クジラ、リラックスしすぎだよ」
虚池は早々にベッドにダイブして、靴下まで脱ぎ始めている。
「当然だろ。時間まで寝るから起こしてくれ」
「あの落書きがなぜ消されたのか考えなくていいのか? さっき『前提一つでまったくの無駄な思考とわかる』とか言ってたけど」
「まだ材料が揃ってないのに考えるだけ無駄ってことさ」
「……だったら、せっかくだし、村を散策でもしようじゃないか」
「莫迦をいえ。眠りの世界ほどの楽園があると思うか?」
「君は偏屈王だ。とりあえず、もう一組のゲストに挨拶してくるよ」
虚池は僕の顔をちらりと見た。
「恋人がいるって言ってたぞ」
「べ、べつに口説くわけじゃない。ただお近づきの印に……」
内心の動揺を読まれるのは、今に始まったことではない。
「好きにしろ。君は惚れっぽいからな。新たなロマンスにときめきたい気持ちはわからないじゃない」
「だ、だからそんなんじゃ……」
「どうせ行くなら、その二人がなぜこの村へ来たのか、きちんと聞いておいてくれ」
「ん? どうして来たのか?」
「彼らは昨日の時点で到着してる。単なる見学や観光なら、たまたま我々と時期が重なっただけということになるが、もしも一昨日のあのSNSの投稿を見て来たというのなら、決断が早すぎる」
「早すぎたらダメなのかい?」
「べつに構わないが、事実は事実として整理しておきたい」
奔放な自由律俳句を詠むわりに、こうした事実確認には煩い。
「わかった。聞いておくよ」
僕には彼がなぜそんなことを気にするのか皆目わからなかった。どうでもいいじゃないか。人には人の目的があるものだ。
部屋を出ると、通路の壁に自然に目がいく。案内された時は気にも留めなかったが、廊下の壁には蛍の標本がずらりと飾られていた。ゲンジボタル、ヘイケボタル、ヒメボタル、マドボタル、オバボタル……それぞれの特徴や生息地について説明するボードもある。
縦横に交差した白い厚紙に張り付けられた蛍たちは、十字架のイエスを思わせた。恐らく〈ほたるとぴあ〉時代からの展示物だろう。
廊下の通路西側にあるドアをノックした。
「誰?」とくぐもった男性の声が返ってくる。例の恋人か。
「今日この村を訪れた者です。同じゲストということで、ご挨拶を」
ほどなくドアが開く。髪の長い上半身裸の男が現れた。猜疑心の塊のような目が、僕を見据えたまま「よろしく」と短く応じた。
「よろしくお願いします。僕は出版社の人間で……」
「木村といいます。木村ミツル。充電の充と書きます。N大二年生。で、あそこにいるのがリリ。〈瑠璃〉の〈璃〉で璃々。苗字は有名な名探偵と同じだから秘密らしいです。あ、そうそう俺たちミステリ研究会なんですよ」
木村が室内を振り返って顎で示した先には、下着姿でシャワールームへ向かう女の姿があった。さっき葡萄を踏んでいた女だ。作業から戻ってきたようだ。意表を突かれて、僕の頰は熱くなった。
「ま、また後ほどに……お寛ぎのところを、ごめんなさい」
「彼女はあんまり気にしませんから」
いや、こっちが気にするのだ。僕は俯くしかなかった。
「み、ミステリ研究会の方が……なぜこの村に?」
その問いに、不意に木村は笑みを消し、手招きをした。中へ入れということらしい。奥のほうでシャワーの音が聞こえる。すぐにお暇するぞ。そう自分に言い聞かせて中に入った。
木村はベッドに腰を下ろすと、声を落としてこう言った。
「俺たち、〈ほたるとぴあ〉の廃墟探訪に来たんですよ。まさかこんな村が出来てるなんて思いもしなくて」
「廃墟探訪に……それじゃあ、当てが外れましたね」
「まあね。それはまあいいんです。学生だし、暇が潰れればそれでよかった。だけど、問題が一つあるんですよ。じつは一日早くここへ着いたはずのメンバーが音信不通なんです。村の人たちに聞いても、ここへはそんな人間来ていないって言うばかりで……」
「その方がここに来たのは確かなんですか?」
「もちろんです。昨日の夜、ここに着いてすぐ撮影したものです。これは間違いなく彼の筆跡なんですよ」
彼が見せたスマホの画面には、あの川辺の碑が映っていた。
「これが証拠……つまりこれを書いたのがそのご友人なんですか?」
思いがけぬところに作者を知る者が現れた。
「マサシの筆跡だと思います。でもあいつらは証拠隠滅を図って今朝までにこれを消したみたいです」
ということは、昨夜までは野良句は消されていなかった?
聞き捨てならない一言だった。つまり、あの野良句が消されたのは今日僕たちが到着するまでの限られた時間ということになる。
「誰が消したとお考えですか?」
「さあ、とにかくこの村の連中ですよ」
どこまでを真に受けていいのかわからないが、興味深い見解ではある。ことのついでに野良句の意味についての見解を聞いてみようとしかけた時、シャワーの音がやんだ。
「し、失礼します……また後でゆっくりお話を」
「ちょっと。もう少し話していってくださいよ」
「……失礼します、ちょっと気分が」
逃げるように退散しながら、頭の隅には疑問が渦巻いていた。
なぜ──村人は昨夜まであった野良句をなかったことにしようとするのだろう?
6
集会場へは伊藤が案内してくれた。歩き始めてすぐ、伊藤が僕らそれぞれに団扇、手拭い、虫よけスプレー、水筒の入ったエコバッグを渡してきた。
「劇は長いので脱水症状対策です」
そんなことを言われたら、ワグナーの楽劇でも始まるのかと不安になってしまう。
「あ、ありがとう……ございます。助かります」
僕はエコバッグを受け取ると、その中から水筒を取り出した。蓋を外して、早速ひと口飲む。香草茶なことは匂いからわかった。加密列、薄荷、ほかにも入っている。香草本来の甘味が心地よい。
だが、虚池は「香草の匂いが苦手なので遠慮します」と水筒を返した。代わりに、虫よけスプレーのほうは向こう百年虫が逃げそうなくらいふんだんにかけていた。
道中、僕は団扇で扇ぎながら二人に木村たちとの会話を話した。
「なるほど、先に到着しているはずのご友人が書いた句だというわけか。何を根拠にそう断言するんだろうな」
虚池が怪訝そうに尋ねた。
「筆跡だと言ってたけどね」
「筆跡ねえ……それほど特徴があるとも思えないが」
すると、となりで聞いていた伊藤が苦笑した。
「木村さんには村の人たちも困っているようです。昨日も集会の席で村長に『マサシをどこに隠したんだ』なんて言いだすから、ひやひやしました」
「そういえば、伊藤さんは二日前にいらしたんですよね? マサシさんという方が訪れた現場に遭遇したりはしませんでしたか?」
「んん、僕は見てませんねぇ……もしかしたら僕より前に訪れて門前払いされた、とかいうこともあるとは思いますけど」
「門前払い? それはなぜです?」
虚池が鋭く質問を返した。
「僕みたいに村に興味がある場合はともかく、ここを廃墟と思って訪れる人はかなりの確率で門前払いされるらしいんですよ」
「なるほど──」
虚池はそう呟いたきり押し黙った。その間に、伊藤は橋を渡った。川はピンクから紫へと少しずつ色を深めつつあった。
虚池が考えているであろうことは、何となくわかった。廃墟と思って訪れる人を冷遇したい気持ちはわかる。しかし、それならば木村と璃々だって村に入れてもらえていないのではないのか?
「着きました。ここが、〈ひかりの広場〉です」
伊藤が足を止めたのは、村の中央のイベントスペースだった。楕円形のステージを、扇状に取り囲むように席が配されている。かつてはコンサートイベントでもやっていたのかもしれない。いまはそこかしこに村人たちがひしめき合って腰を下ろしている。
見られている──。不意に、そう感じた。それも一人や二人の視線ではなかった。露骨ではないが、村人たちが僕らを観察していることが肌でわかった。
「それにしても、日も暮れたのに、蛍が光っていないな」
虚池が周囲を見回してそう感想を洩らした。
「まだ時間が浅いだけじゃないかな。蛍なんて久しく見てないから楽しみだね」
「あんなの、ただのアトラクションだ。辰野がゲンジボタルの名所なのは確かだが、現在はほぼ移入種だと判明しているらしいしね」
「同じゲンジボタルなのに、移入種なんてあるのか」
「辰野の中でも蛍の名所として有名な松尾峡を知っているか? あそこは観光のために、他県の業者からゲンジボタルを大量に譲渡されたらしい。結果、本来の生態系は大いに乱れた。ここの蛍も、そうした移入種のせいで発光周期が異なるのかもしれない」
すると会話を聞いていた伊藤が口を挟む。
「蛍のことならご心配なく。劇の中で、素敵な光景をご覧になれます」
何かいたずらでも仕掛けるような笑みを浮かべると、「僕はちょっと作業の後片付けを手伝ってくるので失礼します。とにかく、楽しんでくださいね」と言い残して消えた。
ほどなく、最前列から「お、さっきの人、こっちこっち」との声。見れば、木村と璃々が陣取っている。璃々と目が合った。彼女が微笑むと、なぜか重力が消えたように気持ちが軽くなった。
「ちょうどいい。あの二人にはまだ聞いてみたいこともあるしな」
二人のもとへと向かう虚池を、慌てて追いかける。
「初めまして。虚池空白と言います。こちらは編集の古戸馬くん。俺の金づるです」
金づると紹介されて仕方なく金づるですと頭を下げると、璃々がくすくすと笑った。僕らは木村と璃々のすぐ後ろに陣取った。
虚池が木村に突然話しかけた。
「ご友人の行方がわからないと聞きました。あの碑の落書きの筆跡がご友人のものだとか」
「しー」木村は慌てて指を口に当てた。それから周囲を見回しつつ、「ええ、そうなんです」と声を落として応じた。
だが、肝心の虚池は声に気を配る気すらない。
「あの言葉の意味には、何か思い当たる節がありますか?」
木村は虚池の声の大きさに相変わらず心配そうに周囲を見つつ、顔を近づけてこう囁いたのだった。
「ええ、たぶん。あれは他の意味には取りようがない」
「ほう……具体的にどういう……」
虚池が重ねて尋ねようとした時だった。
突如、会話を遮って盛大に銅鑼が鳴った。次いで、客席の明りが消えて真っ暗になる。
その刹那――巨大な蛍が姿を現した。
いや、それは蛍ではなかった。
蛍の光を模した金箔の和装をした男だ。銀髪オールバックのその男は、海中のマンタが神秘的な動きを繰り返すように、周囲に静かに手を振りながらステージに向かった。
驚いたのは村人たちの歓声の大きさだ。「村長さま!」という声がそこかしこで洩れた。それだけで、この人物が単なる指導者の域を超えた存在なのだと感じられた。
すると、スピーカーからナレーションが流れた。
「光の神は下界を見下ろして言われた。『蛍よ、其方たちの仄かな光があってこその私なのだ。逆ではない』」
声の主はステージ脇に立つ風間のものだった。その言葉を聞くやいなや、村人たちは総立ちとなった。何が起こるのかこちらはまったく分からず固唾をのんで事態を見守る。どうやら単なる劇ではなさそうだ。もしや観衆参加型なのか。
やがて、金箔の和装男が、仰々しく芝居がかった調子で言った。
「蛍たちよ、今日も一日、元気にしていたのか? 答えたまえ」
一瞬耳を疑った。いま村人に〈蛍たち〉と呼びかけたのか? いや、そうか、これは劇なのか。つまり彼はいま〈光の神〉とやらを演じているわけだ。
「元気です!」「もちろん!」「神様!」
さっきまでの「村長さま」という声援は鳴りを潜め、いまは飽くまで劇中の人物として参加している。それにしたって、いちげんさんの我々には入り込みづらいことこの上ない。
風間が再びナレーションを続ける。
「光の神は、蛍たちのために楽園を作られ、皆を集めて言われた。『皆、この土地の空気を吸いなさい。そして輝きなさい。その空気は私の血。あなたたちの光はやがて私の身体に還る』」
そこで銅鑼が鳴る。二回、ゆっくりとその音が場内に浸透するまで、壇上の〈光の神〉は何も言わずに両手を広げていた。スポットライトがそこに集中し、眩い光に包まれる。
やがて、光の渦に吞まれ、光そのもののようになった村長が、朗々とした声で歌うように宣言した。
「蛍たちよ、君たちは皆素晴らしい。持続可能な奇跡の存在だ。今日も精一杯頑張った。社会と人権と物作りと、すべての発展のために生きる其方たちは尊い。この世界の代表たる蛍たちよ。もっと照らしたまえ。君たちの力こそが、明日の私の光の源──いざ行かん。新世界へ」
その言葉を合図に、銅鑼が連打された。それは、鼓膜の衝撃にとどまらず、骨を伝って心臓の鼓動を乱した。
〈光の神〉のねぎらいの言葉に感極まったものか、村人たち──いや、今は〈蛍たち〉なのか──はそこかしこで泣き始めた。嗚咽、号泣が幾重にも重なる。
これは一体──何なのだ? ここにいる村人たちを演者と捉えればいいのか、それとも劇に心を打たれた観衆と捉えるべきなのか。
心もとない気持ちで隣の虚池を見る。虚池はうたたね中だった。不謹慎な奴だ。木村はといえば、もう見慣れたものか退屈そうにしており、となりの璃々は気まずそうに俯いていた。村の外から来た者は、やはりこの空気に同調できないようだ。
そもそもSDGsの自治村で、こんな聖劇を見せられること自体想定外だ。これではまるで宗教ではないか。
すると、そんな我々の疎外感を読み取ったかのごとくナレーター役の風間がこう続けた。
「この新世界に、今宵は新たに招かれた者たちがいた。彼らはまだ光を知らないので、光の神と蛍たちの対話には戸惑うばかりであった。しかし、光の神は言われた。『素直であれ。心の解放こそ環境創生の鍵。まずは自身の心をSDGsに』と」
あのずんぐり体型の強烈な目が、僕らを見据えていた。どう考えても、それは劇中の台詞を装った僕らへのメッセージだった。
「光の神は言われた。『招かれし者たちよ、本来の姿をお見せなさい。さあ、あなたたちも皆輝ける蛍』」
その言葉を受けて、村人たちの目が僕たちに注がれた。そして、あたかもありもしない台詞を僕たちがしゃべりだすのを待つかのように銅鑼の一打一打の間隔が空いていく。
何か喋るべきなのか? だが、何を……?
ところが、その刹那のこと。
「俺は──ゴキブリで結構だよ」
いつの間にか目覚めた虚池が、ひねたことを言う。軽く小突いたが、ときすでに遅しだった。
「静止!」
銅鑼が完全に鳴りやむ。村人たちも涙を拭い各々顔を上げた。
それが劇の演出なのか何なのか、僕には皆目わからなかった。いや、僕だけではない。虚池や木村たちだって同じだっただろう。
ただ、村人たちに関して言えば、それがたとえ演出でなかったとしても、すぐに劇の一部に取り込むだけの一体感をもっているように見えた。
「そこの招かれし者よ」
やはりこれも演出なのか。判然とせぬまま、事の次第を見守った。もしかしたら、演出と見せかけて虚池が怒られる、ということもあり得るだろう。露骨に野次を飛ばしたのだ。劇を乱したと見做されても仕方がない。
だが、〈光の神〉の目は虚池ではなく前列、木村に向いていた。
「足を上げなさい」
「え? なに、俺が何をしたんですか……」
木村は動揺して周囲を見回した。
だが、周囲の目は、無感動にただ木村に注がれていた。
近くにいた村人二人が、一斉に木村の両腕を摑んで立たせた。
木村の足の下に、何があったのかは暗すぎて僕の位置からは見えない。だが、険しくなる風間の表情からは、嫌な予感しかしない。
「踏みましたね……あれほど注意しておいたはずですが?」
木村は足元を見て、わずかに後ずさった。
背後で、村人の誰かが「てるがみさまがお怒りになる……」と呟いた。てるがみ? 天照大神を想起するネーミングだ。何か土着の信仰でもあるのか。SDGsとは水と油にみえる。それとも、これもまた劇中の設定の一つに過ぎないのか?
「う、うそだ……俺じゃないです……俺じゃ……」
「村の愛すべき存在が天に召されました」
また銅鑼が鳴り響く。
風間の命令にしたがって、村人たちが木村を取り囲み、ついには神輿のように持ち上げた。暴れる木村はさながら逆さになった亀だ。
「やめろ……よせ……どうする気だよ……」
すると、〈光の神〉が立ち上がって告げた。
「其方を許します。これまでの生き方の何がいけなかったのか。別室でゆっくりと考えましょう。持続可能な社会のために。安心なさい。あなたの罪は許され、必ずや輝ける蛍となることができます」
銅鑼の連打が、鼓動を速める。村人たちが木村を抱えて連れ去った。これがもしもまだ劇なのだとしたら、木村はまさに劇という名の鯨に吞まれたようなものだった。
むろん、昨今のアミューズメントパークでは、こうした強引な観客巻き込み型の催事もあることはあるのだろうが──。
前方の璃々が戸惑いながら叫んだ。
「待ってください! 充をどこへ連れていくんですか?」
追いすがろうとする璃々を、虚池が取り押さえた。
「今は騒がないほうがいい。様子を見ましょう。まだ劇が続いています」
璃々は逡巡するような表情を浮かべていたが、やがて小さく頷いた。それから、力なくその場に頽れたのだった。
(つづく)
プロフィール
-

森晶麿 (もり・あきまろ)
1979年生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。日本大学大学院芸術学研究科博士前期課程修了。2011年、『黒猫の遊歩あるいは美学講義』で第1回アガサ・クリスティ―賞受賞。〈黒猫シリーズ〉の他『探偵は絵にならない』『切断島の殺戮理論』『名探偵の顔が良い 天草茅夢のジャンクな事件簿』『あの日、タワマンで君と』等著書多数。
関連書籍
新着コンテンツ
-
連載2026年03月13日
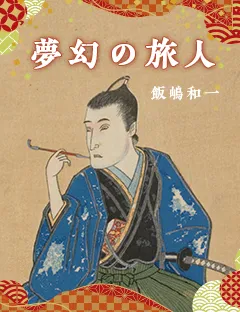 連載2026年03月13日
連載2026年03月13日夢幻の旅人
飯嶋和一
平賀源内の生涯を描く歴史大長篇。
-
インタビュー・対談2026年03月12日
 インタビュー・対談2026年03月12日
インタビュー・対談2026年03月12日トークイベント 永井玲衣×後藤正文「いまことばとは」
永井玲衣さんと後藤正文さんが言葉を通して今を考えるトークイベント「いまことばとは」の様子を再構成してお届けします。
-
お知らせ2026年03月06日
 お知らせ2026年03月06日
お知らせ2026年03月06日すばる4月号、好評発売中です!
特集のテーマは「道をゆく」。椎名誠さん×高田晃太郎さんの対談、駒田隼也さんの紀行ほか、小説、エッセイなど一挙16本立てです。
-
インタビュー・対談2026年03月06日
 インタビュー・対談2026年03月06日
インタビュー・対談2026年03月06日椎名 誠×高田晃太郎「自由に人は生きられる」
最新刊は逃避行がテーマの椎名誠さん。ロバを相棒に旅をしている高田晃太郎さんをお相手に、おふたりのこれまでの旅を振り返っていただきました。
-
新刊案内2026年03月05日
 新刊案内2026年03月05日
新刊案内2026年03月05日たったひとつの雪のかけら
ウン・ヒギョン 訳/オ・ヨンア
韓国を代表する作家のひとりウン・ヒギョンが、生きる孤独と哀しみ、そして人と人の一瞬の邂逅を描く、6篇の珠玉の短編集。
-
新刊案内2026年03月05日
 新刊案内2026年03月05日
新刊案内2026年03月05日劇場という名の星座
小川洋子
劇場を愛し、劇場を作り上げてきた人々の密やかな祈りがきらめく豊饒な短編集。




