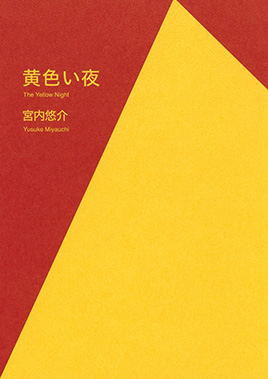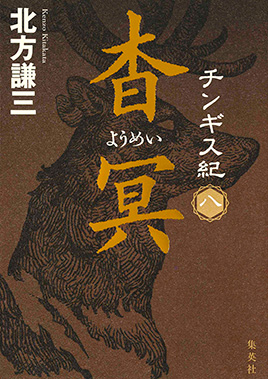刊行記念特別インタビュー
広島に奇跡の復興をもたらした歴史に迫る、感動の群像ノンフィクション──。石井光太著『原爆 広島を復興させた人びと』
アジアの路上で物乞いをする障がい者に密着したルポ『物乞う仏陀』でデビュー以来、貧困、殺人事件、医療、災害など、国や領域を問わず、知られざる事実や社会問題に光を当て続けている作家・石井光太さん。まもなく刊行される新刊は、広島を平和都市として復興させた人びとを描いた骨太ノンフィクションです。
本書刊行にあたり、ノンフィクション作家として戦争を書く意味、そして、広島の取材を通して見えてきたこと、感じたことをじっくりと伺いました。
聞き手・構成=鎗田 淳/撮影=HAL KUZUYA
- 人間くささこそが、最大の魅力
-
── 石井さんは作家として戦争や戦後を書くということについて、どのような思いがありますか?
戦争を書くことには大きく分けてふたつの方法があると思います。ひとつは過去に誰もやっていない分野を掘り起こす方法。僕の本で言えば『浮浪児1945- 戦争が生んだ子供たち』がそれに当たります。もうひとつは、今回の本のように、歴史の正史を真っ向勝負で掘り下げる方法です。この方法で書くにあたって僕が強く意識したのは、「なぜ、自分が書かなければいけないのか」という目線でした。
戦後、広島は平和都市として復興されることになります。広島を元の姿に戻そうとするのではなく、未来に向かって「平和」というバトンを引き継いでいく気持ちが、被爆者をはじめ大勢の人びとのなかにあったわけです。そして、そのバトンの先にいるのは誰かと言えば、現代の僕たちですよね。彼らから僕たちに託されたものは何なのかを、時代のなかできちんと見つめること。これはノンフィクション作家としてやらなければならない仕事のひとつだと思いました。── 今回は取材の苦労という点ではどうでしたか?
取材についてはいつも、とりあえず現場に行けば何とかなるだろうとしか考えていないんです。今回は取り上げる本人はもちろん、友人も、子どもでさえすでに亡くなっている人もいる。だけど、取材ってやってみると、想定外の奇跡もたくさん起こります。だから、今回の本に限らず、やりたい、と思ったらやるしかない。やってみるところからしか、何もはじまらない(笑)。取材に行ってみて、そこからいろいろなコネクションを作ったり、できる取材を探していったりというのが僕の方法論なんです。
── 本書では、まず長岡省吾(ながおかしようご)という人物に焦点が当てられています。広島平和記念資料館の初代館長でありながら、歴史のなかでは「名前が消されてきた」人物です。この人物を知ったことが執筆の動機となったそうですね。
二〇一四年の八月にテレビ番組の仕事で広島を訪れたときに、長岡省吾のことを初めて知りました。知れば知るほど僕が興味をもったのは、彼がものすごく「人間くさい人」だったからです。
一九四五年当時、広島文理科大学(現・広島大学)の地質学鉱物学教室で嘱託として働いていた長岡は、あの日、調査で山口県にいました。被爆はまぬがれたものの、翌日には広島に戻り、八日には市内に入ります。放射能に覆われた、目を覆いたくなるような惨(むご)い光景を目の当たりにしながらも、彼は、すぐに、原爆の痕跡となる石や瓦、熱で溶解した陶器や瓶などを集め始める。なぜかと言えば、後世に原爆の記録を残すためです。長崎に比べて、広島に被爆当時の資料があれだけ多く残されているのは長岡の功績によるところが大きい。長岡の文字通り「命がけ」の行動によって、現在、広島には資料館があり、そして毎年百万人以上が足を運んでいるんです。
ただ、立派な地質学者という顔は彼の一面に過ぎず、複雑な過去や事情を抱えてもいました。満州の陸軍特務機関に属していたため、過去を消さなければならなかったし、そのせいで、学術界で正当な評価を得られなかった。私生活でも問題を抱えていた。なかでも特攻隊の一員として終戦を迎え、戦後も軍国主義的思想が抜けなかった長男の成一とは仲たがいしていて、それが原因で彼の人生は歴史から消されることになった。
しかし、もしも長岡が清廉潔白な人間だったならば、僕は共感できなかった。彼はあれだけ複雑な過去をかかえていたからこそ、おそらく命をなげうって原爆研究をはじめたんです。自分ばかりでなく、家族まで原爆症の危険にさらし、止められても、馬鹿にされても、毎日のように爆心地周辺を歩き回って被爆資料を集めた。歴史に翻弄され、挫折を重ねてきた彼だからこそできたことなんです。
もし彼が単なるエリート学者だったら、命をかけて原爆研究をしようとは思わなかったでしょう。僕は、長岡のこうした人間くささこそが、最大の魅力だと思っています。── 長岡以外の登場人物はどのように決められたのですか?
実は、はじめは長岡省吾についてだけ書こうかと考えていました。でもそうすると、長岡の評伝になる。それよりもこの本は、今につながる「広島」の話にしたいと考えたんです。試行錯誤を重ね、長岡のほかに、広島復興のキーマンとして三人を取り上げました。〝原爆市長〟と呼ばれた浜井信三(はまいしんぞう)。高校時代を広島で過ごし、平和記念公園や資料館を設計した建築家の丹下健三(たんげけんぞう)。そして中学生で被爆するも生き延び、原爆ドームの保存に貢献した高橋昭博(たかはしあきひろ)です。ひとつのテーマを立体的に描き出していくためには、評伝ではなく、群像劇として複数の目線を置くことが有効です。
- 平和の重みを感じるため、鍵となるのが「ストーリー」
-
── 長岡や浜井、そして丹下は、運良く生き長らえましたが、本当に紙一重のところだったのだと本書を読んで驚きました。それぞれが「生かされた」と言いますか、宿命を背負っている気すらしてきます。
人間の行動や言動には、ひと言、ふた言では語り得ないそこに至るまでの過去、つながりといった「ストーリー」があるはずです。けれども報道においては、ほとんどの場合、情報はピンポイントでしか取り上げられません。乱暴に言えば「偉い人が偉いことをやった」で終わってしまう。長岡省吾という地質学の研究者が爆心地近くの微妙な石の変化に気づき、瓦や石を集め、資料館ができました、とか、浜井信三という東大卒の役人が市長となり復興に尽力しましたとか。
そこで終わらず、なぜ彼らはそれをやらざるを得なかったのか、そして、その上で、未来に何を託そうとしたのか、までを突きつめるのがノンフィクションだと思います。そうしてはじめて、平和が重みをもってくる。その重みこそが、僕たちが感じ、考えなければならないものだと思っています。
実際、長岡をはじめみな、戦争で仲間を多く失った悲しみや生き残った後ろめたさを感じていて、それが戦後の行動へつながったんだと思うんです。丹下だって、高校時代の知人を数多く失っているでしょう。それまで何度もコンペで一等を取りながら、建物が完成したことは一度もなかった。彼にとって資料館が最初の作品なんです。無数の挫折の末に、広島にたどり着いているんです。── 戦争体験者の高齢化に伴い、語り手も著しく減少していくなかで、どうやってこれからの世代に歴史を伝えていくのか。今おっしゃった、ストーリーが大きな鍵となりそうですね。
そうですね。資料や情報が無数にあっても、ストーリーが欠落している状態で、はたして人はそれらにアクセスするのでしょうか。そして、それらは十全に活用されるのでしょうか。被爆者の証言にしても、語り手はなぜ語らなければならなかったのか、未来に何を残そうとしたのか。また、受け取る側は、なぜそれを聞かなければいけないのか。こうしたストーリーが重要なのだと思います。
── そのあたりは、第6章で書かれている原爆ドームの保存の経緯にもつながってきます。
「ダークツーリズム」という言葉が日本では数年前から流行(はや)っていますが、その枠組みのなかで、原爆ドームや資料館を訪れる人もいるようです。戦争や災害、事故があった負の遺産を巡るダークツーリズムは、ひとつのきっかけとしてはよいと思います。
ただ、原爆ドームは決して「ダーク」だけで語れるものではない。背景のストーリーをきちんと見つめてほしいんです。
本書にも書いた通り、原爆ドームが今なお広島に存在している背景には、必死になって悲劇の記憶を残そうとした人たちのストーリーがありました。原爆症によって十代で亡くなった女の子の遺志を受け継いで同年代の少年少女たちが原爆ドームの保存運動を始めたこと。そこに自分のお小遣いをはたいてまで募金をした子どもたちがいたこと。市長である浜井信三自らも街頭で募金を呼びかけ、ついには全国からも募金が集まったこと。浜井を含め、保存運動に参加した多くの人が自身も原爆症に苦しんでいました。そして浜井は原爆ドームの保存工事が完了した翌年(一九六八年)に亡くなった。まるで平和のバトンを託し終えたかのように……。
だから原爆ドームを受け継いでいくという時、僕たちは、建物そのものとともに、原爆ドームを残そうと尽力した人たちのストーリーと、そこから発せられるものすごく熱いエネルギーを受け取って、そして未来へと手渡していかなければならないはずなんです。── 一方で本書には、資料館や原爆ドームが日米をはじめとする時々の政治的思惑に利用され、関係者が翻弄(ほんろう)される様が書かれています。「平和」は政治と無縁でないことを思い知らされます。
例えば一九五六年、広島で原子力の「平和利用博覧会」が行われると、資料館からは長岡が集めた資料の一部が撤去され、代わりに、原子力の平和利用をアピールする展示品が運び込まれました。ただ、そうした動きと比例するように反核運動も高まっていく。現実に生きている人間は絶対に政治とぶつかると僕は思っています。政治はときに、人々が積み上げてきたものを簡単に踏みにじります。またときに、人間が生きていく上での隠れ蓑にもなったりする。本書では、そうした実感を、長岡をはじめとする資料館にかかわった人たちの目線から伝えたいと思いました。だから政治を書きたいという気持ちはなくて、あくまでも被爆者や広島の人びとが、どう見ていたかを書きたかったのです。
- 戦争で壊れた町の再生、家族の再生
-
── 物も建物も、そして記憶にしても、残そうとする人がいたからこそ残っていく。そして、平和は一人ひとりが主体となって守っていくものなのだと、本書によって強く再認識しました。
終戦直後に復興の計画を立てる段階では、今の広島駅前周辺に中心街をつくる案も出ていました。戦争の痕跡を捨てて、まったく新しい町をつくることはできたんですよね。多くの人間が広島から去っていったという事実もあります。でも実際は、残った人間が平和都市として町を再生させていこうと決め、見事に達成した。
原爆によってあれだけ破壊された町を平和都市として甦(よみがえ)らせてしまう人間の強さというのは、もしかしたら原爆以上のものかもしれない。言い方はおかしいかもしれないですけれど、戦争よりも人間は強いと、書き終えて感じています。
長岡にしても浜井にしても、ほかの登場人物にしても、あの極限状態においては、理屈を通り越して情熱が行動原理になった。その情熱が結集したから、破壊されたものを上回るエネルギーになっていったし、新しいものが生まれていった。戦争っていけないよねという理屈だけからは、絶対にそうしたエネルギーって生まれないと思うんです。── 人の情熱が生み出すエネルギーごと受け止めて、未来へ引き継いでいくこと、これはまさに石井さんがはじめにおっしゃっていた「バトンを引き継ぐ」の姿ですね。本書の最終部でもそうしたことが描かれています。
長岡省吾も、そして長男の成一も、言ってみれば戦争の犠牲者です。戦争は家族を壊します。けれども長岡省吾の歴史や思いはきちんと受け継がれていた。あれだけ父・長岡省吾を拒絶していた成一が、実は、死ぬ間際まで父が残したものをきっちり保管していたことや、父の業績を認める発言をしていたこともわかりました。そこのところを、今回の取材のなかで見つけられたのはとてもよかったなと思っています。
長岡省吾や成一、そしてほかの登場人物を含めた多くの人びとから僕たちに託されたものをこの本で提示できたならば、読者は、戦争反対ということを、平和ということをもっと強く願ってくれるのかもしれない。大きく言えば、もっと人間が人間に対する自信をもてるようになるかもしれない。そして、その自信が未来に向けての具体的な行動につながっていくことを著者として願っています。
(「青春と読書」2018年7月号転載)
著者プロフィール

- 石井光太いしい・こうた
- 作家。1977年東京都生まれ。日本大学藝術学部文芸学科卒業。国内外の文化、歴史、医療などをテーマに取材、執筆活動を行う。ノンフィクション作品に『物乞う仏陀』『絶対貧困』『遺体 震災、津波の果てに』『「鬼畜」の家 わが子を殺す親たち』『43回の殺意 川崎中1男子生徒殺害事件の深層』。小説作品に『蛍の森』『砂漠の影絵』『世界で一番のクリスマス』他多数。