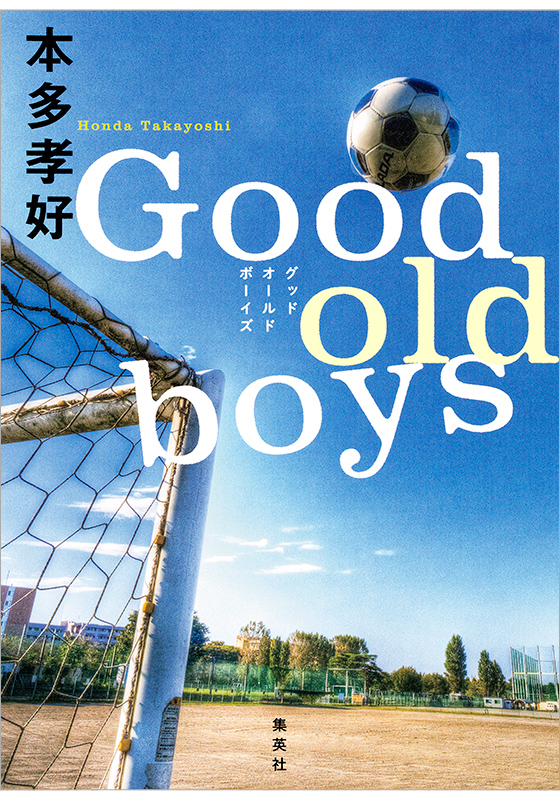沈黙を聞き、引き受ける覚悟を現代に問う――本多孝好 『アフター・サイレンス』刊行記念インタビュー
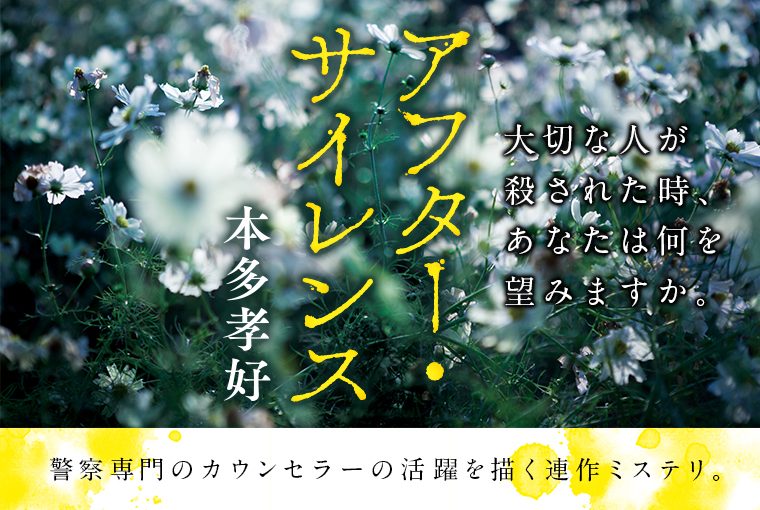
80万部を突破した「MOMENT」シリーズや映画化された『ストレイヤーズ・クロニクル』など、多彩なジャンルで活躍される本多孝好さん。
このたび刊行された『アフター・サイレンス』は、刑事事件の被害者や被害者家族のカウンセリングをおこなう公認心理師・高階唯子(たかしなゆいこ)を主人公にした作品。
様々な形で傷つき、不安定になったクライエントと向き合う唯子が、沈黙に耳を傾けていく姿が描かれます。
唯子に託した思いや、沈黙を認めながら生きることなどについて、Zoomによるリモート取材でお聞きしました。
構成/倉本さおり
初出/「小説すばる」2021年9月号
「寄り添う」という言葉への違和感と親近感
――新刊『アフター・サイレンス』は、刑事事件の被害者やその家族のカウンセリングを専門に担当する公認心理師・唯子を中心に、人びとの抱える心の傷が複層的に絡みあってゆく連作スタイルのミステリになっています。執筆のきっかけや核となったものは何だったのでしょうか?
本多 書きはじめるときに、その物語が自分の日常とどこで接点を持っているのか考えることが多いんですけれども、この作品に関して言うならば、「寄り添う」という言葉に対する違和感と親近感が端緒だったように思っています。「人に寄り添う」という言葉がここ何年かで本当に耳につくようになったけれど、昔は今みたいな文脈では使われなかった言葉だと思うんですよ。「助ける」とか「手を貸す」とか、いつのまにかそういうニュアンスで発せられるようになっていることに、日常生活の中でとても違和感があったんですね。寄り添われることを求める心持ちがある一方で、「寄り添う」という言葉が持っている、どうしようもない無責任さといいますか。寄り添うという行為だけで自己完結ができてしまう、その言葉のニュアンスに対する違和感みたいなものを、カウンセラーという仕事に結びつけて物語にできたら……と思ったのが執筆の最初のきっかけです。
──主人公である唯子の仕事は犯罪被害者に寄り添って耳を傾けることですが、タイトルに象徴されているとおり、この作品では「沈黙」が重要なプロセスになっていますよね。クライエントだけでなく、彼らを取り巻く家族や刑事も含め、人びとが話し出す瞬間に必ず沈黙がある。
本多 本来、沈黙の中に囲われているもの、個々の人たちが自分の沈黙の中に包み込んでいるものっていっぱいあると思いますし、それがむしろ当たり前であると思うんですね。人というのはそう何もかも開けっ広げに生きてはいけないわけで。ただ、沈黙の中で囲われているものが中から手を伸ばす瞬間というのもあると思うんですよ。どうしても発したくなる、ある種の悲鳴みたいなもの。それは沈黙を通してでしか聞き取れない言葉だろうなと。普段の生活の中では解消されないもの、その言葉を聞く人として唯子という人間をつくったというところはあります。自分のクライエントだけではなくて、いろんな人が抱えている沈黙の前で立ち止まれる人であってほしいと。
──ミステリにおけるカウンセラー役というのは、話をどうにかして聞き出すことに重きを置くという勝手なイメージがあったので、「むしろこの沈黙を守ることが、今の私の仕事なのだ」というふうに思える主人公像は新鮮に映りました。
本多 彼女自身が重たい過去を抱え、沈黙を抱えている人なので、あまり人の沈黙に対してずかずかと踏み込んでいかない。それを待ってあげられる人。唯子という人間の特殊性というか、主人公としての特殊性みたいなものは確かにそこに託した部分があると思います。沈黙を聞く人ですね。最後の事件に関して言うならば、沈黙を聞き損ねたことによってこんがらがっていったものが核になっていくわけですけれども。単純に話を聞いて謎を解くみたいな、そういうタイプの物語にはしたくなかったんです。
この小説を最初に書こうと思ったときに、とにかく悪い人を書くのをやめようと思ったんですね。悪い人を書くと、その人のせいにできちゃうので。現実には誰のせいにもできないものだから、みんながつっかえているのであって。それに、悪意によって傷つけられたわけではなくて、ただ救いがなかったから傷つくことってあるだろうし。
そもそも加害者と被害者という対立軸の中で何か落とすところを探すような物語を自分は書きたかったんじゃないんです。罪というものでぼこっと開けられた穴、その前でたたずんでしまった、足を動かせなくなってしまった人たちの物語を書きたかったんだということに後から気づきました。
──確かに、作中のクライエントたちはカテゴリー上は被害者遺族であるにもかかわらず、みんな罪悪感を抱えていますね。
本多 人が犯した罪というものにすぐ近くで触れたときに、その人を責める気持ちというのは当然生まれるとともに、自分にも何かできたんじゃないかという罪悪感ってどこかにあるような気がするんですね。そういうものって人を立ち止まらせてしまうし、時に曲げてしまうこともある。その感情全てが間違っているとは思わないんですけれども、やっぱりそういう感情を見守ってくれる人がいるといいんだろうなというふうには思います。
──「もしもの自分ともしもじゃない自分」というフレーズが繰り返し出てくる点もすごく印象に残りました。
本多 特に、事件被害者の家族、加害者の家族というのは、選び得た立場ではなく、ある日突然ぽんと染まってしまうようなものですよね。たぶんそういう条件でなかったら自分は違う状況になっていた、という場所にいる。じゃあ、そこにいる自分と今の自分に共通するような、本当の自分みたいなものってどこにいるんだろう、というところを常に悩みながら生きている人たちだと思います。
キャラクターの生活の内訳を考える
──唯子のバディにあたる刑事にして元彼でもある仲上(なかがみ)や、メンター役の安曇(あずみ)教授など、周囲を固めるキャラクターの個性も際立っていて面白いです。同業者同士のちょっとした友情みたいなものをはじめ、物語自体の重たい展開の中にも読み手の心を高ぶらせてくれるものが入っているというか。
本多 被害者がいて、加害者がいて、罪があって、傷ついた人たちがそこにいる以上、どうしても重い話になってしまう。でも傷ついた人たちが集まったところにもユーモアはあると思うし、人同士が触れ合うことによって生まれる柔らかさもあると思う。単に厳しい側面、冷たい側面、硬い側面だけに寄らないようにしようというのは意識しました。
──唯子は国家資格を持っていても、公務員として警察に所属しているわけでも病院に勤務しているわけでもないから、どうしても立場が弱くなるし収入にも余裕がない。働く女性のしみったれた暮らしぶりがリアルに描かれていて親近感を覚えました(笑)。
本多 以前、臨床心理士を主人公にした連ドラがあったらしくて、そこでの主人公の生活があまりに華やかで、実際に臨床心理士として働いている人からするとかなり違和感があったという話を聞いたんです。自分はキャラクターを考えるときに生活の内訳について考えるんですよ。単純な話、どこに住んでいるのか、何を食べているか、お小遣いは月どれくらい自由に使えるのかみたいなところはやっぱり想像する。例えば、「この人は犯罪加害者の娘だから、たぶん大学に行くときも奨学金もらって返したりしているんだろうな」って。あまり声高に書くことはありませんが、そういうところはキャラクターの中に必ず落とし込みます。
──安曇教授のキャラクターもいいですよね。普段は物腰が柔らかくておとぼけキャラなんだけど、言葉をめぐる対話のときには全然甘やかさない。人に寄り添うということの本質はどこにあるのか、というテーマを整理していくような役どころを負っているように見えます。
本多 安曇教授に関しては、味方である以前に師匠である、という点から、どこかで主人公が見ていない、見えない部分までも見ているキャラクターということを意識しています。結局のところは「休むな、諦めるな、手を抜くな」ということを繰り返し言っているだけなんですけれども、たぶん人と人とが接することってそういうことなんだろうなと思うんですよね。諦めないこと、手を抜かないこと。安曇教授はそういうことを見通しているキャラクターとして作中に立ってもらっています。何ならもっと書きたいキャラクターではあったんですけれども、あまり書いちゃうとうるさくなるので(笑)。
その点、仲上というキャラクターは当初とイメージが違うんですよ。最初は単に、「信頼し合っている相手」くらいのイメージしかなかった。でも物語上、やっぱり唯子が安心して弱さを見せられる相手は必要だなと思って。じゃあ、それを受け止められるキャラクターというのはどういう感じだというふうにイメージをしながら書きました。
差し出された手を握り返せるようになるまでの物語
──最後の最後で、それまではある種依存されていた唯子をみんなが止めるというシーンがあるじゃないですか。あの場面はすごくほっとしました。一人の人間だけに背負わされるものはないんだということを、ちゃんとプロットとして提示してもらえたというか。
本多 やっぱり「寄り添う」っていう行為には限界がある。他人なんですから。突き詰めると、その人に成り代わるしかないんですよね。でも、そこで成り代わるっていうのはやっぱり違うと思うんですよ。それは悩みであれ、痛みであれ、どうしたってその人のものなんだから。ただ、それを引き受ける覚悟を他者から示されたときに、どこか人って救われた気持ちになるんじゃないかなという気持ちがあって。何か自分の気持ちを反射させながら自分自身を見つめ直していくきっかけにはなるんだろうなと。じゃあ、唯子にはそれを見せてもらいましょうということになったんです。最終的には、差し出された手を唯子が握り返せるようになるまでの物語、ということだったんだろうなと思いました。
──いち読者としては、自分を追い詰めるゲームから降りるための物語というか、指標みたいなものから自由になる物語なのかなと感じました。ある意味、新自由主義的な息苦しさに対する反駁とも読み取れるなと。
本多 ああ、そういえば、話はちょっと逸れるんですが、この間「ファスト映画」なるものの存在をはじめて知ったんです。10分くらいの長さに編集した映画をYouTubeにアップするという。さすがにあ然としましたね。映画すら情報になる時代なのかと思って。
──コスパ主義の極みといった感がありますよね。
本多 この小説の中で「普通の生活の、普通の時間は、沈黙を許さない」と書きましたけれども、最早それすら問題にならない事態になってきているのかなと。沈黙を許さない以前に、コミュニケーション自体がそれこそコスパで測られるようになってきているのかもしれないですね。「これは何のためにやっているの? 今日は何の話するの?」という感覚で動かされているのかもしれない。でも、「つまるところ、あなたは何?」と言われ続ける人生って、ちょっとしんどいですよね。
──そういう意味では、この物語に出てくる唯子たちは真逆のことをしているとも言えます。わかりやすい成果に向かっていかない、そうした事象のややこしさ自体を認める作業というか。
本多 逆に、要約してと言われちゃうと困るんですよね、小説って。そういうコスパ主義の対極にあるものだから。このスピードで、たったひとつの物語に読者が時間とエネルギーを割くわけで、こんなに効率の悪いものはない。それに対してどこまで自分が応えられるのか。別に自分が書かなくても他に優れたものがいっぱいあるからいいじゃないかと思う瞬間は昔からありますけど、最近の時間の流れの中では特に感じます。
そもそも映画の観客という役割すら降りてしまうんだったら、とてもじゃないけれど読者の役割を果たしてくれとは言いづらい。そもそも小説というのは「あなた」が介在しないと成立しないものだから。プレイヤーとして読者が参加してくれないと成立しない。本当に、なかなかの時代になりましたね(苦笑)。
プロフィール
-

本多 孝好 (ほんだ・たかよし)
1971年東京都生まれ。慶應義塾大学卒業。94年「眠りの海」で第16回小説推理新人賞受賞。99年、受賞作を収録した短篇集『MISSING』で単行本デビュー。2003年『MOMENT』、04年『FINE DAYS』で2年連続吉川英治文学新人賞候補。05年『真夜中の五分前』で第132回直木賞候補、10年『WILL』で第23回山本周五郎賞候補。他に『MEMORY』『ストレイヤーズ・クロニクル ACT 1~3』『チェーン・ポイズン』『at home』『君の隣に』『dele 1~3』『アフター・サイレンス』『こぼれ落ちる欠片のために』など著書多数。
新着コンテンツ
-
連載2025年07月15日
 連載2025年07月15日
連載2025年07月15日【ネガティブ読書案内】
第44回 ホリコシさん
「10分遅刻して卒論を出せなかった時」
-
インタビュー・対談2025年07月08日
 インタビュー・対談2025年07月08日
インタビュー・対談2025年07月08日桜木柴乃「波風立てずに生きる器用さを、ちょっと残念だなと感じる大人に読んでほしい」
著者五十代の最後を飾る、集大成的な短編集である本作。仕事に対する現在の思いや、短編を書く面白さをうかがいました。
-
お知らせ2025年07月04日
 お知らせ2025年07月04日
お知らせ2025年07月04日すばる8月号、好評発売中です!
演劇界注目の劇作家・演出家ピンク地底人3号さんによる初の小説を掲載! 遠野遥さんの短期集中連載も最終回を迎えます。
-
インタビュー・対談2025年07月04日
 インタビュー・対談2025年07月04日
インタビュー・対談2025年07月04日石井遊佳×藤野可織「魂を自由にする虚構の力」
ホラー愛好家を自認する藤野さんは石井さんの新作に詰まった四つの物語をどう味わい、そこに何を見つけたのか。
-
新刊案内2025年07月04日
 新刊案内2025年07月04日
新刊案内2025年07月04日給水塔から見た虹は
窪美澄
2人の“こども”が少しずつ“おとな”になるひと夏を描いた、ほろ苦くも大きな感動を呼ぶ、ある青春の逃避行。
-
新刊案内2025年07月04日
 新刊案内2025年07月04日
新刊案内2025年07月04日青の純度
篠田節子
煌びやかな「バブル絵画」の裏に潜んだ底知れぬ闇に迫る、渾身のアート×ミステリー大長編!