『地図と拳』刊行記念対談 小川 哲×新川帆立「地図とは何か。建築とは何か。そして、小説とは何か。」

日露戦争前夜から第二次大戦までの半世紀を描いた、超巨編『地図と拳』。
小説すばるにて連載されておりました本作が、このたび遂に単行本として刊行されました。
物語の舞台となるのは、満洲の名もなき都市。
その地を巡って、国家の、人々の思惑が交錯していきます。
刊行を記念して、著者の小川哲さんと、小川さんの大ファンである新川帆立さんに対談していただきました。
※なお、作品全体への言及をさせていただいておりますため、ネタバレ等にはご留意いただけますと幸いです。(編集部)
聞き手・構成/大森 望 撮影/キムラミハル
――小川さんの大作『地図と拳』がついに完成したということで、今日は大の小川哲ファンだという新川帆立さんをお招きして、刊行記念対談をお願いしたいと思います。新川さんのほうも5月に『競争の番人』が出たばかりで。
小川 おまけにまたドラマ化。
――『元彼の遺言状』に続いて月9でドラマ化。7月には『先祖探偵』も刊行予定という、破竹の勢いの新川さんです。
新川 この対談、「何でこの組み合わせ?」って思っている方が多いでしょうが、小川さんとは麻雀卓を囲んだ仲ということで、のこのこ出てまいりました。地図が読めない女、新川帆立です。
小川 僕はつい先日、逢坂冬馬さんと『SFマガジン』で対談したんですよ。売れっ子の作家にどんどん寄生していこうと(笑)。「売れてる人が読んだらしいから、俺も読もう」みたいな人が増えるといいなって。
新川 小川さんは圧倒的先輩なので、相手が私でいいのかと思いつつ。
難産の理由
――『地図と拳』はたいへん難産というか、最初、『小説すばる』に連載しはじめたときから言うと……4年?
小川 初回掲載が2018年10月号なので、4年近くですね。1年連載して、1年休載して、また1年連載して、そこから半年ぐらいかけて単行本化の作業をしたって感じですかね。確かに大変でした。
――思った以上に難産だった?
小川 休載したのは、短編集の『噓と正典』と重なったせいですね。表題作を書き下ろしたり、他の短編に手を入れたりの作業を『地図と拳』の連載と並行してやらなくちゃいけなくて、もう頭おかしくなりそうだったので、一回休ませてくださいってお願いして。でも、その間ただ休んでいたわけじゃなくて、それまで書いた1年分の連載原稿、納得いってなかった部分をぜんぶ修正した。基礎工事からやり直した感じです。
新川 率直に聞きたいんですけど、これってプロットつくっているんですか。
小川 いや、プロットはつくらずに書いたんです。だから、道が続いてるかなと思って書いていたら袋小路だった、みたいなことは結構頻繁に起こって。
新川 地図なしで歩いていたんですね。
小川 そうですね。
新川 下調べはどのぐらいかかったんですか? 明らかに大変ですよね。
小川 でも、連載前に勉強した量で言うと、そんなに多くない。そもそも僕、高校でも世界史とってなくて、ほぼゼロの状態だったので、そこから一応ちゃんと勉強しつつ。でも、基本的には書きながらわからないことを調べる場合が多いし、そのほうが効率いいですよね。書いてみないとわからないことっていっぱいあるんで。戦前とか戦中の小説だと、登場人物が道を歩いているとき、この時代の街灯って電気なのかガスなのか、そもそも街灯があるのかないのか、そこから調べなきゃいけない。暖房手段はストーブなのか薪なのかガスなのかとか。そういうのが地味に大変でしたね。
新川 書き手目線で考えると、めちゃくちゃ大変そうです。
小川 建築のことも全然知らなかったので、それも勉強しました。僕、勉強するのが好きなんで、わりと。
新川 私も資料読むのは好きなんですけど。
――今日の対談は、東大を出た人同士だけあって、二人とも勉強が好きなんですね(笑)。
新川 資料読んでると、そっちが楽しくなっちゃって、いつまでも書き始めなかったり。
小川 確かにね。僕はそれで3年以上かかってしまった。なのに新川さんはもう何冊も出してる。
――でも、新川さん的には、逆に、1冊に3年も4年も時間をかけられるのがうらやましいと言ってましたね。
新川 ほんとそうです。対談で言うのも何だけど、わたし、3年、4年かけて1冊書くみたいな作品をとくに求められてなくて。
小川 求められてないでしょうね。
――手っ取り早く現金化したい換金作物みたいな。
新川 さすがにそれは言い過ぎですが(笑)。
小川 僕の場合も、編集者はとっとと出してほしいと思ってると思いますよ(笑)。僕が勝手に3、4年かけてるだけなんで。新川さんは原稿を書いてしまうから本が出ちゃうわけで、「書けません」って言えば本は出ない。
新川 それ、すごいですよね、そのメンタル(笑)。3年出さなかったら、「俺、干されるかも」とか思わないんですか?
小川 それはないですね、まったく。10年出さなかったら干されるかもしれないけど。それに、3年出さないっていっても、3年間まったく仕事してないわけじゃなくて、雑誌に短編とかは書いてるし、『地図と拳』の連載も進んでるし。結局、干されるかどうかって、面白い小説が書けるかどうか。面白い小説書く人って、1冊に何年かかっても、仕事はあると思うんでね。飛浩隆さんとか。
新川 間隔があけばあくほど、次回作のハードルが上がるじゃないですか。これはすべれないみたいな。
小川 でも、それで言うと、すぐ出すからすべれるみたいな意識も僕はあんまりないんで。全部の作品すべりたくない。
新川 私はちょっとすべったなって思ったら、たくさん書いて薄めるしかないみたいな気がして。
小川 そういう発想もあるんだ、なるほど。とはいえ僕も、こういうふうに3年もかけて一冊の本をつくるのは、たぶん、この先しばらくはないですね。『地図と拳』は、『ゲームの王国』のときに自分の中でやり残した課題をやるみたいな感じだったので。だから、プロットもつくらず、行き当たりばったりで書きながらテーマを見つけて、それをどんどん重ね合わせていった。あえて『ゲームの王国』のときと同じやり方をしたんです。当時よりも作家としてのスキルは上がっているだろうから、いま同じことをやったら、小説技術的な面で、もっといいものができるんじゃないか。それが『地図と拳』を書くときの個人的な課題でした。その課題はもう済んだので、今後こういうつくり方することはないなっていう感じですね。
――話のつくりかたにも『ゲームの王国』と重なるところがありますね。一度だけ偶然出会った主人公格の男女が時を隔てて再会するとか。ダンスホールの場面なんか、『ゲームの王国』にわざと寄せてるみたいな印象があって。姉妹編的な感覚なんですか?
小川 姉妹編ではまったくないですけど、『ゲームの王国』はほんとに何もわからない状態から、自分に何ができるかを見つけながら書くみたいな感覚だったんで、あのときに使ってうまくいった技術とか、これ使うと楽だなと思った展開の仕方とかは、今回、使えるだけ使いました。同時に、そこから自分の実力が上がったと思ってるものを使って、『ゲームの王国』に足りなかった部分を埋めるみたいなイメージで。ガワは全然違うけど、展開の仕方とか話のつくり方に関しては、『ゲームの王国』で見つけて自分が得意技にしている手法を使ってる箇所は結構あるかもしれないですね。
構造とディテール
新川 限りなく下から目線で分析するのも恐縮なんですけど、小説が構造とディテールでできてるとしたら、『地図と拳』の場合は、ディテールを積み重ねるやり方でいったん書かれて、そのうえで構造を調整するみたいな手法をとられてるのかなと。いままでの作品を読むと、小川さん自身が、構造とディテールの間を行ったり来たりされてる方なのかなと勝手に思っていて。構造とディテールって、理性と本能とか、知性と感情とかって言い換えてもいいんですけど、デビュー作の『ユートロニカのこちら側』だと、理が突き抜ける感じがあって、それですごく精緻な世界観になっている。逆に、『ゲームの王国』だと、ディテールの面白さを積み上げて、読者を煙に巻くみたいなところが面白かった。『噓と正典』だと、短編集だからっていうのもあるんですけど、それが一転、機能美みたいなものを有する短編が並ぶ感じで、構造に寄ってるなと。だから今回、どっちで来るのかなって、すごく楽しみにしてたんですね。そうしたら、こちらの予想をはるかに超えて、どちらに寄ることもなく、両方ともすごいレベルで。ディテールの積み上げ方の進歩ももちろんあるんですけど、構造もより強くなったっていう印象でした。なので、いまのお話を聞いて、ああ、やっぱり、と。
小川 うまくいってるかどうか別にして、考えていたことは100パーセントそのとおりです。今回、建築っていうテーマを選んだのも、小説としての構造が建築の構造と重なるので、作品の中で建築について考えることがそのまま小説について考えることになると思ったからです。僕は、読者としては、やっぱりディテールをすごく大事にするんですよ。その一方、小説の完成度や評価は構造で決まることが多いと思ってて。『ゲームの王国』は、ディテールを積み上げることで建物がギリ建ってるか建ってないか……みたいな建築になったんで、今回は、建物としてちゃんと建つようにしようと。ところが、さっき言ったように諸事情あって基礎工事がちょっとぐらぐらになってたんで、1年かけて基礎をつくり直したみたいなイメージですね。
新川 戦争ものって、そもそも事実レベルでディテールが面白いというか、生のエピソード自体にドラマ性がある。漫然とディテールを重ねていっても、それが感情を揺さぶって、それなりに面白くなる。だから、私がいままで読んだ戦争ものって、ディテールに飲み込まれて、構造を見失ってる作品が多い気がしたんです。それはそれで面白かったりもするんですけど、『地図と拳』は戦争を背景にしているのに、ちゃんと構造を踏まえて描かれてるのが何よりもすごいなと。その上で、もちろんディテールも一切手抜きなく、血肉がついた形で造形されている。
小川 ありがとうございます。そう思ってもらえたんだったら満足です。
新川 建築っていうテーマも、ほんとにそうだなと思って。作品自体が地図っぽいというか。作中でも書かれてますけど、地図をつくることが、混沌とした現実を理性的に把握する試みとして描かれていて、それはまさに、この小説自体が試みてることでもある。
小川 そもそも小説っていうものが、現実を整理整頓して、象徴によって再整備するみたいなものなんで、地図と似てるんですよね。
新川 そうなんです。なので、扱ってるモチーフと作品の構造がリンクしてて、すごくきれいだなと思っておりました。
小川 書いている小説としてうまくいくかいかないかっていうのは、そういう重なり合いで決まると思うんです。扱ってるモチーフ同士が構造的に相似形になってたりすることで、個々の話がメタレベルで重なり合ったり響き合ったりする。陳腐な言い方ですけど、その結果、小説に深みが出る。「地図とは」「国家とは」「戦争とは」「建築とは」みたいなテーマをいろんな階層で重ねたりぶつけたりする。『ゲームの王国』でも、同じことをやってたんです。「ゲームとは何か」という問題と、「国家とは」「政治とは」という問題を重ねる。その手法を、僕のいまの小説技術でもう一回やってみようと。一個のディテールが、小説のいろんな階層で、ほかのエピソードや大きい物語の骨組みと結びつくみたいな。それを計算して組んでいくのが好きというか、得意なので、それを意識してちゃんとやろうとしたのがこの作品ですね。こういうつくり方はもうしばらくやりたくないし、しないです、もう疲れたんで。
新川 すごくわかります。相似形って言葉がしっくりくる。
小川 こういうのって、最初からプロット組んでできないんですよね。実際にディテールを書いていく中で、そのディテールのいろんなメタレベルの要素を見比べて、それをほかのディテールとパズルのように組み合わせたり重ね合わせたりする作業になる。さすがにそれを最初から計算してやるのは人間業では無理。
新川 無理ですよね。素直に深掘りしていくと、自分が興味を持ったことだから、やっぱり何かしらつながりがあって、同じ構造が自然と見つかるみたいなこともあると思うし。自然科学的な面白さも感じました。自然界でも、いろんなところで同じかたちや比率が発見されたりするじゃないですか。そういう面白さもあって、私はそこがすごく好きでした。

いま戦争小説を書く意味
――小説で満洲事変を描くとなると、また別の問題も出てきますね。
新川 センシティブな題材を扱っているのに、特定のイデオロギーに寄りかからないで、フラットな視点が貫徹されてて、それは知的な骨格の強さがないとできないことだし、この小説のすばらしいところだと思います。
小川 戦争小説を書く上で、どっちかのイデオロギーに寄せちゃうのは一番わかりやすく売れるだろうけど、一番面白くないんでね。あらゆる人に開かれてる小説にしたいなって思ってたんで。もちろん、僕のイデオロギーはあるんですけど、小説の中には、なるべく多面的にいろんな人の考え方を出したい。それは逢坂冬馬さんとも話したんですけど、いま戦争小説を書く意味って、僕はそこにしかないと思ってて。戦争中に起こったあらゆる事柄をぜんぶ相対化する。「こういうことが悪かったよね」とかっていうことじゃなくて。小説って個人を描けるところに強みがあると思うんで。個人レベルでは、人それぞれが正しいと思うことをやってる。だから、すべての善悪を一旦置いて、個人の話を徹底して書く。戦争を経験した人だと、こういう書き方ってたぶんなかなかできなくて、戦争がいいものだ、悪いものだっていう話になりやすい。戦後何十年も経って、戦争を知らない世代だからこそ書ける小説なのかなと。言葉は悪いんですけど、第三者だからこそできるのかなと。
新川 そういうのって、無意識に偏りが出ちゃうものなのに、ほんとにバランスとれてますね。
小川 そこがむずかしいところですね。解釈をめぐって論争中の問題もたくさんあるし、何か描写するだけで片方に振れることになる。戦争文学として、そういう問題を正面から書くべきだという考えももちろんあったんですが、この小説には、もっと別の角度から戦争について考えられるようにしようと。
新川 すごい上手に切り抜けてるというか。どういう見方の人が読んでも受け入れられるように書かれている。
――実際、撫順襲撃事件とか、平頂山事件とかも扱われてて、それこそセンシティブな領域ですよね。ただ、作中では❝平頂山❞とは書いてないし、物語の焦点となる李家鎮(のちの仙桃城)も、そもそも❝撫順❞ではない。
小川 そう、撫順ではない。それで書きやすくなったというか、歴史を審判するっていう役割からは離れて書いたつもりです。
――❝空想科学小説❞ならぬ❝空想歴史小説❞ですね。
小川 そもそも小説家には、歴史上の出来事について、実際に起こったとか起こってないとかジャッジする権利というか、スキルがないですよね、単純に。だから今回、そういう立場からは書いてない。『ゲームの王国』のときは、そもそもカンボジアの史実というか、正しい歴史を知らない人がいっぱいいるんで、小説の中で歴史を書きつつ、その中でフィクションを駆動させるみたいなことが僕の中のミッションだったんですけど。日本の戦前戦中に関しては、カンボジアと比べれば、歴史を知ってる人がたぶんいっぱいいるんで、正しい歴史を書こうとはしていない。だから今回、実在の人物をあんまりメインに押し出してないんですよね。満洲の話だったら、甘粕正彦とか石原莞爾とか、岸信介とか、名前がちょっと出てくるぐらいで。この小説を書くときのリアリティ・レベルとしてそれがちょうどよかったのと、あと、いまさら❝僕なりの石原莞爾❞みたいなものを描くことにそんなに魅力も感じなかったので。都市についても一緒で、実在する都市の、実際の都市計画や歴史と突き合わせる行為からは自由になりたい。もうちょっと抽象化したレベルの戦争を物語に還元することが、架空の都市だからこそできたのかなみたいな。そもそも連載始める前に、この作品の構造は『百年の孤独』にすると決まってたんで、李家鎮はマコンドみたいなイメージですよね。

キャラクターの魅力
――戦前戦中の満洲で『百年の孤独』をやるっていうのもかなり無茶な試みだと思いますが、すごく虚構性の強い話とリアルな史実の話がマジックリアリズム的に同居しているところがすごく面白い。
新川 こんなに真顔で噓つかれると、だまされそうになる。噓のつき方がうまくなりすぎてますよ。素っ頓狂なフィクションの部分がなくても、作品としては成立すると思うんですけど。『百年の孤独』だから入ってるのかなと
小川 それこそ莫言の小説とか読むと、当時の中国を描くときもわりとそういう感じなんですよ。いきなりドラゴンが空を飛ぶのと、結構まじめな史実っぽい話とが隣の行同士で競争してるみたいな。とくに中国人たちの視点でそういうことが起こってると思うんですけど、それは当時の中国の人々にとってのリアルがそういうものだったからじゃないか。変なことを書こうとして書いたというよりは、そういう視点で見た満洲というつもりで僕は書いてますね。義和団事件だって、神が憑依して素手で西洋の武器と戦うみたいな運動だったんで。
――義和団と言えば、楊日綱が義和拳を習得する訓練シーンがよかった。『鬼滅の刃』の竈門炭治郎みたいな。
新川 あの訓練シーン、わたしもめっちゃ好きで。笑っちゃいました。
小川 あれは一応、『HUNTER×HUNTER』のネテロをイメージしてたんですけど(笑)。
新川 アホな小学生が真似しそうで怖い(笑)。
小川 ネテロの感謝の正拳突きみたいな、すごく単純なことを異常なぐらい繰り返すと、すごいことになる――みたいなイメージは最初にあって、それを屁理屈でこじつけてる。
――やっぱり、タイトルが『地図と拳』だから。拳も大事にしないといけない。
新川 「宇宙卵って何だよ」とか。
小川 あれは高橋名人ですね。高橋名人が(連射の訓練のために)指でスイカを連打して、スイカを割ったみたいな話が好きなんで、その修業をイメージして。
新川 でもね、日本であれやっちゃう人が何人か出ますよ。
――SFでは、ニール・スティーヴンスンが『ダイヤモンド・エイジ』の中で義和団事件を未来の出来事として書いてるんだけど、とても実際にあったこととは思えないくらい小説的なエピソードになってて。それを思い出しましたね。
新川 笑っていいのかあれだけど、面白かった。
小川 ほんとは、そのさらに強烈なのが洪秀全なんですよ、太平天国の乱の。義和団よりもっとカルトなんで、ほんとはそこから始めたかったんですけど。
――でも、周天佑が洪秀全のなり代わりみたいなキャラですよね。科挙に5回落ち続けて、そこから語り部というか説話人になる。
小川 洪秀全もああいう人なんですよね。科挙に落ちまくって、コンプレックスのかたまりで、それでカルト宗教始めちゃう。麻原彰晃みたいな。
新川 史実がめちゃくちゃ面白いから、それを小説にもってきたときに、フィクションが勝てない現象ってあると思うんですけど、『地図と拳』は史実に負けてなくてちゃんと面白い。
――『地図と拳』で好きなキャラクターはいますか?
新川 私は明男くんですよ。明男くん。
――万能計測器、須野明男ですね。逆から読むとオケアノス。
小川 あれはだから、ムイタック・リベンジですよね、僕の中では。
新川 そうそう、『ゲームの王国』のムイタック寄りの。でも、ああいう人、いるんですよ、東大とかに。
小川 いますね。あと、僕の中にも明男みたいなところがあるしね。
新川 私、小川さんの第一印象が❝面白い先輩❞なんですけど、何で面白いかっていうと、一緒に麻雀して、そのあと、居酒屋に行ったんですね。
小川 行きましたね。
新川 その居酒屋で、「日本一おいしい卵かけご飯」っていうメニューがあって、私、「日本一だって!」と思って注文したら、黄身がすごく黄色い卵が出てきたんです。今まで見たことないぐらい黄身が黄色くて、「えっ、すごい黄色い! めっちゃ高級そう!」って言ったら、小川さんが、「いや、黄身の色は鶏が食べた餌の成分で決まるから、高級かどうかは関係ない」とおっしゃって。めっちゃ面白いなと(笑)。
小川 覚えてない。そうやって聞くととても失礼な人間ですね。まあ、僕が言いそうだけど(笑)。
新川 そこに、明男くんの片鱗を見ました。
――明男くんがいろいろ言う理屈はだいたい小川さんが言いそうなことだよね。
新川 言いそう言いそう。ムイタックですね。
小川 明男くんのキャラには、一応、下敷きがあって。内藤廣先生っていう、東大の教授だった建築家の人の本の中に、気温や湿度が体感で判定できるように自分で訓練したみたいな話が出てきて。僕、その話がめっちゃ好きで、それをさらに膨らませた感じですね。
新川 そういう人、実際いますよね。「ほんとかよ」みたいな人。
小川 ムイタックみたいなキャラクターを出す予定はなかったんですけど、温度とか湿度とか風向きとかが歩いてるだけでぜんぶわかる人を出したら、必然的にムイタック的な人物になっちゃった。
新川 そういう人がいるのを知ってるから、私はあんまり違和感ない。例えば私、いま『競争の番人』っていう小説で、頭いいキャラを出してるんですけど、❝頭いいキャラ❞というより、「こういう人いるよね」っていう感覚なんです。でも、キャラ立ちのために極端に描いてるんでしょ、みたいに受けとられて、それが非常に不本意で。
小川 これぐらいの人はいますよ、と。
新川 いますよ! 『ゲームの王国』の輪ゴムとか泥とかも、そんなに違和感がないというか。大学のとき、5円玉をたくさん持ってる人がいて、5円玉投げてくるんですよ。そいつ、「5円玉」って呼ばれてたんですけど(笑)。はかまと下駄で毎日登校する人とかもいて。
小川 下駄! その人知ってますよ。いましたよね、しかも、その下駄が一本歯で。
新川 そう、一本歯の下駄! 私、その人に「何で下駄履いてるんですか」って聞いたら、「僕、天狗になりたいんです」って言われて(笑)。
――理由があるんだ。
新川 ちゃんと理由がある。そういう奇人変人が実際にいるわけだから、そういう人たちを描きたいと思って書いてるのに、「キャラ立ちですね」とか言われると「はあ?」って思う。
小川 実際にいるやつらをそのまま書いたら、「こんなやついないよ」ってなる人、いっぱいいるじゃないですか。
新川 いますね、いっぱいいます。
小川 むしろちょっと抑えめに、これぐらいだったら許されるだろうみたいな感じで書いてるみたいなところ、ありますよね。
――奇人変人がいろいろ出てくる中で、作中では五十年くらい時間が経過して、登場人物も、『百年の孤独』じゃないけど代替わりしていく。そういう長い時の流れの中で、物語の最初に非常に頼りない感じで登場する細川が、ずっと軸になりますね。
小川 『虐殺器官』(伊藤計劃)のジョン・ポールみたいな感じでね。あんな黒幕じゃないけど。
新川 でも、読者的には、細川さんっていう補助線みたい存在が一本あるのが読みやすいと思いましたけどね。人物が全員入れ替わるとついていくのが大変なので。
――テーマを演説してくれるし。
小川 そうそう。この本自体は、わりと細川の話っていう感じですよね。全体として、じつはね。
新川 建築も軸になりますよね。うしろのほうで千里眼ビルディングが出てくると「おおーっ」みたいになりますもん、作中の時間経過を読者も経験してるから。「きみ、まだいたのか、千里眼ビルディング」みたいな。

すべてのピースがハマるとき
――『地図と拳』は、帯にあるように、「ひとつの都市が現われ、そして消えた」話でもありますが、ロシアのウクライナ侵攻によって、ひとつの街があとかたもなく消えてしまうことのリアリティがぐっと身近になりましたね。
小川 確かに。全然考えてなかったですけど。
――マリウポリも、こういう街だったかもしれないのに、あっさり消し去られてしまう。『地図と拳』も、世の中が比較的平和なときに読むのと、毎日ニュースで戦争の話が伝えられてる状況で読むのとでは、ずいぶん印象が変わってくるかなと。
小川 そうですね。どうやったら第二次世界大戦を他人事じゃなく、自分たちの身に起こるかもしれないこととして考えられるか。いま戦争小説を書くとしたら、それが大事になる。なぜ日本が戦争したのか、今後なにがあると僕たちはまた戦争するかもしれないのか――みたいなことは、作品の中で自分なりにずっと考えてたことですね。
――細川の視点は小川さんの視点に近いんですか。
小川 そうですね。もちろん僕だけじゃなくて、現代から過去を眺めたときの歴史家の視点でもあって。この2020年代に第二次世界大戦について考えたときにどう見えるかみたいな視点を投影したキャラクターになりますよね。それを可能にするために、未来を見るとか、千里眼とかのモチーフが必要になったというか。現代から過去の歴史を見ることを作中でさまざまにリフレインさせてるって感じですね、僕の中では。
――戦争構造学研究所もそのためにある。SF的なガジェットを使うともっと簡単に書けそうですけどね。タイムトラベルとか、未来からの通信とか、量子コンピュータとか。ただ、敗戦の未来がわかってからの細川の行動が面白い。
小川 最初は開戦を防ごうとするんだけど、どうやらそれは無理だとわかってくる。現代の僕たちがその場に行ったとして、もう開戦は止められないとなったとき、最善の行動は何なのか。それを細川にやってもらってるみたいなところがありますね。
――タイムトラベラーが最善を尽くしたとしても、あれが精いっぱいだろうと。
小川 あと単純に、史実として、満洲の建材や資材を戦時中に横流しとかしてて巨万の富を築いた児玉誉士夫みたいな人もいるわけで、そういう話とも重なる。別にそれは、敗戦の未来を知ったからやったことじゃないだろうけど。
――合理的に行動するとそうなる。
新川 そこも、地図というテーマとつながりますよね。自分がいる場所って、自分ではわからない。でも、地図を描いてみると、すごく危険な場所にいるって気づけたり。自分にとって不都合な地図を目の前にしても、その地図をもとにして進まなきゃいけないみたいなことってたぶんあるので。だからその点も、モチーフと整合する。SF的には見てなかったけど、自然だと思います。
小川 この小説を書いてるときにやってることは、SFを書いてるときとほぼ変わらなかったですね。
新川 そういえば、昨年だか、小川さんがこれを書いてらっしゃるときにお目にかかったら、「最近、小説書くのが楽しいんです」みたいなことをおっしゃってて。書いていて違いましたか、過去作品と?
小川 楽しかったですね。とくに後半、全部のピースがカチッとハマって、「ああ、これ終わりに到着できる」ってわかってからは、めちゃくちゃ楽しかったのを覚えてます。こうやって、余すところなくピースを拾って終えられたのは、長編では初めてなので、その楽しさはあったかもしれない。
新川 確かに、自分の中で構造が見えて、それがぴったりはまることがわかって、あとは詰めてく作業って結構、勝ちいくさというか、楽しい。
小川 最後、復員船の船で終わるところまで見えて、それが構造的にきれいに閉じたので、その場面にたどりつくのが楽しみだった。『ゲームの王国』は、暴れ回ってるいろんな要素を、何とかなだめすかして風呂敷に包んで上から縛っておもりをつけて終わったみたいなイメージだったんですけど、今回は、僕の中ではきれいに閉じられたような気がしますね。船で始まって船で終わって。
新川 すごくきれいでした、ほんとうに。
――まだまだ話はつきませんが、時間が来てしまいましたので、今日はこのへんで。ありがとうございました。
「小説すばる」2022年8月号転載
プロフィール
-
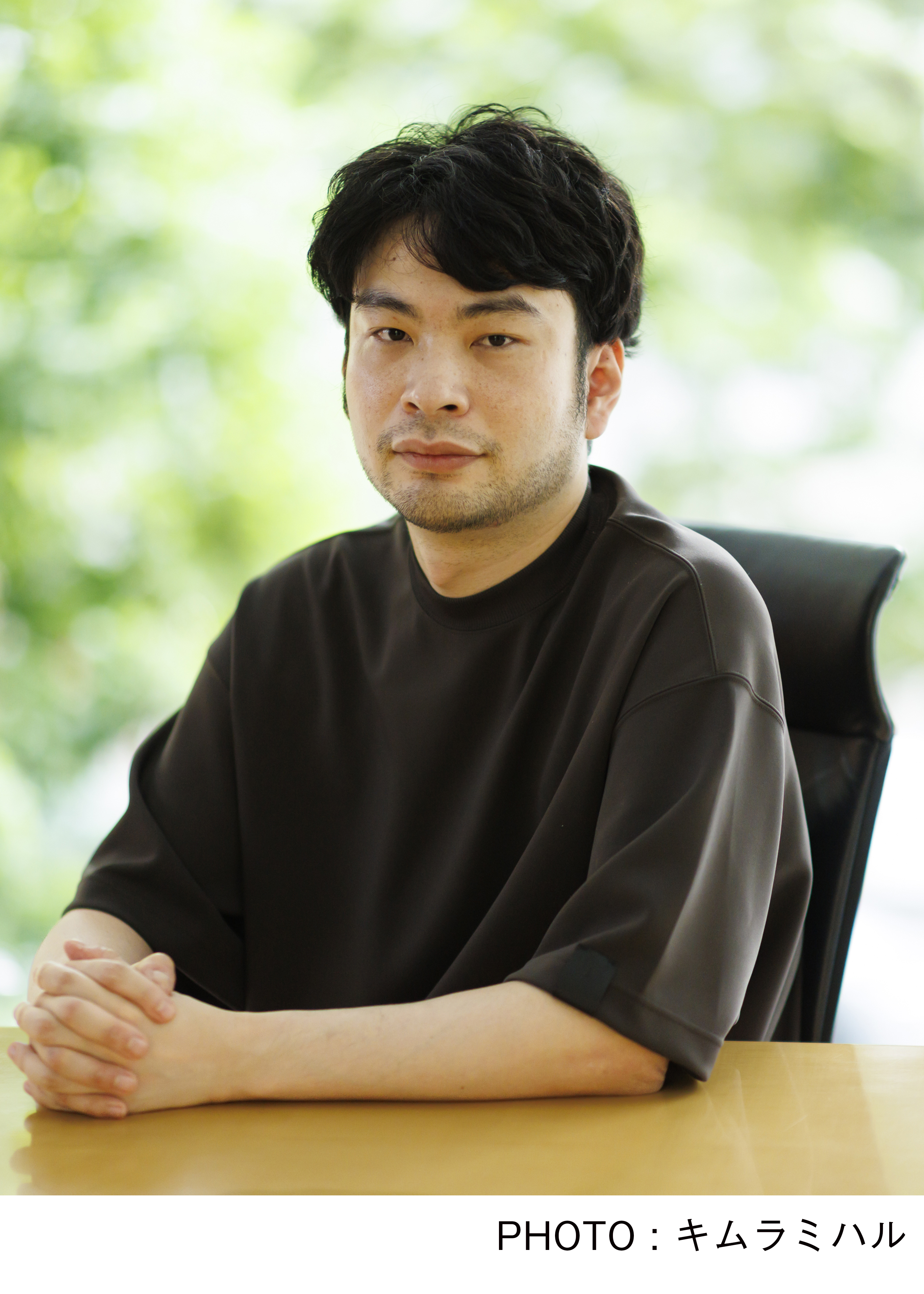
小川 哲 (おがわ・さとし)
1986年千葉県生まれ。東京大学大学院総合文化研究科博士課程退学。2015年に『ユートロニカのこちら側』で第3回ハヤカワSFコンテスト〈大賞〉を受賞しデビュー。『ゲームの王国』(2017年)が第38回日本SF大賞、第31回山本周五郎賞を受賞。『嘘と正典』(2019年)で第162回直木三十五賞候補となる。『地図と拳』で第13回山田風太郎賞、第168回直木賞を受賞。
-
新川 帆立 (しんかわ・ほたて)
1991年アメリカ合衆国テキサス州ダラス生まれ、宮崎県宮崎市育ち。東京大学法学部卒業、同法科大学院修了後、弁護士として勤務。第19回『このミステリーがすごい!』大賞を受賞し、2021年に『元彼の遺言状』でデビュー。最新刊は『先祖探偵』。
新着コンテンツ
-
連載2025年07月15日
 連載2025年07月15日
連載2025年07月15日【ネガティブ読書案内】
第44回 ホリコシさん
「10分遅刻して卒論を出せなかった時」
-
インタビュー・対談2025年07月08日
 インタビュー・対談2025年07月08日
インタビュー・対談2025年07月08日桜木柴乃「波風立てずに生きる器用さを、ちょっと残念だなと感じる大人に読んでほしい」
著者五十代の最後を飾る、集大成的な短編集である本作。仕事に対する現在の思いや、短編を書く面白さをうかがいました。
-
お知らせ2025年07月04日
 お知らせ2025年07月04日
お知らせ2025年07月04日すばる8月号、好評発売中です!
演劇界注目の劇作家・演出家ピンク地底人3号さんによる初の小説を掲載! 遠野遥さんの短期集中連載も最終回を迎えます。
-
インタビュー・対談2025年07月04日
 インタビュー・対談2025年07月04日
インタビュー・対談2025年07月04日石井遊佳×藤野可織「魂を自由にする虚構の力」
ホラー愛好家を自認する藤野さんは石井さんの新作に詰まった四つの物語をどう味わい、そこに何を見つけたのか。
-
新刊案内2025年07月04日
 新刊案内2025年07月04日
新刊案内2025年07月04日給水塔から見た虹は
窪美澄
2人の“こども”が少しずつ“おとな”になるひと夏を描いた、ほろ苦くも大きな感動を呼ぶ、ある青春の逃避行。
-
新刊案内2025年07月04日
 新刊案内2025年07月04日
新刊案内2025年07月04日青の純度
篠田節子
煌びやかな「バブル絵画」の裏に潜んだ底知れぬ闇に迫る、渾身のアート×ミステリー大長編!


