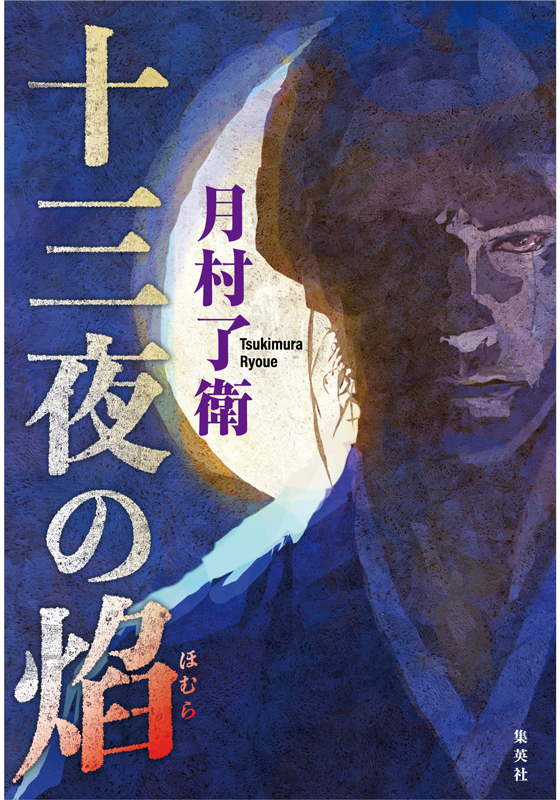第36回小説すばる新人賞受賞作『我拶もん』刊行記念対談 神尾水無子×柳家喬太郎「小説と落語が交わるところ」

落語と出会わなければ時代小説を書くことはなかった。
そう語るのは、陸尺と呼ばれる江戸時代の駕籠舁を主人公にした『我拶もん』で、第36回小説すばる新人賞を受賞した神尾水無子さん。
このたび、受賞作の刊行を記念して、神尾さんが大ファンだという柳家喬太郎師匠との対談が実現!
「小説」と「落語」。
表現方法の異なるお二人に、創作についてのお考えをたっぷり伺いました。
「陸尺」を知った驚きが出発点
――神尾さんは喬太郎師匠の大ファンだそうですね。
神尾 師匠が創作された『ハンバーグができるまで(※)』や『午後の保健室』が大好きなんです。『午後の保健室』のどんでん返しのあざやかさには本当に圧倒されました。
※舞台化もされた喬太郎師匠の人気創作落語。妻と離婚し、普段の夕食は惣菜や弁当で済ませているマモル。そんな彼が突然、合い挽き肉、タマネギ、大嫌いなニンジンなどを買いに来たから商店街の店主たちは大騒ぎ。寂しさのあまり死のうとしているのではと心配した店主たちがマモルの家をこっそり訪ねると、そこにはなぜか元妻の姿があって……。
喬太郎 ありがとうございます。僕も昔は小説が好きだったんです。特にミステリーをよく読んでいて、都筑道夫先生の初期の作品みたいな、小説という形式それ自体がトリックになっているようなものから影響を受けましたね。『午後の保健室』のどんでん返しもそこからだと思います。でも、今日は神尾さんのお話ですからね。小説に関しては、僕はただのおじさんですから。
神尾 いえいえそんな(笑)。『ハンバーグができるまで』を初めて聴いた時、私にはマモル君の最後のセリフが悲しく聞こえてしまったんです。でも、あれは彼の強がりだったのかなとか、もう二度と食べられない奥さんの料理で、苦手なニンジンの味さえも変わってしまったのかなとか、ときどきふっと考えることがあって、まるで短編小説のような味わいがある噺だなと思っています。生意気な言い方ですが。
喬太郎 作り手としては何も考えてないんですよ。聴いた方がいろいろと考えてくだされば、それでいいのかなと思うんですよね。こっちは球を放っているだけで、受けてもらった人たちの『ハンバーグができるまで』になればいい。
『ハンバーグができるまで』は、別れた夫婦ってどんな会話をするんだろうってことへの興味からできた噺なんです。それと、下北沢のスーパーで買ったものを袋詰めしているお客さんの姿を見て、当たり前だけど、いろんな人たちが買い物をしに来て、そこにはそれぞれの人生があるんだなと思って。それを自分なりにくっつけたらああいう噺になりました。
……って、僕の話より神尾さんの話だ。拝読しましたよ、『我拶もん』。
神尾 ありがとうございます。
喬太郎 とっても面白くて、よくこれだけのことをお調べになったなって思いました。僕らもよく高座で駕籠舁をやってますけど、陸尺って言葉は知りませんでしたよ。でも、確かにそうだよな。考えてみりゃ、そのへんの人や荷物を運ぶ雲助と、大名の駕籠を担ぐ人は違うわけだし、こういう職業もあるんだなと。
神尾 ある意味、選ばれた存在でもある陸尺のことを知った時、とても興味が湧きました。でも、陸尺は物語の主人公にならないんじゃないかなとちょっと不安だったんです。誰が興味を持つんだろうって。噺家さんは、創作落語にしろ、古典落語にしろ、今の時代に合ってるだろうか、お客さんにウケるだろうかっていうことを心配されますか。
喬太郎 しますね。だけど、僕らはとりあえずやっちゃうっていうのができるんですよ。一遍やってみて、駄目ならやめちゃえって。僕らがやっていることは文字のかたちで残らないじゃないですか。だからできる。お客さんが面白がってくれるだろうかという不安もなくはないですけど、それも見方によるんだと思うんですよね。陸尺も、確かにこれまでの時代小説では脇役だったかもしれない。でも、それを主役に据えたことで、読者がいろんなことを知れるじゃないですか。陸尺にはこんなにたくさん階級があって、そのてっぺんには御公儀が召し抱える御駕籠之者っていうのまでいたんだって。びっくりですよ。
神尾 私も調べてびっくりしました。
喬太郎 時代小説を手に取る人だったら「へえ、駕籠舁の世界ってこんななんだ」って、興味津々なんじゃないかと思いますよ。
神尾 そう言っていただけると嬉しいです。

説明しすぎるのは野暮
神尾 喬太郎師匠も参加していらっしゃった『十八番の噺 落語家が愛でる噺の話』を拝読して、師匠が言葉遣いをすごく大事にしているとおっしゃっていたのが印象的でした。例えば、「かっこいい」と言わずに「様子がいい」と言うとか、「ど真ん中」は上方の言葉だから、江戸では「まん真ん中」と言うとか。
喬太郎 古典落語をやる時には、やっぱり「かっこいい」よりも「様子がいい」だと思うし、二ツ目の頃に「ど真ん中」と言ったら、とある方から「喬太郎、おまえ、それを言うなら『まん真ん中』だぜ」と言われて、それから気になっちゃうようになりましたね。
神尾 例えば「様子がいい」って、若いお客さんにちゃんと意味が伝わるのかなっていう不安は感じませんか。
喬太郎 前後の流れでわかるだろうって思ってますね。僕も若い頃、古典落語で「様子がいい」なんて言い方を初めて知りましたけど、何となく「かっこいい」ってことかなと思いましたよ。よく覚えているのは「もやいを解く」。「船をもやっておく」っていうのが出てきて、ああ、船を繋いでおくことかと。前後の流れで「あ、こういうこと言ってんのかな」と察しましたね。説明していくと情報量が多くなって、肝心の噺の内容がお客さんに入っていかないと思うんです。野暮ですしね。
神尾 説明って話を止めてしまいますよね。できるだけしたくはないですが、わからないのは困るなって。小説を書くうえでも悩ましいところです。
喬太郎 羨ましいのは、小説は文字で読むじゃないですか。『我拶もん』に出てくる「乙粋」なんて言葉も、文字を見りゃ乙で粋だって想像がつく。やっぱり文字のほうが察しやすいのかなと思います。神尾さんは、ああいう古い言葉をお調べになるのがきっとお好きなんですよね。
神尾 大好きです。書いてるより楽しい時もあるくらいです。
喬太郎 そこが小説家と噺家の違いですよ。僕らは調べるのは嫌いだから。もちろん調べる噺家もいますけど、自分の中にあるもので噺を作る人が多いんじゃないかな。さっきの『ハンバーグができるまで』にしても、自分がハンバーグを作ってみたことがあるから、材料があれとあれとあれだってのがわかってできた噺なんで。これが舌平目のムニエルとかだったらわからないし、たぶん調べても実感をもってしゃべれない気がします。
神尾 そうなんですね。ただ、調べたつもりでも、あとで間違いが見つかることもあって。『我拶もん』の最初の原稿には落語の『花色木綿』のことをチラッと出したんです。でも、あれは当時なかったんですね。気になって調べ直してみたら、『花色木綿』は一八〇二年くらいにできたらしいんです。『我拶もん』の設定が一七四二年なので、『落語手帳』で調べて『てれすこ』に変えました。
喬太郎 そういえば昔、時代劇の『銭形平次』だったと思いますけど、噺家が主人公の回があって、高座で『野ざらし』をやってたんです。その時はまだ単なる落語好きだった大学生の僕から見ても「違うぞ」って思いましたもんね。『野ざらし』が今の形になったのは明治時代ですから。まあ、いいんですけどね。
小説は大変ですよね。史実ってものがあるし、綿密に書かれているからこそ嘘にしていい部分とそうじゃない部分ってのがありますもんね。僕らは「いいんだ、落語だから」の一言で終わっちゃうから。ただ、先輩からは「そんなわけないだろってのも、本当は違うってわかっててやってんだったらいいよ、でも知らずにはやるなよ」って言われますね。
三題噺の作り方
神尾 せっかくの機会なので、もう一つお尋ねしてよろしいですか。
喬太郎 何でも聞いてください。
神尾 師匠の創作落語に『棄て犬』ってありますよね。これをどなたかが「これ以上後味の悪い話はない」っておっしゃっていて。
喬太郎 『棄て犬』はそうかもしれないですね。
神尾 『拾い犬』のほうは本当にいい人情噺で。うるっときてしまったんですけれど。
喬太郎 『拾い犬』はちょっと時代小説みたいな噺ですよね。
神尾 だから、後味が悪いって言われるような『棄て犬』は、どういうふうにお作りになったのかなって。
喬太郎 『棄て犬』は真打になる前にこさえたんですけど、精神的に荒れているというか、落ち込んでいた時期のものなんです。作ったきっかけは三題噺で、何だっけな、棄て犬と、あと二つなんかあって、男が女に棄てられるなんとも救われない噺を作ったんです。もうちょっと救いのあるサゲ(オチ)も考えたんですが、「ぬるいぬるい。何言ってんだ、おめえ」と思ってやめたんですよ。よっぽどの精神状態だったんでしょうね(笑)。
神尾 三題噺は寄席でおこなうものなんですか。
喬太郎 昔は寄席で、前日に三つお題をもらって作ったらしいです。古典落語の『芝浜』も三題噺からですね。『芝浜』は、酔っぱらい、芝の浜、革の財布かな。今はイベント的にやるので、当日お題をもらって二時間か、長くても三時間ぐらいで作るっていうのが多いですね。
神尾 そんな短時間で? すごいですね。
喬太郎 いや、もう追い詰められるとね、何か出てくるもんですよ。新作でも、明日やんなきゃなんねえと思っても噺ができてないとか。最悪、会場に向かいながら考えたりもしますから。
噺家には二種類いて、詳しく台本を作る人と作らない人。僕は作らないというか作れない人なので、作りながらしゃべるみたいな感じですね。切羽詰まると何とかひねり出せるもんなんですよ。だから、その時の精神状態が影響するのも無理ない話で。
神尾 サゲを決めておくとかでもないんですか。
喬太郎 その時によりますね。三題噺だと、一席の落語を作らなければならないので、例えばですね……なんかまた僕のことばかりしゃべってないですか? 「小説すばる」の読者さんは、小説に関係のないじじいの話なんかより、神尾さんの創作の秘密を聞きたいんじゃないですか?
神尾 いえいえ、落語に出会わなければ、私は時代小説を書こうと思いませんでしたし、落語から大切なものをたくさんもらいましたから。『我拶もん』の最後の一行も、落語のサゲのつもりで書いたんです。
喬太郎 そうでしたか。じゃあ、話しますけど、新作落語って、最初にサゲを決めちゃって、謎かけみたいにして作るってやり方もあるんですけど、それだけじゃつまんないんですよね。全く逆にストーリーから作るやり方が僕は多いですね。三題噺で言うと、『ハワイの雪』がそうです。
神尾 はい。存じています。
喬太郎 あれは、お題がハワイアンと雪と八百長なんですよ。それを素直に繋げてうまくいった例です。ハワイは常夏の島。実はハワイでも雪は降るんだけど、そこはイメージでいいので、雪というハワイでは降りそうにないものをくっつければいい。そこに八百長を絡めるってそんなに難しくないので、けっこう簡単にできたんですけどね。
神尾 そのくっつけ方がすごいんです!

ランク付けがあった陸尺の世界
――喬太郎師匠の落語の作り方を伺いましたが、神尾さんはどういう順番で今回の物語を組み立てていったんですか。
神尾 とある時代小説で陸尺という言葉を知りまして、調べてみると背丈でランキングされるってことがわかったのがきっかけです。江戸時代の人ってランキング好きですよね。
喬太郎 相撲の番付のようなものですね。
神尾 ランク付けがあるって知って、がぜん興味がわきました。トップにいる人は嫌なやつに決まってる。有頂天になって、下がなにくそって反発する。そこに江戸抱と国抱の陸尺が仲が悪かったっていうのも知って、きっと見栄の張り合いなんかもあったんじゃないかと思いました。それだけ面白そうな材料が揃ったので、これは書けるんじゃないかと。
喬太郎 駕籠舁は体が資本の仕事ですから、荒っぽいところもあったでしょうしね。
神尾 そうなんですよね。実際、本気で殿様に喧嘩を売るようなところもあって、陸尺が大名を乗せた駕籠を橋のたもとに置き去りにしたという逸話も結構あるんです。それに市村座の騒動を史料で知って、戌の満水という天災があって、トップにいる主人公の桐生がどーんと地に落ちた時にどうなるのかなと。そうして物語が組み上がっていったんです。
喬太郎 おかみさん連中が大名行列の中にいる陸尺を見て、「ご覧よ、あれが噂の“風の桐生”だよ」なんて言うのを読むと、ああ、そういうことあったんだろうなと思いますよね。当時のことですから、テレビなんかの娯楽があるわけじゃないし。
神尾 そうですね。町人からしたら大名行列は邪魔だったと思うんですけど、陸尺みたいなのがいたら、見世物としては面白かったんじゃないかと思うんです。「あのこしらえは貧乏だね」とか、「あそこは金かけてんね」とか。
喬太郎 そういうこともあったでしょうね。
落語から影響を受けた名場面
――『我拶もん』には桐生をはじめ、魅力的なキャラクターが数多く登場します。人物造形はどのようにされたのですか。
神尾 桐生に関しては、さっき申し上げた、トップにいる人間ならではの傲慢さとか、他人の心の見えなさがあって、すんなりと形になったんです。桐生と相対するのが小弥太。二人を真逆の位置に置いてどれくらい喧嘩してくれるかって考えました。私、いい歳してすごく人見知りなので、キャラクターを作る時にも相手になかなか近づけないんです。何となく様子を窺って、どうしよう、どうしよう、みたいな感じで。
喬太郎 へえ。面白いですね。自分が創作した人物に対してもそうなんですか。
神尾 そうなんです。向こうも警戒するんでしょうね。「得体の知れない人がこっちをじろじろ見てる。嫌だわ」みたいな。
喬太郎 「俺のこと、こんなふうに書いてる人がいるよ」ってことですか?
神尾 はい。そんなふうに思ってしまうので、キャラクターが動き出すまでに時間がかかるんです。新人賞の選評を読んでいると、落選作について「誰がしゃべっているかがわかりにくい」という指摘をよく見かけるんですけど、やっぱり人物の書き分けって難しい。落語でも人物の語り分けに苦労なさいますか。
喬太郎 しますね。そうそう、神尾さんの『我拶もん』は誰がしゃべってるかがちゃんとわかるんですよ。桐生と龍太、翔次は同じ陸尺で歳も近いんだけど、どこか違う感じがあってわかりやすい。人物が生きてる。最後のほうで、十歳になったばかりの大工の末弟子が、桐生に内緒話をしますよね。あそこなんか目に浮かびましたね。好きだな、あのシーンは。
神尾 あの場面は落語を意識していました。「こしょこしょ(と囁く)」という表現とか。それに私、落語に出てくる子どもがすごく好きなんです。生意気だったり、こすっからかったりもするんですけど。
喬太郎 あと、深川芸者の粧香って人が出てきますよね。昔、とある師匠に教わった文句を思い出しました。「婀娜な深川、勇肌の神田、腹の悪いは飯田町」。深川芸者は色っぽくて粋なんですね。神田は勇ましい。飯田町、今の神楽坂ですが、あのあたりの芸者は人が悪いっつうんです。今の神楽坂の人たちは「そんなことないよ」って怒るでしょうけど。
神尾 婀娜な深川。その通りですね。男物の羽織を着て、年中素足でっていうイメージです。
喬太郎 あの男物の羽織っていうのは様子がいいですよね。
神尾 本当に。一度実際に見たことがあるんですけど、すごくかっこよくて。
喬太郎 『我拶もん』を拝読していて、最後のほうは「これを読み終わっちゃうと、桐生とか粧香とか、大工の親方の甚吉さん、あと、小太郎もとい小弥太たちにもう会えねえんだ」って思ったら、ふっと寂しくなりました。
神尾 そう言っていただけるとすごく嬉しいです。私も書き終わった時に泣いてしまいました。最後は二人で走って行ってしまったので。あーあっていう感じで。
喬太郎 そうですねえ。でも、あれ、その後の道中の話があるんじゃないのかなと思いましたけど。
神尾 そうなんですよ。ものすごく書きたい気持ちになりました。
喬太郎 それも面白いんじゃないかな。読んでみたいですね。

好きなものにギリギリまで寄せる
神尾 師匠がこれから創作落語でやってみたいジャンルとか、気になる題材はありますか。
喬太郎 等身大になってくんだろうなっていう気はしますね。自分が若い頃は、若者の恋愛物が多かったんですよね。
神尾 『純情日記』とか『すみれ荘』ですね。
喬太郎 そう。でも、中年になって『ハンバーグができるまで』ができて、僕ももう還暦を迎えましたので、同じような歳の人たちの噺を作りたいと思うし、きっとそうなっていくんだと思う。けど、その時に、前期高齢者を主役にするとこういう噺になるよね、っていうものじゃないものをどう作っていけるかですね。
あとは、『我拶もん』もそうですけど、実話を絡めて作るのも楽しいじゃないですか。僕にも古典落語を材料にした『本当は怖い松竹梅』っていう噺があるんです。探偵役のご隠居さんが古典落語の前座噺『松竹梅』の謎を解いていくミステリーです。完全に趣味の世界なので、お客さんにはごめんなさいなんですけど。
神尾 ぜひ聴いてみたいです。
喬太郎 作るのに苦労したんですけど、楽しいんですよね。神尾さんはどんなものに挑戦してみたいですか。
神尾 私はやっぱり江戸時代のお話を書きたいですね。できれば芸能にまつわるものを。大道芸とか、手妻とかが大好きなので。いわゆる王道の時代小説とは違うものになってしまうかもしれませんが。
喬太郎 江戸時代の芸能には、神尾さんが小説にできる題材がいっぱいあるんじゃないですか。ご自分の書きたいものを書けばいいと思いますよ。自分の好きなものに寄せて、これ以上やると独り善がりだよねっていうギリギリまでやっちゃっていい。ギリギリだからこそお客さんが喜んでくれる。僕も落語家としてそんなふうにやっていきたいなって思ってます。
神尾 それが一番幸せですよね。私も自分が好きなものに寄せて、かつ読者の皆さんにも喜んでもらえるような小説を書ける作家を目指したいです。
「小説すばる」2024年3月号転載
プロフィール
-

神尾 水無子 (かみお・みなこ)
1969年、東京都生まれ。神奈川県在住。2023年、「我拶もん」で第36回小説すばる新人賞を受賞しデビュー。
撮影/藤澤由加
新着コンテンツ
-
インタビュー・対談2025年07月08日
 インタビュー・対談2025年07月08日
インタビュー・対談2025年07月08日桜木柴乃「波風立てずに生きる器用さを、ちょっと残念だなと感じる大人に読んでほしい」
著者五十代の最後を飾る、集大成的な短編集である本作。仕事に対する現在の思いや、短編を書く面白さをうかがいました。
-
お知らせ2025年07月04日
 お知らせ2025年07月04日
お知らせ2025年07月04日すばる8月号、好評発売中です!
演劇界注目の劇作家・演出家ピンク地底人3号さんによる初の小説を掲載! 遠野遥さんの短期集中連載も最終回を迎えます。
-
インタビュー・対談2025年07月04日
 インタビュー・対談2025年07月04日
インタビュー・対談2025年07月04日石井遊佳×藤野可織「魂を自由にする虚構の力」
ホラー愛好家を自認する藤野さんは石井さんの新作に詰まった四つの物語をどう味わい、そこに何を見つけたのか。
-
新刊案内2025年07月04日
 新刊案内2025年07月04日
新刊案内2025年07月04日給水塔から見た虹は
窪美澄
2人の“こども”が少しずつ“おとな”になるひと夏を描いた、ほろ苦くも大きな感動を呼ぶ、ある青春の逃避行。
-
新刊案内2025年07月04日
 新刊案内2025年07月04日
新刊案内2025年07月04日青の純度
篠田節子
煌びやかな「バブル絵画」の裏に潜んだ底知れぬ闇に迫る、渾身のアート×ミステリー大長編!
-
新刊案内2025年07月04日
 新刊案内2025年07月04日
新刊案内2025年07月04日情熱
桜木柴乃
直木賞受賞作『ホテルローヤル』、中央公論文芸賞受賞作『家族じまい』に連なる、生き惑う大人たちの物語。