『花散るまえに』刊行記念対談 佐藤雫×今村翔吾「勇気をもって、暗く苦しいほうへ進め」

妻を失う恐怖と孤独から、逆に妻を傷つけてしまう細川忠興。
夫の歪んだ愛と、神の愛のあいだで揺れるガラシャ。
戦国で最も知られた夫婦の壮絶な愛を描いた歴史小説、『花散るまえに』が刊行されます。
刊行を記念して、著者の佐藤雫さんが、憧れの先輩作家・今村翔吾さんに会いに行きました。
新作の話から始まり、面白い歴史小説を書くコツ、直木賞受賞作の創作秘話、そして初めて口にするプライベートの秘密まで、徹底的に話していただきました。
構成/タカザワケンジ 撮影/露木聡子
歪んだ愛に挑戦してみたい
――まずは『花散るまえに』の今村さんの感想からお聞かせください。
今村 佐藤さんが『言の葉は、残りて』でデビューされた時に、この人は伸びるって周りに言ってたんですよ。『花散るまえに』を読んで、着実に伸びてるな、成長しているなって思いました。小説にはキャラクターやストーリー、いろいろな要素があるけれど、佐藤さんは最近の作家の中でも文章が上手い。すごく丁寧な書き方をされる。帯に「たおやかな筆致で描かれる、苛烈な愛のゆくえ。この作品を書く感性をまぶしく思う」という言葉を寄せたんですが、あえて「たおやかな筆致」としたのも文章を味わってほしいから。いまの時代にたおやかという表現は古いかもしれないけど、少なくとも僕は書かないようなやわらかい感じで書かれる方だから。
佐藤 ありがとうございます。
今村 それに題材。細川ガラシャと忠興の夫婦。「この題材できたか」と思いましたね。僕も「何でそんな題材にしたん?」って言われることが多いんやけど、佐藤さんはそれを最後まで書き切ったと僕は思いましたね。
なぜ「この題材できたか」と思ったかというと、僕はガラシャの夫の細川忠興が嫌いなんですよ(笑)。嫌いというか、理解できない。『花散るまえに』は、忠興について佐藤さんなりの答えを出してくれているから、これからは僕の中の忠興はこのイメージです。忠興って、ちょっと精神的に不安定なんじゃないかっていうぐらい――
佐藤 アップダウンが激しいですよね。
今村 そうそう。僕はそういう人間がようわからんし、そもそも行動原理が不明な人間を僕は書きたがらないところがあって。どうして忠興とガラシャを書こうと思ったんですか。
佐藤 『言の葉は、残りて』はデビュー作なので、自分が好きな源実朝を書いたんです。二作目の『さざなみの彼方』は、担当編集者さんから「戦国か江戸でお願いします」と言われて、「じゃあ、戦国で」と、戦国時代で一番興味があった茶々(淀殿)と大野治長の関係を書きました。
今村 僕、『さざなみの彼方』ね。思い出した。読んでたわ、「小説すばる」の連載で。
佐藤 今村さんの『塞王の楯』と連載時期がちょっとだけかぶってました。
今回の『花散るまえに』の打ち合わせでは、担当編集者さんから「題材は何でもいいですよ」と言ってもらえたんですけど、デビュー作からずっと単行本を担当してくださった方なので、私から「佐藤雫に何を書いてほしいですか」と聞いたんですね。いろいろと案が出たんですけど「細川忠興の歪んだ愛が読みたい」と言われて、「あっ、面白そう」と思って。
今村 担当編集が歪んでいるんじゃないの?(笑)
佐藤 そこはわからないですけど(笑)。いままでの作品はピュアというか、純粋な恋愛関係みたいなものを書いてきたので、ここで歪んだ愛に挑戦するのも面白そうだなと思ったんです。
ネットで「細川忠興」を検索すると、「戦国時代のヤンデレ」とか言われていて、ちょっとヤバい人なのかもと思いつつ、忠興がそうなってしまった理由を私なりに考えてみたいと思いました。彼の人格を形成していったものは何だったんだろうと。
とくに彼が、妻の玉――細川ガラシャ――に対して、史実では「死んでほしい」みたいなことを言い残して出陣しています。なぜだろう。その理由を、私なりに考えてみたかったんです。作品の中で彼の人格を形成していくにつれて、書けば書くほど彼のことが好きになってしまって、最後はもう大好きでした。『花散るまえに』は私の創作がだいぶ入っていて、ちょっと現代的な感覚でものを見てしまっていると思うんですけど。
現代的な価値観を持っているのはおかしい?
今村 現代的な感覚でものを見る歴史小説は反発されると言うか、マイナスの意味で言うてくる人も絶対いるし、僕も言われ続けてきたけど、それでいいと思うねんな。
理由の第一は読む人が現代の人やということ。第二は「こんな現代的な人間は当時はいなかった」という決めつけこそが現代人の傲慢やと思うから。この時代に奇人、変人と呼ばれてる人が未来でスタンダードになってる可能性があるように、過去にも「奇人」と呼ばれた価値観で生きてた人がいてもおかしくない、というか絶対いた。
佐藤 すごく共感します。私も、書く人も読む人も現代の人なんだから、現代人の悩みや葛藤、苦しみを、歴史上の人物に重ねてもいいんじゃないのかなとずっと思っていて。
今村 主人公が現代の価値観に近い人物だと、当時の価値観を持った人たちがガヤとして周りを囲むことになる。周囲から批判されたり迫害されたり、逆に憧れられたり、差異を見せることで現代と当時の価値観の違いを表現できる。僕はそれがこれからの歴史小説のあるべき姿の一つやと思ってますね。
そして『花散るまえに』を読んでもらったらわかるけど、ガラシャが神への愛と、夫との人生のあいだでの揺れ動いている気持ちが非常によく描かれている。佐藤さんはご結婚されているそうだけど、やっぱり夫婦とは何かとか考えた?
佐藤 実は『花散るまえに』を書いてる途中で離婚したんです。
今村 そうなんや。聞いてよかったんかな。
佐藤 いいんです。と言うか、かえってありがたいです。小説すばる新人賞の受賞の言葉で「夫に感謝している」と書いていたので、どこかの機会で「離婚しました」と言わないとなと思っていたので。
今村 そうなんや。僕も離婚してるで。僕も言う機会がなくて困ってたからようわかる。しかも僕は作家になる前に離婚してるからたちが悪い。わざわざ言う必要ないやん。言いたいねんけど、ツイッターでいきなり「今村翔吾、バツイチです」って言うのはおかしいやろ(笑)。だから言う機会をずっと探ってた。お子さんは?
佐藤 いないです。
今村 僕もいない。一番気楽なパターンや。
佐藤 そうなんです。だから、自分が食べていければいいっていう感覚でいます。
私は、結婚生活が約七年間あったんですけど、その中で夫婦のあり方に悩んでる時期があって。しかも『花散るまえに』を書いてる時に離婚したので、愛って何だろうって考えずにいられませんでした。『花散るまえに』には夫婦の愛だけでなく、いろんな形の愛が出てきます。親子の愛もあれば、主君と家臣の愛もあるし。もちろん神の愛もあって。
今村 神の愛が一番難しかったんとちゃう? 宗教はハードルが高いって言うか、腑に落ちんと言うか。僕は自分の腑に落ちるまでは書かへんみたいなところがあって、だから難しい題材やと思うねん。佐藤さんが勇気があるなと思ったんは、この題材で宗教は避けられへんやん。
佐藤 難しかったです。キリスト教の愛と一般的な愛は、考え方が違うので。私はキリスト教徒ではないので、しっかり勉強しないと書けないな、と。事前に本や資料を読んで、カトリック教会にも行って取材をしました。
でも、私の中でキリスト教の神の愛がどうしても腑に落ちない部分があったので、その部分をどうするか。ガラシャ自身には腑に落とさせないといけなくて、なおかつ読者にも共感してほしい。高いハードルでした。
今村 忠興っていう存在がいるから、腑に落ちない部分が描けたのかもしれへんね。忠興にとっても神の愛は腑に落ちんもんやから。これが玉だけの一人称小説やったら、どうにかして腑に落とさなあかんねんけど。忠興と玉、この二人の対比によって、宗教への迷いとか、つかみどころのなさが描かれてるからよかったと思うよ。

小説の新大陸へ向かう冒険者に
佐藤 あと、苦労したのはラストシーンですね。ガラシャが死を選択する理由を史実のままでは書けない。史実のままだと、夫の留守中に何かがあれば、妻は名誉を守るために自害しろということになってしまう。ガラシャは夫の命に従って死んだというのが史実だと思うんですけど、それだと今の価値観には合わないし、私自身が納得がいかないんです。
夫に従順な妻、敬虔なクリスチャンのガラシャ像で終わらせてしまっては、この作品は駄目だと思いました。現代の読者、それもキリスト教になじみがない人が読んだとしても共感できるラストシーンにしないと。最初の原稿ではそれができていなくて。
今村 編集者から何て言われた?
佐藤 本にできるレベルにはなってる。だけど「佐藤さん、これで本にしたら、次の仕事来ないよ」って。あとで担当編集者さんは、そんな言い方はしてない、「来ない可能性がありますよ」って言ったって言うんですけど、私にはそう聞こえました(笑)。「僕は佐藤さんをここで終わらせたくないんです」と言われたのははっきり覚えてます。
今村 それはほんとやと思う。作家は一作一作がほんま勝負やと思うし、とくに三作目、四作目は大事。シビアな話をすると、たぶん出版業界の編集者は、一作目から三、四作目までの点の高さと、腕を上げるベクトルの角度を見てるんよ。この間の成長の仕方で、何年かあとの作家の未来をイメージしてるところがある。一作目と二作目だけではデータが少ない。三、四作目まで見れば大体見えてくる。そういう意味では、編集者がこの作品に力を入れたくなる気持ちはよくわかる。
佐藤 そのあとに担当編集者さんとじっくり話し合った内容を反映させてこの形になりました。『言の葉は、残りて』は楽しくて、『さざなみの彼方』はとにかく夢中で、今回は初めて書いてて苦しかったです。真っ暗な夜の海を一人で小舟を漕いでいると言うか。
作家って自分が書かないと出口にたどり着かないですよね。そのことに気づいて、怖くなってしまって。「出口にたどり着かなかったらどうしよう」。その怖さや苦しさを抱えつつ、何とか対岸にたどり着かなきゃと、必死で櫂を漕いでる感じでした。
今村 出口が見えんくなった時には、あえて真っ暗なほうを目指して漕いでいったほうが小説は跳ねると思う。航海中の真っ暗闇も含めて楽しめるようになったら、佐藤雫さんはどんどん小説を書けるようになるんやろうなと思いますね。
ゴールどうしようかとかって考えるやろ。最後どう落とそうかなって思うやろ。考えんでええ。「何とかなるわ」って。経験上、そん時に光明が見えるんよ。僕も『じんかん』の時にそんな状況になったからようわかる。
佐藤 たしかに先にゴールを考えて、そこに着地するためにはどうしたらいいかみたいに考えてしまうところがあるかも。今のお話を聞いて勇気が湧きました。
今村 勇敢なる冒険者に対して、読者も出版界も意外と寛容やと僕は思ってんねん。むしろ勇気をなくした小説家に対してのほうが厳しい。勇敢に挑めば、小説の新大陸、見たことない島に小説の神様が連れていってくれるという謎現象が起こるねん。
僕はどっちかって言うと、最初から無鉄砲やから、まずブワーッて風呂敷を広げて、やたらめったら高くでっかい話を考える。ボールをできるだけ高く投げて、捕れるかどうかわからんけど、ダッシュで捕りに行く。それが楽しめたら、そのわくわく感は次の楽しさにつながりますよ。
佐藤 最初にボールを高く投げるっていうのは、具体的にはどんなことでしょうか。
今村 難しいテーマを設定するってことです。絶対無理みたいなテーマを投げてみる。あとはもっと広いテーマ。自分の手に負えへんぐらい、でっかいテーマを投げて、自分なりの答えを作中の人物と一緒に探していく。
『塞王の楯』で言うと「相互確証破壊」というキーワード。核戦略の専門用語やねんけど、核を持った二国間で、どちらか一方が核兵器を使った場合、使われた方は必ず核で報復する。だからお互いに核は使わない――という理論があるねんな。そのキーワードを戦国時代の砲に適用しつつ、「どうしたら争いのない世が作れるのか」「なぜ戦争が起こるのか」ぐらいの大きなテーマを投げて書くわけよ。
実は、『塞王の楯』は書きながら「これ、最後どうやって落とし込もう?」って思ってた。ぶっちゃけ、ラスト二、三百枚までそうやった。けど、何とか「うりゃーっ」と。そうやって乗り越えると地力がつくよ。挑戦すれば、たとえ失敗しても編集者が修正のヒントをくれるから大丈夫。
佐藤 今回、編集者さんの力をすごく感じました。支えてくれている安心感みたいな。
今村 そういうのはあるな。櫂が流されちゃったら拾ってくれるのが編集者やから。
タイトルも内容もテーマが中心
――佐藤さんから先輩作家の今村さんに聞きたいことがあればぜひどうぞ。
佐藤 たくさん聞きたいことがあるんですが、まずタイトルについて。『塞王の楯』もそうですけど、今村作品のタイトルはいつもかっこいいですよね。タイトルはご自分で考えるんですか。
今村 基本そうやな。人が決めたタイトルってあんまりない気がする。
佐藤 私、いつもタイトルが最後まで決められなくて。
今村 みんな言ってることやけど、タイトルって顔やん。ぶん投げるテーマが決まってるのやったら、一番そのテーマに近いタイトルにしたらそれでOK。小細工は必要ない。テーマが真ん中にないと、こんなんがかっこいいとか、しゃれてんじゃないだろうかという雑念が入ってよくないと思うねんな。先にテーマが決まれば、タイトルが少々ダサくても、書いているうちに話とマッチしてきて、タイトルらしい顔してくんねん。
佐藤 メモしていいですか。「テーマからずれないように」。
今村 まじめやな。僕もめっちゃまじめなこと言ってる、普段と違って(笑)。
佐藤 テーマはどうやって決めていますか。編集者さんと相談しながらとか、自分から「これを書きたい」っていうとか。
今村 僕は自分が書きたいもんや、「この人物を書きたい」があんまりなくて。テーマは日常生活の中、具体的に言えば、ニュースから見つけることが多いかな。
最近だと、タイタニック号の残骸を見に行くツアーで潜水艇が事故を起こしたやん。わざわざ大金を払って、危ないところに行こうとする。何でそんなことするかって言ったら、好奇の心やん。人間は時として命よりも好奇心が上回る。それで書くとか。
テーマを見つけてから、小説に書くならどの時代のどの人物だろうって考えるのよ。パッと今、思いついたけど、人間の飽くなき好奇心がテーマだったら、間宮林蔵で書いてみようとか。絶対に危険ってわかってるし周りも止めるのに「それでも俺は行かねばならぬのだ」みたいな間宮林蔵を描いたら、小説になるかもねとか。そう考える。
テーマが先にあって題材を決めると、常にテーマを中心に据えた小説にできる。先に題材があって後づけでテーマを決めると、ゆで卵の黄身が片っぽに寄ってるみたいになるのよ。常にきれいに黄身が真ん中にあるようになるには、テーマを先に決めるほうがいいねん。次の質問ある?

最後に主人公を送り出す
佐藤 悪役が書けないって言われて、どうしたらいいだろうって悩んでます。書こうと思っても、誰でもそうなるに至った理由があるって思っちゃうんです。どんなに悪い人でも幼いころがあったはず、とか考えてしまう。今回の『花散るまえに』でも、石田三成を悪役にしてくださいって言われたんですけど、三成なりのこうなる理由みたいなものを書いちゃっていますね。
今村 わかるわかる。僕もどっちかっていうと佐藤さん寄り。でも悪を書くべきやとは思うねん。まだ完結してないけど、三部作で書いている『イクサガミ』では根っからの悪人を書こうとしたんよ。もちろんそいつにも悪になった理由みたいのがあんねん。けど、そこは書かんかったらいいねん。僕は表に出してない人物設定がいっぱいあって、それを書かないことで、悪を描こうとしとる。
『イクサガミ』は明治十一年が舞台で、武芸に秀でた二百九十二人が殺し合う話やねんけど、名前すら出てこおへん二百九十二人の人生がある。全員にそうなった理由があんねんけど書かへん。ただ、考えておくと、何かあるやろなって深みだけは残るんよ。その深みで十分って割り切れる勇気を、最近やっと僕も持てるようになってきた。何も考えずにモブを書くと「こいつキャラ使い捨ててるわ」って読者に気づかれるんやけど、考えた上で書かへんのはちゃんと読者に伝わるんやって。
佐藤 今村さんは『八本目の槍』で三成を書いてるから、『花散るまえに』の三成をどう思ったのか気になっていたんですけど。
今村 僕は『八本目の槍』で三成をめっちゃいいやつに書いてるやん。そういう意味で言うと、『花散るまえに』の三成には、「何をっ」って、三成派の弁護人として出ていくところやけど、小説としては佐藤さんが書いた忠興から見た三成でいいと思うねん。
今の話で言うと、自分が誰の弁護人なのかを意識したほうがいいかもしれん。弁護士は相手方に有利な証拠を持っていても、出さへん時もあるやん。そういう感覚かな。「私は誰それの小説を書いてるんだ」「これこれをテーマにした小説を書いてるんだ」と思えば、全員の味方をしなくても成り立つ。僕いま、めっちゃ小説を理解してるやつみたいなしゃべり方やな(笑)。
佐藤 勉強になります。
今村 僕もまだまだ勉強中ですよ。キャラクターって不思議で、自分がつくってるのに理解が追いつかん場合がある。作者とキャラクターが乖離していくと、小説として暴走気味になるから、自分がキャラクターをしっかり理解してあげなあかんなっていう感覚がある。いい小説になりそうな時ほどキャラクターが勝手に走り始めるから、作者はしっかり横について走り続けてあげな、変な方向に行ってしまうような気がするね。
『塞王の楯』の時にそういう危険性を感じた。僕は常に主人公の匡介の隣にいたつもりだけど。ただ、一番最後に必要なのは主人公をリリースしてあげること。
佐藤 リリース?
今村 最後の十ページで、主人公の背中を見送る。旅立たせてあげなあかんと思うのよ。読者のもとに送り出すイメージ。時には離されそうになって必死で追いつき、並走するんだけど、最後はいつも主人公の背中を見てる。
ドキュメンタリー番組でカメラを持って主人公を追いかけている感じ。『情熱大陸』のテーマソングが鳴り始めて「今日から、また匡介は、石を積むのである」と、去っていくシーンで終わる、行き先は読者のところ。
佐藤 わかるって言うとおこがましいんですけど、私もラストシーンを書き終わったあとは、登場人物たちに「いってらっしゃい」という気分になりますね。読者のもとに「行っておいで」って送り出すみたいな。
今村 寂しいね。一つの物語が終わると。
佐藤 そうなんです。すごく寂しくなります。
今村 そういう意味ではシリーズものはいいで。見送っても、また帰ってきよるから。
『ぼろ鳶』(「羽州ぼろ鳶組」シリーズ)は「お邪魔しました」って感じ。必ず家族団らんのシーンで終わるから、大家族もののドキュメンタリーみたいなイメージ。次のシーズンが始まったら「また、お邪魔します」って行けるから。
佐藤 シリーズものも書いてみたいですね。今日、今村さんからお話をうかがって、これからも書いていく勇気がもてました。
今村 がんばってや。小説が好きなんやったら、書き続けて、生き残り続けるしかないんやから。
「小説すばる」2023年9月号転載
プロフィール
-
佐藤 雫 (さとう・しずく)
1988年香川県生まれ。「言の葉は、残りて」(「海の匂い」改題)で第32回小説すばる新人賞を受賞してデビュー。著書に『さざなみの彼方』『白蕾記』がある。
-
今村 翔吾 (いまむら・しょうご)
1984年京都府生まれ。2017年『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』でデビューし、同作で第7回歴史時代作家クラブ賞・文庫書き下ろし新人賞を受賞。2018年「童神」(刊行時『童の神』に改題)で第10回角川春樹小説賞を受賞、同作は第160回直木賞候補となった。『八本目の槍』で第41回吉川英治文学新人賞を受賞。2020年『じんかん』で第11回山田風太郎賞を受賞、第163回直木賞候補となった。2021年、「羽州ぼろ鳶組」シリーズで第6回吉川英治文庫賞、2022年『塞王の楯』で第166回直木賞を受賞。他の文庫書き下ろしシリーズに「くらまし屋稼業」がある。
新着コンテンツ
-
新刊案内2025年06月26日
 新刊案内2025年06月26日
新刊案内2025年06月26日筏までの距離
水原涼
デビュー作で芥川賞候補に挙がった著者が贈る、わたしとあなたの8つの物語。
-
インタビュー・対談2025年06月20日
 インタビュー・対談2025年06月20日
インタビュー・対談2025年06月20日宇山佳佑×檜山沙耶(フリーアナウンサー)「風が吹くたび、物語が生まれる」
ウェザーニューズで気象キャスターとして活躍し、その後も活動の幅を広げる檜山沙耶さんと作品、風、お天気について語っていただきました。
-
お知らせ2025年06月17日
 お知らせ2025年06月17日
お知らせ2025年06月17日小説すばる7月号、好評発売中です!
新連載はいずれも小説すばる新人賞出身の佐藤雫さん、神尾水無子さんの2本立て!
-
お知らせ2025年06月17日
 お知らせ2025年06月17日
お知らせ2025年06月17日本日開店、「スキマブックス」!!
文芸ステーションに新しい読みもののコーナー「スキマブックス」がオープンしました!
-
スキマブックス2025年06月17日
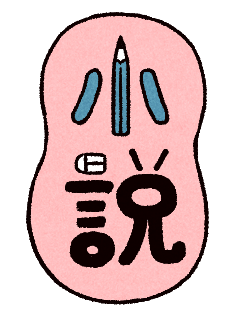 スキマブックス2025年06月17日
スキマブックス2025年06月17日今度こそ許すまじ春野菜といんげん豆の冷製スープ事件
結城真一郎
彼氏が浮気をしているのではないかと疑った大学生は、「あるレストラン」に浮気調査を依頼するが――。
-
インタビュー・対談2025年06月17日
 インタビュー・対談2025年06月17日
インタビュー・対談2025年06月17日堂場瞬一「日本政治の未来をフィクションで問う」
堂場瞬一さんの通算195冊目の作品にして、実験的政治小説第二弾『ポピュリズム』の世界観を語ってもらった。








