デビュー20周年記念インタビュー 絶望から他者理解へ 金原ひとみの20年

2003年、『蛇にピアス』ですばる文学賞を、その数ヶ月後、同作で芥川賞を受賞するという鮮烈なデビューを果たした金原ひとみさん。その後、めまぐるしく変化する社会の空気を鋭くとらえ、その中でもがきながら生きる人間を圧倒的なリアリティをもって描き出してきました。それらの作品が数々の文学賞を受賞してきただけでなく、最近では、ワンオペ育児と母親のペルソナについてのエッセイ(「朝日新聞」2023年11月15日)が大きな反響を呼ぶなど、社会や人間への透徹した眼差しが、属性や世代を超え、幅広い読者の信頼を得ています。若者たちの生の実態を活写した近著『ミーツ・ザ・ワールド』(22年)の映画化も決定し、作家生活20周年を迎えてさらに勢いを増す金原さんの、ここまでの足取りと、今見えている風景、そして今後について。金原さんがもっとも信頼する江南亜美子氏をインタビュアーに招き、伺いました。
聞き手・構成/江南亜美子 撮影/隼田大輔

*
――作家生活20周年、おめでとうございます。2003年、20歳のときに『蛇にピアス』ですばる文学賞を受賞しデビューされた金原さんは、この20年、ひじょうに順調に見えるキャリアを積まれました。40歳になり、ライフステージも変化したかと思いますが、と同時に日本という国を見ても、社会構造が変わり、人の距離感も変容し、共有していたはずの価値観が崩壊、より個人主義が進んだ殺伐たる時代になったといえます。作家として走り続けてこられて、いかがでしたか。
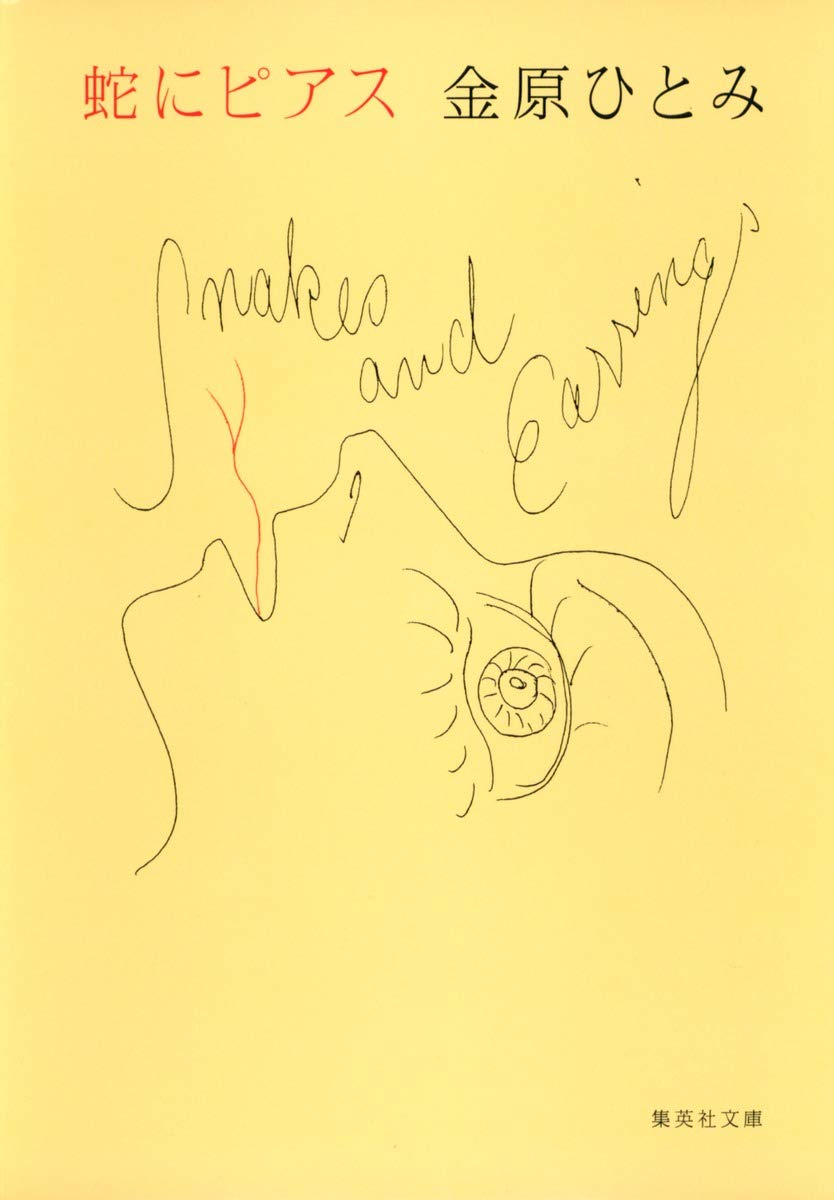
金原 いろんなことが起き、つねに書きたいことやいま書かなきゃいけないことがあり、それを実直に書いていくしかないと痛感し続けた20年でした。フランスに移住したてのころや赤ん坊の育児中は物理的に時間が取れずに書けないときもありましたが、それ以外にスランプらしいものの自覚もなく、ずっと書いてきました。私は出し惜しみせず、そのときの持ち物を全部作品に入れてしまいたいと全力投球するので、長編を書き終えるともう次は何も出てこないかもと不安になるのですが、しばらくすると短編から書き出して、それが連作になっていく。編集の人にも助けられ、書き続けることができました。
――金原さんは、個人の生活と意見を描くなかで、社会の実相や問題点を浮き彫りにしていくタイプの作家だと思います。ただしデビュー当時の『蛇にピアス』から『アッシュベイビー』(04年)、『AMEBIC』(05年)あたりは、個人的な不満や世界の居心地の悪さを全開にする作風で、その後だんだんに変わってこられたという印象です。
金原 最初のころは、大人といわず同世代といわず、自分も含めた全てのものにとがりまくっていました。コントロールのきかない自分自身に振り回され、ブイーンと遠心力でまわっているような強烈な力をつねに感じていて。そんな苛立ちを言葉にかえることで少しずつ自分をたしなめられるようになり、薬を処方するように執筆への衝動に変換していったんです。
――中学3年のときは年齢を偽って、お父様の金原瑞人さんのゼミに潜っていらしたとか。
金原 どうしようもなくアウトプットしたいという欲求だけがあり、確信は持てないけれどいちばんうまくできるのが文章じゃないかと気づいたんです。その道筋が早い段階で発見できたのは、父親の仕事のおかげだと思います。人としてはけっこうごつごつした人生を歩んできましたが、作家としては意外とすーっと行けましたね。
――いまそのころの文章についてどう思われますか。
金原 自分の小説はあまり読み返しませんが、いまだと書かないようなシンプルかつ無骨な文章だと思います。デビュー当時は、技巧的にうまい文章を見てはすげーなと感心していました。たとえば綿矢さんの「さびしさは鳴る」(『蹴りたい背中』)という一文に、これは書けないなと。彼女は文章自体が凝っていて、唯一無二です。自分はたぶんその土俵では戦えないと感じていました。
――2004年、綿矢りささんとの芥川賞の同時受賞は、大きな話題となりました。良くも悪くも対比的に語られる存在です。
金原 たしか芥川賞をとってすぐ、私がOKした対談のオファーを綿矢さんは断ったんです。のちに遊ぶようになったとき、対談断ったよねと聞いたら、「そうだったっけ?」と本人は忘れてて、嫌われてたわけじゃなかったんだー、とホッとしました。
――芥川賞を始めとする文学賞がまだまだ男のものだった時代なので、若手女性作家ブームの到来と周囲が騒ぎすぎたきらいがあります。実際に芥川賞も選考委員の女性の比率が高まるにつれて、女性作家の受賞が目立つようになります。
金原 本当に当時は、担当編集者がみんなおじさんでした。いまは女性や若い人たちが編集部にいっぱいいて、すごく風通しがよくなりましたね。
――デビュー後しばらくしてご結婚と出産を経験されますが、2011年刊行の『マザーズ』は金原さんにとってひとつの転機となったように思います。母親というケア労働、感情労働に対する社会の無理解がパワフルに表現され、社会性を獲得した作品です。

金原 私は不登校の子供時代を過ごし、高校もすぐにやめ、その後はバイトと執筆くらいしかしていなかったので、人間関係を築くといえば恋愛ぐらいでした。しかし子供を持つと、がらりと自分の居場所が変わったんです。何者でもない女の子から、母親になる。周囲も私を母親として見るわけで、出産後の数年間は、ずっと殴られ続けるような、外からの認識と自己認識の差に酔い続けるような感覚がありました。
これをどうにかしたいと考えるなかで、『マザーズ』を構想しはじめ、プロットを練っていたときに、すごい解放感を覚えたんです。全部書いてやる、出してやるぞと。表現することでしか乗り越えられないと自覚していたので、怒りやうらみ、憤りではちきれんばかりの母たちを描くことで、社会に対する自分の考えをうまく外に出す回路を作っていけた。それまでは作品をパッションで乗り切って書いていたのが、『マザーズ』では余すところなく伝えたいという思いから、かなり細かくプロットを作ったんです。初めての連載でしたし、毎回相当の枚数を1年ちょっと書き続けたのできつくはあったんですけど、これをやりきれたのは自信になりました。
――『マザーズ』で展開されるのは、従来型の「よき結婚」や「よき妻」のロールモデルに理想を見出せない女たちが、どのように現代社会をサバイブするかの物語です。同じ保育園に子供を預ける20代の母親3人が登場し、それぞれが一人称の語りを担いながら、育児という社会的再生産の労働への不満を吐露する。ドラッグに逃げたり、愛人を持ったり、子への虐待の衝動を抱えたりもします。
金原 やっぱり母親に求められる顔というものが、つまり「こうであれ」という強烈な要請があるんです。これは実際に自分が母親にならないと見えてこなかったので、とにかく驚きました。保育園の送り迎え、週に何度も病院に連れていき、つねに睡眠不足で、普通の生活を送っているだけでへとへとになるんだけど、なんとか自分を律しつつ、社会と折り合いをつけていかなければならない。そうしたとんでもない状況を三者三様に描いたつもりです。三者三様に破綻し、その不可能性のほうに最終的には行き着いてしまいましたが、私自身はこの破綻を書いて救われました。
――3人がシスターフッド的に連帯して問題がすべて解決、とはならないのが、リアルです。
金原 たがいにすごく突き放しているところがあるし、ばかにしているところもある。ここの部分では連帯できても、この面ではとても同意はできないとはっきりさせていく必要が、現代の人間関係では強まってきたように感じています。
――味方であるはずの夫たちは役に立たないし……。
金原 『マザーズ』の男性たちは本当にひどかったですね。個人的な話ですが、自分が子育てしていたときのワンオペ育児に対する怒りがいまだに、まさにただなかにあるときと同じ鮮やかさでよみがえることがあるんです。殺してやるという意思となって。あの怒りだけは忘れられない。私は小説にアウトプットすることで言いたいことを随分言ったわけですが、その上でこれだけの時間経過があっても全然癒やされていないので、はけ口がない人たちにとっては憤死するような事態だと思います。
――男たちよ、その鈍感さに気づけ、というメッセージがつまっていますか?
金原 もちろん男性にしかわからない抑圧や痛みもあるとは思いますが、母親になった女性たちが世間からどれほどの抑圧を受けているのか、全ての人に知ってほしいと思いました。
*
――金原さんのフェーズがもうひとつ変わったのが『持たざる者』(15年)ではないでしょうか。これは震災後小説と呼びうるもので、物語では震災から3年が経過しており、災害と事故直後の混乱は収束して、表面的には世界は平穏さを取り戻しています。しかし目に見えない同調圧力がひじょうに高まった時代の空気をとらえていますね。
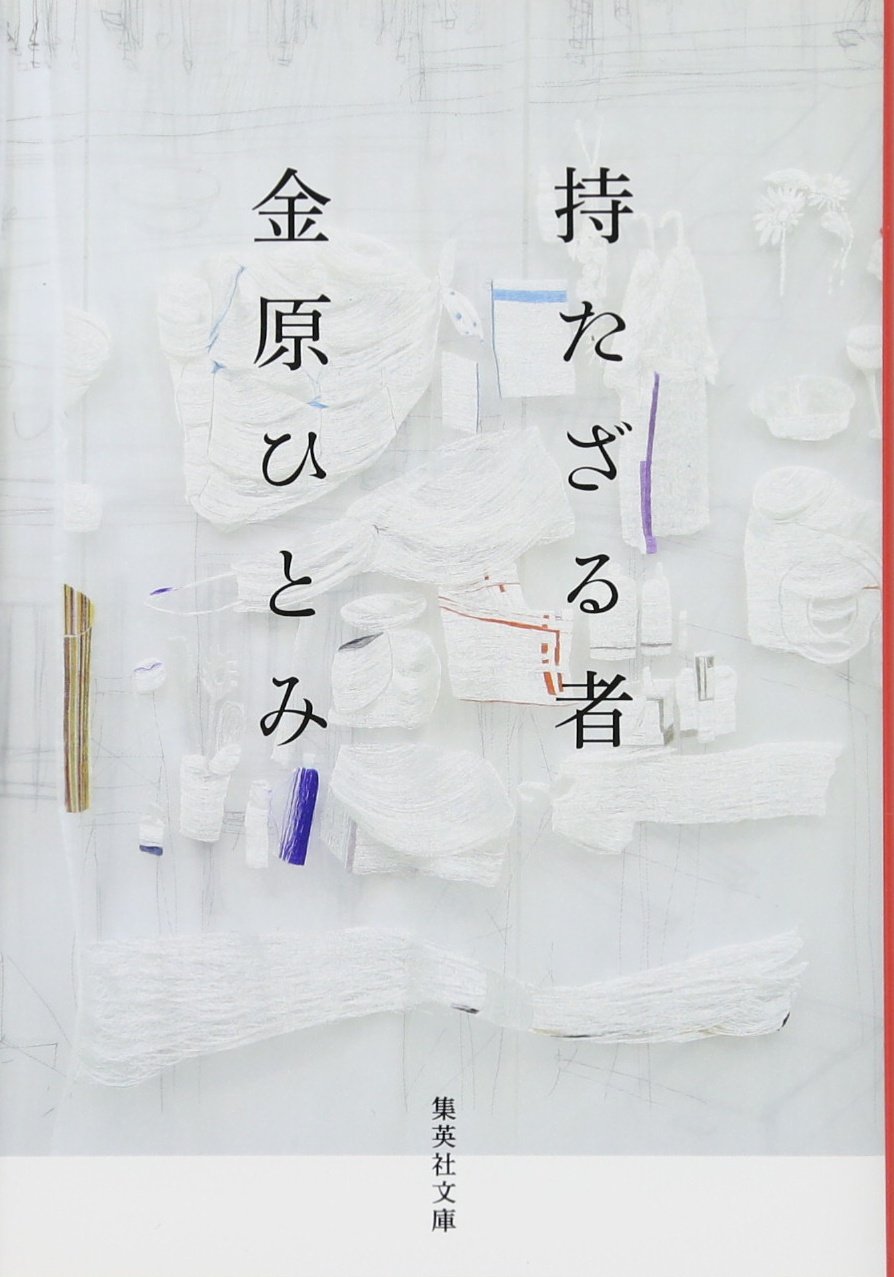
金原 震災とその後の社会については、どうしても総括しなければならないと考えていました。私は震災後に次女を出産してフランスに移住したので、ちょっと離れたところから俯瞰的な視点を獲得できたこともあり、立場によって見えてくるものの違いも体感しました。日本にい続けたらきっと書けなかったであろう視点も交えることで、なんとか震災にアプローチすることができた。いま思えば難産の小説でした。
『マザーズ』が個人的な怒りや思いが三者三様に交ざり合うその裏側で、社会が見えてくるという図式だったのに対し、『持たざる者』は、もっと社会の嫌な部分と密接に関わる物語なんです。書いてすっきりするという感覚もなく、嫌な気持ちと闘い続けながら書く、書かなきゃいけないから書くという感じ。これを書かないと次の作品には行けないと思いました。
――三人称の、男性も含めた視点人物のリレーという形式です。角度によって、その人の見え方が違ってきます。
金原 大震災自体、人の多面性や一筋縄ではいかない部分を照らし出しましたよね。表に出す顔をこれと決めている感覚だったり、でも割り切れないものが残って忖度する必要性にがんじがらめになっていたり。状況によって意外なもろさや、思わぬしたたかさがぱっと現れる、そういう人の複雑さを書きたかったんです。
――最初の語り手の「修人」は、自分の人生のイニシアチブを取るといった強いタイプの人で、自己決断で「母子避難」をさせたのに、震災ダメージで駄目になっていく。いっぽうで「エリナ」は要領のいい姉に比べてイマイチの子だったはずが、ここ一番で状況を打開する力を発揮する。感情のナマナマしさが印象的ですが、どうやって構築されたんでしょうか。
金原 私はそれまでも、日本という国や政治に対して期待はしていなかったけれど、あのときはここまでひどいことになるのかという絶望感と怒りを抱えていました。今回(23年10月)のイスラエルからの邦人救出の際に飛行機代を徴収したのもそうですが、人権を何とも思っていないことが明らかになったことのショックが大きかったです。そんな人権無視が当然という環境に置かれていると、自分もどんどん何が正しいのかわからなくなっていくのではないか、という恐怖もありました。
それと当時は、Twitterを見ても無法地帯と化し、デマも流言も飛び交っていて、誰も信用できない、何を信じるかもこっちに委ねられているという状況でしたよね。インターネットがどういうものなのか、自覚的に考え直さなければならない契機となりました。ポストトゥルースに流されていく人間の面白さも浮き彫りになるツールではあるんですけど。あのときインターネットがなかったら、全く違う世界線だったでしょうね。
――先ほど、この作品を震災後小説だと紹介しましたが、じつは震災とは直接関係なしに自分の持ち物が奪われる「朱里」の視点があることで、普遍的な物語になっています。意識的に書かれたことですか?
金原 震災で不可抗力的に土地を奪われる人もいれば、本当に内輪のくだらない小競り合いで自分のテリトリーを侵される人もいます。こっちはかわいそうだけど、おまえのはどうでもいいということはなくて、その人の主観にならないと見えてこないものがある。人の精神をぶっ壊すのは、物事の大きさには拠らないし、社会がはかることもできません。そして、2つの怒りはしっかり通じています。
いま思うに、みんなの多様性を尊重して仲良くするという価値観には限界があるんじゃないかと、疑義をもたらしたのが震災という出来事だったと思います。私が震災後に岡山に仮住まいをしていたとき、取材を受けたら、東京から逃げるのかとものすごい叩かれかたをしたんですが、私も2人目を産んだばかりで気が立っている状態だったから、誰からも指図を受けたくないという気持ちと、それを許さない人たちがいる状況のはざまでショックを受けました。不寛容さ、同調圧力、あらゆる忖度、いろんな憤りが渦巻いたままフランスに行き、それを煮詰めて煮詰めて、あの物語に落とし込んだんです。

――フランスでは、2015年の「シャルリ・エブド襲撃事件」で、震災というきっかけでなくても不寛容があらわになるさまをご覧になったわけですね。
金原 あれは非常に象徴的な出来事でした。風刺の質はともかく、それが本当に殺意の対象になるところまで行き着いたのを見て、人のあり方がこれまでと変わってしまったと実感した。派生するように11月に起きた「同時多発テロ」では、ちょっとレベルの違う恐怖、アイデンティティクライシスに近いものを感じました。フランスでも多様性の尊重というきれいごとでは収まらない状況があって、国境沿いの人たちは移民問題を抱えているから極右のル・ペン支持者が多かったり。マクロンとル・ペンが競っていたときには、マイノリティの側にはもしもル・ペンが勝ったら自分はどうやって生きていったらいいんだろうという不安が渦巻いていました。当然私も、自分たちがどうなるか分からないと感じました。
――その翌年にアメリカでは大統領選でトランプが勝利し、日本でも排外主義が進んでいった時期でしたね。政治や世相が人々の心や日常に影響を与えてしまうそんな危機感が、金原さんの作品には滲んでいると改めて思いました。話をすこし変えると、金原さんは「文藝」の責任編集号(22年秋季号)で「私小説」をテーマに設定されて、そこにオルハン・パムクの言葉を引用しています。『パムクの文学講義』(岩波書店)のなかで、小説は三次元のフィクションであり、個人の体験を語ることもできるし、もっとも深いことも書けるとパムクは言います。
金原 直球でドキドキしますよね。私は、普通に生きているだけでは何も把握できないタイプの人間で、例えば資本主義も右傾化も移民問題も、すべて本を通して考えてきたんです。いわゆるドキュメンタリーや批評とかではなく、小説で向き合ってきて初めてつかむことができた。私にとって小説が第一の社会なんです。どうやって社会をよくしていくか、憎悪や抑圧と闘っていくかの足がかりはつねに小説にあったし、自分も小説を書くことで、考えを言葉にすることができた。小説がなかったら、とてつもなく無思考な人間になっていたと思うんです(笑)。
――パムクにもその純粋さはあります。世界に分断が進んでも、他者を理解する方法が小説にはあるという。
金原 それが本当にまぶしく、勇気づけられました。小説を繰り返し読み続けることで、そこに描かれた人物から見えている世界や物語を知る。やっぱり小説にしかできないことってあるよなと、今でも小説を読む中で痛感しています。私自身、自分がすごく苦手なタイプの人間も、ここ10年ぐらいはできるだけ小説に入れ込むようにしていて、保守的な人たちもその人の視点をちょっとずつ肉づけしていくと、そうか、こういう閉塞感にいるのかと分かることもある。全面的な理解は難しいかもしれないけれど、試しているところです。
*
――『腹を空かせた勇者ども』(23年)では、自分とはまったく違う性質の人間を、その視点から書くというチャレンジがなされています。その作品の前の、『アンソーシャル ディスタンス』(21年)の表題作などには、新型コロナ禍の時代の世界の閉塞感が鮮明に描かれていますね。『腹を空かせた――』と『アンソーシャル――』はポジとネガの関係にありますが、これまでの金原読者にとってなじみのあるタイプの女性たちが描かれるのが後者です。
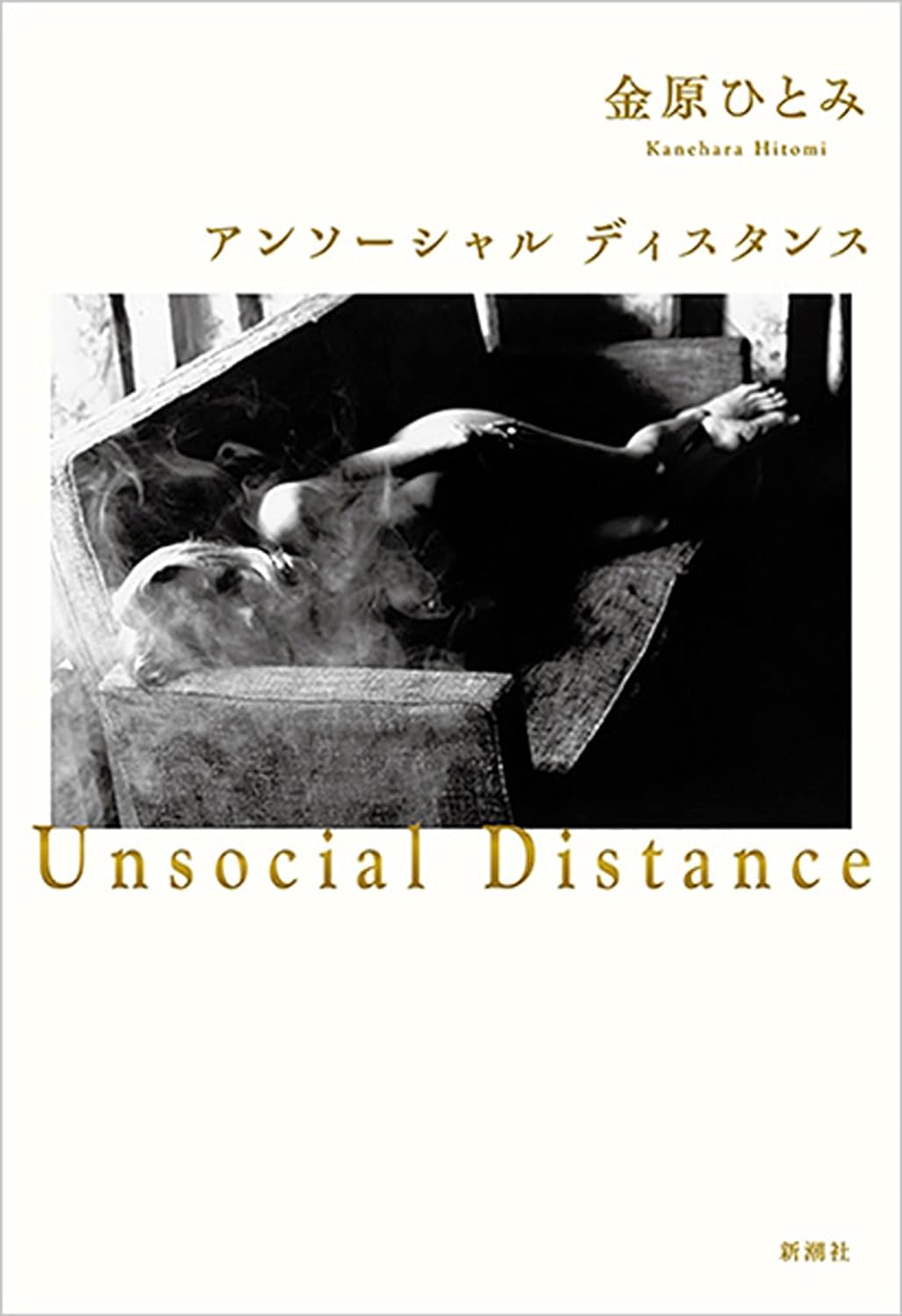
金原 『持たざる者』で、社会的な大きな出来事をどのように小説に生かしていくかを実践したので、コロナ禍でもそれをやりたいと思いました。時間をかけてしまうと、状況がどうなるかまったく分からなかったから、病理が解明される前に、あの瞬間のムードを書いておきたいと思って、スピーディに書きました。まるでハリウッド映画の設定でしたよね。終わりなき日常が突然終わり、非日常に突入した。あんなパラダイムシフトが起こるとは考えもしなかったので、アドレナリンが出ていたんだと思います。人を見るとウイルスのように感じたり、初めての経験がたくさんありました。
――未知の病がどれほど人間にとって恐怖だったか、いまはもう忘れかけていますが……。そしてコロナ以前に書かれた短編も『アンソーシャル――』には収録されていて、「ストロングゼロ」や整形依存症を描く「デバッガー」も時代の空気が濃厚です。
金原 言われてみると、暗い小説ばっかりですね。確かに私がデビューした当時にはなかった空気感――どこまで行っても満たされないものがあるという感覚は社会全体から最近、強く感じます。コロナ禍が引き起こしたのは、同じ出来事でも人によって捉え方が全然異なり、軋轢を生むという状況でした。テロや放射能ではなくウイルスがそれを起こしたというのが絶妙なラインで、日本人の気質に、奇妙に合致してしまった気もします。
――ああ、「マスク警察」とか、ある種の潔癖感が日本らしさ全開でした。
金原 フランスだったら違ったんだろうなと思います。そしてこの、喉元過ぎたあとの何もなかった感、みんなちゃんと忘れちゃうんだという呆気なさは、皮肉な希望でもありますね。
――私は大学で教えているのですが、コロナと同時に入学して大学生活がめちゃくちゃになった学年が、卒業しようとしてます。マスク姿しかなかった4年間を経て、すべては忘れ去られていく。彼らの視座から見たコロナ体験は、私のとは違うだろうなと。
金原 私も中学生の子供の親としてコロナ禍を過ごしたわけですが、子供とはいえ圧倒的な他者である人間と日々暮らしていることが結構身につまされて、『腹を空かせた勇者ども』になっていったんです。家庭内の空気って母親がつくりがちなので、以前は私が重たい空気を醸していたと思うんですけど、長女の陽の力で跳ね返されるようになった。家の中での長女の影響力も強くなっていく。彼女らは新しいものとつねに触れ合っているから、新陳代謝も激しいし、どんどん新しいアプリを使いこなしていく。コロナに対しても、しようがないよねって大人より柔軟に受け止めつつ自分たちのルールに則って平気で遊んでいて、日常にコロナが溶け込んでいる感じがちょっと羨ましくもありました。

――コロナがプリインストールされた世代なんですね。
金原 私はコロナ禍が始まったとき、自分が人間だと思っているものの本質が変わってしまうかも、変わったあとに小説にどんな意味が残るんだろうと、恐怖を感じたんです。でも若い子たちは変わらず生きていてそれは心強かったし、彼らがコロナ禍に果敢に順応していくことに興味を覚えました。
――『腹を空かせた――』は、思考を言葉で表明することをしない、言葉の表現の前に存在している中学生であるレナレナが視点人物でした。金原作品には珍しいタイプなわけですが、チャレンジングでしたね。
金原 そうですね、こういう人を小説で書くのは結構難しくて、1話を書いたときに伝わるかな、中学生たちのモノローグで最後までもつのかなと、もどかしさは感じました。だから母親が登場して言語化すると、書くのもめちゃくちゃ楽しかった(笑)。でもそんな母親のような、言葉で物事を認識する人々を世間がどう受け止めているのか、めっちゃうざいみたいなその空気を描くことができたなと思います。
――なんでも言葉で説明できると考える層を相対化する物語世界です。でもそれが実際の社会でもあるわけで……。
金原 そっちのほうが多いですからね。この世の中で、分かり合えないんだからと線引きをして、お互いに距離を取ってうまくやるというのは現在の処世術として必要なところではありますが、もうちょっと寄り添いたいという気持ちを持てる相手を描きたかった。でも関わりかたはどうしても、自分の流儀じゃないとできないというもどかしさですね。
――レナレナは恋愛至上主義の母親に対し、その価値観をひっくり返すような「はあ?」という反発をみせる。すると母親も、無理に恋愛をしなくていいんだと歩み寄るんです。ここは完全にこれまでの金原作品のプライオリティが相対化されていて、とても面白かったです。
金原 社会自体が変化したのも感じますし、自分が大切にしてきたものがべつに大したものではなかったのかも、という気づきもあります。私はずっと恋愛をしてきて、男の人と一緒に暮らす、ペアになるのがスタンダードでしたが、娘は、なにそれ、という感じ。恋愛はしたいけど、無理してまではしたくないと。恋愛するために恋愛するみたいな、恋愛自体が過大評価されてきた時代じゃなくなったことはいい変化ですね。いろんなものを犠牲にしながら私たちは恋愛を続けていたけれど、莫大なコスト、労力、時間がかかる面倒なものなんだという、新しい視点でした。
――レナレナとも違う、完全な他者の視点で描かれたのが『ミーツ・ザ・ワールド』という作品でしょうか。恋愛にも興味なしの、アニメオタクの27歳、由嘉里が主人公です。堅実に銀行勤めをしながら、オタ活に余念がない人物ですね。

(集英社)
映画化決定!
金原 最初に書きたいなと思ったのは、キャバ嬢の「ライ」が抱く希死念慮です。しかし彼女のモノローグにすると完全な無になってしまうから、あえて「由嘉里」の視点から書いてみようと考えました。ちょっとポップなテンションになりましたね。これまで書いてきた他者の積み重ねがあったので、意外と書いていて楽しかったし、利害が一致した人たちがくっついて、人生のある一瞬を共に過ごすという瞬間を切り取れたかなと思っています。フランスにいるときに構想を考え始め、一時帰国をするときに歌舞伎町にホテルを取ったりして、その町並みから発想していきました。ただこの数年でまた歌舞伎町のニュアンスが変わってしまったんですけど。
――たむろするのがさらに若年化しているのかな。
金原 以前も若い子は溜まっていたとは思いますが、昔はあったセーフティネットがなくなってしまったというか、よりダイレクトな暴力や搾取が増えている気がします。
この作品は、映画化が決まりました。詳細はまだ非公開なのですが、ポップ路線の青春映画になるのかなと、とても楽しみです。
*
――これまでざっと主要な作品について振り返りつつ話していただいたのですが、金原さんが小説を通して世界を観察し、人に媒介することに忠実な作家だと改めてよくわかりました。
金原 私は音楽も好きだし、映画も好きだし、絵画も好きだけど、文章じゃないと届かない場所というのがあると思っています。しかも詩でも俳句でも短歌でもなくて、小説でしか到達できない秘部がある。もちろんその秘部は人によって場所が違うのでしょうが、私はそこに触れたい、触れられたいと願って、読書と執筆を続けています。
――エンタメのためのエンタメを作ろうとは思わないですか?
金原 そうなんですよね。エンターテインメント的なものとして小説を消費できたら、また違ってくるんだろうなとは思うんですが、あんまり惹かれないです。
――教えることにも興味はないですか?
金原 そこまで教えたいことはないですね、小説に書いていることが、いちばん純度が高いと思っているので。島田雅彦さんに、20歳から40歳より、40歳からの20年のほうがあっという間だよと言われたので、より集中して書き続けようと思ってます。
――最後に伺いたいのが、金原さんが責任編集をされた「私小説」の特集などを拝見しても、主人公の存在が自分にオーバーラップして読者に捉えられても、それは構わないという胆力を感じるんです。書かれた存在とご自身の同一視に対して、どう思われていますか?
金原 その特集を組む際にいろんな作家のかたにご依頼をして、何人かにはお断りされたんですが、どちらかといえば断ってきたのは男性が多くて、もしかすると外からの見え方、読者からの同一視を嫌うこともあるのかなと感じました。でも私はそのへんけっこうどうでもよくて。
――オートフィクションの女王ともいうべきアニー・エルノーについて、「自意識について言葉でこれほど肉薄できるのはすごい」ということをおっしゃっていたインタビューもありますが、それは私が金原さんの小説に対して抱く感情と同じです。
金原 私にとって小説は取り繕う場所ではないので。執筆を通して社会を見るということが大事なので、かなりエクストリームな私小説的スタイルを取るエルノーの態度には、共感します。もちろん、周囲の人の理解があるから書けているところもあるのだろうとも思いますが。
――これからも社会や人間というものの様々な変化を受けながら、取り繕うことなく、書いていかれるのだろうと想像しますし、信頼しています。次の作品、そして次の20年も楽しみにしています。
(2023.10.17 神保町にて)
「すばる」2024年1月号転載
プロフィール
-
金原 ひとみ (かねはら・ひとみ)
1983年東京生まれ。
2003年『蛇にピアス』で第27回すばる文学賞を受賞。
04年、同作で第130回芥川賞を受賞。ベストセラーとなり、各国で翻訳出版されている。
10年『TRIP TRAP』で第27回織田作之助賞を受賞。
2012年『マザーズ』で第22回Bunkamuraドゥマゴ文学賞を受賞。
20年『アタラクシア』で第5回渡辺淳一文学賞を受賞。
21年『アンソーシャル ディスタンス』で第57回谷崎潤一郎賞を受賞。
22年『ミーツ・ザ・ワールド』で第35回柴田錬三郎賞を受賞。
新着コンテンツ
-
インタビュー・対談2025年07月08日
 インタビュー・対談2025年07月08日
インタビュー・対談2025年07月08日桜木柴乃「波風立てずに生きる器用さを、ちょっと残念だなと感じる大人に読んでほしい」
著者五十代の最後を飾る、集大成的な短編集である本作。仕事に対する現在の思いや、短編を書く面白さをうかがいました。
-
お知らせ2025年07月04日
 お知らせ2025年07月04日
お知らせ2025年07月04日すばる8月号、好評発売中です!
演劇界注目の劇作家・演出家ピンク地底人3号さんによる初の小説を掲載! 遠野遥さんの短期集中連載も最終回を迎えます。
-
インタビュー・対談2025年07月04日
 インタビュー・対談2025年07月04日
インタビュー・対談2025年07月04日石井遊佳×藤野可織「魂を自由にする虚構の力」
ホラー愛好家を自認する藤野さんは石井さんの新作に詰まった四つの物語をどう味わい、そこに何を見つけたのか。
-
新刊案内2025年07月04日
 新刊案内2025年07月04日
新刊案内2025年07月04日給水塔から見た虹は
窪美澄
2人の“こども”が少しずつ“おとな”になるひと夏を描いた、ほろ苦くも大きな感動を呼ぶ、ある青春の逃避行。
-
新刊案内2025年07月04日
 新刊案内2025年07月04日
新刊案内2025年07月04日青の純度
篠田節子
煌びやかな「バブル絵画」の裏に潜んだ底知れぬ闇に迫る、渾身のアート×ミステリー大長編!
-
新刊案内2025年07月04日
 新刊案内2025年07月04日
新刊案内2025年07月04日情熱
桜木柴乃
直木賞受賞作『ホテルローヤル』、中央公論文芸賞受賞作『家族じまい』に連なる、生き惑う大人たちの物語。







