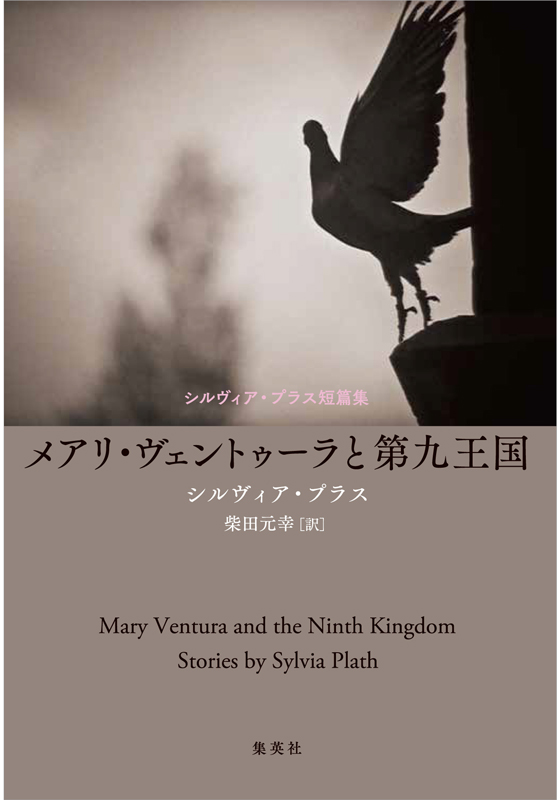『メアリ・ヴェントゥーラと第九王国』対談 柴田元幸×小林エリカ「今日、シルヴィア・プラスを読むということ」
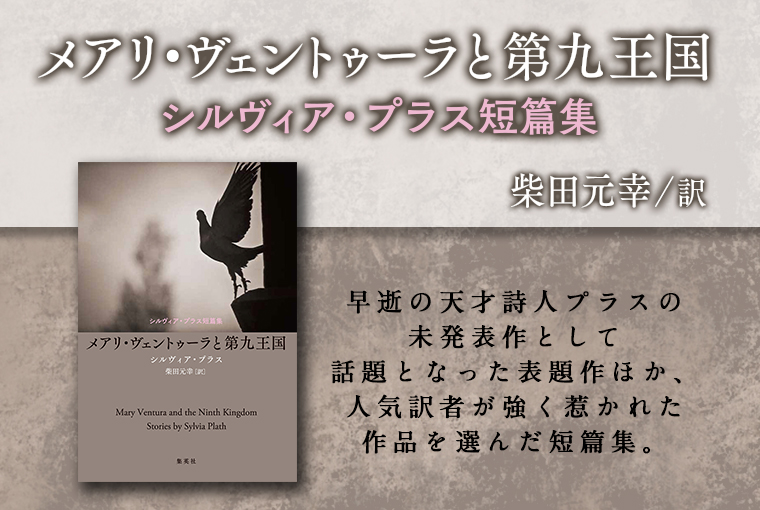
翻訳家の柴田元幸氏がかねてから惹かれていたシルヴィア・プラスの短篇を八篇選んで訳した作品集『メアリ・ヴェントゥーラと第九王国』(本邦初訳三篇を含む)。表題作は没後五十年以上を経て発見され、二〇一九年に全米でも大きな話題となった。
プラスの創作、特に十九歳のときニューヨークで過ごした、“ガラスの覆いに閉じ込められたような”ひと夏の情景から始まる自伝的長篇『ベル・ジャー』(一九六三)を愛読する作家・漫画家の小林エリカ氏がこの短篇集や、対談の前に収録されている、こちらも日本初訳の「ザ・シャドー」を読んで、訳者の柴田元幸氏とプラスの魅力について語り合った。
構成/長瀬海
現在の「生きづらさ」との接点
小林 シルヴィア・プラスに関しては、昔、長篇『ベル・ジャー』を読んだときの衝撃がとにかく凄まじかったんですね。あの体験をよく覚えていたから、今回、柴田さんの翻訳でプラスが読めるって聞いて、わくわくしていました。ただ、一方で、プラスと柴田さんがどう結びつくのか気にもなりました。個人的な印象になってしまうのですけど、プラスと柴田さんの組み合わせは意外というか、どこか少し離れている気がしていたので。でも、最初の作品「メアリ・ヴェントゥーラと第九王国」を読んだときにふっと、宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』を思い出して。柴田さんと、古川日出男さん、管啓次郎さん、小島ケイタニーラブさんたちが朗読劇『銀河鉄道の夜』をなさっていたなって。そのことを思い出したら、意外と直線的に繋がって、なるほどなって勝手に腑に落ちたんです。
柴田 あ、そうですか。よかったです。
小林 私は『ベル・ジャー』が大好きなんですが、プラスの短篇ははじめてのものも多くて。この短篇集は、彼女のエッセンスがぎゅっと一つになっていて、それを柴田さんの翻訳で読めるのが何とも幸福な体験だったということをまずお伝えしなくちゃって思っていました。柴田さんは、なぜ今回、プラスを翻訳なさったのですか?
柴田 おっしゃる通り、『ベル・ジャー』がインパクトの強い作品であることは間違いありません。ただ、短篇には長篇にないような味わいがあることも確かで、それを日本の読者にも知ってもらいたいと思ったんですが、僕がプラスを翻訳することがどこまで許されるのか、実はまだよくわからないんです。お前なんかにプラスの何がわかるんだって言われると、言葉に詰まる。
小林 どんなふうにですか?
柴田 まず僕は女性ではないし、例えばプラスの自殺衝動に反応できるわけでもない。大学の授業で僕は、登場人物を外から見て裁くんじゃなくて、まずはその人の身になってみることから始めた方が建設的に読めるんじゃないかとよく言っていたんですが、シルヴィア・プラスの場合には、そう簡単にこの人の身にはなれない。というか、この人の身になって読むというのはすごく覚悟が要ることだと常々考えていました。特に長篇の場合はそうですよね。
プラスの長篇や詩には、彼女自身のことが書かれていることが多い。だから、そこに書かれている「自分」というのが僕の「自分」と相当違うので、なかなか入っていくのが難しい。ただ、短篇だとかなり違っていて、プラスはそこで他人とか世界とか、「自分」の外を見ようとしている。これだったら語り手、あるいは書き手の身になることもできるかなと。
小林 なるほど。確かに彼女自身のことをすべて理解しようとするのは難しいですよね。
柴田 ええ。ただ、生きづらさという言葉が広く使われるようになった現在の世の中で、プラスの作品は以前より身近に感じられるようになっているんじゃないか。だから僕みたいな人間、つまりプラスの門外漢にも開かれていいんじゃないかとは思いました。
そもそも文学って他人になってみるためのツールなので、男が女性の文学をわかっちゃいけないなんてことはないと思うけれど、僕自身、一九八〇年代から翻訳を始めて、二〇一〇年ぐらいまでは、女性作家の作品は立ち入ってはいけない領分のように思っていました。あるいはイギリスの作家は自分の専門じゃないからやるべきじゃない、とかね。でも、当事者じゃないと書いちゃいけない、訳しちゃいけないみたいな空気は嫌なんですよね。だから逆に、当事者じゃなくても翻訳していいんじゃないかっていう気になってきたし、好きなものはなんでも翻訳しようと今では思っています。そもそも日本人がアメリカ文学を訳してるところから、もう当事者じゃないんだよね。
小林 柴田さんがそういった逡巡をされた末に、この短篇集の翻訳を手掛けられたっていうのは、なるほどと思うのと同時に、素晴らしいお考えだと感じます。私も作家として活動しているなかで、当事者性について考えることが多々あります。私は戦争を経験していないし、“放射能”にまつわることを書くときも同様です。戦争のことが、“放射能”のことの何がお前なんかにわかるのかっていつか誰かに言われるんじゃないかって悩みながら書いてきました。でも、民話を採訪されている小野和子さんや被災地の声を掬い取られている瀬尾夏美さんのお仕事を拝見していると、部外者であるからこそ見えてくるものもあり、声を聞いて伝えるということの覚悟を思うようになりました。
それは翻訳にも言えるのかもしれないと、今お話を聞いてはじめて気がつきました。立場が違うからこそ見えてくるものもあるかもしれない。シルヴィア・プラスという小説家に、私自身、すごく熱い気持ちで共感しながら読んできました。女として生きることの苦しさや生きづらさを彼女がきちんと言葉にしてくれたことは、私にとって本当に支えになりましたし、今なお共感する女の人たちもすごく多いと思う。けれど、その苦しさや悔しさを他の性の人もまた理解しようとすることができる、というのが小説の素晴らしさだし、実際翻訳をとおしてそれを実践するというのは凄いことだと思う。
柴田 よかったです。もちろん、訳すと決めるのはあくまでも対象に惹かれることが大前提なんですけれど。
小林 柴田さんがおっしゃった、現在の世界の生きづらさとの接点というお話には目を開かされました。やっぱり柴田さんの訳でこの短篇を読むことができたのが嬉しいし、プラスとはなんとなく距離を感じてしまうような人にも読んでほしいと思います。
柴田 この訳書がその役割を果たせれば嬉しいですね。
小林 あとがきで書かれていますけれど、冷戦下の社会の苦しみと、抑圧を受けてきた女性という個人の苦悩が繫がって書かれている、というのはこの短篇集を読むとよりはっきりとわかります。もちろん『ベル・ジャー』でも同じことを感じたはずですが、今回、もっとクリアになった気がして、新しいプラス像が発見できた気がします。

シルヴィア・プラス 著
青柳祐美子 訳
(河出書房新社)
嘘をつかない物語
柴田 『ベル・ジャー』という作品は、『キャッチャー・イン・ザ・ライ』の女性版とも見られると思うんです。つまり、カウンターカルチャーが一九六〇年代後半に登場するとともに、若者が生きるための選択肢も増えるんだけど、『ベル・ジャー』と『キャッチャー~』はそれ以前の、男の子や女の子に与えられた役割がすごく限定されていた時代の若者の物語として二つとも読めるんじゃないかなと。『キャッチャー・イン・ザ・ライ』では、はっきりとは書かれていないけどホールデンは最後、精神を病んで病院に入っているし、『ベル・ジャー』のエスターも入院することになる。共通点は多くて、二つ並べてみると見えてくるものがあると思う。ただ、もちろん違いもあって、肉体的な痛みの感覚などは『ベル・ジャー』の方が生々しくて、エスターの痛みが行間から伝わってきます。
小林 すごく面白いです。若者のバイブルって意味では確かに似ているところがあるのかも。私自身、『ベル・ジャー』は、なんでこんなに私の痛みをわかってくれるんだろうって衝撃を受けて、バイブルのように読んだ経験があります。だからこそそれを書いたプラス本人が最後に自殺してしまうのは、とても辛くて……。憤りのようなものがずっとあったんですけど。
柴田 『キャッチャー・イン・ザ・ライ』との相違点のほうをもっと考えた方が良いかもしれない。例えば、ホールデンには、もしかしたらそれは幻に過ぎないのかもしれないけど、一応、拠り所はある。妹がいて、死んだ弟がいて、彼女たちが体現しているものにしがみつくことができる。でも、『ベル・ジャー』の主人公には何もない。それが苦しいですね。
小林 それとやはり肉体的なひりひりとした暴力的な痛みですよね。サリンジャーの『キャッチャー・イン・ザ・ライ』は私にとってはもっとクールで洗練された痛みというか。まあどちらの痛みがいいとかそういうわけではないのですが。
今回の作品集で言えば、「十五ドルのイーグル」や「五十九番目の熊」にも肉体的な感触を伴う痛みが克明に描かれていて、肌感覚への訴え方が凄まじい。実際に登場人物が痛みを感じている描写だけでなく、会話一つにも肉体的な痛みが込められています。
柴田 だから、時々、社会的他者を表現するときにやや差別的とも感じられる言い方になったりするけれど、それはプラスが自分とは違う人々の持つものに生々しく反応していることの表われだと思います。そのことと小林さんのおっしゃった肉体的な痛みの描写の根元は同じなんじゃないかな。感度の良さのようなものを持っているから、自分とは異なる人間の「醜さ」にも強く反応する。
小林 そうした「醜さ」は他人事ではなくて、社会のなかで自分自身が持っていたものだって書き方をするから驚かされるんです。外の世界をここまで見て書かなきゃいけないんだと。例えば、「ブロッサム・ストリートの娘たち」は最後、語り手の非常にドライな言葉で終わります。皮肉といえば皮肉だし、痛々しくもあるんだけど、切実に共感できる。この人はきれいごとや嘘なしに世界を見ていて、そんな世界の見方を私たちにも教えてくれる小説家なんだなって。
柴田 そこが僕にとってプラスの作品を『キャッチャー・イン・ザ・ライ』とは別の意味で自分のこととして受け止められる理由なんでしょうね。
小林 作家自身の世界の見方や、物語るという本質的な部分に共感できるというような。
柴田 そうですね。先ほど小林さんが「メアリ・ヴェントゥーラと第九王国」を読んで『銀河鉄道の夜』を思い出したっておっしゃいましたけど、言われてみれば、『銀河鉄道の夜』はジョバンニ以外、みんな死者ですよね。「メアリ・ヴェントゥーラと第九王国」も汽車に乗る話ですが、第九王国に向かっている人々はある意味では死者であるわけです。そのなかでメアリという少女は一人、私は死なない、死んでたまるかと決める。メアリは建設的なジョバンニなのかもしれない(笑)。
小林 本当ですね(笑)。私のなかでは二つの作品がふっと繋がりました。両作とも、人を傷つけたり、自分も傷つけられたりといった、加害や被害、あるいは良心の呵責というものに真正面から向き合っていて、それでもなおこの世界で生き続けることに逡巡する人たちの物語なのかもしれないな、と。鉄道というメタファーも、そう考えると両方の作品において、どこか切実なものとして選ばれている気がします。勝手な読み方かもしれませんが。
柴田 いえ、とても面白いです。しかしこの作品、シルヴィア・プラスが大学在学中に創作の授業で書いたものなんですけど、先生はこれにAマイナスをつけたんです。どうしてAじゃないんだって思っちゃいますよね。
小林 厳しい! 私は今、その先生よりずっと先の未来を生きているから、そう思ってしまうのかもしれないけれど。作中でこの汽車に乗ったのは自分の意思じゃないんだって主張するメアリに対して放たれる、「あなたは受け容れた。あなたは反抗しなかったのよ」って言葉が余計苦しく感じられる。プラスの生涯の結末を知って読むとそれがなお重い。
柴田 その反面、さきほど僕は『ベル・ジャー』のエスターには誰も拠り所となる人がいなかったと言いましたが、この短篇集にはときどき、そばにいてくれる人がいるんですよね。今おっしゃった「あなたは受け容れた。あなたは反抗しなかったのよ」という言葉を突きつける「メアリ・ヴェントゥーラと第九王国」の女性も、実は主人公をよき場所に導こうとしています。「ブロッサム・ストリートの娘たち」の「あたし」が勤め先の病院で仲良くなったドティなども、その奔放な態度で、「こうふるまえばいいんだ」という範を主人公に示している。実は『ベル・ジャー』でも最初、ドリーンという自由闊達な女性がそうした役割を担っているんです。でも、彼女はすぐ消えてしまう。結局のところシルヴィア・プラスは、誰かが答えを持ってくれているという希望みたいなものをいつも持てたわけではなさそうです。
「待ち」のしんどさ
小林 今回の短篇集に収められた物語はどれも死の感覚が濃厚ですよね。特に後ろに行けば行くほど、だんだんと迫ってくる感じを受けます。
柴田 末尾に「みなこの世にない人たち」を持ってきたのは、最後で死の世界に入っていくような並びにしたかったんです。
小林 なるほど。「これでいいのだスーツ」でさえ、一見、明るい童話的なフォルムの物語なのに、不思議と暗さを感じさせる。
柴田 それはどのあたりですか?
小林 マックスの家族のもとに、一着のスーツが届きますよね。お父さんから順番に着ていくんだけど、誰もしっくりこない。みんなが口々に自分は「カラシ色のスーツを着る歳じゃない」とかって言って、着るのをやめる。そんな場面が続くと、どこかどんよりとしたムードになる。それと、これは柴田さんがあとがきで指摘されていますけど、試着する段階で母親だけスーツを着ることから除外されている。母親はスーツを直そうと奮闘しては毎回、やっぱりいらないと断られていますよね。それも悲しいし、シビアな世界がほんのりうかがえます。
柴田 しかも、みんな試着しては、これは僕に似合わない、じゃなくて、これを着たら周りにどう思われるだろう、って考えるでしょう。会社でこんなスーツ着てる人いない、みたいに。
小林 そう、それって『ベル・ジャー』にも実は繋がることなんじゃないかと、読み返して思いました。こうしたらこう周りに思われるかも、誰にどう見られるかを常に考えなくてはいけない息苦しさが、繰り返し繰り返し、しつこいほどに描かれている。
自分から積極的に選びとることで恋も仕事もかわいさも獲得していきたいはずなのに、誰かに認められたり見出されたり選ばれて初めてそれを保証される、そんな世界が描かれている。だから、懸命に努力してもそれが報われなかったり、選ばれたとしても気持ちがすれ違う。そもそも自分自身が選ぶ側には立てないという不幸。
柴田 実は、僕も今日の対談前に『ベル・ジャー』を読み直したんですけど、そのことを一番強く感じました。
小林 常にかわいく見られなきゃ、とか、洗練されているように見られなきゃ、賢く見られなきゃ、経験豊富なように思われたい、という強迫観念がある。女の子同士もいつも比較対象になってしまう。そこから逃れられない苦しさ。あの時代、特に女性であるがゆえに選ばれるのを待たなきゃいけないという「待ち」のしんどさとそこへの憤りが綴られていると思うんです。それは「これでいいのだスーツ」にも通じるものなんじゃないかな、と。
柴田 なるほど、面白いですね。
小林 周りの人、特に力や地位のある男性たちにこう思われたら「待ち」から外されるんじゃないか、でも本当はもっと自分で積極的に選びたい、という矛盾と息苦しさ。それは現代の日本でもありますよね。
柴田 現代でも女性は特に大変だと思います。もちろんそれは男性も無縁なことじゃなくて、外からの評価をすべて取り払って、自分で「これでいいのだ」って確信できることって、普段、僕たちが生きていてそんなに多くないんじゃないですかね。
小林 私たちに必要なのは「これでいいのだ」ですね。
柴田 そうそう。これはバカボンのパパから借りたんですけど(笑)。
小林 名訳ですね!
柴田 「これでいいのだ」も難しくて、下手をすると排他的な発言になってしまう。誰も傷つけずに自分で確信を持って「これでいいのだ」って言えることって、実は限られているんじゃないかなと今回、改めて思いました。
小林 確かに、ここに描かれているのは排他的な「これでいいのだ」とは違うものですね。バカボンのパパ的な、別の次元から自分自身を全肯定できる「これでいいのだ」がある。
柴田 だから結論としては、我々に必要なのはバカボンのパパになることである(笑)。
小林 プラスもバカボンのパパになれれば、もしかしたらもっと楽になれたかもしれないし、生き延びられたのかもしれないと、思わずにいられないですね。
柴田 シルヴィア・プラスは極貧家庭に育ったわけじゃないんですが、お父さんが早くに亡くなっています。それで奨学金や助成金をもらって、何とかやりたい道を進んでいった。作家になってからも、作品を出版社に送ってアクセプトされた/リジェクトされた、と毎回一喜一憂しています。他人の評価なんか無視して達観していればいい、なんて空気じゃないんですね。
小林 それもやっぱり常に他人から選ばれないと、評価がないと生きられないってことに直結しますね。その切実さがプラスの作品には書かれているんですね。『ベル・ジャー』の中でも男の子にあの女の子は選ばれるけれど自分は選ばれない、あるいは選ばれても気が乗らない、という場面や状況が綿密な筆致で描かれている。そういうことの連続がとにかく辛い。
柴田 開き直って、私はそういう価値観とは無縁な場所で生きますからって言いたくても、そんな場所はたぶんどこにもない。
小林 どこにもないというのはすごく苦しいですね。とはいえ、この短篇集の作品は、苛烈な状況のなかに救いがあったりして、そうしたアンビバレントさがうまく編み込まれているものが多いような気もします。「ブロッサム・ストリートの娘たち」もラストは社会の側から見ると皮肉な結末なんだけど、でもそれが真実でもあって、読んでいてすっきりもするけど、複雑な気持ちにもなる。そもそも舞台が病院で、女の子たちが一緒に働いている情景が描かれているのがいいですね。
柴田 この女の子たちのチーム感は救いになっていると思います。一方で「ジョニー・パニックと夢聖書」の方はそれがないからけっこうきつい。語り手は一人で孤立しています。「ブロッサム・ストリートの娘たち」には暗い面と明るい面が同居していて、リアリズムの枠のなかでうまく表現されている気がします。
小林 女の子たちのやりとりがスラップスティックみたいで、いい味を出していますね。
ジャッジをしない
小林 「ミスター・プレスコットが死んだ日」では知人の男性が亡くなって葬式に駆けつけた「あたし」が、知らずに故人の最後に使ったグラスで水をごくごく飲みますよね。すると、そこの娘さんが、それは「パパが最後に飲んだグラス」って言う。「あたし」が急いで謝ると、息子さんが「いつか誰かが飲まなきゃいけないんだからさ」ってフォローします。私はその場面がすごく好きです。しかもグラスを使っちゃった直後、「あたし」の頭のなかに故人が最後の一杯を飲んで顔が真っ青になる姿が浮かんでくるのも。
死ってそんなに遠いところじゃなくて、グラスに口をつけるだけですぐそこにあるものなのだとあの文章を読んで思いました。例えば、ふだん何気なく東京を歩いていても、ああ、この道にも空襲で亡くなった人の遺体が転がっていたんだ、とふと気づくことがある。よく考えてみると、死って実は身の回りにある。自分の日常と人の死がすっと接続される表現で、とても印象深い場面です。しかも、プラスの実体験らしいですね。
柴田 そうなんです。実体験だからうまく書ける、というふうに決めちゃいけないと思うけど、あそこの実感はちょっと特別ですね。わあごめんなさい、ってあわてて謝って、「いつか誰かが……」って慰められてまたあっさりホッとする。自分に自信がないから、やたら針が左右に振れるんですね。個人的にはそこにすごく共感する。自分が正しいと思うから、人間は独善的になってしまうわけですから。
小林 確かに、自分に自信がないと断定できないですもんね。そうした自信のなさが、かえって真摯に感じられる。
柴田 自分は正解を持っているわけじゃないってところから始める。ホールデンは正解を持っている。彼は感受性の部分では、これはphonyでこれは本物、みたいな判断をしますよね。その判断を周りの人と共有できないところが彼の痛さで、プラスの小説の女性たちのしんどさとは別です。
小林 それは、さっきお話しした、女性が選ばれる側の存在として社会に規定されがち、ということにも繋がっているのでしょうか。
柴田 まったくそうですね。
小林 普通だったら、あそこでグラスのシーンなんてわざわざ入れたりしないと思うんだけど、それをあえて書き込む。すごく挑戦的だし、そこにこそ真意があるってプラスは思ってるんだろうなというのが伝わってきます。
柴田 小説を書く人ならではの意見ですね。僕は、ただユーモアとリアリティがあるな、ぐらいにしか考えてなかった。
小林 私はプラスを読んでいて、あ、ここまで書くんだと思うことがけっこうあるんです。あえて過剰な書き方をしているというか。例えば、『ベル・ジャー』で物語の最初の方に、ドリーンがバーで知り合ったレニーという男性の家に遊びに行き二人がじゃれ合っているのを見せつけられる。真夜中、酔いつぶれたドリーンがホテルの部屋の前にやってきて、廊下で吐いて倒れてしまうシーンがあります。彼女を抱えていたエスターはドリーンをわざと吐瀉物とともに廊下に放置して、朝起きたら黒い染みだけがあった。えっ、ここまで書く? と。けれどさすがにドアに鍵だけはかけずにいる。こんな描写に誠実さを感じて、あぁ、すごく好きだなぁって思います。
小説を書いていると、作者である自分の醜さがさらけだされすぎないようにどうしても気配りや手加減をしてしまうという罠がある。だけど、プラスは、それが真意であるなら、自分の心の醜さも手加減なしにちゃんと書く。本当にかっこいい。
柴田 作中の人物が友達にきついこと言ったりもしますしね。しかも、それを反省したりしない。超自我がないから正解もないというか。ここではこう振る舞うのが正しい、みたいな視点がないんです。だから、あいつのあれは間違っている、なんてジャッジもしない。
小林 そう! ジャッジがないんです。それがすごい。
柴田 生理的な好悪だけ。
小林 その生理的な好悪を誤魔化さずに書いているのがいいですね。例えば、「十五ドルのイーグル」で、最後にタトゥー職人の奥さんが出てくる場面で、これまでのことがひっくり返されるんだけど、彼の奥さんの嫌な態度や、それに対する語り手の感じ方もぜんぶ素直に書いている。こうきたか!って(笑)。あれもまた、ジャッジをしているわけではない書き方。やはりジャッジをしないという姿勢の奥底には、常に選ばれる立場でしか生きられない苦しさが潜んでいるんでしょうね。
柴田 そのとおりですね。ジャッジできるのに黙っているんじゃなくて、そもそもできない。
小林 ジャッジされることしか経験してこなかったということですね。先ほど柴田さんがおっしゃった出版社に原稿をリジェクトされる話も、そうだと思います。幼い子どもが二人いるのに原稿料をもらえなかったら生活できなくなるから、そういうジャッジが生きることと死ぬことに直結してくる。身を削りながら書くような作風の作家だから、きっとリジェクトされることは自分を否定されているようにも思えただろうし、余計に辛い。そんなギリギリのところにいるのに、自分ではジャッジできないし選べない。
柴田 「ジョニー・パニックと夢聖書」なんかも、今ではプラス短篇の代表作とされていますけど、実は最初に出版社に掲載を断られています。
小林 あの作品に関しては、何の前知識もなく短篇集を最初から読んでいくと、「ブロッサム・ストリートの娘たち」と物語上のコネクションがあったりして、びっくりしました。
柴田 「ブロッサム・ストリートの娘たち」で「あたし」のボスだったミス・テイラーが出てきたりしてね。話が繋がると同時に、見方を変えれば同じ人間も違ったように見えるかもしれませんよと言っているようにも思える。
小林 プラスは自分のなかにもう一つの世界があったんじゃないかと思います。それが現実とは別の居場所になっていたかもしれない。でも、そうした別の世界があってもなお彼女が生き延びられなかったということが、私にはすごく悔しい。別の居場所があって小説を書いていても耐えられないほどの痛みを彼女に与え続けた何ものかに、私は憤りを覚えます。
柴田 ヴァージニア・ウルフも同じでしょうか。
小林 そうなんです。私の好きな作家たちが最後に自殺してしまうということがすごくショックで。小説を読んでいると自分の指針になってくれるような先輩を見つけたような気持ちになるのに。彼女たちが自殺しないでだらだらとでもいいから生き延びて年を取った先に書いた作品が、物語が読みたかった、と私は切実に思います。
これからのシルヴィア・プラスたちに
小林 今回、短篇集に収録されなかった作品で柴田さんが翻訳された「ザ・シャドー」という小説を読ませていただきました。これがまた素晴らしい。
柴田 やっぱり入れればよかったかな(笑)。「五十九番目の熊」か「ザ・シャドー」かで迷って、前者を入れたんですね。
小林 プラスって現実を物語に昇華する、その仕方で驚かせてくれますよね。さっきの「ミスター・プレスコットが死んだ日」でのグラスで水を飲む場面、「五十九番目の熊」では彼女の夫だったテッド・ヒューズを模した人物が痛い目を見たり。『ベル・ジャー』ももちろんそうだけど、現実に起きていることを世界と接続しながら物語に仕立てている。「ザ・シャドー」もまさにそんな作品で、何もわからず読んでいると、だんだん父親がドイツ人であるという個人的なことと体制の問題に接続されていって、さらにそれがもっと大きなものに繋がるラストが見事。「夜が世界の半分、あたしたちがいる方の半分をかき消し、もっと先まで消していくとともに、あたしの心のなかの影も長くなっていった」。名文ですね。
柴田 よかったです。それと僕は、末尾のお母さんの一言が悲しいなと思います。悲しいけど、いい。お母さんは綺麗事を並べれば娘が納得するとは思っていないし、だからと言って、世の中ってそういうもんだからへこたれるなって根性論を説くわけでもない。「そういうふうに考える人もいるわ」って一言で終わるところに、突き放すわけでもなく受け入れるわけでもない、さっきのジャッジをしないという姿勢が表われていていいなと思います。
小林 「ザ・シャドー」じゃなくて、「五十九番目の熊」の方が柴田さんとしては収録したかったのですか?
柴田 いやー、迷うところですけど、「五十九番目の熊」は夫との実体験に基づいた作品で、その結末が体験とあまりに違うのが衝撃で、その衝撃に引きずられて(笑)。まああと「ザ・シャドー」は、一人称の主人公に語らせる上でプラスが子どもになりきってないところがあるのはちょっとマイナス。
ちなみに「五十九番目の熊」は、夫のテッド・ヒューズがあんまり評価していないんですよね。「ブロッサム・ストリートの娘たち」でせっかくあそこまで行けたのに、この作品でまた平凡な次元に戻ってしまっていると言ってます。自分に相当する人物がひどい目に遭うことが、判断に影響しているかどうかはわかりませんが。
小林 ひどい! 上から目線だし。すみません怒りしかわいてきません。ていうか、私は「五十九番目の熊」好きです。
柴田 それはやっぱり、シルヴィア・プラスの味方をしたくなりますよね。
小林 彼が「これはよく書けてた」、「これはダメだ」ってジャッジをする側に立って、決して自分が脅かされることはないだろうという立ち位置にいることもまた……。
柴田 彼女の死後にヒューズが編んだ短篇集も、「うまくいっている作品」と「その他の作品」というふうに章分けしてあって、Aマイナスをつけた先生みたいだなあって思うよね。写真だけ見ると、売れっ子詩人の夫と作家兼詩人として前途有望な妻の美男美女夫婦に見えるんですけど。
小林 今でこそ、グルーミングなどの概念も広がって、ジェンダーにおける権力関係が問題としてはっきり見えてくるようになりましたけど、昔はすごく見えにくかったですよね。私自身の子どもの頃を思い返しても、権力のある年を取った男の人と若い女の子の組み合わせはロマンチックなもののように思っていたし憧れさえ抱いていたけれど、今の視点から見ると、あれってもしかしてホラーだったのかもしれない、と思います。私が今現在から過去のプラスを振り返って見ると、いやいや、そんな辛いこと頑張らないで、酷い夫からはとにかく逃げて! という気持ちになりますけど、そうした世界の渦中で生きていると見えないこともあるし、逃げ場もない。もしかしたら、今の私にもまだ見えていなくて、未来にわかるような苦しさもあるのだろうと思います。
以前、『光の子ども』を描くために、二十世紀前半の科学者の歴史を調べているなかで女性に関する記述が非常に少なかったことに驚いたのを覚えています。こんなにも書き残されていないんだとショックでした。やっぱり歴史に残る有名な偉い科学者は男性がほとんどなんですね。マリー・キュリーみたいな人ってすごくレアで。それすらもたまたま結婚した夫がいい人で、たまたま本人も頑張り屋さんで、みたいな「たまたま」でしかない。一方で、科学者を目指したけど結婚した夫ばかりが研究に打ち込み自分は子育てに追われて病んでいくとか、業績を横取りされて踏み躙られるとか、そういうケースはたくさんありました。歴史に描かれずに消えてしまった女の人生ってなんなんだろうって、すごくもやもやしました。
そういう声をどうやったら聞けるんだろうというのは、私がずっと考えていることです。プラスの向こうにはたくさんのプラスがいて、彼女たちは第九王国さえ持てずに死んでいった。そう思いながら読むと、ますます物語の重みと凄みを感じます。
柴田 最初に『ベル・ジャー』を通して伝わってくるのは生理的な感覚だという話をしました。渦中にいる本人は、そうした痛みがなんなのか自分ではわからないんだと思います。もしそれを自分で完璧に整理した言葉で、私の内面にあるのはこういうことですって抽象的な次元で提示するとしたら、やっぱり伝わってこないでしょう。そういう感覚的な事柄を、よくわからないまま物語を通して伝えるというのが小説の効用なんじゃないでしょうか。
小林 プラスの作品を読んで、その息苦しさに気づくという体験は、私にとってはとても救いになりました。誰かが息苦しいと嘆いている声を聞いて、あぁ、自分もそういえば息苦しかったんだ、と、初めてわかることもある。それがないと、息苦しいことにさえ気づかず日常生活を送りながら、ただ追いつめられていってしまう。短い作品一つを読んだだけでもハッと目を開かせてくれるものがありますね。
柴田 プラスを読んで、小説を書く上で影響を受けた部分はありますか?
小林 創作上の技法に関することっていうよりも、例えば、こんなふうに思っていることを素直に書いていいんだと知ることができたのがとても大きいですね。小説を読んで物語の作り方や表現に感銘を受けることはたくさんあります。でも、自分の人生の指針になるような、自分にとっての切実な小説って私にとってはそんなに多いわけじゃなくて。『アンネの日記』、ウルフの『ダロウェイ夫人』、それからプラスの『ベル・ジャー』。こうした作品には、その書き方を通して、生き方について多くのことを教えてもらいました。こういうふうに世界を見て、生きていてもいいんだ、と思えるきっかけになりました。
ウルフの「意識の流れ」も、私が見たり感じたりしていた世界を、そのまま物語にしてもいいんだよ、と示してくれた。物語や社会というものは、きっちり直線的で論理的なだけでなくてもいい。プラスには、あたりまえのように自分自身も選びジャッジする側の目線になって読んだり書いたりしていたことを反省するきっかけを与えてもらえました。自分が見たり感じたりしている世界をそのままに勇気を持って書いていいっていうことを教えられた。プラスやウルフとの出会いは、そういう意味でとても大切なものです。彼女たちの小説を読んで以降、自分の心のなかにあるものについてはどんなに醜いことも、複雑なことでも、誠実に書いていこうと意識するようになりました。
柴田 具体的な生き方というより、正直になっていいんだっていうことですね。
小林 はい。正直に感じたことを正直に書く、そういった真摯な書き方を学びました。柴田さんが今日、絶対的な正しさがないのがプラスの特徴だっておっしゃいましたけど、私がプラスに共鳴していたのは、そこなんだと改めて思いました。彼女の不安だったり、これが正しいって言えない、そんな曖昧さのなかにある優しさだったりを私は求めてシルヴィア・プラスを読んでいたんだって、今回の短篇集を読んで改めて気づかされました。発見されたばかりの小説を、こんなに早く届けてくださって、本当にありがとうございます。
柴田 いやいや、こちらこそ、しっかり読み込んでくださってありがとうございました。これからもプラスが読まれる世の中であってほしいですね。
(2022・5・31 神保町にて)
「すばる」2022年8月号転載
プロフィール
-
柴田 元幸 (しばた・もとゆき)
1954年東京都生まれ。翻訳家、東京大学名誉教授。著書に『生半可な學者』(講談社エッセイ賞受賞)、『アメリカン・ナルシス』(サントリー学芸賞受賞)など。現代アメリカ文学のみならず、古典も含めて多くの翻訳を発表。トマス・ピンチョン『メイスン&ディクスン』の翻訳で日本翻訳文化賞受賞。編集代表を務める文芸誌「MONKEY」および英語文芸誌MONKEY New Writing from Japanでは鮮烈な企画を展開、日米の読者を魅了している。2017年、早稲田大学坪内逍遥大賞受賞。
-
小林 エリカ (こばやし・えりか)
1978年東京生まれ。作家・マンガ家。2014年『マダム・キュリーと朝食を』で第27回三島由紀夫賞・第151回芥川龍之介賞にノミネート。その他の著書に『親愛なるキティーたちへ』、『彼女は鏡の中を覗きこむ』、『光の子ども』(1巻~3巻)など。
新着コンテンツ
-
新刊案内2024年07月26日
 新刊案内2024年07月26日
新刊案内2024年07月26日地面師たち ファイナル・ベッツ
新庄耕
不動産詐欺の組織犯罪の闇に迫る、新時代のクライムノベル『地面師たち』の待望の続編!!
-
インタビュー・対談2024年07月26日
 インタビュー・対談2024年07月26日
インタビュー・対談2024年07月26日新庄耕「釧路がシンガポールになる、というあり得なさで「いける!」と」
今夏Netflixでドラマシリーズ化された前作と、その待望の続編である本作への思いを著者に伺いました。
-
インタビュー・対談2024年07月19日
 インタビュー・対談2024年07月19日
インタビュー・対談2024年07月19日青波杏「「語れない」をテーマに描く、女性同士の繫がりと植民地の歴史」
現代の台湾に生きる女性二人が、古い日記に隠された真実を探る物語。謎と日常、過去の歴史と現在が交わる中で見えてくるものとは。
-
インタビュー・対談2024年07月19日
 インタビュー・対談2024年07月19日
インタビュー・対談2024年07月19日ファン・ボルム「休めない社会だからこそ、休む人たちの物語を描きたいと思った」
本屋大賞翻訳小説部門第1位に輝き、ロングセラーを続けている本作への思いを、著者のファン・ボルムさんに伺いました。
-
お知らせ2024年07月17日
 お知らせ2024年07月17日
お知らせ2024年07月17日小説すばる8月号、好評発売中です!
奥田英朗さん「家」シリーズの待望の新作読切を始めとした大特集のテーマは”家族”。新川帆立さん、遠田潤子さんの対談も必読です!
-
連載2024年07月12日
 連載2024年07月12日
連載2024年07月12日【ネガティブ読書案内】
第32回 浅倉秋成さん
「ポジティブ思考が羨ましくて仕方がない時」