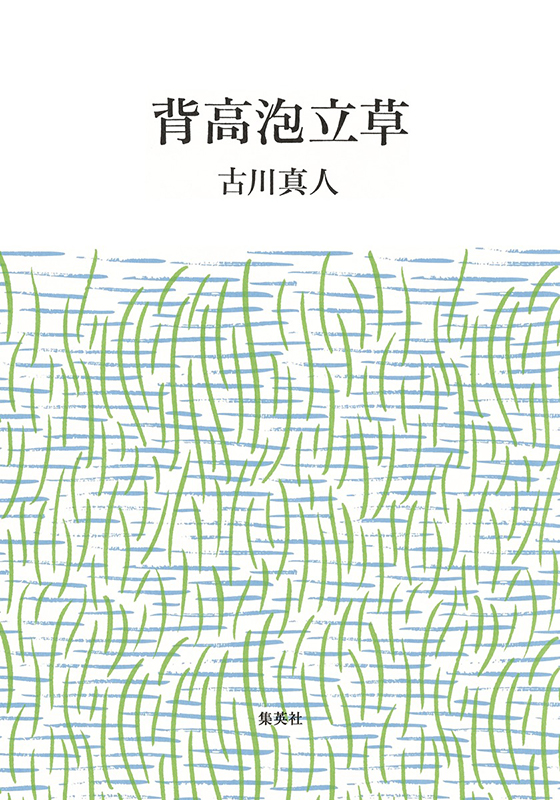プロフィール
-

高瀬 隼子 (たかせ・じゅんこ)
1988年愛媛県生まれ。東京都在住。立命館大学文学部卒業。「犬のかたちをしているもの」で第43回すばる文学賞を受賞。「水たまりで息をする」が第165回芥川賞候補に。『おいしいごはんが食べられますように』で第167回芥川賞を受賞。著書に『犬のかたちをしているもの』『水たまりで息をする』『おいしいごはんが食べられますように』がある。
担当編集より
第43回すばる文学賞受賞作
間橋薫、30歳。恋人の田中郁也と半同棲のような生活を送っていた。21歳の時に卵巣の手術をして以来、男性とは付き合ってしばらくたつと性交渉を拒むようになった。郁也と付き合い始めた時も、そのうちセックスしなくなると宣言した薫だが「好きだから大丈夫」だと彼は言った。普段と変らない日々を過ごしていたある日、郁也に呼び出されコーヒーショップに赴くと、彼の隣にはミナシロと名乗る見知らぬ女性が座っていた。大学時代の同級生で、郁也がお金を払ってセックスした相手だという。そんなミナシロが妊娠してしまい、彼女曰く、子供を堕すのは怖いけど子供は欲しくないと薫に説明した。そして「間橋さんが育ててくれませんか、田中くんと一緒に。つまり子ども、もらってくれませんか?」と唐突な提案をされる。自ら子供を産みたいと思ったこともなく、可愛いと思ったこともない薫だったが、郁也のことはたぶん愛している。セックスもしないし出来にくい身体である薫は、考えぬいたうえ、産まれてくる子供の幸せではなく、故郷の家族を喜ばせるためにもらおうかと思案するのだったが……。
生殖や愛について、切実に描くデビュー作。
第43回すばる文学賞受賞『犬のかたちをしているもの』 刊行記念エッセイ
わたしの正直な体
自分の書いた小説について語るのは困難なことだなと思います。小説は読んでくださった方のものです。どう読むか、どう受け取るか拒むか。それを語る場所から、わたしが一番遠くにいるように感じています。
三十歳か、五十歳か、七十歳の時か。いつかは分からないけど、生きている間に本を出すのが夢でした。東京の本屋には本がたくさんあります。こんなにたくさん本があるのだから、わたしの本がないのはおかしいと思う日と、これだけたくさん面白い本が溢れているんだから、わたしは作家になれないと思う日がありました。
「犬のかたちをしているもの」の執筆期間は三か月ほどでしたが、書き始める数か月前から何かを書かなきゃと考え続けていました。でもその何かが分からなくて、しんどかった。その年、三十歳になりました。同世代の友人たちは、大きな仕事を任されたり、転職してキャリアアップしたり、夜間大学院に通っていたり、子どもを産み育てていたり、それぞれがすべきことをし、前に進んでいるように見えました。対する自分は仕事にやりがいを見いだせず、ただ生活のために働き、小説も書き進められず、応募締切に間に合わないかもと焦っているくせに、酒を飲んだり無意味にスマートフォンをいじったりしているだけ。出したってどうせまた落選だ、誰にも読んでもらえないんだと腐り、だけど、それでもこれを書き上げて応募したかった。大げさなようですが、三月末締切のすばる文学賞に応募できなかったらわたしはわたしを見限るだろう、とそんな気持ちでした。今思うと、仕事の繁忙期が重なっていたこともあり精神状態がめためただったのだと思います。
応募締切間際になってなんとか書き上げたのですが、困ったことになりました。黒いひもがなかったのです。応募原稿を綴じるひもです。毎年やり方が分からず「小説 応募 原稿 綴じ方 ひも」で検索する、あの黒いひもです。コンビニプリントで原稿を印刷してから気づきました。家に黒いひもがないこと。
慌てて近所の百円ショップや文房具店をまわりましたが、売り切れていました。そんな人気商品なの、と思いながら別の百円ショップにも行きましたが売り切れ。電車で数駅行った文房具店にもありませんでした。新人賞の締切が集中している三月末だからでしょうか。みんな、応募に使うんでしょうか。きっとそうに違いない。黒いひもが売り切れるほど大勢が挑戦するんだ、そう思い昨年度の応募数を検索し、その数字に震え上がりました。黒いひもがない。ひもがないから応募ができない。応募するなってことだこれは。どうせまた落選するんだし……と半ば気持ちが折れていたその時「黒いひもあったよ!」と夫から電話がありました。自転車であちこち探しまわってくれていたのでした。最後の一個だったよ、と言っていたので、わたし以外にも黒いひもが入手できず苦しんだ方が大勢いたはずです。危ないところでした。
選考会の日は、朝からげりが止まりませんでした。無論、極度の緊張のためです。汚い話で大変恐れ入ります。その日は水曜日で日中は仕事だったのですが、げりは昼前から始まりました。食事も喉を通らず、緊張がこんなに顕著に体に出るのは初めてのことだったのでこれはすごいぞと妙な感動がありました。仕事と言いつつ、パソコンに向かって座っているだけで頭の中はぐるぐると、まさしくぐるぐると様々なことが浮かんでは沈み、再浮上しては砕け散る、を繰り返していました。その間もげりは数十分置きにやってきて、その周期を持った腹痛に、選考結果が告げられる時間が近づいていることを感じました。
選考結果の電話を待っている間落ち着かないので、連絡を受けた時になんて言うか想像して書いていました。落選パターンと受賞パターンの両方、各三十種類くらいずつ。でも、実際に「受賞しました」と言われた時は用意していた言葉は何も出ず、というより喉がきゅっと締まって声が出ませんでした。数秒ののち「本当ですか」と尋ねました。声って震えるんだ、と思いました。
嬉しかったかというと、そりゃもう当然跳び上がるほど嬉しかった、のは一瞬だけで、あの日から今日まで手放しで心が喜びだけになった瞬間というのは、受賞の連絡を受けたあの時だけのことです。それ以降は、やっていけるのか、何が書けるのか、何が書けるかって自分の中にあるものしか書けない、じゃあ自分の中には何があるのか、と悶々と問い続けて、嬉しいより苦しいが大きいです。問い続けていくしかないのだと思います。自分の中身を検分するのはとてもこわいです。それでも塵ひとつ、見逃す余裕はもうない。わたしには覚悟してもらわないといけません。
かつてないプレッシャーによって、げりは相変わらず今日も止まりませんが、げりのおかげでエッセイがひとつ書けるのだからげりになってよかった、まさしくひねり出したってやつだ、とも思っています。
「青春と読書」2020年1月号より転載
新着コンテンツ
-
インタビュー・対談2025年07月08日
 インタビュー・対談2025年07月08日
インタビュー・対談2025年07月08日桜木柴乃「波風立てずに生きる器用さを、ちょっと残念だなと感じる大人に読んでほしい」
著者五十代の最後を飾る、集大成的な短編集である本作。仕事に対する現在の思いや、短編を書く面白さをうかがいました。
-
お知らせ2025年07月04日
 お知らせ2025年07月04日
お知らせ2025年07月04日すばる8月号、好評発売中です!
演劇界注目の劇作家・演出家ピンク地底人3号さんによる初の小説を掲載! 遠野遥さんの短期集中連載も最終回を迎えます。
-
インタビュー・対談2025年07月04日
 インタビュー・対談2025年07月04日
インタビュー・対談2025年07月04日石井遊佳×藤野可織「魂を自由にする虚構の力」
ホラー愛好家を自認する藤野さんは石井さんの新作に詰まった四つの物語をどう味わい、そこに何を見つけたのか。
-
新刊案内2025年07月04日
 新刊案内2025年07月04日
新刊案内2025年07月04日給水塔から見た虹は
窪美澄
2人の“こども”が少しずつ“おとな”になるひと夏を描いた、ほろ苦くも大きな感動を呼ぶ、ある青春の逃避行。
-
新刊案内2025年07月04日
 新刊案内2025年07月04日
新刊案内2025年07月04日青の純度
篠田節子
煌びやかな「バブル絵画」の裏に潜んだ底知れぬ闇に迫る、渾身のアート×ミステリー大長編!
-
新刊案内2025年07月04日
 新刊案内2025年07月04日
新刊案内2025年07月04日情熱
桜木柴乃
直木賞受賞作『ホテルローヤル』、中央公論文芸賞受賞作『家族じまい』に連なる、生き惑う大人たちの物語。